3 / 5
#3
しおりを挟む
部屋に戻るのを見透かしたように、スマホが着信を知らせた。しゃくりあげそうになる感情を抑え込んで、深呼吸をする。
癪に障るほど正確に連絡を入れてくる。感心すら覚える電話の相手が誰か、見なくたってわかる。
確認もせずに出ると、桜井の予想通り、佐藤からだった。
揺れる気持ちを、佐藤に知られたくない。桜井は努めて平静を装ったが、声が震えているのが自分でもわかる。
『桜井、そっちの都合はどうだ? こっちもようやくお勉強会が終わったよ』
「私も時間が空きました。夕食でしたっけ? できれば……」
風邪をひいたと嘘をつこう。声が震えていてもこれなら佐藤にもわからないだろう。
『キャンセルか?』
「そうしていただければ。風邪をひきまして、体調がよくないんです」
綾樹のあの困った顔が桜井の脳裏から離れない。
『行くなって、言ってくれないんですか?』
冗談だと濁したが、あれは冗談ではなく、桜井の本心だ。
それを綾樹は目を伏せることで拒絶した。
桜井のことなど、綾樹には重い荷物であるほかない。
こんな気分のまま、食事なんて喉を通りそうにない。佐藤には悪いが、今夜はひとりで過ごしたかった。
だが相手は桜井に食い下がる。
『約束を反故にするのは構わんが、理由を教えろ』
「理由……ですか?」
『俺が納得する理由だったら、今日は引き下がってやる』
「私の体調が悪い。それだけですよ」
『そんな涙声でか?』
「――!」
……どうして。
『どうせ新城がらみ。そんなところだろう。あの堅物は優しすぎる。おまえの気持ちにも気づいているはずなのに、あいつはおまえを中途半端に引き離している。違うか』
……どうしてわかるんだろう。しかも佐藤はさっきのやり取りをずっと見ていたかのように、正確に言い当てる。
だから嫌いなのだ。ナイーヴな部分に土足で入り込もうとする、彼のその強引さが。
だが、それならそれで話が早い。
「あなたがストーカーなのかと疑いたくなるほど、あなたは私のことがわかっているんですね。そう、ひとりになりたいんです。今夜はほっておいてくれませんか」
『一人でさめざめ泣いて、おまえに振り向きもしないあの堅物を想いながら、自分を慰めるのか?』
「……」
デリカシーのない皮肉が、怒りの感情を昂らせていく。
「あなたは本当に、人の気持ちがわからないんですね」
怒鳴りたくなるのを必死に抑えてそれだけ言うと、桜井は電話を切った。
かけていた眼鏡を外し、苛立ちをぶつけるようにベッドの上にスマホと一緒に放り投げ、自分も広いベッドに腕を広げて背中から倒れ込む。
さすがに高い部屋だけあり、ビジネスホテルの硬いベッドとはわけが違う。ふんわりと桜井の体を受け止めてくれる。心地いいのに、なぜだか涙があふれ出る。
いい部屋でゆっくりくつろげるように。――そんな綾樹の気遣いすら、苛立ってしまう。
本当に欲しいものは、こんなものじゃない。
つかの間の優しさなんかじゃなくて、永遠にそれがほしい。
「新城社長」ではなく、「新城綾樹」の優しさと愛情が欲しいのだ。会社にいるときだけ独占できる、半分だけの気持ちじゃなくて、綾樹のすべてが。
嫉妬と欲求が耳障りな音を立てながら、波紋の亀裂を心に作っていく。
どうしてこんなに綾樹だけが欲しいのか、自分にも理解できない。
世の中には、たくさんの人間がいるのに、綾樹でなくちゃダメなんて。
「うっ、ふぐっ……」
部屋の明かりが眩しくて、左腕で目を隠す。
あふれる涙を我慢しても、泣き声を押し殺しても、このどうにもならない恋情の渦は、うねりを伴ってその力を増すばかりだ。
理性で抑え込んでも、片想いの欲求は抑え込むほどに破裂寸前まで大きくなって、桜井を苦しめる。
大抵のものは努力すれば手に入れられるのに、人の心はそうはいかない。
「綾樹……」
過分なほど優しく扱われているのに、彼の心はここにない。
なら、その彼の優しさに満たされたこの部屋で、ひとり妄想の海を漂いながら泡になりたい。
どうせこの恋は夢だ。人魚姫が想望して叶わなかった恋と同じ。
新工場の名称すら、桜井への当てつけかと穿ってしまう。
綾樹の弟の春樹がいる限り、綾樹は絶対に桜井のものにはならない。
ならせめて、頭の中だけでも、綾樹に愛される自分を想像していたい。それが泡となる夢でも。
ふんわりと桜井の身体を包む羽毛布団は綾樹だ。自分は今、綾樹に抱かれている……
「ん……」
そう思うだけで、後ろがじわりと疼いてくる。
「綾樹……」
スラックスのベルトとボタンを外し、そこから手を差し入れる。
綾樹ならどんな風に触れてくれるんだろう。そういえば彼の指は長かった。製薬会社の社長だからと、指先の手入れはいつも怠らなかったから、腕のたくましさとは裏腹に、指先はスッと長くて形のいい、清潔感のある繊細な指だった。
その指を想像しながら釣鐘に触れると、自身はもう硬くなっている。茎に指を絡ませると、もう蜜をこぼし始めていた。その蜜で指を濡らし、窄まりに触れれば、もうそこは雄芯の侵入を期待して疼いている。
つぷりと指先を沈めれば、内壁がその指を中に引きずり込もうと蠢きだす。
「ああ……」
頭の中に素裸の綾樹を想い描く。彼はどんな風に春樹を抱くのだろう。昨夜ロビーで見た綾樹を思い出す。胸をはだけて、肌を少し紅潮させた危険な色気と欲望をもって、相手が官能に色づくさまを見下ろしながら、焦らして楽しむタイプなのだろうか。
「綾樹……綾樹……」
彼に抱かれる自分を想像し、指を激しく出し入れするほどに、桜井の中に生まれるのは欲求不満だ。だめだ、指なんかじゃ足りない。もっと大きくて熱いものが欲しくなる。
扱いてイケる感覚じゃなく、中でイキたい……
ベッドに横たわったまま、周囲を見渡すと、テーブルの上に自分の万年筆を見つけた。
黒いボディに光を受けるとエメラルドの模様が見えるそれは、かなり前に綾樹からもらったものだ。
綾樹が言うには、大人になった記念に万年筆を買ってみたものの、あの独特の書き味になじめなかったという。
さらにはインクを中で詰まらせたりして、彼は早々に万年筆に見切りをつけた。
『私にはこれは合わない。桜井、よかったら使ってくれないか?』
綾樹は冗談めかして『高いやつだぞ、それ』と言っていたが、実際にヴィンテージ品であり、あとで調べて値段を知った。
相性が良ければずっと使うつもりだったのだろう。ボディには綾樹のフルネームが筆記体で彫られている。世界で一つしかない、綾樹の万年筆だ。
桜井はベッドから起き上がり、窓際のテーブルへと向かう。震える手で万年筆を手に取った。
「綾樹……」
それをぎゅっと握りしめ、ベッドに戻る。自分が何をしようとしているかなんてもはやどうでもよかった。
綾樹の代わりになるなら、何でもいい……
桜井がベッドに腰かけた瞬間。
ピンポーン。
部屋の呼び出しベルが鳴った。意外に大音量で、身体がびくっと反応する。
急激に性の熱が醒め、桜井は衣服を軽く直してインターホンを取った。
『こちら、桜井様のお部屋でお間違いないでしょうか?』
若い男性の声だ。
「どなたですか?」
『ルームサービスでございます。お客様よりご依頼を受けまして、桜井様にお持ちするようにと』
桜井は受話器を握りしめ、しばし考えた。ルームサービスなんか気の利いたものをよこしてくれる人間に心当たりがないからだ。
「依頼主はどなたでしょうか」
『ええと……新城様、ですね。新城綾樹様』
「綾樹が!? ちょ、ちょっと待って。すぐに開けます」
綾樹からだと聞いて気分が舞い上がる。さっきまでは綾樹の愛がほしくてたまらなくて悶々としていたのに、それも吹き飛んでしまった。ボーイに何か頼むくらいなら、むしろ夕飯を一緒に食べてくれてもよかったじゃないか。
そんなことを思いながら、身支度をささっとすませる。眼鏡をきちんとかけ直し、万年筆を胸ポケットにしまって、部屋の入り口にある鏡の前に立った。
なにせさっきまで欲情と片恋が作る自慰の海に沈みかけていたのだ。
不備がないのを3秒で確認し、桜井はドアを開けた。
「お待たせしました、わっ!」
「お邪魔しまーす」
ルームサービスを持ってきたボーイは、いきなり押し入ってきた。あまりの強引さに文句を言う隙もない。
「ちょ、ちょっと……! いったい何を持ってきたんです?」
「相手をよく確認してドアは開けろ」
「えっ……?」
「不用心すぎるぞ、恭司」
名前を呼ばれハッとする。この男はボーイではない!
「あなた……なんでここにいるんですか!」
「俺の三文芝居に引っかかるとは。おまえお疲れだねぇ」
顔を上げれば、そこにいたのはさっきまで電話で話していた佐藤だ。
「外から見たら、明かりがついている高層階の部屋はここだけだったからな。新城は一般の宿泊室だとほざいたが、あいつがおまえのために部屋を取るなら、おそらく最高級の部屋だとふんだ。だがまさか当たるとは思わなかった。最初の1発目で正解を引くとか、俺は運がいい」
「私が聞いているのは、そういうことではなくて……」
「いきなり電話を切られちまったからな。心配になるだろ?」
「あなたに心配される覚えも必要もありませんが」
「おまえになくても、俺にはある」
佐藤はずいと1歩踏み出す。なんだかよくわからないが今は佐藤が怖い。
思わず1歩後ずさると、膝の裏側に何かが当たった。ベッドの縁だ。
「あ……」
逃げ道がない……。このままでは。
「おまえを素直にさせるには、抱いてやるのが一番早い」
「いきなり来てそれですか。残念ながら私はそんな気分じゃないんです」
「おまえがそういう気分ではないのはいつものことだ。それに今日は新城に置いてけぼりを食らったんだろうが」
「どうしてそれを……」
「このホテルに着いた時、新城と鉢合わせたんでな。桜井がいないじゃないかとからかってやったら、おまえに1日休暇をくれてやったと教えてくれたぜ。ちょうどフロントで宿泊費の清算をしていた。結構な額を支払っていたが、あいつの財布から出ていたから、おそらくこの部屋の宿泊費だろう。最近、桜井が疲れているようだから、のんびりさせてから帰らせるとそう言っていた」
「綾樹が……」
さすがに綾樹は桜井の部屋番号まで教えなかったようだが、佐藤の洞察力にはたまに驚かされる。その正確な予測を、医療の方にもっと役立てればいいのに。
「才能の無駄遣いですね。私をサーチするより、診断確定の方に注力すればよろしいのに」
「俺は田舎の病院の雇われドクター。東京の7割程度のパワーで、充分優秀扱いだ」
入院患者や医療スタッフが聞いたら激怒しそうなことを平気で言ってのけ、佐藤は桜井を抱きしめ、ベッドに押し倒す。
「いやっ……!」
掛布とスプリングが二人分の体重を受け止め、身体が弾む。桜井は両手で佐藤の身体を押し戻そうとするが、彼はがっちりと桜井を抱きしめて離さない。
「離して……苦しい……」
佐藤の胸を叩いて絞り出すように訴える。
「お願い……離して。息が……」
胸を圧迫されて苦しかった。このまま圧死しそうなそんな感覚すら覚え、呼吸が浅くなっていく。
「苦しいか。そうだろうな。だが今のおまえを離せない」
「どうして……」
「どうせどん底に落ちて、鬱屈した気分を味わっていたんだろう。なにせ、大好きな新城に、たったひとり置いていかれたんだからな、おまえは」
「それは綾樹の厚情です」
「いいや違うな。さっきフロントで会った時、あいつは眉間に皺をよせていた。体調がよくなさそうなんだが、それでも帰らなければならない理由があるんだとしたら、あいつにはおまえ以上に大切なことがある。だからおまえは置いていかれた」
「……だったらどうだっていうんです?」
「慰めるのにも、それなりのもんが必要だ。足りないだろう、こんな細いモンじゃ」
佐藤が桜井の胸ポケットから、すっと抜き出したのは綾樹の万年筆だ。
それを目の前でちらちらと見せつけられ、桜井は唇を噛んで顔をそむけた。
「あいつの名前が彫ってあるな。新城の万年筆か。そういえばあいつがこんな筆記具を持っているのは見たことがない。だがデザインはあの堅物の好みだ。よく言えば渋い。悪く言えばじじむさい」
「綾樹は重厚感のあるものを好むだけですよ」
「その感覚がじじむさいんだよ。あいついくつだ」
確かに綾樹は若者が好むものはあまり好まない傾向にはあるし、周囲の時流や流行にはとんと無頓着どころか、無知だ。
仕事に関しての最新技術や世間の流れはきちんと読むけれど、時折若い技術者と最新トレンド情報の話をしていると、目を丸くして「ほー……」と固まっていることがある。
おそらく意味が分かっていないのだろうと桜井は推測している。
仕事以外のことに関心がないのもいかがなものかと思うことはあるが、だからといって佐藤に言われる筋合いはない。
「あなたには、綾樹が選ぶものの価値なんてわからないでしょう?」
皮肉を込めて言い返すと、佐藤はニヤリと不敵に笑った。
「そうでもないぜ。この万年筆、モノは一級、ヴィンテージだ」
「わかるんですか、意外です」
「職業柄、それなりに稼ぎがあるんでね。いいものは知ってるさ。ただ俺には合わん。だが……」
佐藤が万年筆でシャツ越しに胸を滑る。そこにラインを引くように、徐々に下肢へと降りていく。シャツ越しのその感触が、桜井の中に潜む淫猥な感情を探しているようで、否応にもその感触を意識してしまう。
「……っ」
「あいつは人間を見る目が欠けているようだ」
万年筆の先が桜井の股間に触れ、そのまま軽く円を描くように擦られた。
桜井はおもわず鼻にかかった吐息を漏らしてしまう。
「こんな超一級品の男が目の前にいて、食指を伸ばさないんだからな」
官能に色づきかけた身体は、またすぐに熱を取り戻し、股間を佐藤の手のひらに擦り付けてしまう。
「あんっ……やっ……」
「おやおやどうした。今日はずいぶん感度がいいじゃないか」
「あなたが……さわるから……」
「そうやってすぐ人のせいにするのは悪い癖だぞ、恭司」
「あなたはいつも、私が嫌がる事ばかりする」
「ここは嫌がっているように見えないが?」
佐藤の手がスラックスのボタンにかかった。
「確かめてみようか、恭司。ここがどうなっているか」
「やめ、ちょっと……」
抵抗する間もなく生まれたままの姿を暴かれ、桜井の全身が真っ赤に染まる。
桜井の性器はすでに硬くなっていた。性器全体がしっとりと濡れ、鈴口が透明な蜜をこぼしながら、何か言いたげにぱくぱくと時折口を開いている。
さっきまで自分で弄っていたことが佐藤にバレてしまう。
この男のことだ、桜井が自慰をしていたとなれば、徹底的にそれを詰ってくるに決まっている。
恥ずかしすぎてどう誤魔化そうか考えていると、どうも佐藤は既にお見通しのようで「自分でしたのか?」とニヤニヤ笑っている。
「だったらなんです?」
「いや? 前戯の手間が省けた」
てっきり馬鹿にされると思っていたのに、佐藤は予想外にそれ以上追及しては来なかった。
「後ろもきっと大丈夫ですよ。その手にしている綾樹の万年筆でも何でも入れてみたらどうですか」
やけくそになって開き直ると、佐藤の表情がスッと変わった。今までは桜井をからかうようにニヤニヤ笑っていたのに、急に表情が消えた。
「……? 私を抱かないんですか?」
大事なものを扱うように、佐藤は万年筆をベッドサイドにそっと置く。
「抱くさ」
かすれた声の小さな返答が、桜井の感情を抉る。何かを戒めるような、だがそれでいてどこか悲しげに揺れる彼の視線が、桜井を見下ろしていた。
「新城は残酷だな。おまえはずっとあいつに囚われ続けているつもりか」
「どういうことです?」
「こういうことだ」
いきなり茎を握られ、そのまま激しく扱かれる。
急な刺激に桜井は思わず嬌声を上げたが、ここが普通の観光ホテルだと気づき、唇を噛んだ。
こんな痴態を他の宿泊客に知られたくないし、部屋の外には誰がいるかわからない。
声を必死に抑えて、人の手で強制的に与えられる快楽を我慢していると、佐藤の手の速さがさらに増した。裏筋や鈴口も佐藤の親指で容赦なく捏ねられる。その刺激が気持ちいい……。
「声を抑えるな。感じるままに乱れろ、恭司」
佐藤の声が硬く、冷たい。
「新城の手でこうしてほしいんだろう?」
「そんなっ……そんなこと……」
必死に頭を振って否定する。
「綾樹には、綾樹には……恋人が…いる……」
「それでも、あいつに触れられたい。扱いて貫かれたい……そうだろ?」
「そんなこと、ない……」
「だが、あいつの恋人はおまえじゃない」
わかっている。そんな残酷な現実を今更言われなくたって。
「おまえを解放してやれるのは、俺だけだ。恭司、わかるか。新城を思い続けても、あいつはおまえを苦しめるしかできないんだ」
「わかって、ます……んんっ」
腰の奥が熱くなる。熱水が噴き出す感覚が急速に上がっていく。
「恭司、ほら……イキそうだろ」
低い声が耳元で桜井をそそのかす。もう限界だった。
「だめ、もう、もう、出そ……」
近づく絶頂が、切なさを秘めて桜井に襲い掛かる。
「あーーーーっ!」
白い闇が頭の中で弾けた。ひときわ高い声を上げ、腰をがくがくさせながら熱水を噴き上げる。
「ああ、だめ……止まらない……」
身体から力が抜ける。四肢を投げ出し、解放感に浸っていると、ふいに性器が何かに包まれた。驚いて体を起こすと、佐藤が桜井のものをしゃぶっている。
「ちょ、何してるんです」
「掃除してやってるんだ。大人しく寝てろ」
「だってそれ、汚い……」
「好きな奴のもんが汚いわけあるか」
陰茎からふくろ、鈴口の中まで残滓なきようしっかり清められ、出したばかりだというのに、またゆるゆると硬くなっていく。
どうして綾樹じゃないのに、自分は受け入れてしまえるのか。
片恋と現実の狭間で、自己嫌悪ばかりが強くなる。
結局、男を受け入れるのは自身の意思だ。
無理矢理だろうが、流されてしまおうが、結局身体を許してしまうのは、桜井自身だ。
綾樹に気持ちが届かないから、半ば自棄で佐藤に身をゆだねている。
ずっと思い続けてきたのに、桜井はもう、綾樹に好きだと言うことすらできない。
告白したところで、する前から結果が見えているのだから。
「あなたにはわからないでしょう……私の恋がどんなにつらいか」
「ならおまえは、俺の気持ちがわかるのか?」
「えっ……?」
「好きな奴に触れているのに、そいつはいつだって悲しみに沈んだ目で幻に泣いている。その涙をいくら拭っても、そいつに笑顔は戻らない。愛している奴が苦しんでいるのに、何もできない」
「だってそれは……」
「このままおまえを奪い去りたくなる。おまえをどこかに閉じ込めて、その記憶と意識から新城の影が消えるまで監禁してやろうかとも思うさ。だけど、そんなことはおまえが一番望まないだろう。だから俺は毎回おまえに触れるたびに祈ってる。この時間だけ、つかの間でいい。俺に気持ちを向けてくれ、と。無理やり抱けば、この時間だけでもおまえの涙が止まり、俺が与える快楽だけを求めるようになる。だが、それは俺自身が求められているわけじゃない」
「……?」
「性の快楽ってのは人間の本能だ。そこに働きかけているのに、おまえの気持ちはここにはない。今のおまえは自我を失くして新城という鎖に囚われ、俺に身体を差し出すだけの人形だ。そこに意思も熱もない。こんなに冷たくて悲しいセックスはないぜ」
仕方がない。桜井の胸を焦がす人は佐藤ではない。綾樹だ。
「だが俺はいい。好きでやってることだから。しかしおまえはどうだ? 新城にそんなふうに抱かれたいのか。あいつがおまえを『代用』として扱うことに、おまえは満足できるのか」
「……」
いちいち気に障る。佐藤の言うことはどれも真実だ。
綾樹の心が自分に向いていない以上、彼と身体を重ねても、自らの心がズタズタに切り裂かれていくだけだ。
身体はどうとでもなる。でも、長く胸に抱えたその影を、簡単に消してしまえるほど軽はずみな恋なんかじゃない。
本気でずっと好きだったのだ。
「そんなに私の気持ちが向かないのが嫌なら、私のことなど諦めてしまったらいかがですか? 楽になれますよ」
「同じことをそっくりおまえに返してやろうか。おまえにはできるのか。新城をあっさり諦めることが?」
「……それが出来れば……」
苦労はしない。できないからこうして苦しんでいるのだ。
綾樹のそばを離れることも、思いつめて自らを終わりにすることもできない。
結局、そばにいられるのなら何でもいい。たとえ綾樹が自分を見てくれなくても。
そう割り切っているのだ。それ以上はいらないのだと。
だけど。
それを時折、我慢できなくなる。
身体と心が求めてしまうのだ。
そんな感情の隙間を感知して、ふいに秘蕾に男の指が入り込んでくる。
「あ、んっ」
男の指は隘路を割って、粘膜を磨き込むように出入りしているが、その指が桜井の敏感なところをかすめた。
「んああっ」
強い電圧にも似た激しい痺れが全身を駆け抜け、身体が弓なりに反る。佐藤はそんな桜井の痴態を楽しむように、着々と男を受け入れさせる準備を続けていた。
何度も何度も敏感な部分に触れられていると、快楽と共に鎌首を持ち上げてくるのは、桜井の本性だ。
「だめ、だめ、あっ、また、あっ……!」
きつく立ち上がった己から薄くなった白濁を噴き上げて、息も絶え絶えに快楽に囚われる。
身体も心ももうドロドロだ。
モットイカセテ……モット、モットオクマデ……
「ふふ、もうグズグズだな」
「言わないで……言わないでください……」
「また勃ってきたぞ。イキっぱなしの淫乱だな」
「だったら、その淫乱にふさわしい扱いをしてください」
「ん?」
質問の意味が分からなかったのか、佐藤が身を乗り出して、桜井の顔をじっと見る。
その瞳は、今までの飄々としていた佐藤のそれじゃない。冷たい刃のような鋭さと、燃え盛る野獣のような光の両方を秘め、快楽で泣き濡れた桜井をじっと見つめている。
「恭司、なんと言った?」
「私は淫乱……なんでしょう? なら、それらしい扱いをしてください」
「恭司……」
「壊して……私を」
こんなにも浅ましい自分の身体。このまま脳髄まで性の毒で溶かしてほしい。
佐藤の匂いをまとわせて、汚れ爛れた体と心なんか、綾樹が受け入れるはずもない。
だったらもういっそのこと、壊してほしい。
佐藤が淫乱だというなら、きっと自分はそうなのだろう。
「一生あなたの奴隷でいい……」
綾樹にこの思いが届かないなら――。
「壊して……」
子供のようにしゃくりあげて泣きながら佐藤に懇願する
「――おまえを壊して済むなら、とっくにそうしてる」
「…?」
佐藤は指を抜くと、代わりに自身を桜井の蕾にあてがった。
指とは違う、熱い切っ先がゆっくりと桜井の中に入ってくる。
「あ……」
隘路を割って入ってくる熱核は桜井を傷つけぬように、時間を掛けて入ってくる、やがて互いの叢が触れ、桜井の中に佐藤がすべて収まった。
「あったかいな、おまえの中は」
佐藤がふうと息を吐く。ついでに桜井の唇に優しいキスがふってくる。
「淫乱だなんて言って悪かった」
「どうしたんです、急に……」
「冷たいセックスは嫌だっておまえに言ったのに、俺はおまえにひどい言葉を投げつけた」
その謝罪は佐藤の本心だと感じた。いつもの自分勝手で強引な彼のそれではない。
いったい何事かと、桜井は泣き癖で出てしまったしゃっくりを押さえながら小首をかしげると、佐藤は「それは反則だぞ、恭司」と笑い、また唇にキスをした。
「俺が欲しいのは従順なお人形さんじゃない。生意気でプライドがエベレスト級に高い、そのくせちょっとダメージくらうと、すぐにさめざめ泣いてエロくなる、そんないじっぱりでかわいい弁護士先生が好きなんだ」
「だからあなたの思いは私には……」
「迷惑だって言うんだろ。わかってる。だが俺が勝手にしてることだ。そしておまえも何のかの言って、俺に付き合ってくれてる。俺はそれだけでいいんだよ。おまえは今、俺の腕の中にいる。少なくとも、いま俺が抱いているのは人形なんかじゃない」
その言葉に心臓がどきりと切なく跳ねた。
彼に抱かれるこの身体があたたかくなる。
「俺がいま抱いているのは、俺が世界でいちばん愛しているヤツだ」
心の奥からなにかほんわりとしたものが生まれ、それが全身を包んでいく。
この男はいつも桜井をからかってきた。
だけど、その目は真剣だ。佐藤は桜井を抱くときに、いつもこんな燃え盛る炎を宿した熱い瞳をしていたのだろうか。
「愛しているなんて……気安く言うものではありませんよ」
その視線とかち合うのが気恥ずかしくて、桜井は視線を反らして口を尖らせた。
「いざという時に、その言葉の重みを失ってしまいます」
「おまえを言葉で縛れるなら苦労はしない。だが、おまえに限らず、人はこうして感情を言葉にして、気持ちで示さないとなかなか理解しない」
佐藤が言いながら軽く突き上げてくる。しばらく互いが繋がっていたせいで、桜井の蕾は満開に花咲き、佐藤をなんなく受け入れていた。
奥をコツコツ叩くように軽く突かれ、切ない振動に桜井は思わず甘い声を漏らす。
「好きだ、恭司」
「……あっ」
「ーー愛している」
その低い声が合図となり、桜井の身体が揺すられる。
「だめ、あっ、気持ちいい……あんっ!」
桜井の中で感じる熱い脈動。中を穿たれながら、桜井は自らを犯す男の身体をかき抱いた。
いつもだったら、強引な佐藤に流されるだけのセックスが今日は違う。
佐藤が桜井の身体に与える衝撃は、とんでもなく強力な媚薬になっていた。
気持ちよくて、温かくて。このまま意識と身体が剥がされてしまいそうだ。佐藤の熱核が桜井の中でまた少し大きくなり、いっぱいに開いた花蕾がほんの少し、ひきつられる。
だけど、辛くない。この痛みが幸せに思える。
「恭司、好きだ、恭司……」
「……私、は……」
熱い告白に、胸中が揺れ、桜井の胸の中にいる綾樹の顔がぼんやりと霞んでいく。佐藤の熱核が奥を突くたび、綾樹が見えなくなっていく。
自分はいま、誰を一番愛しているのだろう?
桜井にとって、佐藤はたんなる代用品だった。
しかも桜井が望んだ代用品ではなく、どちらかといえば、押し売りに近い「綾樹の代わり」だ。
それでも今は、佐藤に抱かれるこの時が……愛おしい。
――私は彼のことが好きなのか。いや、そんなはずはない
静かなる混乱が、揺れて落ちそうになっている桜井を苦しめていた。
愛している――そんな言葉一つだけで、自分の中で何かが変化していく。
今、桜井がきつく抱きしめている男は、ずっと想い続けた綾樹ではない。
ましてや、綾樹の代用品なんかじゃない。
この男は佐藤だ。自分は今、佐藤に抱かれている――。
激しく揺らされている間も、佐藤のキスが降ってくる。くすぐったくて、やめてとばかりに顔を上げれば、そのまま唇をふさがれる。
「ん、ちゅ……」
舌を絡める深いキス。上も下も繋がって身も心もとろとろに熟れていく。
彼の情熱を全身で受け、桜井の全てが満たされていく。
佐藤の手で、達したい……。
「ゆう、じ……」
彼の名前が、自然と桜井の口をつく。佐藤は驚いて動きを止めた。
「恭司?」
「もっと抱いて私を……ゆうじ……ゆう、じ……」
一度出てしまったら、あとは止められない。
切なさと淋しさに愛しさが混ざり、佐藤だけがほしくてたまらない。
「お願い、裕二……私の中に……」
「恭司……」
佐藤の動きが激しさを増す。突き入れられる熱核の衝撃を最奥で受けながら、桜井は佐藤の腰に細い足をぎゅっと絡めた。
「一番奥に、あなたの命を注いで……」
「……いいだろう。孕むくらい注いでやる」
佐藤は右手で硬くなった桜井を握ると、そのまま激しく扱きだす。急に直接的な刺激を与えられ、桜井が小さな悲鳴を上げると、佐藤はニヤリと笑った。
「イクときは、一緒だ。俺がイクまで、射精は我慢しろ」
佐藤の熱核に最も感じるポイントを狙い撃ちされながら手淫されるなんて、どうしたって我慢なんかできやしない。腰は既にムズムズして射精の予感を感じる。桜井が陥落するまで時間はない。
「そんな、無理! 無理です! だめ、イク、イキそう! ああ、んんっ!」
激しくいやいやをするように頭を振りながら桜井は「許して」と懇願するが、しょせん相手は佐藤だ。桜井の褥での要求など、絶対に聞いてくれやしないどころか、愉しげに笑って完全スルーだ。
「もう、無理、無理!」
「恭司……いい子だ。よく我慢したな。さあ、イケ……」
耳から注がれる解放の合図。
瞬間、腹の奥から熱いものがせりあがってくる。
「だめぇ、イク、ああああああ!」
「……っ!」
白い闇が意識を塗りつぶす。ジワリ広がる温かなものを腹の奥で感じながら、桜井は自分を抱く男の唇にキスをする。
「恭司?」
「繋がったまま、キスしていたい……」
いけませんか?と耳元で囁けば、佐藤は「えらく積極的だな」と笑いながら、深く口づけてくる。
それを受けながら、桜井は男の背をしっかり抱きしめる。身体の中で蠢く佐藤の熱核を感じながら。
――わかっている。ちゃんとわかっている。
指先でなぞるこの輪郭。
これは綾樹でなく、佐藤の背中だと。
綾樹がずっと好きだった。
昔からずっと、今もそれは決して変わらないはずだ。
だけど今は、あんなに好きだった人の姿が心の中で霞み始めている。
桜井自身の中で、何かが変わろうとしている。
だが、今の桜井にはまだそれをちゃんと認める勇気はなかった。
まだ、今は――。
癪に障るほど正確に連絡を入れてくる。感心すら覚える電話の相手が誰か、見なくたってわかる。
確認もせずに出ると、桜井の予想通り、佐藤からだった。
揺れる気持ちを、佐藤に知られたくない。桜井は努めて平静を装ったが、声が震えているのが自分でもわかる。
『桜井、そっちの都合はどうだ? こっちもようやくお勉強会が終わったよ』
「私も時間が空きました。夕食でしたっけ? できれば……」
風邪をひいたと嘘をつこう。声が震えていてもこれなら佐藤にもわからないだろう。
『キャンセルか?』
「そうしていただければ。風邪をひきまして、体調がよくないんです」
綾樹のあの困った顔が桜井の脳裏から離れない。
『行くなって、言ってくれないんですか?』
冗談だと濁したが、あれは冗談ではなく、桜井の本心だ。
それを綾樹は目を伏せることで拒絶した。
桜井のことなど、綾樹には重い荷物であるほかない。
こんな気分のまま、食事なんて喉を通りそうにない。佐藤には悪いが、今夜はひとりで過ごしたかった。
だが相手は桜井に食い下がる。
『約束を反故にするのは構わんが、理由を教えろ』
「理由……ですか?」
『俺が納得する理由だったら、今日は引き下がってやる』
「私の体調が悪い。それだけですよ」
『そんな涙声でか?』
「――!」
……どうして。
『どうせ新城がらみ。そんなところだろう。あの堅物は優しすぎる。おまえの気持ちにも気づいているはずなのに、あいつはおまえを中途半端に引き離している。違うか』
……どうしてわかるんだろう。しかも佐藤はさっきのやり取りをずっと見ていたかのように、正確に言い当てる。
だから嫌いなのだ。ナイーヴな部分に土足で入り込もうとする、彼のその強引さが。
だが、それならそれで話が早い。
「あなたがストーカーなのかと疑いたくなるほど、あなたは私のことがわかっているんですね。そう、ひとりになりたいんです。今夜はほっておいてくれませんか」
『一人でさめざめ泣いて、おまえに振り向きもしないあの堅物を想いながら、自分を慰めるのか?』
「……」
デリカシーのない皮肉が、怒りの感情を昂らせていく。
「あなたは本当に、人の気持ちがわからないんですね」
怒鳴りたくなるのを必死に抑えてそれだけ言うと、桜井は電話を切った。
かけていた眼鏡を外し、苛立ちをぶつけるようにベッドの上にスマホと一緒に放り投げ、自分も広いベッドに腕を広げて背中から倒れ込む。
さすがに高い部屋だけあり、ビジネスホテルの硬いベッドとはわけが違う。ふんわりと桜井の体を受け止めてくれる。心地いいのに、なぜだか涙があふれ出る。
いい部屋でゆっくりくつろげるように。――そんな綾樹の気遣いすら、苛立ってしまう。
本当に欲しいものは、こんなものじゃない。
つかの間の優しさなんかじゃなくて、永遠にそれがほしい。
「新城社長」ではなく、「新城綾樹」の優しさと愛情が欲しいのだ。会社にいるときだけ独占できる、半分だけの気持ちじゃなくて、綾樹のすべてが。
嫉妬と欲求が耳障りな音を立てながら、波紋の亀裂を心に作っていく。
どうしてこんなに綾樹だけが欲しいのか、自分にも理解できない。
世の中には、たくさんの人間がいるのに、綾樹でなくちゃダメなんて。
「うっ、ふぐっ……」
部屋の明かりが眩しくて、左腕で目を隠す。
あふれる涙を我慢しても、泣き声を押し殺しても、このどうにもならない恋情の渦は、うねりを伴ってその力を増すばかりだ。
理性で抑え込んでも、片想いの欲求は抑え込むほどに破裂寸前まで大きくなって、桜井を苦しめる。
大抵のものは努力すれば手に入れられるのに、人の心はそうはいかない。
「綾樹……」
過分なほど優しく扱われているのに、彼の心はここにない。
なら、その彼の優しさに満たされたこの部屋で、ひとり妄想の海を漂いながら泡になりたい。
どうせこの恋は夢だ。人魚姫が想望して叶わなかった恋と同じ。
新工場の名称すら、桜井への当てつけかと穿ってしまう。
綾樹の弟の春樹がいる限り、綾樹は絶対に桜井のものにはならない。
ならせめて、頭の中だけでも、綾樹に愛される自分を想像していたい。それが泡となる夢でも。
ふんわりと桜井の身体を包む羽毛布団は綾樹だ。自分は今、綾樹に抱かれている……
「ん……」
そう思うだけで、後ろがじわりと疼いてくる。
「綾樹……」
スラックスのベルトとボタンを外し、そこから手を差し入れる。
綾樹ならどんな風に触れてくれるんだろう。そういえば彼の指は長かった。製薬会社の社長だからと、指先の手入れはいつも怠らなかったから、腕のたくましさとは裏腹に、指先はスッと長くて形のいい、清潔感のある繊細な指だった。
その指を想像しながら釣鐘に触れると、自身はもう硬くなっている。茎に指を絡ませると、もう蜜をこぼし始めていた。その蜜で指を濡らし、窄まりに触れれば、もうそこは雄芯の侵入を期待して疼いている。
つぷりと指先を沈めれば、内壁がその指を中に引きずり込もうと蠢きだす。
「ああ……」
頭の中に素裸の綾樹を想い描く。彼はどんな風に春樹を抱くのだろう。昨夜ロビーで見た綾樹を思い出す。胸をはだけて、肌を少し紅潮させた危険な色気と欲望をもって、相手が官能に色づくさまを見下ろしながら、焦らして楽しむタイプなのだろうか。
「綾樹……綾樹……」
彼に抱かれる自分を想像し、指を激しく出し入れするほどに、桜井の中に生まれるのは欲求不満だ。だめだ、指なんかじゃ足りない。もっと大きくて熱いものが欲しくなる。
扱いてイケる感覚じゃなく、中でイキたい……
ベッドに横たわったまま、周囲を見渡すと、テーブルの上に自分の万年筆を見つけた。
黒いボディに光を受けるとエメラルドの模様が見えるそれは、かなり前に綾樹からもらったものだ。
綾樹が言うには、大人になった記念に万年筆を買ってみたものの、あの独特の書き味になじめなかったという。
さらにはインクを中で詰まらせたりして、彼は早々に万年筆に見切りをつけた。
『私にはこれは合わない。桜井、よかったら使ってくれないか?』
綾樹は冗談めかして『高いやつだぞ、それ』と言っていたが、実際にヴィンテージ品であり、あとで調べて値段を知った。
相性が良ければずっと使うつもりだったのだろう。ボディには綾樹のフルネームが筆記体で彫られている。世界で一つしかない、綾樹の万年筆だ。
桜井はベッドから起き上がり、窓際のテーブルへと向かう。震える手で万年筆を手に取った。
「綾樹……」
それをぎゅっと握りしめ、ベッドに戻る。自分が何をしようとしているかなんてもはやどうでもよかった。
綾樹の代わりになるなら、何でもいい……
桜井がベッドに腰かけた瞬間。
ピンポーン。
部屋の呼び出しベルが鳴った。意外に大音量で、身体がびくっと反応する。
急激に性の熱が醒め、桜井は衣服を軽く直してインターホンを取った。
『こちら、桜井様のお部屋でお間違いないでしょうか?』
若い男性の声だ。
「どなたですか?」
『ルームサービスでございます。お客様よりご依頼を受けまして、桜井様にお持ちするようにと』
桜井は受話器を握りしめ、しばし考えた。ルームサービスなんか気の利いたものをよこしてくれる人間に心当たりがないからだ。
「依頼主はどなたでしょうか」
『ええと……新城様、ですね。新城綾樹様』
「綾樹が!? ちょ、ちょっと待って。すぐに開けます」
綾樹からだと聞いて気分が舞い上がる。さっきまでは綾樹の愛がほしくてたまらなくて悶々としていたのに、それも吹き飛んでしまった。ボーイに何か頼むくらいなら、むしろ夕飯を一緒に食べてくれてもよかったじゃないか。
そんなことを思いながら、身支度をささっとすませる。眼鏡をきちんとかけ直し、万年筆を胸ポケットにしまって、部屋の入り口にある鏡の前に立った。
なにせさっきまで欲情と片恋が作る自慰の海に沈みかけていたのだ。
不備がないのを3秒で確認し、桜井はドアを開けた。
「お待たせしました、わっ!」
「お邪魔しまーす」
ルームサービスを持ってきたボーイは、いきなり押し入ってきた。あまりの強引さに文句を言う隙もない。
「ちょ、ちょっと……! いったい何を持ってきたんです?」
「相手をよく確認してドアは開けろ」
「えっ……?」
「不用心すぎるぞ、恭司」
名前を呼ばれハッとする。この男はボーイではない!
「あなた……なんでここにいるんですか!」
「俺の三文芝居に引っかかるとは。おまえお疲れだねぇ」
顔を上げれば、そこにいたのはさっきまで電話で話していた佐藤だ。
「外から見たら、明かりがついている高層階の部屋はここだけだったからな。新城は一般の宿泊室だとほざいたが、あいつがおまえのために部屋を取るなら、おそらく最高級の部屋だとふんだ。だがまさか当たるとは思わなかった。最初の1発目で正解を引くとか、俺は運がいい」
「私が聞いているのは、そういうことではなくて……」
「いきなり電話を切られちまったからな。心配になるだろ?」
「あなたに心配される覚えも必要もありませんが」
「おまえになくても、俺にはある」
佐藤はずいと1歩踏み出す。なんだかよくわからないが今は佐藤が怖い。
思わず1歩後ずさると、膝の裏側に何かが当たった。ベッドの縁だ。
「あ……」
逃げ道がない……。このままでは。
「おまえを素直にさせるには、抱いてやるのが一番早い」
「いきなり来てそれですか。残念ながら私はそんな気分じゃないんです」
「おまえがそういう気分ではないのはいつものことだ。それに今日は新城に置いてけぼりを食らったんだろうが」
「どうしてそれを……」
「このホテルに着いた時、新城と鉢合わせたんでな。桜井がいないじゃないかとからかってやったら、おまえに1日休暇をくれてやったと教えてくれたぜ。ちょうどフロントで宿泊費の清算をしていた。結構な額を支払っていたが、あいつの財布から出ていたから、おそらくこの部屋の宿泊費だろう。最近、桜井が疲れているようだから、のんびりさせてから帰らせるとそう言っていた」
「綾樹が……」
さすがに綾樹は桜井の部屋番号まで教えなかったようだが、佐藤の洞察力にはたまに驚かされる。その正確な予測を、医療の方にもっと役立てればいいのに。
「才能の無駄遣いですね。私をサーチするより、診断確定の方に注力すればよろしいのに」
「俺は田舎の病院の雇われドクター。東京の7割程度のパワーで、充分優秀扱いだ」
入院患者や医療スタッフが聞いたら激怒しそうなことを平気で言ってのけ、佐藤は桜井を抱きしめ、ベッドに押し倒す。
「いやっ……!」
掛布とスプリングが二人分の体重を受け止め、身体が弾む。桜井は両手で佐藤の身体を押し戻そうとするが、彼はがっちりと桜井を抱きしめて離さない。
「離して……苦しい……」
佐藤の胸を叩いて絞り出すように訴える。
「お願い……離して。息が……」
胸を圧迫されて苦しかった。このまま圧死しそうなそんな感覚すら覚え、呼吸が浅くなっていく。
「苦しいか。そうだろうな。だが今のおまえを離せない」
「どうして……」
「どうせどん底に落ちて、鬱屈した気分を味わっていたんだろう。なにせ、大好きな新城に、たったひとり置いていかれたんだからな、おまえは」
「それは綾樹の厚情です」
「いいや違うな。さっきフロントで会った時、あいつは眉間に皺をよせていた。体調がよくなさそうなんだが、それでも帰らなければならない理由があるんだとしたら、あいつにはおまえ以上に大切なことがある。だからおまえは置いていかれた」
「……だったらどうだっていうんです?」
「慰めるのにも、それなりのもんが必要だ。足りないだろう、こんな細いモンじゃ」
佐藤が桜井の胸ポケットから、すっと抜き出したのは綾樹の万年筆だ。
それを目の前でちらちらと見せつけられ、桜井は唇を噛んで顔をそむけた。
「あいつの名前が彫ってあるな。新城の万年筆か。そういえばあいつがこんな筆記具を持っているのは見たことがない。だがデザインはあの堅物の好みだ。よく言えば渋い。悪く言えばじじむさい」
「綾樹は重厚感のあるものを好むだけですよ」
「その感覚がじじむさいんだよ。あいついくつだ」
確かに綾樹は若者が好むものはあまり好まない傾向にはあるし、周囲の時流や流行にはとんと無頓着どころか、無知だ。
仕事に関しての最新技術や世間の流れはきちんと読むけれど、時折若い技術者と最新トレンド情報の話をしていると、目を丸くして「ほー……」と固まっていることがある。
おそらく意味が分かっていないのだろうと桜井は推測している。
仕事以外のことに関心がないのもいかがなものかと思うことはあるが、だからといって佐藤に言われる筋合いはない。
「あなたには、綾樹が選ぶものの価値なんてわからないでしょう?」
皮肉を込めて言い返すと、佐藤はニヤリと不敵に笑った。
「そうでもないぜ。この万年筆、モノは一級、ヴィンテージだ」
「わかるんですか、意外です」
「職業柄、それなりに稼ぎがあるんでね。いいものは知ってるさ。ただ俺には合わん。だが……」
佐藤が万年筆でシャツ越しに胸を滑る。そこにラインを引くように、徐々に下肢へと降りていく。シャツ越しのその感触が、桜井の中に潜む淫猥な感情を探しているようで、否応にもその感触を意識してしまう。
「……っ」
「あいつは人間を見る目が欠けているようだ」
万年筆の先が桜井の股間に触れ、そのまま軽く円を描くように擦られた。
桜井はおもわず鼻にかかった吐息を漏らしてしまう。
「こんな超一級品の男が目の前にいて、食指を伸ばさないんだからな」
官能に色づきかけた身体は、またすぐに熱を取り戻し、股間を佐藤の手のひらに擦り付けてしまう。
「あんっ……やっ……」
「おやおやどうした。今日はずいぶん感度がいいじゃないか」
「あなたが……さわるから……」
「そうやってすぐ人のせいにするのは悪い癖だぞ、恭司」
「あなたはいつも、私が嫌がる事ばかりする」
「ここは嫌がっているように見えないが?」
佐藤の手がスラックスのボタンにかかった。
「確かめてみようか、恭司。ここがどうなっているか」
「やめ、ちょっと……」
抵抗する間もなく生まれたままの姿を暴かれ、桜井の全身が真っ赤に染まる。
桜井の性器はすでに硬くなっていた。性器全体がしっとりと濡れ、鈴口が透明な蜜をこぼしながら、何か言いたげにぱくぱくと時折口を開いている。
さっきまで自分で弄っていたことが佐藤にバレてしまう。
この男のことだ、桜井が自慰をしていたとなれば、徹底的にそれを詰ってくるに決まっている。
恥ずかしすぎてどう誤魔化そうか考えていると、どうも佐藤は既にお見通しのようで「自分でしたのか?」とニヤニヤ笑っている。
「だったらなんです?」
「いや? 前戯の手間が省けた」
てっきり馬鹿にされると思っていたのに、佐藤は予想外にそれ以上追及しては来なかった。
「後ろもきっと大丈夫ですよ。その手にしている綾樹の万年筆でも何でも入れてみたらどうですか」
やけくそになって開き直ると、佐藤の表情がスッと変わった。今までは桜井をからかうようにニヤニヤ笑っていたのに、急に表情が消えた。
「……? 私を抱かないんですか?」
大事なものを扱うように、佐藤は万年筆をベッドサイドにそっと置く。
「抱くさ」
かすれた声の小さな返答が、桜井の感情を抉る。何かを戒めるような、だがそれでいてどこか悲しげに揺れる彼の視線が、桜井を見下ろしていた。
「新城は残酷だな。おまえはずっとあいつに囚われ続けているつもりか」
「どういうことです?」
「こういうことだ」
いきなり茎を握られ、そのまま激しく扱かれる。
急な刺激に桜井は思わず嬌声を上げたが、ここが普通の観光ホテルだと気づき、唇を噛んだ。
こんな痴態を他の宿泊客に知られたくないし、部屋の外には誰がいるかわからない。
声を必死に抑えて、人の手で強制的に与えられる快楽を我慢していると、佐藤の手の速さがさらに増した。裏筋や鈴口も佐藤の親指で容赦なく捏ねられる。その刺激が気持ちいい……。
「声を抑えるな。感じるままに乱れろ、恭司」
佐藤の声が硬く、冷たい。
「新城の手でこうしてほしいんだろう?」
「そんなっ……そんなこと……」
必死に頭を振って否定する。
「綾樹には、綾樹には……恋人が…いる……」
「それでも、あいつに触れられたい。扱いて貫かれたい……そうだろ?」
「そんなこと、ない……」
「だが、あいつの恋人はおまえじゃない」
わかっている。そんな残酷な現実を今更言われなくたって。
「おまえを解放してやれるのは、俺だけだ。恭司、わかるか。新城を思い続けても、あいつはおまえを苦しめるしかできないんだ」
「わかって、ます……んんっ」
腰の奥が熱くなる。熱水が噴き出す感覚が急速に上がっていく。
「恭司、ほら……イキそうだろ」
低い声が耳元で桜井をそそのかす。もう限界だった。
「だめ、もう、もう、出そ……」
近づく絶頂が、切なさを秘めて桜井に襲い掛かる。
「あーーーーっ!」
白い闇が頭の中で弾けた。ひときわ高い声を上げ、腰をがくがくさせながら熱水を噴き上げる。
「ああ、だめ……止まらない……」
身体から力が抜ける。四肢を投げ出し、解放感に浸っていると、ふいに性器が何かに包まれた。驚いて体を起こすと、佐藤が桜井のものをしゃぶっている。
「ちょ、何してるんです」
「掃除してやってるんだ。大人しく寝てろ」
「だってそれ、汚い……」
「好きな奴のもんが汚いわけあるか」
陰茎からふくろ、鈴口の中まで残滓なきようしっかり清められ、出したばかりだというのに、またゆるゆると硬くなっていく。
どうして綾樹じゃないのに、自分は受け入れてしまえるのか。
片恋と現実の狭間で、自己嫌悪ばかりが強くなる。
結局、男を受け入れるのは自身の意思だ。
無理矢理だろうが、流されてしまおうが、結局身体を許してしまうのは、桜井自身だ。
綾樹に気持ちが届かないから、半ば自棄で佐藤に身をゆだねている。
ずっと思い続けてきたのに、桜井はもう、綾樹に好きだと言うことすらできない。
告白したところで、する前から結果が見えているのだから。
「あなたにはわからないでしょう……私の恋がどんなにつらいか」
「ならおまえは、俺の気持ちがわかるのか?」
「えっ……?」
「好きな奴に触れているのに、そいつはいつだって悲しみに沈んだ目で幻に泣いている。その涙をいくら拭っても、そいつに笑顔は戻らない。愛している奴が苦しんでいるのに、何もできない」
「だってそれは……」
「このままおまえを奪い去りたくなる。おまえをどこかに閉じ込めて、その記憶と意識から新城の影が消えるまで監禁してやろうかとも思うさ。だけど、そんなことはおまえが一番望まないだろう。だから俺は毎回おまえに触れるたびに祈ってる。この時間だけ、つかの間でいい。俺に気持ちを向けてくれ、と。無理やり抱けば、この時間だけでもおまえの涙が止まり、俺が与える快楽だけを求めるようになる。だが、それは俺自身が求められているわけじゃない」
「……?」
「性の快楽ってのは人間の本能だ。そこに働きかけているのに、おまえの気持ちはここにはない。今のおまえは自我を失くして新城という鎖に囚われ、俺に身体を差し出すだけの人形だ。そこに意思も熱もない。こんなに冷たくて悲しいセックスはないぜ」
仕方がない。桜井の胸を焦がす人は佐藤ではない。綾樹だ。
「だが俺はいい。好きでやってることだから。しかしおまえはどうだ? 新城にそんなふうに抱かれたいのか。あいつがおまえを『代用』として扱うことに、おまえは満足できるのか」
「……」
いちいち気に障る。佐藤の言うことはどれも真実だ。
綾樹の心が自分に向いていない以上、彼と身体を重ねても、自らの心がズタズタに切り裂かれていくだけだ。
身体はどうとでもなる。でも、長く胸に抱えたその影を、簡単に消してしまえるほど軽はずみな恋なんかじゃない。
本気でずっと好きだったのだ。
「そんなに私の気持ちが向かないのが嫌なら、私のことなど諦めてしまったらいかがですか? 楽になれますよ」
「同じことをそっくりおまえに返してやろうか。おまえにはできるのか。新城をあっさり諦めることが?」
「……それが出来れば……」
苦労はしない。できないからこうして苦しんでいるのだ。
綾樹のそばを離れることも、思いつめて自らを終わりにすることもできない。
結局、そばにいられるのなら何でもいい。たとえ綾樹が自分を見てくれなくても。
そう割り切っているのだ。それ以上はいらないのだと。
だけど。
それを時折、我慢できなくなる。
身体と心が求めてしまうのだ。
そんな感情の隙間を感知して、ふいに秘蕾に男の指が入り込んでくる。
「あ、んっ」
男の指は隘路を割って、粘膜を磨き込むように出入りしているが、その指が桜井の敏感なところをかすめた。
「んああっ」
強い電圧にも似た激しい痺れが全身を駆け抜け、身体が弓なりに反る。佐藤はそんな桜井の痴態を楽しむように、着々と男を受け入れさせる準備を続けていた。
何度も何度も敏感な部分に触れられていると、快楽と共に鎌首を持ち上げてくるのは、桜井の本性だ。
「だめ、だめ、あっ、また、あっ……!」
きつく立ち上がった己から薄くなった白濁を噴き上げて、息も絶え絶えに快楽に囚われる。
身体も心ももうドロドロだ。
モットイカセテ……モット、モットオクマデ……
「ふふ、もうグズグズだな」
「言わないで……言わないでください……」
「また勃ってきたぞ。イキっぱなしの淫乱だな」
「だったら、その淫乱にふさわしい扱いをしてください」
「ん?」
質問の意味が分からなかったのか、佐藤が身を乗り出して、桜井の顔をじっと見る。
その瞳は、今までの飄々としていた佐藤のそれじゃない。冷たい刃のような鋭さと、燃え盛る野獣のような光の両方を秘め、快楽で泣き濡れた桜井をじっと見つめている。
「恭司、なんと言った?」
「私は淫乱……なんでしょう? なら、それらしい扱いをしてください」
「恭司……」
「壊して……私を」
こんなにも浅ましい自分の身体。このまま脳髄まで性の毒で溶かしてほしい。
佐藤の匂いをまとわせて、汚れ爛れた体と心なんか、綾樹が受け入れるはずもない。
だったらもういっそのこと、壊してほしい。
佐藤が淫乱だというなら、きっと自分はそうなのだろう。
「一生あなたの奴隷でいい……」
綾樹にこの思いが届かないなら――。
「壊して……」
子供のようにしゃくりあげて泣きながら佐藤に懇願する
「――おまえを壊して済むなら、とっくにそうしてる」
「…?」
佐藤は指を抜くと、代わりに自身を桜井の蕾にあてがった。
指とは違う、熱い切っ先がゆっくりと桜井の中に入ってくる。
「あ……」
隘路を割って入ってくる熱核は桜井を傷つけぬように、時間を掛けて入ってくる、やがて互いの叢が触れ、桜井の中に佐藤がすべて収まった。
「あったかいな、おまえの中は」
佐藤がふうと息を吐く。ついでに桜井の唇に優しいキスがふってくる。
「淫乱だなんて言って悪かった」
「どうしたんです、急に……」
「冷たいセックスは嫌だっておまえに言ったのに、俺はおまえにひどい言葉を投げつけた」
その謝罪は佐藤の本心だと感じた。いつもの自分勝手で強引な彼のそれではない。
いったい何事かと、桜井は泣き癖で出てしまったしゃっくりを押さえながら小首をかしげると、佐藤は「それは反則だぞ、恭司」と笑い、また唇にキスをした。
「俺が欲しいのは従順なお人形さんじゃない。生意気でプライドがエベレスト級に高い、そのくせちょっとダメージくらうと、すぐにさめざめ泣いてエロくなる、そんないじっぱりでかわいい弁護士先生が好きなんだ」
「だからあなたの思いは私には……」
「迷惑だって言うんだろ。わかってる。だが俺が勝手にしてることだ。そしておまえも何のかの言って、俺に付き合ってくれてる。俺はそれだけでいいんだよ。おまえは今、俺の腕の中にいる。少なくとも、いま俺が抱いているのは人形なんかじゃない」
その言葉に心臓がどきりと切なく跳ねた。
彼に抱かれるこの身体があたたかくなる。
「俺がいま抱いているのは、俺が世界でいちばん愛しているヤツだ」
心の奥からなにかほんわりとしたものが生まれ、それが全身を包んでいく。
この男はいつも桜井をからかってきた。
だけど、その目は真剣だ。佐藤は桜井を抱くときに、いつもこんな燃え盛る炎を宿した熱い瞳をしていたのだろうか。
「愛しているなんて……気安く言うものではありませんよ」
その視線とかち合うのが気恥ずかしくて、桜井は視線を反らして口を尖らせた。
「いざという時に、その言葉の重みを失ってしまいます」
「おまえを言葉で縛れるなら苦労はしない。だが、おまえに限らず、人はこうして感情を言葉にして、気持ちで示さないとなかなか理解しない」
佐藤が言いながら軽く突き上げてくる。しばらく互いが繋がっていたせいで、桜井の蕾は満開に花咲き、佐藤をなんなく受け入れていた。
奥をコツコツ叩くように軽く突かれ、切ない振動に桜井は思わず甘い声を漏らす。
「好きだ、恭司」
「……あっ」
「ーー愛している」
その低い声が合図となり、桜井の身体が揺すられる。
「だめ、あっ、気持ちいい……あんっ!」
桜井の中で感じる熱い脈動。中を穿たれながら、桜井は自らを犯す男の身体をかき抱いた。
いつもだったら、強引な佐藤に流されるだけのセックスが今日は違う。
佐藤が桜井の身体に与える衝撃は、とんでもなく強力な媚薬になっていた。
気持ちよくて、温かくて。このまま意識と身体が剥がされてしまいそうだ。佐藤の熱核が桜井の中でまた少し大きくなり、いっぱいに開いた花蕾がほんの少し、ひきつられる。
だけど、辛くない。この痛みが幸せに思える。
「恭司、好きだ、恭司……」
「……私、は……」
熱い告白に、胸中が揺れ、桜井の胸の中にいる綾樹の顔がぼんやりと霞んでいく。佐藤の熱核が奥を突くたび、綾樹が見えなくなっていく。
自分はいま、誰を一番愛しているのだろう?
桜井にとって、佐藤はたんなる代用品だった。
しかも桜井が望んだ代用品ではなく、どちらかといえば、押し売りに近い「綾樹の代わり」だ。
それでも今は、佐藤に抱かれるこの時が……愛おしい。
――私は彼のことが好きなのか。いや、そんなはずはない
静かなる混乱が、揺れて落ちそうになっている桜井を苦しめていた。
愛している――そんな言葉一つだけで、自分の中で何かが変化していく。
今、桜井がきつく抱きしめている男は、ずっと想い続けた綾樹ではない。
ましてや、綾樹の代用品なんかじゃない。
この男は佐藤だ。自分は今、佐藤に抱かれている――。
激しく揺らされている間も、佐藤のキスが降ってくる。くすぐったくて、やめてとばかりに顔を上げれば、そのまま唇をふさがれる。
「ん、ちゅ……」
舌を絡める深いキス。上も下も繋がって身も心もとろとろに熟れていく。
彼の情熱を全身で受け、桜井の全てが満たされていく。
佐藤の手で、達したい……。
「ゆう、じ……」
彼の名前が、自然と桜井の口をつく。佐藤は驚いて動きを止めた。
「恭司?」
「もっと抱いて私を……ゆうじ……ゆう、じ……」
一度出てしまったら、あとは止められない。
切なさと淋しさに愛しさが混ざり、佐藤だけがほしくてたまらない。
「お願い、裕二……私の中に……」
「恭司……」
佐藤の動きが激しさを増す。突き入れられる熱核の衝撃を最奥で受けながら、桜井は佐藤の腰に細い足をぎゅっと絡めた。
「一番奥に、あなたの命を注いで……」
「……いいだろう。孕むくらい注いでやる」
佐藤は右手で硬くなった桜井を握ると、そのまま激しく扱きだす。急に直接的な刺激を与えられ、桜井が小さな悲鳴を上げると、佐藤はニヤリと笑った。
「イクときは、一緒だ。俺がイクまで、射精は我慢しろ」
佐藤の熱核に最も感じるポイントを狙い撃ちされながら手淫されるなんて、どうしたって我慢なんかできやしない。腰は既にムズムズして射精の予感を感じる。桜井が陥落するまで時間はない。
「そんな、無理! 無理です! だめ、イク、イキそう! ああ、んんっ!」
激しくいやいやをするように頭を振りながら桜井は「許して」と懇願するが、しょせん相手は佐藤だ。桜井の褥での要求など、絶対に聞いてくれやしないどころか、愉しげに笑って完全スルーだ。
「もう、無理、無理!」
「恭司……いい子だ。よく我慢したな。さあ、イケ……」
耳から注がれる解放の合図。
瞬間、腹の奥から熱いものがせりあがってくる。
「だめぇ、イク、ああああああ!」
「……っ!」
白い闇が意識を塗りつぶす。ジワリ広がる温かなものを腹の奥で感じながら、桜井は自分を抱く男の唇にキスをする。
「恭司?」
「繋がったまま、キスしていたい……」
いけませんか?と耳元で囁けば、佐藤は「えらく積極的だな」と笑いながら、深く口づけてくる。
それを受けながら、桜井は男の背をしっかり抱きしめる。身体の中で蠢く佐藤の熱核を感じながら。
――わかっている。ちゃんとわかっている。
指先でなぞるこの輪郭。
これは綾樹でなく、佐藤の背中だと。
綾樹がずっと好きだった。
昔からずっと、今もそれは決して変わらないはずだ。
だけど今は、あんなに好きだった人の姿が心の中で霞み始めている。
桜井自身の中で、何かが変わろうとしている。
だが、今の桜井にはまだそれをちゃんと認める勇気はなかった。
まだ、今は――。
10
あなたにおすすめの小説

真空ベータの最強執事は辞職したい~フェロモン無効体質でアルファの王子様たちの精神安定剤になってしまった結果、執着溺愛されています~
水凪しおん
BL
フェロモンの影響を受けない「ベータ」の執事ルシアンは、前世の記憶を持つ転生者。
アルファ至上主義の荒れた王城で、彼はその特異な「無臭」体質ゆえに、フェロモン過多で情緒不安定な三人の王子たちにとって唯一の「精神安定剤」となってしまう。
氷の第一王子、野獣の第二王子、知略の第三王子――最強のアルファ兄弟から、匂いを嗅がれ、抱きつかれ、執着される日々。
「私はただの執事です。平穏に仕事をさせてください」
辞表を出せば即却下、他国へ逃げれば奪還作戦。
これは、無自覚に王子たちを癒やしてしまった最強執事が、国ぐるみで溺愛され、外堀を埋められていくお仕事&逆ハーレムBLファンタジー!
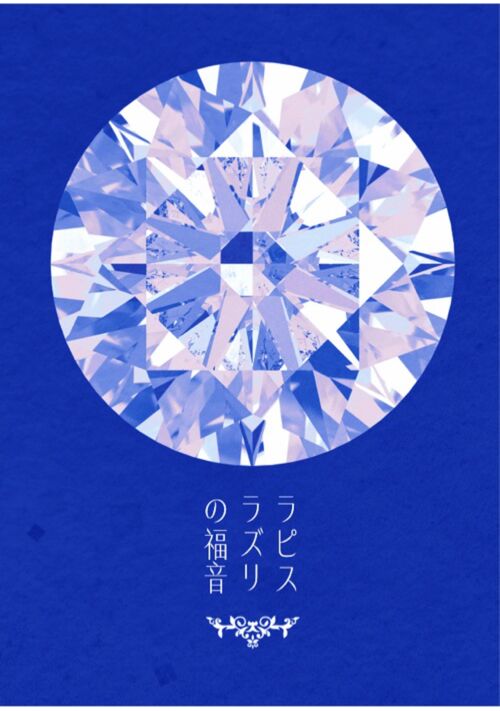
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

無口な愛情
結衣可
BL
『兄の親友』のスピンオフ。
葛城律は、部下からも信頼される責任感の強い兄貴肌の存在。ただ、人に甘えることが苦手。
そんな律の前に現れたのが、同年代の部下・桐生隼人。
大柄で無口、感情をあまり表に出さないが、実は誰よりも誠実で優しい男だった。
最初はただの同僚として接していた二人。
しかし、律が「寂しくて眠れない」と漏らした夜、隼人が迷わず会いに来たことで関係は大きく動き出す。
無口で不器用ながらも行動で示してくれる隼人に、律は次第に素直な弱さを見せるようになり、
日常の中に溶け込むささやかな出来事が、二人の絆を少しずつ深めていく。

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

君のスーツを脱がせたい
凪
BL
学生兼モデルをしている佐倉蘭とオーダースーツ専門店のテーラー加瀬和也は絶賛お付き合い中。
蘭の誕生日に加瀬はオーダースーツを作ることに。
加瀬のかっこよさにドキドキしてしまう蘭。
仕事、年齢、何もかも違う二人だけとお互いを想い合う二人。その行方は?
佐倉蘭 受け 23歳
加瀬和也 攻め 33歳
原作間 33歳


俺は隠して君は噓をつく
雲巡アキノ
BL
諒に片思いしていた敏は思いを告げないまま、卒業と同時に諒の前から姿を消した。
28歳になって偶然都内で再会した二人。片思いを隠して諒と会っていく敏は、彼の言葉に違和感を覚え始めて――
この作品はpixiv、ムーンライトノベルズ、カクヨム、エブリスタにも掲載をしています。
表紙はうきものさんからいただきました。ありがとうございます。

好きなわけ、ないだろ
春夜夢
BL
放課後の屋上――不良の匠は、優等生の蓮から突然「好きだ」と告げられた。
あまりにも真っ直ぐな瞳に、心臓がうるさく鳴ってしまう。
だけど、笑うしかなかった。
誰かに愛されるなんて、自分には似合わないと思っていたから。
それから二人の距離は、近くて、でも遠いままだった。
避けようとする匠、追いかける蓮。
すれ違いばかりの毎日に、いつしか匠の心にも、気づきたくなかった“感情”が芽生えていく。
ある雨の夜、蓮の転校の噂が流れる。
逃げ続けてきた匠は初めて、自分の心と正面から向き合う。
駅前でずぶ濡れになりながら、声を震わせて絞り出した言葉――
「行くなよ……好きなんだ」
誰かを想う気持ちは、こんなにも苦しくて、眩しい。
曇り空の下で始まった恋は、まだぎこちなく、でも確かにあたたかい。
涙とキスで繋がる、初恋の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















