61 / 104
四十三話 甲斐国 潜入(その二)
しおりを挟む
「痛ぅ~、飲み過ぎたぁ」
少ない睡眠が災いしたのか、重治は最悪の目覚めを迎えていた。
次の日の早朝、それまで重治と共に屋敷に世話になっていた、三人の兄弟が、屋敷をあとにし旅立っている。
甲斐、信濃、上州、駿河、武田の領土となっている国に放った伊蔵の配下で、連絡を絶った者たちの足取りを調べるため、伊蔵たちは、自らの足を使い、その地へ向かう事にしたのである。
久しぶりに伊蔵たちと離れて、一人で過ごす重治には、開放感と、そしてそれとは相反する不安感が合いまみれて、複雑な感情が心を支配していた。
重治にとっての三人は、今では体の一部と言ってもよいほど、大きな存在になっていたのである。
「ふぅ‥‥、もう少し寝ていたかったな……」
三人の見送りを済ませた重治は、痛む頭を押さえつつ、水を欲する体のためと顔を洗うため、井戸のある裏庭へと歩き始めた。
『ギイィ、ギイイィ、ギイイィ』
重治の耳に、つるべ(井戸の水を汲むためにつかう桶)を引き上げる滑車の軋む音が、痛む頭と共鳴するかのように届いていた。
「おはようございます。水をいっぱいいただけま‥‥」
重治の言葉が、動きが、思考が、すべて止まった。
そう、あの時を再現するかのように、凍りついたのである。再現するかのように、凍りついたのである。
「!あっ、おはようごさいます。‥‥お水ですよね……」
重治の言葉に気づいた、その少女は、手に持った空になった釣瓶を井戸に慌てて下ろした。
『ボォチャァン』
釣瓶は、朝早い真田屋敷の静かな裏庭に響いた。
『ギイィ、ギイイィ、ギイイィ』
少女の細い腕が、釣瓶に繋がる縄を力を込めて引き上げていく。
その間の重治と言えば、みっともなくも口をだらしなく少し開けたままで、ただ少女の動きを見ているだけである。
まともな恋愛の一つや二つ、こなしている男なら、まず間違いなく、目前の少女の力作業に手を貸していた筈である。
「ドウゾ……ドウぞ
……どうかなさいましたか?」
少女は、重治になんど呼びかけたのであろうか。
「あっ、あぁっ、ああぁっ!‥‥は、は、はぁいぃぃ」
重治は、にっこりと自分を笑顔で覗き込みながら声をかける少女
に、漸く我に返った。
「!‥‥祐、そいつから離れろ!!!」
漸く我に返った重治に怒りに満ちた罵声が飛んだ。
「‥‥突然に何ですか、信繁」
「何でもいい、ともかく、そいつに近づくな!」
悪意の満ちた言葉の発生源には、叫びながら重治達に近づき、仁王立ちに睨みつける信繁の姿があった。
重治の捉えた映像は、そのあと重治に想像もしない新展開を見せる。
ゆっくりと信繁に近づいた少女は、信繁のすぐ前に立った。
「‥‥のぶしげぇ!……」
「い、痛いです‥‥」
にっこりと微笑みながら、全く笑顔を崩さずその少女は、信繁のこめかみにあてた握り拳をグリグリと捻り込んだのである。
「祐ねぇ‥‥、か、勘弁してください……」
重治は、そんな二人の姿を ただただ、呆気にとられて見つめるだけであった。
「信繁。あれほど誰彼構わず噛みつくなと注意してるのが、わからないのですか!?」
「だって、そいつは……」
「だってぇ??」
祐姉と呼ばれたその少女は、笑顔の中にも威厳、迫力があり、信繁を完全に圧倒していた。
「い、痛い、痛い。痛うございます‥‥申し訳ありませぬ、私が悪う御座いました」
更に力を込めた拳骨が信繁を締め付け、ついには信繁は、全面降伏するに至るのであった。
「ごめんなさいね。この子、わがままに育ったから礼儀作法が出来てなくって……」
「…………」
重治は、そのか細く弱々しい清楚な少女からは想像も出来ない行動に呆気にとられた。
しかし、だだ清楚で大人しい可憐な少女のイメージよりも、遥かに親しみが持てる。重治は、真田家にまつわる人物で、祐と言う名前を頭の辞書から、ひたすら探し求めた。
頭でひたすら名前を探し求めながらも、視線は、祐に釘付けになった。
その天使のような笑顔は、手を伸ばせば、すぐにでも届く距離にある。
「……ユ、ユうさん……」
名前がデータ検索に引っからない重治は、たまらず名前を口にした。
「……?」
「‥‥ユうさぁ~……」
重治が再び勇気をだして、『祐』の名前を口にしかけた時、背後から突然、着物の襟首を掴み上げられたのである。
「重治!稽古をつけてやる。一緒について参れ」
こてんぱんに凹まされた信繁は、鬱憤晴らしの標的として、重治に目をつけたのである。
一昨日の無様な姿を見ている信繁にとっての重治は、鬱憤晴らしに最適な軟弱者に思われたのである。
有無をいわさず重治は、首根っこを抑えられ、無抵抗のまま無様に、信繁に引きずられていく。
それでも重治は、幸せだった。
通りすがりに出会った、二度と会う事などないと思っていた少女に、再び巡り会えたのである。
与えられた任務の重さを考えた時、重治には、出会った少女を探したくとも、探すようなまねをする訳にはいかなかった。
諦めたその相手が、何もせずに、今、目の前にいる。しかも、その少女は、まず間違いなく真田家に縁のある者に違いなかった。
今は、話す機会を失ってしまったが、この先、いつでも会える筈である。
重治は、幸せの絶頂のなか、信繁に引きずられるまま、先日の広場にまでついて行き、少年たちと汗を流す羽目になる。
「あぁ、疲れたぁ……」
稽古を終えた後の重治の素直な感想である。
気分ルンルン最高潮の重治は、馬鹿にされても蔑まれても、最後まで実力を伏せたままで稽古を終えた。
重治が、実力をそのまま少年たちに、ぶつければ、そこにいる八人の少年を一瞬にして倒す事ができてしまう。
しかし、自分よりも確実に格下の相手に稽古をつける時、相手の成長を促すならば、一方的な戦いは自信喪失を招くだけであり、その事が相手の成長に結びつく事は決してない。
それは、重治自身が自分の成長を促してくれた、超一流の師匠の達の域に達したからこそ、わかり得た事実であった。
重治の場合、幸運と言ってもいいほど、師匠には恵まれていた。
体の使い方、動かし方を幼き時から爺様に、竹中家伝来の古武術として叩き込まれ、戦略、策略ありあらゆる戦国の世を生き抜くに必要な秘訣を 時の麒麟児、天才軍師と言われたご先祖、竹中半兵衛から直々に学んだ。
そして、現在では、容易に学ぶことのできない槍術さえも、より実戦的な形で、猛将として名高い柴田勝家から体に叩き込まれている。
しかし、師匠が優秀だからとて、弟子の総てが優秀になるとは限らない。
重治に関して言えば、もちろんそれには当てはまらない。
素質に関しても、優秀な師匠を得た事も、すべての関わりを糧として重治は一流の戦国武将として成長してきた。
重治は、現在、唯一の弱点を除けば、無敵と言われる者にも匹敵するほどの力を手に入れていたのかもしれない。
相手を傷つけることを 恐れ躊躇うという最大の弱点を 除いてはである。
少年たちとの稽古の中では、信繁の力は、抜きん出ていた。
しかし、それはあくまで少年たちの中での話しである。
重治にとっての少年達は、大人と子供、それも幼子程度の相手としか言い様のないレベルであったのである。
少年たちからすれば、重治は、兄貴分にあたる年齢である。
重治は、自分が育てられたように、少年たちにも接していこうと思った。
それは事態は、間違いではなかったが、考え方を甘くみていた分のツケは、当然、本人が払うことになっていく。
それぞれの少年と剣を構えあえば、重治には相手の力を即座に判断出来てしまう。
相手の力量に合わせて打ち合い、相手に華を持たせた。その事が、自分の立場をどんどん悪くするとは思わずにいた。
「よし。今日の稽古はこれまでじゃ。‥‥重治。帰るぞ!!」
少年たちは、信繁に頭を軽く下げて礼をした。
それからの重治の立場は、八人の少年たちの弟分、使いパシリの立場に甘んじる日々が続いていく。
この平和な村を襲う、その大事件が起こる、その日になるまで。
年が明けても、少年たちの稽古は、いつもと変わらずにおこなわれていた。
相手の力量を見極める事の出来ない少年たちには、重治はそこそこの剣の使い手でしかなかった。
パシリであろうとなかろうと、ずっと、命の削り合いの中で、剣をふるってきた重治にとって、年の近い少年たちとのチャンバラごっこは、体の一部の三人がいない重治に、一つの心の安らぎを与えていた。
もちろん、祐と交わす朝の挨拶もまた、いわずと知れた事ではあるのだが。
重治が、そんな幸せな日常を過ごすある日、その出来事は始まった。
始まりは、稽古の最中、重治の耳に、ごく小さな悲鳴が聞こえた事からであった。
聞こえたとは言ったが、それはあまりにも小さく、周りの少年たちに聞こえることはなかった。
もちろん、それは信繁にも、ほぼ同様の事が言えた。
かけ声を張り上げ、打ち合う少年たちの中にいて、聞き分けられるような声ではない極々小さな悲鳴であった。
重治にしてみても、この段階ではまだ、悲鳴を悲鳴として捉える事は出来ないでいた。
その次の異常は、少年たちのすべてに感じる事が出来た。
『ガンガンガーン、ガンガンガーン、ガンガンガーン、ガンガンガーン、ガンガンガーン、ガンガンガーン、ガンガンガーン』
村の異常をすべての村人に伝えるため、半鐘が続けざまに打ち続けられたのである。
村を襲ったその異様な集団は、何の前触れもなく突如として現れた。
数十騎の馬にまたがった、一見、野武士崩れの盗賊集団であった。
もちろん、内部崩壊寸前の治安の悪いこの国では、食いはぐれた者たちが徒党をくんだ盗賊が当然のように存在する。
しかし、この時に現れた数十騎の統率のとれた騎馬武者風の者達は、誰の目から見ても、明らかに普通の物取りの盗賊とは違っていたのである。
「重治は、ここにいて、こいつらを守っていてくれ!!」
そう、重治に告げた信繁は、騒ぎのする村の入り口に向かって走り出した。
戦場では、未だ初陣を経験していない信繁の歴史には記録に残らない記念すべき初陣であった。
重治の信繁の戦力としての評価は、決して悪くはない。
並みの武将とならば、一対一で闘えば、まず負ける事はないとさえ感じていた。
しかし、それはつまる所、稽古の上でならばの話しであって、実践としては未知数としか言えない。
命のやり取りの実戦の場では、当然、経験がものを言う。
命のやり取りに、稽古の時のような正々堂々と言うものは、存在しない。どれだけの修羅場を潜り抜けてきたかが、勝敗の左右を決していく。
重治は、走り出した信繁を見て、慌ててそこにいる七人の少年たちに強く言いつけた。
「いいか。おまえたちは、何があってもここを動くな。いいな!」
少年たちの前で叫んだ重治は、それまでの少年たちの知る、稽古でへらへらと自分たちにやられる重治とは、まるで別人であった。
目をまん丸く見開き、驚き頷く少年たちをその場に残し、重治もまた、信繁の後を追い、駆け出した。
その盗賊の群れは、家屋に火を放ち、大声で騒ぎ立てていた。
しかし、刃向かっていく行く者に対しては攻撃をしかけるものの、村人すべてを虐殺するような行動はとってはいなかった。
食糧、金品を奪う訳でもなく、ただ騒ぎを大きく目立たせているようであった。
そう、明らかに盗賊とは違う行動。盗賊に見せかけてはいるが、そこには明らかなる別の目的が感じられた。
そんな盗賊集団の襲撃は、信繁の気付く遥かその前、盗賊が村に入る前に、物見の者から屋敷にいた真田家当主、昌幸のもとに知らされていた。
「ええぃ、よいか。男衆には武器を携えて、すぐに集まるように伝えよ!」
それだけを配下のものに伝えると、昌幸は腕組みをして、唸りだした。
「ううぅん……、おかしい……、どう考えてもおかしい……」
昌幸は、最初にもたらされた情報のみにも関わらず、現れた盗賊に疑問を抱いた。
真田屋敷のあるこの村は、近隣にある村などに比べ、遥かに防備は堅い。
そんな村を危険を冒してまで盗賊が、わざわざ襲う理由が存在し得るのか?答えは、否である。
強いて、その答えを見つけ出すとしたならば、それは、そこに真田屋敷があり、当主である昌幸がいる。ただそれだけに行き当たる。
「……やはりな。‥‥それ以外にはあり得ぬな‥‥」
結論を導き出した昌幸は、危険を承知で、外に集まりだした男衆のもとへと屋敷を飛び出した。
信繁が、その場所に駆けつけた時、それは合戦の始まりを告げられたところであった。
いつも見慣れた村の風景は、あちこちから火の手が舞い上がり、まったく見たことのない別の空間を作りあげていた。
そんな緊迫した場所で、信繁の目に飛び込んだのが、重治が初めに僅かに聞き分けた悲鳴の持ち主が、盗賊に捕らわれた姿であった。
「祐ねえ!!」
信繁には、現状を把握できるほどの経験はなかった。気がつけば、捕らわれた、祐を目指して、まっすぐに走り出してしまっていたのである。
「‥‥!、信繁!信繁、来ちゃ駄目!!」
敵の真っ只中を祐に向かって突っ走る信繁。
盗賊の陣容の把握すらせずに走る信繁には、祐の悲鳴にも似た叫びは届かなかった。
「のぶしげ?‥‥あやつが、信繁か、はっはははは……」
祐の首もとに小刀を突き付けた男は、信繁を見て笑った。
「飛んで火にいる‥‥はっはははは。わざわざ人質になりにくるとわな‥‥」
盗賊がその時、何を考えているかなど、周りにすら目がいかない信繁には、わかる筈がなかった。
盗賊が不適な笑いを漏らす間も信繁は、盗賊たちの中心に向かっていた。
信繁が危機を迎えていた頃、昌幸は、全体の状況を見渡せるその場所で、集まった男衆達を統率し盗賊と対峙していた。
昌幸の冷静的確な指示により村人達は、盗賊の群れに対し辛うじて応戦する事が出来ていた。
しかし、辛うじての戦いをしているとはいっても、防戦一方の村人たちと、盗賊たちとでは、状況的に差がありすぎた。
村人たちとは違い、盗賊たちには、余裕さえあったのである。
信繁を追いかけて走り出した重治ではあったが、最初の出遅れは、最悪の事態へと結びついていく。
「重治様。信繁が、信繁が……」
祐を見つけた重治が近づくと、祐は、重治の胸に泣き叫びながら飛び込んだ。
「……ゆ、ゆ、ゆうさん。だ、大丈夫ですか!?」
「はい。‥‥でも、信繁が、信繁が……」
重治に抱きしめられたことにより、少しは落ち着きを取り戻したのであろうか、祐は、重治の目をしっかりと見つめて話しを始めた。
「あいつらの目的は、お館様です。‥‥信繁様を人質に……」
「いいですか、祐さんは、ここを動かないで‥‥。信繁は、俺が、必ず助け出しますから‥‥」
不安な表情の祐をその場に残し、重治は、再び走り出した。
少ない睡眠が災いしたのか、重治は最悪の目覚めを迎えていた。
次の日の早朝、それまで重治と共に屋敷に世話になっていた、三人の兄弟が、屋敷をあとにし旅立っている。
甲斐、信濃、上州、駿河、武田の領土となっている国に放った伊蔵の配下で、連絡を絶った者たちの足取りを調べるため、伊蔵たちは、自らの足を使い、その地へ向かう事にしたのである。
久しぶりに伊蔵たちと離れて、一人で過ごす重治には、開放感と、そしてそれとは相反する不安感が合いまみれて、複雑な感情が心を支配していた。
重治にとっての三人は、今では体の一部と言ってもよいほど、大きな存在になっていたのである。
「ふぅ‥‥、もう少し寝ていたかったな……」
三人の見送りを済ませた重治は、痛む頭を押さえつつ、水を欲する体のためと顔を洗うため、井戸のある裏庭へと歩き始めた。
『ギイィ、ギイイィ、ギイイィ』
重治の耳に、つるべ(井戸の水を汲むためにつかう桶)を引き上げる滑車の軋む音が、痛む頭と共鳴するかのように届いていた。
「おはようございます。水をいっぱいいただけま‥‥」
重治の言葉が、動きが、思考が、すべて止まった。
そう、あの時を再現するかのように、凍りついたのである。再現するかのように、凍りついたのである。
「!あっ、おはようごさいます。‥‥お水ですよね……」
重治の言葉に気づいた、その少女は、手に持った空になった釣瓶を井戸に慌てて下ろした。
『ボォチャァン』
釣瓶は、朝早い真田屋敷の静かな裏庭に響いた。
『ギイィ、ギイイィ、ギイイィ』
少女の細い腕が、釣瓶に繋がる縄を力を込めて引き上げていく。
その間の重治と言えば、みっともなくも口をだらしなく少し開けたままで、ただ少女の動きを見ているだけである。
まともな恋愛の一つや二つ、こなしている男なら、まず間違いなく、目前の少女の力作業に手を貸していた筈である。
「ドウゾ……ドウぞ
……どうかなさいましたか?」
少女は、重治になんど呼びかけたのであろうか。
「あっ、あぁっ、ああぁっ!‥‥は、は、はぁいぃぃ」
重治は、にっこりと自分を笑顔で覗き込みながら声をかける少女
に、漸く我に返った。
「!‥‥祐、そいつから離れろ!!!」
漸く我に返った重治に怒りに満ちた罵声が飛んだ。
「‥‥突然に何ですか、信繁」
「何でもいい、ともかく、そいつに近づくな!」
悪意の満ちた言葉の発生源には、叫びながら重治達に近づき、仁王立ちに睨みつける信繁の姿があった。
重治の捉えた映像は、そのあと重治に想像もしない新展開を見せる。
ゆっくりと信繁に近づいた少女は、信繁のすぐ前に立った。
「‥‥のぶしげぇ!……」
「い、痛いです‥‥」
にっこりと微笑みながら、全く笑顔を崩さずその少女は、信繁のこめかみにあてた握り拳をグリグリと捻り込んだのである。
「祐ねぇ‥‥、か、勘弁してください……」
重治は、そんな二人の姿を ただただ、呆気にとられて見つめるだけであった。
「信繁。あれほど誰彼構わず噛みつくなと注意してるのが、わからないのですか!?」
「だって、そいつは……」
「だってぇ??」
祐姉と呼ばれたその少女は、笑顔の中にも威厳、迫力があり、信繁を完全に圧倒していた。
「い、痛い、痛い。痛うございます‥‥申し訳ありませぬ、私が悪う御座いました」
更に力を込めた拳骨が信繁を締め付け、ついには信繁は、全面降伏するに至るのであった。
「ごめんなさいね。この子、わがままに育ったから礼儀作法が出来てなくって……」
「…………」
重治は、そのか細く弱々しい清楚な少女からは想像も出来ない行動に呆気にとられた。
しかし、だだ清楚で大人しい可憐な少女のイメージよりも、遥かに親しみが持てる。重治は、真田家にまつわる人物で、祐と言う名前を頭の辞書から、ひたすら探し求めた。
頭でひたすら名前を探し求めながらも、視線は、祐に釘付けになった。
その天使のような笑顔は、手を伸ばせば、すぐにでも届く距離にある。
「……ユ、ユうさん……」
名前がデータ検索に引っからない重治は、たまらず名前を口にした。
「……?」
「‥‥ユうさぁ~……」
重治が再び勇気をだして、『祐』の名前を口にしかけた時、背後から突然、着物の襟首を掴み上げられたのである。
「重治!稽古をつけてやる。一緒について参れ」
こてんぱんに凹まされた信繁は、鬱憤晴らしの標的として、重治に目をつけたのである。
一昨日の無様な姿を見ている信繁にとっての重治は、鬱憤晴らしに最適な軟弱者に思われたのである。
有無をいわさず重治は、首根っこを抑えられ、無抵抗のまま無様に、信繁に引きずられていく。
それでも重治は、幸せだった。
通りすがりに出会った、二度と会う事などないと思っていた少女に、再び巡り会えたのである。
与えられた任務の重さを考えた時、重治には、出会った少女を探したくとも、探すようなまねをする訳にはいかなかった。
諦めたその相手が、何もせずに、今、目の前にいる。しかも、その少女は、まず間違いなく真田家に縁のある者に違いなかった。
今は、話す機会を失ってしまったが、この先、いつでも会える筈である。
重治は、幸せの絶頂のなか、信繁に引きずられるまま、先日の広場にまでついて行き、少年たちと汗を流す羽目になる。
「あぁ、疲れたぁ……」
稽古を終えた後の重治の素直な感想である。
気分ルンルン最高潮の重治は、馬鹿にされても蔑まれても、最後まで実力を伏せたままで稽古を終えた。
重治が、実力をそのまま少年たちに、ぶつければ、そこにいる八人の少年を一瞬にして倒す事ができてしまう。
しかし、自分よりも確実に格下の相手に稽古をつける時、相手の成長を促すならば、一方的な戦いは自信喪失を招くだけであり、その事が相手の成長に結びつく事は決してない。
それは、重治自身が自分の成長を促してくれた、超一流の師匠の達の域に達したからこそ、わかり得た事実であった。
重治の場合、幸運と言ってもいいほど、師匠には恵まれていた。
体の使い方、動かし方を幼き時から爺様に、竹中家伝来の古武術として叩き込まれ、戦略、策略ありあらゆる戦国の世を生き抜くに必要な秘訣を 時の麒麟児、天才軍師と言われたご先祖、竹中半兵衛から直々に学んだ。
そして、現在では、容易に学ぶことのできない槍術さえも、より実戦的な形で、猛将として名高い柴田勝家から体に叩き込まれている。
しかし、師匠が優秀だからとて、弟子の総てが優秀になるとは限らない。
重治に関して言えば、もちろんそれには当てはまらない。
素質に関しても、優秀な師匠を得た事も、すべての関わりを糧として重治は一流の戦国武将として成長してきた。
重治は、現在、唯一の弱点を除けば、無敵と言われる者にも匹敵するほどの力を手に入れていたのかもしれない。
相手を傷つけることを 恐れ躊躇うという最大の弱点を 除いてはである。
少年たちとの稽古の中では、信繁の力は、抜きん出ていた。
しかし、それはあくまで少年たちの中での話しである。
重治にとっての少年達は、大人と子供、それも幼子程度の相手としか言い様のないレベルであったのである。
少年たちからすれば、重治は、兄貴分にあたる年齢である。
重治は、自分が育てられたように、少年たちにも接していこうと思った。
それは事態は、間違いではなかったが、考え方を甘くみていた分のツケは、当然、本人が払うことになっていく。
それぞれの少年と剣を構えあえば、重治には相手の力を即座に判断出来てしまう。
相手の力量に合わせて打ち合い、相手に華を持たせた。その事が、自分の立場をどんどん悪くするとは思わずにいた。
「よし。今日の稽古はこれまでじゃ。‥‥重治。帰るぞ!!」
少年たちは、信繁に頭を軽く下げて礼をした。
それからの重治の立場は、八人の少年たちの弟分、使いパシリの立場に甘んじる日々が続いていく。
この平和な村を襲う、その大事件が起こる、その日になるまで。
年が明けても、少年たちの稽古は、いつもと変わらずにおこなわれていた。
相手の力量を見極める事の出来ない少年たちには、重治はそこそこの剣の使い手でしかなかった。
パシリであろうとなかろうと、ずっと、命の削り合いの中で、剣をふるってきた重治にとって、年の近い少年たちとのチャンバラごっこは、体の一部の三人がいない重治に、一つの心の安らぎを与えていた。
もちろん、祐と交わす朝の挨拶もまた、いわずと知れた事ではあるのだが。
重治が、そんな幸せな日常を過ごすある日、その出来事は始まった。
始まりは、稽古の最中、重治の耳に、ごく小さな悲鳴が聞こえた事からであった。
聞こえたとは言ったが、それはあまりにも小さく、周りの少年たちに聞こえることはなかった。
もちろん、それは信繁にも、ほぼ同様の事が言えた。
かけ声を張り上げ、打ち合う少年たちの中にいて、聞き分けられるような声ではない極々小さな悲鳴であった。
重治にしてみても、この段階ではまだ、悲鳴を悲鳴として捉える事は出来ないでいた。
その次の異常は、少年たちのすべてに感じる事が出来た。
『ガンガンガーン、ガンガンガーン、ガンガンガーン、ガンガンガーン、ガンガンガーン、ガンガンガーン、ガンガンガーン』
村の異常をすべての村人に伝えるため、半鐘が続けざまに打ち続けられたのである。
村を襲ったその異様な集団は、何の前触れもなく突如として現れた。
数十騎の馬にまたがった、一見、野武士崩れの盗賊集団であった。
もちろん、内部崩壊寸前の治安の悪いこの国では、食いはぐれた者たちが徒党をくんだ盗賊が当然のように存在する。
しかし、この時に現れた数十騎の統率のとれた騎馬武者風の者達は、誰の目から見ても、明らかに普通の物取りの盗賊とは違っていたのである。
「重治は、ここにいて、こいつらを守っていてくれ!!」
そう、重治に告げた信繁は、騒ぎのする村の入り口に向かって走り出した。
戦場では、未だ初陣を経験していない信繁の歴史には記録に残らない記念すべき初陣であった。
重治の信繁の戦力としての評価は、決して悪くはない。
並みの武将とならば、一対一で闘えば、まず負ける事はないとさえ感じていた。
しかし、それはつまる所、稽古の上でならばの話しであって、実践としては未知数としか言えない。
命のやり取りの実戦の場では、当然、経験がものを言う。
命のやり取りに、稽古の時のような正々堂々と言うものは、存在しない。どれだけの修羅場を潜り抜けてきたかが、勝敗の左右を決していく。
重治は、走り出した信繁を見て、慌ててそこにいる七人の少年たちに強く言いつけた。
「いいか。おまえたちは、何があってもここを動くな。いいな!」
少年たちの前で叫んだ重治は、それまでの少年たちの知る、稽古でへらへらと自分たちにやられる重治とは、まるで別人であった。
目をまん丸く見開き、驚き頷く少年たちをその場に残し、重治もまた、信繁の後を追い、駆け出した。
その盗賊の群れは、家屋に火を放ち、大声で騒ぎ立てていた。
しかし、刃向かっていく行く者に対しては攻撃をしかけるものの、村人すべてを虐殺するような行動はとってはいなかった。
食糧、金品を奪う訳でもなく、ただ騒ぎを大きく目立たせているようであった。
そう、明らかに盗賊とは違う行動。盗賊に見せかけてはいるが、そこには明らかなる別の目的が感じられた。
そんな盗賊集団の襲撃は、信繁の気付く遥かその前、盗賊が村に入る前に、物見の者から屋敷にいた真田家当主、昌幸のもとに知らされていた。
「ええぃ、よいか。男衆には武器を携えて、すぐに集まるように伝えよ!」
それだけを配下のものに伝えると、昌幸は腕組みをして、唸りだした。
「ううぅん……、おかしい……、どう考えてもおかしい……」
昌幸は、最初にもたらされた情報のみにも関わらず、現れた盗賊に疑問を抱いた。
真田屋敷のあるこの村は、近隣にある村などに比べ、遥かに防備は堅い。
そんな村を危険を冒してまで盗賊が、わざわざ襲う理由が存在し得るのか?答えは、否である。
強いて、その答えを見つけ出すとしたならば、それは、そこに真田屋敷があり、当主である昌幸がいる。ただそれだけに行き当たる。
「……やはりな。‥‥それ以外にはあり得ぬな‥‥」
結論を導き出した昌幸は、危険を承知で、外に集まりだした男衆のもとへと屋敷を飛び出した。
信繁が、その場所に駆けつけた時、それは合戦の始まりを告げられたところであった。
いつも見慣れた村の風景は、あちこちから火の手が舞い上がり、まったく見たことのない別の空間を作りあげていた。
そんな緊迫した場所で、信繁の目に飛び込んだのが、重治が初めに僅かに聞き分けた悲鳴の持ち主が、盗賊に捕らわれた姿であった。
「祐ねえ!!」
信繁には、現状を把握できるほどの経験はなかった。気がつけば、捕らわれた、祐を目指して、まっすぐに走り出してしまっていたのである。
「‥‥!、信繁!信繁、来ちゃ駄目!!」
敵の真っ只中を祐に向かって突っ走る信繁。
盗賊の陣容の把握すらせずに走る信繁には、祐の悲鳴にも似た叫びは届かなかった。
「のぶしげ?‥‥あやつが、信繁か、はっはははは……」
祐の首もとに小刀を突き付けた男は、信繁を見て笑った。
「飛んで火にいる‥‥はっはははは。わざわざ人質になりにくるとわな‥‥」
盗賊がその時、何を考えているかなど、周りにすら目がいかない信繁には、わかる筈がなかった。
盗賊が不適な笑いを漏らす間も信繁は、盗賊たちの中心に向かっていた。
信繁が危機を迎えていた頃、昌幸は、全体の状況を見渡せるその場所で、集まった男衆達を統率し盗賊と対峙していた。
昌幸の冷静的確な指示により村人達は、盗賊の群れに対し辛うじて応戦する事が出来ていた。
しかし、辛うじての戦いをしているとはいっても、防戦一方の村人たちと、盗賊たちとでは、状況的に差がありすぎた。
村人たちとは違い、盗賊たちには、余裕さえあったのである。
信繁を追いかけて走り出した重治ではあったが、最初の出遅れは、最悪の事態へと結びついていく。
「重治様。信繁が、信繁が……」
祐を見つけた重治が近づくと、祐は、重治の胸に泣き叫びながら飛び込んだ。
「……ゆ、ゆ、ゆうさん。だ、大丈夫ですか!?」
「はい。‥‥でも、信繁が、信繁が……」
重治に抱きしめられたことにより、少しは落ち着きを取り戻したのであろうか、祐は、重治の目をしっかりと見つめて話しを始めた。
「あいつらの目的は、お館様です。‥‥信繁様を人質に……」
「いいですか、祐さんは、ここを動かないで‥‥。信繁は、俺が、必ず助け出しますから‥‥」
不安な表情の祐をその場に残し、重治は、再び走り出した。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

転生したら名家の次男になりましたが、俺は汚点らしいです
NEXTブレイブ
ファンタジー
ただの人間、野上良は名家であるグリモワール家の次男に転生したが、その次男には名家の人間でありながら、汚点であるが、兄、姉、母からは愛されていたが、父親からは嫌われていた

ゲームコインをザクザク現金化。還暦オジ、田舎で世界を攻略中
あ、まん。
ファンタジー
仕事一筋40年。
結婚もせずに会社に尽くしてきた二瓶豆丸。
定年を迎え、静かな余生を求めて山奥へ移住する。
だが、突如世界が“数値化”され、現実がゲームのように変貌。
唯一の趣味だった15年続けた積みゲー「モリモリ」が、 なぜか現実世界とリンクし始める。
化け物が徘徊する世界で出会ったひとりの少女、滝川歩茶。
彼女を守るため、豆丸は“積みゲー”スキルを駆使して立ち上がる。
現金化されるコイン、召喚されるゲームキャラたち、 そして迫りくる謎の敵――。
これは、還暦オジが挑む、〝人生最後の積みゲー〟であり〝世界最後の攻略戦〟である。

【㊗️受賞!】神のミスで転生したけど、幼児化しちゃった!〜もふもふと一緒に、異世界ライフを楽しもう!〜
一ノ蔵(いちのくら)
ファンタジー
※第18回ファンタジー小説大賞にて、奨励賞を受賞しました!投票して頂いた皆様には、感謝申し上げますm(_ _)m
✩物語は、ゆっくり進みます。冒険より、日常に重きありの異世界ライフです。
【あらすじ】
神のミスにより、異世界転生が決まったミオ。調子に乗って、スキルを欲張り過ぎた結果、幼児化してしまった!
そんなハプニングがありつつも、ミオは、大好きな異世界で送る第二の人生に、希望いっぱい!
事故のお詫びに遣わされた、守護獣神のジョウとともに、ミオは異世界ライフを楽しみます!
カクヨム(吉野 ひな)にて、先行投稿しています。

45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる
よっしぃ
ファンタジー
2巻決定しました!
【書籍版 大ヒット御礼!オリコン18位&続刊決定!】
皆様の熱狂的な応援のおかげで、書籍版『45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる』が、オリコン週間ライトノベルランキング18位、そしてアルファポリス様の書店売上ランキングでトップ10入りを記録しました!
本当に、本当にありがとうございます!
皆様の応援が、最高の形で「続刊(2巻)」へと繋がりました。
市丸きすけ先生による、素晴らしい書影も必見です!
【作品紹介】
欲望に取りつかれた権力者が企んだ「スキル強奪」のための勇者召喚。
だが、その儀式に巻き込まれたのは、どこにでもいる普通のサラリーマン――白河小次郎、45歳。
彼に与えられたのは、派手な攻撃魔法ではない。
【鑑定】【いんたーねっと?】【異世界売買】【テイマー】…etc.
その一つ一つが、世界の理すら書き換えかねない、規格外の「便利スキル」だった。
欲望者から逃げ切るか、それとも、サラリーマンとして培った「知識」と、チート級のスキルを武器に、反撃の狼煙を上げるか。
気のいいおっさんの、優しくて、ずる賢い、まったり異世界サバイバルが、今、始まる!
【書誌情報】
タイトル: 『45歳のおっさん、異世界召喚に巻き込まれる』
著者: よっしぃ
イラスト: 市丸きすけ 先生
出版社: アルファポリス
ご購入はこちらから:
Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4434364235/
楽天ブックス: https://books.rakuten.co.jp/rb/18361791/
【作者より、感謝を込めて】
この日を迎えられたのは、長年にわたり、Webで私の拙い物語を応援し続けてくださった、読者の皆様のおかげです。
そして、この物語を見つけ出し、最高の形で世に送り出してくださる、担当編集者様、イラストレーターの市丸きすけ先生、全ての関係者の皆様に、心からの感謝を。
本当に、ありがとうございます。
【これまでの主な実績】
アルファポリス ファンタジー部門 1位獲得
小説家になろう 異世界転移/転移ジャンル(日間) 5位獲得
アルファポリス 第16回ファンタジー小説大賞 奨励賞受賞
第6回カクヨムWeb小説コンテスト 中間選考通過
復活の大カクヨムチャレンジカップ 9位入賞
ファミ通文庫大賞 一次選考通過
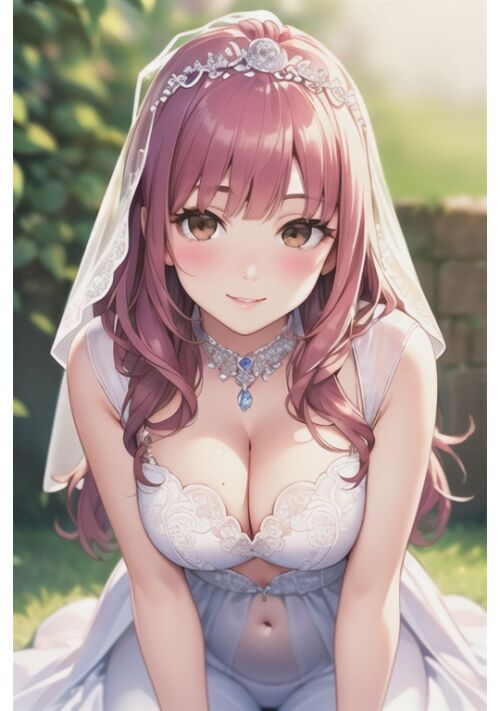
兄貴のお嫁さんは異世界のセクシー・エルフ! 巨乳の兄嫁にひと目惚れ!!
オズ研究所《横須賀ストーリー紅白へ》
ファンタジー
夏休み前、友朗は祖父の屋敷の留守を預かっていた。
その屋敷に兄貴と共に兄嫁が現れた。シェリーと言う名の巨乳の美少女エルフだった。
友朗はシェリーにひと目惚れしたが、もちろん兄嫁だ。好きだと告白する事は出来ない。
兄貴とシェリーが仲良くしているのを見ると友朗は嫉妬心が芽生えた。
そして兄貴が事故に遭い、両足を骨折し入院してしまった。
当分の間、友朗はセクシー・エルフのシェリーとふたりっきりで暮らすことになった。

異世界転移魔方陣をネットオークションで買って行ってみたら、日本に帰れなくなった件。
蛇崩 通
ファンタジー
ネットオークションに、異世界転移魔方陣が出品されていた。
三千円で。
二枚入り。
手製のガイドブック『異世界の歩き方』付き。
ガイドブックには、異世界会話集も収録。
出品商品の説明文には、「魔力が充分にあれば、異世界に行けます」とあった。
おもしろそうなので、買ってみた。
使ってみた。
帰れなくなった。日本に。
魔力切れのようだ。
しかたがないので、異世界で魔法の勉強をすることにした。
それなのに……
気がついたら、魔王軍と戦うことに。
はたして、日本に無事戻れるのか?
<第1章の主な内容>
王立魔法学園南校で授業を受けていたら、クラスまるごと徴兵されてしまった。
魔王軍が、王都まで迫ったからだ。
同じクラスは、女生徒ばかり。
毒薔薇姫、毒蛇姫、サソリ姫など、毒はあるけど魔法はからっきしの美少女ばかり。
ベテラン騎士も兵士たちも、あっという間にアース・ドラゴンに喰われてしまった。
しかたがない。ぼくが戦うか。
<第2章の主な内容>
救援要請が来た。南城壁を守る氷姫から。彼女は、王立魔法学園北校が誇る三大魔法剣姫の一人。氷結魔法剣を持つ魔法姫騎士だ。
さっそく救援に行くと、氷姫たち守備隊は、アース・ドラゴンの大軍に包囲され、絶体絶命の窮地だった。
どう救出する?
<第3章の主な内容>
南城壁第十六砦の屋上では、三大魔法剣姫が、そろい踏みをしていた。氷結魔法剣の使い手、氷姫。火炎魔法剣の炎姫。それに、雷鳴魔法剣の雷姫だ。
そこへ、魔王の娘にして、王都侵攻魔王軍の総司令官、炎龍王女がやって来た。三名の女魔族を率いて。交渉のためだ。だが、炎龍王女の要求内容は、常軌を逸していた。
交渉は、すぐに決裂。三大魔法剣姫と魔王の娘との激しいバトルが勃発する。
驚異的な再生能力を誇る女魔族たちに、三大魔法剣姫は苦戦するが……
<第4章の主な内容>
リリーシア王女が、魔王軍に拉致された。
明日の夜明けまでに王女を奪還しなければ、王都平民区の十万人の命が失われる。
なぜなら、兵力の減少に苦しむ王国騎士団は、王都外壁の放棄と、内壁への撤退を主張していた。それを拒否し、外壁での徹底抗戦を主張していたのが、臨時副司令官のリリーシア王女だったからだ。
三大魔法剣姫とトッキロたちは、王女を救出するため、深夜、魔王軍の野営陣地に侵入するが……

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















