10 / 11
第十話 禁忌の行い
しおりを挟む
アルバイト先だったコンビニをスローンと責任者に任せ、天魔郷に急いで向かって行く俺とセラフィー。
セラフィーの顔には吹っ切れたのか、先程までの暗い表情は既に消えていて、今は自分の成すべき事に集中しているかのように決心付いた頼りになる眼をしていた。
「どうして、こんな事に……っ」
セラフィーは痛むように顔が強張る。
「……元々は、俺達が望んでいた事だ」
「……」
「何もかもが正反対。考えも価値観も、野望も。それが俺達にとっての妨げとなり、いつしか恨むようになっていた」
セラフィーも思い当たるのか、ただ黙って頷く。
「それが長く続く度に恨みの念は底は強く絡みつき、間の亀裂は取り返しのつかない程まで広がっていってしまった」
「……」
「でも、今は違う」
「!」
「ちゃんと心の底にある自分の気持ちを、勇気を持って踏み出し、本音を打ち明ければ、こうして仲を取り戻す事だって出来るんだって、俺達が証明出来た。だからあいつらだって、少しの勇気を出せば何かが変わると思うんだ。ま、本気で嫌っている奴もいると思うけどな」
ニカっと爽やかな笑みを向けてきたルシフェルに、セラフィーはキョトンとしてしまう。
「……ふふっ」
何かが可笑しかったのか、セラフィーは口元を手で覆い隠し、笑みを隠す仕草をする。
「な、何が可笑しいんだよっ」
笑う姿が無邪気で可愛かったのか、それとも俺の歯に青海苔が付いているのか、俺の発言が可笑しかったのか知らないが、なんとなく顔を赤くしてしまう。
「いえ。なんだか、天使みたいだな~と思って」
「なっ!」
度肝を突かれたように、俺は後ろ髪を引っ張られるように仰け反ってしまう。
「まるで天使のような悪魔、または悪魔のような天使といった感じです」
「……それどっちも同じ意味なんじゃねーの?」
「……あ、そうかもですね」
「なんだそりゃ」
たわいもない会話に俺達は思わず微笑んでしまう。
天魔郷の危機が訪れているというのに呑気だなあと自分でも思う。
きっと、心の底では何とかなると安心しきっているのかもしれない。
一人では不可能でも、こうして二人で手を取り合えば解決出来てしまう事だってある。
その安堵の心地よさに俺は依存するかのように甘えてしまっているのかもしれない。
だが勿論、セラフィーに大きな荷を背負わせない。
むしろ甘えて欲しいぐらいである。
なんなら甘々の甘さ加減に甘い味の甘さを余す事なく甘えて貰って甘い時間を共有したいぐらいだ。
……なんか俺、本当変わったな。
まあそれは願望としてさて置き、俺自身が男としてかっこよく頼りになる所をアピール出来る絶好のチャンスでもあるので、頑張るぞい!
「……見えてきましたね」
「……ああ」
何が、とは言わなくても分かる。
––––––天魔郷だ。
外から見る分にはなんの変哲も無い俺達が良く知る天魔郷にしか感じられないが、中では世界が逆転したかのように重々しい空気に覆われているに違いない。
それは外見だけ取り繕って中身はスカスカな人間界の労働環境に似ている。
外見だけで判断してはいけない。
しっかりと、中身を確認せねば……。
天魔郷に近づくにつれ、俺達は緊張感が高まり、よりいっそう気合が入った。
★
天魔郷に着いた俺達は地に足を付け、翼を引っ込める。
人間界では外は真っ暗であった為、こちらの世界も同じく真っ暗であった。
人間界と時差は変わらないこの世界では、人間界と同じく今は就寝の時間だ。
その為、外は度々発生するそよ風とそれに踊らされる草の音しか聞こえない。
人間界と違い、外灯がないこの世界は月の光を頼りに道を進まなければならない。
といっても、月の光がなくても特段困る事はなく、あったほうがハッキリと道や建物が見えるからイイヨネ! ぐらいの感じだ。
それに長く住んでいるこの世界は俺達の庭みたいなものなので、道に迷う事はない。
俺達は数多の樹木やレンガの建物を潜り抜けスイスイと進んで行く。
そうして進んで行く中で、俺達は良からぬ気を感じてしまった。
「……セラフィー」
「ええ。この気……。ちょっとやばい気がします」
「急ぐぞ」
「はい」
俺達は僅かに冷や汗をかきながら、先へと進んで行く。
唾を飲み込むゴクリという音が、そよ風に紛れ込むように新たに聞こえた。
★
程なくして、天使城と悪魔城の丁度境目に到着した俺達は、気の感じる方向にそれぞれ体を向ける。
「え?」
「ん? そっちですか?」
「俺は悪魔城から感じるけど……」
「私は天使城ですね……」
二人は気を感じる方向に指をさしながら顔だけを向かい合わせ、見当違いにキョトンとしてしまう。
「……まさか」
セラフィーは何か思いついたようにハッとなり、強張った表情で言う。
「『結界』ですね」
「なるほど。それだ」
『結界』とはその名の通り、一定の範囲内に神々のオーラを具現化して幕を張り、外からの攻撃や侵入を防ぐ事が出来る防御技である。
耐久力はオーラの量に比例し、結界に巡らせるオーラが多ければ多いほどその
防御力は真価を施す。
しかし、神々のスタミナの源であるオーラを常に放出維持するのは至難で、長く保つ事は王レベルの実力者が複数いても不可能な程。
そして何よりこの結界の優れている点は防御力の他にもう一つ。
––––––相手に『気』を感知させる事を不可能にする事。
結界には元々二種類が存在しており、天使が張る『陽結界』、悪魔が張る『陰結界』がある。
どちらの結界も性能には変わりはないが、己の種族が張った結界の中であれば膨大なオーラを放出しようとも、同種族でなければ相手には感知されなくなるという違いがある。
これは結界の外にいる者にも適用される。
今回でいえば、ルシフェルは陰結界、セラフィーは陽結界を感知出来ていた。
それは同種族が張った結界であるからだ。
つまり、この結界の恐ろしい所は膨大なオーラを必要とする大技を『不意打ちで』放つ事が可能になるという事。
例えば、『禁忌魔法』など……。
スローンの話を照らし合わせると結界を張る動機にも合点が付く。
俺とセラフィーは片方だけを阻止するだけでは意味が無い事を理解し、要点だけを伝えて各々で行いを阻止する作戦に。
「じゃ、気をつけてな」
「ルシフェルこそ、無茶はなさらないで下さいね」
「ああ、セラフィーもな。こっちが片付いたら直ぐに応援に行くから」
「ふふっ、それは頼もしいです。––––––では、また会いましょう」
「おう!」
短いやり取りを終え、俺は悪魔城、セラフィーは天使城へと向かい、禁忌魔法の発動を阻止する為に、全力で走って向かって行く。
間に落ちていた一枚の落ち葉がひらりと宙に舞い、ヒラヒラと捩りながらゆっくりと落ちていった。
★
––––––悪魔城の屋上。
月夜に照らされながら瞳を閉じ、両手を頭上に上げ佇んでいる一人がいた。
「もう直ぐ……もう直ぐで……この争いも終わる」
––––––第二使徒ベルゼだ。
両手の上で禍々しい紫色の高エネルギーを元気玉のように溜めている。
通称––––––『魔玉』
その高エネルギーさゆえ、地は揺れ、風は舞い、見た者を萎縮させる。
絶望の始まりであり、世界の終わりをこれから告げるかのように。
それだけの高魔力を維持しておきながらも、天界の者に気づかれないのは結界の効力によるもの。
そして、それだけの魔力を維持し続けられるのは、それに協力するかのように魔界の者一人一人が少量ながらもベルゼに分け与え続けているからだ。
例え雀の涙程でしかなくても、全員が合わさればその量は膨大な量となる。
一人の力では決して成立する事が出来ない禁忌魔法。それが最大の威力を誇る六式であれば尚更の事だ。
そんな魔力を与え続けている魔界の一人が膝を屈し、疲労を浮かべる。
「……くっ、申し訳ございません。ベルゼ様。……私は、そろそろ限界かもしれません」
「ええ。無茶はしなくて結構よ。ありがとう。そこで少し休んでなさい」
魔力とは生命力そのもの。それが尽きてしまえば死に繋がる。
魔力の量は各々で異なり、その量は力にも比例する。
その気持ちを十分に理解しているベルゼは責める事なく、優しく休むよう告げた。
それからドミノ倒しのように、次々と魔力を分け与え続けていた者達も脱落していく。
長い時間やっていた為、魔力が尽き始めてきているのだろう。
今はベルゼ一人がやや疲労感を浮かべならも魔力を与え続けている。
脱落した者は尊敬の目でベルゼの後ろ姿を見つめている。
やはり、代王だけあってその光景に見惚れてしまっているだろう。
普段はであるルシフェルが執り行う事だが、こうしてルシフェルの代わりを務めているのだから見惚れてしまうのも無理は無い。
他ではそうはいかないだろう。
使徒は、たった一つ離れているだけで力量の差は火を見るより明らか。
「……こんなところね」
ベルゼにも魔力が尽き始めたのか、魔玉に魔力を与える手を止めてしまう。
改めて魔玉を見返してみると、その禍々しさに自分でも恐怖を感じてしまった。
ふわふわと中に浮かんでいる魔玉は禍々しさは更に顕著になり、天界だけではなく、魔界もろとも消し飛んでしまうのではないかと、そう思わせるからだ。
これまで禁忌魔法の使用を試みた事は愚か、拝見した事もないベルゼは扱いによる不安も感じてしまっている。
天界を滅ぼす意志が強く働き、その情の勢いに任せて禁忌魔法を試みたものの、いざ使用するとなるとミスが許されない一発勝負の本番みたいで心のざわつきは鳴りを潜めなくなる。
実際、手は微かに震えていた。
きっと疲労によるものだろう。そうやって現実から目を逸らして、自分を偽って落ち着かせる。
そして瞳を閉じ、冷静さを取り戻そうと精神を落ち着かせようとすると、ある人物が浮かび上がる。
「……リヴァイアは、何処に行ったのかしら」
その呟きは風と共に月夜に消えていく。
ベルゼはこれまで、急に姿を消したリヴァイアを心配して魔界の者達に事情を話したものの、これといった情報は得られないでいた。
リヴァイアに何があったのか皆目見当もつかない。
魔界の周辺を探したが姿は見つからない。
であれば、人間界に足を運んだと考えるのが妥当だった。
その意図は……何処か引っかかる部分もあった。
でも、知らないふり。
だから、止むを得ずリヴァイア抜きで取り行った。
悔やみがあるとすれば、リヴァイアがいれば魔玉も更に強力な物に出来たという事。
第三使徒程の魔力があれば魔玉の威力を底上げする事が出来、より作戦の成功率がグッと高める事が出来た。
でも、それでも、天界を滅ぼすには十分な魔力が集まった。
後は結界を外し、魔玉を放つだけ。
「……さぁ、始めましょうか」
「何をだ?」
「!?」
ベルゼの背後に突如現れた黒い少年。
腕を組み、鋭く細められた眼光に向けられた者は自然と後ろめいてしまい、ひれ伏してしまいそうだ。
先程までベルゼを見惚れていた者達も今はその対象が変わり、片膝を屈して頭を下げている。
そんな予想を裏切るように現れた、現れてしまった事態に思わずベルゼはたじろぎ、重い口が開かずにいる。
そして覚悟の覚悟に重ねた強い意を決っすると、ようやくその重い口は僅かに開き始める。
「ル……ルシフェル様……っ。お帰りになられたのですね……」
無理して笑顔を取り繕うとするも、それはただ顔を引きっているだけの苦笑いでしかなかった。いや、それが精一杯だった。
王の静かに怒りが満ちている瞳に気圧されてしまっているからだ。
その為、普段自然と行っている頭を下げる崇拝の意を示すのを忘れてしまっている。
「ああ。たった今な。––––––で? これはどういう事だ? ベルゼ」
ルシフェルはふわふわと浮かんでいる魔玉にチラッと視線を向けて問う。
ベルゼは額に冷や汗を浮かべており、その勢いが止まる事はない。
「こ、これはっ……」
「……」
黙って何も口を聞かないルシフェルに対して窮屈に感じてしまい、観念したかのように正直に話し出す。
「……禁忌魔法を使い、天界を滅ぼそうとした所存です」
正直に告げた言葉は今にも消えてしまいそうに掠れていた。
「……ふむ」
「ルシフェル様がご不在の間、一時的に王の権力が譲渡された私は––––––」
「もういい」
「!」
ベルゼの弁解の余地を途中で遮るルシフェルの口調は苛立ちを含んでいた。
「ベルゼ、お前のやろうとしている事は十分理解している。俺達の宿敵である天界の者達を滅ぼし、この天魔郷を魔界だけの世界にしようとしたのだろう?」
「お、仰る通りでございます! ルシフェル様!」
ここでようやく、ベルゼは片膝を地につき、頭を下げ始める。
「俺が不在であれば王の権限は第二使徒であるお前に譲渡される。故に、何をしようとも許されるに等しい。だからお前は何も間違ってなどいない」
「い、痛み入ります!」
「だが、俺を抜きに禁忌魔法を使用するなど驚いたぞ。ベルゼ」
「……も、申し訳ございません」
「謝るな、さっきも言ったはずだぞ。お前は何も間違ってなどいないってな……」
「…………」
俺は魔玉を見つめながら、ベルゼに問う。
「……それ程、天界の奴らが憎いか?」
質問の返答を試されているかのように感じたベルゼは一度はハッとするが、直ぐに冷静さを取り戻す。
「……はい。これまで失った仲間達の死を……私は、果たしてやりたいのですっ」
ベルゼの顔は、今にでも泣いてしまいそうな程弱々しくなっいた。
「失ったものは帰って来ない……。なのにっ! 奪ったあいつらがのこのこと正義ぶって生きているのが許せないです!」
急に感情的になったベルゼに驚きを感じてしまう。
それは俺だけではなく、他の悪魔達も一緒だった。
普段は冷静で取り乱す事はなく平然とやり過ごすベルゼだが、この瞬間だけは別人のように感じた。
「でもっ、分かっているんです。それはあいつらも同じ想いでいるのではないかと……」
仲間の命を失ったのは天界も同じ。だからベルゼの思っている事は天界の者達も思っているという事。
あれだけ敵意を向けておきながらも、しっかりと相手の気持ちを汲み取っているのが分かる。
「だから私は、この争いに終止符を打とうと決めたのです! もう誰も悲しまない、魔界だけの世界にしようと」
天使と悪魔が同じ世界にいるから争いは止まないでいる。なら、どちらかが滅んでしまえば自ずと争いは無くなるだろうという極シンプルな考え。
一人残らず滅ぼす。すれば、仲間の死を悲しまずにして、一生の眠りにつく事が出来る。それは孤独に生きるよりも、いっそ殺してやった方が相手の為なのかもしれない。
「……そうか」
俺はベルゼの本心を聞いて、瞳を閉じて思う。
ベルゼの言っている事は正しい選択の一つであると理解してしまったのだ。
天使と悪魔がこれから先も変わらぬ関係で変わらぬ日々を過ごしていこうというならば、それはある意味精神的拷問に近い感覚だ。
争いは鳴り止まず、ただ命の危険性が伴うだけの関係。
さして広くない天魔郷。そんな小さな箱の中で元々水と油の関係である天使と悪魔が一緒に住んでいる事自体おかしな話なのかもしれない。
これが悪魔だけの世界だったら……。と、想像してしまうだけでも幸せな世界しか想像つかない。
スッキリとした、晴々とした、イキイキとした表情で、雰囲気で、幸せそうに暮らしている奴らの事が容易に浮かんでしまう。
殺そうとするのは簡単。
逆に、俺が思い描いていた世界は複雑。
その方が楽で、実現性が高くて、確実性がある。
もしかしたら、ベルゼの方が王に相応わしいのかもしれない。
俺はもしかしたら、もしかしたらと自分に言い訳をし、天界を滅ぼそうとするのをはぐらかしてきた。
その結果、仲間を失う事態が起こってしまった。
でも、ベルゼは違う。
これから先、仲間の死を見ない為に、失わせないように、自ら率先して禁忌魔法まで用いてその世界を実現させようとした。
行動力が違う。信念の強さが違う。仲間への思いが……違う。
自分の行動が浅はかで、愚かであったと実感する。
セラフィーと二人だけで過ごしたいという欲に溺れ、天魔郷の問題を後回しにし、人間界でのこのこと平和に暮らしていた。
実に、滑稽だ。
王、失格だ。
ベルゼの方が余程、王に相応わしいじゃねぇか……。
……俺は今まで、何をしていたんだっ……。
ズザッと、地に両膝をつく音が屋上に響いた。
その音の出だしに視線を向けたみんなは、驚愕しながら絶句している。
両膝を地についたと思えば、今度は力尽きたかのように体を前に倒してしまう。
そこから動きを見せる事ないその姿は、王の姿として有り得ない光景だった。
––––––土下座だ。
全員が目を疑った。
誇り高き悪魔の王が、こんなにも惨めで、情けなくて、弱い姿を晒しているのだから。
今までに一度も見た事がない光景に、全員は硬直し、空気までにも伝染してしまう。
今聞こえるのは葉っぱが散っていく音のみ。
やがて居心地が悪い空間を引き裂くように、ベルゼがようやく重たそうな口を開いた。
「ル、ルシフェル様……?」
土下座している俺を、全員が見下ろす構図になっている。
その中でも一際近い位置にいたベルゼが代表みたく声を発した。
それに対し、俺は土下座のまま言葉を発した。
「……俺の不甲斐なさで、お前達を不安にさせて、本当に申し訳ない……」
途中で言葉が詰まりかける。
「お前達を……天魔郷をこうさせてしまっているのは、全部俺の責任だ」
「な、何をおっしゃいますか! ルシフェル様!」
「いいや、本当の事だ。俺は王でありながら、今までお前達に何もしてやれなかった」
「そんな事ございません! 堕天使の襲撃の時、ルシフェル様は私達を命懸けでお守りくださいました!」
「……でも、それだけだ」
「それだけじゃありません! 私達は知っています! ルシフェル様が私達の為に、常に気にかけてお守りしている事も!」
ベルゼ言葉に魔界の者達も微笑みながら無言で頷く。
俺は頭を下げっぱなしで、その顔を、表情を伺う事は出来ない。
それでも、みんなの代表で告げているその言葉には、嘘偽りなく答えている気がした。
その証拠に、俺の眼には一滴の滴が浮かび上がっている。
それを見せまいと、目を数回パチパチさせて滴を瞳に浸す。
そしてようやく、俺は重たそうに体を立ち上がらせる。
最初に映ったのは、微笑みの顔を浮かべている魔界の者達。
––––––あぁ、俺はなんて幸せ者なんだ。
こんな俺に、まだ付いて来てくれるのか。
なんて返したらいいのか、分からんな。
いや、返す必要はないのかもしれないな。
言葉にしなくとも、こいつらは理解している。
全く、厄介な奴らだ。
今まで隠して来たつもりが全部お見通しという事わけかよ。
かっこいい姿だけを見せてやりたいと思っていたが、かっこ悪い姿まで見られていたのかもしれない。
全く、惨めだ。
それでも、こいつらは。
俺は全員の顔を見渡した後、決して揺らぐ事のない強い意志を持って王として告げる。
「……お前達に、一生のお願いがある!」
★
ルシフェルと分かれた私はこれまでにないスピードで天使城に向かっている。
私の役目は部屋に閉じ込められているリヴァイアを救出し、禁忌魔法を阻止する事。
「急がないと……っ」
天使城の入り口に着いた私は扉を開き、中に入る。
普段は一階リビングで誰かしら迎え入れてくれるものの、今回はそれがない事による違和感を感じてしまう。
「やはり、屋上ですね」
なんとなくは理解していた。
それでも私が一階に来た理由は、リヴァイアの救出を先に選んだ為だ。
友人が、仲間が部屋に閉じ込められている情報を聞いて、それを後回しにする事は出来なかった。
私は急いで一階奥にある部屋に向かう。
辿り着くと、ふご丁寧にしっかりと施錠されている。
ガチャガチャと雑に弄ってみても、開く気配は無い。
だがそれを開ける鍵を持っておらず、取りに行くのにも時間が惜しかった。
「……仕方がありませんね」
なので、強引にこじ開ける事に。
「ホーリーレーザー(聖なる光線)」
指先から僅かに放たれる光線が鍵をぶっ壊す。
床に落ちた鍵がカランと音を高く響きさせると同時に、僅かにドアがギィと開き始める。
まるで誘導されているかのようだ。
慌てた様子で中に入ると、中には意識がなさそうに倒れているリヴァイアがいた。
それを見て、不安な気持ちにさせられる。
「リヴァイアさん!」
リヴァイアの元まで走り寄り、肩を揺らす。
いくら声をかけても肩を揺らしても反応は無い。
まさかと思ったセラフィーは、リヴァイアの額に覆い被さっている前髪を手で覆い上げる。
その額の中心には文字とは言えない術式が描かれている。
「……これは、催眠の術式」
セラフィーにも心当たりがあるのか、直ぐに術式を理解すると、その術式に手を当て解き始める。
「解!」
すると、リヴァイアの額に描かれていた術式がスゥーっと消失する。
完全に無くなると、リヴァイアは目を薄らと開き始め、徐々に意識が回復していくように目覚め始める。
最初に視界に映った私を見て、リヴァイアは目をパチクリと大きくして驚く。
「セ、セラフィー……?」
「良かった。お怪我はありませんか?」
「えぇっと……。リィは、なんでこんな所に…………!」
記憶を思い返すとリヴァイアは思い出し、焦りと怒りを含んでいるかのような口調でセラフィーに告げる。
「そうだ、あいつらだ! スローンがリィを騙して、それで––––––」
「いいえ。スローンはそんな事していません。ただ、タイミングが悪かっただけですよ」
リィヴァイアは怪訝そうな顔でセラフィーを見つめる。
「……どういう、事?」
「説明は後です。今は、禁忌魔法を阻止しなければなりませんので」
「はっ、そうだ。スローンもそんな事言ってた……」
「なるほど。やはり、スローンも私達と同じですね」
「同じ?」
「いずれ分かりますよ。では、私はこれで––––––」
言葉だけを残し、その場を立ち去ろうとするセラフィーの手が掴まれる。
不意に掴まれた事に反射的に驚いてしまい、振り返る。
そこには口元を強く結びながら強く決意した瞳が向けられていた。
「リィも、行く」
初めは頼りになる発言に思わず頼みそうになってしまったが、その言葉を無理やり飲み込んで抑える。
そして首を振り、セラフィーは告げる。
「ありがとうございます、リヴァイア。でも、これは私の責務です。リヴァイアさんを巻き込む訳にはいきません」
ごもっともな言葉を並べてみたものの、リヴァイアは納得がいっていない様子。
「ううん、違うよ。こんな事になっているのは……リィ達にも、原因はあるから」
その暗く後悔しているような表情に、セラフィーは言葉を詰まらせてしまう。
「だから、セラフィーだけに重荷を背負わせたくないの!」
「!」
気付いたら、リヴァイアの目には涙が潤っていた。
今まで自分が振る舞って来ていた行動に自責と後悔の念が湧き上がり、心を痛めているに違いない。
そんな勇気を持って心の内を明かしてくれた事に対して断るのも罪悪感のようにも感じてしまうに違いない。
本気の言葉には本気の返事を。
セラフィーは一度微笑み、リヴァイアに協力の願いを告げた。
「ふふっ、ではお言葉に甘えても宜しいですか?」
「うん!」
セラフィーは現在の状況を詳しく説明する。
「今、天界と魔界でそれぞれ禁忌魔法を用いて、相手を滅ぼそうとしています。しかも厄介な事に結界を張り巡らせて察知できないようにまで施されています。おそらく、不意打ちで放つつもりなのでしょう」
「結界……。だから気が感じられないんだね」
セラフィーはコクリと頷く。
「魔界側はルシフェル、天界側は私で阻止する作戦を二人で決め、今に至っています」
リヴァイアは無言でうんうんと頷き納得している様子。
というのも、話の素性はベルゼやスローンから聞いているからだ。
リヴァイアはスローンの言っている事は本当だったんだと改め、自分を騙していた悪人だと決め付けていた事に罪悪感を感じてしまっていた。
「リヴァイアさんは、ルシフェルの援護に向かってもらっても宜しいですか?」
「え、こっちはいいの?」
「ええ。天界側の問題は展開側で済ませるべきでしょう。それに、魔界側のリヴァイアさんが姿を現してしまえば手を出してくる者もいるかもしれません。まだ、些細な認識は払拭されていませんでしょうから」
「……分かった」
それに対し、セラフィーはニコッと微笑む。
そして踵を返し、部屋を出ようとする。
ドアを出てリビングに出ると、二階に進む通路と城の出口に進む通路で分かれる際、二人は背中合わせで答える。
「お願いします、リヴァイアさん」
「大丈夫! ルシフェル様がいるもん!」
ウィンクをかまし、親指を立てグッジョブのポーズを示す。
それを見て、思わず微笑んでしまう。
「ええ。そうですね」
二人は互いに微笑み合うと、直ぐに行くべき道に向かって進んでいく。
今、リビングには誰一人といない。
そんな音ひとつ無い静まり返った空間に、ドアの閉まる音だけが響き渡った。
★
リヴァイアと別れ、室内の階段を凄まじい勢いで駆け上がっていくセラフィー。
本来なら城の外に出て翔んで行った方が速いのではないかと思うが、気が動転していた為、冷静な判断が下せなくなっていたのかもしれない。
それでも私は屋上へと続く階段を登る足を緩める事なく駆け上がる。
今更引き返して翔んでいくのも気が進まないし、何より余計に時間が掛かってしまう。
それに、硬直気味である体をほぐすには丁度良い。
僅かに息が乱れてくると頭の中がクリアになっていく感じがするし、硬直気味な体が解れてきた。
体のコンディションが整いつつあるその絶好のタイミングで屋上への扉を開いた。
最初に目に映ったのは、大勢の天界の者達。
目を瞑り、祈るようにして何やら聖なる力、いわゆる聖力をある物体へと注いでいる。
その物体とは、禁忌魔法六式である『聖玉』だ。
ある者の両手の上で禍々しい黄金色の高エネルギーを元気玉のように溜めている。
その高エネルギーさゆえ、地は揺れ、風は舞い、見た者を萎縮させる。
魔玉と何ら変わらない。
唯一相違点があるとすれば色の違いだけ。
そんな大勢の天界の者達より先頭に立って聖玉を支えている人物……天界における第二使徒、ケルビムだ。
「ケルビム、これは一体どういう事ですか?」
背後から細い声が屋上に響く。その声は直ぐに風と共にかき消されそうな程であったが、やや怒りを含んであるかのようなトーンに自然と耳に入ってきてしまう。
その証拠として、聖玉に注いでいた天界の者達全員が一斉にセラフィーに振り返る。
振り返った者達は、口をわなわなと震えながら怯えている。
だが、先頭に立っているケルビムは振り返らず、そのまま声を発する。
「……セラフィー様なら、ご理解頂けると思うのですが」
その通りだ。ケルビムが何故、禁忌魔法を行っているのかは既に理解していた。
––––––魔界の者達を全滅させる為。
頭の中では理解していたのにも関わらず、それでも口走って聞いてしまったのは、やはり気が動転していて、動揺してしまっているからだろう。
「……ケルビム、どうして……っ」
もう一つ理由を挙げるとすれば、ケルビムがこのような行いをしている事にある。
ケルビムは真面目で上の命令であれば卒なくこなし、下の者から助けを求められれば迷う事なく救う。
自分勝手な行動も、判断も、決断もする事はない。
必ず、今まで王であるセラフィーに相談してくれていた。
そんなイメージを持っていたセラフィーは、今回のような行いを受け入れ難かったのだろう。
まるで裏切られたような感覚。それが、セラフィー良心を傷つけた。
ケルビムが振り返らないのは、そんなセラフィーを目にしたくないという思いもあるのかもしれない。
セラフィーに長く慕って来たからこそ、お互いがお互いの事を理解してしまっているのだろう。
「私は、もう終わらせたいのです。この醜き争いを」
今、ケルビムがどのような顔をしているのか伺う事は出来ない。
それでも、言葉のトーンやニュアンスは少なくとも悲しそうであった。
「失った仲間達は、もう戻らない。これから先、いつまた争いが起こるかも分からない。そんな日々を過ごしていくのは、もう嫌なのです!」
最後の方、怒りの感情が含まれているのを感じた。
そしてようやく、ケルビムは振りかえる。
「勝手な行動を起こしてしまった事は、深くお詫び致します。––––––でも! どうか、私達の気持ちを、ご理解下さいっ……」
ケルビムが深々と頭を下げると、それに合わせて他の天界の者達も同じように頭を下げ始める。
全員が、セラフィーに向かって頭を下げ始める光景に思わずたじろいでしまう。
普段は挨拶がてらに頭を下げられる光景は何度も目にしているものの、今回のはそれとまるっきり違う。
それは、覚悟の強さを見せしめているかのようだった。
私は、言葉が出てこない。
天使と悪魔が仲良い世界を作ろうと思っていた夢を、否定されている感覚だったから。いや、初めから全員思ってすらいないのかもしれない。
所詮は理想論だと。現実を見ろと。
口には出さなくとも想いは伝わるのだと、初めて今分かってしまった。
もう、頭の中がごちゃごちゃだ。
私達の夢が灰のように崩れ去ろうとしている事、禁忌魔法を用いてでも相手を滅ぼそうとする事、今私は、どうするのが正解なのかという事。
頭の中に溜まっていくだけで、決して減る事がない。
頭痛のように頭が重く、痛くなってくるような感覚だ。
王として情けない。
こんな非常事態にも関わらず、ただ唇を噛みしめ、手をプルプルと震えさせて込み上がってくる自責の念を押さえ付けることしか出来ないのだから。
……私はただ、目を背けていただけなのかもしれない。
みんなの声を、こうなる事を……。
そう言った意味では、私は王失格だ。
むしろケルビムの方が王として相応しいのかもしれませんね。
その証拠に、こうして一致団結している。
中には嫌々やっている者もいるかもしれませんが、みんなの真剣な顔つきからしてそれはありませんね。
––––––………………。
私はゆっくりと、ケルビムまで歩き出す。
重りが付けられているかのように重い足を、確実に一歩ずつ踏み出していく。
天界の者達は端に避けて道を空けてくれる。
何も口にしなくても、その行き先はケルビムである事は皆察したのだろう。
ケルビムは代王であり、禁忌魔法をとり行った。
それなら、王同士で事の行き先を話し合うのは当然。
だが、歩み寄ってくるセラフィーの目は、覚悟を決したような鋭い目つきをしている。
普段は温厚で笑顔を絶やさないセラフィーだが、今のセラフィーには何処か悪魔のような戦闘狂にも感じる。
それを感じたケルビムは、思わず武器を転送しそうになる。
だが、その異様な圧に押され、転送する手が怯えて動かない。
武器をセラフィーに向ける事は本来ならあってはならない事。
いくら代王とはいえ、その権限は王であるセラフィーが戻って来た時点で剥奪されるのも当然だからだ。
今は通常通り、王と第二使徒の関係。
だが現状、ケルビムはそんな常識的観点は頭にはなく、武器を転送し始めた瞬間腕の一本は持ってかれるイメージを感じてしまい、それに怯えてしまっているのだ。
やがて、ケルビムに人一人分まで近づき足を止めたセラフィーは、細くてしなやかな指をケルビムの頬に向かって伸ばし始める。
「!」
殺されると思った矢先、その指はケルビムの頬を優しく撫で始めた。
「えっ?」
自分の想定していた現実と異なり、情けない声を出してしまった。
それに気付いていないかのように、セラフィーは告げる。
その時の顔は、いつもの温厚で優しい笑顔をしていた。
「私が不在の間、皆さんをお守り頂き、ありがとうございます」
「……そ、そんなっ、滅相もございません!」
深々と頭を下げ始めるセラフィーを見て、それを返すようにケルビムも慌てて深々と頭を下げ始める。
暫くして頭をあげたセラフィーは、聖玉をジッと見つめる。
「それにしても、良くここまでエネルギーを溜め込みましたね」
そう聞かれ、頭をあげたケルビムは聖玉を一緒に見つめて答える。
「は、はい! 皆で力を合わせて、ここまで溜め込む事が出来ました」
「ふふっ。皆で、ですか」
思わず、微笑んでしまった。
力を合わせて作られた聖玉。その強いエネルギーには、みんなの想いが募っている気がした。
「では、ケルビム」
「はい!」
キリッとした顔つきで名前を呼ばれ、ケルビムもキリッとした顔つきで振り返る。
セラフィーがスッと視線を背けた先には悪魔城が。
それに釣られ、ケルビムも悪魔城に目を向ける。
「代王を務めたからには、しっかりと最後まで責任を取ってもらいますよ?」
「あ、はい!」
初めからそのつもりで代王の座に君臨していたケルビムは迷う事なくハッキリとした返事をする。
その真っ直ぐな返事に、嬉しく感じてしまう。
(ごめんなさい……。ルシフェル……)
心の中で祈りに似た言葉を呟くと、セラフィーは悪魔城に向かって手を伸ばす。
「…………。……ケルビム、放つ準備をお願いします」
「はっ!」
ケルビムによって作られた聖玉。それを放つのも、コントロールするのもケルビムにおいて他にいない。
聖玉は、禁忌魔法を発動した者に委ねられる。
ケルビムは頭上で浮かばせている聖玉の前に、六式魔法陣を発動する。
そして、発射口である六式魔法陣の中央部分を悪魔城に合わせる。
片目を閉じながら少しずつ微調整し、完了するとセラフィーに体を向ける。
「発射準備、整いました。後は、放つだけです」
「……ご苦労様、ケルビム。……では、私の合図と共に、放って下さい」
「承知致しました」
「……………………………………………………お願いしますっ」
セラフィーが発射の合図を出すと、ケルビムは聖玉を放った。
膨大なエネルギーが六式魔法陣の中心部分から轟音を鳴り響かせながら悪魔城に一直線に向かって行く。
神々しいエネルギーが通ろうとする周辺は地を削り、木や建物を吹き飛ばし、風までも切り裂いて行く。
時刻は夜中だというのに、そこだけ陽が差しているかのようだった。
天界の者達は遂にこの時が来たのだと期待を胸に多く膨らませながら喜ばしい表情をしている。
その高鳴る気持ちを共感しようと、ケルビムは隣にいるはずのセラフィーに声を掛けようとした。
––––––だが既にセラフィーの姿はそこに無く、あるのは誰も気付く筈のない地に染み付いた、一滴の水跡だけだった。
セラフィーの顔には吹っ切れたのか、先程までの暗い表情は既に消えていて、今は自分の成すべき事に集中しているかのように決心付いた頼りになる眼をしていた。
「どうして、こんな事に……っ」
セラフィーは痛むように顔が強張る。
「……元々は、俺達が望んでいた事だ」
「……」
「何もかもが正反対。考えも価値観も、野望も。それが俺達にとっての妨げとなり、いつしか恨むようになっていた」
セラフィーも思い当たるのか、ただ黙って頷く。
「それが長く続く度に恨みの念は底は強く絡みつき、間の亀裂は取り返しのつかない程まで広がっていってしまった」
「……」
「でも、今は違う」
「!」
「ちゃんと心の底にある自分の気持ちを、勇気を持って踏み出し、本音を打ち明ければ、こうして仲を取り戻す事だって出来るんだって、俺達が証明出来た。だからあいつらだって、少しの勇気を出せば何かが変わると思うんだ。ま、本気で嫌っている奴もいると思うけどな」
ニカっと爽やかな笑みを向けてきたルシフェルに、セラフィーはキョトンとしてしまう。
「……ふふっ」
何かが可笑しかったのか、セラフィーは口元を手で覆い隠し、笑みを隠す仕草をする。
「な、何が可笑しいんだよっ」
笑う姿が無邪気で可愛かったのか、それとも俺の歯に青海苔が付いているのか、俺の発言が可笑しかったのか知らないが、なんとなく顔を赤くしてしまう。
「いえ。なんだか、天使みたいだな~と思って」
「なっ!」
度肝を突かれたように、俺は後ろ髪を引っ張られるように仰け反ってしまう。
「まるで天使のような悪魔、または悪魔のような天使といった感じです」
「……それどっちも同じ意味なんじゃねーの?」
「……あ、そうかもですね」
「なんだそりゃ」
たわいもない会話に俺達は思わず微笑んでしまう。
天魔郷の危機が訪れているというのに呑気だなあと自分でも思う。
きっと、心の底では何とかなると安心しきっているのかもしれない。
一人では不可能でも、こうして二人で手を取り合えば解決出来てしまう事だってある。
その安堵の心地よさに俺は依存するかのように甘えてしまっているのかもしれない。
だが勿論、セラフィーに大きな荷を背負わせない。
むしろ甘えて欲しいぐらいである。
なんなら甘々の甘さ加減に甘い味の甘さを余す事なく甘えて貰って甘い時間を共有したいぐらいだ。
……なんか俺、本当変わったな。
まあそれは願望としてさて置き、俺自身が男としてかっこよく頼りになる所をアピール出来る絶好のチャンスでもあるので、頑張るぞい!
「……見えてきましたね」
「……ああ」
何が、とは言わなくても分かる。
––––––天魔郷だ。
外から見る分にはなんの変哲も無い俺達が良く知る天魔郷にしか感じられないが、中では世界が逆転したかのように重々しい空気に覆われているに違いない。
それは外見だけ取り繕って中身はスカスカな人間界の労働環境に似ている。
外見だけで判断してはいけない。
しっかりと、中身を確認せねば……。
天魔郷に近づくにつれ、俺達は緊張感が高まり、よりいっそう気合が入った。
★
天魔郷に着いた俺達は地に足を付け、翼を引っ込める。
人間界では外は真っ暗であった為、こちらの世界も同じく真っ暗であった。
人間界と時差は変わらないこの世界では、人間界と同じく今は就寝の時間だ。
その為、外は度々発生するそよ風とそれに踊らされる草の音しか聞こえない。
人間界と違い、外灯がないこの世界は月の光を頼りに道を進まなければならない。
といっても、月の光がなくても特段困る事はなく、あったほうがハッキリと道や建物が見えるからイイヨネ! ぐらいの感じだ。
それに長く住んでいるこの世界は俺達の庭みたいなものなので、道に迷う事はない。
俺達は数多の樹木やレンガの建物を潜り抜けスイスイと進んで行く。
そうして進んで行く中で、俺達は良からぬ気を感じてしまった。
「……セラフィー」
「ええ。この気……。ちょっとやばい気がします」
「急ぐぞ」
「はい」
俺達は僅かに冷や汗をかきながら、先へと進んで行く。
唾を飲み込むゴクリという音が、そよ風に紛れ込むように新たに聞こえた。
★
程なくして、天使城と悪魔城の丁度境目に到着した俺達は、気の感じる方向にそれぞれ体を向ける。
「え?」
「ん? そっちですか?」
「俺は悪魔城から感じるけど……」
「私は天使城ですね……」
二人は気を感じる方向に指をさしながら顔だけを向かい合わせ、見当違いにキョトンとしてしまう。
「……まさか」
セラフィーは何か思いついたようにハッとなり、強張った表情で言う。
「『結界』ですね」
「なるほど。それだ」
『結界』とはその名の通り、一定の範囲内に神々のオーラを具現化して幕を張り、外からの攻撃や侵入を防ぐ事が出来る防御技である。
耐久力はオーラの量に比例し、結界に巡らせるオーラが多ければ多いほどその
防御力は真価を施す。
しかし、神々のスタミナの源であるオーラを常に放出維持するのは至難で、長く保つ事は王レベルの実力者が複数いても不可能な程。
そして何よりこの結界の優れている点は防御力の他にもう一つ。
––––––相手に『気』を感知させる事を不可能にする事。
結界には元々二種類が存在しており、天使が張る『陽結界』、悪魔が張る『陰結界』がある。
どちらの結界も性能には変わりはないが、己の種族が張った結界の中であれば膨大なオーラを放出しようとも、同種族でなければ相手には感知されなくなるという違いがある。
これは結界の外にいる者にも適用される。
今回でいえば、ルシフェルは陰結界、セラフィーは陽結界を感知出来ていた。
それは同種族が張った結界であるからだ。
つまり、この結界の恐ろしい所は膨大なオーラを必要とする大技を『不意打ちで』放つ事が可能になるという事。
例えば、『禁忌魔法』など……。
スローンの話を照らし合わせると結界を張る動機にも合点が付く。
俺とセラフィーは片方だけを阻止するだけでは意味が無い事を理解し、要点だけを伝えて各々で行いを阻止する作戦に。
「じゃ、気をつけてな」
「ルシフェルこそ、無茶はなさらないで下さいね」
「ああ、セラフィーもな。こっちが片付いたら直ぐに応援に行くから」
「ふふっ、それは頼もしいです。––––––では、また会いましょう」
「おう!」
短いやり取りを終え、俺は悪魔城、セラフィーは天使城へと向かい、禁忌魔法の発動を阻止する為に、全力で走って向かって行く。
間に落ちていた一枚の落ち葉がひらりと宙に舞い、ヒラヒラと捩りながらゆっくりと落ちていった。
★
––––––悪魔城の屋上。
月夜に照らされながら瞳を閉じ、両手を頭上に上げ佇んでいる一人がいた。
「もう直ぐ……もう直ぐで……この争いも終わる」
––––––第二使徒ベルゼだ。
両手の上で禍々しい紫色の高エネルギーを元気玉のように溜めている。
通称––––––『魔玉』
その高エネルギーさゆえ、地は揺れ、風は舞い、見た者を萎縮させる。
絶望の始まりであり、世界の終わりをこれから告げるかのように。
それだけの高魔力を維持しておきながらも、天界の者に気づかれないのは結界の効力によるもの。
そして、それだけの魔力を維持し続けられるのは、それに協力するかのように魔界の者一人一人が少量ながらもベルゼに分け与え続けているからだ。
例え雀の涙程でしかなくても、全員が合わさればその量は膨大な量となる。
一人の力では決して成立する事が出来ない禁忌魔法。それが最大の威力を誇る六式であれば尚更の事だ。
そんな魔力を与え続けている魔界の一人が膝を屈し、疲労を浮かべる。
「……くっ、申し訳ございません。ベルゼ様。……私は、そろそろ限界かもしれません」
「ええ。無茶はしなくて結構よ。ありがとう。そこで少し休んでなさい」
魔力とは生命力そのもの。それが尽きてしまえば死に繋がる。
魔力の量は各々で異なり、その量は力にも比例する。
その気持ちを十分に理解しているベルゼは責める事なく、優しく休むよう告げた。
それからドミノ倒しのように、次々と魔力を分け与え続けていた者達も脱落していく。
長い時間やっていた為、魔力が尽き始めてきているのだろう。
今はベルゼ一人がやや疲労感を浮かべならも魔力を与え続けている。
脱落した者は尊敬の目でベルゼの後ろ姿を見つめている。
やはり、代王だけあってその光景に見惚れてしまっているだろう。
普段はであるルシフェルが執り行う事だが、こうしてルシフェルの代わりを務めているのだから見惚れてしまうのも無理は無い。
他ではそうはいかないだろう。
使徒は、たった一つ離れているだけで力量の差は火を見るより明らか。
「……こんなところね」
ベルゼにも魔力が尽き始めたのか、魔玉に魔力を与える手を止めてしまう。
改めて魔玉を見返してみると、その禍々しさに自分でも恐怖を感じてしまった。
ふわふわと中に浮かんでいる魔玉は禍々しさは更に顕著になり、天界だけではなく、魔界もろとも消し飛んでしまうのではないかと、そう思わせるからだ。
これまで禁忌魔法の使用を試みた事は愚か、拝見した事もないベルゼは扱いによる不安も感じてしまっている。
天界を滅ぼす意志が強く働き、その情の勢いに任せて禁忌魔法を試みたものの、いざ使用するとなるとミスが許されない一発勝負の本番みたいで心のざわつきは鳴りを潜めなくなる。
実際、手は微かに震えていた。
きっと疲労によるものだろう。そうやって現実から目を逸らして、自分を偽って落ち着かせる。
そして瞳を閉じ、冷静さを取り戻そうと精神を落ち着かせようとすると、ある人物が浮かび上がる。
「……リヴァイアは、何処に行ったのかしら」
その呟きは風と共に月夜に消えていく。
ベルゼはこれまで、急に姿を消したリヴァイアを心配して魔界の者達に事情を話したものの、これといった情報は得られないでいた。
リヴァイアに何があったのか皆目見当もつかない。
魔界の周辺を探したが姿は見つからない。
であれば、人間界に足を運んだと考えるのが妥当だった。
その意図は……何処か引っかかる部分もあった。
でも、知らないふり。
だから、止むを得ずリヴァイア抜きで取り行った。
悔やみがあるとすれば、リヴァイアがいれば魔玉も更に強力な物に出来たという事。
第三使徒程の魔力があれば魔玉の威力を底上げする事が出来、より作戦の成功率がグッと高める事が出来た。
でも、それでも、天界を滅ぼすには十分な魔力が集まった。
後は結界を外し、魔玉を放つだけ。
「……さぁ、始めましょうか」
「何をだ?」
「!?」
ベルゼの背後に突如現れた黒い少年。
腕を組み、鋭く細められた眼光に向けられた者は自然と後ろめいてしまい、ひれ伏してしまいそうだ。
先程までベルゼを見惚れていた者達も今はその対象が変わり、片膝を屈して頭を下げている。
そんな予想を裏切るように現れた、現れてしまった事態に思わずベルゼはたじろぎ、重い口が開かずにいる。
そして覚悟の覚悟に重ねた強い意を決っすると、ようやくその重い口は僅かに開き始める。
「ル……ルシフェル様……っ。お帰りになられたのですね……」
無理して笑顔を取り繕うとするも、それはただ顔を引きっているだけの苦笑いでしかなかった。いや、それが精一杯だった。
王の静かに怒りが満ちている瞳に気圧されてしまっているからだ。
その為、普段自然と行っている頭を下げる崇拝の意を示すのを忘れてしまっている。
「ああ。たった今な。––––––で? これはどういう事だ? ベルゼ」
ルシフェルはふわふわと浮かんでいる魔玉にチラッと視線を向けて問う。
ベルゼは額に冷や汗を浮かべており、その勢いが止まる事はない。
「こ、これはっ……」
「……」
黙って何も口を聞かないルシフェルに対して窮屈に感じてしまい、観念したかのように正直に話し出す。
「……禁忌魔法を使い、天界を滅ぼそうとした所存です」
正直に告げた言葉は今にも消えてしまいそうに掠れていた。
「……ふむ」
「ルシフェル様がご不在の間、一時的に王の権力が譲渡された私は––––––」
「もういい」
「!」
ベルゼの弁解の余地を途中で遮るルシフェルの口調は苛立ちを含んでいた。
「ベルゼ、お前のやろうとしている事は十分理解している。俺達の宿敵である天界の者達を滅ぼし、この天魔郷を魔界だけの世界にしようとしたのだろう?」
「お、仰る通りでございます! ルシフェル様!」
ここでようやく、ベルゼは片膝を地につき、頭を下げ始める。
「俺が不在であれば王の権限は第二使徒であるお前に譲渡される。故に、何をしようとも許されるに等しい。だからお前は何も間違ってなどいない」
「い、痛み入ります!」
「だが、俺を抜きに禁忌魔法を使用するなど驚いたぞ。ベルゼ」
「……も、申し訳ございません」
「謝るな、さっきも言ったはずだぞ。お前は何も間違ってなどいないってな……」
「…………」
俺は魔玉を見つめながら、ベルゼに問う。
「……それ程、天界の奴らが憎いか?」
質問の返答を試されているかのように感じたベルゼは一度はハッとするが、直ぐに冷静さを取り戻す。
「……はい。これまで失った仲間達の死を……私は、果たしてやりたいのですっ」
ベルゼの顔は、今にでも泣いてしまいそうな程弱々しくなっいた。
「失ったものは帰って来ない……。なのにっ! 奪ったあいつらがのこのこと正義ぶって生きているのが許せないです!」
急に感情的になったベルゼに驚きを感じてしまう。
それは俺だけではなく、他の悪魔達も一緒だった。
普段は冷静で取り乱す事はなく平然とやり過ごすベルゼだが、この瞬間だけは別人のように感じた。
「でもっ、分かっているんです。それはあいつらも同じ想いでいるのではないかと……」
仲間の命を失ったのは天界も同じ。だからベルゼの思っている事は天界の者達も思っているという事。
あれだけ敵意を向けておきながらも、しっかりと相手の気持ちを汲み取っているのが分かる。
「だから私は、この争いに終止符を打とうと決めたのです! もう誰も悲しまない、魔界だけの世界にしようと」
天使と悪魔が同じ世界にいるから争いは止まないでいる。なら、どちらかが滅んでしまえば自ずと争いは無くなるだろうという極シンプルな考え。
一人残らず滅ぼす。すれば、仲間の死を悲しまずにして、一生の眠りにつく事が出来る。それは孤独に生きるよりも、いっそ殺してやった方が相手の為なのかもしれない。
「……そうか」
俺はベルゼの本心を聞いて、瞳を閉じて思う。
ベルゼの言っている事は正しい選択の一つであると理解してしまったのだ。
天使と悪魔がこれから先も変わらぬ関係で変わらぬ日々を過ごしていこうというならば、それはある意味精神的拷問に近い感覚だ。
争いは鳴り止まず、ただ命の危険性が伴うだけの関係。
さして広くない天魔郷。そんな小さな箱の中で元々水と油の関係である天使と悪魔が一緒に住んでいる事自体おかしな話なのかもしれない。
これが悪魔だけの世界だったら……。と、想像してしまうだけでも幸せな世界しか想像つかない。
スッキリとした、晴々とした、イキイキとした表情で、雰囲気で、幸せそうに暮らしている奴らの事が容易に浮かんでしまう。
殺そうとするのは簡単。
逆に、俺が思い描いていた世界は複雑。
その方が楽で、実現性が高くて、確実性がある。
もしかしたら、ベルゼの方が王に相応わしいのかもしれない。
俺はもしかしたら、もしかしたらと自分に言い訳をし、天界を滅ぼそうとするのをはぐらかしてきた。
その結果、仲間を失う事態が起こってしまった。
でも、ベルゼは違う。
これから先、仲間の死を見ない為に、失わせないように、自ら率先して禁忌魔法まで用いてその世界を実現させようとした。
行動力が違う。信念の強さが違う。仲間への思いが……違う。
自分の行動が浅はかで、愚かであったと実感する。
セラフィーと二人だけで過ごしたいという欲に溺れ、天魔郷の問題を後回しにし、人間界でのこのこと平和に暮らしていた。
実に、滑稽だ。
王、失格だ。
ベルゼの方が余程、王に相応わしいじゃねぇか……。
……俺は今まで、何をしていたんだっ……。
ズザッと、地に両膝をつく音が屋上に響いた。
その音の出だしに視線を向けたみんなは、驚愕しながら絶句している。
両膝を地についたと思えば、今度は力尽きたかのように体を前に倒してしまう。
そこから動きを見せる事ないその姿は、王の姿として有り得ない光景だった。
––––––土下座だ。
全員が目を疑った。
誇り高き悪魔の王が、こんなにも惨めで、情けなくて、弱い姿を晒しているのだから。
今までに一度も見た事がない光景に、全員は硬直し、空気までにも伝染してしまう。
今聞こえるのは葉っぱが散っていく音のみ。
やがて居心地が悪い空間を引き裂くように、ベルゼがようやく重たそうな口を開いた。
「ル、ルシフェル様……?」
土下座している俺を、全員が見下ろす構図になっている。
その中でも一際近い位置にいたベルゼが代表みたく声を発した。
それに対し、俺は土下座のまま言葉を発した。
「……俺の不甲斐なさで、お前達を不安にさせて、本当に申し訳ない……」
途中で言葉が詰まりかける。
「お前達を……天魔郷をこうさせてしまっているのは、全部俺の責任だ」
「な、何をおっしゃいますか! ルシフェル様!」
「いいや、本当の事だ。俺は王でありながら、今までお前達に何もしてやれなかった」
「そんな事ございません! 堕天使の襲撃の時、ルシフェル様は私達を命懸けでお守りくださいました!」
「……でも、それだけだ」
「それだけじゃありません! 私達は知っています! ルシフェル様が私達の為に、常に気にかけてお守りしている事も!」
ベルゼ言葉に魔界の者達も微笑みながら無言で頷く。
俺は頭を下げっぱなしで、その顔を、表情を伺う事は出来ない。
それでも、みんなの代表で告げているその言葉には、嘘偽りなく答えている気がした。
その証拠に、俺の眼には一滴の滴が浮かび上がっている。
それを見せまいと、目を数回パチパチさせて滴を瞳に浸す。
そしてようやく、俺は重たそうに体を立ち上がらせる。
最初に映ったのは、微笑みの顔を浮かべている魔界の者達。
––––––あぁ、俺はなんて幸せ者なんだ。
こんな俺に、まだ付いて来てくれるのか。
なんて返したらいいのか、分からんな。
いや、返す必要はないのかもしれないな。
言葉にしなくとも、こいつらは理解している。
全く、厄介な奴らだ。
今まで隠して来たつもりが全部お見通しという事わけかよ。
かっこいい姿だけを見せてやりたいと思っていたが、かっこ悪い姿まで見られていたのかもしれない。
全く、惨めだ。
それでも、こいつらは。
俺は全員の顔を見渡した後、決して揺らぐ事のない強い意志を持って王として告げる。
「……お前達に、一生のお願いがある!」
★
ルシフェルと分かれた私はこれまでにないスピードで天使城に向かっている。
私の役目は部屋に閉じ込められているリヴァイアを救出し、禁忌魔法を阻止する事。
「急がないと……っ」
天使城の入り口に着いた私は扉を開き、中に入る。
普段は一階リビングで誰かしら迎え入れてくれるものの、今回はそれがない事による違和感を感じてしまう。
「やはり、屋上ですね」
なんとなくは理解していた。
それでも私が一階に来た理由は、リヴァイアの救出を先に選んだ為だ。
友人が、仲間が部屋に閉じ込められている情報を聞いて、それを後回しにする事は出来なかった。
私は急いで一階奥にある部屋に向かう。
辿り着くと、ふご丁寧にしっかりと施錠されている。
ガチャガチャと雑に弄ってみても、開く気配は無い。
だがそれを開ける鍵を持っておらず、取りに行くのにも時間が惜しかった。
「……仕方がありませんね」
なので、強引にこじ開ける事に。
「ホーリーレーザー(聖なる光線)」
指先から僅かに放たれる光線が鍵をぶっ壊す。
床に落ちた鍵がカランと音を高く響きさせると同時に、僅かにドアがギィと開き始める。
まるで誘導されているかのようだ。
慌てた様子で中に入ると、中には意識がなさそうに倒れているリヴァイアがいた。
それを見て、不安な気持ちにさせられる。
「リヴァイアさん!」
リヴァイアの元まで走り寄り、肩を揺らす。
いくら声をかけても肩を揺らしても反応は無い。
まさかと思ったセラフィーは、リヴァイアの額に覆い被さっている前髪を手で覆い上げる。
その額の中心には文字とは言えない術式が描かれている。
「……これは、催眠の術式」
セラフィーにも心当たりがあるのか、直ぐに術式を理解すると、その術式に手を当て解き始める。
「解!」
すると、リヴァイアの額に描かれていた術式がスゥーっと消失する。
完全に無くなると、リヴァイアは目を薄らと開き始め、徐々に意識が回復していくように目覚め始める。
最初に視界に映った私を見て、リヴァイアは目をパチクリと大きくして驚く。
「セ、セラフィー……?」
「良かった。お怪我はありませんか?」
「えぇっと……。リィは、なんでこんな所に…………!」
記憶を思い返すとリヴァイアは思い出し、焦りと怒りを含んでいるかのような口調でセラフィーに告げる。
「そうだ、あいつらだ! スローンがリィを騙して、それで––––––」
「いいえ。スローンはそんな事していません。ただ、タイミングが悪かっただけですよ」
リィヴァイアは怪訝そうな顔でセラフィーを見つめる。
「……どういう、事?」
「説明は後です。今は、禁忌魔法を阻止しなければなりませんので」
「はっ、そうだ。スローンもそんな事言ってた……」
「なるほど。やはり、スローンも私達と同じですね」
「同じ?」
「いずれ分かりますよ。では、私はこれで––––––」
言葉だけを残し、その場を立ち去ろうとするセラフィーの手が掴まれる。
不意に掴まれた事に反射的に驚いてしまい、振り返る。
そこには口元を強く結びながら強く決意した瞳が向けられていた。
「リィも、行く」
初めは頼りになる発言に思わず頼みそうになってしまったが、その言葉を無理やり飲み込んで抑える。
そして首を振り、セラフィーは告げる。
「ありがとうございます、リヴァイア。でも、これは私の責務です。リヴァイアさんを巻き込む訳にはいきません」
ごもっともな言葉を並べてみたものの、リヴァイアは納得がいっていない様子。
「ううん、違うよ。こんな事になっているのは……リィ達にも、原因はあるから」
その暗く後悔しているような表情に、セラフィーは言葉を詰まらせてしまう。
「だから、セラフィーだけに重荷を背負わせたくないの!」
「!」
気付いたら、リヴァイアの目には涙が潤っていた。
今まで自分が振る舞って来ていた行動に自責と後悔の念が湧き上がり、心を痛めているに違いない。
そんな勇気を持って心の内を明かしてくれた事に対して断るのも罪悪感のようにも感じてしまうに違いない。
本気の言葉には本気の返事を。
セラフィーは一度微笑み、リヴァイアに協力の願いを告げた。
「ふふっ、ではお言葉に甘えても宜しいですか?」
「うん!」
セラフィーは現在の状況を詳しく説明する。
「今、天界と魔界でそれぞれ禁忌魔法を用いて、相手を滅ぼそうとしています。しかも厄介な事に結界を張り巡らせて察知できないようにまで施されています。おそらく、不意打ちで放つつもりなのでしょう」
「結界……。だから気が感じられないんだね」
セラフィーはコクリと頷く。
「魔界側はルシフェル、天界側は私で阻止する作戦を二人で決め、今に至っています」
リヴァイアは無言でうんうんと頷き納得している様子。
というのも、話の素性はベルゼやスローンから聞いているからだ。
リヴァイアはスローンの言っている事は本当だったんだと改め、自分を騙していた悪人だと決め付けていた事に罪悪感を感じてしまっていた。
「リヴァイアさんは、ルシフェルの援護に向かってもらっても宜しいですか?」
「え、こっちはいいの?」
「ええ。天界側の問題は展開側で済ませるべきでしょう。それに、魔界側のリヴァイアさんが姿を現してしまえば手を出してくる者もいるかもしれません。まだ、些細な認識は払拭されていませんでしょうから」
「……分かった」
それに対し、セラフィーはニコッと微笑む。
そして踵を返し、部屋を出ようとする。
ドアを出てリビングに出ると、二階に進む通路と城の出口に進む通路で分かれる際、二人は背中合わせで答える。
「お願いします、リヴァイアさん」
「大丈夫! ルシフェル様がいるもん!」
ウィンクをかまし、親指を立てグッジョブのポーズを示す。
それを見て、思わず微笑んでしまう。
「ええ。そうですね」
二人は互いに微笑み合うと、直ぐに行くべき道に向かって進んでいく。
今、リビングには誰一人といない。
そんな音ひとつ無い静まり返った空間に、ドアの閉まる音だけが響き渡った。
★
リヴァイアと別れ、室内の階段を凄まじい勢いで駆け上がっていくセラフィー。
本来なら城の外に出て翔んで行った方が速いのではないかと思うが、気が動転していた為、冷静な判断が下せなくなっていたのかもしれない。
それでも私は屋上へと続く階段を登る足を緩める事なく駆け上がる。
今更引き返して翔んでいくのも気が進まないし、何より余計に時間が掛かってしまう。
それに、硬直気味である体をほぐすには丁度良い。
僅かに息が乱れてくると頭の中がクリアになっていく感じがするし、硬直気味な体が解れてきた。
体のコンディションが整いつつあるその絶好のタイミングで屋上への扉を開いた。
最初に目に映ったのは、大勢の天界の者達。
目を瞑り、祈るようにして何やら聖なる力、いわゆる聖力をある物体へと注いでいる。
その物体とは、禁忌魔法六式である『聖玉』だ。
ある者の両手の上で禍々しい黄金色の高エネルギーを元気玉のように溜めている。
その高エネルギーさゆえ、地は揺れ、風は舞い、見た者を萎縮させる。
魔玉と何ら変わらない。
唯一相違点があるとすれば色の違いだけ。
そんな大勢の天界の者達より先頭に立って聖玉を支えている人物……天界における第二使徒、ケルビムだ。
「ケルビム、これは一体どういう事ですか?」
背後から細い声が屋上に響く。その声は直ぐに風と共にかき消されそうな程であったが、やや怒りを含んであるかのようなトーンに自然と耳に入ってきてしまう。
その証拠として、聖玉に注いでいた天界の者達全員が一斉にセラフィーに振り返る。
振り返った者達は、口をわなわなと震えながら怯えている。
だが、先頭に立っているケルビムは振り返らず、そのまま声を発する。
「……セラフィー様なら、ご理解頂けると思うのですが」
その通りだ。ケルビムが何故、禁忌魔法を行っているのかは既に理解していた。
––––––魔界の者達を全滅させる為。
頭の中では理解していたのにも関わらず、それでも口走って聞いてしまったのは、やはり気が動転していて、動揺してしまっているからだろう。
「……ケルビム、どうして……っ」
もう一つ理由を挙げるとすれば、ケルビムがこのような行いをしている事にある。
ケルビムは真面目で上の命令であれば卒なくこなし、下の者から助けを求められれば迷う事なく救う。
自分勝手な行動も、判断も、決断もする事はない。
必ず、今まで王であるセラフィーに相談してくれていた。
そんなイメージを持っていたセラフィーは、今回のような行いを受け入れ難かったのだろう。
まるで裏切られたような感覚。それが、セラフィー良心を傷つけた。
ケルビムが振り返らないのは、そんなセラフィーを目にしたくないという思いもあるのかもしれない。
セラフィーに長く慕って来たからこそ、お互いがお互いの事を理解してしまっているのだろう。
「私は、もう終わらせたいのです。この醜き争いを」
今、ケルビムがどのような顔をしているのか伺う事は出来ない。
それでも、言葉のトーンやニュアンスは少なくとも悲しそうであった。
「失った仲間達は、もう戻らない。これから先、いつまた争いが起こるかも分からない。そんな日々を過ごしていくのは、もう嫌なのです!」
最後の方、怒りの感情が含まれているのを感じた。
そしてようやく、ケルビムは振りかえる。
「勝手な行動を起こしてしまった事は、深くお詫び致します。––––––でも! どうか、私達の気持ちを、ご理解下さいっ……」
ケルビムが深々と頭を下げると、それに合わせて他の天界の者達も同じように頭を下げ始める。
全員が、セラフィーに向かって頭を下げ始める光景に思わずたじろいでしまう。
普段は挨拶がてらに頭を下げられる光景は何度も目にしているものの、今回のはそれとまるっきり違う。
それは、覚悟の強さを見せしめているかのようだった。
私は、言葉が出てこない。
天使と悪魔が仲良い世界を作ろうと思っていた夢を、否定されている感覚だったから。いや、初めから全員思ってすらいないのかもしれない。
所詮は理想論だと。現実を見ろと。
口には出さなくとも想いは伝わるのだと、初めて今分かってしまった。
もう、頭の中がごちゃごちゃだ。
私達の夢が灰のように崩れ去ろうとしている事、禁忌魔法を用いてでも相手を滅ぼそうとする事、今私は、どうするのが正解なのかという事。
頭の中に溜まっていくだけで、決して減る事がない。
頭痛のように頭が重く、痛くなってくるような感覚だ。
王として情けない。
こんな非常事態にも関わらず、ただ唇を噛みしめ、手をプルプルと震えさせて込み上がってくる自責の念を押さえ付けることしか出来ないのだから。
……私はただ、目を背けていただけなのかもしれない。
みんなの声を、こうなる事を……。
そう言った意味では、私は王失格だ。
むしろケルビムの方が王として相応しいのかもしれませんね。
その証拠に、こうして一致団結している。
中には嫌々やっている者もいるかもしれませんが、みんなの真剣な顔つきからしてそれはありませんね。
––––––………………。
私はゆっくりと、ケルビムまで歩き出す。
重りが付けられているかのように重い足を、確実に一歩ずつ踏み出していく。
天界の者達は端に避けて道を空けてくれる。
何も口にしなくても、その行き先はケルビムである事は皆察したのだろう。
ケルビムは代王であり、禁忌魔法をとり行った。
それなら、王同士で事の行き先を話し合うのは当然。
だが、歩み寄ってくるセラフィーの目は、覚悟を決したような鋭い目つきをしている。
普段は温厚で笑顔を絶やさないセラフィーだが、今のセラフィーには何処か悪魔のような戦闘狂にも感じる。
それを感じたケルビムは、思わず武器を転送しそうになる。
だが、その異様な圧に押され、転送する手が怯えて動かない。
武器をセラフィーに向ける事は本来ならあってはならない事。
いくら代王とはいえ、その権限は王であるセラフィーが戻って来た時点で剥奪されるのも当然だからだ。
今は通常通り、王と第二使徒の関係。
だが現状、ケルビムはそんな常識的観点は頭にはなく、武器を転送し始めた瞬間腕の一本は持ってかれるイメージを感じてしまい、それに怯えてしまっているのだ。
やがて、ケルビムに人一人分まで近づき足を止めたセラフィーは、細くてしなやかな指をケルビムの頬に向かって伸ばし始める。
「!」
殺されると思った矢先、その指はケルビムの頬を優しく撫で始めた。
「えっ?」
自分の想定していた現実と異なり、情けない声を出してしまった。
それに気付いていないかのように、セラフィーは告げる。
その時の顔は、いつもの温厚で優しい笑顔をしていた。
「私が不在の間、皆さんをお守り頂き、ありがとうございます」
「……そ、そんなっ、滅相もございません!」
深々と頭を下げ始めるセラフィーを見て、それを返すようにケルビムも慌てて深々と頭を下げ始める。
暫くして頭をあげたセラフィーは、聖玉をジッと見つめる。
「それにしても、良くここまでエネルギーを溜め込みましたね」
そう聞かれ、頭をあげたケルビムは聖玉を一緒に見つめて答える。
「は、はい! 皆で力を合わせて、ここまで溜め込む事が出来ました」
「ふふっ。皆で、ですか」
思わず、微笑んでしまった。
力を合わせて作られた聖玉。その強いエネルギーには、みんなの想いが募っている気がした。
「では、ケルビム」
「はい!」
キリッとした顔つきで名前を呼ばれ、ケルビムもキリッとした顔つきで振り返る。
セラフィーがスッと視線を背けた先には悪魔城が。
それに釣られ、ケルビムも悪魔城に目を向ける。
「代王を務めたからには、しっかりと最後まで責任を取ってもらいますよ?」
「あ、はい!」
初めからそのつもりで代王の座に君臨していたケルビムは迷う事なくハッキリとした返事をする。
その真っ直ぐな返事に、嬉しく感じてしまう。
(ごめんなさい……。ルシフェル……)
心の中で祈りに似た言葉を呟くと、セラフィーは悪魔城に向かって手を伸ばす。
「…………。……ケルビム、放つ準備をお願いします」
「はっ!」
ケルビムによって作られた聖玉。それを放つのも、コントロールするのもケルビムにおいて他にいない。
聖玉は、禁忌魔法を発動した者に委ねられる。
ケルビムは頭上で浮かばせている聖玉の前に、六式魔法陣を発動する。
そして、発射口である六式魔法陣の中央部分を悪魔城に合わせる。
片目を閉じながら少しずつ微調整し、完了するとセラフィーに体を向ける。
「発射準備、整いました。後は、放つだけです」
「……ご苦労様、ケルビム。……では、私の合図と共に、放って下さい」
「承知致しました」
「……………………………………………………お願いしますっ」
セラフィーが発射の合図を出すと、ケルビムは聖玉を放った。
膨大なエネルギーが六式魔法陣の中心部分から轟音を鳴り響かせながら悪魔城に一直線に向かって行く。
神々しいエネルギーが通ろうとする周辺は地を削り、木や建物を吹き飛ばし、風までも切り裂いて行く。
時刻は夜中だというのに、そこだけ陽が差しているかのようだった。
天界の者達は遂にこの時が来たのだと期待を胸に多く膨らませながら喜ばしい表情をしている。
その高鳴る気持ちを共感しようと、ケルビムは隣にいるはずのセラフィーに声を掛けようとした。
––––––だが既にセラフィーの姿はそこに無く、あるのは誰も気付く筈のない地に染み付いた、一滴の水跡だけだった。
0
あなたにおすすめの小説

義兄に恋してたら、男になっちゃった!? こじ恋はじめます
桜 こころ🌸
恋愛
恋と変身が同時進行!? 波乱すぎる兄妹(仮)ラブストーリー♡
お兄ちゃんが好き。でも私、ドキドキすると“男”になっちゃう体質なんです――!
義兄・咲夜に片想い中の唯。
血はつながっていないけど、「兄妹」という関係が壁になって、想いを伝えられずにいた。
そんなある日、謎の薬を飲まされ、唯の体に異変が――なんと“男”に変身する体質になってしまった!?
ドキドキするとスイッチが入り、戻るタイミングはバラバラ。
恋心と秘密を抱えた、波乱の日々が始まる!
しかも、兄の親友や親友の恋心まで巻き込んで、恋はどんどん混線中!?
果たして唯は元に戻れるのか?
そして、義兄との禁断の恋の行方は……?
笑ってキュンして悩ましい、変身ラブコメディ開幕!


出ていってください!~結婚相手に裏切られた令嬢はなぜか騎士様に溺愛される~
白井
恋愛
イヴェット・オーダム男爵令嬢の幸せな結婚生活が始まる……はずだった。
父の死後、急に態度が変わった結婚相手にイヴェットは振り回されていた。
財産を食いつぶす義母、継いだ仕事を放棄して不貞を続ける夫。
それでも家族の形を維持しようと努力するイヴェットは、ついに殺されかける。
「もう我慢の限界。あなたたちにはこの家から出ていってもらいます」
覚悟を決めたら、なぜか騎士団長様が執着してきたけれど困ります!

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました
桜あずみ
恋愛
異世界に転移して2年。
言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。
しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。
──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。
その一行が、彼の目に留まった。
「この文字を書いたのは、あなたですか?」
美しく、完璧で、どこか現実離れした男。
日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。
最初はただの好奇心だと思っていた。
けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。
彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。

天然だと思ったギルド仲間が、実は策士で独占欲強めでした
星乃和花
恋愛
⭐︎完結済ー本編8話+後日談7話⭐︎
ギルドで働くおっとり回復役リィナは、
自分と似た雰囲気の“天然仲間”カイと出会い、ほっとする。
……が、彼は実は 天然を演じる策士だった!?
「転ばないで」
「可愛いって言うのは僕の役目」
「固定回復役だから。僕の」
優しいのに過保護。
仲間のはずなのに距離が近い。
しかも噂はいつの間にか——「軍師(彼)が恋してる説」に。
鈍感で頑張り屋なリィナと、
策を捨てるほど恋に負けていくカイの、
コメディ強めの甘々ギルド恋愛、開幕!
「遅いままでいい――置いていかないから。」

「25歳OL、異世界で年上公爵の甘々保護対象に!? 〜女神ルミエール様の悪戯〜」
透子(とおるこ)
恋愛
25歳OL・佐神ミレイは、仕事も恋も完璧にこなす美人女子。しかし本当は、年上の男性に甘やかされたい願望を密かに抱いていた。
そんな彼女の前に現れたのは、気まぐれな女神ルミエール。理由も告げず、ミレイを異世界アルデリア王国の公爵家へ転移させる。そこには恐ろしく気難しいと評判の45歳独身公爵・アレクセイが待っていた。
最初は恐怖を覚えるミレイだったが、公爵の手厚い保護に触れ、次第に心を許す。やがて彼女は甘く溺愛される日々に――。
仕事も恋も頑張るOLが、異世界で年上公爵にゴロニャン♡ 甘くて胸キュンなラブストーリー、開幕!
---

転生したので推し活をしていたら、推しに溺愛されました。
ラム猫
恋愛
異世界に転生した|天音《あまね》ことアメリーは、ある日、この世界が前世で熱狂的に遊んでいた乙女ゲームの世界であることに気が付く。
『煌めく騎士と甘い夜』の攻略対象の一人、騎士団長シオン・アルカス。アメリーは、彼の大ファンだった。彼女は喜びで飛び上がり、推し活と称してこっそりと彼に贈り物をするようになる。
しかしその行為は推しの目につき、彼に興味と執着を抱かれるようになったのだった。正体がばれてからは、あろうことか美しい彼の側でお世話係のような役割を担うことになる。
彼女は推しのためならばと奮闘するが、なぜか彼は彼女に甘い言葉を囁いてくるようになり……。
※この作品は、『小説家になろう』様『カクヨム』様にも投稿しています。
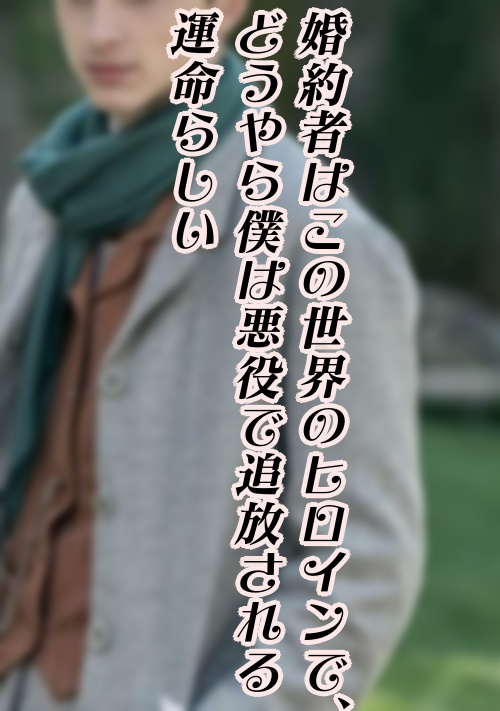
婚約者はこの世界のヒロインで、どうやら僕は悪役で追放される運命らしい
結城芙由奈@コミカライズ連載中
恋愛
僕の前世は日本人で25歳の営業マン。社畜のように働き、過労死。目が覚めれば妹が大好きだった少女漫画のヒロインを苦しめる悪役令息アドルフ・ヴァレンシュタインとして転生していた。しかも彼はヒロインの婚約者で、最終的にメインヒーローによって国を追放されてしまう運命。そこで僕は運命を回避する為に近い将来彼女に婚約解消を告げ、ヒロインとヒーローの仲を取り持つことに決めた――。
※他サイトでも投稿中
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















