61 / 62
6話 ようこそ、Goワールドへ!
61話 皆さんと一緒に
しおりを挟む
「俺って結構、貧弱体質だったんですね……」
朝食の席でまず話題に上ったのは、脱稃作業における俺の失態だった。
すっかり火の弱まった《焚き火》を囲み、各々|《平焼きパン》を頬張る。見馴れた食事の風景。その中で、いち早く食事を終えたサミュエル――俺の作業を見守り、最後には肩代わりしてくれた少年が短く息を吐く。
「アンタ向きじゃないのかもね」
「やっと手伝えると思ったのに」
俺は今なお、この村における殻潰しである。
生産性のある仕事はほぼ不可能に近く、出来ることと言えば設計図の描出や運搬くらいだ。後者においては村人も可能である為、俺が存在する意義は、実質設計図のみである。
一一七番植民地が『村長』を欲した理由と同じように。
「随分嬉しそうじゃない、クローイ」
「え?」
ルシンダに指摘され、彼女は目を丸くする。緩んだ口元、垂れる眉。その顔は、どこからどう見ても俺に共感しているとは思えなかった。
クローイの手に、ジャムの付着した唇が隠れる。しばらくの間、視線を辺りに彷徨わせていたが、
「……村長さん、仕事できないのが嬉しくて」
観念したように呟いた。
「その発言はちょっと傷つきます」
「ええっ! そ、そんなつもりじゃ――」
クローイは明らかに狼狽していた。
「そ、村長さんにとっては納得のいかない結果かもしれないですけど……でも、私は嬉しいんです。だって私達、御役御免にならないんですよ。まだここで、村長さんと一緒に開拓を続けられる」
御役御免。それは、一度たりとも考えたことのない話であった。
この地――何もない、どこまでも続く平野に入植してから早十六日。国から派遣される者、捕虜となり村へ加入した者、経緯は違えど俺の村には総勢五名、ナビ子も含めると六名の、心強い『村人』達を迎えた。
この先も、彼等と共に開拓の歴史を紡いでいく――それが当然と思っていた。そう思って止まなかった。今もその気持ちは変わらない。
「もしかして、『村長』が仕事できないのは……」
自分一人で完結させない。村人と協力して村を発展させる。その為に『村長』と『村人』、双方に欠点を作り、噛み合うよう構想した。
このゲームは、そういうゲームなのだ。『プレイヤー』が『村長』となり、『村人』を率いて自分だけの村を作る。それが何よりの基盤である。
「たとえ俺が作業できるようになったとしても、皆さんと一緒に開拓を続けるつもりでしたよ」
御役御免、そうされると危惧していたクローイもまた、大切な歯車の一つである。
クローイは、アランとほぼ同時期――最初期に入植してきた女性だ。希望通りの『木工師』に着任し、建築の現場で大いに活躍してくれた。彼女がいなければ小屋を作ることは勿論、道具類を揃えることも不可能であった。
村人との交流の面でも、彼女は緩衝材としてよく機能してくれた。
俺が入植間もない時期のルシンダに強く当たってしまった時や、カップランドへ拉致――俺的には訪問していた際にも、甲斐甲斐しく世話を焼いてくれた。
普段はオドオドと頼りない様子でありながら、いざとなれば確固たる意志をもって聳《そび》える。
彼女がいなければ、きっとこの村は、ここまで円滑に事を運ぶことが出来なかったであろう。少なくとも、『石工師』の女性と、こうして仲良く《焚き火》を囲むことも叶わなかった。
「……で、そこの二人は、何でそんなに嫌そうなんですかね」
御役御免を免れたところで安堵する人もいれば、そうでない人もいるのである。全くもって雰囲気ぶち壊しの、空気読めない希望役職『ニート』の面々は、不貞腐れたように揃って唇を曲げていた。
「いや、だって、なぁ? ここでの労働が終われば帰れる訳だし」
「開拓事業完遂の報酬金も貰えますし」
「つまり、国の金で飯が食える」
「最高ですわ!」
恍惚と、二人は語る。
働かずに飯を食う、その魅力は俺も理解しているつもりだ。だが、それとこれとは話が別である。
「絶対二人は帰しませんから」
「鬼畜!」
「そういう差別はよくないと思うぜ、村長」
非難を一身に受けつつ、俺はちらりとナビ子に視線を遣る。
三枚目の《平焼きパン》を今まさに平らげようとしている彼女は、俺の視線に気付くと、ニコリと太陽のような笑みを浮かべた。
「村人の送還権限は、村長さんに一任されています」
「チイッ、政府の犬め!」
ルシンダの声は、世の恨みを全て練り込んだかのようだった。
思い返せば、彼女は政争の末この地にやって来たのだったか。やはり彼女と「国」との間には、浅からぬ因縁があるのだろう。
俺は、彼女の言う「政府」――レオタロン公国の命の下、開拓事業を行っているという設定だから、ルシンダにしてみれば、俺もまた「政府の犬」だ。ナビ子同様、詰られて相応の立場である。
これはただの戯れ事だ。ルシンダも本気ではないだろうが、牙を剥かれるとどうしても戸惑う。
だが一方のナビ子はまるで臆することなく、ピンと人差し指を立てて、
「逆に言えば、村長さんに帰ってくれと思わせられるような言動を行えば、国へ戻れるのです。まだまだチャンスはありますよ!」
「あの、ナビ子さん。あまりそれを推奨しないでください」
「あはは~、冗談ですよ。当たり前じゃないですか」
「冗談じゃなかったら驚きですよ」
最も信頼すべき少女に扇動されては、何を信じてよいのか分からなくなる。疑心暗鬼の中で開発を行う程マゾヒストではない。
「この村の人は、何やかんやでいい人ばかりですからね。途中で投げ出すことなんて、きっとしないですよね」
この村の構成員は、文句を垂れつつも、与えられた仕事はしっかり熟してくれる人ばかりだ。俺が困っていれば手を差し伸べ、時に叱咤と激励を送る。
『村長』と『村人』という役職上の高低はあるものの、それは事実、形骸に留まっている。俺が村人に、村人が俺に、どちらから意見を申し立てても、俺は決して傲慢に語ることはしないつもりだし、村人達も媚びる真似はしない。
もともと俺は、先輩だとか後輩だとか、時間的前後を由来とした身分の差を重視しない人間だ。幾年か前に引退した部活動でも、敬語を使われるのがむず痒くて仕方なかったくらいだ。むしろ疑問すら覚える。
あくまで対等に。同じ開拓者として平等に。俺が心掛けてきたのは、そういう体制だ。
「そういや、この村この村って呼んでるけどよ」
ふと、気抜けしたようにアランが口を開く。
「村の名前、何て言うんだ?」
入植十六日目。これが議題に上がったのは初めてのことであった。
朝食の席でまず話題に上ったのは、脱稃作業における俺の失態だった。
すっかり火の弱まった《焚き火》を囲み、各々|《平焼きパン》を頬張る。見馴れた食事の風景。その中で、いち早く食事を終えたサミュエル――俺の作業を見守り、最後には肩代わりしてくれた少年が短く息を吐く。
「アンタ向きじゃないのかもね」
「やっと手伝えると思ったのに」
俺は今なお、この村における殻潰しである。
生産性のある仕事はほぼ不可能に近く、出来ることと言えば設計図の描出や運搬くらいだ。後者においては村人も可能である為、俺が存在する意義は、実質設計図のみである。
一一七番植民地が『村長』を欲した理由と同じように。
「随分嬉しそうじゃない、クローイ」
「え?」
ルシンダに指摘され、彼女は目を丸くする。緩んだ口元、垂れる眉。その顔は、どこからどう見ても俺に共感しているとは思えなかった。
クローイの手に、ジャムの付着した唇が隠れる。しばらくの間、視線を辺りに彷徨わせていたが、
「……村長さん、仕事できないのが嬉しくて」
観念したように呟いた。
「その発言はちょっと傷つきます」
「ええっ! そ、そんなつもりじゃ――」
クローイは明らかに狼狽していた。
「そ、村長さんにとっては納得のいかない結果かもしれないですけど……でも、私は嬉しいんです。だって私達、御役御免にならないんですよ。まだここで、村長さんと一緒に開拓を続けられる」
御役御免。それは、一度たりとも考えたことのない話であった。
この地――何もない、どこまでも続く平野に入植してから早十六日。国から派遣される者、捕虜となり村へ加入した者、経緯は違えど俺の村には総勢五名、ナビ子も含めると六名の、心強い『村人』達を迎えた。
この先も、彼等と共に開拓の歴史を紡いでいく――それが当然と思っていた。そう思って止まなかった。今もその気持ちは変わらない。
「もしかして、『村長』が仕事できないのは……」
自分一人で完結させない。村人と協力して村を発展させる。その為に『村長』と『村人』、双方に欠点を作り、噛み合うよう構想した。
このゲームは、そういうゲームなのだ。『プレイヤー』が『村長』となり、『村人』を率いて自分だけの村を作る。それが何よりの基盤である。
「たとえ俺が作業できるようになったとしても、皆さんと一緒に開拓を続けるつもりでしたよ」
御役御免、そうされると危惧していたクローイもまた、大切な歯車の一つである。
クローイは、アランとほぼ同時期――最初期に入植してきた女性だ。希望通りの『木工師』に着任し、建築の現場で大いに活躍してくれた。彼女がいなければ小屋を作ることは勿論、道具類を揃えることも不可能であった。
村人との交流の面でも、彼女は緩衝材としてよく機能してくれた。
俺が入植間もない時期のルシンダに強く当たってしまった時や、カップランドへ拉致――俺的には訪問していた際にも、甲斐甲斐しく世話を焼いてくれた。
普段はオドオドと頼りない様子でありながら、いざとなれば確固たる意志をもって聳《そび》える。
彼女がいなければ、きっとこの村は、ここまで円滑に事を運ぶことが出来なかったであろう。少なくとも、『石工師』の女性と、こうして仲良く《焚き火》を囲むことも叶わなかった。
「……で、そこの二人は、何でそんなに嫌そうなんですかね」
御役御免を免れたところで安堵する人もいれば、そうでない人もいるのである。全くもって雰囲気ぶち壊しの、空気読めない希望役職『ニート』の面々は、不貞腐れたように揃って唇を曲げていた。
「いや、だって、なぁ? ここでの労働が終われば帰れる訳だし」
「開拓事業完遂の報酬金も貰えますし」
「つまり、国の金で飯が食える」
「最高ですわ!」
恍惚と、二人は語る。
働かずに飯を食う、その魅力は俺も理解しているつもりだ。だが、それとこれとは話が別である。
「絶対二人は帰しませんから」
「鬼畜!」
「そういう差別はよくないと思うぜ、村長」
非難を一身に受けつつ、俺はちらりとナビ子に視線を遣る。
三枚目の《平焼きパン》を今まさに平らげようとしている彼女は、俺の視線に気付くと、ニコリと太陽のような笑みを浮かべた。
「村人の送還権限は、村長さんに一任されています」
「チイッ、政府の犬め!」
ルシンダの声は、世の恨みを全て練り込んだかのようだった。
思い返せば、彼女は政争の末この地にやって来たのだったか。やはり彼女と「国」との間には、浅からぬ因縁があるのだろう。
俺は、彼女の言う「政府」――レオタロン公国の命の下、開拓事業を行っているという設定だから、ルシンダにしてみれば、俺もまた「政府の犬」だ。ナビ子同様、詰られて相応の立場である。
これはただの戯れ事だ。ルシンダも本気ではないだろうが、牙を剥かれるとどうしても戸惑う。
だが一方のナビ子はまるで臆することなく、ピンと人差し指を立てて、
「逆に言えば、村長さんに帰ってくれと思わせられるような言動を行えば、国へ戻れるのです。まだまだチャンスはありますよ!」
「あの、ナビ子さん。あまりそれを推奨しないでください」
「あはは~、冗談ですよ。当たり前じゃないですか」
「冗談じゃなかったら驚きですよ」
最も信頼すべき少女に扇動されては、何を信じてよいのか分からなくなる。疑心暗鬼の中で開発を行う程マゾヒストではない。
「この村の人は、何やかんやでいい人ばかりですからね。途中で投げ出すことなんて、きっとしないですよね」
この村の構成員は、文句を垂れつつも、与えられた仕事はしっかり熟してくれる人ばかりだ。俺が困っていれば手を差し伸べ、時に叱咤と激励を送る。
『村長』と『村人』という役職上の高低はあるものの、それは事実、形骸に留まっている。俺が村人に、村人が俺に、どちらから意見を申し立てても、俺は決して傲慢に語ることはしないつもりだし、村人達も媚びる真似はしない。
もともと俺は、先輩だとか後輩だとか、時間的前後を由来とした身分の差を重視しない人間だ。幾年か前に引退した部活動でも、敬語を使われるのがむず痒くて仕方なかったくらいだ。むしろ疑問すら覚える。
あくまで対等に。同じ開拓者として平等に。俺が心掛けてきたのは、そういう体制だ。
「そういや、この村この村って呼んでるけどよ」
ふと、気抜けしたようにアランが口を開く。
「村の名前、何て言うんだ?」
入植十六日目。これが議題に上がったのは初めてのことであった。
0
あなたにおすすめの小説
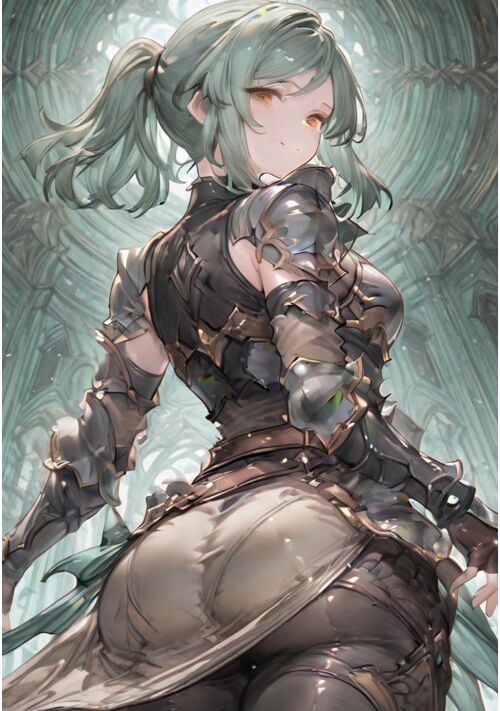
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

おっさん武闘家、幼女の教え子達と十年後に再会、実はそれぞれ炎・氷・雷の精霊の王女だった彼女達に言い寄られつつ世界を救い英雄になってしまう
お餅ミトコンドリア
ファンタジー
パーチ、三十五歳。五歳の時から三十年間修行してきた武闘家。
だが、全くの無名。
彼は、とある村で武闘家の道場を経営しており、〝拳を使った戦い方〟を弟子たちに教えている。
若い時には「冒険者になって、有名になるんだ!」などと大きな夢を持っていたものだが、自分の道場に来る若者たちが全員〝天才〟で、自分との才能の差を感じて、もう諦めてしまった。
弟子たちとの、のんびりとした穏やかな日々。
独身の彼は、そんな彼ら彼女らのことを〝家族〟のように感じており、「こんな毎日も悪くない」と思っていた。
が、ある日。
「お久しぶりです、師匠!」
絶世の美少女が家を訪れた。
彼女は、十年前に、他の二人の幼い少女と一緒に山の中で獣(とパーチは思い込んでいるが、実はモンスター)に襲われていたところをパーチが助けて、その場で数時間ほど稽古をつけて、自分たちだけで戦える力をつけさせた、という女の子だった。
「私は今、アイスブラット王国の〝守護精霊〟をやっていまして」
精霊を自称する彼女は、「ちょ、ちょっと待ってくれ」と混乱するパーチに構わず、ニッコリ笑いながら畳み掛ける。
「そこで師匠には、私たちと一緒に〝魔王〟を倒して欲しいんです!」
これは、〝弟子たちがあっと言う間に強くなるのは、師匠である自分の特殊な力ゆえ〟であることに気付かず、〝実は最強の実力を持っている〟ことにも全く気付いていない男が、〝実は精霊だった美少女たち〟と再会し、言い寄られ、弟子たちに愛され、弟子以外の者たちからも尊敬され、世界を救って英雄になってしまう物語。
(※第18回ファンタジー小説大賞に参加しています。
もし宜しければ【お気に入り登録】で応援して頂けましたら嬉しいです!
何卒宜しくお願いいたします!)

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

『異世界庭付き一戸建て』を相続した仲良し兄妹は今までの不幸にサヨナラしてスローライフを満喫できる、はず?
釈 余白(しやく)
ファンタジー
毒親の父が不慮の事故で死亡したことで最後の肉親を失い、残された高校生の小村雷人(こむら らいと)と小学生の真琴(まこと)の兄妹が聞かされたのは、父が家を担保に金を借りていたという絶望の事実だった。慣れ親しんだ自宅から早々の退去が必要となった二人は家の中で金目の物を探す。
その結果見つかったのは、僅かな現金に空の預金通帳といくつかの宝飾品、そして家の権利書と見知らぬ文字で書かれた書類くらいだった。謎の書類には祖父のサインが記されていたが内容は読めず、頼みの綱は挟まれていた弁護士の名刺だけだ。
最後の希望とも言える名刺の電話番号へ連絡した二人は、やってきた弁護士から契約書の内容を聞かされ唖然とする。それは祖父が遺産として残した『異世界トラス』にある土地と建物を孫へ渡すというものだった。もちろん現地へ行かなければ遺産は受け取れないが。兄妹には他に頼れるものがなく、思い切って異世界へと赴き新生活をスタートさせるのだった。
連載時、HOT 1位ありがとうございました!
その他、多数投稿しています。
こちらもよろしくお願いします!
https://www.alphapolis.co.jp/author/detail/398438394

元王城お抱えスキル研究家の、モフモフ子育てスローライフ 〜スキル:沼?!『前代未聞なスキル持ち』の成長、見守り生活〜
野菜ばたけ@既刊5冊📚好評発売中!
ファンタジー
「エレンはね、スレイがたくさん褒めてくれるから、ここに居ていいんだって思えたの」
***
魔法はないが、神から授かる特殊な力――スキルが存在する世界。
王城にはスキルのあらゆる可能性を模索し、スキル関係のトラブルを解消するための専門家・スキル研究家という職が存在していた。
しかしちょうど一年前、即位したばかりの国王の「そのようなもの、金がかかるばかりで意味がない」という鶴の一声で、職が消滅。
解雇されたスキル研究家のスレイ(26歳)は、ひょんな事から縁も所縁もない田舎の伯爵領に移住し、忙しく働いた王城時代の給金貯蓄でそれなりに広い庭付きの家を買い、元来からの拾い癖と大雑把な性格が相まって、拾ってきた動物たちを放し飼いにしての共同生活を送っている。
ひっそりと「スキルに関する相談を受け付けるための『スキル相談室』」を開業する傍ら、空いた時間は冒険者ギルドで、住民からの戦闘伴わない依頼――通称:非戦闘系依頼(畑仕事や牧場仕事の手伝い)を受け、スローな日々を謳歌していたスレイ。
しかしそんな穏やかな生活も、ある日拾い癖が高じてついに羊を連れた人間(小さな女の子)を拾った事で、少しずつ様変わりし始める。
スキル階級・底辺<ボトム>のありふれたスキル『召喚士』持ちの女の子・エレンと、彼女に召喚されたただの羊(か弱い非戦闘毛動物)メェ君。
何の変哲もない子たちだけど、実は「動物と会話ができる」という、スキル研究家のスレイでも初めて見る特殊な副効果持ちの少女と、『特性:沼』という、ヘンテコなステータス持ちの羊で……?
「今日は野菜の苗植えをします」
「おー!」
「めぇー!!」
友達を一千万人作る事が目標のエレンと、エレンの事が好きすぎるあまり、人前でもお構いなくつい『沼』の力を使ってしまうメェ君。
そんな一人と一匹を、スキル研究家としても保護者としても、スローライフを通して褒めて伸ばして導いていく。
子育て成長、お仕事ストーリー。
ここに爆誕!

追放令嬢と【神の農地】スキル持ちの俺、辺境の痩せ地を世界一の穀倉地帯に変えたら、いつの間にか建国してました。
黒崎隼人
ファンタジー
日本の農学研究者だった俺は、過労死の末、剣と魔法の異世界へ転生した。貧しい農家の三男アキトとして目覚めた俺には、前世の知識と、触れた土地を瞬時に世界一肥沃にするチートスキル【神の農地】が与えられていた!
「この力があれば、家族を、この村を救える!」
俺が奇跡の作物を育て始めた矢先、村に一人の少女がやってくる。彼女は王太子に婚約破棄され、「悪役令嬢」の汚名を着せられて追放された公爵令嬢セレスティーナ。全てを失い、絶望の淵に立つ彼女だったが、その瞳にはまだ気高い光が宿っていた。
「俺が、この土地を生まれ変わらせてみせます。あなたと共に」
孤独な元・悪役令嬢と、最強スキルを持つ転生農民。
二人の出会いが、辺境の痩せた土地を黄金の穀倉地帯へと変え、やがて一つの国を産み落とす奇跡の物語。
優しくて壮大な、逆転建国ファンタジー、ここに開幕!

攻撃魔法を使えないヒーラーの俺が、回復魔法で最強でした。 -俺は何度でも救うとそう決めた-【[完]】
水無月いい人(minazuki)
ファンタジー
【HOTランキング一位獲得作品】
【一次選考通過作品】
---
とある剣と魔法の世界で、
ある男女の間に赤ん坊が生まれた。
名をアスフィ・シーネット。
才能が無ければ魔法が使えない、そんな世界で彼は運良く魔法の才能を持って産まれた。
だが、使用できるのは攻撃魔法ではなく回復魔法のみだった。
攻撃魔法を一切使えない彼は、冒険者達からも距離を置かれていた。
彼は誓う、俺は回復魔法で最強になると。
---------
もし気に入っていただけたら、ブクマや評価、感想をいただけると大変励みになります!
#ヒラ俺
この度ついに完結しました。
1年以上書き続けた作品です。
途中迷走してました……。
今までありがとうございました!
---
追記:2025/09/20
再編、あるいは続編を書くか迷ってます。
もし気になる方は、
コメント頂けるとするかもしれないです。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















