1 / 2
月のうすいひかり
しおりを挟むハリスは、夜がきらいであるのだけれど、これとはまた別に、月を見ることは、うすい光が、自分に何か大切なことを教えてくれている様で、すきであった。
一日の終わるときは、かならず悲しい気持ちになるのだけれど、また新しい物語がはじまる様な、月のうすい光が、彼をやさしく、はぐれないように、つかまえてくれて、どこかへ連れていってくれる様で、きっとそれが、大切なことを教えてくれる様で、ハリスは、うれしい気持ちになった。
ハリスは、少しずつ自分の、心の中にあるおかしな部分が、ほんとに少しずつ、変わっていくことを、まったく喜ばなかった。いや、むしろ、そのことを、恐れた。
ハリスは、外へ顔をやると、黒い世界に自分の考えを、張り付けるような目で、一番輝いている星を見た。
ハリスは、きれいに部屋を片づけると、何も持たないで、ベッドの上にいる黒猫に、さよならと、小さな声で言って、自分の部屋の扉を開けると、廊下へ出た。
月のうすい光が、つきあたりの窓から入ってきていて、ハリスはその、月のうすい光を、たどる様に歩いて、右手に見える階段を、寝室で寝ている父さんや母さんを起こさないように、静かに下りていった。
ハリスは、この日の夜、月に誘われた様に、誰にも、何も言わないで、家を出た。
ハリスは、もうここへは戻らないと決めていた。それがいいと思っていた。
周りの、闇に包まれた風景が、ぼやけて見えた。
ハリスは、自分は何なのか、知りたい。それは確かであった。
今までの生活で培った様々なことに矛盾を感じていて、肯定できないでいて、困って、何かしらここでは学ぶことの出来ない、本当のことを知りたがっていて、そしてそれを、深く望んだ。
ここには答えがないということが、目に見えていたのかもしれなかった。
しかし、月のうすい光は、ハリスをやさしく、受け止めてくれていて、その時は一筋の希望の上に、自分がいる様に思えた。それは、不思議と、呼吸をすることと同じ様で、自然であった。
ハリスは、前へ踏み出そうとした。
すると、どうしてか彼は、いつの日か後悔してしまう様な、まとわりつく、よどよどしたものに、さえぎられた。
それは、実のところ、今すぐにでも、誰かが自分に襲いかかってきて、何か大変なことに巻き込まれてしまう様な、恐さと、彼の本心の裏側にある、まだ形として、しっかり出来ていない、弱々しい天秤の、片方へながれこむ量だけ、それは大きくゆりうごき、いつか、それが均等を保てなくなってしまう様な、不安であった。
ハリスは、追い払おうとしたが、無理であったから、足もとを照らす、月のうすい光を見て、そして、夜空に目を向けた。
深呼吸して、どこへ行こうかと、ハリスは考えた。しかし、どこでもいいと思った。
ハリスは、しばらくして前へ進んだ。月の下を黒く塗った地の上を、何も持たずに前へ進んだ。
月のうすい光が、道をつくってくれていて、やはり、その光は、どこに繋がっているのか分からなかった。
ハリスは、長い間、その道を歩いていると、老婆が、木のベンチへ腰掛けているのに、気が付いた。
暗い夜の中で一人、老婆はベンチに座っていた。
ハリスは、こんばんは、と言い、通り過ぎようとしたが、老婆が、何か話をし始めたので、ハリスは、隣に座り、話を聞くことにした。
少しも恐くはなく、親しみのある口調であるから、心配はいらないと、ハリスは思った。
その声は、しかし、かすれていた。
「どこへ行くのか?」
「知りません、前に進めば何かあるかと」
「そうですか、何かありますか、それはいい、きっと何かありますよ」
「それはうれしい、でもなぜ分かるのか?」
「ええ、分かるとも、あなたのその青い瞳は、この世を探り続けていますよ」
「はい、探しています、でもどこにあるのか知りません」
「それはそうでしょう」
「なぜです?」
「なぜって、面白いことを聞きますね、あなたは今探しているのでしょう?」
「はい」
「ではもうすでに、分かっているではないですか」
老婆はそう言うと、黙ったままになった。
ハリスは、しょうがなくベンチから離れると、再び前へ歩き出した。
0
あなたにおすすめの小説


隣のじいさん
kudamonokozou
児童書・童話
小学生の頃僕は祐介と友達だった。空き家だった隣にいつの間にか変なじいさんが住みついた。
祐介はじいさんと仲良しになる。
ところが、そのじいさんが色々な騒動を起こす。
でも祐介はじいさんを信頼しており、ある日遠い所へ二人で飛んで行ってしまった。

ローズお姉さまのドレス
有沢真尋
児童書・童話
*「第3回きずな児童書大賞」エントリー中です*
最近のルイーゼは少しおかしい。
いつも丈の合わない、ローズお姉さまのドレスを着ている。
話し方もお姉さまそっくり。
わたしと同じ年なのに、ずいぶん年上のように振舞う。
表紙はかんたん表紙メーカーさまで作成

ユリウスの絵の具
こうやさい
児童書・童話
昔、とある田舎の村の片隅に売れない画家の青年が妻とともに住んでいました。
ある日その妻が病で亡くなり、青年は精神を病んでしまいました。
確か大人向けの童話な感じを目指して書いた話。ガイドラインから児童書・童話カテゴリの異世界禁止は消えたけど、内容・表現が相応しいかといわれると……うん、微妙だよね、ぶっちゃけ保険でR付けたいくらいだし。ですます調をファンタジーだということに相変わらず違和感凄いのでこっちにしたけど……これ、悪質かねぇ? カテ変わってたり消えてたら察して下さい。なんで自分こんなにですます調ファンタジー駄目なんだろう? それでもですます調やめるくらいならカテゴリの方諦めるけど。
そして無意味に名前がついてる主人公。いやタイトルから出来た話なもので。けどそもそもなんでこんなタイトル浮かんだんだ? なんかユリウスって名前の絵に関係するキャラの話でも読んでたのか? その辺記憶がない。消えてたら察して下さい(二回目)。記憶力のなさがうらめしい。こういうの投稿前に自動で判別つくようにならないかなぁ。
ただいま諸事情で出すべきか否か微妙なので棚上げしてたのとか自サイトの方に上げるべきかどうか悩んでたのとか大昔のとかを放出中です。見直しもあまり出来ないのでいつも以上に誤字脱字等も多いです。ご了承下さい。
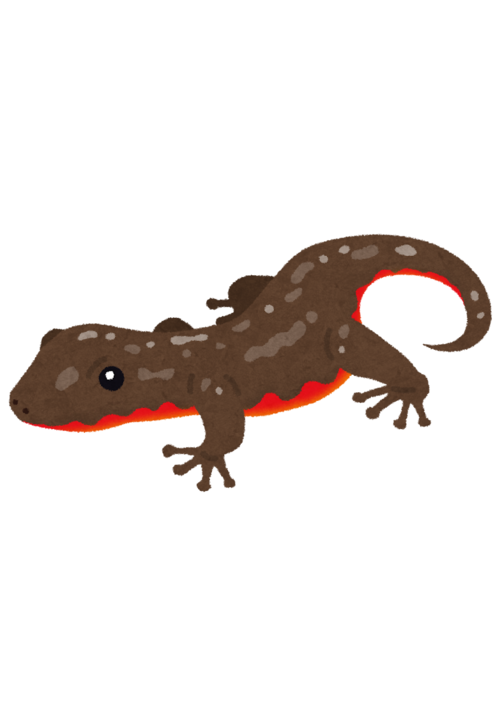

緑色の友達
石河 翠
児童書・童話
むかしむかしあるところに、大きな森に囲まれた小さな村がありました。そこに住む女の子ララは、祭りの前日に不思議な男の子に出会います。ところが男の子にはある秘密があったのです……。
こちらは小説家になろうにも投稿しております。
表紙は、貴様 二太郎様に描いて頂きました。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















