14 / 35
第13章 ウォーホランディの赤いピストル
しおりを挟む
むきゅっむきゅっ、むきゅっむきゅっ。ヴァイキングの島と大陸をつなぐ砂州は、エレンが踏みしめるたびに、小動物の泣き声にも窓磨きの音にも聞こえる、音の出る砂でできていました。
この海の真ん中にできた白い道は、エレンが歩きはじめて以来どんどん幅を広げ、最終的に方側二車線の高速道路くらいになっていました。しかし太陽が高くなると幅はまた狭まりはじめ、エレンが大陸に着く頃には、時折波間に顔を覗かせていた赤いトマト缶が、だいぶ砂州に置いていかれるようになっていました。
エレンが着いたのは、自動車もテレビもある近代的な都市ウォーホランディ。港にはベルゲンにもあるようなタグボートが並び、洒落たネイビーのウッドデッキが整備されています。しかし何よりエレンを喜ばせたのは、ポテトを揚げる油のしゅわしゅわいう音とハンバーグの焼けるいい匂い。エレンは唾をごくりと飲み込むと、匂いの元と思われるダイナーへ向かいました。
オーロフにもらった大陸の紙幣を握りしめて、食べたいものを全部注文すると、エレンはテラスデッキにあるこの店の特等席に陣取りました。三段重ねの特大ハンバーガーに、皮付きフライドポテト。そしてコーラ! これです。これ、これ! これが食べたかったんです。何時間も歩いてお腹ぺこぺこだったエレンは、無我夢中で食べました。
味を楽しみたいばかりに、エレンがいつまでも手についたポテトの塩を舐めていると、突然店内に悲鳴が響きました。慌てて振り返えると、お店のおばさんがちょうどカウンターの下に隠れようとしているところです。エレンが様子を見に行こうと立ち上がった瞬間、何か冷たいものがぴちゃっと頬に当たりました。触ってみると、それは真っ赤なトマトケチャップでした。
エレンが顔を上げると、げちゃげちゃと品の悪い笑い声がして、四人組の男の子たちが窓の外から覗き込んでいるのが目に入りました。年はエレンと同じくらいか、それより下で、それぞれの手には「ナツィオン・ケチャップ」と書かれた赤いボトルを装填した銃が握られています。エレンはむっとして言いました。
「なんてことするの。ひどいじゃないか」
お腹いっぱい美味しいものを食べて幸せな気分だったのに、これではぶち壊しです。エレンはなんとしても謝らせようと決意しました。なのに男の子たちは、敵はまだ生きているぞ、援護しろとか言って、エレンがケチャップまみれになるまで攻撃をやめませんでした。
男の子たちが逃げ去ると、エレンのまわりにはケチャップの水たまりができていました。エレンが惨めさのあまり呆然としていると、カウンターの奥からおばさんが出てきて、冷たいけど我慢してよ、とバケツ一杯の水をかけてくれました。すると頭の先から靴の先までまんべんなくついていたケチャップはほとんど洗い流され、どろどろと排水溝へ流れていきました。
「旅行者でしょう。驚かせて悪かったね。子どもたちの間であのケチャップ銃が流行っていてね。誰彼構わず、発射するんだよ」
赤いタオルをエレンに渡すと、おばさんはエレンの服をつまんでじっと見つめました。
「あーあ。やっぱりシミになっちゃってる」
おばさんがつまんだところを見ると、水を浴びたのとは違う変色した部分があります。エレンがあとで洗うから大丈夫です、というとおばさんは首を横に振りました。
「このケチャップはケーニヒさんとこの店じゃないと落ちないんだよ」
ケーニヒというのはナツィオン・ケチャップを町で唯一落とすことができるクリーニング屋でしたが、ノウハウを独占しているということで、料金がべらぼうに高いことで有名でした。しかしケーニヒの店以外にケチャップを落とせるところがないので、みんな渋々通っているのでした。
「全部が全部クリーニングに出せないから、みんなお気に入りの服は着ないようにしたり、赤い服ばかり着たりしているのさ。あんたも着替えを買うなら気をつけて」
おばさんの言っていたことは本当で、町には赤い服か、だめになっても諦めがつくようなお古を着た人しかいませんでした。それにお店で売っているのも赤い服ばかりです。中にはケチャップ銃を浴びても絵になるように、絵の具をぶちまけたようなデザインのTシャツもありましたが、エレンは無難なTシャツと赤いパーカー、それにジーンズを買いました。
新しい服に着替えてさっぱりすると、エレンは噂のケーニヒの店に向かいました。ケチャップをかけられた服はオレグのものだったので、きちんとクリーニングしたかったのです。ケーニヒの店は繁盛しているだけあって、町で一番地価の高いメインストリートに店を構えているとのことでした。エレンは標識を頼りになんとなく進みましたが、ある角を曲がった途端、それまでと百八十度様子が変わったので、ストリートに入ったことがすぐに分かりました。
このストリートにはナツィオン・ケチャップ社をはじめとする大企業の本社や、工場に勤務する労働者たちのために作られた高層アパート、それに彼らに供給する食べ物や衣服や娯楽品を取り扱う大型商業施設が立ち並んでいて、とても都会的です。しかし下から見上げるだけでも目が回りそうな高層ビルに住んだり、秒刻みで働いたりするとしたら、いくらハイソな暮らしでも、エレンはここの住人になりたいとは思いませんでした。
さて、ケーニヒの店はウォーホランディの中心から三ブロックいった角にありました。清潔感溢れる白を基調とした建物に、気品ある濃紺の筆記体で書かれた看板がかけられています。
「ケーニヒ・クリーニング店 月曜日~土曜日 朝七時~夜七時」
どの横断歩道を渡る人にも一目で分かるように、店の入り口をブロックの角に設えているあたりはさすがです。ちょっとした階段を上がってドアを開けると、ドアベルがチリンと鳴りました。
広い店内にはやはり白を基調としたカウンターと、クリーム色と紺色の配色が光る待ち合い椅子があり、なかなか洒落た内装です。カウンターの奥のハンガーラックに出来上がった衣服が、整然と並べられた様も好印象を与えます。しかし看板に書いてある営業時間内にも関わらず、カウンターには誰もいません。店の奥からは、パンッパンッという洗濯物の皺を伸ばす音が聞こえてくるのに、誰も対応しようとしないのです。
エレンはドアベルが聞こえなかったのかと思って、わざと大きな咳払いをしてみました。しかし誰も出てきません。仕方なく大きな声でこんにちはと言ってみましたが、それでも反応がありません。ダイナーのおばさんが高飛車な店だと言っていましたが、あんまりです。エレンはカウンターをくぐって、奥へ続く廊下をすすみました。
狭い廊下は洗濯待ちの衣料品がところ狭しと置かれていました。洗剤やブラシ、洗濯バサミにアイロンが置かれた水色の棚もありましたが、とにかく洗濯物の量がものすごいのです。ほとんどは白い服でしたが、中には水色や黄色もあり、どれも真っ赤なケチャップが付着しています。それぞれの洗濯物にはタグがついていて、持ち主の名前、預かり日、それに「袖のボタンとれかけ」といった特記事項が書かれています。
エレンが天井まで堆く積まれた洗濯物の山に見入っていると、またあのパンッパンッという洗濯物の皺を伸ばす音が聞こえてきました。エレンは棚に隠れるようにそっと裏庭を覗きました。
気持ちのいい風に翻る真っ白なシーツのカーテンの向こうで、誰かがせわしなく洗濯をしています。エレンはすぐさま声をかけようと思いましたが、お店のプライベートな部屋にエレンがいて、しかも誰も出てこないなんてどうなっているんだ、なんて言ったら、お店の人はどう思うでしょう。下手をすると、警察に突き出されるかもしれません。
このまま待合室に戻ろうと思い始めたそのとき、ピンと張っていた洗濯ひもに突然びーんと振動がありました。そして次の瞬間には、何者かがシーツに突っ込んで、干してあったものだけでなく、ひもを結びつけていた支柱までなぎ倒して、あたりはめちゃめちゃになりました。
エレンはすぐに助けに行こうとしましたが、見覚えのある二人組がもぞもぞと洗濯物の山から顔を覗かせたので、慌てて物陰に隠れました。それはあの、ひょろりと小男・ガストンでした。空飛ぶトラムには乗れなかったけれど、どうにかここまで追って来たのでしょう。
ひょろりがふとこちらを見た気がしたので、エレンはどきりとしました。悪党二人は目と鼻の先です。エレンはどきどきしすぎて心臓の音が聞こえてしまうのではないかと思いました。しかしもっと驚くべきことが起きたので、ひょろりはすぐにそちらに気をとられました。だって洗濯物の山から、なんとレネが姿を現したのです!
レネが二人の間に飛び出すかたちになったのに、状況を飲み込めなかったのか、男たちはしばらく目をぱちくりさせるだけでした。しかしこれがまたとない機会であることにやっとこさ気がつくと、一斉にレネに飛びかかりました。幸いレネは、慌てふためくガストンの顔を踏んずけて鮮やかに逃げきりましたが。
「なんてすばしっこい奴なんだ」
玉のような汗を拭おうと、ガストンは律儀にハンカチを取り出しました。しかしひょろりに突き飛ばされたので、イニシャル入りのハンカチは空を撫でただけになりました。そしてハンカチの代わりに、前のめりにつっぷしたガストンの汗は、散乱した洗濯物にしみ込むことになりました。
他方相棒をぞんざいに扱ったひょろりは、ものすごい勢いでシーツをかき分けていましたが、やがて何かを引っ張りだすと、苦虫を噛み潰したような表情を浮かべました。お気に入りの帽子がガストンの下敷きになって形が崩れています。
「ご、ご、ご、ごめんよ、アルフォンス兄貴。そこに帽子があるなんて思わなくて」
ガストンはアルフォンスひょろりの帽子をなんとか元に戻そう躍起になりました。しかしもう遅すぎました。帽子はガストンプレスで、ぺっちゃんこを形状記憶していたのです。アルフォンスは帽子を地面に叩き付けました。
「くそっ!」
「兄貴、そんなことしちゃいけません。これはまた必要になるんだから」
ガストンは帽子を拾い上げ、そっと埃を払いました。
「お前、本気でそんなことを思っているのか。それともそう言えば俺が安心するからか。ガストン、お前とは長い付き合いだが、いい加減なことは言うものじゃない。俺はいまあれを躍起になって探しているが、近頃はそもそもそんなものはなかったようにも思うのだ」
アルフォンスがしんみりこう言ったので、ガストンは必死に否定しました。
「何を弱気になっているんです。あいつを取り戻せば、すべてうまくいくに決まってます。上手いものでも食べて計画を練り直しましょう。通りの向こうに日本食のレストランがありましたぜ」
「なぜそれを早く言わない。日本食は足の早いものが多いんだ。急がないと追いつけなくなるぞ」
そういってアルフォンスが足早に立ち去ったので、短足のガストンは全速力で追いかけなくてはなりませんでした。
謎の二人組が行ってしまうと、エレンは洗濯物に埋もれた人物を助けるため裏庭に出ました。みなさんは忘れてしまったかもしれませんが、シーツをパンパンしていたあの人物はまだ発掘されていないのです。
それにしても、アルフォンスにあんな気弱な一面があったなんて。レネに大切なものを食べられて追い回しているというのは知っていましたが、あれほど落ち込むということはよほど大事なものなのでしょう。脅し方こそ卑劣ですが、エレンはなんだかアルフォンスが気の毒に思えてきました。
そんなことを考えながら掘り進んでいると、エレンは渦中の人物の腕を探り当てました。小さくて柔らかな手からして、小さな女の子かもしれません。気を失ってしまったらしく、ぐったりとしていますが、エレンなんとかその人を救出することに成功しました。しかしひっぱりだしてびっくり仰天。現われたのはまったく予想外の人物だったのです。
「フラッフィ!」
エレンは思わず大きな声を上げました。レネの安心毛布にして相談役のくまさん、フラッフィがどうしてここにいるのでしょう。しかもフラッフィはたしか、エレンが家の裏の森に投げ捨てたはずです。
「真っ白ふんわりおひさまのにおい。ケーニヒ・クリーニング店へようこそ。お洗濯コースは通常ですか、お急ぎですか」
まだ半分気を失っているのに、フラッフィはとても流暢に話しました。
しかしエレンが身体を少し揺さぶってやると、フラッフィは完全に意識を取り戻して、ねずみ取りのバネみたいに飛び起きました。
「ごめんなさい、店長! 僕、決してさぼるつもりは・・・あれ」
「フラッフィ! エレンだよ。まさかこんな風に会えるなんて。なんて懐かしいんだろう。実はレネが猫になっちゃったんだ。さっきいた、あの猫さ」
エレンは思わずフラッフィを抱きしめました。しかしフラッフィの方はまったくそっけない態度を示して、うんざりしたような重いため息までつきました。またフラッフィはエレンのことを知らない風で、レネについて訊いてもまったくなびく気配がないのでした。
「エレン、今日は会えてよかったよ。でも僕はレネなんて人は知りもしないし、そもそも君の思っているようなくまじゃないんだ。気が済んだら帰っておくれ」
ぞんざいにエレンとの握手を済ませると、フラッフィはまたまた大きな溜息をつきました。綺麗に洗い上げた洗濯物が泥だらけになっています。落胆するのも無理はありません。エレンが手伝いを申し出ようかしらと思案していると突然、男の怒鳴り声がしました。
「フラッフィ、何をやってる! 仕事はうんと残ってるんだぞ!」
それはクリーニング店の二階から見下ろしている、恰幅の良い頭の禿げ上がった男で、ひん曲がった口の上には黒々とした口ひげが乗っていました。しかしこの男の一番の特徴は、こめかみのあたりからにょろりと立ち上がった一本の毛で、しかもなんとほくろから生えています。まわりがきれいに禿げ上がっている分、これはかなり目を引きます。
「すみません、ケーニヒさん。すぐにやり直しますから」
雇用主に詫びを入れると、フラッフィは黙々と洗濯物を集めはじめました。
エレンは、悪いのはフラッフィじゃないと言わないのかと耳打ちしましたが、フラッフィは眉間に皺を寄せて、迷惑だからやめてくれと言いました。こういわれては取りつく島もありません。エレンはすごすご帰るほかありませんでした。
この海の真ん中にできた白い道は、エレンが歩きはじめて以来どんどん幅を広げ、最終的に方側二車線の高速道路くらいになっていました。しかし太陽が高くなると幅はまた狭まりはじめ、エレンが大陸に着く頃には、時折波間に顔を覗かせていた赤いトマト缶が、だいぶ砂州に置いていかれるようになっていました。
エレンが着いたのは、自動車もテレビもある近代的な都市ウォーホランディ。港にはベルゲンにもあるようなタグボートが並び、洒落たネイビーのウッドデッキが整備されています。しかし何よりエレンを喜ばせたのは、ポテトを揚げる油のしゅわしゅわいう音とハンバーグの焼けるいい匂い。エレンは唾をごくりと飲み込むと、匂いの元と思われるダイナーへ向かいました。
オーロフにもらった大陸の紙幣を握りしめて、食べたいものを全部注文すると、エレンはテラスデッキにあるこの店の特等席に陣取りました。三段重ねの特大ハンバーガーに、皮付きフライドポテト。そしてコーラ! これです。これ、これ! これが食べたかったんです。何時間も歩いてお腹ぺこぺこだったエレンは、無我夢中で食べました。
味を楽しみたいばかりに、エレンがいつまでも手についたポテトの塩を舐めていると、突然店内に悲鳴が響きました。慌てて振り返えると、お店のおばさんがちょうどカウンターの下に隠れようとしているところです。エレンが様子を見に行こうと立ち上がった瞬間、何か冷たいものがぴちゃっと頬に当たりました。触ってみると、それは真っ赤なトマトケチャップでした。
エレンが顔を上げると、げちゃげちゃと品の悪い笑い声がして、四人組の男の子たちが窓の外から覗き込んでいるのが目に入りました。年はエレンと同じくらいか、それより下で、それぞれの手には「ナツィオン・ケチャップ」と書かれた赤いボトルを装填した銃が握られています。エレンはむっとして言いました。
「なんてことするの。ひどいじゃないか」
お腹いっぱい美味しいものを食べて幸せな気分だったのに、これではぶち壊しです。エレンはなんとしても謝らせようと決意しました。なのに男の子たちは、敵はまだ生きているぞ、援護しろとか言って、エレンがケチャップまみれになるまで攻撃をやめませんでした。
男の子たちが逃げ去ると、エレンのまわりにはケチャップの水たまりができていました。エレンが惨めさのあまり呆然としていると、カウンターの奥からおばさんが出てきて、冷たいけど我慢してよ、とバケツ一杯の水をかけてくれました。すると頭の先から靴の先までまんべんなくついていたケチャップはほとんど洗い流され、どろどろと排水溝へ流れていきました。
「旅行者でしょう。驚かせて悪かったね。子どもたちの間であのケチャップ銃が流行っていてね。誰彼構わず、発射するんだよ」
赤いタオルをエレンに渡すと、おばさんはエレンの服をつまんでじっと見つめました。
「あーあ。やっぱりシミになっちゃってる」
おばさんがつまんだところを見ると、水を浴びたのとは違う変色した部分があります。エレンがあとで洗うから大丈夫です、というとおばさんは首を横に振りました。
「このケチャップはケーニヒさんとこの店じゃないと落ちないんだよ」
ケーニヒというのはナツィオン・ケチャップを町で唯一落とすことができるクリーニング屋でしたが、ノウハウを独占しているということで、料金がべらぼうに高いことで有名でした。しかしケーニヒの店以外にケチャップを落とせるところがないので、みんな渋々通っているのでした。
「全部が全部クリーニングに出せないから、みんなお気に入りの服は着ないようにしたり、赤い服ばかり着たりしているのさ。あんたも着替えを買うなら気をつけて」
おばさんの言っていたことは本当で、町には赤い服か、だめになっても諦めがつくようなお古を着た人しかいませんでした。それにお店で売っているのも赤い服ばかりです。中にはケチャップ銃を浴びても絵になるように、絵の具をぶちまけたようなデザインのTシャツもありましたが、エレンは無難なTシャツと赤いパーカー、それにジーンズを買いました。
新しい服に着替えてさっぱりすると、エレンは噂のケーニヒの店に向かいました。ケチャップをかけられた服はオレグのものだったので、きちんとクリーニングしたかったのです。ケーニヒの店は繁盛しているだけあって、町で一番地価の高いメインストリートに店を構えているとのことでした。エレンは標識を頼りになんとなく進みましたが、ある角を曲がった途端、それまでと百八十度様子が変わったので、ストリートに入ったことがすぐに分かりました。
このストリートにはナツィオン・ケチャップ社をはじめとする大企業の本社や、工場に勤務する労働者たちのために作られた高層アパート、それに彼らに供給する食べ物や衣服や娯楽品を取り扱う大型商業施設が立ち並んでいて、とても都会的です。しかし下から見上げるだけでも目が回りそうな高層ビルに住んだり、秒刻みで働いたりするとしたら、いくらハイソな暮らしでも、エレンはここの住人になりたいとは思いませんでした。
さて、ケーニヒの店はウォーホランディの中心から三ブロックいった角にありました。清潔感溢れる白を基調とした建物に、気品ある濃紺の筆記体で書かれた看板がかけられています。
「ケーニヒ・クリーニング店 月曜日~土曜日 朝七時~夜七時」
どの横断歩道を渡る人にも一目で分かるように、店の入り口をブロックの角に設えているあたりはさすがです。ちょっとした階段を上がってドアを開けると、ドアベルがチリンと鳴りました。
広い店内にはやはり白を基調としたカウンターと、クリーム色と紺色の配色が光る待ち合い椅子があり、なかなか洒落た内装です。カウンターの奥のハンガーラックに出来上がった衣服が、整然と並べられた様も好印象を与えます。しかし看板に書いてある営業時間内にも関わらず、カウンターには誰もいません。店の奥からは、パンッパンッという洗濯物の皺を伸ばす音が聞こえてくるのに、誰も対応しようとしないのです。
エレンはドアベルが聞こえなかったのかと思って、わざと大きな咳払いをしてみました。しかし誰も出てきません。仕方なく大きな声でこんにちはと言ってみましたが、それでも反応がありません。ダイナーのおばさんが高飛車な店だと言っていましたが、あんまりです。エレンはカウンターをくぐって、奥へ続く廊下をすすみました。
狭い廊下は洗濯待ちの衣料品がところ狭しと置かれていました。洗剤やブラシ、洗濯バサミにアイロンが置かれた水色の棚もありましたが、とにかく洗濯物の量がものすごいのです。ほとんどは白い服でしたが、中には水色や黄色もあり、どれも真っ赤なケチャップが付着しています。それぞれの洗濯物にはタグがついていて、持ち主の名前、預かり日、それに「袖のボタンとれかけ」といった特記事項が書かれています。
エレンが天井まで堆く積まれた洗濯物の山に見入っていると、またあのパンッパンッという洗濯物の皺を伸ばす音が聞こえてきました。エレンは棚に隠れるようにそっと裏庭を覗きました。
気持ちのいい風に翻る真っ白なシーツのカーテンの向こうで、誰かがせわしなく洗濯をしています。エレンはすぐさま声をかけようと思いましたが、お店のプライベートな部屋にエレンがいて、しかも誰も出てこないなんてどうなっているんだ、なんて言ったら、お店の人はどう思うでしょう。下手をすると、警察に突き出されるかもしれません。
このまま待合室に戻ろうと思い始めたそのとき、ピンと張っていた洗濯ひもに突然びーんと振動がありました。そして次の瞬間には、何者かがシーツに突っ込んで、干してあったものだけでなく、ひもを結びつけていた支柱までなぎ倒して、あたりはめちゃめちゃになりました。
エレンはすぐに助けに行こうとしましたが、見覚えのある二人組がもぞもぞと洗濯物の山から顔を覗かせたので、慌てて物陰に隠れました。それはあの、ひょろりと小男・ガストンでした。空飛ぶトラムには乗れなかったけれど、どうにかここまで追って来たのでしょう。
ひょろりがふとこちらを見た気がしたので、エレンはどきりとしました。悪党二人は目と鼻の先です。エレンはどきどきしすぎて心臓の音が聞こえてしまうのではないかと思いました。しかしもっと驚くべきことが起きたので、ひょろりはすぐにそちらに気をとられました。だって洗濯物の山から、なんとレネが姿を現したのです!
レネが二人の間に飛び出すかたちになったのに、状況を飲み込めなかったのか、男たちはしばらく目をぱちくりさせるだけでした。しかしこれがまたとない機会であることにやっとこさ気がつくと、一斉にレネに飛びかかりました。幸いレネは、慌てふためくガストンの顔を踏んずけて鮮やかに逃げきりましたが。
「なんてすばしっこい奴なんだ」
玉のような汗を拭おうと、ガストンは律儀にハンカチを取り出しました。しかしひょろりに突き飛ばされたので、イニシャル入りのハンカチは空を撫でただけになりました。そしてハンカチの代わりに、前のめりにつっぷしたガストンの汗は、散乱した洗濯物にしみ込むことになりました。
他方相棒をぞんざいに扱ったひょろりは、ものすごい勢いでシーツをかき分けていましたが、やがて何かを引っ張りだすと、苦虫を噛み潰したような表情を浮かべました。お気に入りの帽子がガストンの下敷きになって形が崩れています。
「ご、ご、ご、ごめんよ、アルフォンス兄貴。そこに帽子があるなんて思わなくて」
ガストンはアルフォンスひょろりの帽子をなんとか元に戻そう躍起になりました。しかしもう遅すぎました。帽子はガストンプレスで、ぺっちゃんこを形状記憶していたのです。アルフォンスは帽子を地面に叩き付けました。
「くそっ!」
「兄貴、そんなことしちゃいけません。これはまた必要になるんだから」
ガストンは帽子を拾い上げ、そっと埃を払いました。
「お前、本気でそんなことを思っているのか。それともそう言えば俺が安心するからか。ガストン、お前とは長い付き合いだが、いい加減なことは言うものじゃない。俺はいまあれを躍起になって探しているが、近頃はそもそもそんなものはなかったようにも思うのだ」
アルフォンスがしんみりこう言ったので、ガストンは必死に否定しました。
「何を弱気になっているんです。あいつを取り戻せば、すべてうまくいくに決まってます。上手いものでも食べて計画を練り直しましょう。通りの向こうに日本食のレストランがありましたぜ」
「なぜそれを早く言わない。日本食は足の早いものが多いんだ。急がないと追いつけなくなるぞ」
そういってアルフォンスが足早に立ち去ったので、短足のガストンは全速力で追いかけなくてはなりませんでした。
謎の二人組が行ってしまうと、エレンは洗濯物に埋もれた人物を助けるため裏庭に出ました。みなさんは忘れてしまったかもしれませんが、シーツをパンパンしていたあの人物はまだ発掘されていないのです。
それにしても、アルフォンスにあんな気弱な一面があったなんて。レネに大切なものを食べられて追い回しているというのは知っていましたが、あれほど落ち込むということはよほど大事なものなのでしょう。脅し方こそ卑劣ですが、エレンはなんだかアルフォンスが気の毒に思えてきました。
そんなことを考えながら掘り進んでいると、エレンは渦中の人物の腕を探り当てました。小さくて柔らかな手からして、小さな女の子かもしれません。気を失ってしまったらしく、ぐったりとしていますが、エレンなんとかその人を救出することに成功しました。しかしひっぱりだしてびっくり仰天。現われたのはまったく予想外の人物だったのです。
「フラッフィ!」
エレンは思わず大きな声を上げました。レネの安心毛布にして相談役のくまさん、フラッフィがどうしてここにいるのでしょう。しかもフラッフィはたしか、エレンが家の裏の森に投げ捨てたはずです。
「真っ白ふんわりおひさまのにおい。ケーニヒ・クリーニング店へようこそ。お洗濯コースは通常ですか、お急ぎですか」
まだ半分気を失っているのに、フラッフィはとても流暢に話しました。
しかしエレンが身体を少し揺さぶってやると、フラッフィは完全に意識を取り戻して、ねずみ取りのバネみたいに飛び起きました。
「ごめんなさい、店長! 僕、決してさぼるつもりは・・・あれ」
「フラッフィ! エレンだよ。まさかこんな風に会えるなんて。なんて懐かしいんだろう。実はレネが猫になっちゃったんだ。さっきいた、あの猫さ」
エレンは思わずフラッフィを抱きしめました。しかしフラッフィの方はまったくそっけない態度を示して、うんざりしたような重いため息までつきました。またフラッフィはエレンのことを知らない風で、レネについて訊いてもまったくなびく気配がないのでした。
「エレン、今日は会えてよかったよ。でも僕はレネなんて人は知りもしないし、そもそも君の思っているようなくまじゃないんだ。気が済んだら帰っておくれ」
ぞんざいにエレンとの握手を済ませると、フラッフィはまたまた大きな溜息をつきました。綺麗に洗い上げた洗濯物が泥だらけになっています。落胆するのも無理はありません。エレンが手伝いを申し出ようかしらと思案していると突然、男の怒鳴り声がしました。
「フラッフィ、何をやってる! 仕事はうんと残ってるんだぞ!」
それはクリーニング店の二階から見下ろしている、恰幅の良い頭の禿げ上がった男で、ひん曲がった口の上には黒々とした口ひげが乗っていました。しかしこの男の一番の特徴は、こめかみのあたりからにょろりと立ち上がった一本の毛で、しかもなんとほくろから生えています。まわりがきれいに禿げ上がっている分、これはかなり目を引きます。
「すみません、ケーニヒさん。すぐにやり直しますから」
雇用主に詫びを入れると、フラッフィは黙々と洗濯物を集めはじめました。
エレンは、悪いのはフラッフィじゃないと言わないのかと耳打ちしましたが、フラッフィは眉間に皺を寄せて、迷惑だからやめてくれと言いました。こういわれては取りつく島もありません。エレンはすごすご帰るほかありませんでした。
0
あなたにおすすめの小説

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

笑いの授業
ひろみ透夏
児童書・童話
大好きだった先先が別人のように変わってしまった。
文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。
それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。
伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。
追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。

あだ名が242個ある男(実はこれ実話なんですよ25)
tomoharu
児童書・童話
え?こんな話絶対ありえない!作り話でしょと思うような話からあるある話まで幅広い範囲で物語を考えました!ぜひ読んでみてください!数年後には大ヒット間違いなし!!
作品情報【伝説の物語(都道府県問題)】【伝説の話題(あだ名とコミュニケーションアプリ)】【マーライオン】【愛学両道】【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】【トモレオ突破椿】など
・【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】とは、その話はさすがに言いすぎでしょと言われているほぼ実話ストーリーです。
小さい頃から今まで主人公である【紘】はどのような体験をしたのかがわかります。ぜひよんでくださいね!
・【トモレオ突破椿】は、公務員試験合格なおかつ様々な問題を解決させる話です。
頭の悪かった人でも公務員になれることを証明させる話でもあるので、ぜひ読んでみてください!
特別記念として実話を元に作った【呪われし◯◯シリーズ】も公開します!
トランプ男と呼ばれている切札勝が、トランプゲームに例えて次々と問題を解決していく【トランプ男】シリーズも大人気!
人気者になるために、ウソばかりついて周りの人を誘導し、すべて自分のものにしようとするウソヒコをガチヒコが止める【嘘つきは、嘘治の始まり】というホラーサスペンスミステリー小説

かつて聖女は悪女と呼ばれていた
朔雲みう (さくもみう)
児童書・童話
「別に計算していたわけではないのよ」
この聖女、悪女よりもタチが悪い!?
悪魔の力で聖女に成り代わった悪女は、思い知ることになる。聖女がいかに優秀であったのかを――!!
聖女が華麗にざまぁします♪
※ エブリスタさんの妄コン『変身』にて、大賞をいただきました……!!✨
※ 悪女視点と聖女視点があります。
※ 表紙絵は親友の朝美智晴さまに描いていただきました♪


14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。
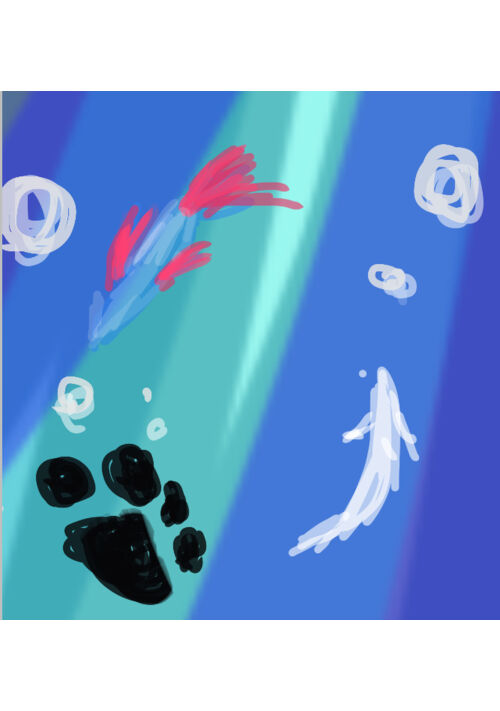
25匹の魚と猫と
ねこ沢ふたよ
児童書・童話
コメディです。
短編です。
暴虐無人の猫に一泡吹かせようと、水槽のメダカとグッピーが考えます。
何も考えずに笑って下さい
※クラムボンは笑いません
25周年おめでとうございます。
Copyright©︎

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















