27 / 35
第26章 氷の民と思わぬ味方
しおりを挟む
氷の民が住むという集落を目指して、エレン、リン、アルベルトの三人は真っ白な雪原を黙々と歩いていました。キルステンとフラッフィは、ゾフィを見ているという名目で飛行船に残ることになりましたが、それは危険な場所に二人を連れて行けないというリンの判断でした。最初リンは、エレンも子ども扱いして、アルベルトと二人で行こうとしました。けれどエレンはドラゴンの試練のことを持ち出して、リンはいざというとき裏切る可能性があるけど、僕は本当に勇気があるんだと主張しました。リンはすぐには首を縦に振りませんでしたが、アルベルトの後押しもあって、承諾せざるをえませんでした。
さて歩きはじめて小一時間ほど経った頃、どこまでも水平だった氷の大地に、人の住まいらしき雪の建築群が見えてきました。それらはエレンが雪の日に作るかまくらの親玉みたいなものの集合体でしたが、遊びで作るのとは違う、現役の生活拠点としてのリアリティがあります。林立しているかまくらのそれぞれには、押し固めた雪のブロックをきっちり積み上げた大小二つのドームと、それらをつなぐ通路がついているのです。
エレンたちは、氷の家の中でもあまり大きくないものの一つを訪ねました。あまり大きい家だと大きい人が住んでいたり、家族がいっぱいいるような気がしたのです。入り口から声をかけてしばらくすると、この家の主婦らしき女の人が顔を出しました。ライオンのたてがみのようなフードのついた、ゆったりとした美しい毛皮の服を着ていて、黒いまっすぐな髪をおさげにしています。
「あら。あまり見かけない顔ね。行商かしら」
「母ちゃん、どうしたの」
珍しいお客に、やんちゃそうな少年がひょっこり顔を出しました。しかしアルベルトの顔を見た途端、少年はわーっと叫んで、お母さんの後ろに隠れました。
「早くこいつを追い返して。きっと僕にひどいことをしにきたんだ」
「まさか! そんなことしません」
「僕たちはただ聞きたいことがあって来たんです」
エレンとリンは必死に執り成しました。しかし母親は息子を庇いながら、一同を睨みつけるばかり。するとそこへ少年の妹らしき女の子が走ってきました。
「わぁ、やっぱり! 父ちゃん、ヌッカの父ちゃんだよ」
娘の呼びかけで現れたのは、この家の主らしき、がっちりとした男。厳しい冬を耐えてきた勇ましい顔つきで、深い皺のある顔はよく日に焼けています。エレンはスキーのとき、雪に反射する日光で日焼けしたことを思い出しました。
「父ちゃん、こいつらをやっつけて」
心強い味方を手に入れた男の子は、俄然空いばりをはじめました。しかしお父さんは突如息子にげんこつを食らわせました。
「アドゥラルトク! 父ちゃんが何も知らないと思ったら大間違いだぞ。話はイクニクから聞いているんだ」
男の子は涙を浮かべると、奥に走り去りました。
「キラルラク。一体何があったの」
お母さんは、夫と息子の行った方を交互に見ました。するとキラルラクと呼ばれた男の人は腕組みをしました。
「あんな奴、放っておけ。あいつは弱いものいじめをする卑怯者だ」
男の人はそう言うと、突然アルベルトの手をとりました。
「お客人、息子がご子息に失礼をいたしました。お許し下さい」
アルベルトはびっくりして目をぱちくりさせました。
この家の主人・キラルラクの勧めで、三人は母屋にお邪魔することになりました。そこは雪の家に毛皮を敷いたシンプルな部屋でしたが、外とは比べものにならないほど温かく、驚いたことに火まで焚かれていました。
三人が席に着くと、女の子は嬉しそうに飛び跳ねました。先にきて、泣きべそをかいていた男の子はまだ仏頂面をしていましたが(彼は三人が入ってきたのを見て逃げようとしたのですが、お父さんに首根っこを掴まれ、仕方なく留まっているのです)。
「ね、父ちゃん。ヌッカにそっくりでしょう。毛がもじゃもじゃなの」
どうやら女の子は、ゾフィのことをアルベルトの子どもだと思っているようでした。キラルラクは娘の頬を両手で挟むと、その額に自分の額を寄せて、本当だね、イクニクと言いました。
「ご子息は実は私が拾ったのです。雪の中ひとりでおりましたので。しかし差し出がましいことでした」
相手が謝っているのに、アルベルトがむっつり黙っているので、エレンとリンはとんでもないと言いました。しかしアルベルトが突然、あの子は女の子ですと言ったので、氷の民は、これは失敬と謝ることになりました。
「あの、もし違ったら失礼なんですけど、光る玉を知りませんか。星みたいな」
エレンはランプ星がどんな姿をしているのか分からなかったので、曖昧な聞き方をしました。しかしキラルラクとその妻は顔を見合わせました。
「私たちは知らないし、たぶんほかのみんなも知らないだろうね。私たちはだれが何を手に入れたか教え合うから」
キラルラクが娘を膝に乗せながらこう言ったので、一同は嬉しいような、がっかりしたような、変な気持ちになりました。この人たちが盗人でなかったのはもちろん喜ばしいことですが、ランプ星がいまだ行方不明なのは気がかりです。
「それが見つからないとなにか困るの」
温かい飲み物を注ぎ足しながら、奥さんは聞きました。
「極夜が迫っているのはご存知かと思いますが、極夜のあいだ空を照らす星が何者かによって盗まれたのです。闇に生きる太古のものたちが来る前に、僕たちはそれを取り返したいと思っていまして」
リンがこう言うと、キラルラクは一笑しました。
「南の方の人たちは、そんなことをおそれているのか。大丈夫。太古のものたちはそっとしておけば悪さはしない。なにせ私たち氷の民は、彼らを『遠い友達』と呼ぶくらいだから」
三人が理解できずにいると、小さいイクニクが、『遠い友達』とは、交流できなくてもずっと心がつながっている相手のことだ、と教えてくれました。
「そう、そう。だからあんな星はなくたっていいんだ。実際私はあれがなくなってよかったと思っているよ。あれがあると本当の闇を感じられないからね」
奥さんがこう言ったので、エレンは危うくカップを倒しそうになりました。
「しかし動物たちの中には、彼らを恐れて南下したものもいるんです。トナカイたちは、早く逃げた方がいいと僕たちに言いました」
エレンがこう言うと、キラルラクは腕組みをしました。
「太古のものたちが危険でないことを、動物たちはよぉく知っているはずだ。それなのにどうして」
そう言ったきり、この家の長が黙りこくってしまったので、気のまわる奥さんは、今日は泊まっていくかい、とエレンたちに聞いてくれました。しかしリンは首を横に振りました。
「残してきた仲間がいるんです。そろそろ心細くなっている頃でしょうから、もうお暇します。ところでつかぬことをお尋ねしますが、石炭か薪を少し分けていただけないでしょうか」
しかしキラルラクも奥さんも非常に申し訳なさそうに、それはできませんと言いました。元々限りある燃料を、彼らは長い冬を越せるよう、計画的に使っているのです。他人に分けてあげる余裕はありません。
エレンたちは途方に暮れました。太陽も出ず、燃料も調達できないとなると、いよいよ飛行船を動かすことはできません。しかももっと悪ければ、冷えきった飛行船の中で全員凍死するか、あるいは太古のものたちの犠牲になってしまうかもしれません。氷の民は何もしなければ大丈夫だと言っていますが。
「燃料は分けてあげられないけれど、冬の間ここにいてもいいのよ」
意気消沈するエレンたちを、奥さんはなんとか勇気づけようとしました。
「お気持ちはありがたいですが、人を探しているんです。行き倒れになる前に見つけてやらないと」
「そんなら犬ぞりを使えばいい。あいつらならかなりのスピードが出るし、燃料もいらない。食べ物を少しはやらなきゃいけないけど」
男の子がぼそっとこう言うと、キラルラクは息子の頭をぽんと叩きました。
「そいつは名案だ! すぐに用意しよう!」
そりの前で待っていた三人は、少年が連れてきた犬を見て、肝を冷やしました。氷の民の犬は、まるでオオカミのように目つきが鋭く、尖った歯を持っていたからです。エレンはアルベルトが当然こわがるだろうと思いました。しかしアルベルトはこわがるどころか、すぐにしっぽを振る犬たちに取り囲まれ、何頭かは彼の顔をしつこく舐め回しています。それを見てリンは、この人は人間より動物の方が、気が楽なのかもしれないなと言いました。
ご夫婦の厚意で、エレンがそりにお土産を積んでいると、両手に収まるくらいの箱を持ったリンが、息を弾ませて戻ってきました。エレンがそれは何かと尋ねると、リンは少し気まずそうに鶏だと答えました。
「貴重な食べ物をもらっちゃったの!」
エレンが非難すると、リンは言い訳しました。
「向こうが持って行けって言ったんだ。食べ物なら漁に出れば手に入るからって。ほら、アザラシを食べるってアルベルトも言っていただろ。それにこれは雄鶏だからたまごを産むわけでもない」
エレンはフォルトゥーナの予言に鶏があったことを思い出しましたが、なんだか腑に落ちません。
「代わりに何を渡したの」
エレンに問いつめられると、リンは目を白黒させましたが、やがて観念したように、ダイヤモンドをちょっと、と言いました。エレンは呆れました。やっぱりリンは自分のためなら手段を選ばない人間なのです。
「そんなことをしたら、自分の身を危険に晒すって分からない? キラルラクはいい人だったからいいけど、良からぬことを企む人だっているんだよ」
エレンとリンが言い争っていると、突然怯えるような男の悲鳴が上がりました。
駆けつけたエレンが飛び出す直前、リンは相棒を慌てて押しとどめました。というのも、そこにいたのが思わぬ人物だったのです。それは犬たちに吠えられて身を寄せ合っているアルフォンスとガストンでした。
「あいつら、こんなところまで追ってきたのか!」
氷の家の陰に身を隠していたエレンは唇を噛みました。ソール・ヌール・ヴァスト・アウストのパレードで見て以来、二人のことはすっかり忘れていました。しかし二人がいるということは、レネが近いということかもしれません。
「被害者ってのは、ときに加害者に転じるくらいエネルギッシュなものさ」
エレンは肩をすくめました。
「僕だって申し訳ないと思わないわけじゃない。でもあいつらは、レネのお腹を切るとか言うんだ」
「方法は検討した方がいいけど、出てきたら返してやれよ。いま助けるかは別にして」
リンが眉をくっと持ち上げたので、エレンは早くそりを出そうと耳打ちしました。
アルフォンスたちに気づかれないうちに出発しようと、犬たちをそりにつないでいると、犬たちが突然走り出しました。なので、そりに乗っていたエレンとリンは遮るものがない雪原で、ともするとアルフォンスたちから丸見えになりました。しかも、このまま走り去ってしまえばギリギリセーフだったのに、そりの犬たちは急に足が止めるどころか、アルフォンスたちを引き止めていた犬たちを呼び寄せました。
「あ! お前は! あの猫の!」
視界がよくなったアルフォンスとガストンは、足をもつれさせながらも、確実にこちらに向かって走ってきます。それなのに犬たちは、群れ合って遊んでいるばかり。おまけにエレンもリンも、犬の統制の仕方を知りません。
このままでは捕まってしまう! エレンの頭が真っ白になりかけたそのとき、犬たちの間から思いかけないことばが飛び出しました。
「アルフォンスに、ガストンじゃないか!」
アルフォンスとガストンは一瞬、何が起こったのか分からないようでした。しかし飛びついてくる犬を器用にあしらって、その間からアルベルトが顔を出すと、二人は口をあんぐり開けました。
「ぼ、坊ちゃん!」
氷の民に貰った分厚い毛皮を着て、エレンは北極の夜風になっていました。そりを曳くのは、神話の中から出てきたような美しいオオカミの子孫たちで、彼らはオーロラ舞う空のもと、南に向けてひた走ります。
エレンはそういえばオーロラを見に来たんだったなあと思って、隣のそりを見ました。キルステンとフラッフィの乗るそりを御すリンは、まだどこかおっかなびっくりですが、バスケットのような部分に座る二人は、頬を真っ赤にしてきゃっきゃと笑っています。
エレンは後方をついてくる、もう一台のそりに視線を移しました。こちらはバスケットに座るアルフォンスと立ち乗りのガストンのそりで、アルフォンスは氷の民がくれたお土産を広げています。中には氷の民のサングラスである、眼鏡型の木片に横長の切り込みを入れた遮光器が大量に入っていて、アルフォンスはふざけてガストンにかけさせようとしました。しかしガストンはまったく心の準備ができていなかったので、そりは大きく蛇行し、結局アルフォンスはガストンをどやすことになりました。
これはついさっき判明したことですが、実はアルフォンスとガストンは、アルベルトのお父さんの会社の社員でした。そしてその会社というのは、エレンがCMを何度も見た、あのクノックス商会でした。
マフィア風害虫駆除ヒーローでおなじみのクノックス商会の長男として生まれたアルベルトは、当然ファミリービジネスを継ぐものと思われていました。しかし優しくて動物を殺すことができないアルベルトを、ファミリーは後継者と認めず、アルベルトは次第に居場所をなくしました。そして思い詰めた彼は、ついにあるときランプ星を盗んだのです。
ちなみにアルフォンスの探しものも判明しました。それは映画の祭典・アカデミー賞で貰う、あのオスカー像でした。これもまた驚くべきことなのですが、アルフォンスはなんと一昔前に一世を風靡した俳優でした。彼はその渋い演技で、西部劇全盛期にオスカーを獲得したそうですが、その後、時代の流れに乗って性に合わないコミックヒーロー作品に出続けた結果、とうとう彼のもとにはオファーが一本も来なくなってしまいました。
いまはクノックス商会の駆除員として働くアルフォンスですが、いつか本業の俳優業で返り咲きたいと考えていて、熱烈な彼のファンで、マネージャーを兼ねているガストンと再起のチャンスを狙っています。しかしそんな矢先、挫けそうになったときの拠り所にしていたオスカー像をレネが食べてしまい、その信念が揺らいでいるのでした。しかしアルフォンスの才能に心底惚れているガストンは、なんとしてもオスカーを取り戻して、銀幕に復活してほしいのだ、とエレンに熱く語りました。
エレンは前に向き直す途中で、すぐ後ろで立ち乗りしているアルベルトを見上げました。アルベルトはすこぶる幸せそうで、エレンが目を細めるとひゃっほーと叫びました。するとエレンたちのそりを曳く犬たちはぐんと速度をあげ、アルベルトの胸元のゾフィはぴーぴー喜びました。しかしほかのそりも負けじとスピードを上げます。どんどん表情を変えるオーロラびように、三台のそりは抜いたり抜かれたりを繰り返すのでした。
さて歩きはじめて小一時間ほど経った頃、どこまでも水平だった氷の大地に、人の住まいらしき雪の建築群が見えてきました。それらはエレンが雪の日に作るかまくらの親玉みたいなものの集合体でしたが、遊びで作るのとは違う、現役の生活拠点としてのリアリティがあります。林立しているかまくらのそれぞれには、押し固めた雪のブロックをきっちり積み上げた大小二つのドームと、それらをつなぐ通路がついているのです。
エレンたちは、氷の家の中でもあまり大きくないものの一つを訪ねました。あまり大きい家だと大きい人が住んでいたり、家族がいっぱいいるような気がしたのです。入り口から声をかけてしばらくすると、この家の主婦らしき女の人が顔を出しました。ライオンのたてがみのようなフードのついた、ゆったりとした美しい毛皮の服を着ていて、黒いまっすぐな髪をおさげにしています。
「あら。あまり見かけない顔ね。行商かしら」
「母ちゃん、どうしたの」
珍しいお客に、やんちゃそうな少年がひょっこり顔を出しました。しかしアルベルトの顔を見た途端、少年はわーっと叫んで、お母さんの後ろに隠れました。
「早くこいつを追い返して。きっと僕にひどいことをしにきたんだ」
「まさか! そんなことしません」
「僕たちはただ聞きたいことがあって来たんです」
エレンとリンは必死に執り成しました。しかし母親は息子を庇いながら、一同を睨みつけるばかり。するとそこへ少年の妹らしき女の子が走ってきました。
「わぁ、やっぱり! 父ちゃん、ヌッカの父ちゃんだよ」
娘の呼びかけで現れたのは、この家の主らしき、がっちりとした男。厳しい冬を耐えてきた勇ましい顔つきで、深い皺のある顔はよく日に焼けています。エレンはスキーのとき、雪に反射する日光で日焼けしたことを思い出しました。
「父ちゃん、こいつらをやっつけて」
心強い味方を手に入れた男の子は、俄然空いばりをはじめました。しかしお父さんは突如息子にげんこつを食らわせました。
「アドゥラルトク! 父ちゃんが何も知らないと思ったら大間違いだぞ。話はイクニクから聞いているんだ」
男の子は涙を浮かべると、奥に走り去りました。
「キラルラク。一体何があったの」
お母さんは、夫と息子の行った方を交互に見ました。するとキラルラクと呼ばれた男の人は腕組みをしました。
「あんな奴、放っておけ。あいつは弱いものいじめをする卑怯者だ」
男の人はそう言うと、突然アルベルトの手をとりました。
「お客人、息子がご子息に失礼をいたしました。お許し下さい」
アルベルトはびっくりして目をぱちくりさせました。
この家の主人・キラルラクの勧めで、三人は母屋にお邪魔することになりました。そこは雪の家に毛皮を敷いたシンプルな部屋でしたが、外とは比べものにならないほど温かく、驚いたことに火まで焚かれていました。
三人が席に着くと、女の子は嬉しそうに飛び跳ねました。先にきて、泣きべそをかいていた男の子はまだ仏頂面をしていましたが(彼は三人が入ってきたのを見て逃げようとしたのですが、お父さんに首根っこを掴まれ、仕方なく留まっているのです)。
「ね、父ちゃん。ヌッカにそっくりでしょう。毛がもじゃもじゃなの」
どうやら女の子は、ゾフィのことをアルベルトの子どもだと思っているようでした。キラルラクは娘の頬を両手で挟むと、その額に自分の額を寄せて、本当だね、イクニクと言いました。
「ご子息は実は私が拾ったのです。雪の中ひとりでおりましたので。しかし差し出がましいことでした」
相手が謝っているのに、アルベルトがむっつり黙っているので、エレンとリンはとんでもないと言いました。しかしアルベルトが突然、あの子は女の子ですと言ったので、氷の民は、これは失敬と謝ることになりました。
「あの、もし違ったら失礼なんですけど、光る玉を知りませんか。星みたいな」
エレンはランプ星がどんな姿をしているのか分からなかったので、曖昧な聞き方をしました。しかしキラルラクとその妻は顔を見合わせました。
「私たちは知らないし、たぶんほかのみんなも知らないだろうね。私たちはだれが何を手に入れたか教え合うから」
キラルラクが娘を膝に乗せながらこう言ったので、一同は嬉しいような、がっかりしたような、変な気持ちになりました。この人たちが盗人でなかったのはもちろん喜ばしいことですが、ランプ星がいまだ行方不明なのは気がかりです。
「それが見つからないとなにか困るの」
温かい飲み物を注ぎ足しながら、奥さんは聞きました。
「極夜が迫っているのはご存知かと思いますが、極夜のあいだ空を照らす星が何者かによって盗まれたのです。闇に生きる太古のものたちが来る前に、僕たちはそれを取り返したいと思っていまして」
リンがこう言うと、キラルラクは一笑しました。
「南の方の人たちは、そんなことをおそれているのか。大丈夫。太古のものたちはそっとしておけば悪さはしない。なにせ私たち氷の民は、彼らを『遠い友達』と呼ぶくらいだから」
三人が理解できずにいると、小さいイクニクが、『遠い友達』とは、交流できなくてもずっと心がつながっている相手のことだ、と教えてくれました。
「そう、そう。だからあんな星はなくたっていいんだ。実際私はあれがなくなってよかったと思っているよ。あれがあると本当の闇を感じられないからね」
奥さんがこう言ったので、エレンは危うくカップを倒しそうになりました。
「しかし動物たちの中には、彼らを恐れて南下したものもいるんです。トナカイたちは、早く逃げた方がいいと僕たちに言いました」
エレンがこう言うと、キラルラクは腕組みをしました。
「太古のものたちが危険でないことを、動物たちはよぉく知っているはずだ。それなのにどうして」
そう言ったきり、この家の長が黙りこくってしまったので、気のまわる奥さんは、今日は泊まっていくかい、とエレンたちに聞いてくれました。しかしリンは首を横に振りました。
「残してきた仲間がいるんです。そろそろ心細くなっている頃でしょうから、もうお暇します。ところでつかぬことをお尋ねしますが、石炭か薪を少し分けていただけないでしょうか」
しかしキラルラクも奥さんも非常に申し訳なさそうに、それはできませんと言いました。元々限りある燃料を、彼らは長い冬を越せるよう、計画的に使っているのです。他人に分けてあげる余裕はありません。
エレンたちは途方に暮れました。太陽も出ず、燃料も調達できないとなると、いよいよ飛行船を動かすことはできません。しかももっと悪ければ、冷えきった飛行船の中で全員凍死するか、あるいは太古のものたちの犠牲になってしまうかもしれません。氷の民は何もしなければ大丈夫だと言っていますが。
「燃料は分けてあげられないけれど、冬の間ここにいてもいいのよ」
意気消沈するエレンたちを、奥さんはなんとか勇気づけようとしました。
「お気持ちはありがたいですが、人を探しているんです。行き倒れになる前に見つけてやらないと」
「そんなら犬ぞりを使えばいい。あいつらならかなりのスピードが出るし、燃料もいらない。食べ物を少しはやらなきゃいけないけど」
男の子がぼそっとこう言うと、キラルラクは息子の頭をぽんと叩きました。
「そいつは名案だ! すぐに用意しよう!」
そりの前で待っていた三人は、少年が連れてきた犬を見て、肝を冷やしました。氷の民の犬は、まるでオオカミのように目つきが鋭く、尖った歯を持っていたからです。エレンはアルベルトが当然こわがるだろうと思いました。しかしアルベルトはこわがるどころか、すぐにしっぽを振る犬たちに取り囲まれ、何頭かは彼の顔をしつこく舐め回しています。それを見てリンは、この人は人間より動物の方が、気が楽なのかもしれないなと言いました。
ご夫婦の厚意で、エレンがそりにお土産を積んでいると、両手に収まるくらいの箱を持ったリンが、息を弾ませて戻ってきました。エレンがそれは何かと尋ねると、リンは少し気まずそうに鶏だと答えました。
「貴重な食べ物をもらっちゃったの!」
エレンが非難すると、リンは言い訳しました。
「向こうが持って行けって言ったんだ。食べ物なら漁に出れば手に入るからって。ほら、アザラシを食べるってアルベルトも言っていただろ。それにこれは雄鶏だからたまごを産むわけでもない」
エレンはフォルトゥーナの予言に鶏があったことを思い出しましたが、なんだか腑に落ちません。
「代わりに何を渡したの」
エレンに問いつめられると、リンは目を白黒させましたが、やがて観念したように、ダイヤモンドをちょっと、と言いました。エレンは呆れました。やっぱりリンは自分のためなら手段を選ばない人間なのです。
「そんなことをしたら、自分の身を危険に晒すって分からない? キラルラクはいい人だったからいいけど、良からぬことを企む人だっているんだよ」
エレンとリンが言い争っていると、突然怯えるような男の悲鳴が上がりました。
駆けつけたエレンが飛び出す直前、リンは相棒を慌てて押しとどめました。というのも、そこにいたのが思わぬ人物だったのです。それは犬たちに吠えられて身を寄せ合っているアルフォンスとガストンでした。
「あいつら、こんなところまで追ってきたのか!」
氷の家の陰に身を隠していたエレンは唇を噛みました。ソール・ヌール・ヴァスト・アウストのパレードで見て以来、二人のことはすっかり忘れていました。しかし二人がいるということは、レネが近いということかもしれません。
「被害者ってのは、ときに加害者に転じるくらいエネルギッシュなものさ」
エレンは肩をすくめました。
「僕だって申し訳ないと思わないわけじゃない。でもあいつらは、レネのお腹を切るとか言うんだ」
「方法は検討した方がいいけど、出てきたら返してやれよ。いま助けるかは別にして」
リンが眉をくっと持ち上げたので、エレンは早くそりを出そうと耳打ちしました。
アルフォンスたちに気づかれないうちに出発しようと、犬たちをそりにつないでいると、犬たちが突然走り出しました。なので、そりに乗っていたエレンとリンは遮るものがない雪原で、ともするとアルフォンスたちから丸見えになりました。しかも、このまま走り去ってしまえばギリギリセーフだったのに、そりの犬たちは急に足が止めるどころか、アルフォンスたちを引き止めていた犬たちを呼び寄せました。
「あ! お前は! あの猫の!」
視界がよくなったアルフォンスとガストンは、足をもつれさせながらも、確実にこちらに向かって走ってきます。それなのに犬たちは、群れ合って遊んでいるばかり。おまけにエレンもリンも、犬の統制の仕方を知りません。
このままでは捕まってしまう! エレンの頭が真っ白になりかけたそのとき、犬たちの間から思いかけないことばが飛び出しました。
「アルフォンスに、ガストンじゃないか!」
アルフォンスとガストンは一瞬、何が起こったのか分からないようでした。しかし飛びついてくる犬を器用にあしらって、その間からアルベルトが顔を出すと、二人は口をあんぐり開けました。
「ぼ、坊ちゃん!」
氷の民に貰った分厚い毛皮を着て、エレンは北極の夜風になっていました。そりを曳くのは、神話の中から出てきたような美しいオオカミの子孫たちで、彼らはオーロラ舞う空のもと、南に向けてひた走ります。
エレンはそういえばオーロラを見に来たんだったなあと思って、隣のそりを見ました。キルステンとフラッフィの乗るそりを御すリンは、まだどこかおっかなびっくりですが、バスケットのような部分に座る二人は、頬を真っ赤にしてきゃっきゃと笑っています。
エレンは後方をついてくる、もう一台のそりに視線を移しました。こちらはバスケットに座るアルフォンスと立ち乗りのガストンのそりで、アルフォンスは氷の民がくれたお土産を広げています。中には氷の民のサングラスである、眼鏡型の木片に横長の切り込みを入れた遮光器が大量に入っていて、アルフォンスはふざけてガストンにかけさせようとしました。しかしガストンはまったく心の準備ができていなかったので、そりは大きく蛇行し、結局アルフォンスはガストンをどやすことになりました。
これはついさっき判明したことですが、実はアルフォンスとガストンは、アルベルトのお父さんの会社の社員でした。そしてその会社というのは、エレンがCMを何度も見た、あのクノックス商会でした。
マフィア風害虫駆除ヒーローでおなじみのクノックス商会の長男として生まれたアルベルトは、当然ファミリービジネスを継ぐものと思われていました。しかし優しくて動物を殺すことができないアルベルトを、ファミリーは後継者と認めず、アルベルトは次第に居場所をなくしました。そして思い詰めた彼は、ついにあるときランプ星を盗んだのです。
ちなみにアルフォンスの探しものも判明しました。それは映画の祭典・アカデミー賞で貰う、あのオスカー像でした。これもまた驚くべきことなのですが、アルフォンスはなんと一昔前に一世を風靡した俳優でした。彼はその渋い演技で、西部劇全盛期にオスカーを獲得したそうですが、その後、時代の流れに乗って性に合わないコミックヒーロー作品に出続けた結果、とうとう彼のもとにはオファーが一本も来なくなってしまいました。
いまはクノックス商会の駆除員として働くアルフォンスですが、いつか本業の俳優業で返り咲きたいと考えていて、熱烈な彼のファンで、マネージャーを兼ねているガストンと再起のチャンスを狙っています。しかしそんな矢先、挫けそうになったときの拠り所にしていたオスカー像をレネが食べてしまい、その信念が揺らいでいるのでした。しかしアルフォンスの才能に心底惚れているガストンは、なんとしてもオスカーを取り戻して、銀幕に復活してほしいのだ、とエレンに熱く語りました。
エレンは前に向き直す途中で、すぐ後ろで立ち乗りしているアルベルトを見上げました。アルベルトはすこぶる幸せそうで、エレンが目を細めるとひゃっほーと叫びました。するとエレンたちのそりを曳く犬たちはぐんと速度をあげ、アルベルトの胸元のゾフィはぴーぴー喜びました。しかしほかのそりも負けじとスピードを上げます。どんどん表情を変えるオーロラびように、三台のそりは抜いたり抜かれたりを繰り返すのでした。
0
あなたにおすすめの小説

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

笑いの授業
ひろみ透夏
児童書・童話
大好きだった先先が別人のように変わってしまった。
文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。
それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。
伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。
追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。

かつて聖女は悪女と呼ばれていた
朔雲みう (さくもみう)
児童書・童話
「別に計算していたわけではないのよ」
この聖女、悪女よりもタチが悪い!?
悪魔の力で聖女に成り代わった悪女は、思い知ることになる。聖女がいかに優秀であったのかを――!!
聖女が華麗にざまぁします♪
※ エブリスタさんの妄コン『変身』にて、大賞をいただきました……!!✨
※ 悪女視点と聖女視点があります。
※ 表紙絵は親友の朝美智晴さまに描いていただきました♪


生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

あだ名が242個ある男(実はこれ実話なんですよ25)
tomoharu
児童書・童話
え?こんな話絶対ありえない!作り話でしょと思うような話からあるある話まで幅広い範囲で物語を考えました!ぜひ読んでみてください!数年後には大ヒット間違いなし!!
作品情報【伝説の物語(都道府県問題)】【伝説の話題(あだ名とコミュニケーションアプリ)】【マーライオン】【愛学両道】【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】【トモレオ突破椿】など
・【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】とは、その話はさすがに言いすぎでしょと言われているほぼ実話ストーリーです。
小さい頃から今まで主人公である【紘】はどのような体験をしたのかがわかります。ぜひよんでくださいね!
・【トモレオ突破椿】は、公務員試験合格なおかつ様々な問題を解決させる話です。
頭の悪かった人でも公務員になれることを証明させる話でもあるので、ぜひ読んでみてください!
特別記念として実話を元に作った【呪われし◯◯シリーズ】も公開します!
トランプ男と呼ばれている切札勝が、トランプゲームに例えて次々と問題を解決していく【トランプ男】シリーズも大人気!
人気者になるために、ウソばかりついて周りの人を誘導し、すべて自分のものにしようとするウソヒコをガチヒコが止める【嘘つきは、嘘治の始まり】というホラーサスペンスミステリー小説

王女様は美しくわらいました
トネリコ
児童書・童話
無様であろうと出来る全てはやったと満足を抱き、王女様は美しくわらいました。
それはそれは美しい笑みでした。
「お前程の悪女はおるまいよ」
王子様は最後まで嘲笑う悪女を一刀で断罪しました。
きたいの悪女は処刑されました 解説版
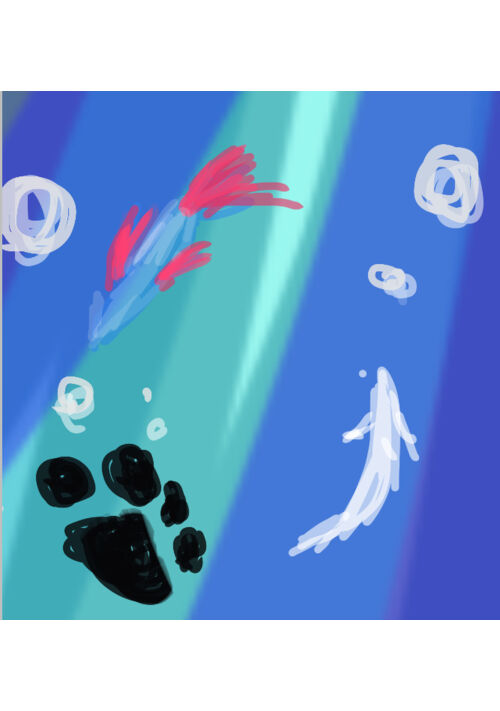
25匹の魚と猫と
ねこ沢ふたよ
児童書・童話
コメディです。
短編です。
暴虐無人の猫に一泡吹かせようと、水槽のメダカとグッピーが考えます。
何も考えずに笑って下さい
※クラムボンは笑いません
25周年おめでとうございます。
Copyright©︎
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















