17 / 43
二.喋らない猫と最後の夏
17.最後の夏
しおりを挟む
「ふふ。なんだかいい雰囲気じゃないか。ボクの事なんてすっかり忘れてしまっているようだね」
不意に声が響く。足下でミーシャがたたずんでいた。
「わわわっ。ミーシャの事忘れてなんてないよ」
「いや、良いんだよ。ボクの事なんて気にしなくて。所詮ボクはただの猫だからね。人の恋路を邪魔する事しか出来ない、しがない猫の輩なんだからさ」
「もう。すねないでよ、ミーシャ」
「すねてはないよ。それなら君のそのメガネの方がよっぽど素直じゃないさ」
「いいじゃない。眼鏡可愛いよ」
ありすはいいながら縁の太いメガネを指先であげてみせる。
「メガネが素直じゃないって、どういうこと?」
ふと疑問に思ったことをそのまま口に出していた。
「そりゃあ有子のメガネは」
「わーっわーーーっわーーーっ。だめっ。いっちゃだめなの。えっと、眼鏡は目が悪いからかけているんですぅ。そして有子って言わないでっ。ありす、ありすって呼んでよぅ」
ミーシャの言葉を慌てて大きな声で止めると、明らかにごまかしの言葉を漏らす。
「はいはい。ありすね」
何度となく繰り返してきたやりとりに、どこか微笑ましくて思わず口角を上げてしまう。
今の反応で何となくメガネの秘密は分かってしまった。
「もしかしてそれ、度が入ってないの?」
「そ、そんなことはないですよー」
顔をそっぽむけていたが、はっきりと目が泳いでいる。
やっぱりありすのメガネは伊達だったらしい。
ありすは麦わら帽子のつばをもって顔を隠すように下げる。どこか顔が赤らんでいるのが、少しだけ見てとれていた。
確かに考えてみると夜に僕のところにきた時はメガネをしていなかった。あまり気にしていなかったけれど、実際に目が悪くないのであればメガネを外していても気にはならないのだろう。
「なんで伊達メガネなんて」
「だ、だてじゃないですよー。目が悪いんですぅ」
そのままぷいっと背を向けてしまう。
あんまりつっこんでほしくないところらしい。
「そっか。目が悪いんなら、仕方ないね」
僕の言葉にほっとしたのか、ありすはあからさまに大きく息を吐きだしていた。
「そう。そうなんです。目が悪いんです。あはは」
「あ、有子ちゃん。こんなところにいたの。春渡しの件で話をしたいって、太郞さんがいってたよ」
不意にかけられた声に僕とありすの二人が目をやる。
土手の向こう側にあかねの姿が見えた。
黒いシースルーのロングスカートの上に、トップスも少し袖が透けたようなシャツを合わせていた。やや大人っぽい感じのスタイルが、あかねにはよく似合っている。
「あれー。今朝でお話終わったと思っていたのに。でも、あかねちゃんありがとー。行ってみるね。謙人さん、そういう訳なのでまたあとでー」
ありすは言いながら慌てて土手を降りていく。
そのまま麦わら帽子がとてとてと村に向かっていくのがわかる。
僕はしばらくの間、その様子を見つめていた。
「有子ちゃんとの逢い引きの邪魔しちゃってごめんね」
あかねがいじわるな笑みを浮かべてくる。
「いや、別にそういうんじゃないんで」
「ふふ。でもよかった。仲良くやっているみたいで。これなら今年の春渡しも無事に終わるわね」
あかねはにこやかな笑顔を僕に向けてくる。
「まぁ僕はいまだに何をやるんだかよくわかってないんですけどね」
「ふふ。まぁ謙人くんは特にこれといってやることはないかな。有子ちゃんと一緒に過ごすだけだよ。有子ちゃんはいろいろやることがあるけどね」
意地悪な笑みを浮かべながら、ゆっくりと告げる。
「それともお姉さんと予行演習しておく?」
あかねはぐっと顔を近づけてくる。
ち、近い。この村の人はどうしてこんなに近づいてくるかな。
「いやっ。遠慮しておきますっ」
慌てて距離をとると、あかねはその場で笑っていた。
たぶん彼女らは僕をからかって遊んでいるんだと思う。この村には他に男の子がいないらしいから、珍しくて面白いのだろう。
「そ、そんなことよりですねっ」
慌てて話題を変える。この話を続けていてもろくな事にはならなそうだ。
「最後の夏って、どういう事なんですか。あかねさんだけじゃなくて、こずえやかなたちゃんも同じような事を言っていたんです」
「そうなの。やっぱりみんな思う事は同じなのね」
あかねは少し寂しげな瞳を覗かせながらつぶやく。
それでも僕の方へと視線を向けてゆっくりと微笑んでいた。
「最後の夏は、そのままの意味だよ。私たちにとって多分この夏が最後なの。はっきりとはわからないけど、そうなるんだろうなって感じているの」
あかねの声は少し憂いを残した寂しいとも悲しいともつかない言葉だった。
「最後の夏って、この村がダムの下に沈むとか?」
「ふふ。ダムには沈まないかな。村はまだ残っていると思うよ」
「みんな引っ越しするとか?」
「そうね。少し近いけど、ちょっと違うかな」
「実はみんな人工的に遺伝子操作された戦闘兵で、特殊な力がある代わりに反動で特定の年になったら死んでしまうとか」
「ぷっ。なにそれ」
あかねが唐突に吹き出していた。さすがにちょっと突拍子も無かったかもしれない。
「昔読んだ小説の話です」
「そうなんだ。謙人くんは小説とか読むんだね。旅人だから本なんて読まないかと思ってた」
あかねはなんだか楽しそうに笑うと、でも急に僕に背を向けていた。
「でもそれが一番近いかもね」
「え!?」
告げた声は普通の、特に何も感情も含まれていないようにも思えた。
背を向けているから表情は見て取れない。だからあかねが本気なのか、冗談を告げているのかもわからなかった。
あかねは空を見上げていた。
夏空はどこまでも広がっていて、大きな雲が僕達を見つめている。
ちょうど空の上を飛行機が通り過ぎていた。飛行機雲が現れては消えていく。
これが一番近い。まさか本当に遺伝子強化兵という訳ではないだろうから、それが近いというのはどういう意味なのだろう。
僕は思わず考え込む。
と、思案を重ねようとしていたところに。
「なーんてね」
あかねはそのままもういちど振り返り、僕の鼻先に伸ばした指を当てた。
「わっ。な、なにをするんですかっ」
「ふふ。四月一日くんは、可愛いなぁ。すごく反応が新鮮で」
「これ、ありすもやってきました。村で流行っているんですか?」
「ああ。有子ちゃんはきっと私の真似してるのね。これ私の癖なの」
のばした指先をそのまま自分の口元にあてる。
「だって反応が面白いんだもの」
そしてそのままその指を僕の口元へと伸ばす。
「わーーーっ。や、やめてくださいよっ。もう」
慌ててその指を避ける。
「あらー。逃げられちゃった。残念」
さほど残念そうでもない口調で告げると、あかねは僕へといつもの少しいじわるな瞳を向けてきていた。もう何事もなかったかのように、ごく普通のあかねだった。
「……それで、さすがに冗談ですよね」
「ふふっ。そうね」
あかねはくすくすと笑みを漏らしながら、そして再び空を見上げていた。
なんだかはぐらかされてしまったようだけれど、最後の夏という響きだけが、僕の中に残っていた。
不意に声が響く。足下でミーシャがたたずんでいた。
「わわわっ。ミーシャの事忘れてなんてないよ」
「いや、良いんだよ。ボクの事なんて気にしなくて。所詮ボクはただの猫だからね。人の恋路を邪魔する事しか出来ない、しがない猫の輩なんだからさ」
「もう。すねないでよ、ミーシャ」
「すねてはないよ。それなら君のそのメガネの方がよっぽど素直じゃないさ」
「いいじゃない。眼鏡可愛いよ」
ありすはいいながら縁の太いメガネを指先であげてみせる。
「メガネが素直じゃないって、どういうこと?」
ふと疑問に思ったことをそのまま口に出していた。
「そりゃあ有子のメガネは」
「わーっわーーーっわーーーっ。だめっ。いっちゃだめなの。えっと、眼鏡は目が悪いからかけているんですぅ。そして有子って言わないでっ。ありす、ありすって呼んでよぅ」
ミーシャの言葉を慌てて大きな声で止めると、明らかにごまかしの言葉を漏らす。
「はいはい。ありすね」
何度となく繰り返してきたやりとりに、どこか微笑ましくて思わず口角を上げてしまう。
今の反応で何となくメガネの秘密は分かってしまった。
「もしかしてそれ、度が入ってないの?」
「そ、そんなことはないですよー」
顔をそっぽむけていたが、はっきりと目が泳いでいる。
やっぱりありすのメガネは伊達だったらしい。
ありすは麦わら帽子のつばをもって顔を隠すように下げる。どこか顔が赤らんでいるのが、少しだけ見てとれていた。
確かに考えてみると夜に僕のところにきた時はメガネをしていなかった。あまり気にしていなかったけれど、実際に目が悪くないのであればメガネを外していても気にはならないのだろう。
「なんで伊達メガネなんて」
「だ、だてじゃないですよー。目が悪いんですぅ」
そのままぷいっと背を向けてしまう。
あんまりつっこんでほしくないところらしい。
「そっか。目が悪いんなら、仕方ないね」
僕の言葉にほっとしたのか、ありすはあからさまに大きく息を吐きだしていた。
「そう。そうなんです。目が悪いんです。あはは」
「あ、有子ちゃん。こんなところにいたの。春渡しの件で話をしたいって、太郞さんがいってたよ」
不意にかけられた声に僕とありすの二人が目をやる。
土手の向こう側にあかねの姿が見えた。
黒いシースルーのロングスカートの上に、トップスも少し袖が透けたようなシャツを合わせていた。やや大人っぽい感じのスタイルが、あかねにはよく似合っている。
「あれー。今朝でお話終わったと思っていたのに。でも、あかねちゃんありがとー。行ってみるね。謙人さん、そういう訳なのでまたあとでー」
ありすは言いながら慌てて土手を降りていく。
そのまま麦わら帽子がとてとてと村に向かっていくのがわかる。
僕はしばらくの間、その様子を見つめていた。
「有子ちゃんとの逢い引きの邪魔しちゃってごめんね」
あかねがいじわるな笑みを浮かべてくる。
「いや、別にそういうんじゃないんで」
「ふふ。でもよかった。仲良くやっているみたいで。これなら今年の春渡しも無事に終わるわね」
あかねはにこやかな笑顔を僕に向けてくる。
「まぁ僕はいまだに何をやるんだかよくわかってないんですけどね」
「ふふ。まぁ謙人くんは特にこれといってやることはないかな。有子ちゃんと一緒に過ごすだけだよ。有子ちゃんはいろいろやることがあるけどね」
意地悪な笑みを浮かべながら、ゆっくりと告げる。
「それともお姉さんと予行演習しておく?」
あかねはぐっと顔を近づけてくる。
ち、近い。この村の人はどうしてこんなに近づいてくるかな。
「いやっ。遠慮しておきますっ」
慌てて距離をとると、あかねはその場で笑っていた。
たぶん彼女らは僕をからかって遊んでいるんだと思う。この村には他に男の子がいないらしいから、珍しくて面白いのだろう。
「そ、そんなことよりですねっ」
慌てて話題を変える。この話を続けていてもろくな事にはならなそうだ。
「最後の夏って、どういう事なんですか。あかねさんだけじゃなくて、こずえやかなたちゃんも同じような事を言っていたんです」
「そうなの。やっぱりみんな思う事は同じなのね」
あかねは少し寂しげな瞳を覗かせながらつぶやく。
それでも僕の方へと視線を向けてゆっくりと微笑んでいた。
「最後の夏は、そのままの意味だよ。私たちにとって多分この夏が最後なの。はっきりとはわからないけど、そうなるんだろうなって感じているの」
あかねの声は少し憂いを残した寂しいとも悲しいともつかない言葉だった。
「最後の夏って、この村がダムの下に沈むとか?」
「ふふ。ダムには沈まないかな。村はまだ残っていると思うよ」
「みんな引っ越しするとか?」
「そうね。少し近いけど、ちょっと違うかな」
「実はみんな人工的に遺伝子操作された戦闘兵で、特殊な力がある代わりに反動で特定の年になったら死んでしまうとか」
「ぷっ。なにそれ」
あかねが唐突に吹き出していた。さすがにちょっと突拍子も無かったかもしれない。
「昔読んだ小説の話です」
「そうなんだ。謙人くんは小説とか読むんだね。旅人だから本なんて読まないかと思ってた」
あかねはなんだか楽しそうに笑うと、でも急に僕に背を向けていた。
「でもそれが一番近いかもね」
「え!?」
告げた声は普通の、特に何も感情も含まれていないようにも思えた。
背を向けているから表情は見て取れない。だからあかねが本気なのか、冗談を告げているのかもわからなかった。
あかねは空を見上げていた。
夏空はどこまでも広がっていて、大きな雲が僕達を見つめている。
ちょうど空の上を飛行機が通り過ぎていた。飛行機雲が現れては消えていく。
これが一番近い。まさか本当に遺伝子強化兵という訳ではないだろうから、それが近いというのはどういう意味なのだろう。
僕は思わず考え込む。
と、思案を重ねようとしていたところに。
「なーんてね」
あかねはそのままもういちど振り返り、僕の鼻先に伸ばした指を当てた。
「わっ。な、なにをするんですかっ」
「ふふ。四月一日くんは、可愛いなぁ。すごく反応が新鮮で」
「これ、ありすもやってきました。村で流行っているんですか?」
「ああ。有子ちゃんはきっと私の真似してるのね。これ私の癖なの」
のばした指先をそのまま自分の口元にあてる。
「だって反応が面白いんだもの」
そしてそのままその指を僕の口元へと伸ばす。
「わーーーっ。や、やめてくださいよっ。もう」
慌ててその指を避ける。
「あらー。逃げられちゃった。残念」
さほど残念そうでもない口調で告げると、あかねは僕へといつもの少しいじわるな瞳を向けてきていた。もう何事もなかったかのように、ごく普通のあかねだった。
「……それで、さすがに冗談ですよね」
「ふふっ。そうね」
あかねはくすくすと笑みを漏らしながら、そして再び空を見上げていた。
なんだかはぐらかされてしまったようだけれど、最後の夏という響きだけが、僕の中に残っていた。
0
あなたにおすすめの小説

美味しいコーヒーの愉しみ方 Acidity and Bitterness
碧井夢夏
ライト文芸
<第五回ライト文芸大賞 最終選考・奨励賞>
住宅街とオフィスビルが共存するとある下町にある定食屋「まなべ」。
看板娘の利津(りつ)は毎日忙しくお店を手伝っている。
最近隣にできたコーヒーショップ「The Coffee Stand Natsu」。
どうやら、店長は有名なクリエイティブ・ディレクターで、脱サラして始めたお店らしく……?
神の舌を持つ定食屋の娘×クリエイティブ界の神と呼ばれた男 2人の出会いはやがて下町を変えていく――?
定食屋とコーヒーショップ、時々美容室、を中心に繰り広げられる出会いと挫折の物語。
過激表現はありませんが、重めの過去が出ることがあります。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎 未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。
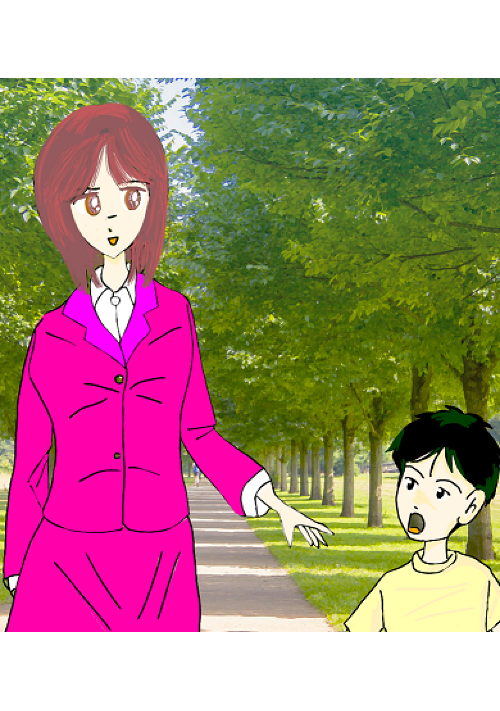
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……


むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム
ピコサイクス
青春
顔は普通、性格も地味。
けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。
学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?
大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。
真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















