4 / 4
大きな愛
しおりを挟む
僕は、空から伸びるそのテープを見て途方に暮れた。
「辿るって言っても、空から伸びてる。掴めるけど、これを登って行けるかな……」
そう呟きながらも、他にどうするべきなのかがわからず、なんとなくそれをぐいっと引っ張ってみる。すると、その反動で僕の体はテープと共にふわりと空へ持ち上げられてしまった。
「わあああああああ!」
僕は高いところが苦手なんだ。そもそも今回の怪我も、仕事で少しだけ高いところに行かなければならなくて、目をつぶってしまって落ちたのが原因だった。
今だって、飛び上がって雲の間を突き抜ける時、怖くて思わずぎゅっと目をつぶってしまっている。見えないけれど、空気を割いてどんどん進んでいく感覚が肌を走る。
それは、いつまでだって、どこまでだって続いていきそうなほどに長くて、瞼の内側に涙が溜まっていくのを止められなかった。
ぎゅっと強く閉じられているのに、ボロボロとこぼれ落ちてしまうほどに泣いてしまった。
「怖い! 止まってくれよ!」
それでも、その勢いは変わらなかった。
それからどれほど登って行ったのだろう。もう瞼を閉じておくことすら辛くなってき始めていた。
あまりに長く空を飛んだからか、恐怖にさえ少し慣れてしまったような気がした。
「どっ、どうしよう。 手が痺れてきた!」
でも、慣れたと思った途端に体に限界が来た。このまま手に力が入らなくなってしまって、地面に叩きつけられてしまったらどうしようかと、新たな恐怖で全身が震えた。
「あれ? スピードが落ちた気がする……え? 落ちる?」
怯え続けた僕は、その頃にはかなりのパニックを起こしていた。他にすがるものが無く、テープにしがみついてしまうほどには冷静さを失っていた。
すると、もっと酷いことが起きた。
パッとテープが消えて無くなってしまったのだ。
「わあああああ! テープが!」
慌てて目を開けると、いつの間にか高度が下がっていたようで、目の前に小さな島のようなものが浮いているのが見えた。
ただ、もう本当に着地寸前の状態で、僕は慌ててその島に降り立つ心構えをした。
「……っと、わ、わ、わ、とまれっ!」
数歩走って着地の勢いを消し、どうにか転ばずに立ち止まることができた。
「すごい、真っ白だ。なんだろう、これ……」
その島は、一面が真っ白なものに覆われていた。まるで雪が降り積もっているように見えるのだけれども、それ自体も冷たさを感じないし、そもそも全く寒く無かった。
真っ青な青空と雲海の中に浮かぶ、真っ白で不思議な場所だった。
その中心に、大きくて美しくて、銀色に輝く鐘があった。それは燦々と降り注ぐ太陽の光を反射して、眩くキラキラと輝いていた。
「わあ、綺麗だな」
僕はその鐘に触ってみたくなり、近づいてみた。そして、大きな白銀の鐘にそっと手を触れる。すると突然、カーンカーンと抜けるような明るい音が響き渡った。
鳴らしているわけでもないのに、ひとりでになり始めたことに違和感を感じることもなく、僕はただその音の美しさに耳を奪われていた。
「すごい。明るくて軽くて、なんだか心が躍る音がする」
僕は、その抜けるような美しい音をもっと耳で楽しみたくて、そっと目を閉じてみた。
カーン、カーン、カーン
乾いた空気の中を飛び交う鐘の音が、いつの間にか一つではなくなり、二つ三つと増えていった。
だんだんと音が入り乱れ、少しうるさいくらいに感じ始めた時、だんだんと鐘の音が小さく、遠くなっていくのを感じた。
僕はどうしたんだろうと思って、目を開けた。
カーン、カーン、カーン
白銀の鐘の前に、白い彼が立っていた。隣には、同じように白くて長い髪の毛の女の人が寄り添うように立っていた。
二人は仲睦まじく並んで歩き、微笑みあっている。その姿は、まるで結婚式に臨む新郎新婦の姿のようだ。
僕が白い彼と彼女を見ていると、ふと彼と目が合った。そして、彼は僕にゆっくりと近づいてくると、優しく微笑みながら僕をふわりと抱き上げてくれた。
『会いにきてくれて、ありがとう。幸せに生きていくんだよ』
そう言って、愛おしそうに僕を抱きしめると、また白い彼女の方へと戻って行った。
白い彼が彼女の隣に立ち、ひそひそと小さく言葉をかける。促されるように、彼女は僕を見つけた。そして、一筋の涙を流すと、その景色に溶けてしまいそうなほどの柔らかな笑顔をくれた。
カーン、カーン、カーン……。
また、音が小さくなっていった。
◇◇◇
「……く、ぼく、僕!」
鐘の音と、あいつが呼ぶ声が重なって聞こえた後、僕は白い天井を見上げた状態で目を覚ました。
「僕! 良かった、目が覚めて……」
僕の目の前には、あいつがいた。
「え……なんで……」
僕の目の前には、あいつがいた。ベッドに横たわる僕、白い天井、たくさんの機器……何度も見た光景だ。その度に希望を失って来た、とても嫌いな景色だった。
「僕……もしかして、危篤だった?」
僕が尋ねると、あいつはボロボロに泣き腫らした目とびしょびしょの顔を向けて、首がもげそうなくらいに頷いた。その手には、ボロボロになったテープが握られていた。
そこには、あの子が書いた願い事と同じことが書かれていた。
『かみさま、おねがいします。だいすきな『僕』と、しあわせになれますように……』
「これを書いた時、大人になった僕に会いたかったんだよな?」
僕が尋ねると、「どうして知ってるんだ?」とあいつは驚いて目を丸くした。長いまつ毛と、左目のほくろが見え隠れする瞼をシパシパと瞬かせて、大きな目が落ちそうなほどに驚いていた。
「父さんが……連れて行ってくれたよ。10歳のお前に会いに。あの頃の願いは叶ってるよ」
「父さん?」
あいつは、僕に家族がいないことを知っている。でも、生まれてきた以上、親はどこかにいるはずだ。そして、白い彼は僕の幸せを願って死んでいったのだろう。
彼も、大人になった僕に会いたかったから、幸せを願ったから、きっと自分でテープにそう書いたんだ。その願いが、僕を連れて行ってくれた。
父さんの願いと、あいつの願いを、神様がいっぺんに叶えてくれたんだろう。
「あ、じゃあこのテープはお父さんのものかな? どうしようかと思って、取っておいたんだ」
そう言って、あいつは僕の手に、一本のテープを渡してくれた。それは、もう黒くなっていて、ところどころ破けていて、銀色かどうかもわからなくなっていた。
『大人になった『僕』が道に迷う日が来たら、私が光となって導いてあげられますように』
「これ……」
やっぱりそうだった。あの白い彼と白い彼女は、僕の両親なんだ。真っ白なのは、きっと二人とも亡くなっているからなんだろう。それでも、僕の幸せを願ってくれていた。
だから、クリスマスの奇跡に願いをかけたんだろう。そう思ってテープをぎゅっと握りしめると、それは手の中でだんだん光の粒になって消えて行った。
「消えちゃった……消えたってことは、会えたってことだよね? 良かったね、僕」
そう言って、あいつは少し泣いてくれた。その優しさと、ずっと僕を必要としてくれていたということが嬉しくて、僕は思わず涙をこぼしてしまった。
——父さん、僕、ちゃんと生きていきます。
僕は、これからもずっとあいつと一緒にいる。そう決心してしまえば、胸の中には温かい気持ちで満たされていくのを感じた。それはそのまま体を満たし、溢れて流れ落ちていく。
「僕、大丈夫? どこか痛むの?」
あいつが銀色のテープを毎年結んでくれていなかったら、僕は今ここにいなかったんだろう。
「先生呼んでくるね」
僕は、そう言って立ち上がったあいつの手を掴んで、引き留めた。
「ん? どうかした?」
ずっと嫌いだった。
いつか誰かに、大切な人を奪われるかもしれないクリスマスが、大嫌いだった。
「ねえ、愛しているよ」
感謝と愛が溢れて、僕はあいつを抱きしめた。
「えっ?」
驚いて言葉を失っているあいつを、自分の方へと引き寄せた。
僕はただ抱きしめることしかできなくて、あいつは驚きすぎて反応が出来ずにいた。しばらくそうしていると、僕たちの目の前にゆらりと光の粒が舞い、白い彼と彼女が現れた。
『幸せになってね、僕。一緒にいてあげられなくて、ごめん。』
僕は、あいつを抱きしめる手に、ぎゅっと力を込めた。そして、彼と彼女に微笑んだ。
「ありがとう。心配しないでね。僕たちは大丈夫だよ」
僕のその言葉を聞いて、二人は顔を見合わせて微笑むと、そのまますうっと消えていった。
「僕」
あいつが、僕を呼んで抱きしめ返してきた。
「俺も、僕を愛しているよ。なあ、おじいちゃんになっても……」
「いいよ。一緒の墓に入ろうな」
僕がその先を知っていたから、あいつは驚いて、また大きな目を落としそうなほどしぱしぱと瞬かせていた。
◇◇◇
僕たちは、その年に結婚した。
あの、白銀の鐘のある教会を見つけて、そこで式を挙げた。
そして、それから毎年二人で銀色のテープを結んでいる。
一人ぼっちで寂しがっている誰かが、一人でも多く幸せになれることを願って。
「辿るって言っても、空から伸びてる。掴めるけど、これを登って行けるかな……」
そう呟きながらも、他にどうするべきなのかがわからず、なんとなくそれをぐいっと引っ張ってみる。すると、その反動で僕の体はテープと共にふわりと空へ持ち上げられてしまった。
「わあああああああ!」
僕は高いところが苦手なんだ。そもそも今回の怪我も、仕事で少しだけ高いところに行かなければならなくて、目をつぶってしまって落ちたのが原因だった。
今だって、飛び上がって雲の間を突き抜ける時、怖くて思わずぎゅっと目をつぶってしまっている。見えないけれど、空気を割いてどんどん進んでいく感覚が肌を走る。
それは、いつまでだって、どこまでだって続いていきそうなほどに長くて、瞼の内側に涙が溜まっていくのを止められなかった。
ぎゅっと強く閉じられているのに、ボロボロとこぼれ落ちてしまうほどに泣いてしまった。
「怖い! 止まってくれよ!」
それでも、その勢いは変わらなかった。
それからどれほど登って行ったのだろう。もう瞼を閉じておくことすら辛くなってき始めていた。
あまりに長く空を飛んだからか、恐怖にさえ少し慣れてしまったような気がした。
「どっ、どうしよう。 手が痺れてきた!」
でも、慣れたと思った途端に体に限界が来た。このまま手に力が入らなくなってしまって、地面に叩きつけられてしまったらどうしようかと、新たな恐怖で全身が震えた。
「あれ? スピードが落ちた気がする……え? 落ちる?」
怯え続けた僕は、その頃にはかなりのパニックを起こしていた。他にすがるものが無く、テープにしがみついてしまうほどには冷静さを失っていた。
すると、もっと酷いことが起きた。
パッとテープが消えて無くなってしまったのだ。
「わあああああ! テープが!」
慌てて目を開けると、いつの間にか高度が下がっていたようで、目の前に小さな島のようなものが浮いているのが見えた。
ただ、もう本当に着地寸前の状態で、僕は慌ててその島に降り立つ心構えをした。
「……っと、わ、わ、わ、とまれっ!」
数歩走って着地の勢いを消し、どうにか転ばずに立ち止まることができた。
「すごい、真っ白だ。なんだろう、これ……」
その島は、一面が真っ白なものに覆われていた。まるで雪が降り積もっているように見えるのだけれども、それ自体も冷たさを感じないし、そもそも全く寒く無かった。
真っ青な青空と雲海の中に浮かぶ、真っ白で不思議な場所だった。
その中心に、大きくて美しくて、銀色に輝く鐘があった。それは燦々と降り注ぐ太陽の光を反射して、眩くキラキラと輝いていた。
「わあ、綺麗だな」
僕はその鐘に触ってみたくなり、近づいてみた。そして、大きな白銀の鐘にそっと手を触れる。すると突然、カーンカーンと抜けるような明るい音が響き渡った。
鳴らしているわけでもないのに、ひとりでになり始めたことに違和感を感じることもなく、僕はただその音の美しさに耳を奪われていた。
「すごい。明るくて軽くて、なんだか心が躍る音がする」
僕は、その抜けるような美しい音をもっと耳で楽しみたくて、そっと目を閉じてみた。
カーン、カーン、カーン
乾いた空気の中を飛び交う鐘の音が、いつの間にか一つではなくなり、二つ三つと増えていった。
だんだんと音が入り乱れ、少しうるさいくらいに感じ始めた時、だんだんと鐘の音が小さく、遠くなっていくのを感じた。
僕はどうしたんだろうと思って、目を開けた。
カーン、カーン、カーン
白銀の鐘の前に、白い彼が立っていた。隣には、同じように白くて長い髪の毛の女の人が寄り添うように立っていた。
二人は仲睦まじく並んで歩き、微笑みあっている。その姿は、まるで結婚式に臨む新郎新婦の姿のようだ。
僕が白い彼と彼女を見ていると、ふと彼と目が合った。そして、彼は僕にゆっくりと近づいてくると、優しく微笑みながら僕をふわりと抱き上げてくれた。
『会いにきてくれて、ありがとう。幸せに生きていくんだよ』
そう言って、愛おしそうに僕を抱きしめると、また白い彼女の方へと戻って行った。
白い彼が彼女の隣に立ち、ひそひそと小さく言葉をかける。促されるように、彼女は僕を見つけた。そして、一筋の涙を流すと、その景色に溶けてしまいそうなほどの柔らかな笑顔をくれた。
カーン、カーン、カーン……。
また、音が小さくなっていった。
◇◇◇
「……く、ぼく、僕!」
鐘の音と、あいつが呼ぶ声が重なって聞こえた後、僕は白い天井を見上げた状態で目を覚ました。
「僕! 良かった、目が覚めて……」
僕の目の前には、あいつがいた。
「え……なんで……」
僕の目の前には、あいつがいた。ベッドに横たわる僕、白い天井、たくさんの機器……何度も見た光景だ。その度に希望を失って来た、とても嫌いな景色だった。
「僕……もしかして、危篤だった?」
僕が尋ねると、あいつはボロボロに泣き腫らした目とびしょびしょの顔を向けて、首がもげそうなくらいに頷いた。その手には、ボロボロになったテープが握られていた。
そこには、あの子が書いた願い事と同じことが書かれていた。
『かみさま、おねがいします。だいすきな『僕』と、しあわせになれますように……』
「これを書いた時、大人になった僕に会いたかったんだよな?」
僕が尋ねると、「どうして知ってるんだ?」とあいつは驚いて目を丸くした。長いまつ毛と、左目のほくろが見え隠れする瞼をシパシパと瞬かせて、大きな目が落ちそうなほどに驚いていた。
「父さんが……連れて行ってくれたよ。10歳のお前に会いに。あの頃の願いは叶ってるよ」
「父さん?」
あいつは、僕に家族がいないことを知っている。でも、生まれてきた以上、親はどこかにいるはずだ。そして、白い彼は僕の幸せを願って死んでいったのだろう。
彼も、大人になった僕に会いたかったから、幸せを願ったから、きっと自分でテープにそう書いたんだ。その願いが、僕を連れて行ってくれた。
父さんの願いと、あいつの願いを、神様がいっぺんに叶えてくれたんだろう。
「あ、じゃあこのテープはお父さんのものかな? どうしようかと思って、取っておいたんだ」
そう言って、あいつは僕の手に、一本のテープを渡してくれた。それは、もう黒くなっていて、ところどころ破けていて、銀色かどうかもわからなくなっていた。
『大人になった『僕』が道に迷う日が来たら、私が光となって導いてあげられますように』
「これ……」
やっぱりそうだった。あの白い彼と白い彼女は、僕の両親なんだ。真っ白なのは、きっと二人とも亡くなっているからなんだろう。それでも、僕の幸せを願ってくれていた。
だから、クリスマスの奇跡に願いをかけたんだろう。そう思ってテープをぎゅっと握りしめると、それは手の中でだんだん光の粒になって消えて行った。
「消えちゃった……消えたってことは、会えたってことだよね? 良かったね、僕」
そう言って、あいつは少し泣いてくれた。その優しさと、ずっと僕を必要としてくれていたということが嬉しくて、僕は思わず涙をこぼしてしまった。
——父さん、僕、ちゃんと生きていきます。
僕は、これからもずっとあいつと一緒にいる。そう決心してしまえば、胸の中には温かい気持ちで満たされていくのを感じた。それはそのまま体を満たし、溢れて流れ落ちていく。
「僕、大丈夫? どこか痛むの?」
あいつが銀色のテープを毎年結んでくれていなかったら、僕は今ここにいなかったんだろう。
「先生呼んでくるね」
僕は、そう言って立ち上がったあいつの手を掴んで、引き留めた。
「ん? どうかした?」
ずっと嫌いだった。
いつか誰かに、大切な人を奪われるかもしれないクリスマスが、大嫌いだった。
「ねえ、愛しているよ」
感謝と愛が溢れて、僕はあいつを抱きしめた。
「えっ?」
驚いて言葉を失っているあいつを、自分の方へと引き寄せた。
僕はただ抱きしめることしかできなくて、あいつは驚きすぎて反応が出来ずにいた。しばらくそうしていると、僕たちの目の前にゆらりと光の粒が舞い、白い彼と彼女が現れた。
『幸せになってね、僕。一緒にいてあげられなくて、ごめん。』
僕は、あいつを抱きしめる手に、ぎゅっと力を込めた。そして、彼と彼女に微笑んだ。
「ありがとう。心配しないでね。僕たちは大丈夫だよ」
僕のその言葉を聞いて、二人は顔を見合わせて微笑むと、そのまますうっと消えていった。
「僕」
あいつが、僕を呼んで抱きしめ返してきた。
「俺も、僕を愛しているよ。なあ、おじいちゃんになっても……」
「いいよ。一緒の墓に入ろうな」
僕がその先を知っていたから、あいつは驚いて、また大きな目を落としそうなほどしぱしぱと瞬かせていた。
◇◇◇
僕たちは、その年に結婚した。
あの、白銀の鐘のある教会を見つけて、そこで式を挙げた。
そして、それから毎年二人で銀色のテープを結んでいる。
一人ぼっちで寂しがっている誰かが、一人でも多く幸せになれることを願って。
10
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。


【完結】真実の愛はおいしいですか?
ゆうぎり
恋愛
とある国では初代王が妖精の女王と作り上げたのが国の成り立ちだと言い伝えられてきました。
稀に幼い貴族の娘は妖精を見ることができるといいます。
王族の婚約者には妖精たちが見えている者がなる決まりがありました。
お姉様は幼い頃妖精たちが見えていたので王子様の婚約者でした。
でも、今は大きくなったので見えません。
―――そんな国の妖精たちと貴族の女の子と家族の物語
※童話として書いています。
※「婚約破棄」の内容が入るとカテゴリーエラーになってしまう為童話→恋愛に変更しています。

可愛らしい人
はるきりょう
恋愛
「でも、ライアン様には、エレナ様がいらっしゃるのでは?」
「ああ、エレナね。よく勘違いされるんだけど、エレナとは婚約者でも何でもないんだ。ただの幼馴染み」
「それにあいつはひとりで生きていけるから」
女性ながらに剣術を学ぶエレナは可愛げがないという理由で、ほとんど婚約者同然の幼馴染から捨てられる。
けれど、
「エレナ嬢」
「なんでしょうか?」
「今日の夜会のパートナーはお決まりですか?」
その言葉でパートナー同伴の夜会に招待されていたことを思い出した。いつものとおりライアンと一緒に行くと思っていたので参加の返事を出していたのだ。
「……いいえ」
当日の欠席は著しく評価を下げる。今後、家庭教師として仕事をしていきたいと考えるのであれば、父親か兄に頼んででも行った方がいいだろう。
「よければ僕と一緒に行きませんか?」

新緑の光と約束~精霊の愛し子と守護者~
依羽
ファンタジー
「……うちに来るかい?」
森で拾われた赤ん坊は、ルカと名付けられ、家族に愛されて育った。
だが8歳のある日、重傷の兄を救うため、ルカから緑の光が――
「ルカは精霊の愛し子。お前は守護者だ」
それは、偶然の出会い、のはずだった。
だけど、結ばれていた"運命"。
精霊の愛し子である愛くるしい弟と、守護者であり弟を溺愛する兄の、温かな家族の物語。
他の投稿サイト様でも公開しています。


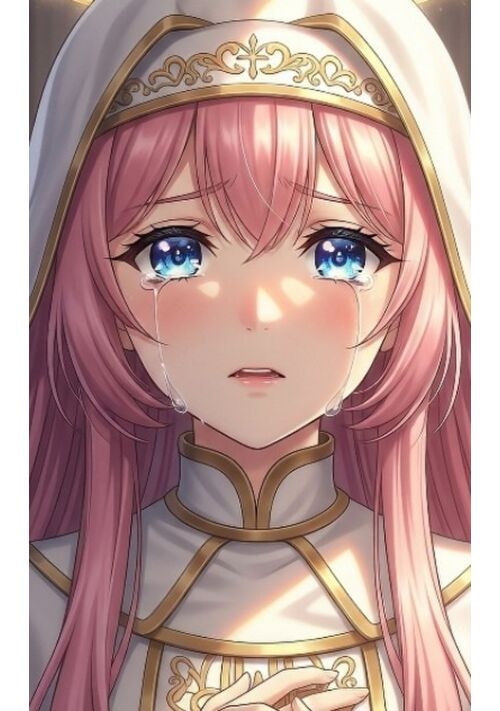
聖女は聞いてしまった
夕景あき
ファンタジー
「道具に心は不要だ」
父である国王に、そう言われて育った聖女。
彼女の周囲には、彼女を心を持つ人間として扱う人は、ほとんどいなくなっていた。
聖女自身も、自分の心の動きを無視して、聖女という治癒道具になりきり何も考えず、言われた事をただやり、ただ生きているだけの日々を過ごしていた。
そんな日々が10年過ぎた後、勇者と賢者と魔法使いと共に聖女は魔王討伐の旅に出ることになる。
旅の中で心をとり戻し、勇者に恋をする聖女。
しかし、勇者の本音を聞いてしまった聖女は絶望するのだった·····。
ネガティブ思考系聖女の恋愛ストーリー!
※ハッピーエンドなので、安心してお読みください!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















