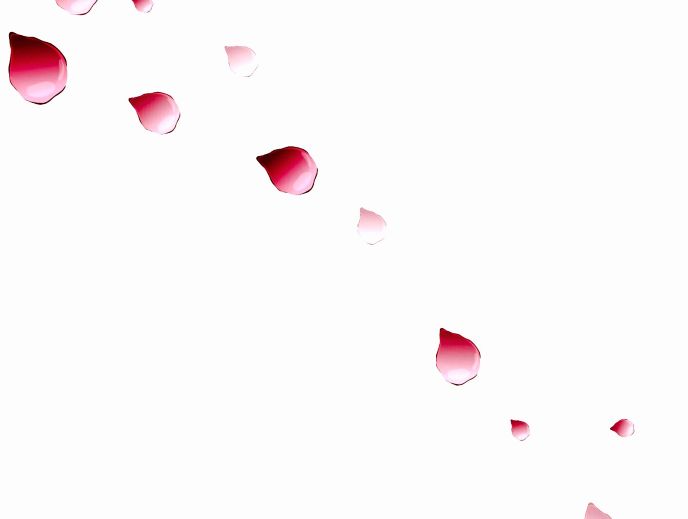3 / 14
第3章~愛し、愛されず~
第3章~愛し、愛されず~
しおりを挟む
彼は居た、いつものファーストフード店の前に。ポケットに手を入れ、空を見上げている。
そんなんじゃあ、彼女が来ても気付かないぞ。
僕は心でそう毒付き、歩を進める。
だが、まだ気付かない。カバンを脇腹に当てる。履き慣れている訳もないスカートの丈の寂しさに、思わず八つ当たりする。
「待たせたな」
「お、待ってないぜ」
「悪かったな」
ずいぶん待っていたということは、彼の瞳を見れば明らかだった。
彼の視線は僕の全身を何度も行ったり来たりしている、気のせいだと思うが、周りの視線も感じる。
自分でも違和感がある、スカートが…短い。
「可愛い。男だって、絶対分からないな」
無邪気に笑う彼に、僕はスカートの裾を気にしながら言った。
「それも嫌だな!」
「今日は1日、付き合ってもらうからな」
こうして始まった本格的シミュレーションは、意外に楽しく、あっという間に経った。
時刻は18時を過ぎた頃だった。
「もうこの季節は、暗いなぁ。もうそろそろお開きにするか?」
「そうだな、てか終わるなら手を離せ!」
そう言って僕は手を振り払う。それを寂しそうに見ている龍都。
「さ、帰るぞ!今度、何か奢れよ?」
僕の言葉に、龍都は笑みを返し、わざとらしく言う。
「あ、この後なんか用事あるか?今日は家に誰も居ないから何か作ってやるよ」
「用事は無いな、お前んち行って食いまくってやる!」
この時、意気込んでいたのは龍都の方だったのかもしれない。彼は、口の端に浮かべた笑みを隠すように、手を差し伸べ言った。
「だから、それまで…俺の彼女な?」
「家までだぞ、ほら早く歩け」
僕は、彼が差し伸べた手を握る。そこから伝わる体温は、全身に伝わり、やがて僕を温めてくれた。 歩のペースはあがることなく、着々と龍都の家に向かっていた。
「あれ、龍都クンかな?」
背後の少女に2人が気付くことは無かった。
「もしかして…浮気?私が告白しても乗り気じゃなかったのに付き合ってくれたのって…本命が居たから、なの…?」
彼女は、イケナイと頭で理解しつつ、後を付けた。これからどこに行こうと、何を見ようと信じられない。でも、受け止める覚悟は出来ていた。
付き合ったのに乗り気じゃない、あの感じが、今の状況を納得させていたからかも知れない。
龍都の家はオシャレな一軒家、と言ってもガレージに外車が突っ込んであるし、伊達に金持ちじゃないのかもしれない。
「お邪魔します」
玄関で龍都の靴まで揃える。これが、僕がいつもお邪魔する時に、やってしまう癖だ。
「何か食べたいもんあるか?特別に今日は俺が作ってやる」
誇らしげに言う彼に、自信があるんだなぁ、と感心する。
「1番自信がある料理を食べたい」
「1番かぁー、あれかな?」
などと1人事を言うと彼は、キッチンに入って行った。
スカートの裾を気にすることも、歩き方を気にすることも、無くやっと安心感に浸れる。何より周りの目が1番毒だ。
安堵からか、僕は思わずため息を付いた。
ふといい匂いと音が流れてきた。
あのスポーツ系龍都が、料理とは…。外見からも性格からも、ギャップが生まれた。
それから数分待って出てきたのは、沢山の種類の天ぷらだった。
「揚げ物か、珍しいな」
「嫌いか?」
彼の不安そうな表情を裏切るように、僕は微笑んだ。彼の眩しい笑顔にはほど遠いが。
「あ、あっい」
「ははっ、出来立てに被りつくからだ」
僕のドジさに、腹を抱えて笑う龍都。そんなに面白いだろうか?
「…でも、美味しい」
僕が、天ぷらとご飯を交互に食べている向かいで、彼はゆっくり味わう様に、もしくは考え事をする様に、箸を動かしていた。
「どうしたんだ?」
思わず聞いてしまう僕に、彼は笑みを浮べ誤魔化した。
「何でもない」
何でもないようには見えない僕は、問いただす。
「何かあるなら言ってくれ、協力もしたい。それとも今日も、僕は力不足だったのか?」
彼は箸を天ぷらに向け、食べ始める。漂う雰囲気が変わった気がした。だが、気にしたら負けだと思い、気が付かないフリをし、味噌汁を啜る。
「お前、本当に可愛いよな」
「ガハッ」
飲んでいた味噌汁を噴き出しそうになり、我慢すると、噎せた。
「どん臭いとこも、ツンデレなとこも、容姿も…」
彼は僕を男として見ているのだろうか?もしかして、弟とかそんな感覚なのだろうか?
「な、何が言いたい」
「可愛いな、って言いたい」
「ふざけんな、あれはフリだ」
気にしていることを弄られ、ムキになる。
「何怒ってんだよ、別に良いだろ。人間には、男性と女性の二つが備わってるんだから。どっちが強いかであって、そんな事どうだって良い」
「僕は男だ!お前だって…可愛いとか、可笑しいだろ!」
「可笑しいのか?」
「え?」
「それって、本当に、可笑しいのか?」
瞳が真っ直ぐと僕を捉えた。僕は、彼の散漫していた意識を全て向けられ、緊張した。
そのせいか可笑しいと、即答も出来なかった。
「じゃ、もし。俺が本当は女子が好きじゃなくて、男子が好きだったら?それって、やっぱり可笑しいのか…」
彼の表情がとても、もし、にはみえず僕は言う。
「問題を身近に感じ過ぎだ」
彼の反応を見るが、自覚しているのか笑った。
「それに、問題が入れ替わってる。今は男が可愛いのが可笑しいと言っているんだ」
畳み掛けるが、やはり彼は堂々とした様子で、全く指摘されている事柄を理解していないようだった。
「男子が好きだから、可愛いと思える。ってのだったら?問題の答えにさえなるんじゃないか?」
「好きって…もしかして、」
「あぁ、そのもしかしてだ」
僕の手から、箸が滑り落ちた。
「僕の事を…そんな目で、見ていたのか…」
龍都に答えを求めるが、僕が求めている答えは真実ではなく、否定だった。
だが、龍都は悪びれもなく笑っている。
「俺の中ではしっくり来ないが、そうなるな…」
彼は、僕の事を…弟どころか、男として目に映ってさえ居なかった。いや、男を恋愛対象に見ていた、が正しいか。
落ちた箸の存在が、目に入る。箸は…自分を箸だと思われている、と考え使われているのだろうか?そんな、答えのない事にさえ疑問を抱き、現実から逃げようとする。
「俺は…お前が」
とっさに、耳を塞ぎ目を力いっぱい瞑る。それがせめてもの抵抗だった。
『ははっ、お前はほんとに騙されやすいな』そんな言葉が脳内に再生された。
いつ言われたんだ?記憶を回想していると、思い出した。一週間前、僕の姉と付き合うことになった、という話題だ。これには心底驚いたと共に、龍都に失望した。何故なら、あんな何処がいいのか分からないうるさい奴が好みだとは思わなかったからだ。
だが、彼は真剣に聞いていた僕を30分間遊んだ。
あの感覚で、もう一度、言ってもらえないだろうか?僕のリアクションを見たいが為の出任せだと。
望みを実現させるべく、耳から手を離す。ゆっくりと視界を広げる。
「…冗談だ」
彼は言った、確かに冗談だと。だが、彼の正直過ぎる性格が裏目に出た。
頬が引きつっている。作り笑いだ。彼は人に話題を合わせる時に、必ずこの笑いをする。
この事は、冗談ではないと、彼自身が訴えていた。
「今回のは、結構ヘビーだったんじゃないか?俺の予想を超えるリアクションだ」
彼は、僕に嫌われまいと、これ以上拒絶される前に、冗談にする事にしたのだろう。
だが、僕には受け止められない。これが冗談だという事も、カレが僕に…恋愛観を持っていたことも。
「誤魔化さなくて良い、龍都…そんな奴だとは知らなかった」
僕は席を立つと、玄関へ行った。靴を履いてドアに手を掛ける。振り返るが、彼は居なかった。
引き留められるより、良いが、心にポッカリ穴が開いてしまった様に、虚しさが際立った。
僕達は、ここで終わってしまうんだな。
僕は一生ここには来ないだろうな、そう覚悟してドアを開けた。
冷たい風が吹きつける。目的が無くなった、僕の服装は哀れなだけだ。早く帰って寝よう。寝て、全てを解消してしまおう。
そう決意し、僕の歩みは速度を上げた。
そんなんじゃあ、彼女が来ても気付かないぞ。
僕は心でそう毒付き、歩を進める。
だが、まだ気付かない。カバンを脇腹に当てる。履き慣れている訳もないスカートの丈の寂しさに、思わず八つ当たりする。
「待たせたな」
「お、待ってないぜ」
「悪かったな」
ずいぶん待っていたということは、彼の瞳を見れば明らかだった。
彼の視線は僕の全身を何度も行ったり来たりしている、気のせいだと思うが、周りの視線も感じる。
自分でも違和感がある、スカートが…短い。
「可愛い。男だって、絶対分からないな」
無邪気に笑う彼に、僕はスカートの裾を気にしながら言った。
「それも嫌だな!」
「今日は1日、付き合ってもらうからな」
こうして始まった本格的シミュレーションは、意外に楽しく、あっという間に経った。
時刻は18時を過ぎた頃だった。
「もうこの季節は、暗いなぁ。もうそろそろお開きにするか?」
「そうだな、てか終わるなら手を離せ!」
そう言って僕は手を振り払う。それを寂しそうに見ている龍都。
「さ、帰るぞ!今度、何か奢れよ?」
僕の言葉に、龍都は笑みを返し、わざとらしく言う。
「あ、この後なんか用事あるか?今日は家に誰も居ないから何か作ってやるよ」
「用事は無いな、お前んち行って食いまくってやる!」
この時、意気込んでいたのは龍都の方だったのかもしれない。彼は、口の端に浮かべた笑みを隠すように、手を差し伸べ言った。
「だから、それまで…俺の彼女な?」
「家までだぞ、ほら早く歩け」
僕は、彼が差し伸べた手を握る。そこから伝わる体温は、全身に伝わり、やがて僕を温めてくれた。 歩のペースはあがることなく、着々と龍都の家に向かっていた。
「あれ、龍都クンかな?」
背後の少女に2人が気付くことは無かった。
「もしかして…浮気?私が告白しても乗り気じゃなかったのに付き合ってくれたのって…本命が居たから、なの…?」
彼女は、イケナイと頭で理解しつつ、後を付けた。これからどこに行こうと、何を見ようと信じられない。でも、受け止める覚悟は出来ていた。
付き合ったのに乗り気じゃない、あの感じが、今の状況を納得させていたからかも知れない。
龍都の家はオシャレな一軒家、と言ってもガレージに外車が突っ込んであるし、伊達に金持ちじゃないのかもしれない。
「お邪魔します」
玄関で龍都の靴まで揃える。これが、僕がいつもお邪魔する時に、やってしまう癖だ。
「何か食べたいもんあるか?特別に今日は俺が作ってやる」
誇らしげに言う彼に、自信があるんだなぁ、と感心する。
「1番自信がある料理を食べたい」
「1番かぁー、あれかな?」
などと1人事を言うと彼は、キッチンに入って行った。
スカートの裾を気にすることも、歩き方を気にすることも、無くやっと安心感に浸れる。何より周りの目が1番毒だ。
安堵からか、僕は思わずため息を付いた。
ふといい匂いと音が流れてきた。
あのスポーツ系龍都が、料理とは…。外見からも性格からも、ギャップが生まれた。
それから数分待って出てきたのは、沢山の種類の天ぷらだった。
「揚げ物か、珍しいな」
「嫌いか?」
彼の不安そうな表情を裏切るように、僕は微笑んだ。彼の眩しい笑顔にはほど遠いが。
「あ、あっい」
「ははっ、出来立てに被りつくからだ」
僕のドジさに、腹を抱えて笑う龍都。そんなに面白いだろうか?
「…でも、美味しい」
僕が、天ぷらとご飯を交互に食べている向かいで、彼はゆっくり味わう様に、もしくは考え事をする様に、箸を動かしていた。
「どうしたんだ?」
思わず聞いてしまう僕に、彼は笑みを浮べ誤魔化した。
「何でもない」
何でもないようには見えない僕は、問いただす。
「何かあるなら言ってくれ、協力もしたい。それとも今日も、僕は力不足だったのか?」
彼は箸を天ぷらに向け、食べ始める。漂う雰囲気が変わった気がした。だが、気にしたら負けだと思い、気が付かないフリをし、味噌汁を啜る。
「お前、本当に可愛いよな」
「ガハッ」
飲んでいた味噌汁を噴き出しそうになり、我慢すると、噎せた。
「どん臭いとこも、ツンデレなとこも、容姿も…」
彼は僕を男として見ているのだろうか?もしかして、弟とかそんな感覚なのだろうか?
「な、何が言いたい」
「可愛いな、って言いたい」
「ふざけんな、あれはフリだ」
気にしていることを弄られ、ムキになる。
「何怒ってんだよ、別に良いだろ。人間には、男性と女性の二つが備わってるんだから。どっちが強いかであって、そんな事どうだって良い」
「僕は男だ!お前だって…可愛いとか、可笑しいだろ!」
「可笑しいのか?」
「え?」
「それって、本当に、可笑しいのか?」
瞳が真っ直ぐと僕を捉えた。僕は、彼の散漫していた意識を全て向けられ、緊張した。
そのせいか可笑しいと、即答も出来なかった。
「じゃ、もし。俺が本当は女子が好きじゃなくて、男子が好きだったら?それって、やっぱり可笑しいのか…」
彼の表情がとても、もし、にはみえず僕は言う。
「問題を身近に感じ過ぎだ」
彼の反応を見るが、自覚しているのか笑った。
「それに、問題が入れ替わってる。今は男が可愛いのが可笑しいと言っているんだ」
畳み掛けるが、やはり彼は堂々とした様子で、全く指摘されている事柄を理解していないようだった。
「男子が好きだから、可愛いと思える。ってのだったら?問題の答えにさえなるんじゃないか?」
「好きって…もしかして、」
「あぁ、そのもしかしてだ」
僕の手から、箸が滑り落ちた。
「僕の事を…そんな目で、見ていたのか…」
龍都に答えを求めるが、僕が求めている答えは真実ではなく、否定だった。
だが、龍都は悪びれもなく笑っている。
「俺の中ではしっくり来ないが、そうなるな…」
彼は、僕の事を…弟どころか、男として目に映ってさえ居なかった。いや、男を恋愛対象に見ていた、が正しいか。
落ちた箸の存在が、目に入る。箸は…自分を箸だと思われている、と考え使われているのだろうか?そんな、答えのない事にさえ疑問を抱き、現実から逃げようとする。
「俺は…お前が」
とっさに、耳を塞ぎ目を力いっぱい瞑る。それがせめてもの抵抗だった。
『ははっ、お前はほんとに騙されやすいな』そんな言葉が脳内に再生された。
いつ言われたんだ?記憶を回想していると、思い出した。一週間前、僕の姉と付き合うことになった、という話題だ。これには心底驚いたと共に、龍都に失望した。何故なら、あんな何処がいいのか分からないうるさい奴が好みだとは思わなかったからだ。
だが、彼は真剣に聞いていた僕を30分間遊んだ。
あの感覚で、もう一度、言ってもらえないだろうか?僕のリアクションを見たいが為の出任せだと。
望みを実現させるべく、耳から手を離す。ゆっくりと視界を広げる。
「…冗談だ」
彼は言った、確かに冗談だと。だが、彼の正直過ぎる性格が裏目に出た。
頬が引きつっている。作り笑いだ。彼は人に話題を合わせる時に、必ずこの笑いをする。
この事は、冗談ではないと、彼自身が訴えていた。
「今回のは、結構ヘビーだったんじゃないか?俺の予想を超えるリアクションだ」
彼は、僕に嫌われまいと、これ以上拒絶される前に、冗談にする事にしたのだろう。
だが、僕には受け止められない。これが冗談だという事も、カレが僕に…恋愛観を持っていたことも。
「誤魔化さなくて良い、龍都…そんな奴だとは知らなかった」
僕は席を立つと、玄関へ行った。靴を履いてドアに手を掛ける。振り返るが、彼は居なかった。
引き留められるより、良いが、心にポッカリ穴が開いてしまった様に、虚しさが際立った。
僕達は、ここで終わってしまうんだな。
僕は一生ここには来ないだろうな、そう覚悟してドアを開けた。
冷たい風が吹きつける。目的が無くなった、僕の服装は哀れなだけだ。早く帰って寝よう。寝て、全てを解消してしまおう。
そう決意し、僕の歩みは速度を上げた。
0
あなたにおすすめの小説

平凡ワンコ系が憧れの幼なじみにめちゃくちゃにされちゃう話(小説版)
優狗レエス
BL
Ultra∞maniacの続きです。短編連作になっています。
本編とちがってキャラクターそれぞれ一人称の小説です。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。


久々に幼なじみの家に遊びに行ったら、寝ている間に…
しゅうじつ
BL
俺の隣の家に住んでいる有沢は幼なじみだ。
高校に入ってからは、学校で話したり遊んだりするくらいの仲だったが、今日数人の友達と彼の家に遊びに行くことになった。
数年ぶりの幼なじみの家を懐かしんでいる中、いつの間にか友人たちは帰っており、幼なじみと2人きりに。
そこで俺は彼の部屋であるものを見つけてしまい、部屋に来た有沢に咄嗟に寝たフリをするが…


BL 男達の性事情
蔵屋
BL
漁師の仕事は、海や川で魚介類を獲ることである。
漁獲だけでなく、養殖業に携わる漁師もいる。
漁師の仕事は多岐にわたる。
例えば漁船の操縦や漁具の準備や漁獲物の処理等。
陸上での魚の選別や船や漁具の手入れなど、
多彩だ。
漁師の日常は毎日漁に出て魚介類を獲るのが主な業務だ。
漁獲とは海や川で魚介類を獲ること。
養殖の場合は魚介類を育ててから出荷する養殖業もある。
陸上作業の場合は獲った魚の選別、船や漁具の手入れを行うことだ。
漁業の種類と言われる仕事がある。
漁師の仕事だ。
仕事の内容は漁を行う場所や方法によって多様である。
沿岸漁業と言われる比較的に浜から近い漁場で行われ、日帰りが基本。
日本の漁師の多くがこの形態なのだ。
沖合(近海)漁業という仕事もある。
沿岸漁業よりも遠い漁場で行われる。
遠洋漁業は数ヶ月以上漁船で生活することになる。
内水面漁業というのは川や湖で行われる漁業のことだ。
漁師の働き方は、さまざま。
漁業の種類や狙う魚によって異なるのだ。
出漁時間は早朝や深夜に出漁し、市場が開くまでに港に戻り魚の選別を終えるという仕事が日常である。
休日でも釣りをしたり、漁具の手入れをしたりと、海を愛する男達が多い。
個人事業主になれば漁船や漁具を自分で用意し、漁業権などの資格も必要になってくる。
漁師には、豊富な知識と経験が必要だ。
専門知識は魚類の生態や漁場に関する知識、漁法の技術と言えるだろう。
資格は小型船舶操縦士免許、海上特殊無線技士免許、潜水士免許などの資格があれば役に立つ。
漁師の仕事は、自然を相手にする厳しさもあるが大きなやりがいがある。
食の提供は人々の毎日の食卓に新鮮な海の幸を届ける重要な役割を担っているのだ。
地域との連携も必要である。
沿岸漁業では地域社会との結びつきが強く、地元のイベントにも関わってくる。
この物語の主人公は極楽翔太。18歳。
翔太は来年4月から地元で漁師となり働くことが決まっている。
もう一人の主人公は木下英二。28歳。
地元で料理旅館を経営するオーナー。
翔太がアルバイトしている地元のガソリンスタンドで英二と偶然あったのだ。
この物語の始まりである。
この物語はフィクションです。
この物語に出てくる団体名や個人名など同じであってもまったく関係ありません。

【完結】 男達の性宴
蔵屋
BL
僕が通う高校の学校医望月先生に
今夜8時に来るよう、青山のホテルに
誘われた。
ホテルに来れば会場に案内すると
言われ、会場案内図を渡された。
高三最後の夏休み。家業を継ぐ僕を
早くも社会人扱いする両親。
僕は嬉しくて夕食後、バイクに乗り、
東京へ飛ばして行った。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる