120 / 204
一番の無能豚は、お前だろう。
しおりを挟む
喫茶店で、山崎と見知らぬ男達と向かい合い、その向こう側の席に八代と、それから、神崎の姿が見えた。霧野の心拍数は跳ね上がった。余程何もかも忘れて、彼の元にすぐさま駆け出して行きたかったが、何事も無いよう報告書の内容を伝え、平然を装った。装う程に憤る。
「そういうわけで……」
視線。他の客も全て、向こう側か、こちら側の、誰かなのだろうと思われた。建物の向こう側から、川名が見ている。川名以外にもきっと監視している。こちら側あちら側共にだろう。鉢合わせして、互いに殺しあってくたばったらいい。漠然と考えながら、機械的に話し続けていた。疲れないコツだ。疲れないコツ、心に風船でも付けるようにして飛ばすこと。そういえば、美里が同じようなことを言っていたっけ。
「どういうことだ?」
質問にも、あらかじめ用意した回答で応える。馬鹿のように納得する公豚老害共。それっぽくにおわせても気が付かない。何故、どうして気が付かない。よほど木崎と示し合わせた合図を送ろうか迷ってやめた。事務所に八代達が来た時、一体どうなった。どんな目に遭わされた。くだらない合図など、とっくに川名達には筒抜けなのに違いない。川名達に囚われ、助けを求めるべき相手を馬鹿にせざるを得ず、自分が、何者でもない、よくわからない機械のような存在に思えてくる。今に始まったことでなく、以前からそうであった。どうしてこんな無能豚に報告を届けないといけないのか。命を懸けるほどの価値はあるのか。意思を殺せ。機械、自動機械。おや、と霧野は思った。これでは最早どちらの味方なのかもわからない。自分が反転していく感覚。自分が自分ではない何者かと思う習慣が身についていた。以前から、澤野であるときは霧野でなかったが、それがもっと濃くなった。
刑事たちと対峙する前、山上の川名の別邸、コテージ風の別荘で、川名と軽く食を共にすることになった。元々は二条や美里を誘うつもりであったようで、食事は三人分、テーブルの上に運ばれてくる。料理人や配膳係、それから見張りのつもりか、黒ずくめの男が何人か手配された。部屋の南面はガラス張りになって、小高い山の上から、森と街が見えた。香り高い食事の数々。部屋の中で呆然と立ち尽くす霧野に対して、席に着くか、床に侍るか、川名は霧野に選択させるのだった。思わず鼻で笑った。
「ふん、なに、選ばせるようなことですか。」
霧野が自信満々の半笑いで椅子の背に手をかけて、先に向かいに腰掛けた川名を見下げた。何もない席、その椅子を引きかけたところで、手が止まる。考えるより先に電流でも走ったように身体が止まったのだった。
「……。どうした?」
静かな、しかし含みのある声。川名が挑発的に霧野を眺めていた。川名と自分の間で生まれた奇妙な感情を振り切るようにして、無理やり川名の対面に座るのだった。
「お前の好きなものを別に頼んでおいたから、好きに、思う存分に食べてから向かうと良い。腹が減っていてはせっかくの頭もまともに働かないだろうし、余計な気を起こされても困るから。」
霧野の目の前にも料理が運ばれてきた。半焼けのレアの肉だった。ほくほくと目の前で、生に近い、肉食獣の好みそうな、殆ど人工的な調理はくわえられていない生焼けの肉が湯気を立て、じゅうじゅうと激しく肉汁と蕩ける脂を滴らせ、血と香草の匂いが漂った。鼻先に突き付けられた久々の美食の香りに気が狂わんばかり。心臓が激しく強く高鳴り、眩暈するほどであった。
口の中に生暖かい液体が漲って溢れた。まるで性交のように、激しい昂ぶりが身体の奥底から溢れて出、声まで漏れ出そうであった。それで、必死に平静を装って「何をたくらんでいるか知りませんが……」とかなんとか微笑して答える。いらねぇんだよ、こんな、馬鹿にして!と堂々きっぱり言えたら如何に良かったか。内臓がうねる。音を立てる。口から溢れでる息の飢えていること。意地を張ることの無駄さ。
「いらないのか?やっぱり人工物、ドッグフードがいいか?せっかくの、いい肉なのに。」
川名が無邪気に言って首を傾げた。霧野は腕を組んで軽く指を噛んだ。
「何の肉ですか、これ、まさか、木崎の肉なんて言うんじゃないでしょうね。」
「何を言ってる。仔羊だよ。こうなる前のも見て、抱いてもみたけれど、とても可愛かったぞ。」
霧野は灼ける子羊を見下ろし、それからまた、川名を上目遣った。川名は水に口つけながら、霧野を観察するように見ていた。ここで、おいそれと手を付けては、貴方の仲間になりましたよ、くだりましたよ、と腹を見せ尻尾を振って言ってるようなものではないのか。目の前のこれが、どうしようもない、奴隷のような、刑務所のような餌であったなら、まだ食べることができただろう。
「食わないか。仕方が無いなぁ。持ち帰ってノアにでもやることにするか。」
川名が、傍らに置かれたベルを鳴らすと、すぐドアの向こうからボーイが現われ、霧野の目の前の肉をさっさと持っていってしまった。霧野は唾をのんで耐え、テーブルの下で拳を握っていた。もし最初に、床に侍ることを選んでいたら、と思わずにおえなかった。そうすれば、きっと、食べられた。一階層人間を降りているから、無駄なプライド、意地を張らずに、喰わされているという精神でもしかしたら、喰いえたかもしれかったのに。椅子の背に手をかけた時の、何とも言えない厭な感じの正体はこれに違いないと霧野は思うことにした。
待て。の状態にさせられたまま、何もなくなった空間、それから二条と美里の不在により、冷めていく人間の食事をちらちらと見ながら、勝手に手を付けたらどうなるだろうかと想像する。川名に肉を引き裂かれる罰を与えられる妄想。彼の足元で打ちひしがれる自分の姿が頭の中に浮かんでは消えた。裂かれた肉から飛沫する血が、川名の顔と青白い手の甲の上に散って、彼の尖った舌が舐めとって爛れ腐った獣の血は不味いと言う。自分の姿が子羊の肉と被ってくる。皿の上で半生に焼かれてナイフで均等に刻まれ、今まさに喰われようとする肉塊。
目の前で、一つの破片も散らさず、機械的に食事をとる男。食べ物の方から進んで彼の中に吸収されていくかのようだった。些細な仕草一つとっても、非の打ち所がないのだ。彼が歩いている後ろ姿。気だるげに、この世のすべてに興味をなくしている時、時に芯から矜持を持って歩いている時、どちらも、人を寄せ付けなかった。逆に人を寄せ付けたいときは、そういう時用のラフなふるまいを敢えてしていた。川名の視線が時折、霧野をなぞるようにして、度々何か話すことを促す。澤野だったら気の利いたことの一つでも言えるのに、何も言えないで固まっていると、彼は口元に憐れみの笑みを浮かべるのだった。
いやしくも、余っているそれらを喰っていいですかの一言さえ、首を上から掴まれているようで、つばを飲み込むだけで、言えない。もし、今その、足元に、地に、さっきまでのお屋敷でのような獣の役目で這っていたなら、川名の指示通り媚びて、もしかしたら、人間の美味しい食べ物の欠片の一つでも食べられたかもしれないのに、と思いながら、霧野は自身が空腹のあまりおかしな異常な思想に堕ちこんでいるぞ、と、心の中で激しく己を叱咤し、自らの太ももに爪をたてた。また、腹が鳴って、天を仰いだ。
「もう、よすか?」
やけに優しい猫撫で声で、ようやく川名が喋ったと思い目を合わせた。彼はとっくに目の前の物を平らげて、オレンジ色のシャーベットが運ばれ、小さなコーヒーカップから香ばしい香りが漂っていた。
「よす?一体何を……」
「人間ごっこ。」
霧野は一瞬笑いかけたが、笑えなくなって、川名を眺めた。
「お前には、俺の元に来る前まで交際していた女が幾人かいたようだが、最後の女にお前はまだ未練があるようだな。確かに彼女はお前のような人間以下の犬には、もったいないほどの器量の女だったようだ。」
「……ありませんよ、一体何年前の話をしてるんだ。」
「ああ、そう。じゃあ」
「だからと言って、殺されて気にしない程の、鬼畜の精神は私にはありません。貴方とは違うから。」
「そうか、それは良かった。念のためそれを、お前の口から、聞いておきたかった。何の罪もないお嬢さん、強いて言えばお前のような被虐癖の果てしない変態色欲狂の隠れホモ野郎と、それを知らずに関係を持ってしまったという哀れな罪のあるお嬢さんを無駄死にさせても、俺だって心が痛むんだよ。さて、これからのほんの数刻の間、お前を元のように自由にさせてみるが、お前を許したわけではないからな、態度を心得ろよ。酷い目に遭うのはお前だけでは済まない。お前から心からの謝罪をもらったわけでもない。皆に、身体を少しずつ屠られ、弄られて、惨めに泣いて、時に許しを乞うたが、そんなその場限りの、噓の言葉を聞いたところでな。」
「……」
「しかし、お前のその肉体からは徐々に、本当の叫びが聞こえるようになってきた。人間の脳など、所詮本能の動きに対して後付けで思考をして、脳の持ち主にフィードバックを繰り返すだけの電子機械。で、さらにそのフィードバックから遅れて、意識的に考えて、あるいは考えたふりをして、言葉が口を出ていく。お前のような病的な嘘つきは、ここの意識的な部分が異常に発達しているのだ。だから、病的な速さで、出まかせを吐ける。それを本当と思っている節さえある。すると、本当のことも、そのしょうもない意識に掻き消されて、本人さえ何が自分にとって良く、何が自分にとって悪いのかさえ、よくわからぬ状態になる。今まで随分つらかったろう。」
「……。……、ははは、気味の悪いプロファイリングだ。じゃあ私から言わせてもらいますが、病的な嘘つきは貴方だってそうでは。じゃなければ犯罪を隠し通すことなんてとてもできない。」
「そうだよ。だから誰よりもお前のことがわかるんじゃないかよ。だがお前と違う点は、俺はある地点から、自分の本能になるべく忠実に従おうと、心の声を聞いてやろうと、誠心誠意心掛けるようにしたのだ。自分の本能と欲望を自分で手なづける。だから無自覚な嘘はつかないし、俺はお前と違って常に、自分自身で居るつもりで自分を見失うことなどない。お前はきっと自分の病的で邪の本能の発露として、正義の、お巡りさんになったのでは。まあ、どうせ、誰よりも俺なんかよりも、底意地の悪いお前のことだ。何癖付けて、違うといいはるだろうが、どこかに確実にその気持ちがあったはず。何年もの間、そういう人間を進んで集めてきたのだから、俺の目に狂いはない。ある種の救済のつもりでもあるんだな。お前達ような哀れなモノを飼って管理してやるのが俺の使命の一つで、この実につまらない世界の中で幾分か、心躍ることでもある。」
「救済?は!救済だって?どこが!かっこつけても、ただの変態の集まりじゃねぇかよ。さっきから好き放題言って。俺のことばかり散々いうが、問題は俺ではない。アンタを筆頭に変態残虐嗜好者の集まりなのが問題なんだ。一人の人間に、それも俺のようなのに寄ってたかって。」
川名はわざと虚を突かれたような顔をして、それから微笑んだ。
「……。その変態共の中で、まさに、他の誰よりも悦んでいるのはお前自身だと思うけど。今も、それから、昔もな。本当は自分が一番わかっているくせに。」
「わからない、っ、わかりたくもない、」
霧野の上ずった叫びに、川名は、ふふふ、と笑って片手をテーブルにつきながら、立ち上がった。それから、一瞬外の景色を眺め、霧野を見降ろした。
「強がって。わかりたくもないだと?じゃあ今から、別の部屋で軽くお前を打ってやるから、欲情せずにいられるか試そうじゃないか。どうだ?それで。お前が、お前が今しがたその口から言った通り、わからず、ただ痛みに苦しむ常人というなら、お前に一言、謝罪しよう。見誤ったと。それから、俺のいないところで犬のお前に、俺と全く同じ食事をとらせてやる。嬉しいな。お前、俺が側に居ると、俺のことが気になるのだろう?」
「……。駄目だったら?」
「おや、そんなこと考える必要があるのか。お前が言いだしたことだぜ。さ、出ようか。」
川名に通された洋広間は、舞踏会でも開けそうなほど広く、やはり南側一面がガラス張りになって、深紅のカーテンは開け放たれていた。芝が植えられた庭、その向こうに街並みが見渡せる景色、傾き始めた光が差し込む。電機などつけなくても十分明るい。天井が高く、梁が幾らかめぐらされて、何かを吊るすのには良さそうであった。壁に複数の鞭が飾られていた。木材と革の匂いがする。鞭の他、大きなふたつ飾り棚が設置されて、棚の上に霧野が使用用途を想像できるものとそうでない物とが、丁寧に並べられ飾られて、何も言わなければ、淫具にさえみえないかもしれない。他に扉の閉じられた重量感ある棚が三つほど並べれた。部屋の隅に、暖炉があり、近くに大きなテーブルと、ソファが並べられている。それにしても、何もない空間が圧倒的な面積を占めた。廊下には黒服の男が二人、控えている。
床に何か怪しい染みがある。奇麗好きな彼のことだ。拭き忘れではない。これは、消え無い染みなのだ。川名の別荘には、何度か来たが、この広間に通されたのは初めてのことだった。霧野が部屋を見回し、立ち尽くしている中、川名の刺すような視線に気が付いた。そうだ、と思って衣服に手をかけた。開放的な空間で裸であることは、川名と一対一であるというのに、羞恥心を普段より掻き立てた。剝き出しの身体で、彼の近くに行き、膝をついた。後ろから光に照らされて、彼の姿が普段より大きく重厚に見えた。真っ白い紙に墨汁を一滴たらしたような、彼がそこに居るだけで、部屋の空気が鎮圧されるようだ。開放的だったはずの部屋、しかし、彼の瞳を見ていると、四方から壁が音を立てて迫ってきて、圧し潰されそうな感覚に陥る。
「そうだな。それから、次は。」
刺す、射るような声質。優しいのに深みと厳しさがある。それから。彼の前で手をついて、頭を下げた。霧野は咄嗟に、もう、やばいぞ、と思った。このままでは、これだけで、まだ鞭打ちが始まってさえいないのに、屈辱感と羞恥と、圧倒される感覚で、川名に、最悪の証明をして敗北してしまうかもしれなかった。
霧野は床の上で惨めに丸くなって、身体を擦るようにして誤魔化していた。川名はそれがわかっているのか、霧野の目の前を右に左に歩き始め、彼の歩くたびに彼の身に着けた革の匂い、ほんの微かなウッド調の香水の香り、そして獣、懐かしさを感じるような、先輩犬ノアの彼にこすりつけたらしい雄の臭気がわずかに漂うのだった。川名は、壁際から一本、乗馬鞭をとって、鞭で空をひゅんひゅんと言わせ始めた。ひゅっひゅっ、音を立てる鞭、それが、今まさに身に降りかかる、今か、今か、という、そんな厭な予感と期待が、恐怖やスリルに付随する興奮となって、霧野の、傷跡に彩られた光沢あるつややかな赤白い身体の表面をぷつぷつと鳥肌を立て、霧野の湿った裸足のつま先が居心地悪そうに丸まった。川名の足が止まった。
「ハル。まだなんにもしていないぞ。」
「く…ぅ…」
「身体が軽く震えているようだが、大丈夫か?」
「あ……、は」
ひゅっ!という音と、背中の右上側に焼け弾ける感じ。歯をぐぅと食いしばった。はじまった。肩甲骨のあたりに鋭い打撃が決まっていた。右腕が特にがくんがくんと震えた。使用された乗馬鞭の先端の小さな面は。二センチ×四センチ程度、一点の肉に刺激を与え、目の前で軽く光が散った。小娘のつま先のような物だ。それが肉を弾いて痛ませる。痛みは背中に与えられたはずなのに、熱くなるのは、そこだけではなかった。
「まさか今、はい、とでも言おうとしたか。違うよな。ハル。」
もう一度同じ位置をスタンプでも押すように、正確に撃ち抜かれて「わん゛!」と吠えていた。
「そうだな。えらいじゃないか。」
するする、と鞭の先端が、霧野の大きな背中を軽く撫で、なぞり撫でた。全身を紅潮させ、はぁはぁと息づく。きつく閉じていた目を薄っすらと開いた。霧野の眉目が左右非対称になって、被虐の欲望を認めると認めないとの間で揺れていた。
……。
背が、痛む。目の前の刑事に報告を続けながら、さっきから視界の端にチラつく男のことを考えた。きっと神崎がこの場を取り付けるのに一役買ったのだろうという確信に近いものがあった。目の前の無能豚が思いつくとはとても思えないし、わざわざ彼が出向くということはそういうことなのだ。美里を使者としたかいが多少なりとも報われたと言える。久しぶりに見る神崎の姿は、以前より鋭さを増して見えた。
霧野は、自分自身の張り付いた様な冷淡な表情の下、助けて!助けて!と叫んだ。同時にその神崎に対して、強い憎悪の感情、幼稚な苛立ちも芽生えはじめた。ここまででてきて、どうして直接手を伸ばしてこない。人が、目の前で溺れているのだぞ。それからまた、心の中で助けを乞うことしかできぬ情けない自分にがっかりするのだった。
神崎を見ていると、何故か、一時忘れていた肉の痛みが蘇り、熱くなっていった。紋様のように、身体に絡みつき、背後から抱かれれでもいるように、よくなじんで、存在を主張する。先刻の五発。
……。
「五発だ、たったの五発。耐えてみせろ。」
川名の手の中に、革で編み上げられた長さ1メートルをゆうに超えた女の髪のように真っ黒い、光沢の強い一本鞭がしな垂れていた。彼は慣れた手つきでそれをなで、引き絞るように伸ばした。ぎぎぎ、と鞭が啼いた。なんとも言えない香ばしいような匂いと鉄の臭いするのを嗅いだ。
「これは幾分か使い込まれたものだ。匂うか?人の皮を破り、皮脂と汗と血とを吸って柔らかくなったのだ。」
霧野は、床の上に四つ這いになっていた。ありがたいことに、残酷な鞭を見せられたことで一瞬恐怖したことで、股間の昂ぶりが少しだけ沈下してまるまったのだった。彼は慣れた手つきで鞭を扱っていたかと思うと、霧野の背面に回った。空中に試し打ちする音、それからすぐ、始まった。背後から背中二発、背骨が弓なりに堕ちる、尻に二発、反対に尻は上がり、猫のような姿、続けざま、最後に、開かれたむちむちとして太ももの間、そこに蛇のような素早さで鞭が踊り、一物を全体を下から巻きとるように、激しい一発が、打ち下ろされた。目の前が激しく明滅し、身体が伏せられ、頭が震え、堪えていた悲鳴が上がった。すっかり身体から力が抜けて、まずは腕を、それから肩、頭、腹まで地面につき、うつ伏せに地に伏してしまう。あ゛、あ゛っ、ううう……と小さく小さく、声が切なく漏れて、痛みに熱くなった身体が冷たい床の上でがくがくと、震えていた。
霧野の周りには、ワインの一滴の雫を堕としたように、肉体を中心として、仄かに周囲に血痕が飛び散って、鉄の臭いを振りまいていた。濃厚で芳醇な香り。背後に、男の立つ気配。零れ落ちた液体のように、霧野の身体は地面に張り付いている。逃げる場所など無く、五発終わったというのに、逃げようと、どこかを掴むように腕が動いていた。しかし、そのような状況下でも、爛れた肉体の下で、一本の、霧野の紅い太魔羅が、激しい呼吸で波打つ厚い腹筋とぬるい床の間で、先刻まで体内に挿入されていた鉄棒よりも、ずっと重く熱い存在感を持って激しく、硬く、膨張、どくどくと脈打って、もう、止まらないのだった。腹の下に隠された酷すぎる蛇淫、膨らみはパンパンに腫れ、蛇淫の代わりに見せつけるように、新しい蚯蚓腫れを二筋もいだだいて、艶を持って汗ばんだ豊かな肉饅頭の間で、犬の可愛らしい裂け目が、引きつって誘うようにしてぶるぶると痙攣していた。
「ん゛ん……くひ……ぃ……」
床の上で、霧野の身体は、悶え、軽くのたうっていた。肉と床が擦れて音を立てるが、霧野から湧き出た汁で、ぬこぬこきゅうきゅうという奇妙な音をたてた。燃える霧野の肉体と反対に冷たい視線が、遥か遥か高み、上から、肉体に注がれつづけ、身体の下に隠された大きくなった欲望まで、よく見透かされているように思える。
どれだけもがいてもあがいても、無意味とわかっている。それでも隠そうと思う程に、息が無様に上がるのだった。隠し切れないことはわかっていて、このまま姿勢を変えてみよ、とたった一言言われたら、たったそれだけで、全てが、明らかになるのだ。それを想像してしまうと、もう、高まりが収まるどころか、ビンビンと、逆に脈打ち、欲望に溺れかけた。息継ぎをしても、息がうまくできず、まだ自分を抑えられると頑張る気持ちと、はやく息の根を止めて欲しいという気持ちとで葛藤した。
「お前の負けだな。」
とどめを刺す声だった。身体と床の間でどくどくと収まるどころかさらに、隠さなければ負けてしまう棒が膨らんでいった。悔し涙か快楽の涙かが目の縁にたまったが堕ちずにいた。見せてみろ、とさえ言ってくれない。身体と仕草と臭いとが代わりに全てを彼に報告する。
……。
霧野は、自分の目の前の男達に、報告する口調が乱雑になってきているのを感じながら、淡々と、あてつけるようにその調子で続けて、また、神崎を見た。神崎は霧野を見ても、表情を変えるでもなく、仏の像のように、伏し目がちに半ば見下すようにして、こちらを見ているかどうかさえ不安だ。いつもそうだった。立場を問わず人を馬鹿にした冷めたその感じ。そういうところが、人として好きであり、嫌いであった。
だから一層、奥さんや新しい女に逃げられて、心の底で傷心している彼を見るのも好きだったのだ。一見わからないが、心の中で、枯れかけの植物のようにしなびて泣いているのだ。酒席で霧野が酔ってしまって介抱された時や、徹夜仕事の延長で神崎の家にいたことが数度あった。朝方、寝覚めの悪い同士ぽやぽやとしている時、誤って神崎が違う名前で霧野を呼び、珍しく赤面していた。お茶をとってくれないか、と言い終えるや否や霧野の顔をじっと見て、はっとしたのだ。霧野は反対に自分の顔が徐々にほころぶのを感じた。
「ふふふ、神崎さん、誰っすか~?それ。」
普段ポカを見せない彼を、ここぞとばかりに馬鹿にしたものだった。それほどに元妻が恋しいようである。
「俺なんかに似ていたのか?くくく、一体どういう女性なのですか。」
彼のことだから、妻がいる時には霧野にしたのと同じように、無神経に違った名前で呼んでしまい、逆鱗に触れたのではなかろうか。何故か神崎のそんな珍しい痴態を思い出した。彼にも乱れることがあるのだ。神崎は霧野の煽りなどは気にしていないという風に無視して黙って自分でお茶を入れていたが、湯のみから茶が溢れそうになっていた。
「というわけで、この件は片付いています。」
神崎の瞳が、霧野の方にわずかに持ち上がって、じっと見た。また、助けて、と声に出しかけると同時、急に、背中に川名から加えられた鞭の痕が痛んで、幻聴を聴き、抱かれた。思わず「ああ‥…っ」とこの場にそぐわない、淫靡な声が出そうになった。この傷を、神崎が見たらどう思うだろうと思った。悲しむか、怒るか、単なる尋問、拷問の痕と判断するだろうか。気が付くだろうか。考え始め、神崎の視線を余計に”感じ”てしまい、屠られた箇所が次々と、熱を持った記憶と共に蘇り、もはや、平静を装えなくなってきた。顔が熱いのだった。それから、神崎を劣情の、揺れる視線で眺めてみても彼の表情は一切変わらず、己が責め立てられているような気になってくる。散々神崎以外の刑事を無能豚と心の中で見下し、罵ったが、一番の無能豚は、お前だろう、と彼から言われているような気分になるし、彼なら言いかねなかった。鼓動がどんどんと速くなる。視線が、さだまらなくなり、卑屈な笑みがでてきた。
「すみません、少し、トイレに。」と、乱暴に席をに立った。
そのまま、逃げようという気も無い。何の策もないまま、無暗に逃走するのは、自殺行為。立ったと同時に眩暈する。視界が歪む。背後から人のついてくる気配がある。川名がこの場に居るわけも居るはずもないのに、身体に何かを施されているわけでもないのにすぐ側に彼がいるように思われる。彼の証がまた、じん、と熱を持って痛むのだ。衣服に擦れて、尻を、秘所をほじくられ、触られているような気分になる。歩いてるだけなのに、十字架をしょわされて、鉄板の上を歩いてるよう、皆の視線を感じた。罪の意識さえ、頭をおかしくさせる。
「……。」
喫茶店にしては広い化粧室、やはり幻覚ではなく、背後に付いてくる者がいる。
背後に居る人間をいくらか想像しながら、振り向いた。
……。
「これじゃ、お前の情けの無く、さもしい肉欲の象徴を、はっきり見なくたってわかる、お前の全身が物語っている。こんなに簡単なことで。何か言い訳はあるか?」
川名が地に伏した灼熱の肉塊のすぐ横に立って、尻を、上から足で踏みつけるのだった。ぐりぐりと肉を揺らされると、高い女のような声が出ていった。身体の奥の熱芯がゆらされ、内にこもった熱、身体の中で焚火でもしているかのような熱が、息をと共に漏れ、吐くと涎が再現なく垂れ、人語とは言えない声がぐるぐると漏れ出ていった。言い訳、俺は違う、違うのだ、と思って、首を横に振るまではできるのだが、何一つ言葉が浮かばず痴呆のように、ぼーっとしていた。川名の言葉がぐるぐると頭の中を回って傷が熱い。違うと言って違わないのだから、それよりも、これから確実にクルであろう懲罰に怯えた。負けたのだから、さらに懲罰がくわえられるのだ。顔をあげられない。頭を掴まれているわけでもないのに、大きな手に上から押さえつけられているようだった。
「珍しく大人しいじゃないか、犬。そんなに激しくしたわけでもないのに。」
「……、……。」
「自分から俺に対して啖呵をきっておいて、無様に負けたのだから、覚悟はできているだろうな。」
役目を終えてしなだれた鞭の先端が、蛇の舌のように、ちろちろと霧野の背中を擽っていた。
「ァぁ‥…」
ゾクゾクと背筋を微電流が流れていった。身体が小刻みに震えた。そこに声が挿しこまれて、脳を突かれた。
「普段の仕事と同じこと。お前は、これからは俺の下で二つの仕事に奉仕していくしかないのだ。表でやりあう普段の仕事と、裏で奉仕する仕事と。おや?これでは前とそんなに変わらないな。割合を、一対九くらいにするのがお前のようなのには、ちょうどいいかな?とにかく、後から、この負けについては、厳しく制裁してやるから、楽しみにしておくといい。思いつめて、くれぐれも仕事中に勃起などしないようにな。しかし、今ので一層腹が減っただろう。喰わせてやる。ノアの、喰いきれず余ってるのがあるから、すぐにノアの古い、おさがりの皿にでも盛って持ってこさせよう。それを俺の足元で、奇麗に舐め、食べるんだよ、わかったか、ハル。」
霧野は餌の姿を思い浮かべ、物言わぬ代わりに、姿勢を崩して川名に流し目を送っていた。川名がじっと霧野の様子をうかがっていてた。
「なるほど……それくらいでは、ドマゾのお前には物足りないとでも言いたいか。上から、いろいろと、かけて、欲しいのだろう?そうなのだろう?おやおや?それでは、まるで、ご褒美じゃないかぁ……??なぁ……霧野……。あの餌が、そんなにうれしかったのか。つけあがって。これから仕事が無ければ、お前を肥溜めの中にでも頭からつっこませて嫌という程喰わせてやったってよかったが、お前が強烈な悪臭を振りまきながら、元同僚たちに会ったら、相手方はどう思う。ただでさえ今のお前は獣臭くて臭くてたまらんのに。周囲の客を含めて最悪な気分になるだろう。自分の気持ちよくなることばかりでなく、たまにも市民のことも考えてやれよ、頭と心の弱い、マゾ警官君。」
「そういうわけで……」
視線。他の客も全て、向こう側か、こちら側の、誰かなのだろうと思われた。建物の向こう側から、川名が見ている。川名以外にもきっと監視している。こちら側あちら側共にだろう。鉢合わせして、互いに殺しあってくたばったらいい。漠然と考えながら、機械的に話し続けていた。疲れないコツだ。疲れないコツ、心に風船でも付けるようにして飛ばすこと。そういえば、美里が同じようなことを言っていたっけ。
「どういうことだ?」
質問にも、あらかじめ用意した回答で応える。馬鹿のように納得する公豚老害共。それっぽくにおわせても気が付かない。何故、どうして気が付かない。よほど木崎と示し合わせた合図を送ろうか迷ってやめた。事務所に八代達が来た時、一体どうなった。どんな目に遭わされた。くだらない合図など、とっくに川名達には筒抜けなのに違いない。川名達に囚われ、助けを求めるべき相手を馬鹿にせざるを得ず、自分が、何者でもない、よくわからない機械のような存在に思えてくる。今に始まったことでなく、以前からそうであった。どうしてこんな無能豚に報告を届けないといけないのか。命を懸けるほどの価値はあるのか。意思を殺せ。機械、自動機械。おや、と霧野は思った。これでは最早どちらの味方なのかもわからない。自分が反転していく感覚。自分が自分ではない何者かと思う習慣が身についていた。以前から、澤野であるときは霧野でなかったが、それがもっと濃くなった。
刑事たちと対峙する前、山上の川名の別邸、コテージ風の別荘で、川名と軽く食を共にすることになった。元々は二条や美里を誘うつもりであったようで、食事は三人分、テーブルの上に運ばれてくる。料理人や配膳係、それから見張りのつもりか、黒ずくめの男が何人か手配された。部屋の南面はガラス張りになって、小高い山の上から、森と街が見えた。香り高い食事の数々。部屋の中で呆然と立ち尽くす霧野に対して、席に着くか、床に侍るか、川名は霧野に選択させるのだった。思わず鼻で笑った。
「ふん、なに、選ばせるようなことですか。」
霧野が自信満々の半笑いで椅子の背に手をかけて、先に向かいに腰掛けた川名を見下げた。何もない席、その椅子を引きかけたところで、手が止まる。考えるより先に電流でも走ったように身体が止まったのだった。
「……。どうした?」
静かな、しかし含みのある声。川名が挑発的に霧野を眺めていた。川名と自分の間で生まれた奇妙な感情を振り切るようにして、無理やり川名の対面に座るのだった。
「お前の好きなものを別に頼んでおいたから、好きに、思う存分に食べてから向かうと良い。腹が減っていてはせっかくの頭もまともに働かないだろうし、余計な気を起こされても困るから。」
霧野の目の前にも料理が運ばれてきた。半焼けのレアの肉だった。ほくほくと目の前で、生に近い、肉食獣の好みそうな、殆ど人工的な調理はくわえられていない生焼けの肉が湯気を立て、じゅうじゅうと激しく肉汁と蕩ける脂を滴らせ、血と香草の匂いが漂った。鼻先に突き付けられた久々の美食の香りに気が狂わんばかり。心臓が激しく強く高鳴り、眩暈するほどであった。
口の中に生暖かい液体が漲って溢れた。まるで性交のように、激しい昂ぶりが身体の奥底から溢れて出、声まで漏れ出そうであった。それで、必死に平静を装って「何をたくらんでいるか知りませんが……」とかなんとか微笑して答える。いらねぇんだよ、こんな、馬鹿にして!と堂々きっぱり言えたら如何に良かったか。内臓がうねる。音を立てる。口から溢れでる息の飢えていること。意地を張ることの無駄さ。
「いらないのか?やっぱり人工物、ドッグフードがいいか?せっかくの、いい肉なのに。」
川名が無邪気に言って首を傾げた。霧野は腕を組んで軽く指を噛んだ。
「何の肉ですか、これ、まさか、木崎の肉なんて言うんじゃないでしょうね。」
「何を言ってる。仔羊だよ。こうなる前のも見て、抱いてもみたけれど、とても可愛かったぞ。」
霧野は灼ける子羊を見下ろし、それからまた、川名を上目遣った。川名は水に口つけながら、霧野を観察するように見ていた。ここで、おいそれと手を付けては、貴方の仲間になりましたよ、くだりましたよ、と腹を見せ尻尾を振って言ってるようなものではないのか。目の前のこれが、どうしようもない、奴隷のような、刑務所のような餌であったなら、まだ食べることができただろう。
「食わないか。仕方が無いなぁ。持ち帰ってノアにでもやることにするか。」
川名が、傍らに置かれたベルを鳴らすと、すぐドアの向こうからボーイが現われ、霧野の目の前の肉をさっさと持っていってしまった。霧野は唾をのんで耐え、テーブルの下で拳を握っていた。もし最初に、床に侍ることを選んでいたら、と思わずにおえなかった。そうすれば、きっと、食べられた。一階層人間を降りているから、無駄なプライド、意地を張らずに、喰わされているという精神でもしかしたら、喰いえたかもしれかったのに。椅子の背に手をかけた時の、何とも言えない厭な感じの正体はこれに違いないと霧野は思うことにした。
待て。の状態にさせられたまま、何もなくなった空間、それから二条と美里の不在により、冷めていく人間の食事をちらちらと見ながら、勝手に手を付けたらどうなるだろうかと想像する。川名に肉を引き裂かれる罰を与えられる妄想。彼の足元で打ちひしがれる自分の姿が頭の中に浮かんでは消えた。裂かれた肉から飛沫する血が、川名の顔と青白い手の甲の上に散って、彼の尖った舌が舐めとって爛れ腐った獣の血は不味いと言う。自分の姿が子羊の肉と被ってくる。皿の上で半生に焼かれてナイフで均等に刻まれ、今まさに喰われようとする肉塊。
目の前で、一つの破片も散らさず、機械的に食事をとる男。食べ物の方から進んで彼の中に吸収されていくかのようだった。些細な仕草一つとっても、非の打ち所がないのだ。彼が歩いている後ろ姿。気だるげに、この世のすべてに興味をなくしている時、時に芯から矜持を持って歩いている時、どちらも、人を寄せ付けなかった。逆に人を寄せ付けたいときは、そういう時用のラフなふるまいを敢えてしていた。川名の視線が時折、霧野をなぞるようにして、度々何か話すことを促す。澤野だったら気の利いたことの一つでも言えるのに、何も言えないで固まっていると、彼は口元に憐れみの笑みを浮かべるのだった。
いやしくも、余っているそれらを喰っていいですかの一言さえ、首を上から掴まれているようで、つばを飲み込むだけで、言えない。もし、今その、足元に、地に、さっきまでのお屋敷でのような獣の役目で這っていたなら、川名の指示通り媚びて、もしかしたら、人間の美味しい食べ物の欠片の一つでも食べられたかもしれないのに、と思いながら、霧野は自身が空腹のあまりおかしな異常な思想に堕ちこんでいるぞ、と、心の中で激しく己を叱咤し、自らの太ももに爪をたてた。また、腹が鳴って、天を仰いだ。
「もう、よすか?」
やけに優しい猫撫で声で、ようやく川名が喋ったと思い目を合わせた。彼はとっくに目の前の物を平らげて、オレンジ色のシャーベットが運ばれ、小さなコーヒーカップから香ばしい香りが漂っていた。
「よす?一体何を……」
「人間ごっこ。」
霧野は一瞬笑いかけたが、笑えなくなって、川名を眺めた。
「お前には、俺の元に来る前まで交際していた女が幾人かいたようだが、最後の女にお前はまだ未練があるようだな。確かに彼女はお前のような人間以下の犬には、もったいないほどの器量の女だったようだ。」
「……ありませんよ、一体何年前の話をしてるんだ。」
「ああ、そう。じゃあ」
「だからと言って、殺されて気にしない程の、鬼畜の精神は私にはありません。貴方とは違うから。」
「そうか、それは良かった。念のためそれを、お前の口から、聞いておきたかった。何の罪もないお嬢さん、強いて言えばお前のような被虐癖の果てしない変態色欲狂の隠れホモ野郎と、それを知らずに関係を持ってしまったという哀れな罪のあるお嬢さんを無駄死にさせても、俺だって心が痛むんだよ。さて、これからのほんの数刻の間、お前を元のように自由にさせてみるが、お前を許したわけではないからな、態度を心得ろよ。酷い目に遭うのはお前だけでは済まない。お前から心からの謝罪をもらったわけでもない。皆に、身体を少しずつ屠られ、弄られて、惨めに泣いて、時に許しを乞うたが、そんなその場限りの、噓の言葉を聞いたところでな。」
「……」
「しかし、お前のその肉体からは徐々に、本当の叫びが聞こえるようになってきた。人間の脳など、所詮本能の動きに対して後付けで思考をして、脳の持ち主にフィードバックを繰り返すだけの電子機械。で、さらにそのフィードバックから遅れて、意識的に考えて、あるいは考えたふりをして、言葉が口を出ていく。お前のような病的な嘘つきは、ここの意識的な部分が異常に発達しているのだ。だから、病的な速さで、出まかせを吐ける。それを本当と思っている節さえある。すると、本当のことも、そのしょうもない意識に掻き消されて、本人さえ何が自分にとって良く、何が自分にとって悪いのかさえ、よくわからぬ状態になる。今まで随分つらかったろう。」
「……。……、ははは、気味の悪いプロファイリングだ。じゃあ私から言わせてもらいますが、病的な嘘つきは貴方だってそうでは。じゃなければ犯罪を隠し通すことなんてとてもできない。」
「そうだよ。だから誰よりもお前のことがわかるんじゃないかよ。だがお前と違う点は、俺はある地点から、自分の本能になるべく忠実に従おうと、心の声を聞いてやろうと、誠心誠意心掛けるようにしたのだ。自分の本能と欲望を自分で手なづける。だから無自覚な嘘はつかないし、俺はお前と違って常に、自分自身で居るつもりで自分を見失うことなどない。お前はきっと自分の病的で邪の本能の発露として、正義の、お巡りさんになったのでは。まあ、どうせ、誰よりも俺なんかよりも、底意地の悪いお前のことだ。何癖付けて、違うといいはるだろうが、どこかに確実にその気持ちがあったはず。何年もの間、そういう人間を進んで集めてきたのだから、俺の目に狂いはない。ある種の救済のつもりでもあるんだな。お前達ような哀れなモノを飼って管理してやるのが俺の使命の一つで、この実につまらない世界の中で幾分か、心躍ることでもある。」
「救済?は!救済だって?どこが!かっこつけても、ただの変態の集まりじゃねぇかよ。さっきから好き放題言って。俺のことばかり散々いうが、問題は俺ではない。アンタを筆頭に変態残虐嗜好者の集まりなのが問題なんだ。一人の人間に、それも俺のようなのに寄ってたかって。」
川名はわざと虚を突かれたような顔をして、それから微笑んだ。
「……。その変態共の中で、まさに、他の誰よりも悦んでいるのはお前自身だと思うけど。今も、それから、昔もな。本当は自分が一番わかっているくせに。」
「わからない、っ、わかりたくもない、」
霧野の上ずった叫びに、川名は、ふふふ、と笑って片手をテーブルにつきながら、立ち上がった。それから、一瞬外の景色を眺め、霧野を見降ろした。
「強がって。わかりたくもないだと?じゃあ今から、別の部屋で軽くお前を打ってやるから、欲情せずにいられるか試そうじゃないか。どうだ?それで。お前が、お前が今しがたその口から言った通り、わからず、ただ痛みに苦しむ常人というなら、お前に一言、謝罪しよう。見誤ったと。それから、俺のいないところで犬のお前に、俺と全く同じ食事をとらせてやる。嬉しいな。お前、俺が側に居ると、俺のことが気になるのだろう?」
「……。駄目だったら?」
「おや、そんなこと考える必要があるのか。お前が言いだしたことだぜ。さ、出ようか。」
川名に通された洋広間は、舞踏会でも開けそうなほど広く、やはり南側一面がガラス張りになって、深紅のカーテンは開け放たれていた。芝が植えられた庭、その向こうに街並みが見渡せる景色、傾き始めた光が差し込む。電機などつけなくても十分明るい。天井が高く、梁が幾らかめぐらされて、何かを吊るすのには良さそうであった。壁に複数の鞭が飾られていた。木材と革の匂いがする。鞭の他、大きなふたつ飾り棚が設置されて、棚の上に霧野が使用用途を想像できるものとそうでない物とが、丁寧に並べられ飾られて、何も言わなければ、淫具にさえみえないかもしれない。他に扉の閉じられた重量感ある棚が三つほど並べれた。部屋の隅に、暖炉があり、近くに大きなテーブルと、ソファが並べられている。それにしても、何もない空間が圧倒的な面積を占めた。廊下には黒服の男が二人、控えている。
床に何か怪しい染みがある。奇麗好きな彼のことだ。拭き忘れではない。これは、消え無い染みなのだ。川名の別荘には、何度か来たが、この広間に通されたのは初めてのことだった。霧野が部屋を見回し、立ち尽くしている中、川名の刺すような視線に気が付いた。そうだ、と思って衣服に手をかけた。開放的な空間で裸であることは、川名と一対一であるというのに、羞恥心を普段より掻き立てた。剝き出しの身体で、彼の近くに行き、膝をついた。後ろから光に照らされて、彼の姿が普段より大きく重厚に見えた。真っ白い紙に墨汁を一滴たらしたような、彼がそこに居るだけで、部屋の空気が鎮圧されるようだ。開放的だったはずの部屋、しかし、彼の瞳を見ていると、四方から壁が音を立てて迫ってきて、圧し潰されそうな感覚に陥る。
「そうだな。それから、次は。」
刺す、射るような声質。優しいのに深みと厳しさがある。それから。彼の前で手をついて、頭を下げた。霧野は咄嗟に、もう、やばいぞ、と思った。このままでは、これだけで、まだ鞭打ちが始まってさえいないのに、屈辱感と羞恥と、圧倒される感覚で、川名に、最悪の証明をして敗北してしまうかもしれなかった。
霧野は床の上で惨めに丸くなって、身体を擦るようにして誤魔化していた。川名はそれがわかっているのか、霧野の目の前を右に左に歩き始め、彼の歩くたびに彼の身に着けた革の匂い、ほんの微かなウッド調の香水の香り、そして獣、懐かしさを感じるような、先輩犬ノアの彼にこすりつけたらしい雄の臭気がわずかに漂うのだった。川名は、壁際から一本、乗馬鞭をとって、鞭で空をひゅんひゅんと言わせ始めた。ひゅっひゅっ、音を立てる鞭、それが、今まさに身に降りかかる、今か、今か、という、そんな厭な予感と期待が、恐怖やスリルに付随する興奮となって、霧野の、傷跡に彩られた光沢あるつややかな赤白い身体の表面をぷつぷつと鳥肌を立て、霧野の湿った裸足のつま先が居心地悪そうに丸まった。川名の足が止まった。
「ハル。まだなんにもしていないぞ。」
「く…ぅ…」
「身体が軽く震えているようだが、大丈夫か?」
「あ……、は」
ひゅっ!という音と、背中の右上側に焼け弾ける感じ。歯をぐぅと食いしばった。はじまった。肩甲骨のあたりに鋭い打撃が決まっていた。右腕が特にがくんがくんと震えた。使用された乗馬鞭の先端の小さな面は。二センチ×四センチ程度、一点の肉に刺激を与え、目の前で軽く光が散った。小娘のつま先のような物だ。それが肉を弾いて痛ませる。痛みは背中に与えられたはずなのに、熱くなるのは、そこだけではなかった。
「まさか今、はい、とでも言おうとしたか。違うよな。ハル。」
もう一度同じ位置をスタンプでも押すように、正確に撃ち抜かれて「わん゛!」と吠えていた。
「そうだな。えらいじゃないか。」
するする、と鞭の先端が、霧野の大きな背中を軽く撫で、なぞり撫でた。全身を紅潮させ、はぁはぁと息づく。きつく閉じていた目を薄っすらと開いた。霧野の眉目が左右非対称になって、被虐の欲望を認めると認めないとの間で揺れていた。
……。
背が、痛む。目の前の刑事に報告を続けながら、さっきから視界の端にチラつく男のことを考えた。きっと神崎がこの場を取り付けるのに一役買ったのだろうという確信に近いものがあった。目の前の無能豚が思いつくとはとても思えないし、わざわざ彼が出向くということはそういうことなのだ。美里を使者としたかいが多少なりとも報われたと言える。久しぶりに見る神崎の姿は、以前より鋭さを増して見えた。
霧野は、自分自身の張り付いた様な冷淡な表情の下、助けて!助けて!と叫んだ。同時にその神崎に対して、強い憎悪の感情、幼稚な苛立ちも芽生えはじめた。ここまででてきて、どうして直接手を伸ばしてこない。人が、目の前で溺れているのだぞ。それからまた、心の中で助けを乞うことしかできぬ情けない自分にがっかりするのだった。
神崎を見ていると、何故か、一時忘れていた肉の痛みが蘇り、熱くなっていった。紋様のように、身体に絡みつき、背後から抱かれれでもいるように、よくなじんで、存在を主張する。先刻の五発。
……。
「五発だ、たったの五発。耐えてみせろ。」
川名の手の中に、革で編み上げられた長さ1メートルをゆうに超えた女の髪のように真っ黒い、光沢の強い一本鞭がしな垂れていた。彼は慣れた手つきでそれをなで、引き絞るように伸ばした。ぎぎぎ、と鞭が啼いた。なんとも言えない香ばしいような匂いと鉄の臭いするのを嗅いだ。
「これは幾分か使い込まれたものだ。匂うか?人の皮を破り、皮脂と汗と血とを吸って柔らかくなったのだ。」
霧野は、床の上に四つ這いになっていた。ありがたいことに、残酷な鞭を見せられたことで一瞬恐怖したことで、股間の昂ぶりが少しだけ沈下してまるまったのだった。彼は慣れた手つきで鞭を扱っていたかと思うと、霧野の背面に回った。空中に試し打ちする音、それからすぐ、始まった。背後から背中二発、背骨が弓なりに堕ちる、尻に二発、反対に尻は上がり、猫のような姿、続けざま、最後に、開かれたむちむちとして太ももの間、そこに蛇のような素早さで鞭が踊り、一物を全体を下から巻きとるように、激しい一発が、打ち下ろされた。目の前が激しく明滅し、身体が伏せられ、頭が震え、堪えていた悲鳴が上がった。すっかり身体から力が抜けて、まずは腕を、それから肩、頭、腹まで地面につき、うつ伏せに地に伏してしまう。あ゛、あ゛っ、ううう……と小さく小さく、声が切なく漏れて、痛みに熱くなった身体が冷たい床の上でがくがくと、震えていた。
霧野の周りには、ワインの一滴の雫を堕としたように、肉体を中心として、仄かに周囲に血痕が飛び散って、鉄の臭いを振りまいていた。濃厚で芳醇な香り。背後に、男の立つ気配。零れ落ちた液体のように、霧野の身体は地面に張り付いている。逃げる場所など無く、五発終わったというのに、逃げようと、どこかを掴むように腕が動いていた。しかし、そのような状況下でも、爛れた肉体の下で、一本の、霧野の紅い太魔羅が、激しい呼吸で波打つ厚い腹筋とぬるい床の間で、先刻まで体内に挿入されていた鉄棒よりも、ずっと重く熱い存在感を持って激しく、硬く、膨張、どくどくと脈打って、もう、止まらないのだった。腹の下に隠された酷すぎる蛇淫、膨らみはパンパンに腫れ、蛇淫の代わりに見せつけるように、新しい蚯蚓腫れを二筋もいだだいて、艶を持って汗ばんだ豊かな肉饅頭の間で、犬の可愛らしい裂け目が、引きつって誘うようにしてぶるぶると痙攣していた。
「ん゛ん……くひ……ぃ……」
床の上で、霧野の身体は、悶え、軽くのたうっていた。肉と床が擦れて音を立てるが、霧野から湧き出た汁で、ぬこぬこきゅうきゅうという奇妙な音をたてた。燃える霧野の肉体と反対に冷たい視線が、遥か遥か高み、上から、肉体に注がれつづけ、身体の下に隠された大きくなった欲望まで、よく見透かされているように思える。
どれだけもがいてもあがいても、無意味とわかっている。それでも隠そうと思う程に、息が無様に上がるのだった。隠し切れないことはわかっていて、このまま姿勢を変えてみよ、とたった一言言われたら、たったそれだけで、全てが、明らかになるのだ。それを想像してしまうと、もう、高まりが収まるどころか、ビンビンと、逆に脈打ち、欲望に溺れかけた。息継ぎをしても、息がうまくできず、まだ自分を抑えられると頑張る気持ちと、はやく息の根を止めて欲しいという気持ちとで葛藤した。
「お前の負けだな。」
とどめを刺す声だった。身体と床の間でどくどくと収まるどころかさらに、隠さなければ負けてしまう棒が膨らんでいった。悔し涙か快楽の涙かが目の縁にたまったが堕ちずにいた。見せてみろ、とさえ言ってくれない。身体と仕草と臭いとが代わりに全てを彼に報告する。
……。
霧野は、自分の目の前の男達に、報告する口調が乱雑になってきているのを感じながら、淡々と、あてつけるようにその調子で続けて、また、神崎を見た。神崎は霧野を見ても、表情を変えるでもなく、仏の像のように、伏し目がちに半ば見下すようにして、こちらを見ているかどうかさえ不安だ。いつもそうだった。立場を問わず人を馬鹿にした冷めたその感じ。そういうところが、人として好きであり、嫌いであった。
だから一層、奥さんや新しい女に逃げられて、心の底で傷心している彼を見るのも好きだったのだ。一見わからないが、心の中で、枯れかけの植物のようにしなびて泣いているのだ。酒席で霧野が酔ってしまって介抱された時や、徹夜仕事の延長で神崎の家にいたことが数度あった。朝方、寝覚めの悪い同士ぽやぽやとしている時、誤って神崎が違う名前で霧野を呼び、珍しく赤面していた。お茶をとってくれないか、と言い終えるや否や霧野の顔をじっと見て、はっとしたのだ。霧野は反対に自分の顔が徐々にほころぶのを感じた。
「ふふふ、神崎さん、誰っすか~?それ。」
普段ポカを見せない彼を、ここぞとばかりに馬鹿にしたものだった。それほどに元妻が恋しいようである。
「俺なんかに似ていたのか?くくく、一体どういう女性なのですか。」
彼のことだから、妻がいる時には霧野にしたのと同じように、無神経に違った名前で呼んでしまい、逆鱗に触れたのではなかろうか。何故か神崎のそんな珍しい痴態を思い出した。彼にも乱れることがあるのだ。神崎は霧野の煽りなどは気にしていないという風に無視して黙って自分でお茶を入れていたが、湯のみから茶が溢れそうになっていた。
「というわけで、この件は片付いています。」
神崎の瞳が、霧野の方にわずかに持ち上がって、じっと見た。また、助けて、と声に出しかけると同時、急に、背中に川名から加えられた鞭の痕が痛んで、幻聴を聴き、抱かれた。思わず「ああ‥…っ」とこの場にそぐわない、淫靡な声が出そうになった。この傷を、神崎が見たらどう思うだろうと思った。悲しむか、怒るか、単なる尋問、拷問の痕と判断するだろうか。気が付くだろうか。考え始め、神崎の視線を余計に”感じ”てしまい、屠られた箇所が次々と、熱を持った記憶と共に蘇り、もはや、平静を装えなくなってきた。顔が熱いのだった。それから、神崎を劣情の、揺れる視線で眺めてみても彼の表情は一切変わらず、己が責め立てられているような気になってくる。散々神崎以外の刑事を無能豚と心の中で見下し、罵ったが、一番の無能豚は、お前だろう、と彼から言われているような気分になるし、彼なら言いかねなかった。鼓動がどんどんと速くなる。視線が、さだまらなくなり、卑屈な笑みがでてきた。
「すみません、少し、トイレに。」と、乱暴に席をに立った。
そのまま、逃げようという気も無い。何の策もないまま、無暗に逃走するのは、自殺行為。立ったと同時に眩暈する。視界が歪む。背後から人のついてくる気配がある。川名がこの場に居るわけも居るはずもないのに、身体に何かを施されているわけでもないのにすぐ側に彼がいるように思われる。彼の証がまた、じん、と熱を持って痛むのだ。衣服に擦れて、尻を、秘所をほじくられ、触られているような気分になる。歩いてるだけなのに、十字架をしょわされて、鉄板の上を歩いてるよう、皆の視線を感じた。罪の意識さえ、頭をおかしくさせる。
「……。」
喫茶店にしては広い化粧室、やはり幻覚ではなく、背後に付いてくる者がいる。
背後に居る人間をいくらか想像しながら、振り向いた。
……。
「これじゃ、お前の情けの無く、さもしい肉欲の象徴を、はっきり見なくたってわかる、お前の全身が物語っている。こんなに簡単なことで。何か言い訳はあるか?」
川名が地に伏した灼熱の肉塊のすぐ横に立って、尻を、上から足で踏みつけるのだった。ぐりぐりと肉を揺らされると、高い女のような声が出ていった。身体の奥の熱芯がゆらされ、内にこもった熱、身体の中で焚火でもしているかのような熱が、息をと共に漏れ、吐くと涎が再現なく垂れ、人語とは言えない声がぐるぐると漏れ出ていった。言い訳、俺は違う、違うのだ、と思って、首を横に振るまではできるのだが、何一つ言葉が浮かばず痴呆のように、ぼーっとしていた。川名の言葉がぐるぐると頭の中を回って傷が熱い。違うと言って違わないのだから、それよりも、これから確実にクルであろう懲罰に怯えた。負けたのだから、さらに懲罰がくわえられるのだ。顔をあげられない。頭を掴まれているわけでもないのに、大きな手に上から押さえつけられているようだった。
「珍しく大人しいじゃないか、犬。そんなに激しくしたわけでもないのに。」
「……、……。」
「自分から俺に対して啖呵をきっておいて、無様に負けたのだから、覚悟はできているだろうな。」
役目を終えてしなだれた鞭の先端が、蛇の舌のように、ちろちろと霧野の背中を擽っていた。
「ァぁ‥…」
ゾクゾクと背筋を微電流が流れていった。身体が小刻みに震えた。そこに声が挿しこまれて、脳を突かれた。
「普段の仕事と同じこと。お前は、これからは俺の下で二つの仕事に奉仕していくしかないのだ。表でやりあう普段の仕事と、裏で奉仕する仕事と。おや?これでは前とそんなに変わらないな。割合を、一対九くらいにするのがお前のようなのには、ちょうどいいかな?とにかく、後から、この負けについては、厳しく制裁してやるから、楽しみにしておくといい。思いつめて、くれぐれも仕事中に勃起などしないようにな。しかし、今ので一層腹が減っただろう。喰わせてやる。ノアの、喰いきれず余ってるのがあるから、すぐにノアの古い、おさがりの皿にでも盛って持ってこさせよう。それを俺の足元で、奇麗に舐め、食べるんだよ、わかったか、ハル。」
霧野は餌の姿を思い浮かべ、物言わぬ代わりに、姿勢を崩して川名に流し目を送っていた。川名がじっと霧野の様子をうかがっていてた。
「なるほど……それくらいでは、ドマゾのお前には物足りないとでも言いたいか。上から、いろいろと、かけて、欲しいのだろう?そうなのだろう?おやおや?それでは、まるで、ご褒美じゃないかぁ……??なぁ……霧野……。あの餌が、そんなにうれしかったのか。つけあがって。これから仕事が無ければ、お前を肥溜めの中にでも頭からつっこませて嫌という程喰わせてやったってよかったが、お前が強烈な悪臭を振りまきながら、元同僚たちに会ったら、相手方はどう思う。ただでさえ今のお前は獣臭くて臭くてたまらんのに。周囲の客を含めて最悪な気分になるだろう。自分の気持ちよくなることばかりでなく、たまにも市民のことも考えてやれよ、頭と心の弱い、マゾ警官君。」
73
あなたにおすすめの小説

邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。


上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。

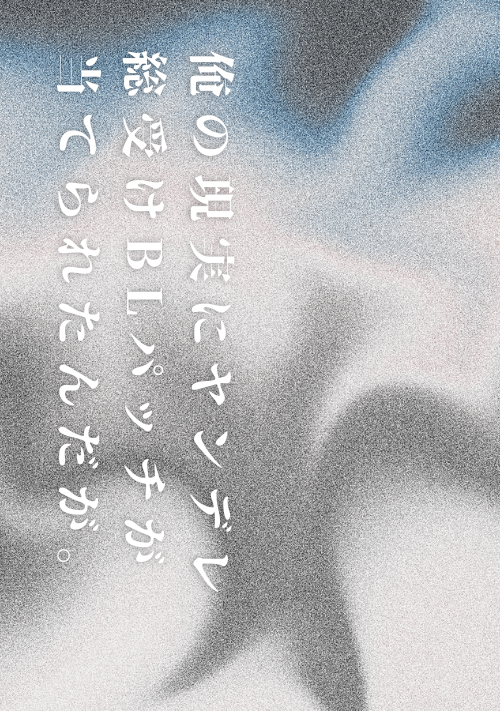

今度こそ、どんな診療が俺を 待っているのか
相馬昴
BL
強靭な肉体を持つ男・相馬昴は、診療台の上で運命に翻弄されていく。
相手は、年下の執着攻め——そして、彼一人では終わらない。
ガチムチ受け×年下×複数攻めという禁断の関係が、徐々に相馬の本能を暴いていく。
雄の香りと快楽に塗れながら、男たちの欲望の的となる彼の身体。
その結末は、甘美な支配か、それとも——
背徳的な医師×患者、欲と心理が交錯する濃密BL長編!
https://ci-en.dlsite.com/creator/30033/article/1422322

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















