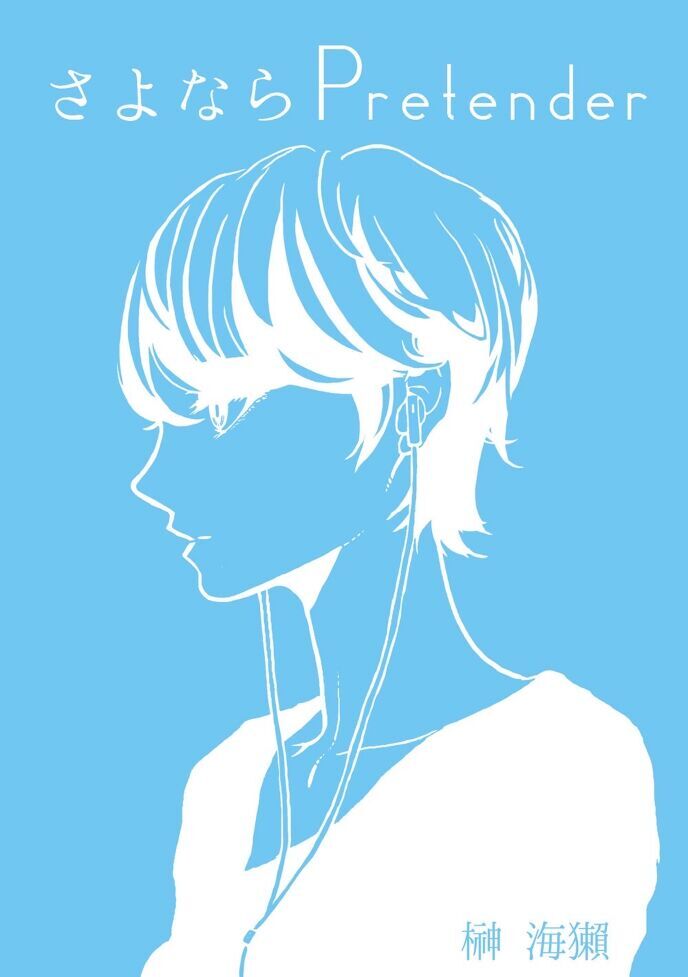5 / 16
高気圧ガール
しおりを挟む
カーステから山下達郎が流れている。それに合わせて君が歌う。
”2000マイル飛び越えて、迎えに来たのさ
Come With Me 連れて行っておくれよ”
夏も終わりに近付き、僕と淳の仕事は順風満帆だった。新作アプリゲームのデザイナーが無事に決まり、打ち合わせを重ねて、最終確認の段階まで来ていた。後は契約書を取り交わせば、僕らの手を離れることになる。
今回僕は資料作成とメールでのやり取りがメインで、営業や接待など先方と対面でのやり取りは淳が担っていた。ほとんど淳のお手柄だろう。
「いやー。さすが淳。でも良く通ったよな。」
「この前の会合の席で分かったんだけどさ、担当の中村さんが神楽坂マイの大ファンだったんだよ。」
「ほー。あの中村さんがね。人は見かけに寄らんね。」
「で、ウチで神楽坂マイのデザイナーの仲介したことを話したら、もう乗り気になっちゃってさ。こっちとしても助かったよ。他当たらなくて良くなったんだから。」
そう言うと、淳はねぎま串を口に運び、レモンサワーで流し込んだ。
「でも、月永先生さすがだよな。上手く神楽坂マイのテイストを残しつつ、全くの別物に仕上げるなんて。」
「そりゃ伊達に長くデザイナーやってないよ。」
「そうだよな。てか、あの人曲者って聞いたけど、淳よく上手く纏めたよね。」
「まだ油断は出来ないけどな。てかさ、徹の資料に結構助けられたよ。説明しなくても、資料見せれば一発なんだもん。出来る男は違うね。このこの。」
「へへん。」
「何それ。」
「なんでもない。」
8月26日。新橋にある焼き鳥屋 鳥藤で、僕らは初めて任されたプロジェクトの順調ぶりを祝して乾杯をした。この後待ち受ける苦難を知りもせずに。
「じゃあな。風邪引くなよ。」
「お前もな。」
散々飲んだ僕らは、山手線の上野駅で解散した。日比谷線の改札を潜りホームへ向かう。金曜日の夜ということもあり、顔を赤らめた人々が散見した。滑り込んだ日比谷線に乗り込む。すると、聴き慣れた声が背後から響いた。
「徹じゃーん。」
その声と同時に腰元に膝蹴りが入る。
「痛っ。あ。千夏。何すんだよ。てか、今帰りか?」
彼女の頬が薄ら赤く染まっている。酔っているのだろうか。
「そうそう。ちょっと飲み会があってさ。徹は?」
「俺もそんなとこ。」
「なんか飲んでる割に冷静だよね。」
「そうか?」
「そうだよ。あー。あたしと飲み直したいんでしょ?」
「それはそっちだろ。」
「あはは。バレたか。」
「バレバレだから。」
北千住に着き、バーという気分でもなかったので、僕らはコンビニで酒とつまみを買って彼女の家へ向かった。
「てかさ、帰りの電車で会うとか奇跡じゃない?」
「まぁ確かにな。なかなかレアだよな。」
「そうだよ。運命感じちゃうよ。」
「どんな運命だよ。」
「酔っ払い同士引きつけ合う運命だよ。」
「そんな運命要らんわ。」
笑い声の絶えない、いつも通りの帰り道だった。ここまでは。
ここから会話は予期せぬ方向へ走り出す。
「そういえばさ、今年まだ海見てないんだわ。連れてってよ。徹。」
この一言で事態は急変する。
「海って、お前なぁ。簡単に言うけど、そんなすぐ行ける距離に海無いぞ。」
「だーかーらー。徹免許くらい持ってるでしょ? レンタカーで連れてってよ。」
「まぁ持ってるけどさ。それはちょっと図々しすぎないか?」
「いいじゃん! いいじゃん! きっと楽しいよ。私と海。あーんなことやこーんなことが待ってるよ?」
そう言うと彼女は目配せした。
「どんなことだよ。」
「それは行ってからのお・た・の・し・み。」
「仕方ないなぁ。分かったよ。」
「じゃあ、来週の土曜日ね!」
「おい。ちょっと待っ、、、。空いてるわー。」
「おー! じゃあ決定ね!」
「はいよ。」
突然にしてすんなりと、千夏との初デートが決まった。
9月3日。快晴。僕らはレンタカーに乗り込み、湘南を目指した。カーステから山下達郎が流れている。それに合わせて君が歌っている。
「なぁ。湘南だから、普通はサザンかTUBEじゃないか?」
「いーの。達郎が好きなの。ふふふふ~ん♫」
Bメロ?サビ?以外は鼻歌だった。でも、そこがまた可愛かった。
助手席に高気圧ガールを乗せた乗用車は、夏の名残りを含んだ日差しをいっぱいに浴びながら、国道134号線を進んでいく。程なくして辿り着いたのは、片瀬海岸だ。
「海の家やってないじゃん。とうもろこし食べたかったのに。」
駄々を捏ねる子どものように彼女が言う。
「9月なんだから当たり前だろ。」
「海の家はさ、もうちょい頑張れよ。」
「無理言うなって。」
彼女は一瞬膨れて、弾けるように笑顔に戻った。
「海だー!!!」
両手を広げ、全身に潮風を浴びる彼女は、まるでタイタニックのそれを再現しているか、はたまたGLAYのTERUの真似しているかのように見えた。
「ねぇ。徹。海の匂いがするよ。」
「海なんだから、そりゃそうだ。」
「えへへへ。」
今思えば、夏の風と共に現れた彼女は、どんな時も輝いて見えた。水面を反射する光のように、キラキラ、キラキラ、キラキラと。
To be continued.
Next story→『サマーヌード』
”2000マイル飛び越えて、迎えに来たのさ
Come With Me 連れて行っておくれよ”
夏も終わりに近付き、僕と淳の仕事は順風満帆だった。新作アプリゲームのデザイナーが無事に決まり、打ち合わせを重ねて、最終確認の段階まで来ていた。後は契約書を取り交わせば、僕らの手を離れることになる。
今回僕は資料作成とメールでのやり取りがメインで、営業や接待など先方と対面でのやり取りは淳が担っていた。ほとんど淳のお手柄だろう。
「いやー。さすが淳。でも良く通ったよな。」
「この前の会合の席で分かったんだけどさ、担当の中村さんが神楽坂マイの大ファンだったんだよ。」
「ほー。あの中村さんがね。人は見かけに寄らんね。」
「で、ウチで神楽坂マイのデザイナーの仲介したことを話したら、もう乗り気になっちゃってさ。こっちとしても助かったよ。他当たらなくて良くなったんだから。」
そう言うと、淳はねぎま串を口に運び、レモンサワーで流し込んだ。
「でも、月永先生さすがだよな。上手く神楽坂マイのテイストを残しつつ、全くの別物に仕上げるなんて。」
「そりゃ伊達に長くデザイナーやってないよ。」
「そうだよな。てか、あの人曲者って聞いたけど、淳よく上手く纏めたよね。」
「まだ油断は出来ないけどな。てかさ、徹の資料に結構助けられたよ。説明しなくても、資料見せれば一発なんだもん。出来る男は違うね。このこの。」
「へへん。」
「何それ。」
「なんでもない。」
8月26日。新橋にある焼き鳥屋 鳥藤で、僕らは初めて任されたプロジェクトの順調ぶりを祝して乾杯をした。この後待ち受ける苦難を知りもせずに。
「じゃあな。風邪引くなよ。」
「お前もな。」
散々飲んだ僕らは、山手線の上野駅で解散した。日比谷線の改札を潜りホームへ向かう。金曜日の夜ということもあり、顔を赤らめた人々が散見した。滑り込んだ日比谷線に乗り込む。すると、聴き慣れた声が背後から響いた。
「徹じゃーん。」
その声と同時に腰元に膝蹴りが入る。
「痛っ。あ。千夏。何すんだよ。てか、今帰りか?」
彼女の頬が薄ら赤く染まっている。酔っているのだろうか。
「そうそう。ちょっと飲み会があってさ。徹は?」
「俺もそんなとこ。」
「なんか飲んでる割に冷静だよね。」
「そうか?」
「そうだよ。あー。あたしと飲み直したいんでしょ?」
「それはそっちだろ。」
「あはは。バレたか。」
「バレバレだから。」
北千住に着き、バーという気分でもなかったので、僕らはコンビニで酒とつまみを買って彼女の家へ向かった。
「てかさ、帰りの電車で会うとか奇跡じゃない?」
「まぁ確かにな。なかなかレアだよな。」
「そうだよ。運命感じちゃうよ。」
「どんな運命だよ。」
「酔っ払い同士引きつけ合う運命だよ。」
「そんな運命要らんわ。」
笑い声の絶えない、いつも通りの帰り道だった。ここまでは。
ここから会話は予期せぬ方向へ走り出す。
「そういえばさ、今年まだ海見てないんだわ。連れてってよ。徹。」
この一言で事態は急変する。
「海って、お前なぁ。簡単に言うけど、そんなすぐ行ける距離に海無いぞ。」
「だーかーらー。徹免許くらい持ってるでしょ? レンタカーで連れてってよ。」
「まぁ持ってるけどさ。それはちょっと図々しすぎないか?」
「いいじゃん! いいじゃん! きっと楽しいよ。私と海。あーんなことやこーんなことが待ってるよ?」
そう言うと彼女は目配せした。
「どんなことだよ。」
「それは行ってからのお・た・の・し・み。」
「仕方ないなぁ。分かったよ。」
「じゃあ、来週の土曜日ね!」
「おい。ちょっと待っ、、、。空いてるわー。」
「おー! じゃあ決定ね!」
「はいよ。」
突然にしてすんなりと、千夏との初デートが決まった。
9月3日。快晴。僕らはレンタカーに乗り込み、湘南を目指した。カーステから山下達郎が流れている。それに合わせて君が歌っている。
「なぁ。湘南だから、普通はサザンかTUBEじゃないか?」
「いーの。達郎が好きなの。ふふふふ~ん♫」
Bメロ?サビ?以外は鼻歌だった。でも、そこがまた可愛かった。
助手席に高気圧ガールを乗せた乗用車は、夏の名残りを含んだ日差しをいっぱいに浴びながら、国道134号線を進んでいく。程なくして辿り着いたのは、片瀬海岸だ。
「海の家やってないじゃん。とうもろこし食べたかったのに。」
駄々を捏ねる子どものように彼女が言う。
「9月なんだから当たり前だろ。」
「海の家はさ、もうちょい頑張れよ。」
「無理言うなって。」
彼女は一瞬膨れて、弾けるように笑顔に戻った。
「海だー!!!」
両手を広げ、全身に潮風を浴びる彼女は、まるでタイタニックのそれを再現しているか、はたまたGLAYのTERUの真似しているかのように見えた。
「ねぇ。徹。海の匂いがするよ。」
「海なんだから、そりゃそうだ。」
「えへへへ。」
今思えば、夏の風と共に現れた彼女は、どんな時も輝いて見えた。水面を反射する光のように、キラキラ、キラキラ、キラキラと。
To be continued.
Next story→『サマーヌード』
0
あなたにおすすめの小説

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました
桜あずみ
恋愛
異世界に転移して2年。
言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。
しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。
──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。
その一行が、彼の目に留まった。
「この文字を書いたのは、あなたですか?」
美しく、完璧で、どこか現実離れした男。
日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。
最初はただの好奇心だと思っていた。
けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。
彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。

狼隊長さんは、私のやわはだのトリコになりました。
汐瀬うに
恋愛
目が覚めたら、そこは獣人たちの国だった。
元看護師の百合は、この世界では珍しい“ヒト”として、狐の婆さんが仕切る風呂屋で働くことになる。
与えられた仕事は、獣人のお客を湯に通し、その体を洗ってもてなすこと。
本来ならこの先にあるはずの行為まで求められてもおかしくないのに、百合の素肌で背中を撫でられた獣人たちは、皆ふわふわの毛皮を揺らして眠りに落ちてしまうのだった。
人間の肌は、獣人にとって子犬の毛並みのようなもの――そう気づいた時には、百合は「眠りを売る“やわはだ嬢”」として静かな人気者になっていた。
そんな百合の元へある日、一つの依頼が舞い込む。
「眠れない狼隊長を、あんたの手で眠らせてやってほしい」
戦場の静けさに怯え、目を閉じれば仲間の最期がよみがえる狼隊長ライガ。
誰よりも強くあろうとする男の震えに触れた百合は、自分もまた失った人を忘れられずにいることを思い出す。
やわらかな人肌と、眠れない心。
静けさを怖がるふたりが、湯気の向こうで少しずつ寄り添っていく、獣人×ヒトの異世界恋愛譚。
[こちらは以前あげていた「やわはだの、お風呂やさん」の改稿ver.になります]


彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

短編【シークレットベビー】契約結婚の初夜の後でいきなり離縁されたのでお腹の子はひとりで立派に育てます 〜銀の仮面の侯爵と秘密の愛し子〜
美咲アリス
恋愛
レティシアは義母と妹からのいじめから逃げるために契約結婚をする。結婚相手は醜い傷跡を銀の仮面で隠した侯爵のクラウスだ。「どんなに恐ろしいお方かしら⋯⋯」震えながら初夜をむかえるがクラウスは想像以上に甘い初体験を与えてくれた。「私たち、うまくやっていけるかもしれないわ」小さな希望を持つレティシア。だけどなぜかいきなり離縁をされてしまって⋯⋯?


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる