15 / 25
ルデル、侯爵家の仕事ができない
しおりを挟む
ルデル、ついに倒れる
(その瞬間、父侯爵が下した決断は——“廃嫡”か“覚醒”か)
侯爵家・執務室 —— 深夜
ランプの灯火が揺らめき、うずたかく積まれた書類の影を長く伸ばしていた。
静寂を破るのは、荒いペンの走り書きと、ルデルの不規則な呼吸音だけだ。
視界が歪む。文字が踊る。
一行読むたびに、針で刺すような痛みがこめかみを貫いた。
自分が承認しようとしているのが領地の予算案なのか、ただの紙切れなのか、それすらも曖昧になっていく。
執事長ハリントンが、見るに見かねて一歩進み出た。
執事長ハリントン
「ルデル様、今宵はここまでに——。これ以上は、お体に障ります」
ルデル
「だ……まだだ……! 終わらん……!」
ルデルは充血した目で書類を睨みつけ、震える指先でペンを握り直す。
ルデル
「こんな……量……!! 僕がやらねば……父上に、認められ……」
言葉は、うわ言のように途切れた。
汗ばんだ指からペンがすっぽ抜け、黒いインクが白い書類の上に無慈悲な染みを作る。
——あ。
そう思った瞬間、世界が横倒しになった。
ガタンッ!!
椅子ごと崩れ落ちる鈍い音が、執務室に響き渡る。
執事長ハリントン
「ルデル様ッ!!」
老執事が血相を変えて駆け寄る。
床に投げ出されたルデルの身体は、燃えるように熱く、それでいて顔色は死人のように青白かった。
浅く速い呼吸が、喉の奥でヒューヒューと鳴っている。
執事長ハリントン
「……なんと。とうに限界を超えておられたか……!」
ハリントンはすぐさま使用人たちに指示を飛ばした。
「医者を呼べ! 旦那様への報告は私がする!」
意識の闇に落ちていくルデルの耳に、遠く、誰かの怒鳴り声が聞こえた気がした。
翌朝 —— ルデルの寝室
重い瞼を持ち上げると、そこには見慣れない天井があった。
いや、自分の部屋の天井だ。だが、ひどく遠く感じる。
独特な薬の匂いが鼻をつく。
視線を動かすと、枕元に二つの影があった。
沈痛な面持ちの執事長ハリントン。
そして、腕を組み、彫像のように静かに佇む——父、侯爵。
ルデル
「……っ……父、上……?」
掠れた声が出た瞬間、喉が焼け付くように痛んだ。
父侯爵
「起きたか」
その声には、安堵も怒りも混じっていない。ただ、事実を確認するだけの冷徹な響きがあった。
ルデルは反射的に身体を起こそうとしたが、鉛のように重い手足はピクリとも動かない。
ルデル
「……すみませ……ぐっ……書類、が……まだ……」
父侯爵
「謝れとは言わん。寝ていろ」
短く遮る言葉は、氷のように冷たい。
ルデルは唇を噛み、シーツを弱々しく握りしめた。
情けない。あれほど意気込んでおきながら、結局は父に迷惑をかけただけだ。
ルデル
「…………」
沈黙が部屋を支配する。
侯爵は、ベッドに横たわる息子を冷ややかな瞳で見下ろしていた。
やがて、その薄い唇が開き、淡々と、しかし残酷な現実を告げる。
父侯爵
「ルデル。お前が昨晩汚した書類だが——あれは、隣国との通商条約に関する重要機密だ」
ルデルの顔から、さらに血の気が引いた。
父侯爵
「インクの染み一つで、我が家の信用は地に落ちる寸前だった。……インク消しでなんとかなったが、それを理解しているか?」
ルデル
「あ……ああ……」
父侯爵
「己の限界を見誤り、結果として家益を損なう。それを『無能』と言うのだ」
侯爵の言葉が、病身のルデルに容赦なく突き刺さる。
そして、父は決定的な一言を口にした。
父侯爵
「これ以上、お前に執務室へ入ることは許さん。——お前の処遇について、考えがある」
父侯爵「二つだけだ。選べ」
父侯爵
「ルデル。お前が倒れた理由は、過労ではない。理由はただ一つだ」
ルデルは乾いた唇を開こうとしたが、言葉が出てこない。
父の視線が、身体の奥底まで射抜くように鋭い。
父侯爵
「“侯爵家の当主”とは何か。……お前はこれまで、その意味を一度たりとも真剣に考えてこなかったからだ」
ルデル
「…………!」
図星を突かれた衝撃に、ルデルの喉がひくりと震える。
父はベッドの端に手を置き、逃げ場を塞ぐように身を乗り出した。
父侯爵
「よく聞け。——今、この瞬間より、お前に残された選択肢は二つしかない」
部屋の空気が張り詰める。執事長ハリントンも、直立不動のまま主人の言葉を待っている。
父侯爵
「一つ目。死に物狂いで仕事を覚え、真の当主として立つこと」
ルデル
「…………っ」
父侯爵
「二つ目。——廃嫡を受け入れることだ」
ルデル
「っ!!」
その単語が耳に入った瞬間、ルデルの心臓が早鐘を打った。
父侯爵
「廃嫡となれば、お前はもはや我が家の人間ではない。爵位も、財産も、後ろ盾も失う。ただの“平民”として路頭に迷うことになる」
ルデル
「へ、平民……!?」
父侯爵
「そうだ。着る服も、明日の食事すら保証されない身分だ」
ルデルの顔が凍りつき、ガタガタと震えだす。想像すらしたことのない恐怖だった。
ルデル
「……や、やめて……ください……父上……! 私は……この侯爵家の長男で……」
父侯爵
「ならば仕事を覚えろ!!」
雷のような一喝が部屋を揺らした。
父侯爵
「“侯爵”という責任を負う覚悟があるのか。それとも、“侯爵家という甘い蜜”を啜りたいだけなのか。……その違いすらわからぬ愚か者に、家は継がせられん」
父は冷ややかな目でルデルを見下ろし、さらに残酷な事実を突きつける。
父侯爵
「それにな、ルデル。……お前が裏で何をしていたか、知らぬとでも思ったか?」
ルデル
「え……?」
父侯爵
「お前は自分の仕事を、あろうことかアルディ公爵家の令嬢……お前の婚約者に押し付けていただろう」
ルデル
「あ、あれは……彼女が、手伝うと……」
父侯爵
「黙れ。公爵家から連絡があった。彼女もまた、お前の分まで背負い込み、心労で倒れ伏しているとな」
ルデル
「…………」
血の気が引く音が聞こえるようだった。
自分が楽をするために利用していた「逃げ道」が、完全に塞がれたのだ。
父侯爵
「彼女の家も、今はそれどころではない。……お前が甘えたツケは、他家の令嬢の健康すら奪ったのだぞ」
ルデル
「…………っ……ぅ……」
父侯爵
「お前がこの家を継ぐと言うなら、もう誰の背中にも隠れられない。逃げる道は、どこにも残っていないと思え」
突きつけられた現実は、あまりにも重く、冷たい。
自分の無力さと浅ましさが、どうしようもなく惨めだった。
ルデル
「うぅ……っ……ぐすっ……」
プライドも何もかもが崩れ去り、ルデルはまるで叱られた幼子のように、ただ涙をこぼすことしかできなかった。
父侯爵の最後の言葉
父侯爵は、ゆっくりと立ち上がった。
それは、決して勢いのある動作ではなかった。
若い頃なら、書類を机に置いたままでも、何のためらいもなく立ち上がれただろう。
だが今は違う。
椅子の肘掛けに手を置き、
一度、深く息を整え、
膝にかかる負担を確かめるように、わずかに体重を前へ移す。
その一連の動きが、
この男が長い年月を“侯爵として生きてきた”証だった。
椅子が床を擦る音が、静かな執務室に響く。
その音は、不思議なほど大きく、
まるで空気そのものを切り裂いたかのようだった。
ルデルは、その音だけで悟った。
——これは、叱責ではない。
——説教でも、説得でもない。
決断の場だ。
父侯爵の背中は、老いていた。
背筋は、わずかに丸みを帯び、
かつて戦場で馬を駆り、
政務の場で誰よりも声を張り上げていた頃の影はない。
それでも。
その背には、
この家を守り、
この領を支え、
無数の失敗と犠牲を飲み込みながら、なお立ち続けてきた者だけが持つ
圧倒的な重みがあった。
(その瞬間、父侯爵が下した決断は——“廃嫡”か“覚醒”か)
侯爵家・執務室 —— 深夜
ランプの灯火が揺らめき、うずたかく積まれた書類の影を長く伸ばしていた。
静寂を破るのは、荒いペンの走り書きと、ルデルの不規則な呼吸音だけだ。
視界が歪む。文字が踊る。
一行読むたびに、針で刺すような痛みがこめかみを貫いた。
自分が承認しようとしているのが領地の予算案なのか、ただの紙切れなのか、それすらも曖昧になっていく。
執事長ハリントンが、見るに見かねて一歩進み出た。
執事長ハリントン
「ルデル様、今宵はここまでに——。これ以上は、お体に障ります」
ルデル
「だ……まだだ……! 終わらん……!」
ルデルは充血した目で書類を睨みつけ、震える指先でペンを握り直す。
ルデル
「こんな……量……!! 僕がやらねば……父上に、認められ……」
言葉は、うわ言のように途切れた。
汗ばんだ指からペンがすっぽ抜け、黒いインクが白い書類の上に無慈悲な染みを作る。
——あ。
そう思った瞬間、世界が横倒しになった。
ガタンッ!!
椅子ごと崩れ落ちる鈍い音が、執務室に響き渡る。
執事長ハリントン
「ルデル様ッ!!」
老執事が血相を変えて駆け寄る。
床に投げ出されたルデルの身体は、燃えるように熱く、それでいて顔色は死人のように青白かった。
浅く速い呼吸が、喉の奥でヒューヒューと鳴っている。
執事長ハリントン
「……なんと。とうに限界を超えておられたか……!」
ハリントンはすぐさま使用人たちに指示を飛ばした。
「医者を呼べ! 旦那様への報告は私がする!」
意識の闇に落ちていくルデルの耳に、遠く、誰かの怒鳴り声が聞こえた気がした。
翌朝 —— ルデルの寝室
重い瞼を持ち上げると、そこには見慣れない天井があった。
いや、自分の部屋の天井だ。だが、ひどく遠く感じる。
独特な薬の匂いが鼻をつく。
視線を動かすと、枕元に二つの影があった。
沈痛な面持ちの執事長ハリントン。
そして、腕を組み、彫像のように静かに佇む——父、侯爵。
ルデル
「……っ……父、上……?」
掠れた声が出た瞬間、喉が焼け付くように痛んだ。
父侯爵
「起きたか」
その声には、安堵も怒りも混じっていない。ただ、事実を確認するだけの冷徹な響きがあった。
ルデルは反射的に身体を起こそうとしたが、鉛のように重い手足はピクリとも動かない。
ルデル
「……すみませ……ぐっ……書類、が……まだ……」
父侯爵
「謝れとは言わん。寝ていろ」
短く遮る言葉は、氷のように冷たい。
ルデルは唇を噛み、シーツを弱々しく握りしめた。
情けない。あれほど意気込んでおきながら、結局は父に迷惑をかけただけだ。
ルデル
「…………」
沈黙が部屋を支配する。
侯爵は、ベッドに横たわる息子を冷ややかな瞳で見下ろしていた。
やがて、その薄い唇が開き、淡々と、しかし残酷な現実を告げる。
父侯爵
「ルデル。お前が昨晩汚した書類だが——あれは、隣国との通商条約に関する重要機密だ」
ルデルの顔から、さらに血の気が引いた。
父侯爵
「インクの染み一つで、我が家の信用は地に落ちる寸前だった。……インク消しでなんとかなったが、それを理解しているか?」
ルデル
「あ……ああ……」
父侯爵
「己の限界を見誤り、結果として家益を損なう。それを『無能』と言うのだ」
侯爵の言葉が、病身のルデルに容赦なく突き刺さる。
そして、父は決定的な一言を口にした。
父侯爵
「これ以上、お前に執務室へ入ることは許さん。——お前の処遇について、考えがある」
父侯爵「二つだけだ。選べ」
父侯爵
「ルデル。お前が倒れた理由は、過労ではない。理由はただ一つだ」
ルデルは乾いた唇を開こうとしたが、言葉が出てこない。
父の視線が、身体の奥底まで射抜くように鋭い。
父侯爵
「“侯爵家の当主”とは何か。……お前はこれまで、その意味を一度たりとも真剣に考えてこなかったからだ」
ルデル
「…………!」
図星を突かれた衝撃に、ルデルの喉がひくりと震える。
父はベッドの端に手を置き、逃げ場を塞ぐように身を乗り出した。
父侯爵
「よく聞け。——今、この瞬間より、お前に残された選択肢は二つしかない」
部屋の空気が張り詰める。執事長ハリントンも、直立不動のまま主人の言葉を待っている。
父侯爵
「一つ目。死に物狂いで仕事を覚え、真の当主として立つこと」
ルデル
「…………っ」
父侯爵
「二つ目。——廃嫡を受け入れることだ」
ルデル
「っ!!」
その単語が耳に入った瞬間、ルデルの心臓が早鐘を打った。
父侯爵
「廃嫡となれば、お前はもはや我が家の人間ではない。爵位も、財産も、後ろ盾も失う。ただの“平民”として路頭に迷うことになる」
ルデル
「へ、平民……!?」
父侯爵
「そうだ。着る服も、明日の食事すら保証されない身分だ」
ルデルの顔が凍りつき、ガタガタと震えだす。想像すらしたことのない恐怖だった。
ルデル
「……や、やめて……ください……父上……! 私は……この侯爵家の長男で……」
父侯爵
「ならば仕事を覚えろ!!」
雷のような一喝が部屋を揺らした。
父侯爵
「“侯爵”という責任を負う覚悟があるのか。それとも、“侯爵家という甘い蜜”を啜りたいだけなのか。……その違いすらわからぬ愚か者に、家は継がせられん」
父は冷ややかな目でルデルを見下ろし、さらに残酷な事実を突きつける。
父侯爵
「それにな、ルデル。……お前が裏で何をしていたか、知らぬとでも思ったか?」
ルデル
「え……?」
父侯爵
「お前は自分の仕事を、あろうことかアルディ公爵家の令嬢……お前の婚約者に押し付けていただろう」
ルデル
「あ、あれは……彼女が、手伝うと……」
父侯爵
「黙れ。公爵家から連絡があった。彼女もまた、お前の分まで背負い込み、心労で倒れ伏しているとな」
ルデル
「…………」
血の気が引く音が聞こえるようだった。
自分が楽をするために利用していた「逃げ道」が、完全に塞がれたのだ。
父侯爵
「彼女の家も、今はそれどころではない。……お前が甘えたツケは、他家の令嬢の健康すら奪ったのだぞ」
ルデル
「…………っ……ぅ……」
父侯爵
「お前がこの家を継ぐと言うなら、もう誰の背中にも隠れられない。逃げる道は、どこにも残っていないと思え」
突きつけられた現実は、あまりにも重く、冷たい。
自分の無力さと浅ましさが、どうしようもなく惨めだった。
ルデル
「うぅ……っ……ぐすっ……」
プライドも何もかもが崩れ去り、ルデルはまるで叱られた幼子のように、ただ涙をこぼすことしかできなかった。
父侯爵の最後の言葉
父侯爵は、ゆっくりと立ち上がった。
それは、決して勢いのある動作ではなかった。
若い頃なら、書類を机に置いたままでも、何のためらいもなく立ち上がれただろう。
だが今は違う。
椅子の肘掛けに手を置き、
一度、深く息を整え、
膝にかかる負担を確かめるように、わずかに体重を前へ移す。
その一連の動きが、
この男が長い年月を“侯爵として生きてきた”証だった。
椅子が床を擦る音が、静かな執務室に響く。
その音は、不思議なほど大きく、
まるで空気そのものを切り裂いたかのようだった。
ルデルは、その音だけで悟った。
——これは、叱責ではない。
——説教でも、説得でもない。
決断の場だ。
父侯爵の背中は、老いていた。
背筋は、わずかに丸みを帯び、
かつて戦場で馬を駆り、
政務の場で誰よりも声を張り上げていた頃の影はない。
それでも。
その背には、
この家を守り、
この領を支え、
無数の失敗と犠牲を飲み込みながら、なお立ち続けてきた者だけが持つ
圧倒的な重みがあった。
70
あなたにおすすめの小説
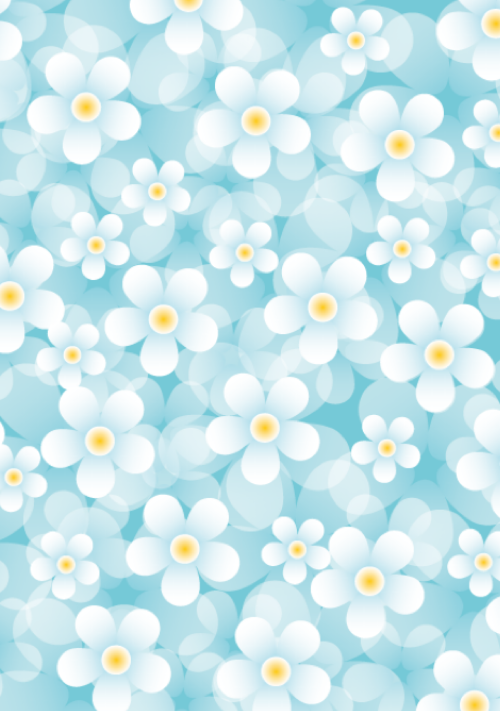
君が幸せになりたくなくても
あんど もあ
ファンタジー
来年には王立学園を卒業する伯爵家嫡男のライアンは、いい加減に婚約者を見つけないといけない。そんなライアンが新入生のクリスティナを好きになって婚約するのだが、実はクリスティナは過去の罪の贖罪のために生きていた。決して喜びや楽しさを求めず、後ろ向きに全力疾走しているクリスティナにライアンは……。

どんなあなたでも愛してる。
piyo
恋愛
遠征から戻った夫の姿が変わっていたーー
騎士である夫ディーノが、半年以上の遠征を終えて帰宅した。心躍らせて迎えたシエラだったが、そのあまりの外見の変わりように失神してしまう。
どうやら魔女の呪いでこうなったらしく、努力しなければ元には戻らないらしい。果たして、シエラはそんな夫を再び愛することができるのか?
※全四話+後日談一話。
※毎日夜9時頃更新(予約投稿済)&日曜日完結です。
※なろうにも投稿しています。

精霊姫の追放
あんど もあ
ファンタジー
栄華を極める国の国王が亡くなり、国王が溺愛していた幼い少女の姿の精霊姫を離宮から追放する事に。だが、その精霊姫の正体は……。
「優しい世界」と「ざまあ」の2バージョン。

結婚初夜、「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と夫に言われました
ましゅぺちーの
恋愛
侯爵令嬢のアリサは婚約者だった王太子テオドールと結婚した。
ちょうどその半年前、アリサの腹違いの妹のシアは不慮の事故で帰らぬ人となっていた。
王太子が婚約者の妹のシアを愛していたのは周知の事実だった。
そんな彼は、結婚初夜、アリサに冷たく言い放った。
「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と。

『白い結婚』が好条件だったから即断即決するしかないよね!
三谷朱花
恋愛
私、エヴァはずっともう親がいないものだと思っていた。亡くなった母方の祖父母に育てられていたからだ。だけど、年頃になった私を迎えに来たのは、ピョルリング伯爵だった。どうやら私はピョルリング伯爵の庶子らしい。そしてどうやら、政治の道具になるために、王都に連れていかれるらしい。そして、連れていかれた先には、年若いタッペル公爵がいた。どうやら、タッペル公爵は結婚したい理由があるらしい。タッペル公爵の出した条件に、私はすぐに飛びついた。だって、とてもいい条件だったから!

あなたの片想いを聞いてしまった夜
柴田はつみ
恋愛
「『好きな人がいる』——その一言で、私の世界は音を失った。」
公爵令嬢リリアーヌの初恋は、隣家の若き公爵アレクシスだった。
政務や領地行事で顔を合わせるたび、言葉少なな彼の沈黙さえ、彼女には優しさに聞こえた。——毎日会える。それだけで十分幸せだと信じていた。
しかしある日、回廊の陰で聞いてしまう。
「好きな人がいる。……片想いなんだ」
名前は出ない。だから、リリアーヌの胸は残酷に結論を作る。自分ではないのだ、と。

真実の愛は水晶の中に
立木
恋愛
学園の卒業を祝うパーティーの最中、レイシア・マレーニ侯爵令嬢は第三王子とピンク髪の女、その取り巻きたちによって断罪されようとしていた。
しかし断罪劇は思わぬ方向へ進んでいく。
※「なろう」にも重複投稿しています。

悪女の最後の手紙
新川 さとし
恋愛
王国を揺るがす地震が続く中、王子の隣に立っていたのは、婚約者ではなかった。
人々から「悪女」と呼ばれた、ひとりの少女。
彼女は笑い、奪い、好き勝手に振る舞っているように見えた。
婚約者である令嬢は、ただ黙って、その光景を見つめるしかなかった。
理由も知らされないまま、少しずつ立場を奪われ、周囲の視線と噂に耐えながら。
やがて地震は収まり、王国には安堵が訪れる。
――その直後、一通の手紙が届く。
それは、世界の見え方を、静かに反転させる手紙だった。
悪女と呼ばれた少女が、誰にも知られぬまま選び取った「最後の選択」を描いた物語。
表紙の作成と、文章の校正にAIを利用しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















