14 / 25
ルデル、男爵家に、怒鳴りこむ
しおりを挟む男爵家:玄関ホール
サリー
(外から馬車の急停止する音……。心臓が痛い、嫌な予感しかしないわ……)
バンッ!!
ノックも待たず、強引に扉が押し開かれる。
土足同然の勢いで踏み込んできたのは、顔を真っ赤に上気させた侯爵ルデルだった。
ルデル
「タイロンはどこだ! 王宮に召喚されたというのは本当か!?」
サリー
(ヒッ……! まともに返事なんてしたら、何を言われるか分かったもんじゃない……!)
「……っ、お、奥へ、どうぞ……」
サリーは震える手で精一杯の案内をする。
その時、コツ、コツと静かな靴音が響き、階段からジュディが降りてくる。その表情は驚くほど冷徹で、落ち着いていた。
ジュディ
「ルデル様。本日は事前の触れもございませんが……一体いかがなさいました?」
ルデル
「とぼけるな! 王宮がタイロンを呼びつけたと聞いたぞ! なぜだ、何の用だ! 理由を説明しろ!」
ジュディ
「理由は……私共も存じ上げませんわ。夫は現在、王宮にて執務中でございます」
ルデル
「ふざけるな! 王宮があの男に『仕事』だと!? ならば、この侯爵家に山積みになっている書類は誰が片付けるのだ!?」
ジュディ
「……それは、侯爵家の執事の方々か、あるいは当主であるあなた様がなさるべきことでは?」
ルデル
「できるわけがないだろうが!!」
ホールにルデルの怒号が響き渡る。
ルデル
「いいか、タイロンがいなければ侯爵家の運営は立ち行かんのだ! 今すぐ戻って来いと、あいつに伝えておけ!」
ジュディ
「……いいえ。夫の身の振り方を命じる権利は、もうあなた様にはございません」
ルデル
「……何だと?」
ジュディ
「タイロンは今や独立した男爵家の当主。そして侯爵家の書類仕事は、あくまで『侯爵であるあなた様の責任』。違いますか?」
ルデルは一瞬、言葉を失って絶句する。しかし、すぐに顔をどす黒く歪ませ、激昂を爆発させた。
ルデル
「な、なら、うちの滞っている書類はどうするつもりだ! 王宮へ行ったきり連絡も寄こさんとは……! このままでは侯爵家の威信に傷がつく、仕事が止まってしまうだろうが!」
ジュディ
「……ですから、先ほどから申し上げておりますわ。侯爵家の仕事は、侯爵がなさればよろしいのです」
サリー
(……奥様、すごい。今日の言い切り方、キレッキレだわ……!)
ルデル
「無茶を言うな! お前たちが勝手に王宮へ取り入り、甘い蜜を吸っているのだろう! 男爵家ごときが、この私……侯爵家の足を引っ張るつもりか!」
ジュディ
「……今の御言葉。聞き捨てなりませんね」
ジュディの瞳が鋭く細まり、一気に空気が凍りつく。
男爵家・玄関前:逃走と捕獲
ジュディの正論に叩きのめされ、ルデルは吐き捨てるように玄関を飛び出した。
ルデル
「ええい、どいつもこいつも! 覚えていろよ、タダで済むと思うな!」
顔を真っ赤にして馬車へ駆け寄ろうとした、その時。
ガシッ!!
鉄の万力のような力で、ルデルの腕が掴み止められた。
ルデル
「なっ……!? どこの無礼者だ、離せ!!」
執事長(ハリントン)
「……どちらへ行かれますか、ルデル様」
そこに立っていたのは、侯爵家を長年支え続けてきた老執事、ハリントンだった。感情を排したその氷のような眼差しに、ルデルの背筋が凍りつく。
ルデル
「は、ハリントン!? なぜここに……離せ! 私は当主だぞ!」
執事長
「左様でございます。当主ならば——当主の仕事場へお戻りくださいませ」
ハリントンは一切の容赦なく、ルデルを無理やり馬車の中へと押し込み、重厚な扉を**バタン!**と閉ざした。
ルデル
「おい!! 降ろせ! まだ言い足りんことが——」
執事長
「男爵家の玄関先で無様に喚き散らすなど、侯爵家の名にこれ以上泥を塗るおつもりですか?」
ルデル
「うっ……」
執事長
「さあ、帰りますよ。屋敷には“あなたのお仕事”が、山をなしてあなたをお待ちです」
御者が鞭を振るい、馬車が動き出す。
ハリントンの冷徹な視線に、ルデルは今更ながら、自分が取り返しのつかない窮地に立たされていることに気づき、青ざめた。
◆侯爵家・執務室:現実の重み
高い天井、壁一面を埋め尽くす分厚い書棚、そして静謐な空間に漂う蝋燭の香り。
かつてはタイロンが黙々とペンを走らせていたその部屋で、ルデルは愕然と立ち尽くした。
巨大な机の上には、もはや壁と呼べるほどびっしりと積み上がった書類の山があった。
ルデル
「……な、なんだ、この量は……嫌がらせか!?」
執事長
「いいえ。本日の分にございます。すべて“侯爵様(あなた様)の決裁”がなければ一歩も進まぬ案件ばかりです」
ルデル
「ム……ムリだ、こんなもの!! 読み解くだけで日が暮れる! タイロンを呼べ! あいつにやらせれば済む話だ!」
執事長
「何度申し上げればお分かりですか。タイロン様は既に独立した男爵家の当主。他家の仕事をする義理も義務も、もうございません」
ルデル
「ぐっ……!!」
逃げ場を失い、机を叩こうとしたルデルに対し、ハリントンは静かに、しかし刃のように鋭い言葉を突きつけた。
執事長
「……よろしいですか、ルデル様。これは“罰”でも“嫌がらせ”でもございません」
ルデル
「は……?」
執事長
「あなたが侯爵位を継ぐと決めたとき——本来ならば、いつか必ずご自身で背負うはずだった“当主の務め”そのものです」
その言葉は、タイロンにすべてを押し付けて甘受してきたルデルの怠慢を、残酷なまでに浮き彫りにした。
ルデル
「…………っ」
ルデルは息を呑み、目の前の紙の山をただ震えながら見つめることしかできなかった。
⸻
◆侯爵家・執務室:父の断罪
重厚な扉が音もなく開き、一人の男が足を踏み入れる。
現れたのは、現当主――父侯爵であった。その足音は静かだが、部屋の空気を一瞬で凍りつかせる重圧があった。
父侯爵
「戻ったか、ルデル」
ルデル
「父上……! 聞いてください! あのタイロンが、我らに断りもなく勝手に王宮へ取り入ったのです! 恩知らずにも程がある——!」
父侯爵
「……聞いている。だが、“王宮がその才を認めた男”を、今さら我らが責める理由がどこにある?」
ルデル
「っ……! それは……」
父侯爵
「それよりもだ、ルデル。お前に任せていたはずの領地報告が進んでいないと報告を受けている」
父の冷徹な眼差しに、ルデルの額から嫌な汗が伝い落ちる。
ルデル
「……父上、あの……。私は、こういう……地味で、細々とした実務には向いていないのです。これまではタイロンが……」
父侯爵は短く嘆息し、背を向けて大きな椅子に腰かけた。その背中は、かつてないほど遠く、冷ややかに見える。
父侯爵
「……知っていたよ」
ルデル
「……え?」
父侯爵
「お前が放蕩に耽り、その裏で、本来お前の務めであるはずの書類をすべて、タイロンが黙々とこなしていたことは……とうに知っていた」
ルデルの顔から血の気が引いていく。
ルデル
「な、なぜ……知っていて、黙っていたのですか……!」
父侯爵
「黙っていたのは——私の息子が、人の上に立つ者としての責任を、“いつか自覚する日”が来るのを待っていたからだ」
ルデル
「…………」
父侯爵
「だが、お前は気づかなかった。それどころか、己の無能を棚に上げて弟を蔑み続けた。……そして今日、あろうことか他家の玄関先で醜態を晒し、騒ぎを起こした」
傍らに控えていた執事長ハリントンが、静かに、しかし断定的に言葉を添える。
執事長
「執事として、これ以上の看過はできかねます」
ルデル
「……っ……」
かつて自分を守るための沈黙だと思っていた父の静寂は、実は自分を見極めるための「猶予」に過ぎなかった。その猶予が、今、完全に尽きたことをルデルは悟った。
◆父侯爵、非情なる決定
父侯爵の声は低く、地を這うような重圧となってルデルを椅子に縛り付けた。
父侯爵
「ルデル。今日、この瞬間から——お前自身が侯爵家の書類すべてを処理しろ。代理は一切認めん」
ルデル
「ム、ムリです父上!! 私はこういう数字や法典を読み解くことには向いていないんです!!」
父侯爵
「向いていないから何だ? “タイロンがやるのが当たり前”だと思い込み、己を磨くことを放棄し続けた結果が、今のその無様な姿だ」
ルデル
「……っ」
父侯爵
「お前がこの家の名を継ぐと言うのなら、やれ。……“できない”などという甘えは、もはやこの屋敷には存在しない」
父の合図を受け、執事長ハリントンが音もなく歩み寄る。そして、ずっしりと重い書類の束を、死刑宣告のようにルデルの眼前に置いた。
執事長
「……ご安心くださいませ、ルデル様。最初の百枚ほどは、この私が丁寧に内容を説明いたしましょう」
ルデル
「ひ、百枚……? 説明だけで百枚も……」
執事長
「ええ。そして、その後に控えている千枚については、ご自身のお力で頑張っていただかなければなりません」
ルデル
「せ、千……!? 千だと!?!?!?」
絶望的な数字に、ルデルの顔から血の気が完全に引き、視界がぐにゃりと歪む。
父侯爵
「逃げるな、ルデル。これまではタイロンの人生を削って、お前の時間を捻出してきた。……だが、これからはお前自身の時間だ。お前が浪費してきたツケを、今ここで支払え」
逃げ道はすべて塞がれた。
震えるルデルの瞳に映るのは、積み上げられた紙の山――それは彼が長年見ぬふりをしてきた「責任」という名の巨大な壁だった。
104
あなたにおすすめの小説
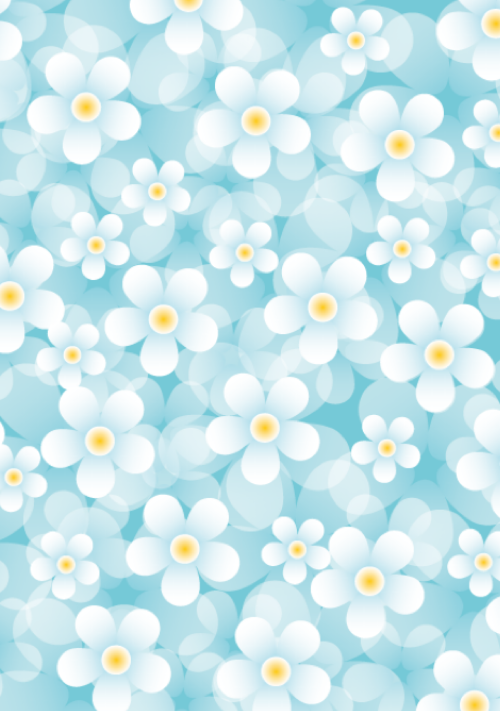
君が幸せになりたくなくても
あんど もあ
ファンタジー
来年には王立学園を卒業する伯爵家嫡男のライアンは、いい加減に婚約者を見つけないといけない。そんなライアンが新入生のクリスティナを好きになって婚約するのだが、実はクリスティナは過去の罪の贖罪のために生きていた。決して喜びや楽しさを求めず、後ろ向きに全力疾走しているクリスティナにライアンは……。

どんなあなたでも愛してる。
piyo
恋愛
遠征から戻った夫の姿が変わっていたーー
騎士である夫ディーノが、半年以上の遠征を終えて帰宅した。心躍らせて迎えたシエラだったが、そのあまりの外見の変わりように失神してしまう。
どうやら魔女の呪いでこうなったらしく、努力しなければ元には戻らないらしい。果たして、シエラはそんな夫を再び愛することができるのか?
※全四話+後日談一話。
※毎日夜9時頃更新(予約投稿済)&日曜日完結です。
※なろうにも投稿しています。

精霊姫の追放
あんど もあ
ファンタジー
栄華を極める国の国王が亡くなり、国王が溺愛していた幼い少女の姿の精霊姫を離宮から追放する事に。だが、その精霊姫の正体は……。
「優しい世界」と「ざまあ」の2バージョン。

結婚初夜、「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と夫に言われました
ましゅぺちーの
恋愛
侯爵令嬢のアリサは婚約者だった王太子テオドールと結婚した。
ちょうどその半年前、アリサの腹違いの妹のシアは不慮の事故で帰らぬ人となっていた。
王太子が婚約者の妹のシアを愛していたのは周知の事実だった。
そんな彼は、結婚初夜、アリサに冷たく言い放った。
「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と。

『白い結婚』が好条件だったから即断即決するしかないよね!
三谷朱花
恋愛
私、エヴァはずっともう親がいないものだと思っていた。亡くなった母方の祖父母に育てられていたからだ。だけど、年頃になった私を迎えに来たのは、ピョルリング伯爵だった。どうやら私はピョルリング伯爵の庶子らしい。そしてどうやら、政治の道具になるために、王都に連れていかれるらしい。そして、連れていかれた先には、年若いタッペル公爵がいた。どうやら、タッペル公爵は結婚したい理由があるらしい。タッペル公爵の出した条件に、私はすぐに飛びついた。だって、とてもいい条件だったから!

あなたの片想いを聞いてしまった夜
柴田はつみ
恋愛
「『好きな人がいる』——その一言で、私の世界は音を失った。」
公爵令嬢リリアーヌの初恋は、隣家の若き公爵アレクシスだった。
政務や領地行事で顔を合わせるたび、言葉少なな彼の沈黙さえ、彼女には優しさに聞こえた。——毎日会える。それだけで十分幸せだと信じていた。
しかしある日、回廊の陰で聞いてしまう。
「好きな人がいる。……片想いなんだ」
名前は出ない。だから、リリアーヌの胸は残酷に結論を作る。自分ではないのだ、と。

真実の愛は水晶の中に
立木
恋愛
学園の卒業を祝うパーティーの最中、レイシア・マレーニ侯爵令嬢は第三王子とピンク髪の女、その取り巻きたちによって断罪されようとしていた。
しかし断罪劇は思わぬ方向へ進んでいく。
※「なろう」にも重複投稿しています。

悪女の最後の手紙
新川 さとし
恋愛
王国を揺るがす地震が続く中、王子の隣に立っていたのは、婚約者ではなかった。
人々から「悪女」と呼ばれた、ひとりの少女。
彼女は笑い、奪い、好き勝手に振る舞っているように見えた。
婚約者である令嬢は、ただ黙って、その光景を見つめるしかなかった。
理由も知らされないまま、少しずつ立場を奪われ、周囲の視線と噂に耐えながら。
やがて地震は収まり、王国には安堵が訪れる。
――その直後、一通の手紙が届く。
それは、世界の見え方を、静かに反転させる手紙だった。
悪女と呼ばれた少女が、誰にも知られぬまま選び取った「最後の選択」を描いた物語。
表紙の作成と、文章の校正にAIを利用しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















