2 / 11
束の間の平穏と嵐の夜の来訪者
しおりを挟む
──そして三ヶ月。
「今日こそ貴様を屠ってくれるわ、『砂漠の魔龍』め!」
そう言って、その屈強な隻眼の騎士は、城の庭から、尖塔の窓辺に経つ白月を見上げ、白刃を向ける。白月はため息をついた。
「この間も吹き飛ばしてやったばかりでしょう。まだ懲りないの? 空見焔」
「黙れ! 貴様を殺して母上の呪いを解くまで、私は不退転の覚悟だ!」
そう、この空見焔という男は、あの詮議の場で白月の殺人を目撃したと偽証したあの女、不知火の息子だった。以来、執拗に白月を狙ってくるのだ。
「あの美しかった母上が……あんな無惨な傷を顔に負わされ、どれほど苦しんでいるか!」
「それは、あの女の偽証の結果でしょうよ」
「黙れ! 何が偽証か、この殺人者め! 大恩ある母上に、よくもあんな仕打ちができたものだ!」
白月は再度ため息をつく。
この男、焔は、よく言えばまっすぐで熱血、悪く言えば近視眼で思い込みが激しい。あの詮議の場で、白月を本当に殺人者だと思いこんでいた、数少ない参列者の一人だった。
次いで、母親が長年、白月を虐め抜いていたのにも気づいていない。
白月が空見家に引き取られたのは、龍宮家の一族がみな流行病で急死し、残るは白月独りになったからだ。白月の祖父が空見家の老当主と親友だったことから空見家が白月の成人までの保護者として名乗りを上げたのだが、白月の世話を任された不知火は、最初から、余計な仕事が増えたとして、白月を邪険にしていた。それでも、老当主が健在だった頃は良かった。彼が急逝してからは、白月の食事は明らかに粗末なものになり、龍宮家から持ち込んだ衣装や宝石は消え、白月が成人になるまで毎月渡されるはずの金銭も、不知火に奪われて、不知火はそれを使って贅沢放題だ。狭く古い物置部屋に押し込められ、行儀見習いと称して、使用人と同様の扱いでこき使われる毎日。ろくな教育も受けられず、白月はただただ、財産を受け継げる成人の日を待っていたが──それも、あの詮議の日で終り。
だが、残された虹蛇王国の者達は、それでは済まなかった。彼らはまず、白月が本当に龍に变化したことに仰天したのだ。龍宮一族が、建国の際初代王に忠誠を誓った龍の末裔であるという伝承は皆に知られていたが、建国から数百年を経て、それはすっかり、ただの言い伝え、龍宮一族の権威を示すための作り話だと思われていたのだ。
しかし、それは本当だった。虹蛇王国は、契約ある限り永劫に受けられるはずだった龍の加護を失ったのだと、そう皆が理解した。そうなれば、白月の処分に賛成していたはずの重臣たちからも、批判の声が上がる。そもそも殺害容疑が馬鹿げたものだったのだ。それは新王への批判にも至った。
新王は、その批判から目を逸らすため──そして、玉座の間を壊されたことへの報復と、領地から消えた龍宮家の財産の奪還も兼ね、白月を『邪悪な魔龍』として、討伐のために軍勢を送った。一夜にして砂漠に建った白亜の城は旅人たちの口の端に上っていたので、白月の居場所は明白だった。
が、王の送った軍勢は、龍の咆哮の一声だけで吹き飛ばされ、今に至るまでその本懐を遂げたことはない。
それでも、度重なる軍勢の来訪に、白月も嫌気が差してきて、ある日、城の図書館にあった魔導書を片手に、城の外に出た。
片手を上げ、魔力を集中させながら、魔導書にある呪文を読み上げる。
「わが城を守る城壁よ、現われよ、汝の色は何ものにも穢されぬ白、汝の背は何ものも通さぬ高さに聳え──」
呪文とともに、地面から城と同じ真珠色の城壁がせり上がってくる。その城壁には門がなく、そして、それが空飛ぶ生き物以外には決して越えられぬ高さになった時、白月は呪文を間違えた。城壁に防御の魔法を加える部分だった。
「──そして、この城壁に触れる者達よ。『己が魂の在るべき場所に還れ』」
言葉にした瞬間、まずい、と思った。
本当は、この部分は、『己が魂の還るべき場所に在れ』というのが正しいのだ。が、途中で詠唱をやめるわけにもいかず、白月は最後まで詠唱を続け、城壁を作り上げたのだった。
結果として、この間違いには、良い面もあり、悪い面もあった。
良い面というのは、失敗した後、よくよくこの呪文を調べてみたら、『城壁に触れた人間の魂を、すべての魂が還る場所、すなわちあの世へ送る魔法』だったことだ。無辜の旅人がうっかり触れることもあろう。さすがにそこまで物騒なことは望んでいなかった。
悪い面というのは、呪文を間違えた結果、魔法の効果が『城壁に触れた人間を、その者が魂をかけるほど大切にしているものの場所に転送する』というものになってしまったことだ。この魔法は、様々な悲喜劇を産んだ。
軍勢の一員として無理やり徴兵された農民は、城壁に触れた次の瞬間、妻子のもとに帰っていた。それはいい。問題は、愛人のもとに帰ってしまって、妻子に激怒された男。逆に、妻子のもとに帰ってしまって、身請けを約束していた遊女に泣き崩れられた男もいた。
騎士の一人は騎士団の旗のもとに帰り、騎士の鏡と褒め称えられたが、気づけば空位の騎士団長の椅子に座っていた男は、恥知らずと罵られた。
長年探していた、生き別れた娘と再会した男もいた。娘は遊郭に売られており、今まさに客の男に抱かれようとしているところで、父親は客をぶん殴り、大騒ぎになった。
その魔法の城壁の話は国境を越えて広まり、大切な誰かを探している人間、自分にとって一番大事なものを知りたいと渇望している人間、手っ取り早く家族のもとに戻りたい旅人などが、続々と集まってきては、城壁を囲んで連日騒ぎ、白月の静寂を妨げるのだった。
だがまぁ、城壁の守りはうまく行っていると言えた。城壁に触れた者は、みな、己にとって大事なものの在る場所へ飛ばされ、多くはそのまま二度と戻ってこないからだ。
だが、二つだけ例外がある。それは、魂をかけるほど大切なものを持ち合わせていない人間。そして、白月自身に会うことを、強く求めている人間だ。
焔は後者だった。彼の白月への怒りと憎しみは、魂にまで至っているらしい。見上げたものだと感心しなくもない。
ただし、他の軍勢はみな城壁に触れた途端故郷その他に飛ばされ、散り散りになってしまうため、いつも彼一人しか城内には入れない。そして彼は、独りで龍に勝てるほどの英雄ではないのである。
今日も白月は龍に变化し、焔を一息で虹蛇王国まで吹き飛ばした。護りの呪文もかけてやったから、まぁ死にはしないだろう。これで当面、白月の平穏は保たれる──はずだった。
その平穏が破られたのは、とある嵐の夜だった。
白月の城には魔法の防護がかけてあり、嵐などものともしない。白月は部屋の中から窓の外を眺め、無数の雨の矢が地上を打ち抜き、砂漠に水の膜を作っていくのを面白がって見物していた。部屋には灯り一つ点けず、まったくの暗闇であったが、龍である白月の翠の目にはすべてが映っており、まるで問題ない。
その時だった。
「ごめんください……」
そんな高く細い声が聞こえたのは。そしてその声は、明らかに城内から聞こえた。
──侵入者だ。
白月は思わず立ち上がる。この嵐の夜に砂漠を越え、しかもあの城壁を越えてこられるものなどいないと、すっかり油断していた。城の一階、人間用の扉には、鍵をかけていなかったのだ。
白月は攻撃魔法の準備を整えながら、声のした方へ行く。城の人間用の扉を開けてすぐの玄関広間に、その招かれざる客はいた。否、客達、だ。
一人のまだ幼い少年が、さらに幼い子どもを背負って、広間の床に跪いている。元々着ているのが襤褸である上に、濡れそぼり、泥にまみれていた。暗闇の中でも、白月には少年の顔が見えた。年の頃は十二歳くらいだろうか。すっかり疲弊し、惨めでもあり、これ以上は一歩も動けないという顔だ。
その幼さと、あまりにひどい有様に、白月は準備していた攻撃魔法を消してしまった。同情心が先に立ったのだ。代わりに、暗闇の中で何も見えないだろう少年のために、灯りの魔法を使ってやる。玄関広間に無数の灯りが点き、少年は突然の光に眩しそうに目を細めた。
が、やがて光に慣れたのか、その目が白月を映す。襤褸雑巾のような少年にそぐわぬ、紫水晶のような美しい瞳。少年は震える声で尋ねた。
「あなたが……『砂漠の魔龍』?」
「そうも呼ばれている」
白月が答えると、少年は瞳に、縋るような色が浮かぶ。
「お願いします! どうか妹を、助けてください!!」
「今日こそ貴様を屠ってくれるわ、『砂漠の魔龍』め!」
そう言って、その屈強な隻眼の騎士は、城の庭から、尖塔の窓辺に経つ白月を見上げ、白刃を向ける。白月はため息をついた。
「この間も吹き飛ばしてやったばかりでしょう。まだ懲りないの? 空見焔」
「黙れ! 貴様を殺して母上の呪いを解くまで、私は不退転の覚悟だ!」
そう、この空見焔という男は、あの詮議の場で白月の殺人を目撃したと偽証したあの女、不知火の息子だった。以来、執拗に白月を狙ってくるのだ。
「あの美しかった母上が……あんな無惨な傷を顔に負わされ、どれほど苦しんでいるか!」
「それは、あの女の偽証の結果でしょうよ」
「黙れ! 何が偽証か、この殺人者め! 大恩ある母上に、よくもあんな仕打ちができたものだ!」
白月は再度ため息をつく。
この男、焔は、よく言えばまっすぐで熱血、悪く言えば近視眼で思い込みが激しい。あの詮議の場で、白月を本当に殺人者だと思いこんでいた、数少ない参列者の一人だった。
次いで、母親が長年、白月を虐め抜いていたのにも気づいていない。
白月が空見家に引き取られたのは、龍宮家の一族がみな流行病で急死し、残るは白月独りになったからだ。白月の祖父が空見家の老当主と親友だったことから空見家が白月の成人までの保護者として名乗りを上げたのだが、白月の世話を任された不知火は、最初から、余計な仕事が増えたとして、白月を邪険にしていた。それでも、老当主が健在だった頃は良かった。彼が急逝してからは、白月の食事は明らかに粗末なものになり、龍宮家から持ち込んだ衣装や宝石は消え、白月が成人になるまで毎月渡されるはずの金銭も、不知火に奪われて、不知火はそれを使って贅沢放題だ。狭く古い物置部屋に押し込められ、行儀見習いと称して、使用人と同様の扱いでこき使われる毎日。ろくな教育も受けられず、白月はただただ、財産を受け継げる成人の日を待っていたが──それも、あの詮議の日で終り。
だが、残された虹蛇王国の者達は、それでは済まなかった。彼らはまず、白月が本当に龍に变化したことに仰天したのだ。龍宮一族が、建国の際初代王に忠誠を誓った龍の末裔であるという伝承は皆に知られていたが、建国から数百年を経て、それはすっかり、ただの言い伝え、龍宮一族の権威を示すための作り話だと思われていたのだ。
しかし、それは本当だった。虹蛇王国は、契約ある限り永劫に受けられるはずだった龍の加護を失ったのだと、そう皆が理解した。そうなれば、白月の処分に賛成していたはずの重臣たちからも、批判の声が上がる。そもそも殺害容疑が馬鹿げたものだったのだ。それは新王への批判にも至った。
新王は、その批判から目を逸らすため──そして、玉座の間を壊されたことへの報復と、領地から消えた龍宮家の財産の奪還も兼ね、白月を『邪悪な魔龍』として、討伐のために軍勢を送った。一夜にして砂漠に建った白亜の城は旅人たちの口の端に上っていたので、白月の居場所は明白だった。
が、王の送った軍勢は、龍の咆哮の一声だけで吹き飛ばされ、今に至るまでその本懐を遂げたことはない。
それでも、度重なる軍勢の来訪に、白月も嫌気が差してきて、ある日、城の図書館にあった魔導書を片手に、城の外に出た。
片手を上げ、魔力を集中させながら、魔導書にある呪文を読み上げる。
「わが城を守る城壁よ、現われよ、汝の色は何ものにも穢されぬ白、汝の背は何ものも通さぬ高さに聳え──」
呪文とともに、地面から城と同じ真珠色の城壁がせり上がってくる。その城壁には門がなく、そして、それが空飛ぶ生き物以外には決して越えられぬ高さになった時、白月は呪文を間違えた。城壁に防御の魔法を加える部分だった。
「──そして、この城壁に触れる者達よ。『己が魂の在るべき場所に還れ』」
言葉にした瞬間、まずい、と思った。
本当は、この部分は、『己が魂の還るべき場所に在れ』というのが正しいのだ。が、途中で詠唱をやめるわけにもいかず、白月は最後まで詠唱を続け、城壁を作り上げたのだった。
結果として、この間違いには、良い面もあり、悪い面もあった。
良い面というのは、失敗した後、よくよくこの呪文を調べてみたら、『城壁に触れた人間の魂を、すべての魂が還る場所、すなわちあの世へ送る魔法』だったことだ。無辜の旅人がうっかり触れることもあろう。さすがにそこまで物騒なことは望んでいなかった。
悪い面というのは、呪文を間違えた結果、魔法の効果が『城壁に触れた人間を、その者が魂をかけるほど大切にしているものの場所に転送する』というものになってしまったことだ。この魔法は、様々な悲喜劇を産んだ。
軍勢の一員として無理やり徴兵された農民は、城壁に触れた次の瞬間、妻子のもとに帰っていた。それはいい。問題は、愛人のもとに帰ってしまって、妻子に激怒された男。逆に、妻子のもとに帰ってしまって、身請けを約束していた遊女に泣き崩れられた男もいた。
騎士の一人は騎士団の旗のもとに帰り、騎士の鏡と褒め称えられたが、気づけば空位の騎士団長の椅子に座っていた男は、恥知らずと罵られた。
長年探していた、生き別れた娘と再会した男もいた。娘は遊郭に売られており、今まさに客の男に抱かれようとしているところで、父親は客をぶん殴り、大騒ぎになった。
その魔法の城壁の話は国境を越えて広まり、大切な誰かを探している人間、自分にとって一番大事なものを知りたいと渇望している人間、手っ取り早く家族のもとに戻りたい旅人などが、続々と集まってきては、城壁を囲んで連日騒ぎ、白月の静寂を妨げるのだった。
だがまぁ、城壁の守りはうまく行っていると言えた。城壁に触れた者は、みな、己にとって大事なものの在る場所へ飛ばされ、多くはそのまま二度と戻ってこないからだ。
だが、二つだけ例外がある。それは、魂をかけるほど大切なものを持ち合わせていない人間。そして、白月自身に会うことを、強く求めている人間だ。
焔は後者だった。彼の白月への怒りと憎しみは、魂にまで至っているらしい。見上げたものだと感心しなくもない。
ただし、他の軍勢はみな城壁に触れた途端故郷その他に飛ばされ、散り散りになってしまうため、いつも彼一人しか城内には入れない。そして彼は、独りで龍に勝てるほどの英雄ではないのである。
今日も白月は龍に变化し、焔を一息で虹蛇王国まで吹き飛ばした。護りの呪文もかけてやったから、まぁ死にはしないだろう。これで当面、白月の平穏は保たれる──はずだった。
その平穏が破られたのは、とある嵐の夜だった。
白月の城には魔法の防護がかけてあり、嵐などものともしない。白月は部屋の中から窓の外を眺め、無数の雨の矢が地上を打ち抜き、砂漠に水の膜を作っていくのを面白がって見物していた。部屋には灯り一つ点けず、まったくの暗闇であったが、龍である白月の翠の目にはすべてが映っており、まるで問題ない。
その時だった。
「ごめんください……」
そんな高く細い声が聞こえたのは。そしてその声は、明らかに城内から聞こえた。
──侵入者だ。
白月は思わず立ち上がる。この嵐の夜に砂漠を越え、しかもあの城壁を越えてこられるものなどいないと、すっかり油断していた。城の一階、人間用の扉には、鍵をかけていなかったのだ。
白月は攻撃魔法の準備を整えながら、声のした方へ行く。城の人間用の扉を開けてすぐの玄関広間に、その招かれざる客はいた。否、客達、だ。
一人のまだ幼い少年が、さらに幼い子どもを背負って、広間の床に跪いている。元々着ているのが襤褸である上に、濡れそぼり、泥にまみれていた。暗闇の中でも、白月には少年の顔が見えた。年の頃は十二歳くらいだろうか。すっかり疲弊し、惨めでもあり、これ以上は一歩も動けないという顔だ。
その幼さと、あまりにひどい有様に、白月は準備していた攻撃魔法を消してしまった。同情心が先に立ったのだ。代わりに、暗闇の中で何も見えないだろう少年のために、灯りの魔法を使ってやる。玄関広間に無数の灯りが点き、少年は突然の光に眩しそうに目を細めた。
が、やがて光に慣れたのか、その目が白月を映す。襤褸雑巾のような少年にそぐわぬ、紫水晶のような美しい瞳。少年は震える声で尋ねた。
「あなたが……『砂漠の魔龍』?」
「そうも呼ばれている」
白月が答えると、少年は瞳に、縋るような色が浮かぶ。
「お願いします! どうか妹を、助けてください!!」
0
あなたにおすすめの小説
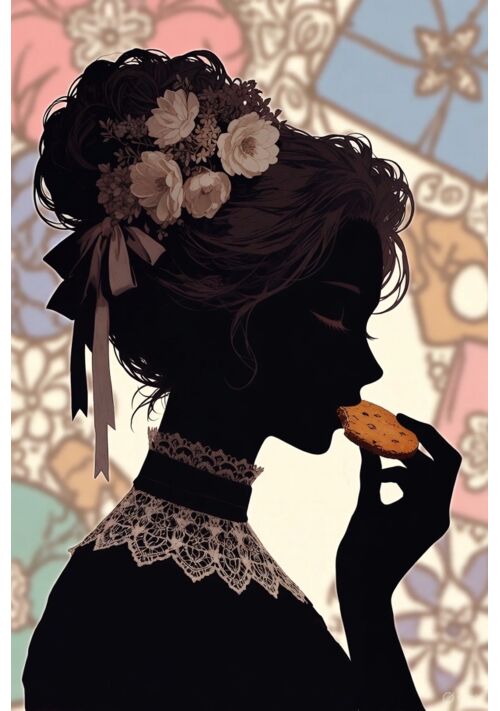
誰からも食べられずに捨てられたおからクッキーは異世界転生して肥満令嬢を幸福へ導く!
ariya
ファンタジー
誰にも食べられずゴミ箱に捨てられた「おからクッキー」は、異世界で150kgの絶望令嬢・ロザリンドと出会う。
転生チートを武器に、88kgの減量を導く!
婚約破棄され「豚令嬢」と罵られたロザリンドは、
クッキーの叱咤と分裂で空腹を乗り越え、
薔薇のように美しく咲き変わる。
舞踏会での王太子へのスカッとする一撃、
父との涙の再会、
そして最後の別れ――
「僕を食べてくれて、ありがとう」
捨てられた一枚が紡いだ、奇跡のダイエット革命!
※カクヨム・小説家になろうでも同時掲載中
※表紙イラストはAIに作成していただきました。

【完結】辺境に飛ばされた子爵令嬢、前世の経営知識で大商会を作ったら王都がひれ伏したし、隣国のハイスペ王子とも結婚できました
いっぺいちゃん
ファンタジー
婚約破棄、そして辺境送り――。
子爵令嬢マリエールの運命は、結婚式直前に無惨にも断ち切られた。
「辺境の館で余生を送れ。もうお前は必要ない」
冷酷に告げた婚約者により、社交界から追放された彼女。
しかし、マリエールには秘密があった。
――前世の彼女は、一流企業で辣腕を振るった経営コンサルタント。
未開拓の農産物、眠る鉱山資源、誠実で働き者の人々。
「必要ない」と切り捨てられた辺境には、未来を切り拓く力があった。
物流網を整え、作物をブランド化し、やがて「大商会」を設立!
数年で辺境は“商業帝国”と呼ばれるまでに発展していく。
さらに隣国の完璧王子から熱烈な求婚を受け、愛も手に入れるマリエール。
一方で、税収激減に苦しむ王都は彼女に救いを求めて――
「必要ないとおっしゃったのは、そちらでしょう?」
これは、追放令嬢が“経営知識”で国を動かし、
ざまぁと恋と繁栄を手に入れる逆転サクセスストーリー!
※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。

不倫されて離婚した社畜OLが幼女転生して聖女になりましたが、王国が揉めてて大事にしてもらえないので好きに生きます
天田れおぽん
ファンタジー
ブラック企業に勤める社畜OL沙羅(サラ)は、結婚したものの不倫されて離婚した。スッキリした気分で明るい未来に期待を馳せるも、公園から飛び出てきた子どもを助けたことで、弱っていた心臓が止まってしまい死亡。同情した女神が、黒髪黒目中肉中背バツイチの沙羅を、銀髪碧眼3歳児の聖女として異世界へと転生させてくれた。
ところが王国内で聖女の処遇で揉めていて、転生先は草原だった。
サラは女神がくれた山盛りてんこ盛りのスキルを使い、異世界で知り合ったモフモフたちと暮らし始める――――
※第16話 あつまれ聖獣の森 6 が抜けていましたので2025/07/30に追加しました。

冷遇妃マリアベルの監視報告書
Mag_Mel
ファンタジー
シルフィード王国に敗戦国ソラリから献上されたのは、"太陽の姫"と讃えられた妹ではなく、悪女と噂される姉、マリアベル。
第一王子の四番目の妃として迎えられた彼女は、王宮の片隅に追いやられ、嘲笑と陰湿な仕打ちに晒され続けていた。
そんな折、「王家の影」は第三王子セドリックよりマリアベルの監視業務を命じられる。年若い影が記す報告書には、ただ静かに耐え続け、死を待つかのように振舞うひとりの女の姿があった。
王位継承争いと策謀が渦巻く王宮で、冷遇妃の運命は思わぬ方向へと狂い始める――。
(小説家になろう様にも投稿しています)


【完結】ひとつだけ、ご褒美いただけますか?――没落令嬢、氷の王子にお願いしたら溺愛されました。
猫屋敷 むぎ
恋愛
没落伯爵家の娘の私、ノエル・カスティーユにとっては少し眩しすぎる学院の舞踏会で――
私の願いは一瞬にして踏みにじられました。
母が苦労して買ってくれた唯一の白いドレスは赤ワインに染められ、
婚約者ジルベールは私を見下ろしてこう言ったのです。
「君は、僕に恥をかかせたいのかい?」
まさか――あの優しい彼が?
そんなはずはない。そう信じていた私に、現実は冷たく突きつけられました。
子爵令嬢カトリーヌの冷笑と取り巻きの嘲笑。
でも、私には、味方など誰もいませんでした。
ただ一人、“氷の王子”カスパル殿下だけが。
白いハンカチを差し出し――その瞬間、止まっていた時間が静かに動き出したのです。
「……ひとつだけ、ご褒美いただけますか?」
やがて、勇気を振り絞って願った、小さな言葉。
それは、水底に沈んでいた私の人生をすくい上げ、
冷たい王子の心をそっと溶かしていく――最初の奇跡でした。
没落令嬢ノエルと、孤独な氷の王子カスパル。
これは、そんなじれじれなふたりが“本当の幸せを掴むまで”のお話です。
※全10話+番外編・約2.5万字の短編。一気読みもどうぞ
※わんこが繋ぐ恋物語です
※因果応報ざまぁ。最後は甘く、後味スッキリ

私はもう必要ないらしいので、国を護る秘術を解くことにした〜気づいた頃には、もう遅いですよ?〜
AK
ファンタジー
ランドロール公爵家は、数百年前に王国を大地震の脅威から護った『要の巫女』の子孫として王国に名を残している。
そして15歳になったリシア・ランドロールも一族の慣しに従って『要の巫女』の座を受け継ぐこととなる。
さらに王太子がリシアを婚約者に選んだことで二人は婚約を結ぶことが決定した。
しかし本物の巫女としての力を持っていたのは初代のみで、それ以降はただ形式上の祈りを捧げる名ばかりの巫女ばかりであった。
それ故に時代とともにランドロール公爵家を敬う者は減っていき、遂に王太子アストラはリシアとの婚約破棄を宣言すると共にランドロール家の爵位を剥奪する事を決定してしまう。
だが彼らは知らなかった。リシアこそが初代『要の巫女』の生まれ変わりであり、これから王国で発生する大地震を予兆し鎮めていたと言う事実を。
そして「もう私は必要ないんですよね?」と、そっと術を解き、リシアは国を後にする決意をするのだった。
※小説家になろう・カクヨムにも同タイトルで投稿しています。

この野菜は悪役令嬢がつくりました!
真鳥カノ
ファンタジー
幼い頃から聖女候補として育った公爵令嬢レティシアは、婚約者である王子から突然、婚約破棄を宣言される。
花や植物に『恵み』を与えるはずの聖女なのに、何故か花を枯らしてしまったレティシアは「偽聖女」とまで呼ばれ、どん底に落ちる。
だけどレティシアの力には秘密があって……?
せっかくだからのんびり花や野菜でも育てようとするレティシアは、どこでもやらかす……!
レティシアの力を巡って動き出す陰謀……?
色々起こっているけれど、私は今日も野菜を作ったり食べたり忙しい!
毎日2〜3回更新予定
だいたい6時30分、昼12時頃、18時頃のどこかで更新します!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















