10 / 14
10:断罪(後)
しおりを挟む
「それでは花の命名は誰が?」
「それは、わたくしが! オーロラ色の丸い花なので、アウロラ・フラワーと名付けました!!」
「なるほどな。すべて間違っている」
「は、はい?」
自信たっぷりのきらめいた目で答えていたローズは、ハリー王子の返答に目を白黒させた。ハリー王子は意に介さずに続ける。
「アウロラの原種はバルーンフラワーだ。そこから色が豊富なアルクス・フロスが生まれ、その次にオーロラ色になった」
「え、そんな事は無いです、最初からオーロラ色で……」
「その過程すべてが、論文にて発表されていると言ってもか?」
「ろ、論文?」
「そうだ。この花は開発者により、すべて論文として発表されている」
「嘘です! 私が聖女の祈りで生み出したものです、論文なんて、嘘です! 誰ですか、そんなのを書いた人は!」
「ルパート・スタンリー伯爵令息だ」
僕の名前が出たとたん、皆が僕を見た。中でも驚きの顔で僕を見たのは、レイモンド王子とその周囲と、妹だった。そして妹はすぐに僕をすさまじい目で睨みつけた。そしてレイモンド王子は笑いだす。
「は、は、はは、そんなわけがないでしょう! その落ちこぼれがそんな高度な事が出来るはずがない! あれはローズの聖女の力ですよ!」
「発生の基順、再現性、全てが確認されている。しかも日付入りで詳細に」
「嘘です! 兄ではありません!!」
「面倒だからもうはっきり言うけどな。先ほどからお前たちがアウロラ・フラワーと呼んでいる名前も違うんだよ。あれはアウロラ・ヴェールだ」
「……は?」
「自分で命名したと言ったくせに、花の名前もきちんと知らないんだな」
「そ、そんな事ないです、あれは、アウロラ・フラワーです!」
妹の絶叫に近い叫びに、ハリー王子はチチ、と指を振った。
「アウロラ・ヴェールの命名は、私だ。おっとまさか、それも嘘だというんじゃないだろうな? この私が、ルパート卿の屋敷で、オーロラ色のバルーンフラワーを見ながら、彼がもともと付けていた名前を変更させたんだ。お前はその事実すら知らないだろう? ついでに言えばこのことは論文にも掲載されている」
これにはさすがにレイモンド殿下も、妹も何も反論できなかった。嘘だと言えばハリー王子への不敬になるし、何より最初にレイモンド王子が間違えて言った名前を、妹は自分が命名したと胸を張って証言してしまっている。
レイモンド王子が花の名前を間違えた時、うん? と思った。ハリー殿下も気が付いて、それ以降ワザと花の名前を出していない。妹とレイモンド王子はその後も花の名前を間違え続けていた。この時点で彼らはこの花の名前すら正確に覚えていなかったという証明にもなる。そんな妹が開発者だと言ったところで誰が信じるだろうか。
オーロラ・バルーンフラワーを見たいと僕の屋敷にアポなしでやってきた城の使者は、実はハリー第一皇子その人だった。花を見た後に自分でそれを明かしてくれて、僕もトマスも仰天したものだ。
ハリー王子が実家に行った時は、僕の屋敷に来た時とおなじように「王城の使いの者」としか説明しなかったらしいが、それでも妹がまとわりついて離れなかったらしい。
ハリー王子に、花の名をアウロラ・ヴェールにしたいと言われたとき、僕にこだわりもなかったし、響きも良かったので二つ返事で受け入れ、そのくだりもすべて論文掲載の許可をもらった。
ウィロウ先生の助言だったが、事細かに記録を付けていて、そしてそれをレポートにまとめていて本当に良かった。論文にしてみようというのもウィロウ先生の助言だった。これで僕が開発者だと証明できるからと。僕はただ、この花を広めるために記録を残せればいいと思っていただけだけど、こんなところで役に立つとは。
ハリー王子の追及は続く。
「アウロラ・ヴェールとアルクス・フロスの命名は私だ。さらに、この花は球根ではない。種と挿し木で増えるんだ。元がオーロラ・バルーンフラワーだからな。お前がいくら球根に祈ったって、この花は咲かないんだよ。それに万一そうだったとしても、祈りで出来た花は祈りでしか育たない。ここにこれだけ飾れるほど増えるわけがないんだ。ルパート卿の育て方などは全て論文に書かれているよ。証人は学院の先生方だ。それすらも嘘だというのなら、その証拠をお前たちが出すことだな。……出せないよな? お前が開発したものではないのだから」
妹は真っ赤な顔で下を向いた。そして目だけを少し上げて僕を睨みつけている。横でレイモンド王子たちはただただ動揺していた。
妹に球根とか種とか言っても分かるとは思えない。それはレイモンド王子もだが。貴族自ら植物を育てる事など無いからだ。僕も花壇を始めるまでは、講義の知識としては知っていたけれど、認識していなかった。マリオさんにこれが種です、と見せられてその小ささに驚愕したほどなのだから。
「ルパート・スタンリー卿の功績はこれだけではない。4年前から植物学会に革命を起こしているんだ、その男は。何せその論文の数も20はくだらない」
「そんな……そんなわけは」
「嘘よ、兄様なんて日がな一日、地べたを這いずり回っているだけじゃないの!」
「だからこそ植物の専門家になれたんだよ。今や彼は植物学になくてはならない人物なのだから」
それは持ち上げすぎだと思う。僕が自立するための研究なだけなのだから。ただそれを、ウィロウ先生の助言でまとめておいただけだ。
「あり得ない! いつもローズの周囲に現れて嫌がらせをしているだけの男が……!!」
「それもあり得ないんだよ。レイモンド。いいか? ルパート卿は、学院高等学部じゃない。学院大学部の学生なんだよ」
「……は?」
「論文がこの国での必要数認められているし、その功績から本来は教授でもおかしくないんだ。だがさすがに高等学部に通わず、大学部の単位も修めていなければ、教授に任命することは出来ないから、現在飛び級で大学部で学んでもらっているんだ。必要単位が取れればすぐにでも研究者として大学に所属してもらう事になっている」
一応高校卒業程度の学力はあると、試験で認められている。そしてそのための特待生扱いだった。そしてこればかりは実はローズに感謝しなくてはいけないかもしれない。
ローズに意地悪をするからと、僕は自由時間がないほどに勉強をさせられた。読み書き計算から始まったそれは、6歳ですでに不自由なく読み書きができ、計算の基礎も完璧に身に付くほどだった。武道には適性がないからとそちらはいつの間にかやらなくてよくなった(見捨てられたともいう)し、貴族教育もマナー以外はやらなくて済んだ。その分を勉強に費やした。生徒が出来るようになれば、先生は更に問題を難しくする。家を追い出された10歳の頃には、すでに高等学部の勉強を始めていたらしい。
家を出てからは宿題は激減したが、生物、化学、社会学、歴史、数学、語学は植物の研究に結びつくから、喜んで勉強していた。
これも、幼少期から勉強し続けていたから、勉強が苦ではなかったのも良かったのだ。おかげで高等学部の入学試験でも、大学部の入試でも高得点を取れた理由だ。
大学部に入学してからは、特待生特権で学年を飛び越して自分の受けたい講義を取る事も出来る。妹が高等学部にいるから、今年は週に3日しか講義を取っていないが、妹が干渉してこなければ週に5日、学校できっちり講義を入れられるようになる。
「そ、そんな……」
「妹の才能を妬む? すでに教授就任が確定しているルパート卿が、高等学部の試験も満点、大学部への入試も9割取れる天才が、妬むと思うか?」
「うそよ……うそよ……!」
「大体、大学部と高等学部は棟も講義時間も違う。移動時間に会うはずがないんだ。しかもルパート卿は時間を空けることなく講義を取っている。高等学部と違って、大学部は講義ごとに教室が変わるから、その移動時間で休み時間は終わりなんだよ。その短い時間に、わざわざ高等学部まで移動して、妹をにらんで、すぐに引き返して、などやっている時間はない」
「しかし、ローズは実際に転ばされたりしています!」
「ルパート卿には護衛が付いている。当初は2人、レイモンドが乗り出してきてからは5人。彼らがお前たちが現れないようにと通路を見張って、安全を確認してからルパート卿を移動させるために、ルパート卿には寄り道をするような時間は全くない。おっと、見張りが嘘を、などというなよ。王室の近衛を付けているんだから」
ハリー殿下が見張りにと、近衛を融通してくれたのだ。彼らが見張りをさぼるはずなどないし、虚偽の報告をするはずもない。それを一番知っているのはレイモンド第2王子と護衛の剣士ガレスだ。その顔色がみるみる悪くなる。
会場内はシンとしていた。皆息を飲んで固唾を飲んで見守っている。
「で、でも、私たちは直接、その男に抗議をしに行きました!」
「護衛を増やすきっかけとなった話だな。高等学部と大学部の休みが重なる時間が、1日に1回だけある。その時間に上手く合わせたものだな。わざわざ高等学部から大学部まで来るとはご苦労な事だ。次の授業に間に合わなかっただろう? 先生から報告が上がっているぞ」
「うう……っ」
レイモンド第2王子の様子から、本当に間に合わなかったらしい。高等学部と大学部は、真ん中に食堂を挟んで左右に分かれて建っている。移動は可能だが、授業の合間の休み時間では間に合わない。だから高等学部の制服を着た彼らが講義棟に来た時には、周りがざわついていた。あれは第2王子が来たから、ではなく、いるはずのない高校生が来たから、だったのだ。
「そんなはずが……。だってローズはそいつに虐められていて……。だが確かに、そいつを教室やイベントで見たことがない……?」
茫然とつぶやくレイモンド王子。その目がローズをとらえると、ローズは王子の腕に抱き着いて叫んだ。
「いつも虐められているわ! 家でも、学校でも! 兄様は私が憎いのよ!」
「そ、そうだ、いつもローズは虐げられていて……」
そんなレイモンド王子とその執念を見て、ハリー王子は大きくため息をついた。
「本当にその女の能力は厄介だな。よくこれに耐えてきたな、ルパート」
「は、はい」
いきなり振らないでほしい。また妹が睨んでいるじゃあないか。
「聖女の能力を厄介とは何ですか!」
レイモンド王子が咬みつく。
「レイモンド、聖女の能力とは何か、簡潔に答えてみろ」
「そんなの、オーロラの加護を戴いた力を持つ者でしょう! ローズ嬢はその中でも稀有な治癒能力を持つ者ですよ!」
「ではその女に治癒能力があると?」
「あるからこそ、魔法研究省も彼女を聖女と認めたのでしょう!?」
「それなら、その女にかすり傷でも治してもらったものはいるか?」
ハリー王子が会場に問いかけるが、帰ってきたのは沈黙だった。レイモンド王子たちが焦ったように周りを見回す。
「レイモンドはどうだ? 護衛の剣士君は?」
「わ、私は、剣で刺した傷を治してもらいました!」
「治るのにどのくらいの時間がかかった?」
「そ、それは……。1週間です」
言いよどんだガレスの答えに、会場から失笑が漏れる。
「1週間? それは普通に治っただけではないのか?」
ガレスはそれにこたえられずに下を向いた。
「兄様、何をおっしゃいたいんですか!」
レイモンドが咬みつくも、その声に先ほどまでの威勢はない。
「その前に、ルパートの功績をもう一つ発表しよう。彼はバルーンフラワーのエキスを香水にすることにも成功している。今、貴族に大流行りの、アウロラ・パルス、もしくは一般用のクローマ・パルスという名前で売りに出ている。私も付けてみたが、虹色の液でさわやかな香りが上品な品だったな。流行るのもよくわかるよ」
「それが、なんだというのですか!」
「ルパート卿、香水の説明を」
いきなりハリー王子にバトンタッチされてしまった。僕はまだ体中が痛くてトマスに支えられている状態だが、できるだけ体を伸ばして発言した。
「バルーンフラワーの香りやエキスには、リラックス効果と、一種の解毒作用がありました。その作用の解明に時間がかかったのですが、大学部の薬学部や化学部、魔法学部の協力で、それらがある魔力の解毒作用だと判明しました」
「ある魔力の解毒作用?」
聞いてきたのはすでにモブと化していた医者の息子エリオットだ。僕はそれに頷いた。
「はい。状態異常を起こす魔法とでもいうのでしょうか、そういう効果を打ち消す作用があるんです。それはバルーンフラワー全種の香りに微量ですが含まれています。さらにアウロラ・ヴェールの香りには、それを強化した作用があるんです」
僕の言葉に、皆が会場内を見回す。そう、ここにはそのアウロラ・ヴェールがそこここに飾られているのだ。そして卒業生と招待者の胸にも。妹の顔が歪んでいて、すさまじい形相になっている。
「さらにこのエキスを濃縮することにも成功しました。こちらは飲み物で割ると効果が高い上に早く効きます。これを摂取すると、誰でもイライラが収まる、リラックスできる、穏やかな気持ちになれます」
続きはハリー王子が引き継いだ。
「今日、この会場には、アウロラ・ヴェールをふんだんに飾らせた。ルパート卿には無理を言って納品させたが、おかげで華やかになったよ。さらにそれを皆の胸にも付けてもらった。もう一つ。会場に入った時に、全員にウエルカムドリンクを渡して、その場で飲んでもらったと思う。あれが、アルクス・フロスのエキス入りドリンクだったんだ。なかなかさわやかな味だっただろう?」
会場内が同意でざわつく。このドリンクは本当にすっきりするのだ。魔法にかかっていなくても徹夜明けや疲れた頭もすっきりする。ハリー王子がにこやかに会場を見回し、最後に妹に目を向けた。
「長々と話をしてきたが、香りとドリンクで、ほとんどの者がすっきりとした頭で我々の話をしっかりと聞くことが出来たと思う。そしてその判断も正確に出来るだろう。だがレイモンドと彼らはドリンクと胸飾りを拒否したから、まだ話が分かってないようだな」
妹がこの香りが大嫌い、と彼らには胸飾りも付けさせなかったし、レイモンド王子と腕を組んでやってきた妹は、ウエルカムドリンクを受け取りはしたが、一口飲んで「まずぅい! レイモンド、こんなの飲んじゃだめ!」と騒いで、彼らにドリンクを飲ませなかったのだ。
それでもこれだけアウロラ・ヴェールの香りが漂っていれば、効き目は遅くても効果は出てくる。その証拠に彼らの中で唯一ドリンクを飲み干していたエリオットは、すでに真っ青な顔ですっかりとおとなしくなっていた。
「そ、それが何だというのですか」
「そろそろ気が付いているだろう? レイモンド。自分の言動の矛盾に。ルパート・スタンリー卿はお前と同じ高等学部ではなく、大学部の植物学科の学生であり、妹に嫉妬する必要などない、優れた才能の持ち主だ。それにいちいち妹にちょっかいを出しに行く暇もないほどに忙しい。また居住も妹がいる本宅とは遠く離れた領地の端に住んでいる。実家には父親である伯爵に呼び出されたときのみ、護衛と共にごく短時間滞在するだけで、これも妹が実家にいない時間の訪問であり、伯爵との面会以外は即座に屋敷を辞している。これらは護衛の近衛が証言しているから間違いない」
「し、しかしローズは虐められているんです……。そ、そうだ、学校へは領地からは来られないでしょう? その時に実家に滞在して!」
「ルパート卿はその身の安全と研究のため、講義がある日は指導教授の自宅に泊まり込んでいる。これも近衛と大学部側の護衛が周りを固めているから、抜け出す隙もないし、彼は研究に没頭しているから出かけることもない」
「そ、そんな……」
レイモンド第2王子もようやく事実が聞こえるようになったようだ。妹を信じたい心と、それには矛盾があるという事実を理解しつつある混乱で、彼らは妹を見たり僕を見たりと忙しい。ハリー王子はそんな彼らを見て、僕に言った。
「本当に、こんなに話が通じないとは想定外だった。ルパート卿、君はよくこの状況に耐えてこれたな」
その言葉に思わず涙がこみ上げてくる。本来の僕は耐えられなかった。耐えられずに妹を排除しようとして、断罪されたのだ。その未来の記憶が流れ込んできたから、耐える必要がないとわかったから。花々の世話に逃げたから、何とか暮らしてこられただけだ。声にならなずに震えている僕を見て、ハリー王子は苦笑しながら答えなくていいよというように手を振った。
「最後の答えだ。アウロラ・ヴェールには心に作用する魔法を解毒する作用がある。それを嫌がっているのは誰だ? ─そう、その聖女様だ」
「──っ!」
「い、嫌がってなんていないわ、嫌いな香りなだけです!」
「確かに香りには好き嫌いがあるだろう。だがそれだけなら周りのお前たちにまでドリンクを飲むなというか? 胸飾りは香りがするという理由はわかるが、これは王族からの賜りものだ。アレルギーがない限り、付けないことは不敬にもなる。まあレイモンドは別だが」
王族だから嫌なら拒否もできる。そしてこの香りと花に関しては、事前にアレルギーがないかを参加者に聞き取りしている。科学部の研究では、アレルギー成分は無いと言われたし、実際にバルーンフラワーでのアレルギー症例はない。それでも万が一のための医者も待機させている。
「その聖女様は、本来ならば遅くとも15歳になったら魔法研究省に所属し、修行を始めなければならないはずだった。今までの聖女は全てそうしてきた。ところが彼女は、それを回避してこの学院へ入学してきた。魔法研究省にも何度も聞き取りをしたが、担当者の返答が矛盾だらけだった。『彼女は優秀だから、修行はあとからでも遅くはない。今は学院に通って学力を伸ばした方がこの国の将来のためにもなる』。そんな返答を繰り返されたよ。ならばどう優秀なのか、どんな力があるのかと尋ねても、具体的な返答は返ってこない。ただただ『優秀なんですよ』というばかりで。しかも彼女は飛び級で学院高等学部に入学したが、その際の試験にも不審な点がある」
「不審な、点?」
レイモンドが体を震わせ、額から汗を流しながら小声で問う。ローズはレイモンドの腕に右手でしがみついているが、その顔は鬼のように険しく、左手の親指の爪を噛みながら僕とハリー王子を睨みつけている。不敬だけどいいのか、ローズ。
「その聖女様の入学試験の答案用紙が、学院のどこにもないんだ。5年間は保管を義務づけられている答案が、彼女の分だけどこにも」
「えっ……」
「さらには、彼女に飛び級での受験を認めた人物が見当たらない。確かに校長の名で彼女の飛び級受験を認めるという書類はある。だが校長はその書類を書いた記憶がないという」
「なっ、なんですって!?」
「そして採点を担当したものは、パーシヴァルが最高点だったと記憶しているが、それに準じる点数を出した女子生徒は記憶にないという。だが書類上では、その聖女様が主席合格、パーシヴァルが2位となっているんだよ」
パーシヴァルは魔法研究省の副会長の孫で、ローズと同じ2年生だ。黒髪を耳下あたりで切りそろえ、黒縁の眼鏡をかけて背が高く瘦せぎすの彼は、聖女の関係で入学前からローズと顔見知りで、点数で負けたことを悔しがってはいても、そんなに優秀なローズと一緒に勉強が出来るのは幸せな事だ、とメガネをクイと上げながら答えたと聞いている。
「さらに不思議な事に、入学後の学内試験も彼女の答案用紙だけがどこにも保管されていない。それなのに、点数上では上位を争っていることになっているんだ」
「そ、そんなばかな!」
「私もそう思って、校長に頼んで、彼女だけに別室で試験を受けさせた。ふっ、そうしたらどうなったと思う?」
ハリー王子は思い出し笑いをしながら続けた。
「その時は試験官と彼女だけにしたんだ。簡単な試験で、他の生徒に受けさせる前に問題の完成度を、優秀な彼女に先に確かめてもらいたいとか、適当な事を言って受けてもらったんだが、その後、彼女と会話を交わした試験官は、全ての答えをその場で彼女に教えたんだ」
「なんですって……?」
「私たちは別室でその様子を見ていた。そして全問教えて彼女が記入し、彼女が退出した後で、試験官は普通に採点して、目を輝かせて私たちの所にその回答を持ってきた。『全問正解です!』と言いながらね。試験官は私たちが別室で見ていることを知っていた。だから不正など出来るはずがないのに。しかも私が試験の様子を尋ねると、自分が教えたことなどなかったかのように、『彼女はスラスラと解いてました』というのだからまいったね。本当に試験官は自分が彼女に答えを教えたことを覚えていなかったんだ。嘘でも演技でもなく」
「確かになんか別室で、私一人でテストを受けさせられたことがあったけれど、そんな不正はしていません!!」
ローズが叫ぶ。まあそうだろう、不正を認める人などいない。それにハリー王子は控えていた侍従から丸いものを受け取って掲げた。
「これもルパート卿の発明の一つだ。記憶媒体装置という。これには動く映像を保存して再生する機能があるんだ。まだ研究段階だから表には出ていないがね」
植物の成長過程などを手書きするのには限界があり、そのままの風景などを切り取ったように保存できる物はないかと探している時に、星彩ノ華と晶華奏|《しょうかそう》という花を思い出した。
幼少期に父から貰った星彩ノ華は、その薄い花びらに衝撃を与えると、その時の周りの様子が花びらに切り取ったように映し出される特徴があった。
晶華奏は同じように衝撃が加わると、周りの音を記憶し、再生するという花だった。両方とも記録されているのは短時間でしばらくするともとに戻るが、それを使えないかと考えた。
先ずは品種改良で両方の花を人の掌ほどの大きさにすることに成功した。さらに星彩華の花びらに、あるタイミングで再度衝撃を与えることで映像を固定することに成功した。さらに星彩華と晶華奏の花びらを組み合わせて圧縮し、高速で回転させることで5分程度であるが、動く映像と音声を定着させて、更には再生させることに、ようやく成功したのだ。
この花々も栽培が難しかったのでそれを大量に生産するまでに時間もかかったけれど、うまく撮れた時には感激したものだ。それで花の開花の記録に使い、それを論文に載せたことでハリー王子の目にもとまったのだけど。
ハリー王子が丸い映像装置を作動させると、空中に映像が浮かんだ。試験中の二人がいる所から少し離れての録画なのではっきりとは見えないけれど、試験官とローズがいるのは十分にわかるし、音声のおかげで試験官が答えを教えてそれを彼女が記入している場面が映っているのがわかる。離れたところにいる人々には見えないだろうけれど、僕たちには十分に見えた。
「なんなの一体! なんでそんなのがあるのよ……!!」
ローズの小声の叫びが聞こえてきた。僕は、世界初の発明なんだぞと少し誇らしげに思ってしまう。
短時間の映像はすぐに終わってしまったが、それでも映像と音声は皆に衝撃を与えた。
「このように証拠が残っていながら、試験官は教えたことを覚えていないし、認識もしていない。これを見せても納得しないほどだった。となれば、聖女が何かをしたとしか考えられない。残念ながらこの映像には最初に彼女と試験官が交わした会話はとれていないから、それは証明できなかったが」
これで彼女が何らかの力をもって、試験官の思考に影響を与えたのではと誰もが考えた。そうして調べたら彼女の言動には事実が伴っていない疑惑が次々と浮かんできたのだ。
魔法研究省が彼女の学院入学を認めたのも、もしかしたら彼女の言葉に影響されたのではないかと考え始め、そこからいわゆる洗脳魔法ではないかと魔法学部の教授たちが仮定した。
そう仮定してローズを監視してみると、彼女が何かを言うたびに、周りにいる人はその通りに動いたり、思い込むことが判明した。
そう、僕の周りがそうだった。彼女が僕が悪いと言えば、僕が悪くなる。彼女が、マナーが良くなったでしょ? というから、どれだけ食べ散らかしても両親も使用人も、それを肯定する。彼女のいう事を鵜呑みにして僕を攻めてくるのだ。
一番の症例は、トマスだった。彼は僕が本宅を出てからも、定期的に雑用や僕の報告をしに本宅に戻っていた。その時にローズに色々と吹き込まれていたのだ。だから実家に戻るたびに彼は僕に対して攻撃的になっていたのだ。
その時僕を支えているトマスの指に力が入ったのを感じて、僕はトマスを見た。
「トマス?」
「申し訳ありませんでした、ルパート様……。本宅にいた時の私は、ルパート様が悪いと思い込んでいたのです。しかも目の前で勝手にローズ様が転んでいるのを見ているのに、口から出るのはルパート様を責める言葉ばかり。わかっていたんです、ルパート様が悪くないという事は! でも気が付くとルパート様を責めているし、ルパート様の口の動きと聞こえてくる言葉があからさまに違うのに、聞こえてくる言葉に対して攻撃的に返答してしまうのです! 私はルパート様と共に本宅を出ましたけど、本宅に戻るたびに同じ現象になってしまって。使用人の皆からも、ウィロウ先生からも、マリオさんからも、お前は何を言っているのかと何度も言われました。でもどうしようもなかったんです……!」
「うん、わかってるよ」
バルーンフラワーの香りの研究は彼の一言から始まったし、エキスの効果はトマスが自ら手を上げて実験してくれた。その時にも散々謝られた。今回は皆に聞かせるために告白してくれたのだ。僕はその勇気に感謝して、支えてくれている手を軽くたたいた。ハリー王子が続ける。
「ローズ令嬢、お前の能力は、自分の発言をそうだと思い込ませる『洗脳』だな」
「ち、ちがうわ!!」
「お前が最初に治癒能力を発揮したと報告された実父の件も改めて検証した。父親の病気は本物だったし、その回復も本物だった」
「そうでしょう!? 私には治癒能力があるんです!」
「それは違う。お前にあるのは言葉による洗脳。『とうさんの病気はすぐに治って良くなる』そう何度も幼いお前に言ってもらったと、実父が言っていた。それにより実父は『治る』と思い込み、体の免疫機能が跳ね上がったんだろう。そこの剣士の怪我もそうだ。お前の言葉で自己治癒力が上がったんだな。とはいえそれでは治癒能力の内には、はいらない」
「そ、そんな事はないわ!」
「いくら叫んでも無駄だぞ。ここにはアウロラ・ヴェールだけでなく、魔法学科制作による状態異常解除のアイテムが存在するんだ。私も身に着けている」
そう言ってハリー王子が自分の右手を上げると、手首には銀色に輝くブレスレットがあった。僕の提案で魔法学科が開発したものだ。これも自分が実験するとトマスが手を上げてくれただ。おかげでデータが取り放題だった。これはウィロウ先生や助手のヘンリー、近衛の人たちなどがすでに装着している。
万が一にも、ローズの言葉に取り込まれないように。
ハリー王子は用意してあったブレスレットをレイモンド王子に差し出した。彼だけでなくガレス、クラレンス、パーシヴァルにも渡し、彼らは茫然とした表情でそれを自身の手に嵌めた。
「ダメよ! そんなのはめちゃだめ! きっと変な効果が付いているのよ! 騙されちゃだめよ!」
ローズの金切り声が響き渡るが、すでに誰一人として彼女の言葉に従う者はいなかった。
レイモンド王子たちは、真横でキーキーと叫ぶローズを直視できず、蒼白の顔で冷や汗をダラダラと垂らしていた。
あの反応は何度も見た。本宅の執事アーサーも、トマスも。そして、父と母もああだった。
香水やエキスと違って、アイテムは効果が高いが、物凄い手間がかかる上に、大量には作れない。今回はどうしても目を覚まさせる必要がある人数分、ハリー王子が個人資産を出して作ってくれたのだ。
それに一度洗脳が解ければ、あとは香りと香水で対抗できる。ハリー王子は前面に立って対峙するので着用しているが、両親や他の者たちのは回収して、使いまわさせてもらっている。
レイモンド王子は自分の腕にしがみついて喚いているローズを恐る恐る見た。
今まで彼女の声は小さすぎるくらいで、令嬢らしくおっとりとしたしゃべりだったはずだ。だが今はどうだ。
この表情を取り繕うことなく、赤ん坊のように騒ぎ立てているのは、本当にローズなのか? しかし自分の脳が知っている。いつも彼女の言動はガサツで、矛盾だらけだったことを。ルパートを見たというが、その場所は何故か大学部の方だった。ルパートがあちらにいる意味は分からなかったが、少なくとも同じ高校の建物の中で見たことがないルパートが、ローズの邪魔をしに来るとは考えにくかった。だけどローズに訴えられるとそれが真実だと思ってしまう。
ついでに言えば兄のハリーがルパートに接触していることも、ルパートが植物学で革命を起こしていることも「知っていた」。だがローズが「落ちこぼれの兄」というと、それらが認識できなくなる。
ローズと茶を取ると、彼女が座っている周辺には食べこぼしが散乱し、茶器の音も耳障りだった。それでも自分には何故か「マナーは完璧」と思えるのだ。
レイモンド王子は泣きそうだった。現実と虚構を認識し、パニックを起こしかけていた。自分はこんな女とどうして一緒に居られたのか。どうして魅力的だなどと思ったのか。
「ねえ! レイ! 何とか言って! 私は悪くないでしょう!」
「ローズ……。君は一体、僕たちに何をしていたんだ?」
「……え?」
「そうだよ、僕たちは知っていたんだ。君がマナーもなっていないガサツな令嬢だという事を。君にはマナーなんて無いし、授業だってまじめに受けていない。君がテスト前になると勉強を教えてとやってくるけれど、君は全く勉強なんてしなかったし、問題を出しても解けなかった。なのに君が分かったというから、解けたというから。僕たちはそう思い込んでしまった」
「えっと、レイ、どうしたのよ!」
「君に言われて君の兄に会ったけれど、彼は君と違って礼儀正しくて、まさにお手本のような伯爵令息だった。僕がどれだけ失礼な事を言っても、彼は声を荒げることもなかった。君が言う人物像とはかけ離れていた!」
「そんなこと、ないわ! 兄様は意地悪で馬鹿で、どうしようもない男なのよ!」
「この国で『肥料』というものが開発された。おかげで野菜と果物の品質と収穫量が爆発的に上がった。それを作ったのは、ルパート・スタンリーという名だということを、僕は報告書を読んで知っていた。でも君が、あれは君が土に祈りを込めたり、世界に願ったからというから、そうだと思い込んだ!」
「レイ、ちょっと、手を離して、痛い!」
「君は一体、僕たちに何をしていたんだ!」
「ハイそこまで。レイモンド、いくら何でも令嬢の腕を力任せに握り締めるのはいただけないな。」
パニックを起こしかけて、ローズの両腕を掴んでいるレイモンド王子を、ハリー王子があっさりと引きはがした。他の者たちも顔を覆ったり顔面蒼白で茫然としている。
「全員、ちゃんと認識したみたいだね。さあ偽物の聖女ローズ、君の化けの皮は剝がれたよ」
「化けの皮ってなによ! 私は聖女よ!」
「ああそれもね、君が自分で聖女だというから、周りが洗脳されてそう思い込んだというのが事実だ。まあさっき言った通り、その力を上手く使えば、本当の聖女になれたかもしれないけれど、君は道を誤ったんだ」
「どういうことよ!」
「人間、思い込みで病気も怪我も治りやすくなる。君の洗脳でそれが可能なのは証明されている。だからその能力を正しく魔法研究省で磨いていれば、他人を思い通りにする洗脳ではなく、救う事も出来る能力として重宝されたという事さ。だが君は勉強嫌いだった。だから適当な理由を付けて教会での修業を拒み続けた。それはきっと、自分の能力がオーロラの色を持たないし、癒し系ではないのを知っていたからだろう。それが知られたら聖女じゃなくなってしまうと思ったんだろうね」
彼女が本当に慈悲深い人物だったら、彼女に励まされるだけで心が軽くなったり、やる気が出たり、その結果、良い結果をもたらすことにもなっただろう。たとえオーロラの加護がなくても、あれだけの力があれば聖女と同格となれる。だが彼女は自分の欲望に素直だった。面倒ごとから逃げて、自分に都合のいい世界を作り上げようとしていた。
「レイモンド、先ほど聞いたが、オーロラの聖人・聖女の認識が少し違っているぞ。彼らは、オーロラの神に愛され、その加護を受けたものを言うんだ。力が発動するときに色が出やすいというだけで、加護さえあればいい。その女はその加護がない。しかも力に色もない。だいだいこんなガサツな女を、オーロラが愛するわけがないだろう?」
「ふざけんじゃないわよ! あたしは愛されし聖女よ!」
キー! と、頭から湯気を出さんばかりにローズが地団駄を踏みながら叫ぶ。その様子に会場にいる者は全員、不快感を覚えるほどだった。それはもちろん、レイモンド第2王子たちもだ。
「まったく聞くに堪えないな。まあこれでここに居る全員に真実が知れ渡っただろう。ついでにもう一つ曝露してやろう。先ほど毒薬と言われた黒菫草のエキスだが、まずこの黒菫草は、国の許可がなければ採取・栽培が出来ない。ルパート卿の家には無いし、その周辺にも存在していない。確かに彼の屋敷の庭には数多くの植物が栽培されているけれど、全ての種類を国に報告し、確認されている。だから黒菫草をコッソリ栽培など出来るはずがない。侍従があると証言したと言っていたが、それはない。なにせその侍従にレイモンド本人も、その友人たちも言葉を交わしたことがないからな。それに、この毒を町医者で確認したと言ったがそれも無理だ。この毒は特殊な装置が無いと検出できない。この城下でその施設があるのは王立医局のみ。検査したこと事態が、その聖女もどきに思い込まされた嘘なんだよ」
ハリー王子がそう言うと、会場から息を飲む音がした。そして静寂が訪れる。
僕は静かに、ローズに話しかけた。
「ひとつわからないのは、君が何故僕を排除しようとしたか、だ」
僕を両親と同じように洗脳すればよかったのに、彼女は僕を悪役に仕立て上げた。
「そんなの! お前に能力が通じないからにきまっているだろうが!!!」
ローズが大声で叫んだ。
「能力が通じない?」
「お前だけは私のいう事をきかなかった! 何をしても乗ってこなかった!」
確かに僕は、彼女が来たばかりの頃、彼女に遊ぼうと言われて断った。彼女がやる事を注意をした。
「あたしの思い通りにならない人間なんていらないんだよ! それならあたしの引き立て役にしてやろうと思ったのに、それも思い通りにならないから!!」
「そんな事で、僕を悪役にしてたのか」
「そんな事!? あたしの言葉をきけない人間なんて、存在しちゃいけないんだよ! あたしの下僕にもならないんなら、さっさと死ねばよかったのに!」
ああ、僕は彼女に憎まれていたのか。僕を怒らせて、彼女に手を出せばそれを理由に排除できると考えたのだろう。ダメでも僕を悪役に出来る。まだ幼かったのによくそんな事を考え付いたものだ。
ローズの言葉に会場からひそひそと声がした。ローズは周囲を見回して息を飲む。激昂しすぎて思わず本音を吐いてしまったのだろうが、彼女の洗脳はもう効かないから、取り消しようがない。
「さてレイモンド。お前はこの場で罪びとを断罪すると言っていたな。……どうする?」
レイモンド王子は青ざめた顔でハリー王子を見た。その体が震えている。それを深呼吸で押さえて、レイモンド王子はおもむろに僕に向き直り、僕に頭を下げた。
「僕は、ルパート・スタンリー伯爵令息を、誤解していました。まずはお詫びしたい。今までいろいろと決めつけて卿に冤罪を掛けたこと、心から謝罪する」
「レイモンド! なんでよーーー!」
「謝罪は確かに受け取りました」
ローズの絶叫が煩いが、僕は痛む体で臣下の礼を取りながら返答した。ガレスたちも口々に謝罪をしてきた。僕をここに連れてきたクラレンスなど、足元にうずくまって謝ってきたほどだ。
それぞれ謝罪が済むと、レイモンド王子はローズに向き直った。今、彼女はハリー王子の命令で近衛が押さえつけている。僕の時の剣士とは違って、逃げられないように暴れられないようにがっちりと拘束はしているけれど、怪我をするような押さえ方はしていない。さすがだ。
「ローズ……。お前にはいろいろ聞きたいことがある」
「なんでも聞いて! それで私を開放して!」
「何故、こんなことをしたんだ? 何故、きちんと修行しなかった?」
「こんなこと? 私が注目されて、誰にでも愛される! 私が主役の世界を望んだだけよ! だって私は幸せになる事が確定している聖女なんだから!」
「そのために他人を蹴落として? その力を修行して役立てようとはしなかったのか?」
「私が幸せになるためよ! 邪魔なものを蹴落として何が悪いの? 修行しなくたって役に立っているじゃない!」
「嘘にまみれているだけだ。お前の洗脳が解けた今、王族を洗脳した罪で、僕はお前を断罪しなくてはならない」
「はあ? 断罪されるのはルパート! 私じゃないわ!」
「今や彼はこの国に居なくてはいけない人物だ。彼が確立した農業技術のおかげで発展しているのだから」
「兄にそんな事が出来るわけがないじゃない! 騙されているのよみんな!」
「……話にならないな。兄さん、彼女を国家反逆罪で拘束したい」
「ちょっと待ってよ! なんであたし!!」
「良いだろう。だが裁くのはこの場ではなく、司法の場だ」
「はい。お願いします」
「うん」
レイモンド王子が頭を下げ、ハリー王子は満足げにうなずき、合図をすると近衛が喚き続けるローズを引きずってこの場を後にした。それに続きレイモンド王子たちもこの場を後にする。
その際に参加者の列がまたきれいに別れたのだが、その中には憔悴しきった両親も混じっていた。
彼らには今朝、ローズが家を出てからハリー王子が状態解除のブレスレットを渡し、更にバルーンフラワーのエキスを飲ませて洗脳を解除していた。僕は大学に泊まり込んでいたからその場には立ち会っていないのだけど、記憶媒体装置で現実を認識した場面は見せてもらっていた。
大学でハリー王子の使いの者─ヘンリーさんだったのだけど─から話を聞いて、ヘンリーさんが帰ったあとに、僕の元へクラレンスが乗り込んできて、僕を乱暴に連れ出したのだ。
両親は遠くからハリー王子に頭を下げる。それに王子は頷いて、すぐにパン、と手を鳴らした。
「諸君、印象深い卒業記念パーティとなってしまったが、どうかしばらくの間はこの話題は広めないでおいてほしい。いずれ正式に全てを発表するから。そしてせっかくのパーティが弟のせいでめちゃくちゃになってしまった事をお詫びする。それに乗ってさらにめちゃくちゃにした私も、重ねてお詫びする」
あの状況をひっくり返すのは無理だった。であればそれに乗って、全てを明らかにするしかなかった。
「さあ、残り時間は少なくなってしまったが、今日のダンスを楽しみにしていたものも多いだろう。今からダンスパーティーを開催しよう。立食も用意してあるぞ」
ハリー王子の言葉で、会場内に控えていた音楽隊が演奏を始めた。彼女に近かった者たちは踊るような気分ではないだろうが、楽しみにしていた舞踏会だ。おずおずとだが皆が中央にやってきて、パートナーと手を組み始めた。
「さあ、みんな、楽しんでくれたまえ!」
にこやかに宣言するハリー王子に自然と拍手がわき、僕たちはそれに送られるように会場を後にした。
「それは、わたくしが! オーロラ色の丸い花なので、アウロラ・フラワーと名付けました!!」
「なるほどな。すべて間違っている」
「は、はい?」
自信たっぷりのきらめいた目で答えていたローズは、ハリー王子の返答に目を白黒させた。ハリー王子は意に介さずに続ける。
「アウロラの原種はバルーンフラワーだ。そこから色が豊富なアルクス・フロスが生まれ、その次にオーロラ色になった」
「え、そんな事は無いです、最初からオーロラ色で……」
「その過程すべてが、論文にて発表されていると言ってもか?」
「ろ、論文?」
「そうだ。この花は開発者により、すべて論文として発表されている」
「嘘です! 私が聖女の祈りで生み出したものです、論文なんて、嘘です! 誰ですか、そんなのを書いた人は!」
「ルパート・スタンリー伯爵令息だ」
僕の名前が出たとたん、皆が僕を見た。中でも驚きの顔で僕を見たのは、レイモンド王子とその周囲と、妹だった。そして妹はすぐに僕をすさまじい目で睨みつけた。そしてレイモンド王子は笑いだす。
「は、は、はは、そんなわけがないでしょう! その落ちこぼれがそんな高度な事が出来るはずがない! あれはローズの聖女の力ですよ!」
「発生の基順、再現性、全てが確認されている。しかも日付入りで詳細に」
「嘘です! 兄ではありません!!」
「面倒だからもうはっきり言うけどな。先ほどからお前たちがアウロラ・フラワーと呼んでいる名前も違うんだよ。あれはアウロラ・ヴェールだ」
「……は?」
「自分で命名したと言ったくせに、花の名前もきちんと知らないんだな」
「そ、そんな事ないです、あれは、アウロラ・フラワーです!」
妹の絶叫に近い叫びに、ハリー王子はチチ、と指を振った。
「アウロラ・ヴェールの命名は、私だ。おっとまさか、それも嘘だというんじゃないだろうな? この私が、ルパート卿の屋敷で、オーロラ色のバルーンフラワーを見ながら、彼がもともと付けていた名前を変更させたんだ。お前はその事実すら知らないだろう? ついでに言えばこのことは論文にも掲載されている」
これにはさすがにレイモンド殿下も、妹も何も反論できなかった。嘘だと言えばハリー王子への不敬になるし、何より最初にレイモンド王子が間違えて言った名前を、妹は自分が命名したと胸を張って証言してしまっている。
レイモンド王子が花の名前を間違えた時、うん? と思った。ハリー殿下も気が付いて、それ以降ワザと花の名前を出していない。妹とレイモンド王子はその後も花の名前を間違え続けていた。この時点で彼らはこの花の名前すら正確に覚えていなかったという証明にもなる。そんな妹が開発者だと言ったところで誰が信じるだろうか。
オーロラ・バルーンフラワーを見たいと僕の屋敷にアポなしでやってきた城の使者は、実はハリー第一皇子その人だった。花を見た後に自分でそれを明かしてくれて、僕もトマスも仰天したものだ。
ハリー王子が実家に行った時は、僕の屋敷に来た時とおなじように「王城の使いの者」としか説明しなかったらしいが、それでも妹がまとわりついて離れなかったらしい。
ハリー王子に、花の名をアウロラ・ヴェールにしたいと言われたとき、僕にこだわりもなかったし、響きも良かったので二つ返事で受け入れ、そのくだりもすべて論文掲載の許可をもらった。
ウィロウ先生の助言だったが、事細かに記録を付けていて、そしてそれをレポートにまとめていて本当に良かった。論文にしてみようというのもウィロウ先生の助言だった。これで僕が開発者だと証明できるからと。僕はただ、この花を広めるために記録を残せればいいと思っていただけだけど、こんなところで役に立つとは。
ハリー王子の追及は続く。
「アウロラ・ヴェールとアルクス・フロスの命名は私だ。さらに、この花は球根ではない。種と挿し木で増えるんだ。元がオーロラ・バルーンフラワーだからな。お前がいくら球根に祈ったって、この花は咲かないんだよ。それに万一そうだったとしても、祈りで出来た花は祈りでしか育たない。ここにこれだけ飾れるほど増えるわけがないんだ。ルパート卿の育て方などは全て論文に書かれているよ。証人は学院の先生方だ。それすらも嘘だというのなら、その証拠をお前たちが出すことだな。……出せないよな? お前が開発したものではないのだから」
妹は真っ赤な顔で下を向いた。そして目だけを少し上げて僕を睨みつけている。横でレイモンド王子たちはただただ動揺していた。
妹に球根とか種とか言っても分かるとは思えない。それはレイモンド王子もだが。貴族自ら植物を育てる事など無いからだ。僕も花壇を始めるまでは、講義の知識としては知っていたけれど、認識していなかった。マリオさんにこれが種です、と見せられてその小ささに驚愕したほどなのだから。
「ルパート・スタンリー卿の功績はこれだけではない。4年前から植物学会に革命を起こしているんだ、その男は。何せその論文の数も20はくだらない」
「そんな……そんなわけは」
「嘘よ、兄様なんて日がな一日、地べたを這いずり回っているだけじゃないの!」
「だからこそ植物の専門家になれたんだよ。今や彼は植物学になくてはならない人物なのだから」
それは持ち上げすぎだと思う。僕が自立するための研究なだけなのだから。ただそれを、ウィロウ先生の助言でまとめておいただけだ。
「あり得ない! いつもローズの周囲に現れて嫌がらせをしているだけの男が……!!」
「それもあり得ないんだよ。レイモンド。いいか? ルパート卿は、学院高等学部じゃない。学院大学部の学生なんだよ」
「……は?」
「論文がこの国での必要数認められているし、その功績から本来は教授でもおかしくないんだ。だがさすがに高等学部に通わず、大学部の単位も修めていなければ、教授に任命することは出来ないから、現在飛び級で大学部で学んでもらっているんだ。必要単位が取れればすぐにでも研究者として大学に所属してもらう事になっている」
一応高校卒業程度の学力はあると、試験で認められている。そしてそのための特待生扱いだった。そしてこればかりは実はローズに感謝しなくてはいけないかもしれない。
ローズに意地悪をするからと、僕は自由時間がないほどに勉強をさせられた。読み書き計算から始まったそれは、6歳ですでに不自由なく読み書きができ、計算の基礎も完璧に身に付くほどだった。武道には適性がないからとそちらはいつの間にかやらなくてよくなった(見捨てられたともいう)し、貴族教育もマナー以外はやらなくて済んだ。その分を勉強に費やした。生徒が出来るようになれば、先生は更に問題を難しくする。家を追い出された10歳の頃には、すでに高等学部の勉強を始めていたらしい。
家を出てからは宿題は激減したが、生物、化学、社会学、歴史、数学、語学は植物の研究に結びつくから、喜んで勉強していた。
これも、幼少期から勉強し続けていたから、勉強が苦ではなかったのも良かったのだ。おかげで高等学部の入学試験でも、大学部の入試でも高得点を取れた理由だ。
大学部に入学してからは、特待生特権で学年を飛び越して自分の受けたい講義を取る事も出来る。妹が高等学部にいるから、今年は週に3日しか講義を取っていないが、妹が干渉してこなければ週に5日、学校できっちり講義を入れられるようになる。
「そ、そんな……」
「妹の才能を妬む? すでに教授就任が確定しているルパート卿が、高等学部の試験も満点、大学部への入試も9割取れる天才が、妬むと思うか?」
「うそよ……うそよ……!」
「大体、大学部と高等学部は棟も講義時間も違う。移動時間に会うはずがないんだ。しかもルパート卿は時間を空けることなく講義を取っている。高等学部と違って、大学部は講義ごとに教室が変わるから、その移動時間で休み時間は終わりなんだよ。その短い時間に、わざわざ高等学部まで移動して、妹をにらんで、すぐに引き返して、などやっている時間はない」
「しかし、ローズは実際に転ばされたりしています!」
「ルパート卿には護衛が付いている。当初は2人、レイモンドが乗り出してきてからは5人。彼らがお前たちが現れないようにと通路を見張って、安全を確認してからルパート卿を移動させるために、ルパート卿には寄り道をするような時間は全くない。おっと、見張りが嘘を、などというなよ。王室の近衛を付けているんだから」
ハリー殿下が見張りにと、近衛を融通してくれたのだ。彼らが見張りをさぼるはずなどないし、虚偽の報告をするはずもない。それを一番知っているのはレイモンド第2王子と護衛の剣士ガレスだ。その顔色がみるみる悪くなる。
会場内はシンとしていた。皆息を飲んで固唾を飲んで見守っている。
「で、でも、私たちは直接、その男に抗議をしに行きました!」
「護衛を増やすきっかけとなった話だな。高等学部と大学部の休みが重なる時間が、1日に1回だけある。その時間に上手く合わせたものだな。わざわざ高等学部から大学部まで来るとはご苦労な事だ。次の授業に間に合わなかっただろう? 先生から報告が上がっているぞ」
「うう……っ」
レイモンド第2王子の様子から、本当に間に合わなかったらしい。高等学部と大学部は、真ん中に食堂を挟んで左右に分かれて建っている。移動は可能だが、授業の合間の休み時間では間に合わない。だから高等学部の制服を着た彼らが講義棟に来た時には、周りがざわついていた。あれは第2王子が来たから、ではなく、いるはずのない高校生が来たから、だったのだ。
「そんなはずが……。だってローズはそいつに虐められていて……。だが確かに、そいつを教室やイベントで見たことがない……?」
茫然とつぶやくレイモンド王子。その目がローズをとらえると、ローズは王子の腕に抱き着いて叫んだ。
「いつも虐められているわ! 家でも、学校でも! 兄様は私が憎いのよ!」
「そ、そうだ、いつもローズは虐げられていて……」
そんなレイモンド王子とその執念を見て、ハリー王子は大きくため息をついた。
「本当にその女の能力は厄介だな。よくこれに耐えてきたな、ルパート」
「は、はい」
いきなり振らないでほしい。また妹が睨んでいるじゃあないか。
「聖女の能力を厄介とは何ですか!」
レイモンド王子が咬みつく。
「レイモンド、聖女の能力とは何か、簡潔に答えてみろ」
「そんなの、オーロラの加護を戴いた力を持つ者でしょう! ローズ嬢はその中でも稀有な治癒能力を持つ者ですよ!」
「ではその女に治癒能力があると?」
「あるからこそ、魔法研究省も彼女を聖女と認めたのでしょう!?」
「それなら、その女にかすり傷でも治してもらったものはいるか?」
ハリー王子が会場に問いかけるが、帰ってきたのは沈黙だった。レイモンド王子たちが焦ったように周りを見回す。
「レイモンドはどうだ? 護衛の剣士君は?」
「わ、私は、剣で刺した傷を治してもらいました!」
「治るのにどのくらいの時間がかかった?」
「そ、それは……。1週間です」
言いよどんだガレスの答えに、会場から失笑が漏れる。
「1週間? それは普通に治っただけではないのか?」
ガレスはそれにこたえられずに下を向いた。
「兄様、何をおっしゃいたいんですか!」
レイモンドが咬みつくも、その声に先ほどまでの威勢はない。
「その前に、ルパートの功績をもう一つ発表しよう。彼はバルーンフラワーのエキスを香水にすることにも成功している。今、貴族に大流行りの、アウロラ・パルス、もしくは一般用のクローマ・パルスという名前で売りに出ている。私も付けてみたが、虹色の液でさわやかな香りが上品な品だったな。流行るのもよくわかるよ」
「それが、なんだというのですか!」
「ルパート卿、香水の説明を」
いきなりハリー王子にバトンタッチされてしまった。僕はまだ体中が痛くてトマスに支えられている状態だが、できるだけ体を伸ばして発言した。
「バルーンフラワーの香りやエキスには、リラックス効果と、一種の解毒作用がありました。その作用の解明に時間がかかったのですが、大学部の薬学部や化学部、魔法学部の協力で、それらがある魔力の解毒作用だと判明しました」
「ある魔力の解毒作用?」
聞いてきたのはすでにモブと化していた医者の息子エリオットだ。僕はそれに頷いた。
「はい。状態異常を起こす魔法とでもいうのでしょうか、そういう効果を打ち消す作用があるんです。それはバルーンフラワー全種の香りに微量ですが含まれています。さらにアウロラ・ヴェールの香りには、それを強化した作用があるんです」
僕の言葉に、皆が会場内を見回す。そう、ここにはそのアウロラ・ヴェールがそこここに飾られているのだ。そして卒業生と招待者の胸にも。妹の顔が歪んでいて、すさまじい形相になっている。
「さらにこのエキスを濃縮することにも成功しました。こちらは飲み物で割ると効果が高い上に早く効きます。これを摂取すると、誰でもイライラが収まる、リラックスできる、穏やかな気持ちになれます」
続きはハリー王子が引き継いだ。
「今日、この会場には、アウロラ・ヴェールをふんだんに飾らせた。ルパート卿には無理を言って納品させたが、おかげで華やかになったよ。さらにそれを皆の胸にも付けてもらった。もう一つ。会場に入った時に、全員にウエルカムドリンクを渡して、その場で飲んでもらったと思う。あれが、アルクス・フロスのエキス入りドリンクだったんだ。なかなかさわやかな味だっただろう?」
会場内が同意でざわつく。このドリンクは本当にすっきりするのだ。魔法にかかっていなくても徹夜明けや疲れた頭もすっきりする。ハリー王子がにこやかに会場を見回し、最後に妹に目を向けた。
「長々と話をしてきたが、香りとドリンクで、ほとんどの者がすっきりとした頭で我々の話をしっかりと聞くことが出来たと思う。そしてその判断も正確に出来るだろう。だがレイモンドと彼らはドリンクと胸飾りを拒否したから、まだ話が分かってないようだな」
妹がこの香りが大嫌い、と彼らには胸飾りも付けさせなかったし、レイモンド王子と腕を組んでやってきた妹は、ウエルカムドリンクを受け取りはしたが、一口飲んで「まずぅい! レイモンド、こんなの飲んじゃだめ!」と騒いで、彼らにドリンクを飲ませなかったのだ。
それでもこれだけアウロラ・ヴェールの香りが漂っていれば、効き目は遅くても効果は出てくる。その証拠に彼らの中で唯一ドリンクを飲み干していたエリオットは、すでに真っ青な顔ですっかりとおとなしくなっていた。
「そ、それが何だというのですか」
「そろそろ気が付いているだろう? レイモンド。自分の言動の矛盾に。ルパート・スタンリー卿はお前と同じ高等学部ではなく、大学部の植物学科の学生であり、妹に嫉妬する必要などない、優れた才能の持ち主だ。それにいちいち妹にちょっかいを出しに行く暇もないほどに忙しい。また居住も妹がいる本宅とは遠く離れた領地の端に住んでいる。実家には父親である伯爵に呼び出されたときのみ、護衛と共にごく短時間滞在するだけで、これも妹が実家にいない時間の訪問であり、伯爵との面会以外は即座に屋敷を辞している。これらは護衛の近衛が証言しているから間違いない」
「し、しかしローズは虐められているんです……。そ、そうだ、学校へは領地からは来られないでしょう? その時に実家に滞在して!」
「ルパート卿はその身の安全と研究のため、講義がある日は指導教授の自宅に泊まり込んでいる。これも近衛と大学部側の護衛が周りを固めているから、抜け出す隙もないし、彼は研究に没頭しているから出かけることもない」
「そ、そんな……」
レイモンド第2王子もようやく事実が聞こえるようになったようだ。妹を信じたい心と、それには矛盾があるという事実を理解しつつある混乱で、彼らは妹を見たり僕を見たりと忙しい。ハリー王子はそんな彼らを見て、僕に言った。
「本当に、こんなに話が通じないとは想定外だった。ルパート卿、君はよくこの状況に耐えてこれたな」
その言葉に思わず涙がこみ上げてくる。本来の僕は耐えられなかった。耐えられずに妹を排除しようとして、断罪されたのだ。その未来の記憶が流れ込んできたから、耐える必要がないとわかったから。花々の世話に逃げたから、何とか暮らしてこられただけだ。声にならなずに震えている僕を見て、ハリー王子は苦笑しながら答えなくていいよというように手を振った。
「最後の答えだ。アウロラ・ヴェールには心に作用する魔法を解毒する作用がある。それを嫌がっているのは誰だ? ─そう、その聖女様だ」
「──っ!」
「い、嫌がってなんていないわ、嫌いな香りなだけです!」
「確かに香りには好き嫌いがあるだろう。だがそれだけなら周りのお前たちにまでドリンクを飲むなというか? 胸飾りは香りがするという理由はわかるが、これは王族からの賜りものだ。アレルギーがない限り、付けないことは不敬にもなる。まあレイモンドは別だが」
王族だから嫌なら拒否もできる。そしてこの香りと花に関しては、事前にアレルギーがないかを参加者に聞き取りしている。科学部の研究では、アレルギー成分は無いと言われたし、実際にバルーンフラワーでのアレルギー症例はない。それでも万が一のための医者も待機させている。
「その聖女様は、本来ならば遅くとも15歳になったら魔法研究省に所属し、修行を始めなければならないはずだった。今までの聖女は全てそうしてきた。ところが彼女は、それを回避してこの学院へ入学してきた。魔法研究省にも何度も聞き取りをしたが、担当者の返答が矛盾だらけだった。『彼女は優秀だから、修行はあとからでも遅くはない。今は学院に通って学力を伸ばした方がこの国の将来のためにもなる』。そんな返答を繰り返されたよ。ならばどう優秀なのか、どんな力があるのかと尋ねても、具体的な返答は返ってこない。ただただ『優秀なんですよ』というばかりで。しかも彼女は飛び級で学院高等学部に入学したが、その際の試験にも不審な点がある」
「不審な、点?」
レイモンドが体を震わせ、額から汗を流しながら小声で問う。ローズはレイモンドの腕に右手でしがみついているが、その顔は鬼のように険しく、左手の親指の爪を噛みながら僕とハリー王子を睨みつけている。不敬だけどいいのか、ローズ。
「その聖女様の入学試験の答案用紙が、学院のどこにもないんだ。5年間は保管を義務づけられている答案が、彼女の分だけどこにも」
「えっ……」
「さらには、彼女に飛び級での受験を認めた人物が見当たらない。確かに校長の名で彼女の飛び級受験を認めるという書類はある。だが校長はその書類を書いた記憶がないという」
「なっ、なんですって!?」
「そして採点を担当したものは、パーシヴァルが最高点だったと記憶しているが、それに準じる点数を出した女子生徒は記憶にないという。だが書類上では、その聖女様が主席合格、パーシヴァルが2位となっているんだよ」
パーシヴァルは魔法研究省の副会長の孫で、ローズと同じ2年生だ。黒髪を耳下あたりで切りそろえ、黒縁の眼鏡をかけて背が高く瘦せぎすの彼は、聖女の関係で入学前からローズと顔見知りで、点数で負けたことを悔しがってはいても、そんなに優秀なローズと一緒に勉強が出来るのは幸せな事だ、とメガネをクイと上げながら答えたと聞いている。
「さらに不思議な事に、入学後の学内試験も彼女の答案用紙だけがどこにも保管されていない。それなのに、点数上では上位を争っていることになっているんだ」
「そ、そんなばかな!」
「私もそう思って、校長に頼んで、彼女だけに別室で試験を受けさせた。ふっ、そうしたらどうなったと思う?」
ハリー王子は思い出し笑いをしながら続けた。
「その時は試験官と彼女だけにしたんだ。簡単な試験で、他の生徒に受けさせる前に問題の完成度を、優秀な彼女に先に確かめてもらいたいとか、適当な事を言って受けてもらったんだが、その後、彼女と会話を交わした試験官は、全ての答えをその場で彼女に教えたんだ」
「なんですって……?」
「私たちは別室でその様子を見ていた。そして全問教えて彼女が記入し、彼女が退出した後で、試験官は普通に採点して、目を輝かせて私たちの所にその回答を持ってきた。『全問正解です!』と言いながらね。試験官は私たちが別室で見ていることを知っていた。だから不正など出来るはずがないのに。しかも私が試験の様子を尋ねると、自分が教えたことなどなかったかのように、『彼女はスラスラと解いてました』というのだからまいったね。本当に試験官は自分が彼女に答えを教えたことを覚えていなかったんだ。嘘でも演技でもなく」
「確かになんか別室で、私一人でテストを受けさせられたことがあったけれど、そんな不正はしていません!!」
ローズが叫ぶ。まあそうだろう、不正を認める人などいない。それにハリー王子は控えていた侍従から丸いものを受け取って掲げた。
「これもルパート卿の発明の一つだ。記憶媒体装置という。これには動く映像を保存して再生する機能があるんだ。まだ研究段階だから表には出ていないがね」
植物の成長過程などを手書きするのには限界があり、そのままの風景などを切り取ったように保存できる物はないかと探している時に、星彩ノ華と晶華奏|《しょうかそう》という花を思い出した。
幼少期に父から貰った星彩ノ華は、その薄い花びらに衝撃を与えると、その時の周りの様子が花びらに切り取ったように映し出される特徴があった。
晶華奏は同じように衝撃が加わると、周りの音を記憶し、再生するという花だった。両方とも記録されているのは短時間でしばらくするともとに戻るが、それを使えないかと考えた。
先ずは品種改良で両方の花を人の掌ほどの大きさにすることに成功した。さらに星彩華の花びらに、あるタイミングで再度衝撃を与えることで映像を固定することに成功した。さらに星彩華と晶華奏の花びらを組み合わせて圧縮し、高速で回転させることで5分程度であるが、動く映像と音声を定着させて、更には再生させることに、ようやく成功したのだ。
この花々も栽培が難しかったのでそれを大量に生産するまでに時間もかかったけれど、うまく撮れた時には感激したものだ。それで花の開花の記録に使い、それを論文に載せたことでハリー王子の目にもとまったのだけど。
ハリー王子が丸い映像装置を作動させると、空中に映像が浮かんだ。試験中の二人がいる所から少し離れての録画なのではっきりとは見えないけれど、試験官とローズがいるのは十分にわかるし、音声のおかげで試験官が答えを教えてそれを彼女が記入している場面が映っているのがわかる。離れたところにいる人々には見えないだろうけれど、僕たちには十分に見えた。
「なんなの一体! なんでそんなのがあるのよ……!!」
ローズの小声の叫びが聞こえてきた。僕は、世界初の発明なんだぞと少し誇らしげに思ってしまう。
短時間の映像はすぐに終わってしまったが、それでも映像と音声は皆に衝撃を与えた。
「このように証拠が残っていながら、試験官は教えたことを覚えていないし、認識もしていない。これを見せても納得しないほどだった。となれば、聖女が何かをしたとしか考えられない。残念ながらこの映像には最初に彼女と試験官が交わした会話はとれていないから、それは証明できなかったが」
これで彼女が何らかの力をもって、試験官の思考に影響を与えたのではと誰もが考えた。そうして調べたら彼女の言動には事実が伴っていない疑惑が次々と浮かんできたのだ。
魔法研究省が彼女の学院入学を認めたのも、もしかしたら彼女の言葉に影響されたのではないかと考え始め、そこからいわゆる洗脳魔法ではないかと魔法学部の教授たちが仮定した。
そう仮定してローズを監視してみると、彼女が何かを言うたびに、周りにいる人はその通りに動いたり、思い込むことが判明した。
そう、僕の周りがそうだった。彼女が僕が悪いと言えば、僕が悪くなる。彼女が、マナーが良くなったでしょ? というから、どれだけ食べ散らかしても両親も使用人も、それを肯定する。彼女のいう事を鵜呑みにして僕を攻めてくるのだ。
一番の症例は、トマスだった。彼は僕が本宅を出てからも、定期的に雑用や僕の報告をしに本宅に戻っていた。その時にローズに色々と吹き込まれていたのだ。だから実家に戻るたびに彼は僕に対して攻撃的になっていたのだ。
その時僕を支えているトマスの指に力が入ったのを感じて、僕はトマスを見た。
「トマス?」
「申し訳ありませんでした、ルパート様……。本宅にいた時の私は、ルパート様が悪いと思い込んでいたのです。しかも目の前で勝手にローズ様が転んでいるのを見ているのに、口から出るのはルパート様を責める言葉ばかり。わかっていたんです、ルパート様が悪くないという事は! でも気が付くとルパート様を責めているし、ルパート様の口の動きと聞こえてくる言葉があからさまに違うのに、聞こえてくる言葉に対して攻撃的に返答してしまうのです! 私はルパート様と共に本宅を出ましたけど、本宅に戻るたびに同じ現象になってしまって。使用人の皆からも、ウィロウ先生からも、マリオさんからも、お前は何を言っているのかと何度も言われました。でもどうしようもなかったんです……!」
「うん、わかってるよ」
バルーンフラワーの香りの研究は彼の一言から始まったし、エキスの効果はトマスが自ら手を上げて実験してくれた。その時にも散々謝られた。今回は皆に聞かせるために告白してくれたのだ。僕はその勇気に感謝して、支えてくれている手を軽くたたいた。ハリー王子が続ける。
「ローズ令嬢、お前の能力は、自分の発言をそうだと思い込ませる『洗脳』だな」
「ち、ちがうわ!!」
「お前が最初に治癒能力を発揮したと報告された実父の件も改めて検証した。父親の病気は本物だったし、その回復も本物だった」
「そうでしょう!? 私には治癒能力があるんです!」
「それは違う。お前にあるのは言葉による洗脳。『とうさんの病気はすぐに治って良くなる』そう何度も幼いお前に言ってもらったと、実父が言っていた。それにより実父は『治る』と思い込み、体の免疫機能が跳ね上がったんだろう。そこの剣士の怪我もそうだ。お前の言葉で自己治癒力が上がったんだな。とはいえそれでは治癒能力の内には、はいらない」
「そ、そんな事はないわ!」
「いくら叫んでも無駄だぞ。ここにはアウロラ・ヴェールだけでなく、魔法学科制作による状態異常解除のアイテムが存在するんだ。私も身に着けている」
そう言ってハリー王子が自分の右手を上げると、手首には銀色に輝くブレスレットがあった。僕の提案で魔法学科が開発したものだ。これも自分が実験するとトマスが手を上げてくれただ。おかげでデータが取り放題だった。これはウィロウ先生や助手のヘンリー、近衛の人たちなどがすでに装着している。
万が一にも、ローズの言葉に取り込まれないように。
ハリー王子は用意してあったブレスレットをレイモンド王子に差し出した。彼だけでなくガレス、クラレンス、パーシヴァルにも渡し、彼らは茫然とした表情でそれを自身の手に嵌めた。
「ダメよ! そんなのはめちゃだめ! きっと変な効果が付いているのよ! 騙されちゃだめよ!」
ローズの金切り声が響き渡るが、すでに誰一人として彼女の言葉に従う者はいなかった。
レイモンド王子たちは、真横でキーキーと叫ぶローズを直視できず、蒼白の顔で冷や汗をダラダラと垂らしていた。
あの反応は何度も見た。本宅の執事アーサーも、トマスも。そして、父と母もああだった。
香水やエキスと違って、アイテムは効果が高いが、物凄い手間がかかる上に、大量には作れない。今回はどうしても目を覚まさせる必要がある人数分、ハリー王子が個人資産を出して作ってくれたのだ。
それに一度洗脳が解ければ、あとは香りと香水で対抗できる。ハリー王子は前面に立って対峙するので着用しているが、両親や他の者たちのは回収して、使いまわさせてもらっている。
レイモンド王子は自分の腕にしがみついて喚いているローズを恐る恐る見た。
今まで彼女の声は小さすぎるくらいで、令嬢らしくおっとりとしたしゃべりだったはずだ。だが今はどうだ。
この表情を取り繕うことなく、赤ん坊のように騒ぎ立てているのは、本当にローズなのか? しかし自分の脳が知っている。いつも彼女の言動はガサツで、矛盾だらけだったことを。ルパートを見たというが、その場所は何故か大学部の方だった。ルパートがあちらにいる意味は分からなかったが、少なくとも同じ高校の建物の中で見たことがないルパートが、ローズの邪魔をしに来るとは考えにくかった。だけどローズに訴えられるとそれが真実だと思ってしまう。
ついでに言えば兄のハリーがルパートに接触していることも、ルパートが植物学で革命を起こしていることも「知っていた」。だがローズが「落ちこぼれの兄」というと、それらが認識できなくなる。
ローズと茶を取ると、彼女が座っている周辺には食べこぼしが散乱し、茶器の音も耳障りだった。それでも自分には何故か「マナーは完璧」と思えるのだ。
レイモンド王子は泣きそうだった。現実と虚構を認識し、パニックを起こしかけていた。自分はこんな女とどうして一緒に居られたのか。どうして魅力的だなどと思ったのか。
「ねえ! レイ! 何とか言って! 私は悪くないでしょう!」
「ローズ……。君は一体、僕たちに何をしていたんだ?」
「……え?」
「そうだよ、僕たちは知っていたんだ。君がマナーもなっていないガサツな令嬢だという事を。君にはマナーなんて無いし、授業だってまじめに受けていない。君がテスト前になると勉強を教えてとやってくるけれど、君は全く勉強なんてしなかったし、問題を出しても解けなかった。なのに君が分かったというから、解けたというから。僕たちはそう思い込んでしまった」
「えっと、レイ、どうしたのよ!」
「君に言われて君の兄に会ったけれど、彼は君と違って礼儀正しくて、まさにお手本のような伯爵令息だった。僕がどれだけ失礼な事を言っても、彼は声を荒げることもなかった。君が言う人物像とはかけ離れていた!」
「そんなこと、ないわ! 兄様は意地悪で馬鹿で、どうしようもない男なのよ!」
「この国で『肥料』というものが開発された。おかげで野菜と果物の品質と収穫量が爆発的に上がった。それを作ったのは、ルパート・スタンリーという名だということを、僕は報告書を読んで知っていた。でも君が、あれは君が土に祈りを込めたり、世界に願ったからというから、そうだと思い込んだ!」
「レイ、ちょっと、手を離して、痛い!」
「君は一体、僕たちに何をしていたんだ!」
「ハイそこまで。レイモンド、いくら何でも令嬢の腕を力任せに握り締めるのはいただけないな。」
パニックを起こしかけて、ローズの両腕を掴んでいるレイモンド王子を、ハリー王子があっさりと引きはがした。他の者たちも顔を覆ったり顔面蒼白で茫然としている。
「全員、ちゃんと認識したみたいだね。さあ偽物の聖女ローズ、君の化けの皮は剝がれたよ」
「化けの皮ってなによ! 私は聖女よ!」
「ああそれもね、君が自分で聖女だというから、周りが洗脳されてそう思い込んだというのが事実だ。まあさっき言った通り、その力を上手く使えば、本当の聖女になれたかもしれないけれど、君は道を誤ったんだ」
「どういうことよ!」
「人間、思い込みで病気も怪我も治りやすくなる。君の洗脳でそれが可能なのは証明されている。だからその能力を正しく魔法研究省で磨いていれば、他人を思い通りにする洗脳ではなく、救う事も出来る能力として重宝されたという事さ。だが君は勉強嫌いだった。だから適当な理由を付けて教会での修業を拒み続けた。それはきっと、自分の能力がオーロラの色を持たないし、癒し系ではないのを知っていたからだろう。それが知られたら聖女じゃなくなってしまうと思ったんだろうね」
彼女が本当に慈悲深い人物だったら、彼女に励まされるだけで心が軽くなったり、やる気が出たり、その結果、良い結果をもたらすことにもなっただろう。たとえオーロラの加護がなくても、あれだけの力があれば聖女と同格となれる。だが彼女は自分の欲望に素直だった。面倒ごとから逃げて、自分に都合のいい世界を作り上げようとしていた。
「レイモンド、先ほど聞いたが、オーロラの聖人・聖女の認識が少し違っているぞ。彼らは、オーロラの神に愛され、その加護を受けたものを言うんだ。力が発動するときに色が出やすいというだけで、加護さえあればいい。その女はその加護がない。しかも力に色もない。だいだいこんなガサツな女を、オーロラが愛するわけがないだろう?」
「ふざけんじゃないわよ! あたしは愛されし聖女よ!」
キー! と、頭から湯気を出さんばかりにローズが地団駄を踏みながら叫ぶ。その様子に会場にいる者は全員、不快感を覚えるほどだった。それはもちろん、レイモンド第2王子たちもだ。
「まったく聞くに堪えないな。まあこれでここに居る全員に真実が知れ渡っただろう。ついでにもう一つ曝露してやろう。先ほど毒薬と言われた黒菫草のエキスだが、まずこの黒菫草は、国の許可がなければ採取・栽培が出来ない。ルパート卿の家には無いし、その周辺にも存在していない。確かに彼の屋敷の庭には数多くの植物が栽培されているけれど、全ての種類を国に報告し、確認されている。だから黒菫草をコッソリ栽培など出来るはずがない。侍従があると証言したと言っていたが、それはない。なにせその侍従にレイモンド本人も、その友人たちも言葉を交わしたことがないからな。それに、この毒を町医者で確認したと言ったがそれも無理だ。この毒は特殊な装置が無いと検出できない。この城下でその施設があるのは王立医局のみ。検査したこと事態が、その聖女もどきに思い込まされた嘘なんだよ」
ハリー王子がそう言うと、会場から息を飲む音がした。そして静寂が訪れる。
僕は静かに、ローズに話しかけた。
「ひとつわからないのは、君が何故僕を排除しようとしたか、だ」
僕を両親と同じように洗脳すればよかったのに、彼女は僕を悪役に仕立て上げた。
「そんなの! お前に能力が通じないからにきまっているだろうが!!!」
ローズが大声で叫んだ。
「能力が通じない?」
「お前だけは私のいう事をきかなかった! 何をしても乗ってこなかった!」
確かに僕は、彼女が来たばかりの頃、彼女に遊ぼうと言われて断った。彼女がやる事を注意をした。
「あたしの思い通りにならない人間なんていらないんだよ! それならあたしの引き立て役にしてやろうと思ったのに、それも思い通りにならないから!!」
「そんな事で、僕を悪役にしてたのか」
「そんな事!? あたしの言葉をきけない人間なんて、存在しちゃいけないんだよ! あたしの下僕にもならないんなら、さっさと死ねばよかったのに!」
ああ、僕は彼女に憎まれていたのか。僕を怒らせて、彼女に手を出せばそれを理由に排除できると考えたのだろう。ダメでも僕を悪役に出来る。まだ幼かったのによくそんな事を考え付いたものだ。
ローズの言葉に会場からひそひそと声がした。ローズは周囲を見回して息を飲む。激昂しすぎて思わず本音を吐いてしまったのだろうが、彼女の洗脳はもう効かないから、取り消しようがない。
「さてレイモンド。お前はこの場で罪びとを断罪すると言っていたな。……どうする?」
レイモンド王子は青ざめた顔でハリー王子を見た。その体が震えている。それを深呼吸で押さえて、レイモンド王子はおもむろに僕に向き直り、僕に頭を下げた。
「僕は、ルパート・スタンリー伯爵令息を、誤解していました。まずはお詫びしたい。今までいろいろと決めつけて卿に冤罪を掛けたこと、心から謝罪する」
「レイモンド! なんでよーーー!」
「謝罪は確かに受け取りました」
ローズの絶叫が煩いが、僕は痛む体で臣下の礼を取りながら返答した。ガレスたちも口々に謝罪をしてきた。僕をここに連れてきたクラレンスなど、足元にうずくまって謝ってきたほどだ。
それぞれ謝罪が済むと、レイモンド王子はローズに向き直った。今、彼女はハリー王子の命令で近衛が押さえつけている。僕の時の剣士とは違って、逃げられないように暴れられないようにがっちりと拘束はしているけれど、怪我をするような押さえ方はしていない。さすがだ。
「ローズ……。お前にはいろいろ聞きたいことがある」
「なんでも聞いて! それで私を開放して!」
「何故、こんなことをしたんだ? 何故、きちんと修行しなかった?」
「こんなこと? 私が注目されて、誰にでも愛される! 私が主役の世界を望んだだけよ! だって私は幸せになる事が確定している聖女なんだから!」
「そのために他人を蹴落として? その力を修行して役立てようとはしなかったのか?」
「私が幸せになるためよ! 邪魔なものを蹴落として何が悪いの? 修行しなくたって役に立っているじゃない!」
「嘘にまみれているだけだ。お前の洗脳が解けた今、王族を洗脳した罪で、僕はお前を断罪しなくてはならない」
「はあ? 断罪されるのはルパート! 私じゃないわ!」
「今や彼はこの国に居なくてはいけない人物だ。彼が確立した農業技術のおかげで発展しているのだから」
「兄にそんな事が出来るわけがないじゃない! 騙されているのよみんな!」
「……話にならないな。兄さん、彼女を国家反逆罪で拘束したい」
「ちょっと待ってよ! なんであたし!!」
「良いだろう。だが裁くのはこの場ではなく、司法の場だ」
「はい。お願いします」
「うん」
レイモンド王子が頭を下げ、ハリー王子は満足げにうなずき、合図をすると近衛が喚き続けるローズを引きずってこの場を後にした。それに続きレイモンド王子たちもこの場を後にする。
その際に参加者の列がまたきれいに別れたのだが、その中には憔悴しきった両親も混じっていた。
彼らには今朝、ローズが家を出てからハリー王子が状態解除のブレスレットを渡し、更にバルーンフラワーのエキスを飲ませて洗脳を解除していた。僕は大学に泊まり込んでいたからその場には立ち会っていないのだけど、記憶媒体装置で現実を認識した場面は見せてもらっていた。
大学でハリー王子の使いの者─ヘンリーさんだったのだけど─から話を聞いて、ヘンリーさんが帰ったあとに、僕の元へクラレンスが乗り込んできて、僕を乱暴に連れ出したのだ。
両親は遠くからハリー王子に頭を下げる。それに王子は頷いて、すぐにパン、と手を鳴らした。
「諸君、印象深い卒業記念パーティとなってしまったが、どうかしばらくの間はこの話題は広めないでおいてほしい。いずれ正式に全てを発表するから。そしてせっかくのパーティが弟のせいでめちゃくちゃになってしまった事をお詫びする。それに乗ってさらにめちゃくちゃにした私も、重ねてお詫びする」
あの状況をひっくり返すのは無理だった。であればそれに乗って、全てを明らかにするしかなかった。
「さあ、残り時間は少なくなってしまったが、今日のダンスを楽しみにしていたものも多いだろう。今からダンスパーティーを開催しよう。立食も用意してあるぞ」
ハリー王子の言葉で、会場内に控えていた音楽隊が演奏を始めた。彼女に近かった者たちは踊るような気分ではないだろうが、楽しみにしていた舞踏会だ。おずおずとだが皆が中央にやってきて、パートナーと手を組み始めた。
「さあ、みんな、楽しんでくれたまえ!」
にこやかに宣言するハリー王子に自然と拍手がわき、僕たちはそれに送られるように会場を後にした。
834
あなたにおすすめの小説

聖女のはじめてのおつかい~ちょっとくらいなら国が滅んだりしないよね?~
七辻ゆゆ
ファンタジー
聖女メリルは7つ。加護の権化である聖女は、ほんとうは国を離れてはいけない。
「メリル、あんたももう7つなんだから、お使いのひとつやふたつ、できるようにならなきゃね」
と、聖女の力をあまり信じていない母親により、ひとりでお使いに出されることになってしまった。
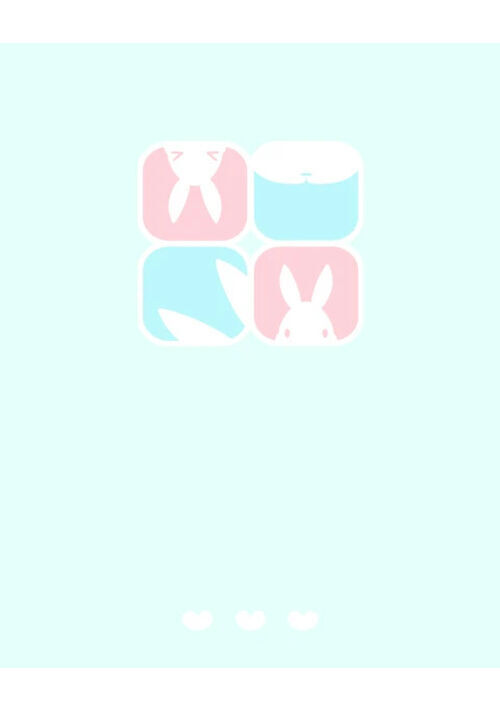
【完結】王太子に婚約破棄され、父親に修道院行きを命じられた公爵令嬢、もふもふ聖獣に溺愛される〜王太子が謝罪したいと思ったときには手遅れでした
まほりろ
恋愛
【完結済み】
公爵令嬢のアリーゼ・バイスは一学年の終わりの進級パーティーで、六年間婚約していた王太子から婚約破棄される。
壇上に立つ王太子の腕の中には桃色の髪と瞳の|庇護《ひご》欲をそそる愛らしい少女、男爵令嬢のレニ・ミュルべがいた。
アリーゼは男爵令嬢をいじめた|冤罪《えんざい》を着せられ、男爵令嬢の取り巻きの令息たちにののしられ、卵やジュースを投げつけられ、屈辱を味わいながらパーティー会場をあとにした。
家に帰ったアリーゼは父親から、貴族社会に向いてないと言われ修道院行きを命じられる。
修道院には人懐っこい仔猫がいて……アリーゼは仔猫の愛らしさにメロメロになる。
しかし仔猫の正体は聖獣で……。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
・ざまぁ有り(死ネタ有り)・ざまぁ回には「ざまぁ」と明記します。
・婚約破棄、アホ王子、モフモフ、猫耳、聖獣、溺愛。
2021/11/27HOTランキング3位、28日HOTランキング2位に入りました! 読んで下さった皆様、ありがとうございます!
誤字報告ありがとうございます! 大変助かっております!!
アルファポリスに先行投稿しています。他サイトにもアップしています。

死に物狂いで支えた公爵家から捨てられたので、回帰後は全財産を盗んで消えてあげます 〜今さら「戻れ」と言われても、私は隣国の皇太子妃ですので〜
しょくぱん
恋愛
「お前のような無能、我が公爵家の恥だ!」
公爵家の長女エルゼは、放蕩者の父や無能な弟に代わり、寝る間も惜しんで領地経営と外交を支えてきた。しかし家族は彼女の功績を奪った挙句、政治犯の濡れ衣を着せて彼女を処刑した。
死の間際、エルゼは誓う。 「もし次があるのなら――二度と、あいつらのために働かない」
目覚めると、そこは処刑の二年前。 再び「仕事」を押し付けようとする厚顔無恥な家族に対し、エルゼは優雅に微笑んだ。
「ええ、承知いたしました。ただし、これからは**『代金』**をいただきますわ」
隠し金庫の鍵、領地の権利書、優秀な人材、そして莫大な隠し資産――。 エルゼは公爵家のすべてを自分名義に書き換え、着々と「もぬけの殻」にしていく。
そんな彼女の前に、隣国の冷徹な皇太子シオンが現れ、驚くべき提案を持ちかけてきて……?
「君のような恐ろしい女性を、独り占めしたくなった」
資産を奪い尽くして亡命した令嬢と、彼女を溺愛する皇太子。 一方、すべてを失った公爵家が泣きついてくるが、もう遅い。 あなたの家の金庫も、土地も、働く人間も――すべて私のものですから。

そんな世界なら滅んでしまえ
キマイラ
恋愛
魔王を倒す勇者パーティーの聖女に選ばれた私は前世の記憶を取り戻した。貞操観念の厳しいこの世界でパーティーの全員と交合せよだなんてありえないことを言われてしまったが絶対お断りである。私が役目をほうきしたくらいで滅ぶ世界なら滅んでしまえばよいのでは?
そんなわけで私は魔王に庇護を求めるべく魔界へと旅立った。

私は聖女(ヒロイン)のおまけ
音無砂月
ファンタジー
ある日突然、異世界に召喚された二人の少女
100年前、異世界に召喚された聖女の手によって魔王を封印し、アルガシュカル国の危機は救われたが100年経った今、再び魔王の封印が解かれかけている。その為に呼ばれた二人の少女
しかし、聖女は一人。聖女と同じ色彩を持つヒナコ・ハヤカワを聖女候補として考えるアルガシュカルだが念のため、ミズキ・カナエも聖女として扱う。内気で何も自分で決められないヒナコを支えながらミズキは何とか元の世界に帰れないか方法を探す。

【完結】私を捨てた国のその後を見守ってみた。
satomi
恋愛
侯爵令嬢のレナは公然の場でというか、卒業パーティーで王太子殿下イズライールに婚約破棄をされた挙句、王太子殿下は男爵令嬢のラーラと婚約を宣言。
殿下は陛下や王妃様がいないときを狙ったんでしょうね。
レナの父はアルロジラ王国の宰相です。実家にはレナの兄が4名いますがみんなそろいもそろって優秀。
長男は領地経営、次男は貿易商、3男は情報屋、4男は…オカマバー経営。
レナは殿下に愛想をつかして、アルロジラ王国の行く末を見守ろうと決意するのです。
次男監修により、国交の断絶しているエミューダ帝国にて。


婚約破棄された聖女様たちは、それぞれ自由と幸せを掴む
青の雀
ファンタジー
捨て子だったキャサリンは、孤児院に育てられたが、5歳の頃洗礼を受けた際に聖女認定されてしまう。
12歳の時、公爵家に養女に出され、王太子殿下の婚約者に治まるが、平民で孤児であったため毛嫌いされ、王太子は禁忌の聖女召喚を行ってしまう。
邪魔になったキャサリンは、偽聖女の汚名を着せられ、処刑される寸前、転移魔法と浮遊魔法を使い、逃げ出してしまう。
、
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















