1
件
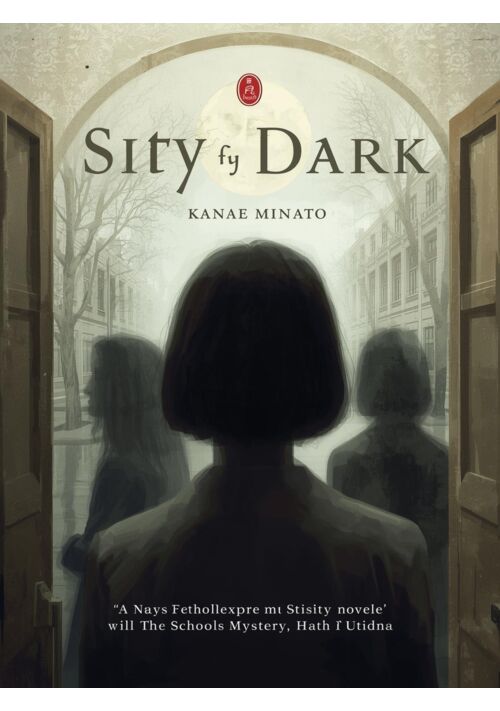
父がいなくなったのは、梅雨入り直後の朝だった。
置きっぱなしの財布と、冷蔵庫に残った昨夜のビールの空き缶。
争った形跡はないのに、家の中の空気だけが妙に冷たい。
母は「そのうち帰ってくるわ」と言い、妹は父の話題になると露骨に顔をしかめる。
家族の反応が、失踪した父よりよほど不可解だった。
違和感を抱えたまま数日が過ぎた頃、物置の奥から古びた封筒が見つかる。
日付は十年前。まだ幼かった私は、その頃の記憶が曖昧だが、
妹は封筒を見るなり怯えたように手を払いのけた。
封筒の中身は、父が書いたと思われる手紙の束。
どれも筆跡が不自然に揺れていて、読むほどに胸がざわつく。
書かれていたのは、十年前の「ある事故」について――誰かを庇うような、言い訳とも懺悔ともつかない言葉。
やがて隣人の老女は、私を見るなり「また隠す気なの?」とつぶやく。
母は目を逸らし、妹はますます頑なになっていく。
調べていくうちに、十年前の事故の“真相”は家族それぞれの中で形を変えていることが分かった。
妹は父を犯人だと信じ、母は自分が加害者だと罪悪感を抱え、
父はその両方を背負うようにして精神をすり減らしていた。
つまり、誰も犯罪者ではないのに、誰も無実ではなかった。
失踪の理由は、父が真犯人扱いされることで、家族に真実が暴かれるのを防ぎたかったから。
罪をかぶるために逃げたのではなく、
「自分が犯人だと家族に思わせるために」
自分から姿を消したのだ。
しかし、父が守ろうとした家族は、父がいなくなって初めて、
互いが抱えてきた“別々の罪”を知る。
真相が明らかになったとき、静かだった家はようやく音を取り戻す。
けれどそこにはもう、父の居場所はなかった。
文字数 970
最終更新日 2025.12.06
登録日 2025.12.06
1
件




















