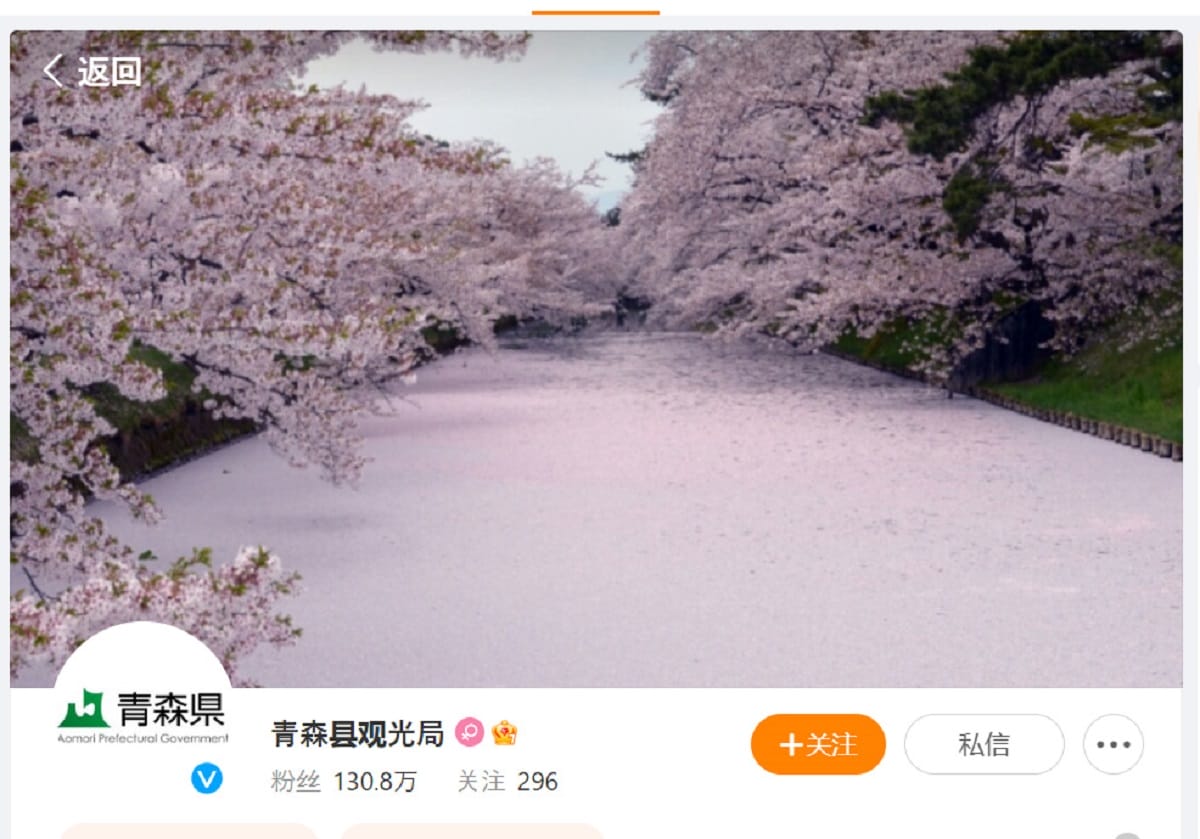
よそ者排除の地方…土佐市・移住者カフェ退去要求、「まちおこし」が死屍累々の理由
2023.05.16
ビジネスジャーナル
良心的に解釈すれば、都会と田舎での暮らし方は違うと説明し、協力を呼び掛けたものだが、言葉遣いが厳しいためにSNSでは批判の的となった。新しく田舎暮らしを考えている人はじっくり考えるべき内容だ。
日本全体が人口減で特定地域だけ増やせるか
「地方創生」「地域創生」「地域活性化」「まちおこし」「むらおこし」――。似たような言葉がたくさんある。それぞれ意味するところは微妙にニュアンスが違うものの、その目的を大雑把にいえば、高齢化・過疎化が進む地方を何とかしようという話である。人口減少・流出を食い止め、人口増加により地域経済を活性化し、魅力的な街づくりをしようということだ。
観光客を誘致して地域活性化を図る取り組みは、全国どこでも行われている。イベントや地元特産品についてうまく情報発信できれば観光客を増やし、特産品の売り上げ増加につなげられるだろう。しかし、それによって過疎化に歯止めをかけ、人口増加に成功した地方の小さな町や村はわずかで、全体で見れば、ほとんど大きな成果は現れていない。
そもそも、日本全体の人口が減少し続けているなかで、特定の地域だけ、あるいは地方の過疎地域だけ人口増加・維持するというのはリアルな話とはいいがたい。もちろん、自治体の地域振興担当者は、東京や大都市圏からの移住者を期待しているのだろうが、雇用機会を提供できなければ、結局は移住者に起業してもらうほかない。地方移住でリモートワークというワークスタイルもよく語られるが、それが可能な職種や業種はかなり限られている。コロナ禍の3年間、東京の一極集中解消を期待する向きもあったが、そんな現象はまったく起きなかった。
また、大都市のサラリーマンが定年後に地方移住するというトレンドも一部にはあるが、現役世代が欲しい自治体地域振興担当者の狙いとは異なるだろう。国による地域振興策は昭和の時代からさまざまな形で続けられている。1988年から1989年にかけて竹下登内閣が各市区町村に対し1億円を交付した「ふるさと創生事業」は税金の無駄遣いとして、今も揶揄されている。
第二次安倍内閣の2014年には「まち・ひと・しごと創生法」を議決、執行した。政府による地方活性化への取り組みは「まち・ひと・しごと創生総合戦略」「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」という形で継続している。地域おこし協力隊も税金を使った国の事業である以上、今後どのような成果を生むのか注視していく必要がある。
(文=横山渉/ジャーナリスト)




























