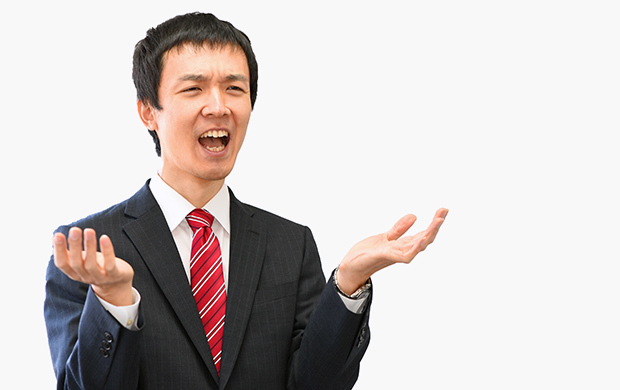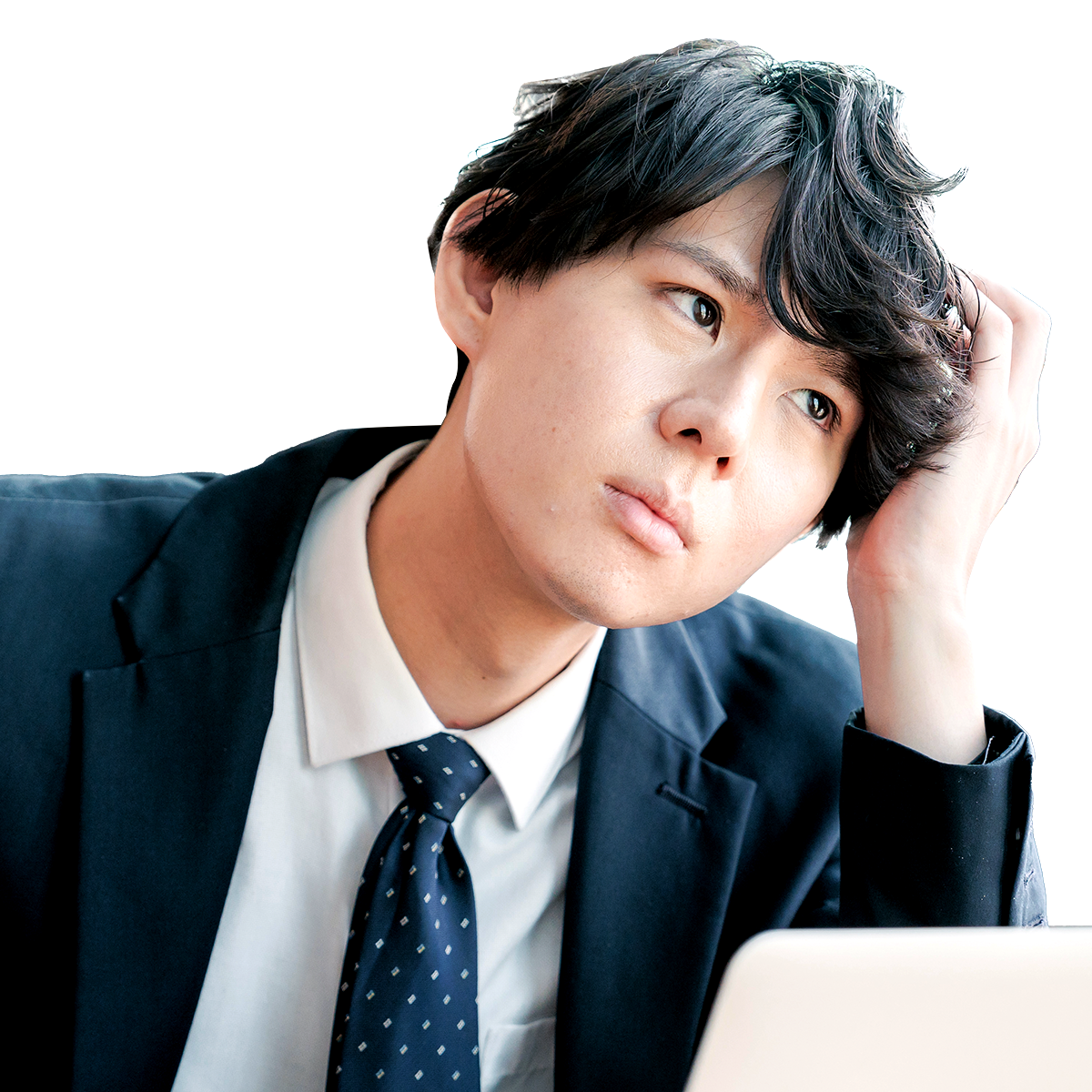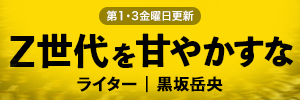「金の蔵」も1店に縮小…サンコーが捨て身の起死回生策、元店長も漁船乗り漁業
2024.05.16
ビジネスジャーナル

かつて「東京チカラめし」や「金の蔵」で一世を風靡した三光マーケティングフーズ(現SANKO MARKETING FOODS/以下、サンコー)。飲食事業が大きく縮小した今、起死回生をかけて水産業に取り組んでいることが話題を呼んでいる。自社で漁船を保有し、社員自らが漁に出るなど、かつては飲食店の店長を務めていた人材なども漁師に配置転換し、まさに背水の陣といえる様子だが、同社が手掛ける水産ビジネスの実態はどのようなものなのか。そして成功のカギを握るものは何か。専門家の見解を交えて追ってみたい。
東京チカラめしの1号店が東京・池袋にオープンしたのは2011年6月。居酒屋「東方見聞録」「月の雫」「金の蔵Jr.」などで知られていたサンコーが運営し、一般的な「煮る牛丼」ではなく「焼く牛丼」を武器に3大チェーンが牙城を占める牛丼業界に殴り込みをかけ、ピーク時には国内で130店まで拡大。一時は500店舗の出店を計画していたが、売上が急減。13年頃からは閉店が相次ぎ、関東圏で唯一営業していた新鎌ヶ谷店(千葉)が昨年11月に閉店。残るは大阪日本橋店のみとなっていたが、今月に東京都内に新規店舗「東京チカラめし食堂」を出店し一部で話題となっている。
サンコーといえば過去に270円均一の居酒屋チェーン「金の蔵」で格安居酒屋ブームを牽引したことでも知られるが、一時期は約100店舗まで拡大したものの現在は1店舗のみの営業。東京チカラめしと金の蔵の縮小を受けサンコーの業績は悪化していき、飲食事業は継続しつつも生き残り策として清掃・除菌事業や官公庁・温浴施設などの飲食店・食堂の運営受託事業などにも手を広げていた。
いまやサンコーは水産企業
そんなサンコーが今、注力しているのが水産業だ。2020年に静岡県の沼津我入道漁業協同組合の組合員となり、自社で漁船を保有し、社員自らが漁に出るなどして生産者の領域に進出。浜松市中央卸売市場の仲卸や豊洲市場で7社しかない大卸・綜合食品の株式を取得してグループ傘下に収めることで、生産・仕入れ・加工・仲卸・飲食店の機能を一気通貫で自社グループに備え、400社以上の仲卸、200社以上の売買参加者、さらには外食・小売事業者との販路を獲得した。このほか「SANKO水産DX」と銘打ち、プラットフォームをインターネット上に構築して漁業・水産事業、飲食事業、Eコマースの事業がリンクするシステムの構築にも取り組んでいる。
サンコーが自社で調達した鮮魚は自社が運営する飲食店でも取り扱っている。沼津で獲れた新鮮な鮮魚を味わえるのをウリとして、大衆酒場「アカマル屋」「アカマル屋鮮魚店」「宮益坂下 酒場」、寿司居酒屋「まるがまる」、寿司店「船上すし みこう」など徐々に店舗を増やしつつある。
外食企業が漁から加工、卸、飲食店まで自社ですべて手掛けるというケースは珍しいのか。外食・フードデリバリーコンサルタントの堀部太一氏はいう。
「外食企業としては非常に珍しいですが、現在のサンコーは事業別売上の規模からみても水産企業といったほうが実態に即しています。同社の24年6月期連結業績予想の売上高110億円のうち、飲食事業の売上高は34億円で全体の30.9%なのに対し、水産事業は74億円で67.3%を占めています」
一企業が飲食事業と水産事業の両方を手掛けるメリットは何か。
「日本は食糧自給率が低いため、価格変動リスクが高いのに加え、食糧を確保できないリスクもあります。自社で一次・二次産業を手掛けることにより、外部環境に依存することなく安定的に原材料を調達でき、変化を察知して事前に対策を打つことができます。もちろん、飲食事業では自社の供給網を使うことで安価に原材料を仕入れられるというメリットもあります。加えて、自社で漁業・加工・卸を手掛けることで外部の多くの飲食店・小売店に商品を卸して販路を拡大できる点もメリットです」(堀部氏)