40 / 57
封土の屋敷 Ⅴ
しおりを挟む
リュディガーが固まるのと、キルシェが息を詰めるのは同時だった。
確かに来訪を伝えるノックに聞こえたが、外は雪が降っているし、そもそもこの屋敷は無人として知られているはずだから、来訪者などいないはず。
__風……?
その可能性を考えたとき、再びノックされて、気の所為ではなかったことが確定した。
__では、誰が……?
妙な緊張がキルシェを襲う。
リュディガーを見れば、キルシェに一瞥した彼は、席を立ったときに流れるような動作で腰に佩いた太刀に手をかけて扉へと向かう。
もう一度ノックがされた。
「__申し訳ない、ご在宅でしょうか?」
ノックとともに、やや張り上げた男の声にキルシェは、新たに鼓動が早くなったのを自覚した。
「待ってくれ、いま出る」
応じながら、リュディガーの目がキルシェへと向けられる。
__奥へ……。
万が一に備えて奥の扉へ駆け込めるように、と目配せで訴えている。キルシェは頷いて、席を立って、静かに扉へと歩み寄った。
部屋は温かいはずなのに、妙に身体が強張っている。
キルシェが扉近くに控えたのを確認してから、リュディガーは玄関の扉を開けた。
蝶番の音とともに、吹き込んでくる寒風の音は鋭い。
細く開けた扉から、リュディガーが外を伺った。
「__これは」
「あ」
最初の声は、外から聞こえた男の声。一瞬遅れた声はリュディガーのそれだが、明らかに驚いた声音だった。
「__どうし……あ、と、とりあえず中へ」
「ありがとうございます。少々お待ちを」
「雪なんて、中で払って構いませんから」
さぁ、と腰の太刀から手を放し、扉をさらに開けてリュディガーは外にいた人物を招き入れた。
厚手の旅装束を纏った男が踏み入ると、リュディガーは急いだ様に扉を閉めるから、キルシェは怪訝にしてしまった。
「来るのは、明日になると記憶していましたが」
「ええ、明日訪れる予定でしたが、最寄りの村に早く着いてしまいました。時間もありましたから、ならばちょっとこちらを見ておこうと思いまして立ち寄ったのです」
__知り合い?
リュディガーが警戒していない様子だから、大丈夫なのだろうが、万が一に備えろ、と控えているキルシェは指示を待つ。
「無人のはずなのに煙が上がっておりましたので……不届き者が居着いてしまったのか、と」
「ああ、なるほど」
穏やかな口調で、上品な喋り方。
大柄なリュディガー越しで、キルシェには会話の相手である男は見えない。
雪を払い落とし、外套を脱いだ男から、リュディガーはそれを受け取ろうとするが、固辞されたようだ。
そこでリュディガーがキルシェへと振り返る。
その顔は、どこか悪戯っぽい顔で、思わず眉をひそめると、リュディガーは身を引いて来訪者を見せた。
来訪者は恰幅があって、穏やかな表情の老年の男。
その顔を、キルシェはそう遠くない過去の記憶に鮮明に残っていて、驚きに思わず口元を抑えた。
「ご無沙汰しております」
恭しく、至極丁寧な手本のような礼をする男。
「ホ、ホルトハウスさん?!」
何故彼が__。
キルシェは言葉を失って、リュディガーを見た。
「お忘れではなくて、安堵いたしました__奥様」
彼は、かつてリュディガーが任務中に下賜された、イェソド州の辺境の屋敷で雇った執事である。
そこで、形式上夫婦として生活したキルシェは、もちろんホルトハウスのことを知っている。__奥様、と呼ばれていたぐらいなのだ。忘れるはずがない。
リュディガーの任務が終わり、その屋敷と土地は別の者へ引き継がれ、雇っていた使用人には数年分の生活費を、退職金としてまとめて支払い解雇した。
希望する者はそのままその屋敷へ新たに来た主に雇われ続けることもでき、それぞれが望むように便宜を図り、手配したと聞いている。
ホルトハウスは、リュディガーが引き払うと同時に、事後の処理を新しい執事へ引き継いでから自身は辞めていたはずである。
だから彼がここにいることは、キルシェにとって驚きでしか無い。__もう会うこともないだろう、と。
「ど、どう……?」
はくはく、と動くばかりの口では、うまく言葉が続いてこない。
それをリュディガーだけでなく、ホルトハウスにもくすり、と笑われてしまう。
「新しいお屋敷で、雇っていただくことになったのです」
「……それは……ここ?」
「左様でございます。ですから、こうしてこちらに」
リュディガーはそこで、テーブルへとホルトハウスを誘った。そして、キルシェにもまた、戻ってくるようにと座っていた席を示すので、キルシェは弾かれるようにして従う。
元の席へ着こうとするが、そこでホルトハウスのお茶を淹れねば、と気づいた。しかし、そのときすでにリュディガーがお茶を淹れるために新しい茶器を持ちに、食器棚に並べられた持参した食器へと向かっていて出る幕はないと悟る。
「どうぞ、お構いなく」
「いやいや。こんな寒いのにお茶も出さないなんてことはないでしょう」
リュディガーが笑って言う言葉に、キルシェも思わず笑ってしまった。では、とキルシェはホルトハウスが手にしたままの濡れた外套を渡すように促した。
「いえ、こんなことまで……とんでもないです」
「ホルトハウスさんは、今はお客様でしょう?」
「そうだな、お客に間違いない。まだ正式に、雇ってはいないからな」
リュディガーがキルシェの言葉に添えるので、思わず、くすり、と笑ってしまう。そこで観念したようにホルトハウスは外套を手放した。
それを暖炉の直ぐ側に掛けていれば、背後でお茶を配する気配がして、キルシェは着席する。
「お手数をおかけいたしまして」
恐縮したようにホルトハウスが言って、お茶を口に運んだ。
ほっ、としたため息を吐き出すのを見守ってから、キルシェは口を開いた。
「ホルトハウスさんを、リュディガーが雇うの?」
「そういう打診をしたんだ。ここの屋敷を下賜されて、使用人を雇わないとならなくなったとき、駄目元で手紙を送ったんだ。駄目なら、ビルネンベルク家の伝手で紹介してもらうということも考えていたが……その後が気になりもしていたから。__で、明日ここに来てもらって実際に見てもらって……という流れだった」
「雪が降りましたから、どうだろうと思っていたのですが、思いの外、旅路が順調で早く着いてしまったのですよ」
「そうだったのですか。__お元気そうで、よかったです」
「奥様も、お変わりなく。拝顔でき、嬉しゅうございます」
奥様、と聞いて、キルシェはいくらか照れを覚える。
「__あの、いまは、そうした間柄ではないので……」
説明済みなのだろうか、と視線でリュディガーに向けると、ホルトハウスが小さく笑った。
確かに来訪を伝えるノックに聞こえたが、外は雪が降っているし、そもそもこの屋敷は無人として知られているはずだから、来訪者などいないはず。
__風……?
その可能性を考えたとき、再びノックされて、気の所為ではなかったことが確定した。
__では、誰が……?
妙な緊張がキルシェを襲う。
リュディガーを見れば、キルシェに一瞥した彼は、席を立ったときに流れるような動作で腰に佩いた太刀に手をかけて扉へと向かう。
もう一度ノックがされた。
「__申し訳ない、ご在宅でしょうか?」
ノックとともに、やや張り上げた男の声にキルシェは、新たに鼓動が早くなったのを自覚した。
「待ってくれ、いま出る」
応じながら、リュディガーの目がキルシェへと向けられる。
__奥へ……。
万が一に備えて奥の扉へ駆け込めるように、と目配せで訴えている。キルシェは頷いて、席を立って、静かに扉へと歩み寄った。
部屋は温かいはずなのに、妙に身体が強張っている。
キルシェが扉近くに控えたのを確認してから、リュディガーは玄関の扉を開けた。
蝶番の音とともに、吹き込んでくる寒風の音は鋭い。
細く開けた扉から、リュディガーが外を伺った。
「__これは」
「あ」
最初の声は、外から聞こえた男の声。一瞬遅れた声はリュディガーのそれだが、明らかに驚いた声音だった。
「__どうし……あ、と、とりあえず中へ」
「ありがとうございます。少々お待ちを」
「雪なんて、中で払って構いませんから」
さぁ、と腰の太刀から手を放し、扉をさらに開けてリュディガーは外にいた人物を招き入れた。
厚手の旅装束を纏った男が踏み入ると、リュディガーは急いだ様に扉を閉めるから、キルシェは怪訝にしてしまった。
「来るのは、明日になると記憶していましたが」
「ええ、明日訪れる予定でしたが、最寄りの村に早く着いてしまいました。時間もありましたから、ならばちょっとこちらを見ておこうと思いまして立ち寄ったのです」
__知り合い?
リュディガーが警戒していない様子だから、大丈夫なのだろうが、万が一に備えろ、と控えているキルシェは指示を待つ。
「無人のはずなのに煙が上がっておりましたので……不届き者が居着いてしまったのか、と」
「ああ、なるほど」
穏やかな口調で、上品な喋り方。
大柄なリュディガー越しで、キルシェには会話の相手である男は見えない。
雪を払い落とし、外套を脱いだ男から、リュディガーはそれを受け取ろうとするが、固辞されたようだ。
そこでリュディガーがキルシェへと振り返る。
その顔は、どこか悪戯っぽい顔で、思わず眉をひそめると、リュディガーは身を引いて来訪者を見せた。
来訪者は恰幅があって、穏やかな表情の老年の男。
その顔を、キルシェはそう遠くない過去の記憶に鮮明に残っていて、驚きに思わず口元を抑えた。
「ご無沙汰しております」
恭しく、至極丁寧な手本のような礼をする男。
「ホ、ホルトハウスさん?!」
何故彼が__。
キルシェは言葉を失って、リュディガーを見た。
「お忘れではなくて、安堵いたしました__奥様」
彼は、かつてリュディガーが任務中に下賜された、イェソド州の辺境の屋敷で雇った執事である。
そこで、形式上夫婦として生活したキルシェは、もちろんホルトハウスのことを知っている。__奥様、と呼ばれていたぐらいなのだ。忘れるはずがない。
リュディガーの任務が終わり、その屋敷と土地は別の者へ引き継がれ、雇っていた使用人には数年分の生活費を、退職金としてまとめて支払い解雇した。
希望する者はそのままその屋敷へ新たに来た主に雇われ続けることもでき、それぞれが望むように便宜を図り、手配したと聞いている。
ホルトハウスは、リュディガーが引き払うと同時に、事後の処理を新しい執事へ引き継いでから自身は辞めていたはずである。
だから彼がここにいることは、キルシェにとって驚きでしか無い。__もう会うこともないだろう、と。
「ど、どう……?」
はくはく、と動くばかりの口では、うまく言葉が続いてこない。
それをリュディガーだけでなく、ホルトハウスにもくすり、と笑われてしまう。
「新しいお屋敷で、雇っていただくことになったのです」
「……それは……ここ?」
「左様でございます。ですから、こうしてこちらに」
リュディガーはそこで、テーブルへとホルトハウスを誘った。そして、キルシェにもまた、戻ってくるようにと座っていた席を示すので、キルシェは弾かれるようにして従う。
元の席へ着こうとするが、そこでホルトハウスのお茶を淹れねば、と気づいた。しかし、そのときすでにリュディガーがお茶を淹れるために新しい茶器を持ちに、食器棚に並べられた持参した食器へと向かっていて出る幕はないと悟る。
「どうぞ、お構いなく」
「いやいや。こんな寒いのにお茶も出さないなんてことはないでしょう」
リュディガーが笑って言う言葉に、キルシェも思わず笑ってしまった。では、とキルシェはホルトハウスが手にしたままの濡れた外套を渡すように促した。
「いえ、こんなことまで……とんでもないです」
「ホルトハウスさんは、今はお客様でしょう?」
「そうだな、お客に間違いない。まだ正式に、雇ってはいないからな」
リュディガーがキルシェの言葉に添えるので、思わず、くすり、と笑ってしまう。そこで観念したようにホルトハウスは外套を手放した。
それを暖炉の直ぐ側に掛けていれば、背後でお茶を配する気配がして、キルシェは着席する。
「お手数をおかけいたしまして」
恐縮したようにホルトハウスが言って、お茶を口に運んだ。
ほっ、としたため息を吐き出すのを見守ってから、キルシェは口を開いた。
「ホルトハウスさんを、リュディガーが雇うの?」
「そういう打診をしたんだ。ここの屋敷を下賜されて、使用人を雇わないとならなくなったとき、駄目元で手紙を送ったんだ。駄目なら、ビルネンベルク家の伝手で紹介してもらうということも考えていたが……その後が気になりもしていたから。__で、明日ここに来てもらって実際に見てもらって……という流れだった」
「雪が降りましたから、どうだろうと思っていたのですが、思いの外、旅路が順調で早く着いてしまったのですよ」
「そうだったのですか。__お元気そうで、よかったです」
「奥様も、お変わりなく。拝顔でき、嬉しゅうございます」
奥様、と聞いて、キルシェはいくらか照れを覚える。
「__あの、いまは、そうした間柄ではないので……」
説明済みなのだろうか、と視線でリュディガーに向けると、ホルトハウスが小さく笑った。
0
あなたにおすすめの小説

捨てられ侯爵令嬢ですが、逃亡先で息子と幸せに過ごしていますので、邪魔しないでください。
蒼月柚希
恋愛
公爵様の呪いは解かれました。
これで、貴方も私も自由です。
……だから、もういいですよね?
私も、自由にして……。
5年後。
私は、ある事情から生まれ育った祖国を離れ、
親切な冒険者パーティーと、その地を治める辺境伯様のご家族に守られながら、
今日も幸せに子育てをしています。
だから貴方も勝手に、お幸せになってくださいね。
私のことは忘れて……。
これは、お互いの思いがこじれ、離れ離れになってしまった一組の夫婦の物語。
はたして、夫婦は無事に、離婚を回避することができるのか?

転生皇女セラフィナ
秋月真鳥
恋愛
公爵家のメイド・クラリッサは、幼い主君アルベルトを庇って十五歳で命を落とした。
目覚めたとき、彼女は皇女セラフィナとして生まれ変わっていた——死の、わずか翌日に。
赤ん坊の身体に十五歳の記憶を持ったまま、セラフィナは新しい人生を歩み始める。
皇帝に溺愛され、優しい母に抱かれ、兄に慈しまれる日々。
前世で冷遇されていた彼女にとって、家族の愛は眩しすぎるほどだった。
しかし、セラフィナの心は前世の主・アルベルトへの想いに揺れ続ける。
一歳のお披露目で再会した彼は、痩せ細り、クラリッサの死を今も引きずっていた。
「わたしは生涯結婚もしなければ子どもを持つこともない。わたしにはそんな幸福は許されない」
そう語るアルベルトの姿に、セラフィナは決意する。
言葉も満足に話せない。自由に動くこともできない。前世の記憶を明かすこともできない。
それでも、彼を救いたい。彼に幸せになってほしい。
転生した皇女が、小さな身体で挑む、長い長い物語が始まる。
※ノベルアップ+、小説家になろうでも掲載しています。

王太子妃専属侍女の結婚事情
蒼あかり
恋愛
伯爵家の令嬢シンシアは、ラドフォード王国 王太子妃の専属侍女だ。
未だ婚約者のいない彼女のために、王太子と王太子妃の命で見合いをすることに。
相手は王太子の側近セドリック。
ところが、幼い見た目とは裏腹に令嬢らしからぬはっきりとした物言いのキツイ性格のシンシアは、それが元でお見合いをこじらせてしまうことに。
そんな二人の行く末は......。
☆恋愛色は薄めです。
☆完結、予約投稿済み。
新年一作目は頑張ってハッピーエンドにしてみました。
ふたりの喧嘩のような言い合いを楽しんでいただければと思います。
そこまで激しくはないですが、そういうのが苦手な方はご遠慮ください。
よろしくお願いいたします。

十年間虐げられたお針子令嬢、冷徹侯爵に狂おしいほど愛される。
er
恋愛
十年前に両親を亡くしたセレスティーナは、後見人の叔父に財産を奪われ、物置部屋で使用人同然の扱いを受けていた。義妹ミレイユのために毎日ドレスを縫わされる日々——でも彼女には『星霜の記憶』という、物の過去と未来を視る特別な力があった。隠されていた舞踏会の招待状を見つけて決死の潜入を果たすと、冷徹で美しいヴィルフォール侯爵と運命の再会! 義妹のドレスが破れて大恥、叔父も悪事を暴かれて追放されるはめに。失われた伝説の刺繍技術を復活させたセレスティーナは宮廷筆頭職人に抜擢され、「ずっと君を探していた」と侯爵に溺愛される——

婚約者が最凶すぎて困っています
白雲八鈴
恋愛
今日は婚約者のところに連行されていました。そう、二か月は不在だと言っていましたのに、一ヶ月しか無かった私の平穏。
そして現在進行系で私は誘拐されています。嫌な予感しかしませんわ。
最凶すぎる第一皇子の婚約者と、その婚約者に振り回される子爵令嬢の私の話。
*幼少期の主人公の言葉はキツイところがあります。
*不快におもわれましたら、そのまま閉じてください。
*作者の目は節穴ですので、誤字脱字があります。
*カクヨム。小説家になろうにも投稿。

ヤンキー、悪役令嬢になる
山口三
恋愛
岸田和華(きしだわか)は異世界に飛ばされた。自分が読んでいた小説の悪役令嬢ジュリエットに憑依してしまったのだ。だが和華は短気でガサツで、中学高校と番を張ってたヤンキーだ。高貴な身分の貴族令嬢なんてガラじゃない。「舞踏会でダンス? 踊りなんて盆踊りしか知らないからっ」
一方、リアル世界に残された和華の中にはジュリエットが入っていて・・。
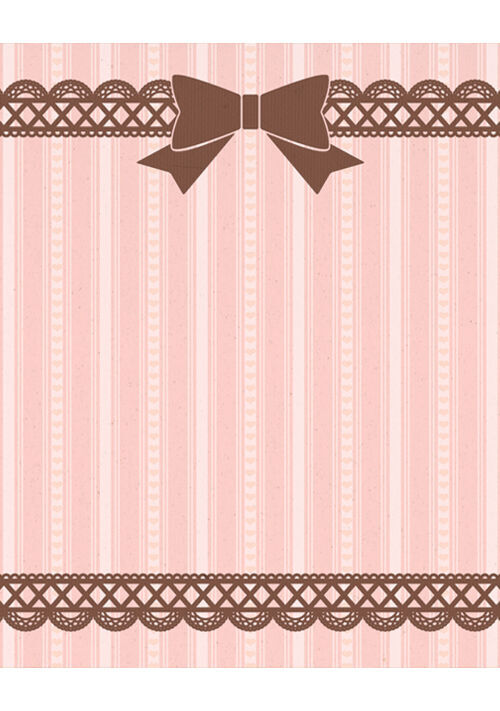
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行「婚約破棄ですか? それなら昨日成立しましたよ、ご存知ありませんでしたか?」完結
まほりろ
恋愛
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行中。
コミカライズ化がスタートしましたらこちらの作品は非公開にします。
「アリシア・フィルタ貴様との婚約を破棄する!」
イエーガー公爵家の令息レイモンド様が言い放った。レイモンド様の腕には男爵家の令嬢ミランダ様がいた。ミランダ様はピンクのふわふわした髪に赤い大きな瞳、小柄な体躯で庇護欲をそそる美少女。
対する私は銀色の髪に紫の瞳、表情が表に出にくく能面姫と呼ばれています。
レイモンド様がミランダ様に惹かれても仕方ありませんね……ですが。
「貴様は俺が心優しく美しいミランダに好意を抱いたことに嫉妬し、ミランダの教科書を破いたり、階段から突き落とすなどの狼藉を……」
「あの、ちょっとよろしいですか?」
「なんだ!」
レイモンド様が眉間にしわを寄せ私を睨む。
「婚約破棄ですか? 婚約破棄なら昨日成立しましたが、ご存知ありませんでしたか?」
私の言葉にレイモンド様とミランダ様は顔を見合わせ絶句した。
全31話、約43,000文字、完結済み。
他サイトにもアップしています。
小説家になろう、日間ランキング異世界恋愛2位!総合2位!
pixivウィークリーランキング2位に入った作品です。
アルファポリス、恋愛2位、総合2位、HOTランキング2位に入った作品です。
2021/10/23アルファポリス完結ランキング4位に入ってました。ありがとうございます。
「Copyright(C)2021-九十九沢まほろ」

魔法師団長の家政婦辞めたら溺愛されました
iru
恋愛
小説家になろうですでに完結済みの作品です。よければお気に入りブックマークなどお願いします。
両親と旅をしている途中、魔物に襲われているところを、魔法師団に助けられたティナ。
両親は亡くなってしまったが、両親が命をかけて守ってくれた自分の命を無駄にせず強く生きていこうと決めた。
しかし、肉親も家もないティナが途方に暮れていると、魔物から助けてくれ、怪我の入院まで面倒を見てくれた魔法師団の団長レオニスから彼の家政婦として住み込みで働かないと誘われた。
魔物から助けられた時から、ひどく憧れていたレオニスの誘いを、ティナはありがたく受ける事にした。
自分はただの家政婦だと強く言い聞かせて、日に日に膨らむ恋心を抑え込むティナだった。
一方、レオニスもティナにどんどん惹かれていっていた。
初めはなくなった妹のようで放っては置けないと家政婦として雇ったが、その健気な様子に強く惹かれていった。
恋人になりたいが、年上で雇い主。
もしティナも同じ気持ちでないなら仕事まで奪ってしまうのではないか。
そんな思いで一歩踏み出せないレオニスだった。
そんな中ある噂から、ティナはレオニスの家政婦を辞めて家を出る決意をする。
レオニスは思いを伝えてティナを引き止めることができるのか?
両片思いのすれ違いのお話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















