16 / 28
第16章: 王太子の守護者
しおりを挟む
毒の一件以来、レオニードの態度は少し変わった気がする。
私を守るために、レオニードがどれだけ気を使ってくれているのか、しばしば感じるようになった。
彼がどこからか見守っている気がする。
たとえば、庭園で侍女と作業しているとき、ふと目を向けると、遠くからその背中が見える。
まるで影のように、誰にも気づかれずに私を見守っている。
「姫様、今日はお花をもう少し摘んでおきましょうか?」
侍女の声に、私ははっと我に返る。
レオニードの姿はすでに見えなくなっていたけれど、その視線がどこかで感じ取られていた気がして、少しドキドキしていた。
「うーん…、もう少しだけ作業をしてみようかな。」
その後も、レオニードがどこかで見守っていることを感じながら、私は一生懸命花を摘んでいた。
彼の目がどこかで僕に向けられている気がして、少し恥ずかしくなる。
まるで監視されているみたいで、でも、心のどこかでその気配が嬉しい自分もいる。
でも、彼は何も言わない。
見守るだけ。
だから、私は何も言わず、敢えて問いただすこともなかった。
その日、カイルと顔を合わせた時、ふとその話が出た。
「アリシア様、レオニード様が姫様のことを気にかけていること、気づいてますか?」
カイルの言葉に、私は思わず顔を赤らめる。
心の中で「何を言ってるのよ…」と思いながらも、カイルの目が真剣そのもので、なかなか反論できない。
「え、ええ? 別にそんな…。」と、私はなんとかごまかそうとしたけれど、カイルはニヤリと笑った。
「姫様、そんなに素直に認めるのが恥ずかしいんですか?」
「別に! そんなことないわよ。」と、私は強がりながらも、目をそらして言う。
その瞬間、胸の中で何かがモヤモヤと渦巻く。
でも、それがなんなのか、まだよくわからない。
カイルが軽く肩をすくめて、「でも、レオニード様が守ってくれているのは確かですよ。あの人、姫様のことを思っているに決まってますから。」
「思ってる…?」
私がその言葉を反復すると、カイルがにっこりと笑う。
「もちろんですよ。レオニード様、いつも姫様のことを見守ってるじゃないですか。あれ、愛情の証拠ですよ。」と、カイルが言うと、私はその言葉にドキっとしてしまった。
愛情…?
その一言が、私の心を少しだけ揺さぶった。
レオニードが見守ってくれるのは、きっと守りたいからだと思っていた。
王太子としての義務からか、もしくは単なる優しさか。
それとも、カイルの言うように、彼が私を…?
その夜、私は寝室で天井を見上げながら、ずっとそのことを考えていた。
レオニードが僕を守ろうとしていること、その心の中に何があるのか、全然わからない。
ただ、彼の存在が少しずつ気になってくる自分がいる。
その時、カイルの言葉が頭をよぎる。
「レオニード様は姫様を想っていますよ。」
あの言葉を思い出すたびに、胸の奥がくすぐったくなるような気持ちになる。
それは、きっと恥ずかしさからだと思うけど、心の中で少しだけレオニードが、私の特別な存在として位置づけられている気がしてならなかった。
次の日、再び庭園でレオニードの姿を見かけた。
遠くから、またもや僕の様子を伺っている。
彼の目が僕に向けられていることに気づくと、なんだか嬉しい気持ちが湧き上がった。
「…また見てる。」と、私は思わずつぶやいてしまう。
でも、そのまま何も言わずに立ち去ろうとした時、ふと彼が近づいてきて、ちょっと照れくさい笑顔を見せてくれた。
「お前、カイルに何か言われたか?」
その問いかけに、私は顔が赤くなる。
「な、なんでもないわよ。」と、慌てて答えるが、レオニードの目が笑っているのがわかる。
「なら、いいけど。だが、俺はお前が無事でいてくれることが一番大切だ。」そう言う彼の真剣な目を見つめ返すと、なんだか胸がドキドキしてくる。
「ありがとう…。」と、私は静かに答える。
その瞬間、レオニードが少しだけ口元をゆるめ、優しく言った。
「お前が笑ってくれるだけで、俺は嬉しいんだ。」
その言葉に、心の中で何かが温かくなった。
彼の優しさに、私は少しだけ勇気を出して、ほんの少しだけ、素直な気持ちを伝えたくなった。
「じゃあ、レオニードも…私を守ってくれてるの?」と、つい言ってしまう。
レオニードは、少しだけ驚いた顔をして、でもすぐににっこりと笑った。
「もちろんだ。これからも、ずっと。」
その言葉に、私は顔を赤くしてうつむき、心の中で小さくガッツポーズをしていた。
私を守るために、レオニードがどれだけ気を使ってくれているのか、しばしば感じるようになった。
彼がどこからか見守っている気がする。
たとえば、庭園で侍女と作業しているとき、ふと目を向けると、遠くからその背中が見える。
まるで影のように、誰にも気づかれずに私を見守っている。
「姫様、今日はお花をもう少し摘んでおきましょうか?」
侍女の声に、私ははっと我に返る。
レオニードの姿はすでに見えなくなっていたけれど、その視線がどこかで感じ取られていた気がして、少しドキドキしていた。
「うーん…、もう少しだけ作業をしてみようかな。」
その後も、レオニードがどこかで見守っていることを感じながら、私は一生懸命花を摘んでいた。
彼の目がどこかで僕に向けられている気がして、少し恥ずかしくなる。
まるで監視されているみたいで、でも、心のどこかでその気配が嬉しい自分もいる。
でも、彼は何も言わない。
見守るだけ。
だから、私は何も言わず、敢えて問いただすこともなかった。
その日、カイルと顔を合わせた時、ふとその話が出た。
「アリシア様、レオニード様が姫様のことを気にかけていること、気づいてますか?」
カイルの言葉に、私は思わず顔を赤らめる。
心の中で「何を言ってるのよ…」と思いながらも、カイルの目が真剣そのもので、なかなか反論できない。
「え、ええ? 別にそんな…。」と、私はなんとかごまかそうとしたけれど、カイルはニヤリと笑った。
「姫様、そんなに素直に認めるのが恥ずかしいんですか?」
「別に! そんなことないわよ。」と、私は強がりながらも、目をそらして言う。
その瞬間、胸の中で何かがモヤモヤと渦巻く。
でも、それがなんなのか、まだよくわからない。
カイルが軽く肩をすくめて、「でも、レオニード様が守ってくれているのは確かですよ。あの人、姫様のことを思っているに決まってますから。」
「思ってる…?」
私がその言葉を反復すると、カイルがにっこりと笑う。
「もちろんですよ。レオニード様、いつも姫様のことを見守ってるじゃないですか。あれ、愛情の証拠ですよ。」と、カイルが言うと、私はその言葉にドキっとしてしまった。
愛情…?
その一言が、私の心を少しだけ揺さぶった。
レオニードが見守ってくれるのは、きっと守りたいからだと思っていた。
王太子としての義務からか、もしくは単なる優しさか。
それとも、カイルの言うように、彼が私を…?
その夜、私は寝室で天井を見上げながら、ずっとそのことを考えていた。
レオニードが僕を守ろうとしていること、その心の中に何があるのか、全然わからない。
ただ、彼の存在が少しずつ気になってくる自分がいる。
その時、カイルの言葉が頭をよぎる。
「レオニード様は姫様を想っていますよ。」
あの言葉を思い出すたびに、胸の奥がくすぐったくなるような気持ちになる。
それは、きっと恥ずかしさからだと思うけど、心の中で少しだけレオニードが、私の特別な存在として位置づけられている気がしてならなかった。
次の日、再び庭園でレオニードの姿を見かけた。
遠くから、またもや僕の様子を伺っている。
彼の目が僕に向けられていることに気づくと、なんだか嬉しい気持ちが湧き上がった。
「…また見てる。」と、私は思わずつぶやいてしまう。
でも、そのまま何も言わずに立ち去ろうとした時、ふと彼が近づいてきて、ちょっと照れくさい笑顔を見せてくれた。
「お前、カイルに何か言われたか?」
その問いかけに、私は顔が赤くなる。
「な、なんでもないわよ。」と、慌てて答えるが、レオニードの目が笑っているのがわかる。
「なら、いいけど。だが、俺はお前が無事でいてくれることが一番大切だ。」そう言う彼の真剣な目を見つめ返すと、なんだか胸がドキドキしてくる。
「ありがとう…。」と、私は静かに答える。
その瞬間、レオニードが少しだけ口元をゆるめ、優しく言った。
「お前が笑ってくれるだけで、俺は嬉しいんだ。」
その言葉に、心の中で何かが温かくなった。
彼の優しさに、私は少しだけ勇気を出して、ほんの少しだけ、素直な気持ちを伝えたくなった。
「じゃあ、レオニードも…私を守ってくれてるの?」と、つい言ってしまう。
レオニードは、少しだけ驚いた顔をして、でもすぐににっこりと笑った。
「もちろんだ。これからも、ずっと。」
その言葉に、私は顔を赤くしてうつむき、心の中で小さくガッツポーズをしていた。
0
あなたにおすすめの小説

つまらない妃と呼ばれた日
柴田はつみ
恋愛
公爵令嬢リーシャは政略結婚で王妃に迎えられる。だが国王レオニスの隣には、幼馴染のセレスが“当然”のように立っていた。祝宴の夜、リーシャは国王が「つまらない妃だ」と語る声を聞いてしまい、心を閉ざす。
舞踏会で差し出された手を取らず、王弟アドリアンの助けで踊ったことで、噂は一気に燃え上がる――「王妃は王弟と」「国王の本命は幼馴染」と。
さらに宰相は儀礼と世論を操り、王妃を孤立させる策略を進める。監視の影、届かない贈り物、すり替えられた言葉、そして“白薔薇の香”が事件現場に残る冤罪の罠。
リーシャは微笑を鎧に「今日から、王の隣に立たない」と決めるが、距離を取るほど誤解は確定し、王宮は二人を引き裂いていく。
――つまらない妃とは、いったい誰が作ったのか。真実が露わになった時、失われた“隣”は戻るのか。

【完結】仰る通り、貴方の子ではありません
ユユ
恋愛
辛い悪阻と難産を経て産まれたのは
私に似た待望の男児だった。
なのに認められず、
不貞の濡れ衣を着せられ、
追い出されてしまった。
実家からも勘当され
息子と2人で生きていくことにした。
* 作り話です
* 暇つぶしにどうぞ
* 4万文字未満
* 完結保証付き
* 少し大人表現あり
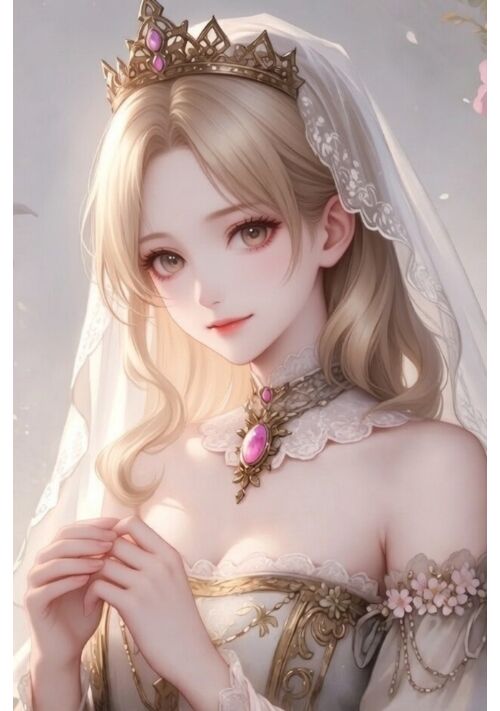
スキルなし王妃の逆転劇〜妹の策略で悪役令嬢にされ、婚約破棄された私が冷酷王の心を歌で揺らすまで〜
雪城 冴
恋愛
聖歌もファンファーレもない無音の結婚式。
「誓いの言葉は省略する」
冷酷王の宣言に、リリアナは言葉を失った。
スキル名を持たないという理由だけで“無能”と蔑まれてきたリリアナ。
妹の企みにより婚約破棄され、隣国の王・オスカーとの政略結婚が決まる。
義妹は悪魔のような笑みで言う。
「次は婚約破棄されないようにお気をつけて」
リリアナに残されたのは、自分を慰めるように歌うことだけ。
ところが、魔力が満ちるはずの王国には、舞踏会すら開かれない不気味な静寂が広がっていた。
――ここは〈音のない国〉
冷酷王が隠している“真実”とは?
そして、リリアナの本当のスキルとは――。
勇気と知性で運命を覆す、
痛快逆転ファンタジー。
※表紙絵はAI生成

夫と息子に邪険にされたので王太子妃の座を譲ります~死に戻ってから溺愛されても今更遅い
青の雀
恋愛
夫婦喧嘩の末に置き去りにされた妻は、旦那が若い愛人とイチャついている間に盗賊に襲われ、命を落とした。
神様の温情により、10日間だけこの世に戻った妻と護衛の騎士は、その10日間の間に心残りを処分する。それは、娘の行く末と……もし、来世があるならば、今度は政略といえども夫以外の人の妻になるということ。
もう二度と夫と出会いたくない彼女は、彼女を蔑ろにしてきた息子とも縁を切ることを決意する。
生まれかわった妻は、新しい人生を強く生きることを決意。
過去世と同じ轍を踏みたくない……

嘘をありがとう
七辻ゆゆ
恋愛
「まあ、なんて図々しいのでしょう」
おっとりとしていたはずの妻は、辛辣に言った。
「要するにあなた、貴族でいるために政略結婚はする。けれど女とは別れられない、ということですのね?」
妻は言う。女と別れなくてもいい、仕事と嘘をついて会いに行ってもいい。けれど。
「必ず私のところに帰ってきて、子どもをつくり、よい夫、よい父として振る舞いなさい。神に嘘をついたのだから、覚悟を決めて、その嘘を突き通しなさいませ」

新婚初夜に『白い結婚にしてほしい』と言われたので論理的に詰めたら夫が泣きました
ささい
恋愛
「愛人がいるから、白い結婚にしてほしい」
政略結婚の初夜にそう告げた夫ルーファス。
妻カレンの反応は——
「それ、契約不履行ですよね?」
「あなたの感情論、論理的に破綻してますよ?」
泣き落としは通じない。
そして初夜の翌朝、夫は泣いていた。
逃げ道は全部塞がれ、気づけば毎日論破されていた。
これは、論破され続けた夫がなぜか幸せになる話。

辺境伯夫人は領地を紡ぐ
やまだごんた
恋愛
王命によりヴァルデン辺境伯に嫁ぐことになった、前ベルンシュタイン公爵令嬢のマルグリット。
しかし、彼女を待っていたのは60年にも及ぶ戦争で荒廃し、冬を越す薪すら足りない現実だった。
物資も人手も足りない中、マルグリットは領地の立て直しに乗り出す。
戦しか知らなかったと自省する夫と向き合いながら、少しずつ築かれていく夫婦の距離。
これは、1人の女性が領地を紡ぎ、夫と共に未来を作る「内政×溺愛」の物語です。
全50話の予定です
※表紙はイメージです
※アルファポリス先行公開(なろうにも転載予定です)

「貴女じゃ彼に不釣りあいだから別れて」と言われたので別れたのですが、呪われた上に子供まで出来てて一大事です!?
綾織季蝶
恋愛
「貴女じゃ彼に不釣りあいだから別れて」そう告げられたのは孤児から魔法省の自然管理科の大臣にまで上り詰めたカナリア・スタインベック。
相手はとある貴族のご令嬢。
確かに公爵の彼とは釣り合うだろう、そう諦めきった心で承諾してしまう。
別れる際に大臣も辞め、実家の誰も寄り付かない禁断の森に身を潜めたが…。
何故か呪われた上に子供まで出来てしまった事が発覚して…!?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















