10 / 28
患者
しおりを挟む
医大六年で国家試験に合格し、卒業後、研修医になった。
研修期間は複数の部署を回る。
小児科で三カ月、整形外科で二カ月、救急病棟で一カ月。
さすがに救急病棟はきつかった。
つぎつぎ運ばれてくる患者。息つく暇もない。
ナース、先輩医師はタフな体育系な人たちばかりだ。
救急病棟は自分には無理だと一日で感じた。
体力的にも精神的にも限界だった。大量の血がきつかった。
とくに交通事故の場合、大量出血を見ているだけで卒倒しそうになった。
夜勤や徹夜も当然ある。
おぼっちゃま育ちのゆるいメンタルの僕には到底務まらない仕事場だった。
次の研修場所は免疫科。
無菌室に入るときはわくわくした。言葉のとおり、菌がいない部屋。
免疫科には免疫力が相当弱っている入院患者がいて、健常者にはなんでもない菌でも感染すれば重篤状態に陥り、死亡することもある。
その科には半年いた。楽だった。大量の血を見ることもなく、フロアーもきれいで静かだった。将来ここで働きたいと思った。
ある日、外来で三十代半ばの男性が診察にやってきた。ボロボロのやさグレた中年だった。
診察が終わり、その患者が帰った後、ベテランの女医が言った。
「もう発症しちゃってるから、あー、もって半年かもね。桐野くん、カルテ見る?」
手渡されたカルテにはヒト免疫不全ウイルス感染と書かれている。
「あの人、ゲイで性交渉で感染しちゃったみたいよ。最近、そういう人、多いみたいね。よそで検査してもらったら、思いっきりポジティブ。おまけにもう手遅れ。うちでどうしろっていうのよ」
「余命僅かってことですか?」
「だって、エイズよ。エイズ。早めに病院にかかっていれば、発症は薬で止められたのにね」
女医の言葉には同情は感じられず、面倒な患者としか思っていないようだった。
二週間後、その男性が入院してきた。インテリで頭の良さそうなニヒルな男性で、矢向さんといった。
たまに回診にいくと、世間話しをした。
職業はフリーのジャーナリストで、よくしゃべる人だった。二十代の時は新聞記者もしていたらしい。
早朝、水をジャグに用意して持って行った。
医者の仕事ではないが、矢向さんに興味を持ったのだ。
個室の病室に入りジャグをテーブルに置く。
「研修はどう?」矢向さんに聞かれた。
「ええ、ぼちぼち」
「君、医者に向いてないよ。なんで医大に行ったの?」
失礼なおじさんだな。いらっとした。
「親は法学部に行って欲しかったみたいですけどね」
「勉強もできたから、親に反発してってことか」
「そうですよ」
本当の理由は国立法学部に落ちたからだ。
無謀すぎるし無理だから止めとけと高校の進路指導の先生に言われたのに東大を受けた。
思いっきり滑った。
たまたま受けていた私立医大に受かっていたので、東大受験に玉砕し心が折れた僕は医大に進んだ。
くくくと矢向さんは笑った。
「俺みたいにならないように気を付けないとな」じっと僕を見て言った。
「え?」
「エイズに罹るなってこと。君、ゲイだろ?」
「はあ?」
「分かるんだよ。しゃべり方とか雰囲気でさ」
なんでもズバズバ言うおじさんだった。
随分元気そうだけど、本当に余命半年なのだろうか。
自分よりかなり年上の人は恋愛対象ではなかったが、話の面白い矢向さんに惹かれた。
よく病室を訪れおしゃべりをした。
たまに矢向さんの友達がお見舞いに訪れ、病室は賑やかになった。
矢向さんの行きつけのゲイ・バー「ベアー」の常連客たちだった。
「矢向ちゃんの好きなぶり大根作ってきたわよ」おねえ言葉のなよなよした若者が言った。
「筑前煮とビールも買ってきたわよ」がたいのいい青年がコンビニの袋を差し出した。
ゲイ仲間がくると病室は二丁目のパブ化した。
僕も酒をすすめられたが断った。
彼らの会話を聞いているだけで楽しかった。
できるならもっと参加したかったが、病院に自分もゲイだと知られるのが怖かったので、あまり深入りはしなかった。
研修期間は複数の部署を回る。
小児科で三カ月、整形外科で二カ月、救急病棟で一カ月。
さすがに救急病棟はきつかった。
つぎつぎ運ばれてくる患者。息つく暇もない。
ナース、先輩医師はタフな体育系な人たちばかりだ。
救急病棟は自分には無理だと一日で感じた。
体力的にも精神的にも限界だった。大量の血がきつかった。
とくに交通事故の場合、大量出血を見ているだけで卒倒しそうになった。
夜勤や徹夜も当然ある。
おぼっちゃま育ちのゆるいメンタルの僕には到底務まらない仕事場だった。
次の研修場所は免疫科。
無菌室に入るときはわくわくした。言葉のとおり、菌がいない部屋。
免疫科には免疫力が相当弱っている入院患者がいて、健常者にはなんでもない菌でも感染すれば重篤状態に陥り、死亡することもある。
その科には半年いた。楽だった。大量の血を見ることもなく、フロアーもきれいで静かだった。将来ここで働きたいと思った。
ある日、外来で三十代半ばの男性が診察にやってきた。ボロボロのやさグレた中年だった。
診察が終わり、その患者が帰った後、ベテランの女医が言った。
「もう発症しちゃってるから、あー、もって半年かもね。桐野くん、カルテ見る?」
手渡されたカルテにはヒト免疫不全ウイルス感染と書かれている。
「あの人、ゲイで性交渉で感染しちゃったみたいよ。最近、そういう人、多いみたいね。よそで検査してもらったら、思いっきりポジティブ。おまけにもう手遅れ。うちでどうしろっていうのよ」
「余命僅かってことですか?」
「だって、エイズよ。エイズ。早めに病院にかかっていれば、発症は薬で止められたのにね」
女医の言葉には同情は感じられず、面倒な患者としか思っていないようだった。
二週間後、その男性が入院してきた。インテリで頭の良さそうなニヒルな男性で、矢向さんといった。
たまに回診にいくと、世間話しをした。
職業はフリーのジャーナリストで、よくしゃべる人だった。二十代の時は新聞記者もしていたらしい。
早朝、水をジャグに用意して持って行った。
医者の仕事ではないが、矢向さんに興味を持ったのだ。
個室の病室に入りジャグをテーブルに置く。
「研修はどう?」矢向さんに聞かれた。
「ええ、ぼちぼち」
「君、医者に向いてないよ。なんで医大に行ったの?」
失礼なおじさんだな。いらっとした。
「親は法学部に行って欲しかったみたいですけどね」
「勉強もできたから、親に反発してってことか」
「そうですよ」
本当の理由は国立法学部に落ちたからだ。
無謀すぎるし無理だから止めとけと高校の進路指導の先生に言われたのに東大を受けた。
思いっきり滑った。
たまたま受けていた私立医大に受かっていたので、東大受験に玉砕し心が折れた僕は医大に進んだ。
くくくと矢向さんは笑った。
「俺みたいにならないように気を付けないとな」じっと僕を見て言った。
「え?」
「エイズに罹るなってこと。君、ゲイだろ?」
「はあ?」
「分かるんだよ。しゃべり方とか雰囲気でさ」
なんでもズバズバ言うおじさんだった。
随分元気そうだけど、本当に余命半年なのだろうか。
自分よりかなり年上の人は恋愛対象ではなかったが、話の面白い矢向さんに惹かれた。
よく病室を訪れおしゃべりをした。
たまに矢向さんの友達がお見舞いに訪れ、病室は賑やかになった。
矢向さんの行きつけのゲイ・バー「ベアー」の常連客たちだった。
「矢向ちゃんの好きなぶり大根作ってきたわよ」おねえ言葉のなよなよした若者が言った。
「筑前煮とビールも買ってきたわよ」がたいのいい青年がコンビニの袋を差し出した。
ゲイ仲間がくると病室は二丁目のパブ化した。
僕も酒をすすめられたが断った。
彼らの会話を聞いているだけで楽しかった。
できるならもっと参加したかったが、病院に自分もゲイだと知られるのが怖かったので、あまり深入りはしなかった。
11
あなたにおすすめの小説

恋人はメリーゴーランド少年だった~永遠の誓い編
夏目奈緖
BL
「恋人はメリーゴーランド少年だった」続編です。溺愛ドS社長×高校生。恋人同士になった二人の同棲物語。束縛と独占欲。。夏樹と黒崎は恋人同士。夏樹は友人からストーカー行為を受け、車へ押し込まれようとした際に怪我を負った。夏樹のことを守れずに悔やんだ黒崎は、二度と傷つけさせないと決心し、夏樹と同棲を始める。その結果、束縛と独占欲を向けるようになった。黒崎家という古い体質の家に生まれ、愛情を感じずに育った黒崎。結びつきの強い家庭環境で育った夏樹。お互いの価値観のすれ違いを経験し、お互いのトラウマを解消するストーリー。

旦那様と僕
三冬月マヨ
BL
旦那様と奉公人(の、つもり)の、のんびりとした話。
縁側で日向ぼっこしながらお茶を飲む感じで、のほほんとして頂けたら幸いです。
本編完結済。
『向日葵の庭で』は、残酷と云うか、覚悟が必要かな? と思いまして注意喚起の為『※』を付けています。

想いの名残は淡雪に溶けて
叶けい
BL
大阪から東京本社の営業部に異動になって三年目になる佐伯怜二。付き合っていたはずの"カレシ"は音信不通、なのに職場に溢れるのは幸せなカップルの話ばかり。
そんな時、入社時から面倒を見ている新人の三浦匠海に、ふとしたきっかけでご飯を作ってあげるように。発言も行動も何もかも直球な匠海に振り回されるうち、望みなんて無いのに芽生えた恋心。…もう、傷つきたくなんかないのに。


平凡な男子高校生が、素敵な、ある意味必然的な運命をつかむお話。
しゅ
BL
平凡な男子高校生が、非凡な男子高校生にベタベタで甘々に可愛がられて、ただただ幸せになる話です。
基本主人公目線で進行しますが、1部友人達の目線になることがあります。
一部ファンタジー。基本ありきたりな話です。
それでも宜しければどうぞ。

あなたのいちばんすきなひと
名衛 澄
BL
亜食有誠(あじきゆうせい)は幼なじみの与木実晴(よぎみはる)に好意を寄せている。
ある日、有誠が冗談のつもりで実晴に付き合おうかと提案したところ、まさかのOKをもらってしまった。
有誠が混乱している間にお付き合いが始まってしまうが、実晴の態度はいつもと変わらない。
俺のことを好きでもないくせに、なぜ付き合う気になったんだ。
実晴の考えていることがわからず、不安に苛まれる有誠。
そんなとき、実晴の元カノから実晴との復縁に協力してほしいと相談を受ける。
また友人に、幼なじみに戻ったとしても、実晴のとなりにいたい。
自分の気持ちを隠して実晴との"恋人ごっこ"の関係を続ける有誠は――
隠れ執着攻め×不器用一生懸命受けの、学園青春ストーリー。

【完結】少年王が望むは…
綾雅(りょうが)今年は7冊!
BL
シュミレ国―――北の山脈に背を守られ、南の海が恵みを運ぶ国。
15歳の少年王エリヤは即位したばかりだった。両親を暗殺された彼を支えるは、執政ウィリアム一人。他の誰も信頼しない少年王は、彼に心を寄せていく。
恋ほど薄情ではなく、愛と呼ぶには尊敬や崇拝の感情が強すぎる―――小さな我侭すら戸惑うエリヤを、ウィリアムは幸せに出来るのか?
【注意事項】BL、R15、キスシーンあり、性的描写なし
【重複投稿】エブリスタ、アルファポリス、小説家になろう、カクヨム
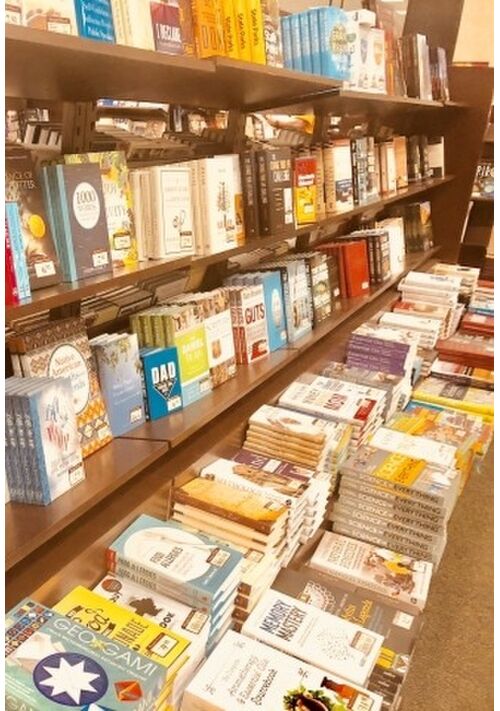
【完結】言えない言葉
未希かずは(Miki)
BL
双子の弟・水瀬碧依は、明るい兄・翼と比べられ、自信がない引っ込み思案な大学生。
同じゼミの気さくで眩しい如月大和に密かに恋するが、話しかける勇気はない。
ある日、碧依は兄になりすまし、本屋のバイトで大和に近づく大胆な計画を立てる。
兄の笑顔で大和と心を通わせる碧依だが、嘘の自分に葛藤し……。
すれ違いを経て本当の想いを伝える、切なく甘い青春BLストーリー。
第1回青春BLカップ参加作品です。
1章 「出会い」が長くなってしまったので、前後編に分けました。
2章、3章も長くなってしまって、分けました。碧依の恋心を丁寧に書き直しました。(2025/9/2 18:40)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















