2 / 6
2
しおりを挟む
リュゼリア王宮の朝は、王都とは比べものにならないほど静かで、どこか優雅だった。
鳥のさえずり、柔らかな風、そして窓から差し込む陽光。
そんな中、私はまだ慣れない王妃候補としての生活を始めていた。
「リリアーナ様、今日の王妃教育の予定は、午前に外交儀礼、午後は舞踏指導、夜には陛下との晩餐会がございます」
侍女長のマリアが淡々と予定を告げる。
……ふぅ。思っていたよりもずっと大変。
でも、これしきで音を上げるつもりはなかった。
なにせ、今の私は――“王に選ばれた女”なのだから。
「外交儀礼、か。君ならすぐに覚えるだろう」
講義の合間、レオネル陛下がふらりと部屋を訪れた。
昼間だというのに、黒衣の軍装姿で、相変わらず威厳に満ちている。
けれど、その金の瞳は私を見た途端、ふっと柔らかくなるのだから、反則だ。
「陛下……授業の途中ですのに」
「君が真剣な顔をしていると、つい見に来たくなるんだ」
その一言で、心臓が跳ねる。
周囲の侍女たちが顔を赤らめてそっと退出していくのが分かる。
「……困りますわ、そんなことを仰っては」
「困らせるのが趣味なんだ」
彼がからかうように微笑む。
そういう時の陛下は、王というよりも、ただ一人の“男性”だ。
「ところで、昨日言っていた話……覚えているか?」
昨日――そう、あの夜。
「私が君を選んだ本当の理由を話す」と言っていた。
私はゆっくりと頷く。
「……はい。お聞きしたいです」
レオネル陛下の瞳が、ほんの少しだけ陰った。
「では、場所を変えよう」
案内されたのは、王宮の最奥にある“銀の間”と呼ばれる場所だった。
磨き抜かれた白銀の壁面、静謐な空気、そして――中央に飾られた、一枚の古い絵画。
そこには、私に瓜二つの女性が描かれていた。
「……この方は?」
「五百年前、リュゼリアを救った聖女エルシア・リュゼリア。初代王の妃でもあった女性だ」
聖女――?
でも、どうしてその絵を私に見せるのだろう。
「驚かないでくれ。君は……彼女の血を引いている」
「……え?」
思わず声を失った。
だが、レオネル陛下は静かに続ける。
「かつて、聖女の血筋は王家によって保護されていた。だが、数百年の時を経て、記録は途絶えた。……しかし、君の魔力反応を見た時、確信したんだ。君の中に“聖女の力”が眠っていると」
聖女の力……?
私が、そんな……?
「信じられないかもしれないが、君があの王都で“選ばれなかった”理由は、それでも説明がつく。君の中の力を見抜けず、ただ表面だけを見た愚か者たちが、君を手放した」
陛下の声が、低く熱を帯びていく。
「だから私は、君を選んだ。運命の再来として、そして――一人の女性として」
その言葉に、胸が高鳴る。
私の中に、そんな力があるなんて信じられない。
けれど、レオネル陛下の真剣な瞳を見ると、疑うことなどできなかった。
「……陛下。もし本当にそのような力があるのなら、私は、それを貴国のために使いたいと思います」
「リリアーナ……君は、いつもそうやって自分より他人を優先するのだな」
彼の手が、そっと私の頬に触れた。
その優しさが、痛いほどに温かい。
だが、王妃候補の道は、決して平坦ではなかった。
「王妃候補? あんな異国の令嬢が?」
「聖女の血筋だと? 冗談も大概にしろ」
貴族たちの中には、私の存在を快く思わぬ者も多かった。
特に、王の従兄である宰相ジルベルト侯爵は、露骨に私を敵視していた。
「リリアーナ殿。王妃になるおつもりなら、まず“出自”を明確にされてはいかがかな?」
「私の家系はエルヴェン公爵家に連なります。記録はすべて揃っておりますわ」
「ふん、だが公爵家とはいえ、今は没落寸前だと聞く。血よりも力の時代ですよ」
その言葉に、周囲の貴族たちが笑い声を上げた。
けれど、私は一歩も引かなかった。
「ええ、確かに力は大切ですわ。ですが――本当に強い者は、他人を見下すことで己を誇るような真似はなさらないでしょう」
一瞬で場が静まり返った。
ジルベルト侯爵の顔が、見る見る赤く染まる。
――痛快だった。
その後、陛下が現れ、まるで庇うように私の隣に立った。
「私の妃に対して無礼は許さぬ。彼女の言葉こそが真理だ」
ざまあみろ、という言葉を飲み込むのに苦労したほどだ。
日が経つにつれ、レオネル陛下との距離は少しずつ縮まっていった。
公務の合間に交わす何気ない会話、夜の庭園での散歩――そのどれもが、私の心を確実に侵食していった。
「リリアーナ。君は、王妃になったら何がしたい?」
「そうですね……誰もが、出自や血筋ではなく、“努力”で評価される国を作りたいです」
「……君らしいな」
陛下がふっと笑い、私の手を取る。
「私も、その理想を共に実現したいと思う。だから――どうか、私の傍にいてくれ」
「……はい」
気づけば、夜風が頬を撫でていた。
近づいた距離、触れた指先。
何も言えなくなるほど、心が熱くなる。
――だが、その静寂を破る報せが届いたのは、翌日のことだった。
「報告です! 隣国アルシオンより使者が……!」
その名を聞いた瞬間、全身が凍りついた。
アルシオン――私がかつて婚約していた王子、ルーク殿下の国だ。
まさか……。
「陛下、どうなさいますか?」
「通せ」
重い扉が開き、入ってきたのは見覚えのある従者たち。
その中心に立つのは、紛れもなく――ルーク殿下本人だった。
「久しいな、リリアーナ」
その声を聞くだけで、心の奥にあの日の屈辱が蘇る。
だが、私はもうあの頃の私ではない。
「これはこれは。ルーク殿下。まさか、わざわざご挨拶に来てくださるとは」
「……私は、君に謝罪するために来た」
その場がざわめいた。
けれど私は、冷ややかに微笑んだ。
「謝罪、ですか? 今さら?」
「私は……間違っていた。君を失ってから気づいたんだ。君の知恵も、優しさも、すべてが必要だったと」
滑稽だった。
彼は今さら後悔の言葉を並べ、私に許しを乞う。
けれど、その背後には焦りと打算が見えていた。
――おそらく、私が“隣国の王妃候補”となったことを知っての行動だろう。
しかし、私が何か言うより先に、レオネル陛下がゆっくりと立ち上がった。
「王太子ルーク殿下。貴殿の言葉は理解した。だが、我が妃に不快な思いをさせたことは、決して軽くはない」
その声には冷たい威厳が宿っていた。
ルーク殿下は顔を引きつらせ、必死に頭を下げる。
「も、もちろん、そのつもりは……!」
「二度と彼女に近づかぬこと。それが謝罪の証だ」
ルーク殿下の顔が青ざめる。
私はただ、静かに一礼した。
「陛下、ありがとうございます」
「当然のことだ。君を侮辱する者は、誰であろうと許さない」
レオネル陛下が私を見るその瞳に、ただひとつの強い感情が宿っていた。
――独占。
それは冷徹さよりも、むしろ甘やかな支配のように感じられた。
その夜。
王宮のバルコニーで、私はひとり風に当たっていた。
ルーク殿下の言葉が頭をよぎる。
そして、陛下の瞳も――。
「……私、どうしてこんなに……」
胸の鼓動が早い。
ただ陛下のそばにいるだけで、呼吸が乱れる。
そんな私の背に、ふいに温もりが触れた。
「こんな時間まで起きているとは、君らしくないな」
「レオネル……陛下……」
「ルークのことを考えていたか?」
「……少しだけ。でも、もう何も感じません」
私の言葉に、陛下は満足げに微笑む。
そして、そっと囁いた。
「ならいい。君の心は、すべて私のものだ」
唇が触れる寸前――風がふわりと吹き抜けた。
夜空には、満天の星。
けれど、私の胸に灯る光は、それよりも強く輝いていた。
――そして翌朝。
王妃候補の私に、ある知らせが届いた。
「リリアーナ様。王都アルシオンから新たな書簡が届きました」
開封すると、そこには見慣れた筆跡。
だが、書かれていたのは――
『リリアーナ・エルヴェン。お前は我が国の“禁忌の血”に関わる存在だ。
聖女の血筋を隠していた罪により、拘束を求める。』
……まさか。
今度は、王妃になる前に“罪人”にされようとしている?
私の指先が震えた。
レオネル陛下の瞳が鋭く光る。
「……どうやら、向こうは本気で仕掛けてきたようだな」
そして、静かに言った。
「リリアーナ。――戦う覚悟はあるか?」
私は息を呑み、ゆっくりと頷いた。
「はい。もう、逃げません。あの国にも、過去にも」
陛下の手が、強く私の手を握る。
その瞬間、運命の歯車が静かに回り始めた。
鳥のさえずり、柔らかな風、そして窓から差し込む陽光。
そんな中、私はまだ慣れない王妃候補としての生活を始めていた。
「リリアーナ様、今日の王妃教育の予定は、午前に外交儀礼、午後は舞踏指導、夜には陛下との晩餐会がございます」
侍女長のマリアが淡々と予定を告げる。
……ふぅ。思っていたよりもずっと大変。
でも、これしきで音を上げるつもりはなかった。
なにせ、今の私は――“王に選ばれた女”なのだから。
「外交儀礼、か。君ならすぐに覚えるだろう」
講義の合間、レオネル陛下がふらりと部屋を訪れた。
昼間だというのに、黒衣の軍装姿で、相変わらず威厳に満ちている。
けれど、その金の瞳は私を見た途端、ふっと柔らかくなるのだから、反則だ。
「陛下……授業の途中ですのに」
「君が真剣な顔をしていると、つい見に来たくなるんだ」
その一言で、心臓が跳ねる。
周囲の侍女たちが顔を赤らめてそっと退出していくのが分かる。
「……困りますわ、そんなことを仰っては」
「困らせるのが趣味なんだ」
彼がからかうように微笑む。
そういう時の陛下は、王というよりも、ただ一人の“男性”だ。
「ところで、昨日言っていた話……覚えているか?」
昨日――そう、あの夜。
「私が君を選んだ本当の理由を話す」と言っていた。
私はゆっくりと頷く。
「……はい。お聞きしたいです」
レオネル陛下の瞳が、ほんの少しだけ陰った。
「では、場所を変えよう」
案内されたのは、王宮の最奥にある“銀の間”と呼ばれる場所だった。
磨き抜かれた白銀の壁面、静謐な空気、そして――中央に飾られた、一枚の古い絵画。
そこには、私に瓜二つの女性が描かれていた。
「……この方は?」
「五百年前、リュゼリアを救った聖女エルシア・リュゼリア。初代王の妃でもあった女性だ」
聖女――?
でも、どうしてその絵を私に見せるのだろう。
「驚かないでくれ。君は……彼女の血を引いている」
「……え?」
思わず声を失った。
だが、レオネル陛下は静かに続ける。
「かつて、聖女の血筋は王家によって保護されていた。だが、数百年の時を経て、記録は途絶えた。……しかし、君の魔力反応を見た時、確信したんだ。君の中に“聖女の力”が眠っていると」
聖女の力……?
私が、そんな……?
「信じられないかもしれないが、君があの王都で“選ばれなかった”理由は、それでも説明がつく。君の中の力を見抜けず、ただ表面だけを見た愚か者たちが、君を手放した」
陛下の声が、低く熱を帯びていく。
「だから私は、君を選んだ。運命の再来として、そして――一人の女性として」
その言葉に、胸が高鳴る。
私の中に、そんな力があるなんて信じられない。
けれど、レオネル陛下の真剣な瞳を見ると、疑うことなどできなかった。
「……陛下。もし本当にそのような力があるのなら、私は、それを貴国のために使いたいと思います」
「リリアーナ……君は、いつもそうやって自分より他人を優先するのだな」
彼の手が、そっと私の頬に触れた。
その優しさが、痛いほどに温かい。
だが、王妃候補の道は、決して平坦ではなかった。
「王妃候補? あんな異国の令嬢が?」
「聖女の血筋だと? 冗談も大概にしろ」
貴族たちの中には、私の存在を快く思わぬ者も多かった。
特に、王の従兄である宰相ジルベルト侯爵は、露骨に私を敵視していた。
「リリアーナ殿。王妃になるおつもりなら、まず“出自”を明確にされてはいかがかな?」
「私の家系はエルヴェン公爵家に連なります。記録はすべて揃っておりますわ」
「ふん、だが公爵家とはいえ、今は没落寸前だと聞く。血よりも力の時代ですよ」
その言葉に、周囲の貴族たちが笑い声を上げた。
けれど、私は一歩も引かなかった。
「ええ、確かに力は大切ですわ。ですが――本当に強い者は、他人を見下すことで己を誇るような真似はなさらないでしょう」
一瞬で場が静まり返った。
ジルベルト侯爵の顔が、見る見る赤く染まる。
――痛快だった。
その後、陛下が現れ、まるで庇うように私の隣に立った。
「私の妃に対して無礼は許さぬ。彼女の言葉こそが真理だ」
ざまあみろ、という言葉を飲み込むのに苦労したほどだ。
日が経つにつれ、レオネル陛下との距離は少しずつ縮まっていった。
公務の合間に交わす何気ない会話、夜の庭園での散歩――そのどれもが、私の心を確実に侵食していった。
「リリアーナ。君は、王妃になったら何がしたい?」
「そうですね……誰もが、出自や血筋ではなく、“努力”で評価される国を作りたいです」
「……君らしいな」
陛下がふっと笑い、私の手を取る。
「私も、その理想を共に実現したいと思う。だから――どうか、私の傍にいてくれ」
「……はい」
気づけば、夜風が頬を撫でていた。
近づいた距離、触れた指先。
何も言えなくなるほど、心が熱くなる。
――だが、その静寂を破る報せが届いたのは、翌日のことだった。
「報告です! 隣国アルシオンより使者が……!」
その名を聞いた瞬間、全身が凍りついた。
アルシオン――私がかつて婚約していた王子、ルーク殿下の国だ。
まさか……。
「陛下、どうなさいますか?」
「通せ」
重い扉が開き、入ってきたのは見覚えのある従者たち。
その中心に立つのは、紛れもなく――ルーク殿下本人だった。
「久しいな、リリアーナ」
その声を聞くだけで、心の奥にあの日の屈辱が蘇る。
だが、私はもうあの頃の私ではない。
「これはこれは。ルーク殿下。まさか、わざわざご挨拶に来てくださるとは」
「……私は、君に謝罪するために来た」
その場がざわめいた。
けれど私は、冷ややかに微笑んだ。
「謝罪、ですか? 今さら?」
「私は……間違っていた。君を失ってから気づいたんだ。君の知恵も、優しさも、すべてが必要だったと」
滑稽だった。
彼は今さら後悔の言葉を並べ、私に許しを乞う。
けれど、その背後には焦りと打算が見えていた。
――おそらく、私が“隣国の王妃候補”となったことを知っての行動だろう。
しかし、私が何か言うより先に、レオネル陛下がゆっくりと立ち上がった。
「王太子ルーク殿下。貴殿の言葉は理解した。だが、我が妃に不快な思いをさせたことは、決して軽くはない」
その声には冷たい威厳が宿っていた。
ルーク殿下は顔を引きつらせ、必死に頭を下げる。
「も、もちろん、そのつもりは……!」
「二度と彼女に近づかぬこと。それが謝罪の証だ」
ルーク殿下の顔が青ざめる。
私はただ、静かに一礼した。
「陛下、ありがとうございます」
「当然のことだ。君を侮辱する者は、誰であろうと許さない」
レオネル陛下が私を見るその瞳に、ただひとつの強い感情が宿っていた。
――独占。
それは冷徹さよりも、むしろ甘やかな支配のように感じられた。
その夜。
王宮のバルコニーで、私はひとり風に当たっていた。
ルーク殿下の言葉が頭をよぎる。
そして、陛下の瞳も――。
「……私、どうしてこんなに……」
胸の鼓動が早い。
ただ陛下のそばにいるだけで、呼吸が乱れる。
そんな私の背に、ふいに温もりが触れた。
「こんな時間まで起きているとは、君らしくないな」
「レオネル……陛下……」
「ルークのことを考えていたか?」
「……少しだけ。でも、もう何も感じません」
私の言葉に、陛下は満足げに微笑む。
そして、そっと囁いた。
「ならいい。君の心は、すべて私のものだ」
唇が触れる寸前――風がふわりと吹き抜けた。
夜空には、満天の星。
けれど、私の胸に灯る光は、それよりも強く輝いていた。
――そして翌朝。
王妃候補の私に、ある知らせが届いた。
「リリアーナ様。王都アルシオンから新たな書簡が届きました」
開封すると、そこには見慣れた筆跡。
だが、書かれていたのは――
『リリアーナ・エルヴェン。お前は我が国の“禁忌の血”に関わる存在だ。
聖女の血筋を隠していた罪により、拘束を求める。』
……まさか。
今度は、王妃になる前に“罪人”にされようとしている?
私の指先が震えた。
レオネル陛下の瞳が鋭く光る。
「……どうやら、向こうは本気で仕掛けてきたようだな」
そして、静かに言った。
「リリアーナ。――戦う覚悟はあるか?」
私は息を呑み、ゆっくりと頷いた。
「はい。もう、逃げません。あの国にも、過去にも」
陛下の手が、強く私の手を握る。
その瞬間、運命の歯車が静かに回り始めた。
21
あなたにおすすめの小説

「偽物の聖女は要らない」と追放された私、隣国で本物の奇跡を起こしたら元の国が滅びかけていた件
歩人
ファンタジー
聖女リーゼロッテは、王太子カールに「お前の加護は偽物だ」と断じられ、
婚約を破棄された。代わりに聖女の座に就いたのは、愛らしく微笑む男爵令嬢エルゼ。
追放されたリーゼロッテが隣国に辿り着いたとき、その地は疫病に苦しんでいた。
彼女が祈ると、枯れた泉が蘇り、病は癒え、荒野に花が咲いた。
——本物の聖女の力が、ようやく枷を外されて目覚めたのだ。
一方、リーゼロッテを失った王国では結界が綻び始め、魔物が溢れ出す。
カールは今さら「戻ってくれ」と使者を送るが、リーゼロッテの隣には、
彼女の力を最初から信じていた隣国の若き王がいた。
「あの国に戻る理由が、もう一つもないのです」

平民出身の地味令嬢ですが、論文が王子の目に留まりました
有賀冬馬
恋愛
貴族に拾われ、必死に努力して婚約者の隣に立とうとしたのに――「やっぱり貴族の娘がいい」と言われて、あっさり捨てられました。
でもその直後、学者として発表した論文が王子の目に止まり、まさかの求婚!?
「君の知性と誠実さに惹かれた。どうか、私の隣に来てほしい」
今では愛され、甘やかされ、未来の王妃。
……そして元婚約者は、落ちぶれて、泣きながらわたしに縋ってくる。
「あなたには、わたしの価値が見えなかっただけです」

悪役令嬢に相応しいエンディング
無色
恋愛
月の光のように美しく気高い、公爵令嬢ルナティア=ミューラー。
ある日彼女は卒業パーティーで、王子アイベックに国外追放を告げられる。
さらには平民上がりの令嬢ナージャと婚約を宣言した。
ナージャはルナティアの悪い評判をアイベックに吹聴し、彼女を貶めたのだ。
だが彼らは愚かにも知らなかった。
ルナティアには、ミューラー家には、貴族の令嬢たちしか知らない裏の顔があるということを。
そして、待ち受けるエンディングを。

花を咲かせるだけと馬鹿にされていたけれど、実は希少な魔法でした
佐倉葵
恋愛
花を咲かせる魔法しか使えないリシェル。
その魔法に価値が見出されることはなく、婚約者からも「無能」と見捨てられていた。
王宮の舞踏会で出会ったのは、銀の瞳を持つ異国の魔導士フェルディア。
彼は、リシェルの中に眠る“花を咲かせる”だけではない、もっと深く、もっと稀有な力を見抜いていた。
元婚約者からの侮蔑の中で、フェルディアの言葉と魔力に導かれ、リシェルは自分の魔法の本質に触れはじめる。
かつて無価値とされた魔法が、たった一つの出会いをきっかけに、その意味を変えていく——

遺産は一円も渡さない 〜強欲な夫と義実家に捨てられた私、真の相続人と手を組み全てを奪い返す~ (全10話)
スカッと文庫
恋愛
「お前の価値なんて、その遺産くらいしかないんだよ」
唯一の肉親だった祖父を亡くした夜、夫の健一と義母から放たれたのは、あまりにも無慈悲な言葉だった。
四十九日も待たず、祖父が遺した1億2000万円の遺産をアテに贅沢三昧を目論む夫。だが、彼には隠し通している「裏切り」があった――。
絶望の淵に立たされた由美の前に現れたのは、亡き祖父が差し向けた若き凄腕弁護士・蓮。
「おじい様は、すべてお見通しでしたよ」
明かされる衝撃の遺言内容。そして、強欲な夫たちを地獄へ叩き落とすための「相続条件」とは?
虐げられてきた妻による、一発逆転の遺産争奪&復讐劇がいま幕を開ける!

かわりに王妃になってくれる優しい妹を育てた戦略家の姉
菜っぱ
恋愛
貴族学校卒業の日に第一王子から婚約破棄を言い渡されたエンブレンは、何も言わずに会場を去った。
気品高い貴族の娘であるエンブレンが、なんの文句も言わずに去っていく姿はあまりにも清々しく、その姿に違和感を覚える第一王子だが、早く愛する人と婚姻を結ぼうと急いで王が婚姻時に使う契約の間へ向かう。
姉から婚約者の座を奪った妹のアンジュッテは、嫌な予感を覚えるが……。
全てが計画通り。賢い姉による、生贄仕立て上げ逃亡劇。
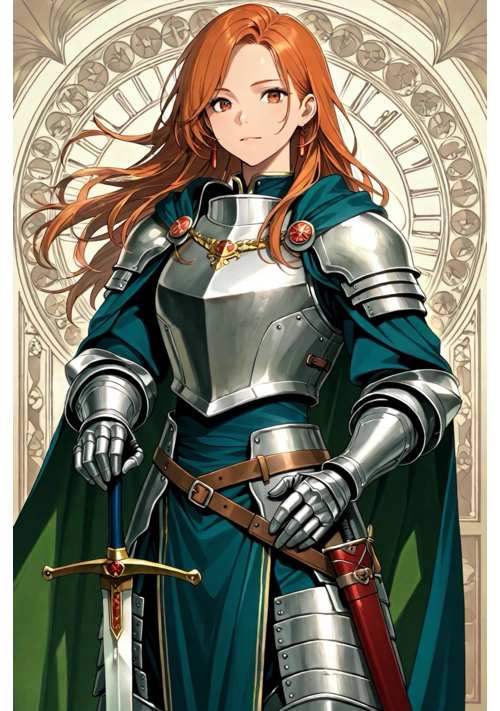
婚約破棄された最強女騎士、年下王子に拾われて亡命したら元婚約者の国が滅びました
lemuria
恋愛
武功ひとつで爵位を得た女将軍マリーは、王国最強の矛として名を轟かせていた。
しかしある日、第一王子アルベルトから公衆の面前で一方的に婚約を破棄される。
屈辱と静まり返る大広間――その沈黙を破ったのは、まだ十三歳の第三王子ノエルだった。
「――だったら、僕がマリーさんと婚約します!」
幼い王子の突飛な言葉から始まった新たな縁。
不器用ながらも必死にマリーを支えようとするノエルと、そんな彼を子供扱いしながらも少しずつ心を揺らされていくマリー。
だが王国の中枢では、王の急逝を機に暴政が始まり、権力争いが渦を巻き始める。
二人を待つのは、謀略の渦に呑まれる日々か、それとも新たな未来か。
女将軍と少年王子――釣り合わぬ二人の“婚約”は、やがて王国の命運をも左右していく。

事務仕事しかできない無能?いいえ、空間支配スキルです。~勇者パーティの事務員として整理整頓していたら、いつの間にか銅像が立っていました~
水月
恋愛
「在庫整理しかできない無能は不要だ」
第一王子から、晩餐会の場で婚約破棄と国外追放を告げられた公爵令嬢ユズハ。
彼女のギフト【在庫整理】は、荷物の整理しかできないハズレスキルだと蔑まれていた。
だが、彼女は知っていた。
その真価は、指定空間内のあらゆる物質の最適化であることを。
追放先で出会った要領の悪い勇者パーティに対し、ユズハは事務的に、かつ冷徹に最適化を開始する。
「勇者様、右腕の筋肉配置を効率化しました」
「魔王の心臓、少し左にずらしておきましたね」
戦場を、兵站を、さらには魔王の命までをも在庫として処理し続けた結果、彼女はいつしか魔王討伐勇者パーティの一人として、威圧感溢れる銅像にまでなってしまう。
効率を愛する事務屋令嬢は、自分を捨てた国を不良債権として切り捨て、再出発する。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















