4 / 11
一章
3
しおりを挟むあの後、佐藤は夜の九時過ぎには帰って行った。
「ちゃんとベッドで寝ろよ」と、私に釘を刺して。
寝て起きて朝になったら、とてもすっきりしていて、お肌もぷにぷにしたままで。
なんだかいつもと違って、すがすがしい朝のような気がした。
『みんなー! 動物園行っこー!!!』
なんていうメッセージがグループのトークに受信されると、私は時計に目を向ける。
時刻は八時を少し過ぎたところで。
決定事項のように鞠からのメッセージが届いたということは、先に佐藤の予定は確保済みということなんだろう。
動物園か……。
めんどくさい半分、けれど行かないなんて選択肢はない。
なんだかんだで私も、四人での時間を大切にしているから。
元気いっぱいですぐハメを外す鞠がいて、それを一緒になって騒いでいる様に見えて実はそばで無茶しないようにフォローしている佐藤がいて、その二人を見守りながらグループのリーダー格でいる緑がいて。
怠惰だけど、四人でいる時間がなんだかんだ好きで、緑とため息をつきながらも世話を焼きたがる自分がいて。
そんな時間が、当たり前のように毎日流れていることが、幸せだから。
それに……今日は肌が、いつもと違ってぷにぷにしている、から。
保湿ってすごいな……。
頬を触りながら思い出すのは、昨夜の佐藤の見慣れない男の顔だった。
十一時に駅集合となり、私はうっすらと化粧を施してから、迎えに来た佐藤と一緒に駅へと向かう。
鞠と緑とも合流してから電車で動物園へと向かった。
「なんで急に動物園?」
恐らくメンバー全員が思っているであろう疑問を、代表するかのように緑が鞠に尋ねる。
「もふもふと触れ合いたかったから……?」
「猫カフェでもよくない?」
「だって昨日サバンナ特集やってんの見てたらなんだかマリも見たくなってきちゃって!!」
「でた、マリもマリも」
鞠はよく、何か見たり聞いたりしたことに刺激を受けて、自分も自分もと求める。
私たちを巻き込みながら。
だから緑は鞠のことを『マリモ』なんて呼んでいる。
佐藤が呼ぶ『マリリン』はよくわからないけど、たぶん佐藤のことだからノリと勢いだろう。
鞠だって佐藤のこと『さとちん』なんて呼んで、仲のよろしいことで……別に気にしてないけど。
「あれ、ねぇ和香」
ふいに何かに気付いたように緑に呼ばれると、するりと細い指が頬を撫でる。
「アンタ今日肌つやよくない?」
「緑、急にイケメンみたいなことしないで。ときめく」
「あらごめん。お手入れしたの?」
「……まぁ、うん」
したというか、されたのだけど。
昨日の話を……他の人にしていいのか、少し悩んでしまった。
本人はすぐそこに居るんだけど、でも、なんだかあの空間での話は、しにくくて。
「ふぅん」
なぜか、緑は楽しそうな笑みを私に向けるから、なんだか心の中を覗かれているような気持になって、俯いてしまった。
「ちょっとみどりん、和香のこと口説かないでよねー」
佐藤の、昨日より高い声が、鼓膜を震わせる。
変なタイミングで思い出してしまったじゃないか、ばか。
「ただ話してるだけじゃない、ねぇ和香? それより佐藤、昨日のことだけど――」
そうやってたくさん話しているうちにいつの間にかチケット売り場に辿り着いていて、四人で入園して、まず現れる遊園地にみんなで目を奪われて。
「ねぇねぇ後で観覧車乗ろう!!!」
そう元気に訴える鞠は、想定内。
「観覧車って四人で乗れるよね?」
「マリモ、乗るなら遊園地ゾーンでどれ乗りたいか先に決めて。先動物園回っちゃうと後で時間無くなるから」
「えー!! うーん、ちょっと地図見よう!!」
ベンチに座って園内マップを開き、緑に相談しながら回る場所を決めている鞠。
一方、私と佐藤は飲み物を買いに自販機へと向かった。
いつも通りの佐藤のままだから、思いの外気まずい気持ちにはなっていない。
そりゃあ、あんな暴露話をされた後は寝れなくもなっていたけれど、よく考えたら今まで佐藤が男だったことで別に不便も何もなかったし、むしろ気付かなかったくらいに馴染んでいたし。
それなら、これからも佐藤が佐藤であることには変わらないのだから、それなら別によくないか?
思いの外、柔軟に受け入れて昨夜は安眠出来ていたことに自分で驚いたくらいだ。
私は佐藤が女趣味でも心が女でも……いや、心は男……か?
でも女子力……いや、佐藤は佐藤という一つのジャンルなのかもしれない。
そういうことにしておこう。
それでも佐藤を避けたり毛嫌いしたりする理由になんかならない。
そう、自分で気付いたんだ。
「ねぇ、和香」
「なに」
「あーしのこと、ちゃあんと男だって意識してないでしょ?」
ふとそんな風に、こんな誰が通りかかるかもわからないところで尋ねられたもんだから、思考も動きも止めて佐藤を見上げる。
「……いや、男なんでしょ、アンタがそう言ったんじゃん」
「そうじゃなくてぇー、なぁんか緑に負けてる気がして」
「負けてるも何も、何を競ってるの?」
そう私が聞き返すと、とても残念な人を見るような佐藤の視線が、私をズキズキと突き刺した。
待って、そんな憐みの瞳を向けられるようなことした覚えは、私の方には一ミリもないんだけど。
「なぁんで和香にだけ話したと思う?」
「それは、私がなんでも受け入れそうだからって……酔っ払いの佐藤が言ってたんじゃない」
「……もしかして酔った勢いで暴露されたとか思ってる……?」
むしろそれ以外の何があるのだろうかと、そう私が思ったところで。
「さとちーん! のどー! 何話してんのー!?」
キャッキャとしたテンションでこちらに駆け寄ってくる鞠に、私たちの話は強制終了されることになる。
佐藤が何を伝えたかったのかは、結局わからないままだった。
「あ、お猿さんだよぉぉぉ!!!」
子供のようにはしゃいでいる鞠を見ると、そんなことも忘れてしまいそうになる。
というかもうここからは動物園のゾーンに入るようだ。
鞠と緑から聞いたけれど、閉演の一時間前には観覧車とバイキング、それにジェットコースターにも軽く乗る予定らしい。
私は観覧車だけでいいや、胃から込み上げてきちゃいけないものがこみ上げそうになるあの感じが無理だから、絶叫系には乗らない。
今回もきっと、佐藤と緑が交代しながら鞠に付き合ってくることだろう。
「きりんさぁぁぁぁぁぁぁん」
「テンションうっさいわマリモ!」
ゴツッと緑の拳を頭に受けていた鞠は、今日は一段と良く騒ぐ、どうどう。
「いたぁい……」
「鞠は元気だね」
鞠の頭をよしよしと撫でながら、上目遣いで潤んだ眼を向ける鞠に困ったように笑みを向ける。
少しは落ち着きな、転ぶよ。
「マリはいつも元気だけどー。のども楽しいといいなぁって」
「……ん?」
私も、何?
「のど、楽しい?」
「もちろん、この四人でいて楽しくないわけがないよ」
「へへっ」
どうやら元気を取り戻したらしい鞠は、佐藤に突撃しに行った。
あ……うん、まぁ、今までと変わらない光景、だけれど……。
「マリモ心配してたからねぇ。頭から八宝菜に突っ込みそうになったり、医務室に運ばれる和香見てて」
「う……ちょっと寝不足だっただけなのに」
「睡眠大好きな和香が寝不足だっていう所からして、ちょっと変」
ぎくりとして、奥歯を噛みしめてしまう。
話さない限り、佐藤からあんな暴露話されたことなんて、緑にはわかるはずもないのに。
なんだか緑には見透かされてしまいそうな怖さがある。
「まぁ佐藤が付いててくれてたみたいだから、いいんだけどね。一人でぶっ倒れることがないようにね? 家近いんだから、風邪でもなんでも、困ったらとりあえず佐藤に頼りな」
「……うん、気を付ける」
その佐藤が睡眠不足の原因だったんだけど……奴が男だと最初に聞いた時の動揺もなくなってきたから、これからはきっと頭を悩ませることもなくなるだろうと思う。
佐藤と鞠はシマウマを見ながら看板の説明を読んでいて。
本当に仲がいいなと、よくわからない不安が、胸にモヤをかけていた。
『ペンギンだー!!』『ライオンだー!!』『白鳥さんだー!!!』なんて騒いでいた鞠も、さすがに夕方近くになると勢いが収まって来ていた。
お土産屋さんに入り、たくさんの動物たちのグッズを見ていると、ふと隣に気配が寄ってくるのを感じる。
「和香はなんか、買いたいものあるのぉ?」
いつものように綺麗にギャルメイクされている佐藤の横顔が、私の顔のすぐ横に並ぶ。
「あー、万華鏡キレー」
その筒を拾い、くるくると回して中を覗き込む佐藤は、いつもと変わらない佐藤で。
私は何をそんなに朝から気にしているのか、自分でもよくわからなかった。
動揺は、もうなくなって来ていたけれど、心がモヤモヤとする時がある。
その理由は、まだよくわからない。
「ねーぇ、和香。アクセとかもあるよー?」
「佐藤はよく付けてるよね」
「和香は付けないの?」
ふと笑みを消す佐藤の顔がこちらに向いていて、一瞬息が止まる。
いや、そんな緊張するほどのことは、起きていないはずなんだけど。
「……付け忘れる、から」
「じゃあ付けたり外したりあんまりしないものがいーかな?」
「……?私別に買わないけど」
ふと手が伸びて来て、髪をかける指先が耳に触れ、肩がビクりと上がる。
急に、なに。
「和香はピアスも開けてないしねぇ。となると」
佐藤に顔を向けにくくて外していた視線の先、左手を持ち上げられると、私の冷たい手が佐藤の熱に触れる。
「指輪、とかなら外さなくていーかも」
するりと触れる指先が、私の指先全体を覆う。
「つけ、ない」
「えー、和香なら絶対似合うのにー」
「指輪に似合うも何も……」
「あるよぉ。和香の指は細くて長くて綺麗で……顔だって美人さんなんだから」
そうやって頬に触れる指先は、今朝緑に撫でられた場所をなぞるように、同じように触れる。
緑とは違う、頭が熱くなるような感覚に、戸惑う。
ふっとからかうように笑う佐藤が、繋がれていた指先をまたきゅっと握る。
「細くて綺麗な指輪が似合うと思うなぁ」
「そう、なの。ねぇもう手、いいでしょ。離して」
「和香の手ぇ冷たいから、今ならあーしがあっためてあげるけどぉ?」
「いい。私あっち見て来る」
「つれなぁい」
ぬいぐるみのコーナーでペンギンのぬいぐるみを手に取って、小さく溜め息を吐く。
何だったんだ、確かに佐藤ならピアスも指輪も似合うだろうけど……指輪、は、佐藤はしてなかったな。
ネックレスを付けて、ピアスを付けて、化粧をしてウィッグを付けて、時にはアンクレットやマニキュア、ペディキュアまで、爪の先まで綺麗に着飾って。
それでも佐藤が指輪を付けている所は見たことがなかったかもしれない。
ピンキーリングとかも、似合いそう、だけど……。
好みの問題とかも、あるのだろうか。
ふと視界に入った、トラのぬいぐるみ。
なんだか佐藤みたいだなぁ、なんて見ていたら、なんだか愛着が湧いて来て。
緑は、孔雀かな、鞠は……小動物だな、ペンギンとか似合いそう。
私は……なんだろう。
ふとまた隣に気配がして見上げると、そこには緑がいた。
「何探してんの?」
トラと孔雀のぬいぐるみを手にしている私に、緑が笑いかける。
「佐藤がトラで、緑が孔雀で、鞠があのペンギンで」
「ふふっ、和香寂しがり屋なの? みんな買う気?」
「いや、なんか……気付いたらイメージしてて」
そう言うと緑は、「うーん」と悩みながら何かを探す。
「そうだなぁ。和香は色白で綺麗だから白鳥とか……可愛いというよりは綺麗系だよね」
「またそうやってイケメンみたいなことサラッと言うんだから」
「和香はそういう言葉に靡いたりなんかしないからいいじゃない」
靡かない……とは、私も思ってるけれど。
なんだか、佐藤といる時は、私のペースが乱されているような気がするんだ。
「……私、心があるかもしれない」
淡々として起伏の少ない感情、めんどくさがり、省エネ、怠惰。
そんな私に起こり始めている小さな変化は、私にも小さすぎて、微かで、ちょっとした違和感でしかないけれど。
「そりゃあ、和香はAIとかじゃないんだから。四人の中の誰よりも、この四人でいることを大事にしてくれてる子だと、私は思ってるけど。違う?」
そんな答えを堂々とくれる緑を見上げれば、ふっと笑った彼女がいて。
「やっぱり、緑はイケメン枠」
「褒められてるってことにしておくわ」
そんな緑の言葉が、何度も何度も反芻してしまうくらい、嬉しくて、本当は泣いてしまいそうになった。
私はただ対応が柔軟なわけじゃない。
関係が壊れてしまうことを、酷く恐れているだけだ。
冷静だからじゃない、優しいからでもない。
淡々と、淡々と。
自分が傷付くことが怖いから感情を大きく揺らさないし、状況に適応しようとすぐ受け入れられるだけなんだ。
私は、誰よりも臆病だから。
遊園地ゾーンへと向かう頃には、夕焼け空が広がっていた。
最後に観覧車に乗りたいというこだわりを見せた鞠は、先に絶叫マシンへと向かうことになったけれど、ここで一つ予定外の問題が発生する。
「あーし、さっき食べたチュロスが出ちゃいそーだから、パース。はいタッチ、みどりん任せた!」
「はぁあ!!?」
いつもは真っ先に鞠と一緒にジェットコースターへと乗りに行く佐藤が、今日はパスだという。
「えええさとちん今日乗らないの!!?」
「だってアレぐるんぐるーんて回るじゃぁん? リバースしたら困るじゃあん?」
「そうなると全部私がマリモに付き合うってことでよろしい? 後でなんかおごれよ」
「おけおけー。じゃあマリリンのことヨロ~」
にっこり笑って二人を送り出した佐藤に、私も驚いた視線を向ける。
「……いいの? 絶叫好きなのに」
「また来ればいーっしょ。四人で」
「そう、だけど」
私とお留守番というのも、つまらないだろうに。
プニッと頬をつつかれ無視していると、その手が私の指先に回り、絡む。
一瞬遅れてその繋がれた手に視線を向けると、恋人つなぎのように、指の間を隙間なく埋めるように絡め取られている。
どくん、鼓動がひとつ、大きく音を立てて痛んだ。
いや……だからまって、よく鞠ともやるじゃない、こういうのは。
友達間でもやる、じゃれていたり、買い物行く時にだって、手なんて繋ぐ。
女子同士なんてそんなもんだ、けれど。
いつもと違う感覚に、また戸惑いが生まれる。
いつも通りの佐藤、いつも通りの触れ合い、いつも通りの四人、いつも通りの……。
なのになんで、今日はこんなに、佐藤の動作一つ一つに振り回されているのだろう。
ふと立ち上がる佐藤に手を引かれ、私も立ち上がる。
「観覧車、いこっか」
それはそれはいい笑顔で、佐藤に提案されるけれど。
「……は? え、待って鞠たちは」
「二回回りゃいーのいーの」
いや、だからなぜ後でみんなで乗るというのにわざわざ先に二人で乗り込もうとしているのか――。
相手が佐藤だったからさほど警戒も抵抗もすることもなく、連れ込まれた観覧車の中。
ゆるゆると登っていくゴンドラに揺られながら、私は何も予測できない佐藤の頭の中のことを考えようとしたけれど、やはり何もわからなかった。
女心よりも秋の空よりも難しいかもしれない、佐藤の心。
「さーて、朝のお話の続きといこうじゃないですかぁ」
にっこりと何を企んでいるのかもわからない佐藤の笑みに、「朝……?」と私は記憶を引っ張り出そうとするけれど、何か話していただろうか。
「ほとんど昼だったけどー、自販機の前で。なぁんで和香にだけ『俺のこと』話したと思う?」
「……あぁ、あれか」
思い出したけれど、また佐藤が残念な人を見るかのような瞳を向けて来るので、私は何か変なことを言っただろうか? と再び頭を悩ませる。
「いや、割とそこ重要なんだけど」
「酔っ払いに重要な話されたところでね」
「今はシラフじゃあん! もー和香ってばほんとつれない」
佐藤はそう言ってぶすくれると、向かい合っていた席を立ち、隣に座りにくるから、また何かと私が頭を悩ませることになる。
なぜ来た、ゴンドラが傾くじゃないか。
ジト目で佐藤を見つめていたけれど、真剣な瞳を向けられる。
「和香にとって、どうとも思われてないことなんて、わかりきってる」
そう佐藤が呟くから、私は「どうともなんてことない」と強めに反論する。
けれど、それは佐藤の求めている言葉じゃないようで、また不満顔を向けられる。
「違う、和香の思ってくれている気持ちとこっちの気持ちにズレがあるってこと」
「は……?」
なに、気持ちにズレがあるって。
わからないよ、佐藤、そんなんじゃ私わからない。
でも怖い、変わってしまいそうな何かを打ち明けられているようで。
「和香とは友達として二年も過ごしてきちゃったんだから、そりゃ、仕方ないことかもしれないけど」
「まって、佐藤……友達してきたことに後悔なんて、してないよね?」
「いや、後悔はしてないけど、そのせいで……和香に意識してもらえてないなら、それは」
「まって、やだ佐藤……私それ聞きたくない、かも」
「離れるわけじゃないよ、和香」
何かが変わろうとしている。
何かを変えようとしている。
佐藤が、私たち二人の関係を変えようと……四人の、関係も、変わってしまう……?
「佐藤は佐藤のまま、だよね」
「そうだけど……和香の中の俺の印象を変えたい」
「なに、言って……」
ゆっくりと登るゴンドラの中、夕焼けなんて見る余裕もない私の瞳は、ただ佐藤を見つめる。
嫌だ、離れるわけじゃないとしても、怖い。
二人きりになる時間まで作って、佐藤は何を……。
風に揺られるゴンドラが、大きく揺れたわけではなかったと思う。
ただ、温かい指先が私を囲うように、両手に乗せられて。
近付いた顔がすぐ近くで「ごめん」と、鼓膜を震わせるのを聞いて。
頬が、頬をこすった。
酷く近い顔に、頭を引くけれど、逃げ場なんてなくて。
ドクドク、沸き立つように心臓が、頭が、体が熱くなって、緊張してきて。
「のどか」
心地の良い響く声が、鼓膜を優しく震わせる。
時間が止まったかのように、動けなかった。
「拒否る時間は、たっぷりとあったんだから。文句言うなよ」
ゆるりと手の甲を撫でられ、正面に回って見えるのは、いつもより近い、佐藤の顔。
いつもと違う……獲物を狙うような真剣な瞳に、私はスッと、何かを理解した。
『あぁ、狙われているのは”私”だ』
自分から、瞼を閉じるとは思っていなかった。
瞼の奥のオレンジ色の光が陰り、柔らかな感触が唇を食む。
瞼を閉じる前、ゴンドラの景色は頂点に差し掛かる手前だった。
迷いがありながらも何度も食まれる唇に、どうしたらいいのかもわからなくなって。
気付いたら指先で上を向かされて、舌で唇を撫でられて、緩やかに侵入してくるそれを……受け入れている自分がいて。
思いの外、心地の良い柔らかさに浸っている自分がいて。
どうして受け入れてしまっているのかも、自分のことなのにわからなくて。
観覧車で四分の三が過ぎる頃、ようやく口が離された。
「ばか……なんで受け入れんだよ、止まらなくなったじゃねぇか」
呆然と俯く私を見て、佐藤はため息を吐く。
「……ごめん、和香。ごめん、ほんと最初は自分の気持ちがこんなんなるとは思ってなくて、気付いたら和香のことばっかり、考えるようになってて」
静かな空間の中で、それは告げられる。
「だから和香、はやく俺を好きになって」
「……なに、それ」
わがまま。
そんな告白、聞いたことない。
これが告白なのかすらも……わからないけれど。
けれどそんな言い方が、佐藤の見慣れない男の姿の中で唯一、佐藤らしさを残していて。
ふっと息を吐いて笑っていた。
佐藤は、ちゃんと私の知っているままの佐藤だから。
しばらくは混乱するだろうけれど、それもそのうち慣れていくんじゃないかと思った。
佐藤は、私たち四人の関係をきっと、変えるつもりなんてない。
それなら私も、この四人での関係が変わらないようにしていくだけだ。
ただ少しだけ、佐藤の気持ちを私が知った。
それだけの変化だ。
観覧車から降りて、二人でソフトクリームを買ってベンチに戻ると、ちょうど緑と鞠もベンチに向かってくる所だった。
「え、ずっるい! マリも! マリも買ってくる!!」
「あーはいはい。でもいいのマリモ? 閉園時間迫って来てるし、こっから退場ゲートまで結構距離あるけど」
「閉園時間早すぎない!?」
「もーちょい遅くまで居たかったらちょっと遠くの遊園地の方行かないとね。ていうか今日の目的は動物園だったでしょう?」
「むー……今度はちゃんと遊園地に行こう!!」
鞠がそう言うもんだから、今日のところは急いで観覧車に行くよりソフトクリームを食べながら退場ゲートに向かおうということになった。
四人で乗るのは、また今度に持ち越しになったということだ。
帰りの電車では鞠と私はすぐに寝てしまって、気付いたら到着する駅の前で佐藤に揺らされて起こされていた。
その肩に頭を乗せていたみたいで一瞬びっくりしたけれど、佐藤がからかってくるから恥ずかしさもどこか飛んで行ってしまう。
今日はたくさん歩いたからということで、駅前で解散して佐藤と一緒に帰り道を歩いたけれど、佐藤はゴンドラの中でのことを掘り返しては来なかった。
そして佐藤とは、コンビニ弁当を二人で買って、私の家の前で別れた。
帰ってきた部屋の中で、私はベッドの上に三つの小さなぬいぐるみを並べて、口元を緩ませる。
トラと、ペンギンと、孔雀と、それから白鳥……迷った末に、結局みんな買ってしまった。
自分が白鳥というのは綺麗すぎないか? と考えたものの、あの緑が選んでくれたのだから、せっかくならば買ってしまおう、と思って。
だって、三人だけだと、私がなんだか寂しいから。
その日は四つのぬいぐるみに見守られて、温かい気持ちで眠りに付いた。
0
あなたにおすすめの小説

「がっかりです」——その一言で終わる夫婦が、王宮にはある
柴田はつみ
恋愛
妃の席を踏みにじったのは令嬢——けれど妃の心を折ったのは、夫のたった一言だった
王太子妃リディアの唯一の安らぎは、王太子アーヴィンと交わす午後の茶会。だが新しく王宮に出入りする伯爵令嬢ミレーユは、妃の席に先に座り、殿下を私的に呼び、距離感のない振る舞いを重ねる。
リディアは王宮の礼節としてその場で正す——正しいはずだった。けれど夫は「リディア、そこまで言わなくても……」と、妃を止めた。
「わかりました。あなたには、がっかりです」
微笑んで去ったその日から、夫婦の茶会は終わる。沈黙の王宮で、言葉を失った王太子は、初めて“追う”ことを選ぶが——遅すぎた。

【完結】冷酷伯爵ディートリヒは、去った妻を取り戻せない
くろねこ
恋愛
名門伯爵家に政略結婚で嫁いだ、正妻エレノア・リーヴェルト。夫である伯爵ディートリヒ・フォン・アイゼンヴァルトは、
軍務と義務を最優先し、彼女に関心を向けることはなかった。
言葉も、視線も、愛情も与えられない日々。それでも伯爵夫人として尽くし続けたエレノアは、ある一言をきっかけに、静かに伯爵家を去る決意をする。
――そして初めて、夫は気づく。
自分がどれほど多くのものを、彼女から与えられていたのかを。
一方、エレノアは新たな地でその才覚と人柄を評価され、
「必要とされる存在」として歩き始めていた。
去った妻を想い、今さら後悔する冷酷伯爵。前を向いて生きる正妻令嬢。
これは、失ってから愛に気づいた男と、
二度と戻らないかもしれない夫婦の物語。
――今さら、遅いのです。


あなたが後悔しても、私の愛はもう戻りません
藤原遊
恋愛
婚約者のアルベルトは、優しい人だった。
ただ――いつも、私より優先する存在がいただけで。
「君は分かってくれると思っていた」
その一言で、リーシェは気づいてしまう。
私は、最初から選ばれていなかったのだと。
これは、奪われた恋を取り戻す物語ではない。
後悔する彼と、もう戻らないと決めた私、
そして“私を選ぶ人”に出会うまでの、静かな恋の終わりと始まりの物語。

初夜に暴言を吐いた夫は後悔し続ける──10年後の償い【完結】
星森 永羽(ほしもりとわ)
恋愛
王命により、辺境伯ロキアのもとへ嫁いだのは、金髪翠眼の美しき公爵令嬢スフィア。
だが、初夜に彼が告げたのは、愛も権限も与えないという冷酷な宣言だった。噂に踊らされ、彼女を「穢れた花嫁」と罵ったロキア。
しかし、わずか一日でスフィアは姿を消し、教会から届いたのは婚姻無効と慰謝料請求の書状──。
王と公爵の怒りを買ったロキアは、爵位も領地も名誉も奪われ、ただの補佐官として生きることに。
そして十年後、運命のいたずらか、彼は被災地で再びスフィアと出会う。
地位も捨て、娘を抱えて生きる彼女の姿に、ロキアの胸に去来するのは、悔恨と赦しを乞う想い──。
⚠️本作はAIの生成した文章を一部に使用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
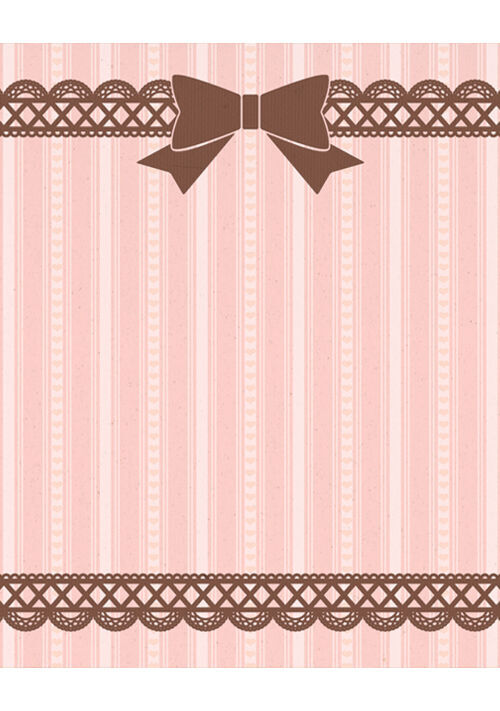
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行「婚約破棄ですか? それなら昨日成立しましたよ、ご存知ありませんでしたか?」完結
まほりろ
恋愛
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行中。
コミカライズ化がスタートしましたらこちらの作品は非公開にします。
「アリシア・フィルタ貴様との婚約を破棄する!」
イエーガー公爵家の令息レイモンド様が言い放った。レイモンド様の腕には男爵家の令嬢ミランダ様がいた。ミランダ様はピンクのふわふわした髪に赤い大きな瞳、小柄な体躯で庇護欲をそそる美少女。
対する私は銀色の髪に紫の瞳、表情が表に出にくく能面姫と呼ばれています。
レイモンド様がミランダ様に惹かれても仕方ありませんね……ですが。
「貴様は俺が心優しく美しいミランダに好意を抱いたことに嫉妬し、ミランダの教科書を破いたり、階段から突き落とすなどの狼藉を……」
「あの、ちょっとよろしいですか?」
「なんだ!」
レイモンド様が眉間にしわを寄せ私を睨む。
「婚約破棄ですか? 婚約破棄なら昨日成立しましたが、ご存知ありませんでしたか?」
私の言葉にレイモンド様とミランダ様は顔を見合わせ絶句した。
全31話、約43,000文字、完結済み。
他サイトにもアップしています。
小説家になろう、日間ランキング異世界恋愛2位!総合2位!
pixivウィークリーランキング2位に入った作品です。
アルファポリス、恋愛2位、総合2位、HOTランキング2位に入った作品です。
2021/10/23アルファポリス完結ランキング4位に入ってました。ありがとうございます。
「Copyright(C)2021-九十九沢まほろ」

Blue Moon 〜小さな夜の奇跡〜
葉月 まい
恋愛
ーー私はあの夜、一生分の恋をしたーー
あなたとの思い出さえあれば、この先も生きていける。
見ると幸せになれるという
珍しい月 ブルームーン。
月の光に照らされた、たったひと晩の
それは奇跡みたいな恋だった。
‧₊˚✧ 登場人物 ✩˚。⋆
藤原 小夜(23歳) …楽器店勤務、夜はバーのピアニスト
来栖 想(26歳) …新進気鋭のシンガーソングライター
想のファンにケガをさせられた小夜は、
責任を感じた想にバーでのピアノ演奏の代役を頼む。
それは数年に一度の、ブルームーンの夜だった。
ひと晩だけの思い出のはずだったが……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















