437 / 814
第二部 宰相閣下の謹慎事情
482 狐火灯る夜(中) ☆
しおりを挟む
右手にティーポットとカップの乗るトレイ。
左手には何かしらの毛皮だろうと思しきブランケット。
いや、ブランケットにしてもちょっと大きいような……それはともかく。
「エ…ドヴァルド様……何で、そんな……」
背筋のピンと伸びた、隙のない佇まいもさることながら、手にしているのがティーセットとブランケット。
一瞬どこのコスプレ執事が来たのかと思ってしまった。
と言うか、天下の宰相閣下が何でそんな用意を!
私が慌てて代わりに持とうと立ち上がったけれど、エドヴァルドは「ああ、気にするな」と、ブランケットを持つ手で私を軽く制して、トレイをティーテーブルの上に静かに置いた。
「シ…イオタだったか。ここへ運んで来る途中だった物を代わりに受け取っただけだ。私が貴女と〝狐火〟を見たいのだと言ったら、快く代わってくれた」
ココロヨク、のところだけちょっと違う響きがした様な気がしたけど、きっとそれは気が付かない方が良いんだろうな……。
うん、ゴメンねシーグ。
「どうやら〝狐火〟は、まだみたいだな」
「あ、そ、そうですね。と言うか、必ず毎日出現する訳でもないって聞いてますし……あくまで確率は高いだろう、と言う話で……」
「なるほど。だから、暖を確保して待つ体制なのか」
そう言ったエドヴァルドは、椅子の近くまで来ると、大判なブランケットを自らに羽織らせる様にして、優雅に腰を下ろした。
何だか……ただ椅子に座るだけの仕種さえ、流れる様なスマートさだ。
さすが幼い頃から礼儀作法を叩きこまれた大貴族は、この辺りからして違う。
――などと、うっかり感心していた所為か、エドヴァルドがその一連の動作の延長線上でこちらに差し出して来た手を、うっかりと取ってしまった。
「ふえっ⁉」
自分でもおかしいと思える声を上げたのは、分かっていた。
だけど気が付いた時には、エドヴァルドの長い足の間に挟まれるようにして座っているなどと、他にどうリアクションのしようがあったと言うのか……‼
「えええ、エドヴァルド様……っ⁉」
そのうえ、出て来る言葉も嚙みまくりだ。
「この方が温かいだろう」
いえ、違う意味でアタマが沸騰しそうです……‼
「イオタもこれ一つしか、羽織る物を持って来なかった事だしな」
それはきっと、自分には必要ないと思っていたからだろう、と思いながらも、色々と動揺していて、それが口に出る事はなかった。
だって、所詮はアイアンチェア。
椅子の幅から言って、座っていると言うよりは、エドヴァルドの上に乗ってしまっていると言った方が、限りなく正しいのだ。
「だ、ダメですって…っ、これ、絶対後でエドヴァルド様の足が痺れますって!わ…私だってそこまで軽くは……っ」
重い、などと言うとちょっと悲しくなるので、せめて「軽くない」と言い換えてみたけれど、エドヴァルドはと言えば、そんな事は気にも留めていないようだった。
「心配しなくて良い。貴女はこちらが不安になるほど華奢だ。慣れない北の地で風邪を引かれるのも困る。これくらいで、ちょうど良い」
「え…や…でも…っ」
「私の足が痺れる心配をしてくれるのなら、むしろ暴れずに大人しくしていてくれ。……それとも、まだ寒いか?」
もう私は、これでもかと言うくらいに首を横に振ってしまった。
ブランケットどころかエドヴァルドに包まれているかの様なこの状況で、一体誰が「寒い」などと言えるのか……‼
自分で自分の心臓の音が聞こえるくらいに動揺している私の耳元で、相も変わらず腰砕けになりそうな囁き声が、止む事なく耳に届く。
「フェドート卿によれば、紫や緑、赤と言った色が夜空に散るらしい。どれか一色の日もあれば、複数の色が混ざり合うように見える日もある、と。貴女の国でも、そんな風に?」
頭の片隅で「やっぱり完璧、オーロラだよねそれ……」と思いながらも、思った事がすぐさま声になったかと言えば、そうでもない。
返事のない私を、さすがにエドヴァルドも訝しんだのか、後ろから私を支える腕に少し力が入って――こちらを覗き込もうとしているのが横目に見えた。
「レイナ?」
「はいっ⁉ああっ、えっと、そうですね、私も直接は見た事がないんですけど、写真――絵とかで見たのは、そんな感じ…だった、かも……?」
写真だの旅番組だのと、当たり前だけど説明が出来ずに、結局「絵」としか言えずじまい。
ただ、私が上手く説明出来る語彙を持たなかったのだと、察したエドヴァルドは、それ以上の細かい事は聞いては来なかった。
やっぱり、察しの良い人だと思う。
思う…けど!
「レイナ、俯いたままだと、せっかく〝狐火〟が顕れても見えないんじゃないか?」
「こっ…こんな姿勢で見るとか…思わなかったので…っ」
だから普通に座りたいと言う私の無言のアピールは、今度は分かっていて無視された。
「日が暮れてしまったから、良くは分からないが……さぞ、貴女の顔は赤くなっているんだろうな……もったいない」
「もっ…⁉」
「今、ここには私しかいない。他の誰にも見られる事はないのは良いとして、肝心の私ですらそれを見る事が出来ないとはな」
「……っ」
そんなモノは見なくても良いです――‼
また、ジタバタと動きかけたところ、ダメだとでも言うように、エドヴァルドの腕に力が入った。
「貴女のいた世界に、私の知らない貴女がいるのは仕方がない。そこは妥協をする」
うん?妥協?
「だが」
聞き捨てならない言葉を振り返る間もなく、言葉が次々と耳元をすり抜けていく。
「今は――私が貴女と言う存在を知った今は、喜怒哀楽における、貴女の表情の全てを、私は知りたい。私しか知らない表情を見せてくれればそれが最良だが、少なくともその逆は、許容出来そうにない」
「⁉」
もう、何を言っているのか理解が及びません――‼
「ああ……それだ」
蕩けるような、色気二割増の声が聞こえた気がした。
「その表情、他の誰にも見せないでくれるか……」
「……っ」
エドヴァルドの右手が私の左頬にかかり、あまりに自然な仕種で斜め上を向かせられてしまった。
「ん…んっ」
ここ、他人ん家――‼︎
なかなか止まないどころか、どんどんと深くなる口づけに、抗議の意味もこめてペシペシと頬に触れられたままの手を叩いてみたけれど、まるで効いた様子がなかった。
そう言えば、宰相室と言いラハデ公爵邸と言い、考えてみれば気にする人じゃなかった!
「……ああ、すまない」
呼吸困難寸前のタイミングで、ようやくエドヴァルドの整った顔が少しだけ視界から外れた。
「これでは〝狐火〟が顕れても見えないな」
さも、今思い出したかの様に言っているけれど、口元に愉悦の笑みが浮かんでいるからには、明らかに、わざとだ。
私は「怒ってます」と主張するつもりで軽く睨んでみたら、何故かエドヴァルドには「レイナ……」と、盛大なため息を零されてしまった。
「確かに、そんな表情をさせてしまった私にも非はあるが、そのまま睨もうとしないでくれ。私には、煽られているとしか見えなくなってしまう」
「⁉︎」
「今すぐ寝台に連れて行きたくなってしまうから、やめてくれ」
「……ハイ」
どんな表情だとか、煽るって何、とか思うところはあれど、とりあえずワカリマシタ。
ここは「はい」一択だと言う事だけは、理解しました。
今の拍子にずり落ちかけていたブランケットを羽織り直すように、体制を元――と言っても、ブランケットとエドヴァルドに包まれた状態――に戻したエドヴァルドが、そこでふと視線を前に向けて、目を細めた。
「始まる……のか?」
何が、とは今は聞くまでもないだろう。
私も慌てて同じように、エドヴァルドが見ている方角に視線を投げた。
左手には何かしらの毛皮だろうと思しきブランケット。
いや、ブランケットにしてもちょっと大きいような……それはともかく。
「エ…ドヴァルド様……何で、そんな……」
背筋のピンと伸びた、隙のない佇まいもさることながら、手にしているのがティーセットとブランケット。
一瞬どこのコスプレ執事が来たのかと思ってしまった。
と言うか、天下の宰相閣下が何でそんな用意を!
私が慌てて代わりに持とうと立ち上がったけれど、エドヴァルドは「ああ、気にするな」と、ブランケットを持つ手で私を軽く制して、トレイをティーテーブルの上に静かに置いた。
「シ…イオタだったか。ここへ運んで来る途中だった物を代わりに受け取っただけだ。私が貴女と〝狐火〟を見たいのだと言ったら、快く代わってくれた」
ココロヨク、のところだけちょっと違う響きがした様な気がしたけど、きっとそれは気が付かない方が良いんだろうな……。
うん、ゴメンねシーグ。
「どうやら〝狐火〟は、まだみたいだな」
「あ、そ、そうですね。と言うか、必ず毎日出現する訳でもないって聞いてますし……あくまで確率は高いだろう、と言う話で……」
「なるほど。だから、暖を確保して待つ体制なのか」
そう言ったエドヴァルドは、椅子の近くまで来ると、大判なブランケットを自らに羽織らせる様にして、優雅に腰を下ろした。
何だか……ただ椅子に座るだけの仕種さえ、流れる様なスマートさだ。
さすが幼い頃から礼儀作法を叩きこまれた大貴族は、この辺りからして違う。
――などと、うっかり感心していた所為か、エドヴァルドがその一連の動作の延長線上でこちらに差し出して来た手を、うっかりと取ってしまった。
「ふえっ⁉」
自分でもおかしいと思える声を上げたのは、分かっていた。
だけど気が付いた時には、エドヴァルドの長い足の間に挟まれるようにして座っているなどと、他にどうリアクションのしようがあったと言うのか……‼
「えええ、エドヴァルド様……っ⁉」
そのうえ、出て来る言葉も嚙みまくりだ。
「この方が温かいだろう」
いえ、違う意味でアタマが沸騰しそうです……‼
「イオタもこれ一つしか、羽織る物を持って来なかった事だしな」
それはきっと、自分には必要ないと思っていたからだろう、と思いながらも、色々と動揺していて、それが口に出る事はなかった。
だって、所詮はアイアンチェア。
椅子の幅から言って、座っていると言うよりは、エドヴァルドの上に乗ってしまっていると言った方が、限りなく正しいのだ。
「だ、ダメですって…っ、これ、絶対後でエドヴァルド様の足が痺れますって!わ…私だってそこまで軽くは……っ」
重い、などと言うとちょっと悲しくなるので、せめて「軽くない」と言い換えてみたけれど、エドヴァルドはと言えば、そんな事は気にも留めていないようだった。
「心配しなくて良い。貴女はこちらが不安になるほど華奢だ。慣れない北の地で風邪を引かれるのも困る。これくらいで、ちょうど良い」
「え…や…でも…っ」
「私の足が痺れる心配をしてくれるのなら、むしろ暴れずに大人しくしていてくれ。……それとも、まだ寒いか?」
もう私は、これでもかと言うくらいに首を横に振ってしまった。
ブランケットどころかエドヴァルドに包まれているかの様なこの状況で、一体誰が「寒い」などと言えるのか……‼
自分で自分の心臓の音が聞こえるくらいに動揺している私の耳元で、相も変わらず腰砕けになりそうな囁き声が、止む事なく耳に届く。
「フェドート卿によれば、紫や緑、赤と言った色が夜空に散るらしい。どれか一色の日もあれば、複数の色が混ざり合うように見える日もある、と。貴女の国でも、そんな風に?」
頭の片隅で「やっぱり完璧、オーロラだよねそれ……」と思いながらも、思った事がすぐさま声になったかと言えば、そうでもない。
返事のない私を、さすがにエドヴァルドも訝しんだのか、後ろから私を支える腕に少し力が入って――こちらを覗き込もうとしているのが横目に見えた。
「レイナ?」
「はいっ⁉ああっ、えっと、そうですね、私も直接は見た事がないんですけど、写真――絵とかで見たのは、そんな感じ…だった、かも……?」
写真だの旅番組だのと、当たり前だけど説明が出来ずに、結局「絵」としか言えずじまい。
ただ、私が上手く説明出来る語彙を持たなかったのだと、察したエドヴァルドは、それ以上の細かい事は聞いては来なかった。
やっぱり、察しの良い人だと思う。
思う…けど!
「レイナ、俯いたままだと、せっかく〝狐火〟が顕れても見えないんじゃないか?」
「こっ…こんな姿勢で見るとか…思わなかったので…っ」
だから普通に座りたいと言う私の無言のアピールは、今度は分かっていて無視された。
「日が暮れてしまったから、良くは分からないが……さぞ、貴女の顔は赤くなっているんだろうな……もったいない」
「もっ…⁉」
「今、ここには私しかいない。他の誰にも見られる事はないのは良いとして、肝心の私ですらそれを見る事が出来ないとはな」
「……っ」
そんなモノは見なくても良いです――‼
また、ジタバタと動きかけたところ、ダメだとでも言うように、エドヴァルドの腕に力が入った。
「貴女のいた世界に、私の知らない貴女がいるのは仕方がない。そこは妥協をする」
うん?妥協?
「だが」
聞き捨てならない言葉を振り返る間もなく、言葉が次々と耳元をすり抜けていく。
「今は――私が貴女と言う存在を知った今は、喜怒哀楽における、貴女の表情の全てを、私は知りたい。私しか知らない表情を見せてくれればそれが最良だが、少なくともその逆は、許容出来そうにない」
「⁉」
もう、何を言っているのか理解が及びません――‼
「ああ……それだ」
蕩けるような、色気二割増の声が聞こえた気がした。
「その表情、他の誰にも見せないでくれるか……」
「……っ」
エドヴァルドの右手が私の左頬にかかり、あまりに自然な仕種で斜め上を向かせられてしまった。
「ん…んっ」
ここ、他人ん家――‼︎
なかなか止まないどころか、どんどんと深くなる口づけに、抗議の意味もこめてペシペシと頬に触れられたままの手を叩いてみたけれど、まるで効いた様子がなかった。
そう言えば、宰相室と言いラハデ公爵邸と言い、考えてみれば気にする人じゃなかった!
「……ああ、すまない」
呼吸困難寸前のタイミングで、ようやくエドヴァルドの整った顔が少しだけ視界から外れた。
「これでは〝狐火〟が顕れても見えないな」
さも、今思い出したかの様に言っているけれど、口元に愉悦の笑みが浮かんでいるからには、明らかに、わざとだ。
私は「怒ってます」と主張するつもりで軽く睨んでみたら、何故かエドヴァルドには「レイナ……」と、盛大なため息を零されてしまった。
「確かに、そんな表情をさせてしまった私にも非はあるが、そのまま睨もうとしないでくれ。私には、煽られているとしか見えなくなってしまう」
「⁉︎」
「今すぐ寝台に連れて行きたくなってしまうから、やめてくれ」
「……ハイ」
どんな表情だとか、煽るって何、とか思うところはあれど、とりあえずワカリマシタ。
ここは「はい」一択だと言う事だけは、理解しました。
今の拍子にずり落ちかけていたブランケットを羽織り直すように、体制を元――と言っても、ブランケットとエドヴァルドに包まれた状態――に戻したエドヴァルドが、そこでふと視線を前に向けて、目を細めた。
「始まる……のか?」
何が、とは今は聞くまでもないだろう。
私も慌てて同じように、エドヴァルドが見ている方角に視線を投げた。
1,007
あなたにおすすめの小説
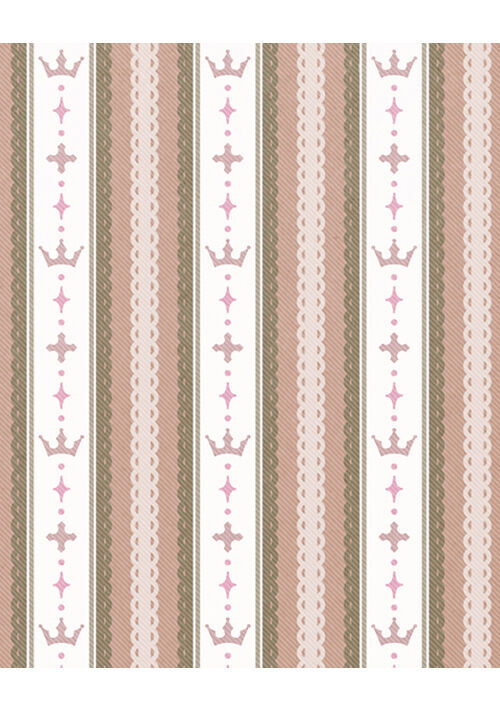
【完結】「神様、辞めました〜竜神の愛し子に冤罪を着せ投獄するような人間なんてもう知らない」
まほりろ
恋愛
王太子アビー・シュトースと聖女カーラ・ノルデン公爵令嬢の結婚式当日。二人が教会での誓いの儀式を終え、教会の扉を開け外に一歩踏み出したとき、国中の壁や窓に不吉な文字が浮かび上がった。
【本日付けで神を辞めることにした】
フラワーシャワーを巻き王太子と王太子妃の結婚を祝おうとしていた参列者は、突然現れた文字に驚きを隠せず固まっている。
国境に壁を築きモンスターの侵入を防ぎ、結界を張り国内にいるモンスターは弱体化させ、雨を降らせ大地を潤し、土地を豊かにし豊作をもたらし、人間の体を強化し、生活が便利になるように魔法の力を授けた、竜神ウィルペアトが消えた。
人々は三カ月前に冤罪を着せ、|罵詈雑言《ばりぞうごん》を浴びせ、石を投げつけ投獄した少女が、本物の【竜の愛し子】だと分かり|戦慄《せんりつ》した。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
アルファポリスに先行投稿しています。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
2021/12/13、HOTランキング3位、12/14総合ランキング4位、恋愛3位に入りました! ありがとうございます!

《完結》金貨5000枚で売られた王太子妃
ぜらちん黒糖
恋愛
「愛している。必ず迎えに行くから待っていてくれ」
甘い言葉を信じて、隣国へ「人質」となった王太子妃イザベラ。
旅立ちの前の晩、二人は愛し合い、イザベラのお腹には新しい命が宿った。すぐに夫に知らせた イザベラだったが、夫から届いた返信は、信じられない内容だった。
「それは本当に私の子供なのか?」

四の五の言わず離婚届にサインをしてくれません?
白雲八鈴
恋愛
アルディーラ公爵夫人であるミレーネは、他の人からみれば羨ましいと思える立場にいた。
王妹の母譲りの美人の顔立ち、公爵夫人として注目を集める立場、そして領地の運営は革命と言えるほど領地に潤いを与えていた。
だが、そんなミレーネの心の中にあるのは『早く離婚したい』だった。
順風満帆と言えるミレーネは何が不満なのか。その原因は何か。何故離婚できないのか。
そこから始まる物語である。

【完結】離縁ですか…では、私が出掛けている間に出ていって下さいね♪
山葵
恋愛
突然、カイルから離縁して欲しいと言われ、戸惑いながらも理由を聞いた。
「俺は真実の愛に目覚めたのだ。マリアこそ俺の運命の相手!」
そうですか…。
私は離婚届にサインをする。
私は、直ぐに役所に届ける様に使用人に渡した。
使用人が出掛けるのを確認してから
「私とアスベスが旅行に行っている間に荷物を纏めて出ていって下さいね♪」

聖女召喚されて『お前なんか聖女じゃない』って断罪されているけど、そんなことよりこの国が私を召喚したせいで滅びそうなのがこわい
金田のん
恋愛
自室で普通にお茶をしていたら、聖女召喚されました。
私と一緒に聖女召喚されたのは、若くてかわいい女の子。
勝手に召喚しといて「平凡顔の年増」とかいう王族の暴言はこの際、置いておこう。
なぜなら、この国・・・・私を召喚したせいで・・・・いまにも滅びそうだから・・・・・。
※小説家になろうさんにも投稿しています。

プロローグでケリをつけた乙女ゲームに、悪役令嬢は必要ない(と思いたい)
犬野きらり
恋愛
私、ミルフィーナ・ダルンは侯爵令嬢で二年前にこの世界が乙女ゲームと気づき本当にヒロインがいるか確認して、私は覚悟を決めた。
『ヒロインをゲーム本編に出さない。プロローグでケリをつける』
ヒロインは、お父様の再婚相手の連れ子な義妹、特に何もされていないが、今後が大変そうだからひとまず、ごめんなさい。プロローグは肩慣らし程度の攻略対象者の義兄。わかっていれば対応はできます。
まず乙女ゲームって一人の女の子が何人も男性を攻略出来ること自体、あり得ないのよ。ヒロインは天然だから気づかない、嘘、嘘。わかってて敢えてやってるからね、男落とし、それで成り上がってますから。
みんなに現実見せて、納得してもらう。揚げ足、ご都合に変換発言なんて上等!ヒロインと一緒の生活は、少しの発言でも悪役令嬢発言多々ありらしく、私も危ない。ごめんね、ヒロインさん、そんな理由で強制退去です。
でもこのゲーム退屈で途中でやめたから、その続き知りません。

【完結】悪役令嬢は3歳?〜断罪されていたのは、幼女でした〜
白崎りか
恋愛
魔法学園の卒業式に招かれた保護者達は、突然、王太子の始めた蛮行に驚愕した。
舞台上で、大柄な男子生徒が幼い子供を押さえつけているのだ。
王太子は、それを見下ろし、子供に向って婚約破棄を告げた。
「ヒナコのノートを汚したな!」
「ちがうもん。ミア、お絵かきしてただけだもん!」
小説家になろう様でも投稿しています。

旦那様、愛人を作ってもいいですか?
ひろか
恋愛
私には前世の記憶があります。ニホンでの四六年という。
「君の役目は魔力を多く持つ子供を産むこと。その後で君も自由にすればいい」
これ、旦那様から、初夜での言葉です。
んん?美筋肉イケオジな愛人を持っても良いと?
’18/10/21…おまけ小話追加
過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている
と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
番外編を閲覧することが出来ません。
過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている
と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。




















