39 / 56
第39話:森の朝、パンの香りと泡立つ一日
第39話:森の朝、パンの香りと泡立つ一日
しおりを挟む
森の朝は静かだが、この家の朝は、静か“だけ”では終わらない。
窓の外では小鳥がさえずり、木々を揺らす風がさらさらと音を立てている。
その一方で、ログハウスの中には、別の“生活の音”が広がっていた。
キッチンから聞こえてくる、電子レンジの小さな駆動音と、オーブンの予熱完了を告げる軽い電子音。
石窯には魔法と電気の両方を利用した熱が回り、大型冷蔵庫の中では、低い唸りが一定のリズムで続いている。
――異世界の森の中なのに、電気が通っているという違和感にも、もうすっかり慣れてしまった。
俺はベッドの上で軽く伸びをした。
1階の廊下側の壁越しに、隣の部屋――ネロの寝返りを打つ気配が伝わってくる。
「⋯⋯んにゃ⋯⋯兄ちゃ⋯⋯パン⋯⋯」
寝言まで食いしん坊か。
もう一つ隣のリオの部屋からは、布団の中でゆっくりと身じろぎする気配だけがした。
どうやら、まだ“意識は現世にログインしていない”らしい。
布団を抜け出して寝間着のまま部屋を出ると、廊下にはすでにかすかなパンの香りが流れてきていた。
キッチンは、リビングを挟んで真正面。
玄関のほうから差し込む朝の光が、木の床を斜めに照らしている。
リビングを抜けてキッチンに顔を出すと、そこにはいつもの光景があった。
「おはよう、シュウさん」
石窯の前に立っているミラが、振り返って微笑んだ。
髪を後ろでまとめ、薄いエプロンの紐を結び直しながら、温度計の表示をちらりと確認する。
「おはよう。窯の機嫌はどうだ?」
「上機嫌よ。ほら」
ミラが指さした先では、石窯の内部に設置した電熱と魔導ヒーターが、均一な温度で赤く光っていた。
その中には、すでに膨らみつつあるパン生地の並んだ天板が収まっている。
「発酵は冷蔵庫の中で一晩ゆっくりさせたから、きっと今日のはふわふわになるわね」
「さすがだな。じゃあ、スープと付け合わせは俺が仕上げるか」
コンロの上では、野菜と豆を煮込んだスープが、ことことと静かに泡を立てていた。
俺は味見をして、塩をひとつまみと、ミラの薬草保存部屋から拝借してきたローリエを一枚足す。
「ミラ、卵とベーコン、焼いていいか?」
「ええ。今日はたくさん動くものね。しっかり食べましょう」
冷蔵庫を開けると、整然と並んだ食材たちが冷気とともに姿を現す。
この冷蔵庫と洗濯機、電子レンジ、ソーラーシステム――全部、神様からもらったスマホでアクセスできる《異世界マーケット》から調達したものだ。
森のど真ん中なのに、電気が通っている生活。
だが、その中で作られるものは、どこまでも“手仕事の温度”をしている。
電子レンジのタイマーを軽く回し、昨夜の残り物の煮込みを温め直す。
フライパンを温め、ベーコンを並べ、卵を落とすと、じゅっと心地いい音が鳴った。
そこへ、廊下から足音が二つぶつかりながら近づいてくる。
「兄ちゃん、パンのいい匂いする!」
「⋯⋯ほんとだ⋯⋯」
ネロが勢いよくリビングに飛び込み、その後ろからリオがまだ半分夢の中みたいな足取りでついてくる。
「おはよう、兄ちゃん!」
「⋯⋯おはよう⋯⋯」
「おはよう。顔洗ってこい。パンが焼き上がる前にな」
「はい!」
ネロは全力で返事をし、そのまま玄関の横の洗面スペースへ走っていく。
リオも小さく頷き、ふらふらしながら後を追った。
そのタイミングで、2階からきしむ足音が聞こえてくる。
「ふぁ~⋯⋯あー、腹減った⋯⋯」
アレンが、今にも階段から落ちそうな勢いで降りてきた。
髪は寝癖で跳ねているが、表情だけはやたら元気だ。
「おっはよー! 今日も働くぞー!」
「⋯⋯声がでかい」
階段の途中で、フェイが小さく眉をひそめていた。
「フェイもおはよう。ヨシュアは?」
「ヨシュア様は⋯⋯今、寝癖と格闘しておられます」
言葉が終わる前に、2階から控えめな声が聞こえてきた。
「アレンさん、そんなに騒がなくても、パンは逃げませんよ⋯⋯」
やがて、髪をどうにか整えたヨシュアが階段を降りてくる。
それでも、前髪の一部はわずかに跳ねていて、ネロに指摘される未来がすでに見える。
「おはようございます、シュウさん。⋯⋯あ、いい匂いですね」
「おはよう。今日は石鹸とポーション作りだからな。エネルギー補給しとかないと」
「はい。皿並べますね」
ヨシュアは慣れた手つきで、棚から皿を取り出し、リビングのテーブルに並べていく。
その姿は、王都の王宮で見る“皇子”の姿とはまるで別人だ。
ちょうどそのとき、石窯の中でパンの表面がこんがりと色づき始めた。
香ばしい匂いが一気に広がり、リビングの空気が一段と明るくなる。
「シュウさん、焼き上がるわよ」
「おう。取り出すぞ」
ミラが窯の扉を開けると、熱気とともに、ふわりと小麦とバターの香りが溢れた。
ふくらんだ丸パンがいくつも並び、その表面にはほんのりとした焼き色がついている。
「わぁぁぁぁ!」
顔を洗って戻ってきたネロが、目を輝かせた。
「⋯⋯きれい」
リオも静かに呟く。
「触るなよ。熱いからな。冷めるまで待つんだぞ」
「はーい⋯⋯」
待てるかどうかは、かなり怪しい返事だった。
テーブルには、焼きたてのパンと、野菜と豆のスープ、ベーコンエッグ、昨夜の残りの煮込みを温め直した一皿が並べられた。
「いただきます!」
ネロの声を合図に、全員が手を合わせる。
パンを割ると、中から湯気が立ち上り、ふわふわとした生地が顔を出した。
バターとハチミツを少しだけ塗ると、甘い匂いが、朝の空気に混ざっていく。
「兄ちゃん、このパン最高!」
「⋯⋯もっちり⋯⋯ふわふわ⋯⋯」
「ミラの発酵管理が良かったからだな」
「いいえ、シュウさんの捏ね方が丁寧だからよ。あの手つき、すごく好き」
「褒め方がややこしいな」
アレンはベーコンをほおばりながら、スープをがぶがぶと飲んでいる。
「んーっ! うまい! これなら石鹸100個くらい余裕だな!」
「兄ちゃん、それはそれ、これはこれです。途中で息切れして倒れないでくださいよ?」
ヨシュアが苦笑する。
「アレン様が倒れた場合、私が引きずってでも作業場まで運びます」
フェイが淡々と言った。
「やめろ、怖えよ」
笑い声がテーブルに広がる。
外の森は相変わらず静かだが、ログハウスの中だけは、しっかりと“生活の喧騒”に満ちていた。
朝食を終えると、それぞれが片付けと準備に動き始める。
「シュウさん、私は先に薬草保存部屋で、今日使うハーブを出しておくわね」
「ああ。石鹸用のハーブは、あの乾燥棚の二段目の右側だな。ポーション用は午後にまとめてでいい」
「分かったわ」
ミラはリビングの奥、囲炉裏の部屋を通って、さらにその奥にある作業部屋と薬草保存部屋のほうへと消えていく。
囲炉裏の部屋には、まだ火は入っていないが、昨日の残りの炭がほんのりと灰の中で眠っていた。
「兄ちゃん、オレ何すればいい?」
「⋯⋯俺も、手伝う」
「まずは作業部屋のテーブルを拭いてこい。昨日のうちに片付けてあるけど、ほこりが溜まってるかもしれないからな」
「了解!」
ネロとリオは雑巾を持って走っていく。
「アレンは?」
「俺、薪運んでくる! 煮込みもするし、石鹸の灰汁も温めるんだろ?」
「ああ。あと、離れの倉庫にしまってある石鹸の木枠型も取ってきてくれ。昨日点検したやつだ」
「任せろ!」
アレンは玄関を飛び出し、テラスを駆け抜けて、石造りの離れへ向かっていった。
離れには温泉風呂とトイレ、そして倉庫がある。
けれど今の時間はまだ湯気も立っていない、ただ静かな石の建物だ。
「フェイとヨシュアは、午前中は自由でいいぞ。午後、ポーションの瓶詰めのときに手を借りる」
「承知しました。⋯⋯では私は、周囲の巡回をしてきます。森の魔物が近づかぬよう」
「僕は、午前中は本を読んでいてもいいですか? この世界の薬草のこと、少し勉強したくて」
「もちろんだ。あとで質問があったらミラに聞くといい」
二人はそれぞれの役割に向かっていき、リビングには一瞬だけ静けさが戻った。
だが、その静けさは、これから始まる“手仕事の一日”の前触れにすぎない。
俺はエプロンの紐を結び直し、囲炉裏の部屋を抜けて、作業部屋へ向かった。
「――さて。石鹸100個とポーション150本。今日も、いい一日にするか」
森の中の小さなログハウスの朝は、パンの香りと、電気の微かな振動音と、仲間たちの笑い声の中で、静かに、けれど確かに動き始めた。
その先に待っているのは、灰汁の泡立ちと、ハーブの香りと、黄金色のポーションの輝き。
そして、夕暮れの食卓で交わされる、何気ない“おつかれさま”の言葉だ。
俺は作業部屋の扉を開け、その一日の始まりへと足を踏み入れた。
工房に、淡い光が満ち始めていた。
石鹸の生地が、まるで呼吸するようにふわりと輝く。
ミラはその光に目を見張り、そっと手を胸に当てた。
「⋯⋯綺麗です、シュウさん。まるで、小さな星のようです」
「ありがとう、ミラ。順調だね」
シュウが火加減を調整すると、ネロが鍋を覗き込む。
「兄ちゃん、これ絶対売れるって! 光る石鹸なんて反則だよ!」
「ネロ、揺らすと気泡が入るよ」
リオが慌ててネロの腕を掴む。
「兄さんが言ってた⋯⋯“石鹸は静かに育てる”って」
「あ、ごめん⋯⋯わかったよ」
ネロは素直に手を離し、リオはほっと息をついた。
ラムが椅子に腰掛け、光る石鹸を静かに見つめていた。
その瞳は、森の奥深くと同じ色をしている。
「⋯⋯人の子の手で紡がれた光は、いつ見ても愛おしいものだな、シュウよ」
「ラム、見ててくれてたんだね」
「うむ。お前たちの“歌”は、今日も澄んでおる」
ミラはその言葉に、少しだけ背筋を伸ばした。
ポーション台ではアレンが瓶を並べ、慎重に分量を量っている。
「⋯⋯よし、基礎液はこれで完成だ」
ミラがそっと近づく。
「アレンさん、こちらの薬草も使いますか?」
「助かる。ミラ、そっちの瓶を取ってくれ」
二人の動きは落ち着いていて、工房に安定したリズムを与えていた。
ラムはその様子を見て、静かに微笑む。
「⋯⋯アレンよ。お前の手は、昔よりずっと優しくなったな」
アレンは少し照れたように鼻をかいた。
リビングではヨシュアが分厚い薬草図鑑を広げ、真剣な顔で読み進めていた。
「⋯⋯“月影草”は夜に光る⋯⋯へぇ⋯⋯」
ページをめくるたびに、知らない世界が広がっていく。
アレンのように役に立ちたい――その思いが、ヨシュアを静かに前へ押していた。
外ではフェイが森の縁を歩き、風の流れを読むように耳を澄ませていた。
その少し後ろを、ウォルフが無言でついてくる。
「⋯⋯今日は静かだな、ウォルフ」
「チッ⋯⋯魔獣の匂いが薄い。つまらん」
フェイは苦笑しながらも、歩みを止めない。
「静かな日も悪くないだろ」
「お前の足音は悪くは無い。狩りなら合格だ」
「褒めてるのか、それ」
「無論、事実を言ったまでだ」
二人の足音だけが、夕暮れの森に溶けていく。
石鹸の光は徐々に落ち着き、
ポーションの香りが甘く広がっていく。
「兄さん、今日の工房⋯⋯なんか、いい匂い」
「そうだね。みんなの気持ちが混ざってるからかな」
リオの言葉に、ミラはそっと微笑んだ。
ラムはその様子を見て、静かに目を細める。
「⋯⋯良い“家”になったものだな」
その言葉に、ウォルフが工房の入口から鼻を鳴らした。
「当たり前だ。ここは群れの家だ。守る理由は、それで足りる」
シュウはその言葉に、静かに微笑んだ。
「⋯⋯おかえり、ウォルフ」
「うむ。無事で何よりだ」
工房の灯り、リビングの静けさ、森の息吹。
それらすべてが一つに溶け合い、家は今日も、優しい光に包まれていた。
工房の空気が、ゆっくりと変わり始めていた。
石鹸の光が落ち着き、代わりにポーション台のほうから、薬草と魔力の混ざり合う甘い香りが漂ってくる。
「アレン、基礎液はもう十分だな。ここから三種類に分けて仕上げるぞ」
「おう! 回復、魔力回復、解毒だな。どれからいく?」
「まずは回復ポーションからだ。ヨシュア、瓶の準備を頼む」
「はい!」
ヨシュアが瓶を並べ、フェイが蓋を整列させる。
ミラは薬草保存棚から、必要な材料をそっと抱えて戻ってきた。
「シュウさん、カモミールとセージ、甘草、それから蜂蜜です」
「ありがとう。癒し魔法は最後に注ぐから、準備しておいてくれ」
鍋にカモミールを入れた瞬間、ふわりと優しい香りが立ち上がる。
続いてセージの落ち着いた香り、甘草の甘い匂いが混ざり合い、工房の空気が柔らかく変わっていく。
「兄ちゃん、なんか⋯⋯眠くなる匂い」
「リオ、寝るなよ。まだラベル貼りがあるんだから」
「⋯⋯がんばる」
アレンが蜂蜜をゆっくりと垂らし、ミラが優しく攪拌する。
シュウは鍋の上に手をかざし、微量の癒し魔法を注ぎ込んだ。
淡い金色の光が、鍋の中で静かに揺れる。
「よし、回復ポーション50本、完成だ」
「瓶詰めします!」
ヨシュアとフェイが息を合わせて瓶に注ぎ、ネロとリオがラベルを貼る。
棚に並んだ金色の瓶は、まるで朝日を閉じ込めたように輝いていた。
「次は魔力回復だ。ローズマリーとミント、それからエネルギー草を頼む」
「はい、こちらです」
ミラが差し出した薬草を鍋に入れると、爽やかな香りが一気に広がった。
ローズマリーの鋭い香りと、ミントの清涼感。
そこに、異世界特有の《エネルギー草》の淡い光が混ざり、鍋の中が淡い緑色に染まっていく。
「兄ちゃん、この匂い⋯⋯なんか元気出る!」
「エネルギー草は魔力の流れを整えるからね。アレン、火加減を一定に」
「了解!」
ミラが攪拌し、シュウが濃度を確認する。
やがて、鍋の中の緑色が落ち着いた輝きを放ち始めた。
「魔力回復ポーション50本、完成だ」
「はい、瓶詰めいきます!」
緑色の瓶が棚に並ぶと、工房が少しだけ涼しく感じられた。
「最後は解毒だ。オレガノとタイム、それからウドの根を」
「浄化魔法を施した水も、ここに」
ミラが差し出した水は、ほんのりと光を帯びていた。
鍋に薬草を入れると、スパイスのような香りが立ち上り、ウドの根の土の匂いが混ざる。
「兄ちゃん、これ⋯⋯なんか薬っぽい匂い」
「毒を消すための香りだからね。アレン、ゆっくり混ぜてくれ」
「任せろ!」
浄化水を注ぐと、鍋の中が薄茶色に変わり、静かに落ち着いていく。
「解毒ポーション50本、完成だ」
「ラベル貼る!」
「⋯⋯ネロ、曲がってる」
「あっ⋯⋯直す!」
薄茶色の瓶が棚に並び、150本のポーションがすべて揃った。
夕暮れ――キッチンに灯りがともる。
「さて、夕飯を作るか」
「ええ。今日は⋯⋯みんな頑張ったものね。少し豪華にしましょう」
ミラが袖をまくり、シュウが包丁を手に取る。
キッチンには、朝とはまた違う温かい空気が満ちていく。
アレンは薪を追加し、フェイは静かにテーブルを整え、ヨシュアは皿を並べる。
ネロとリオは、パンの残りを温め直しながら、つまみ食いを必死に我慢していた。
「兄ちゃん、これ食べていい?」
「ダメだ。夕飯まで待て」
「うぅ⋯⋯」
リオが袖を引っ張る。
「⋯⋯ネロ、がまん⋯⋯」
「リオまで⋯⋯」
やがて、香ばしい肉の焼ける匂いと、ハーブの香りがリビングに広がった。
「できたぞー。今日はハーブローストと野菜のグリル、スープは昼の残りをアレンが煮詰めてくれたやつだ」
「おおっ! うまそー!」
「⋯⋯いい匂い」
「いただきます!」
全員の声が重なり、テーブルに笑顔が広がる。
ミラは静かに微笑み、シュウはその光景を見て、胸の奥が温かくなるのを感じた。
「今日も、いい1日だったな」
「ええ。とても」
ラムが頷き、ウォルフが尻尾を一度だけ揺らした。
夕食を終え、片付けも済ませると、家の中はゆっくりと静けさを取り戻していく。
ネロとリオは眠そうにあくびをし、ヨシュアは本を閉じ、フェイは窓の外を確認し、アレンは大きく伸びをした。
「ふぁぁ⋯⋯今日は働いたなぁ⋯⋯」
「兄ちゃん、明日筋肉痛にならないといいですね」
「やめろヨシュア⋯⋯」
ミラがくすりと笑い、シュウは灯りを少し落とした。
「みんな、お疲れさま。今日はゆっくり休もう」
「「「はーい」」」
森の夜風が、静かにログハウスを撫でていく。
石鹸の淡い光と、棚に並ぶポーションの輝きが、家の中に柔らかな影を落としていた。
その光景は、まるで――
今日一日を祝福する、静かな祈りのようだった。
窓の外では小鳥がさえずり、木々を揺らす風がさらさらと音を立てている。
その一方で、ログハウスの中には、別の“生活の音”が広がっていた。
キッチンから聞こえてくる、電子レンジの小さな駆動音と、オーブンの予熱完了を告げる軽い電子音。
石窯には魔法と電気の両方を利用した熱が回り、大型冷蔵庫の中では、低い唸りが一定のリズムで続いている。
――異世界の森の中なのに、電気が通っているという違和感にも、もうすっかり慣れてしまった。
俺はベッドの上で軽く伸びをした。
1階の廊下側の壁越しに、隣の部屋――ネロの寝返りを打つ気配が伝わってくる。
「⋯⋯んにゃ⋯⋯兄ちゃ⋯⋯パン⋯⋯」
寝言まで食いしん坊か。
もう一つ隣のリオの部屋からは、布団の中でゆっくりと身じろぎする気配だけがした。
どうやら、まだ“意識は現世にログインしていない”らしい。
布団を抜け出して寝間着のまま部屋を出ると、廊下にはすでにかすかなパンの香りが流れてきていた。
キッチンは、リビングを挟んで真正面。
玄関のほうから差し込む朝の光が、木の床を斜めに照らしている。
リビングを抜けてキッチンに顔を出すと、そこにはいつもの光景があった。
「おはよう、シュウさん」
石窯の前に立っているミラが、振り返って微笑んだ。
髪を後ろでまとめ、薄いエプロンの紐を結び直しながら、温度計の表示をちらりと確認する。
「おはよう。窯の機嫌はどうだ?」
「上機嫌よ。ほら」
ミラが指さした先では、石窯の内部に設置した電熱と魔導ヒーターが、均一な温度で赤く光っていた。
その中には、すでに膨らみつつあるパン生地の並んだ天板が収まっている。
「発酵は冷蔵庫の中で一晩ゆっくりさせたから、きっと今日のはふわふわになるわね」
「さすがだな。じゃあ、スープと付け合わせは俺が仕上げるか」
コンロの上では、野菜と豆を煮込んだスープが、ことことと静かに泡を立てていた。
俺は味見をして、塩をひとつまみと、ミラの薬草保存部屋から拝借してきたローリエを一枚足す。
「ミラ、卵とベーコン、焼いていいか?」
「ええ。今日はたくさん動くものね。しっかり食べましょう」
冷蔵庫を開けると、整然と並んだ食材たちが冷気とともに姿を現す。
この冷蔵庫と洗濯機、電子レンジ、ソーラーシステム――全部、神様からもらったスマホでアクセスできる《異世界マーケット》から調達したものだ。
森のど真ん中なのに、電気が通っている生活。
だが、その中で作られるものは、どこまでも“手仕事の温度”をしている。
電子レンジのタイマーを軽く回し、昨夜の残り物の煮込みを温め直す。
フライパンを温め、ベーコンを並べ、卵を落とすと、じゅっと心地いい音が鳴った。
そこへ、廊下から足音が二つぶつかりながら近づいてくる。
「兄ちゃん、パンのいい匂いする!」
「⋯⋯ほんとだ⋯⋯」
ネロが勢いよくリビングに飛び込み、その後ろからリオがまだ半分夢の中みたいな足取りでついてくる。
「おはよう、兄ちゃん!」
「⋯⋯おはよう⋯⋯」
「おはよう。顔洗ってこい。パンが焼き上がる前にな」
「はい!」
ネロは全力で返事をし、そのまま玄関の横の洗面スペースへ走っていく。
リオも小さく頷き、ふらふらしながら後を追った。
そのタイミングで、2階からきしむ足音が聞こえてくる。
「ふぁ~⋯⋯あー、腹減った⋯⋯」
アレンが、今にも階段から落ちそうな勢いで降りてきた。
髪は寝癖で跳ねているが、表情だけはやたら元気だ。
「おっはよー! 今日も働くぞー!」
「⋯⋯声がでかい」
階段の途中で、フェイが小さく眉をひそめていた。
「フェイもおはよう。ヨシュアは?」
「ヨシュア様は⋯⋯今、寝癖と格闘しておられます」
言葉が終わる前に、2階から控えめな声が聞こえてきた。
「アレンさん、そんなに騒がなくても、パンは逃げませんよ⋯⋯」
やがて、髪をどうにか整えたヨシュアが階段を降りてくる。
それでも、前髪の一部はわずかに跳ねていて、ネロに指摘される未来がすでに見える。
「おはようございます、シュウさん。⋯⋯あ、いい匂いですね」
「おはよう。今日は石鹸とポーション作りだからな。エネルギー補給しとかないと」
「はい。皿並べますね」
ヨシュアは慣れた手つきで、棚から皿を取り出し、リビングのテーブルに並べていく。
その姿は、王都の王宮で見る“皇子”の姿とはまるで別人だ。
ちょうどそのとき、石窯の中でパンの表面がこんがりと色づき始めた。
香ばしい匂いが一気に広がり、リビングの空気が一段と明るくなる。
「シュウさん、焼き上がるわよ」
「おう。取り出すぞ」
ミラが窯の扉を開けると、熱気とともに、ふわりと小麦とバターの香りが溢れた。
ふくらんだ丸パンがいくつも並び、その表面にはほんのりとした焼き色がついている。
「わぁぁぁぁ!」
顔を洗って戻ってきたネロが、目を輝かせた。
「⋯⋯きれい」
リオも静かに呟く。
「触るなよ。熱いからな。冷めるまで待つんだぞ」
「はーい⋯⋯」
待てるかどうかは、かなり怪しい返事だった。
テーブルには、焼きたてのパンと、野菜と豆のスープ、ベーコンエッグ、昨夜の残りの煮込みを温め直した一皿が並べられた。
「いただきます!」
ネロの声を合図に、全員が手を合わせる。
パンを割ると、中から湯気が立ち上り、ふわふわとした生地が顔を出した。
バターとハチミツを少しだけ塗ると、甘い匂いが、朝の空気に混ざっていく。
「兄ちゃん、このパン最高!」
「⋯⋯もっちり⋯⋯ふわふわ⋯⋯」
「ミラの発酵管理が良かったからだな」
「いいえ、シュウさんの捏ね方が丁寧だからよ。あの手つき、すごく好き」
「褒め方がややこしいな」
アレンはベーコンをほおばりながら、スープをがぶがぶと飲んでいる。
「んーっ! うまい! これなら石鹸100個くらい余裕だな!」
「兄ちゃん、それはそれ、これはこれです。途中で息切れして倒れないでくださいよ?」
ヨシュアが苦笑する。
「アレン様が倒れた場合、私が引きずってでも作業場まで運びます」
フェイが淡々と言った。
「やめろ、怖えよ」
笑い声がテーブルに広がる。
外の森は相変わらず静かだが、ログハウスの中だけは、しっかりと“生活の喧騒”に満ちていた。
朝食を終えると、それぞれが片付けと準備に動き始める。
「シュウさん、私は先に薬草保存部屋で、今日使うハーブを出しておくわね」
「ああ。石鹸用のハーブは、あの乾燥棚の二段目の右側だな。ポーション用は午後にまとめてでいい」
「分かったわ」
ミラはリビングの奥、囲炉裏の部屋を通って、さらにその奥にある作業部屋と薬草保存部屋のほうへと消えていく。
囲炉裏の部屋には、まだ火は入っていないが、昨日の残りの炭がほんのりと灰の中で眠っていた。
「兄ちゃん、オレ何すればいい?」
「⋯⋯俺も、手伝う」
「まずは作業部屋のテーブルを拭いてこい。昨日のうちに片付けてあるけど、ほこりが溜まってるかもしれないからな」
「了解!」
ネロとリオは雑巾を持って走っていく。
「アレンは?」
「俺、薪運んでくる! 煮込みもするし、石鹸の灰汁も温めるんだろ?」
「ああ。あと、離れの倉庫にしまってある石鹸の木枠型も取ってきてくれ。昨日点検したやつだ」
「任せろ!」
アレンは玄関を飛び出し、テラスを駆け抜けて、石造りの離れへ向かっていった。
離れには温泉風呂とトイレ、そして倉庫がある。
けれど今の時間はまだ湯気も立っていない、ただ静かな石の建物だ。
「フェイとヨシュアは、午前中は自由でいいぞ。午後、ポーションの瓶詰めのときに手を借りる」
「承知しました。⋯⋯では私は、周囲の巡回をしてきます。森の魔物が近づかぬよう」
「僕は、午前中は本を読んでいてもいいですか? この世界の薬草のこと、少し勉強したくて」
「もちろんだ。あとで質問があったらミラに聞くといい」
二人はそれぞれの役割に向かっていき、リビングには一瞬だけ静けさが戻った。
だが、その静けさは、これから始まる“手仕事の一日”の前触れにすぎない。
俺はエプロンの紐を結び直し、囲炉裏の部屋を抜けて、作業部屋へ向かった。
「――さて。石鹸100個とポーション150本。今日も、いい一日にするか」
森の中の小さなログハウスの朝は、パンの香りと、電気の微かな振動音と、仲間たちの笑い声の中で、静かに、けれど確かに動き始めた。
その先に待っているのは、灰汁の泡立ちと、ハーブの香りと、黄金色のポーションの輝き。
そして、夕暮れの食卓で交わされる、何気ない“おつかれさま”の言葉だ。
俺は作業部屋の扉を開け、その一日の始まりへと足を踏み入れた。
工房に、淡い光が満ち始めていた。
石鹸の生地が、まるで呼吸するようにふわりと輝く。
ミラはその光に目を見張り、そっと手を胸に当てた。
「⋯⋯綺麗です、シュウさん。まるで、小さな星のようです」
「ありがとう、ミラ。順調だね」
シュウが火加減を調整すると、ネロが鍋を覗き込む。
「兄ちゃん、これ絶対売れるって! 光る石鹸なんて反則だよ!」
「ネロ、揺らすと気泡が入るよ」
リオが慌ててネロの腕を掴む。
「兄さんが言ってた⋯⋯“石鹸は静かに育てる”って」
「あ、ごめん⋯⋯わかったよ」
ネロは素直に手を離し、リオはほっと息をついた。
ラムが椅子に腰掛け、光る石鹸を静かに見つめていた。
その瞳は、森の奥深くと同じ色をしている。
「⋯⋯人の子の手で紡がれた光は、いつ見ても愛おしいものだな、シュウよ」
「ラム、見ててくれてたんだね」
「うむ。お前たちの“歌”は、今日も澄んでおる」
ミラはその言葉に、少しだけ背筋を伸ばした。
ポーション台ではアレンが瓶を並べ、慎重に分量を量っている。
「⋯⋯よし、基礎液はこれで完成だ」
ミラがそっと近づく。
「アレンさん、こちらの薬草も使いますか?」
「助かる。ミラ、そっちの瓶を取ってくれ」
二人の動きは落ち着いていて、工房に安定したリズムを与えていた。
ラムはその様子を見て、静かに微笑む。
「⋯⋯アレンよ。お前の手は、昔よりずっと優しくなったな」
アレンは少し照れたように鼻をかいた。
リビングではヨシュアが分厚い薬草図鑑を広げ、真剣な顔で読み進めていた。
「⋯⋯“月影草”は夜に光る⋯⋯へぇ⋯⋯」
ページをめくるたびに、知らない世界が広がっていく。
アレンのように役に立ちたい――その思いが、ヨシュアを静かに前へ押していた。
外ではフェイが森の縁を歩き、風の流れを読むように耳を澄ませていた。
その少し後ろを、ウォルフが無言でついてくる。
「⋯⋯今日は静かだな、ウォルフ」
「チッ⋯⋯魔獣の匂いが薄い。つまらん」
フェイは苦笑しながらも、歩みを止めない。
「静かな日も悪くないだろ」
「お前の足音は悪くは無い。狩りなら合格だ」
「褒めてるのか、それ」
「無論、事実を言ったまでだ」
二人の足音だけが、夕暮れの森に溶けていく。
石鹸の光は徐々に落ち着き、
ポーションの香りが甘く広がっていく。
「兄さん、今日の工房⋯⋯なんか、いい匂い」
「そうだね。みんなの気持ちが混ざってるからかな」
リオの言葉に、ミラはそっと微笑んだ。
ラムはその様子を見て、静かに目を細める。
「⋯⋯良い“家”になったものだな」
その言葉に、ウォルフが工房の入口から鼻を鳴らした。
「当たり前だ。ここは群れの家だ。守る理由は、それで足りる」
シュウはその言葉に、静かに微笑んだ。
「⋯⋯おかえり、ウォルフ」
「うむ。無事で何よりだ」
工房の灯り、リビングの静けさ、森の息吹。
それらすべてが一つに溶け合い、家は今日も、優しい光に包まれていた。
工房の空気が、ゆっくりと変わり始めていた。
石鹸の光が落ち着き、代わりにポーション台のほうから、薬草と魔力の混ざり合う甘い香りが漂ってくる。
「アレン、基礎液はもう十分だな。ここから三種類に分けて仕上げるぞ」
「おう! 回復、魔力回復、解毒だな。どれからいく?」
「まずは回復ポーションからだ。ヨシュア、瓶の準備を頼む」
「はい!」
ヨシュアが瓶を並べ、フェイが蓋を整列させる。
ミラは薬草保存棚から、必要な材料をそっと抱えて戻ってきた。
「シュウさん、カモミールとセージ、甘草、それから蜂蜜です」
「ありがとう。癒し魔法は最後に注ぐから、準備しておいてくれ」
鍋にカモミールを入れた瞬間、ふわりと優しい香りが立ち上がる。
続いてセージの落ち着いた香り、甘草の甘い匂いが混ざり合い、工房の空気が柔らかく変わっていく。
「兄ちゃん、なんか⋯⋯眠くなる匂い」
「リオ、寝るなよ。まだラベル貼りがあるんだから」
「⋯⋯がんばる」
アレンが蜂蜜をゆっくりと垂らし、ミラが優しく攪拌する。
シュウは鍋の上に手をかざし、微量の癒し魔法を注ぎ込んだ。
淡い金色の光が、鍋の中で静かに揺れる。
「よし、回復ポーション50本、完成だ」
「瓶詰めします!」
ヨシュアとフェイが息を合わせて瓶に注ぎ、ネロとリオがラベルを貼る。
棚に並んだ金色の瓶は、まるで朝日を閉じ込めたように輝いていた。
「次は魔力回復だ。ローズマリーとミント、それからエネルギー草を頼む」
「はい、こちらです」
ミラが差し出した薬草を鍋に入れると、爽やかな香りが一気に広がった。
ローズマリーの鋭い香りと、ミントの清涼感。
そこに、異世界特有の《エネルギー草》の淡い光が混ざり、鍋の中が淡い緑色に染まっていく。
「兄ちゃん、この匂い⋯⋯なんか元気出る!」
「エネルギー草は魔力の流れを整えるからね。アレン、火加減を一定に」
「了解!」
ミラが攪拌し、シュウが濃度を確認する。
やがて、鍋の中の緑色が落ち着いた輝きを放ち始めた。
「魔力回復ポーション50本、完成だ」
「はい、瓶詰めいきます!」
緑色の瓶が棚に並ぶと、工房が少しだけ涼しく感じられた。
「最後は解毒だ。オレガノとタイム、それからウドの根を」
「浄化魔法を施した水も、ここに」
ミラが差し出した水は、ほんのりと光を帯びていた。
鍋に薬草を入れると、スパイスのような香りが立ち上り、ウドの根の土の匂いが混ざる。
「兄ちゃん、これ⋯⋯なんか薬っぽい匂い」
「毒を消すための香りだからね。アレン、ゆっくり混ぜてくれ」
「任せろ!」
浄化水を注ぐと、鍋の中が薄茶色に変わり、静かに落ち着いていく。
「解毒ポーション50本、完成だ」
「ラベル貼る!」
「⋯⋯ネロ、曲がってる」
「あっ⋯⋯直す!」
薄茶色の瓶が棚に並び、150本のポーションがすべて揃った。
夕暮れ――キッチンに灯りがともる。
「さて、夕飯を作るか」
「ええ。今日は⋯⋯みんな頑張ったものね。少し豪華にしましょう」
ミラが袖をまくり、シュウが包丁を手に取る。
キッチンには、朝とはまた違う温かい空気が満ちていく。
アレンは薪を追加し、フェイは静かにテーブルを整え、ヨシュアは皿を並べる。
ネロとリオは、パンの残りを温め直しながら、つまみ食いを必死に我慢していた。
「兄ちゃん、これ食べていい?」
「ダメだ。夕飯まで待て」
「うぅ⋯⋯」
リオが袖を引っ張る。
「⋯⋯ネロ、がまん⋯⋯」
「リオまで⋯⋯」
やがて、香ばしい肉の焼ける匂いと、ハーブの香りがリビングに広がった。
「できたぞー。今日はハーブローストと野菜のグリル、スープは昼の残りをアレンが煮詰めてくれたやつだ」
「おおっ! うまそー!」
「⋯⋯いい匂い」
「いただきます!」
全員の声が重なり、テーブルに笑顔が広がる。
ミラは静かに微笑み、シュウはその光景を見て、胸の奥が温かくなるのを感じた。
「今日も、いい1日だったな」
「ええ。とても」
ラムが頷き、ウォルフが尻尾を一度だけ揺らした。
夕食を終え、片付けも済ませると、家の中はゆっくりと静けさを取り戻していく。
ネロとリオは眠そうにあくびをし、ヨシュアは本を閉じ、フェイは窓の外を確認し、アレンは大きく伸びをした。
「ふぁぁ⋯⋯今日は働いたなぁ⋯⋯」
「兄ちゃん、明日筋肉痛にならないといいですね」
「やめろヨシュア⋯⋯」
ミラがくすりと笑い、シュウは灯りを少し落とした。
「みんな、お疲れさま。今日はゆっくり休もう」
「「「はーい」」」
森の夜風が、静かにログハウスを撫でていく。
石鹸の淡い光と、棚に並ぶポーションの輝きが、家の中に柔らかな影を落としていた。
その光景は、まるで――
今日一日を祝福する、静かな祈りのようだった。
0
あなたにおすすめの小説

高校生の俺、異世界転移していきなり追放されるが、じつは最強魔法使い。可愛い看板娘がいる宿屋に拾われたのでもう戻りません
下昴しん
ファンタジー
高校生のタクトは部活帰りに突然異世界へ転移してしまう。
横柄な態度の王から、魔法使いはいらんわ、城から出ていけと言われ、いきなり無職になったタクト。
偶然会った宿屋の店長トロに仕事をもらい、看板娘のマロンと一緒に宿と食堂を手伝うことに。
すると突然、客の兵士が暴れだし宿はメチャクチャになる。
兵士に殴り飛ばされるトロとマロン。
この世界の魔法は、生活で利用する程度の威力しかなく、とても弱い。
しかし──タクトの魔法は人並み外れて、無法者も脳筋男もひれ伏すほど強かった。

99歳で亡くなり異世界に転生した老人は7歳の子供に生まれ変わり、召喚魔法でドラゴンや前世の世界の物を召喚して世界を変える
ハーフのクロエ
ファンタジー
夫が病気で長期入院したので夫が途中まで書いていた小説を私なりに書き直して完結まで投稿しますので応援よろしくお願いいたします。
主人公は建築会社を55歳で取り締まり役常務をしていたが惜しげもなく早期退職し田舎で大好きな農業をしていた。99歳で亡くなった老人は前世の記憶を持ったまま7歳の少年マリュウスとして異世界の僻地の男爵家に生まれ変わる。10歳の鑑定の儀で、火、水、風、土、木の5大魔法ではなく、この世界で初めての召喚魔法を授かる。最初に召喚出来たのは弱いスライム、モグラ魔獣でマリウスはガッカリしたが優しい家族に見守られ次第に色んな魔獣や地球の、物などを召喚出来るようになり、僻地の男爵家を発展させ気が付けば大陸一豊かで最強の小さい王国を起こしていた。

異世界へ行って帰って来た
バルサック
ファンタジー
ダンジョンの出現した日本で、じいさんの形見となった指輪で異世界へ行ってしまった。
そして帰って来た。2つの世界を往来できる力で様々な体験をする神須勇だった。

ボクが追放されたら飢餓に陥るけど良いですか?
音爽(ネソウ)
ファンタジー
美味しい果実より食えない石ころが欲しいなんて、人間て変わってますね。
役に立たないから出ていけ?
わかりました、緑の加護はゴッソリ持っていきます!
さようなら!
5月4日、ファンタジー1位!HOTランキング1位獲得!!ありがとうございました!
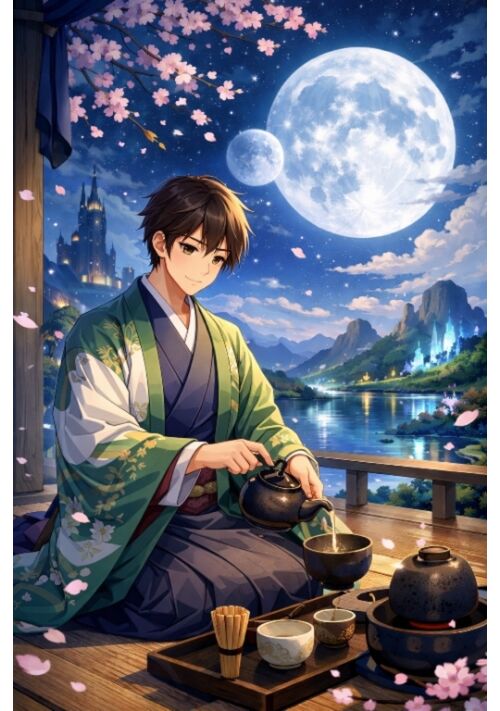
水神飛鳥の異世界茶会記 ~戦闘力ゼロの茶道家が、神業の【陶芸】と至高の【和菓子】で、野蛮な異世界を「癒やし」で侵略するようです~
月神世一
ファンタジー
「剣を下ろし、靴を脱いでください。……茶が入りましたよ」
猫を助けて死んだ茶道家・水神飛鳥(23歳)。
彼が転生したのは、魔法と闘気が支配する弱肉強食のファンタジー世界だった。
チート能力? 攻撃魔法?
いいえ、彼が手にしたのは「茶道具一式」と「陶芸セット」が出せるスキルだけ。
「私がすべき事は、戦うことではありません。一服の茶を出し、心を整えることです」
ゴブリン相手に正座で茶を勧め、
戦場のど真ん中に「結界(茶室)」を展開して空気を変え、
牢屋にぶち込まれれば、そこを「隠れ家カフェ」にリフォームして看守を餌付けする。
そんな彼の振る舞う、異世界には存在しない「極上の甘味(カステラ・羊羹)」と、魔法よりも美しい「茶器」に、武闘派の獣人女王も、強欲な大商人も、次第に心を(胃袋を)掴まれていき……?
「野暮な振る舞いは許しません」
これは、ブレない茶道家が、殺伐とした異世界を「おもてなし」で平和に変えていく、一期一会の物語。

異世界転生したらたくさんスキルもらったけど今まで選ばれなかったものだった~魔王討伐は無理な気がする~
宝者来価
ファンタジー
俺は異世界転生者カドマツ。
転生理由は幼い少女を交通事故からかばったこと。
良いとこなしの日々を送っていたが女神様から異世界に転生すると説明された時にはアニメやゲームのような展開を期待したりもした。
例えばモンスターを倒して国を救いヒロインと結ばれるなど。
けれど与えられた【今まで選ばれなかったスキルが使える】 戦闘はおろか日常の役にも立つ気がしない余りものばかり。
同じ転生者でイケメン王子のレイニーに出迎えられ歓迎される。
彼は【スキル:水】を使う最強で理想的な異世界転生者に思えたのだが―――!?
※小説家になろう様にも掲載しています。

スーパーの店長・結城偉介 〜異世界でスーパーの売れ残りを在庫処分〜
かの
ファンタジー
世界一周旅行を夢見てコツコツ貯金してきたスーパーの店長、結城偉介32歳。
スーパーのバックヤードで、うたた寝をしていた偉介は、何故か異世界に転移してしまう。
偉介が転移したのは、スーパーでバイトするハル君こと、青柳ハル26歳が書いたファンタジー小説の世界の中。
スーパーの過剰商品(売れ残り)を捌きながら、微妙にズレた世界線で、偉介の異世界一周旅行が始まる!
冒険者じゃない! 勇者じゃない! 俺は商人だーーー! だからハル君、お願い! 俺を戦わせないでください!

セーブポイント転生 ~寿命が無い石なので千年修行したらレベル上限突破してしまった~
空色蜻蛉
ファンタジー
枢は目覚めるとクリスタルの中で魂だけの状態になっていた。どうやらダンジョンのセーブポイントに転生してしまったらしい。身動きできない状態に悲嘆に暮れた枢だが、やがて開き直ってレベルアップ作業に明け暮れることにした。百年経ち、二百年経ち……やがて国の礎である「聖なるクリスタル」として崇められるまでになる。
もう元の世界に戻れないと腹をくくって自分の国を見守る枢だが、千年経った時、衝撃のどんでん返しが待ち受けていて……。
【お知らせ】6/22 完結しました!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















