54 / 56
第54話:九尾の大精霊ラム ― 世界樹の揺らぎを観測する者
第54話:九尾の大精霊ラム ― 世界樹の揺らぎを観測する者
しおりを挟む
夜は、沈むのではなく――溶ける。
静けさが押し寄せるのではなく、世界そのものが、自らの輪郭を溶かし始める。
空気は冷たく澄み、月光は銀の刃ではなく、銀の糸――いや、銀の呼吸そのものとなって、森の肌を滑り、木の幹を這い、苔の隙間を縫って、地の奥へと沈んでいく。
風は止まっているのではない。
風が、そもそも「存在する」という前提を、この夜だけは、一時的に忘れているのだ。
虫も、鳥も、獣も、根も、葉も、石も、川も、すべてが、ひとつの巨大な息の間――つまり、世界の肺が膨らむ前の、その一瞬の空白に、身を委ねている。
その沈黙は、音の欠如ではない。
それは、世界の根が、深く、深く、地の底で、何かを待つように、あるいは、何かを思い出すように、ひそやかに、しかし確かに、脈動を止めた瞬間だった。
――世界が、息を呑んだ。
その刹那、遠く、地平の果てにそびえる世界樹の頂で、一枚の葉が、銀から黒へと、淡く、確実に、色を変えて揺れた。
音はなかった。
光は歪まなかった。
空気は震えなかった。
ただ、世界の根が、ひそやかに震えた。
その震えを、誰よりも早く、誰よりも深く、誰よりも静かに感じ取ったのは――九尾の大精霊、ラムであった。
彼女はログハウスのテラスに座っていた。
銀狐――その名に偽りなく、全身を覆う毛並みは、月光を吸い込む銀の絹のようで、微風さえも感じさせぬほどに静かに、空気と同化していた。
九本の尾は、地に広がり、まるで世界樹の根が地を這うように、柔らかく、深く、夜の闇に溶け込んでいた。
その一本一本の尾の先には、微かな光の粒が浮かび、まるで星の断片が落ちたかのようだった。
目は閉じられていた。
だが、彼女の視界は、閉じられてなどいなかった。
彼女の瞳は、閉じたまま、世界の奥底を映していた。
ラムは眠らない。
眠りとは、弱き肉体が世界との境界を保つための術にすぎない。
彼女の肉体は、精霊の形を借りた世界の延長であり、その魂は、世界樹の根が張る地脈そのものと共振している。
彼女の呼吸は、世界の律動とひとつになり、彼女の鼓動は、地の奥で脈打つ世界の鼓動と、完全に同調していた。
だからこそ――世界樹の葉が一枚、銀から黒へと色を変えるだけの、目に見えぬ揺らぎを、彼女は、まるで自らの指先が震えたかのように、瞬時に理解した。
風もないのに、九本の尾がふわりと揺れた。
それは驚きではない。反射でもない。
世界樹の葉が揺れたという事実が、地脈を伝い、根を伝い、尾の先端にまで、静かに、確実に、届いただけのこと。
ラムは、ゆるやかに目を開く。
その瞳は、深い碧から、淡い銀へと、静かに色を変えた。
それは、瞳の色が変わるというより、瞳の奥に、世界そのものが映り込んだ瞬間だった。
その瞳は、夜の闇を映しながら、闇の奥にあるものを、見通す。
星の裏側、時間の隙間、記憶の底、未来の胎動――すべてが、その瞳の奥で、静かに渦を巻いていた。
「⋯⋯世界樹が、ひとつ⋯⋯息を乱したか」
その声は、低く、澄み、揺るぎない。
古の森が語るような、静かな響きがあった。
だが、その静けさの奥には、世界の根が震える音が、確かに混じっていた。
胸が痛むわけではない。
身体が震えるわけでもない。
ただ――世界の奥底で、名も形も持たぬ影が、眠りの底で身じろぎした気配が、水面に落ちた露のように、静かに、しかし確かに、広がっていく。
その気配は、痛みでも、恐怖でも、警告でもない。
それは、世界が、あるべき「理」に応じて、自らの構造を微かに再編し始めた、その最初の兆候だった。
ラムは、九本の尾をわずかに揺らし、その波紋を丁寧に感じ取った。
尾の一本一本が、まるで世界樹の枝葉のように、世界の揺らぎを拾い上げる。
その感覚は、視覚でも聴覚でも触覚でもない。
それは、世界の「律動」を、自らの存在そのもので読み取る、精霊の知覚だった。
世界樹は、世界の中心であり、世界の記憶であり、世界の根である。
その葉が揺れるということは、世界そのものが、何かを感じ取ったということ。
世界樹は、単なる樹ではない。
それは、世界の記録装置であり、世界の神経系であり、世界の魂の地図そのものだ。
葉が銀から黒へと色を変える――それは、世界の記憶が、新たな「光」を記録し始めた瞬間。
そして、光が生まれるとき、影は、必ず、その光の裏側で、最初の胎動を始める。
ラムは静かに息を吸う。
その息は、夜の空気を震わせることなく、ただ世界の深みに沈んでいく。
彼女の肺は、空気を吸うのではなく、世界の律動を吸い込む。
その息は、地脈を伝い、世界樹の根へと流れ、葉へと昇り、そして、再び、銀から黒へと色を変える葉の先端に、静かに届いた。
「⋯⋯光が生まれたのだ。影がざわめくは、理として当然のこと⋯⋯」
その声には、恐れも焦りもない。
ただ、世界の理を知る者の静かな受容だけがあった。
彼女は、光と影の誕生を、まるで季節の移ろいを見るかのように、静かに見守っていた。
ラムは夜空を仰ぐ。
星々は静かに瞬いている。
だが、その中のひとつが――ほんの一瞬だけ、黒く揺らいだ。
星は嘘をつかない。
星は世界の記憶を映し、世界の未来を示す。
その星が黒く揺らぐということは、世界のどこかで、まだ名も形も持たぬ“影”が、光の誕生に応じて、わずかに身を起こしたということ。
「⋯⋯光の誕生に、よく応じたものだ。まだ深き眠りの底にあるはずだが⋯⋯」
九本の尾が、月光を受けて銀の波を描く。
その揺れは、世界樹の葉が風に応えるような、静かで深い律動だった。
だが、その律動は、単なる反応ではない。
それは、ラムが、世界の揺らぎを、自らの存在で「受容」し、「翻訳」し、「記録」しようとしている、精霊の儀式だった。
すると――リオの胸の紋様が、微かに脈打つ気配が、静かに伝わってきた。
それは、星の守護者の末裔としての血が、世界の揺らぎに応じた証。
その肉体の奥に、星の守護者という血が、静かに、しかし確実に、脈打っていた。
彼の血は、世界樹の根と、直接つながっている。
だから、世界樹が息を乱せば、彼の血も、自然と、その律動に応じる。
血は嘘をつかない。
血は記憶を宿し、力を宿し、理を宿す。
リオの血が揺らぎに応じたということは、世界の揺らぎが、彼の存在そのものに触れたということ。
つまり、彼は、単なる「世界の住人」ではなく、「世界の一部」であるという、最も根源的な証明だった。
「⋯⋯リオ。その身が揺らぎに応じたか」
さらに、アレンの魂の奥が震える気配も、静かに届く。
アレンは、かつての星の守護者――その魂は、リオの血よりも古く、リオの記憶よりも深く、リオの肉体よりも、世界と密接に結びついていた。
アレンは今、人間としてこの世界に生きている。
だが、その魂の最も深い層だけは、いまだ星の記憶の海と繋がっていた。
肉体は地上にありながら、魂の根だけが世界の外側に触れている――。
それが、かつて星の守護者であった者の特異性だった。
だが、その魂の奥が震えるということは、世界の根が、彼の魂に、直接、触れたということ。
魂は血より深く、血より古く、血より強い。
アレンの魂が揺らぎに応じたということは、世界の根が、彼の魂に触れたということ。
「⋯⋯アレンもか。星の守護者の魂は⋯⋯やはり敏いな」
ラムは静かに立ち上がる。
九本の尾がゆるやかに広がり、月光を受けて淡く輝く。
その姿は、夜の闇に浮かぶ銀の炎のようであり、世界樹の化身が歩み出したかのような神秘を帯びていた。
彼女の銀色の毛並みは、月光を吸い込み、その光を、まるで世界樹の葉が光を蓄えるかのように、静かに、深く、体内に取り込んでいた。
ラムは世界樹の方角へと、深く一礼する。
その礼は、敬意でも、畏怖でも、祈りでもない。
それは、世界の理を認め、その理に従うという、精霊としての、最も根源的な誓いだった。
「影よ。来るならば来るがよい。この世界には⋯⋯こやつらが在る」
その声は静かでありながら、世界の根にまで届くような深さを持っていた。
声の波動は、空気を震わせることなく、地脈を伝い、世界樹の根へと流れ、葉へと昇り、そして、世界の果てまで、静かに響いた。
「光の子、星の守護者、そして⋯⋯シュウ。この家族が在る限り⋯⋯世界は闇に呑まれはせぬ」
シュウ――その名を口にした瞬間、ラムの九本の尾のうち、一本が、微かに赤く光った。
それは、世界樹の葉が銀から黒へと色を変えるのとは、まったく異なる光。
それは、炎の色ではなく、血の色でもなく、ただ、一つの「誓い」の色だった。
九本の尾が、夜風のない空気の中で、ひとりでに揺れた。
その揺れは、世界樹の葉が応えるように、遠くで微かに響いた。
それは、世界が、ラムの言葉に、静かに応えた証だった。
ラムは再び月を仰ぎ、静かに目を閉じた。
夜は何事もなかったかのように、再び深い静寂を取り戻す。
だが――世界の奥底では、確かに何かが動き始めていた。
それはまだ、名も形も持たぬ影。
ただの揺らぎ、ただの寝返り。
しかし、世界樹が息を乱すほどの存在。
ラムはその気配を、静かに、深く、受け止めていた。
まるで、“世界の夜明け前に立つ唯一の観測者”であるかのように。
――だが、その観測者は、ただの観測者ではなかった。
彼女は、世界の律動を読み取る者であり、世界の揺らぎを受容する者であり、世界の理を記録する者であり、そして、世界の光を守るための、最初の「門」だった。
その門の向こうには、まだ眠るリオの胸の紋様があり、星の記憶の海に浮かぶアレンの魂があり、世界樹の根に刻まれたシュウの誓いがあった。
そして、その門の向こうには、もう一人の存在が、静かに、しかし確実に、動き始めていた。
世界の夜明けは、まだ遠い。
だが、その夜明けを告げる、最初の光は、すでに、世界樹の葉の裏側で、静かに、しかし確実に、生まれていた。
ラムは、再び目を開けた。
その瞳は、銀から、ほんのわずかに、赤みを帯びていた。
それは、世界の闇を知る者の瞳であり、世界の光を守る者の瞳であり、そして、世界の夜明けを、静かに、しかし確実に、待つ者の瞳だった。
「⋯⋯光の子よ。星の守護者よ。そして、シュウの子よ。
お前たちが、この世界に在る限り――私は、この世界の夜明けを、静かに、しかし確実に、見届ける」
その声は、夜の闇に溶け、地脈を伝い、世界樹の根へと流れ、葉へと昇り、そして、世界の果てまで、静かに、しかし確実に、届いた。
世界は、再び静寂を取り戻した。
だが、その静寂は、もはや、ただの沈黙ではなかった。
それは、世界が、静かに、しかし確実に、目覚めようとしている、その一瞬の、息を呑んだ瞬間だった。
――世界の夜明けは、まだ来ない。
だが、その夜明けを告げる、最初の光は、すでに、世界樹の葉の裏側で、静かに、しかし確実に、生まれていた。
そして、その光を、世界の奥底で、ただ一人、静かに、しかし確実に、見守っていたのは――
九尾の大精霊、ラムだった。
銀狐の姿で、碧い眼で、九本の尾を広げ、世界の根を見上げていた、世界の夜明け前に立つ、唯一の観測者。
彼女の銀色の毛並みは、月光を吸い込み、その光を、世界樹の葉が光を蓄えるかのように、静かに、深く、体内に取り込んでいた。
その光は、やがて、リオの胸の紋様を照らし、アレンの魂を呼び覚まし、シュウの誓いを、再び世界樹の葉に刻もうとしていた。
世界の夜明けは、まだ来ない。
だが、その夜明けを告げる、最初の光は、すでに、世界樹の葉の裏側で、静かに、しかし確実に、生まれていた。
ラムは、静かにその揺らぎを受け止めた。
――夜明けはまだ遠い。だが、必ず来る。
その時まで、私は見届けよう。
静けさが押し寄せるのではなく、世界そのものが、自らの輪郭を溶かし始める。
空気は冷たく澄み、月光は銀の刃ではなく、銀の糸――いや、銀の呼吸そのものとなって、森の肌を滑り、木の幹を這い、苔の隙間を縫って、地の奥へと沈んでいく。
風は止まっているのではない。
風が、そもそも「存在する」という前提を、この夜だけは、一時的に忘れているのだ。
虫も、鳥も、獣も、根も、葉も、石も、川も、すべてが、ひとつの巨大な息の間――つまり、世界の肺が膨らむ前の、その一瞬の空白に、身を委ねている。
その沈黙は、音の欠如ではない。
それは、世界の根が、深く、深く、地の底で、何かを待つように、あるいは、何かを思い出すように、ひそやかに、しかし確かに、脈動を止めた瞬間だった。
――世界が、息を呑んだ。
その刹那、遠く、地平の果てにそびえる世界樹の頂で、一枚の葉が、銀から黒へと、淡く、確実に、色を変えて揺れた。
音はなかった。
光は歪まなかった。
空気は震えなかった。
ただ、世界の根が、ひそやかに震えた。
その震えを、誰よりも早く、誰よりも深く、誰よりも静かに感じ取ったのは――九尾の大精霊、ラムであった。
彼女はログハウスのテラスに座っていた。
銀狐――その名に偽りなく、全身を覆う毛並みは、月光を吸い込む銀の絹のようで、微風さえも感じさせぬほどに静かに、空気と同化していた。
九本の尾は、地に広がり、まるで世界樹の根が地を這うように、柔らかく、深く、夜の闇に溶け込んでいた。
その一本一本の尾の先には、微かな光の粒が浮かび、まるで星の断片が落ちたかのようだった。
目は閉じられていた。
だが、彼女の視界は、閉じられてなどいなかった。
彼女の瞳は、閉じたまま、世界の奥底を映していた。
ラムは眠らない。
眠りとは、弱き肉体が世界との境界を保つための術にすぎない。
彼女の肉体は、精霊の形を借りた世界の延長であり、その魂は、世界樹の根が張る地脈そのものと共振している。
彼女の呼吸は、世界の律動とひとつになり、彼女の鼓動は、地の奥で脈打つ世界の鼓動と、完全に同調していた。
だからこそ――世界樹の葉が一枚、銀から黒へと色を変えるだけの、目に見えぬ揺らぎを、彼女は、まるで自らの指先が震えたかのように、瞬時に理解した。
風もないのに、九本の尾がふわりと揺れた。
それは驚きではない。反射でもない。
世界樹の葉が揺れたという事実が、地脈を伝い、根を伝い、尾の先端にまで、静かに、確実に、届いただけのこと。
ラムは、ゆるやかに目を開く。
その瞳は、深い碧から、淡い銀へと、静かに色を変えた。
それは、瞳の色が変わるというより、瞳の奥に、世界そのものが映り込んだ瞬間だった。
その瞳は、夜の闇を映しながら、闇の奥にあるものを、見通す。
星の裏側、時間の隙間、記憶の底、未来の胎動――すべてが、その瞳の奥で、静かに渦を巻いていた。
「⋯⋯世界樹が、ひとつ⋯⋯息を乱したか」
その声は、低く、澄み、揺るぎない。
古の森が語るような、静かな響きがあった。
だが、その静けさの奥には、世界の根が震える音が、確かに混じっていた。
胸が痛むわけではない。
身体が震えるわけでもない。
ただ――世界の奥底で、名も形も持たぬ影が、眠りの底で身じろぎした気配が、水面に落ちた露のように、静かに、しかし確かに、広がっていく。
その気配は、痛みでも、恐怖でも、警告でもない。
それは、世界が、あるべき「理」に応じて、自らの構造を微かに再編し始めた、その最初の兆候だった。
ラムは、九本の尾をわずかに揺らし、その波紋を丁寧に感じ取った。
尾の一本一本が、まるで世界樹の枝葉のように、世界の揺らぎを拾い上げる。
その感覚は、視覚でも聴覚でも触覚でもない。
それは、世界の「律動」を、自らの存在そのもので読み取る、精霊の知覚だった。
世界樹は、世界の中心であり、世界の記憶であり、世界の根である。
その葉が揺れるということは、世界そのものが、何かを感じ取ったということ。
世界樹は、単なる樹ではない。
それは、世界の記録装置であり、世界の神経系であり、世界の魂の地図そのものだ。
葉が銀から黒へと色を変える――それは、世界の記憶が、新たな「光」を記録し始めた瞬間。
そして、光が生まれるとき、影は、必ず、その光の裏側で、最初の胎動を始める。
ラムは静かに息を吸う。
その息は、夜の空気を震わせることなく、ただ世界の深みに沈んでいく。
彼女の肺は、空気を吸うのではなく、世界の律動を吸い込む。
その息は、地脈を伝い、世界樹の根へと流れ、葉へと昇り、そして、再び、銀から黒へと色を変える葉の先端に、静かに届いた。
「⋯⋯光が生まれたのだ。影がざわめくは、理として当然のこと⋯⋯」
その声には、恐れも焦りもない。
ただ、世界の理を知る者の静かな受容だけがあった。
彼女は、光と影の誕生を、まるで季節の移ろいを見るかのように、静かに見守っていた。
ラムは夜空を仰ぐ。
星々は静かに瞬いている。
だが、その中のひとつが――ほんの一瞬だけ、黒く揺らいだ。
星は嘘をつかない。
星は世界の記憶を映し、世界の未来を示す。
その星が黒く揺らぐということは、世界のどこかで、まだ名も形も持たぬ“影”が、光の誕生に応じて、わずかに身を起こしたということ。
「⋯⋯光の誕生に、よく応じたものだ。まだ深き眠りの底にあるはずだが⋯⋯」
九本の尾が、月光を受けて銀の波を描く。
その揺れは、世界樹の葉が風に応えるような、静かで深い律動だった。
だが、その律動は、単なる反応ではない。
それは、ラムが、世界の揺らぎを、自らの存在で「受容」し、「翻訳」し、「記録」しようとしている、精霊の儀式だった。
すると――リオの胸の紋様が、微かに脈打つ気配が、静かに伝わってきた。
それは、星の守護者の末裔としての血が、世界の揺らぎに応じた証。
その肉体の奥に、星の守護者という血が、静かに、しかし確実に、脈打っていた。
彼の血は、世界樹の根と、直接つながっている。
だから、世界樹が息を乱せば、彼の血も、自然と、その律動に応じる。
血は嘘をつかない。
血は記憶を宿し、力を宿し、理を宿す。
リオの血が揺らぎに応じたということは、世界の揺らぎが、彼の存在そのものに触れたということ。
つまり、彼は、単なる「世界の住人」ではなく、「世界の一部」であるという、最も根源的な証明だった。
「⋯⋯リオ。その身が揺らぎに応じたか」
さらに、アレンの魂の奥が震える気配も、静かに届く。
アレンは、かつての星の守護者――その魂は、リオの血よりも古く、リオの記憶よりも深く、リオの肉体よりも、世界と密接に結びついていた。
アレンは今、人間としてこの世界に生きている。
だが、その魂の最も深い層だけは、いまだ星の記憶の海と繋がっていた。
肉体は地上にありながら、魂の根だけが世界の外側に触れている――。
それが、かつて星の守護者であった者の特異性だった。
だが、その魂の奥が震えるということは、世界の根が、彼の魂に、直接、触れたということ。
魂は血より深く、血より古く、血より強い。
アレンの魂が揺らぎに応じたということは、世界の根が、彼の魂に触れたということ。
「⋯⋯アレンもか。星の守護者の魂は⋯⋯やはり敏いな」
ラムは静かに立ち上がる。
九本の尾がゆるやかに広がり、月光を受けて淡く輝く。
その姿は、夜の闇に浮かぶ銀の炎のようであり、世界樹の化身が歩み出したかのような神秘を帯びていた。
彼女の銀色の毛並みは、月光を吸い込み、その光を、まるで世界樹の葉が光を蓄えるかのように、静かに、深く、体内に取り込んでいた。
ラムは世界樹の方角へと、深く一礼する。
その礼は、敬意でも、畏怖でも、祈りでもない。
それは、世界の理を認め、その理に従うという、精霊としての、最も根源的な誓いだった。
「影よ。来るならば来るがよい。この世界には⋯⋯こやつらが在る」
その声は静かでありながら、世界の根にまで届くような深さを持っていた。
声の波動は、空気を震わせることなく、地脈を伝い、世界樹の根へと流れ、葉へと昇り、そして、世界の果てまで、静かに響いた。
「光の子、星の守護者、そして⋯⋯シュウ。この家族が在る限り⋯⋯世界は闇に呑まれはせぬ」
シュウ――その名を口にした瞬間、ラムの九本の尾のうち、一本が、微かに赤く光った。
それは、世界樹の葉が銀から黒へと色を変えるのとは、まったく異なる光。
それは、炎の色ではなく、血の色でもなく、ただ、一つの「誓い」の色だった。
九本の尾が、夜風のない空気の中で、ひとりでに揺れた。
その揺れは、世界樹の葉が応えるように、遠くで微かに響いた。
それは、世界が、ラムの言葉に、静かに応えた証だった。
ラムは再び月を仰ぎ、静かに目を閉じた。
夜は何事もなかったかのように、再び深い静寂を取り戻す。
だが――世界の奥底では、確かに何かが動き始めていた。
それはまだ、名も形も持たぬ影。
ただの揺らぎ、ただの寝返り。
しかし、世界樹が息を乱すほどの存在。
ラムはその気配を、静かに、深く、受け止めていた。
まるで、“世界の夜明け前に立つ唯一の観測者”であるかのように。
――だが、その観測者は、ただの観測者ではなかった。
彼女は、世界の律動を読み取る者であり、世界の揺らぎを受容する者であり、世界の理を記録する者であり、そして、世界の光を守るための、最初の「門」だった。
その門の向こうには、まだ眠るリオの胸の紋様があり、星の記憶の海に浮かぶアレンの魂があり、世界樹の根に刻まれたシュウの誓いがあった。
そして、その門の向こうには、もう一人の存在が、静かに、しかし確実に、動き始めていた。
世界の夜明けは、まだ遠い。
だが、その夜明けを告げる、最初の光は、すでに、世界樹の葉の裏側で、静かに、しかし確実に、生まれていた。
ラムは、再び目を開けた。
その瞳は、銀から、ほんのわずかに、赤みを帯びていた。
それは、世界の闇を知る者の瞳であり、世界の光を守る者の瞳であり、そして、世界の夜明けを、静かに、しかし確実に、待つ者の瞳だった。
「⋯⋯光の子よ。星の守護者よ。そして、シュウの子よ。
お前たちが、この世界に在る限り――私は、この世界の夜明けを、静かに、しかし確実に、見届ける」
その声は、夜の闇に溶け、地脈を伝い、世界樹の根へと流れ、葉へと昇り、そして、世界の果てまで、静かに、しかし確実に、届いた。
世界は、再び静寂を取り戻した。
だが、その静寂は、もはや、ただの沈黙ではなかった。
それは、世界が、静かに、しかし確実に、目覚めようとしている、その一瞬の、息を呑んだ瞬間だった。
――世界の夜明けは、まだ来ない。
だが、その夜明けを告げる、最初の光は、すでに、世界樹の葉の裏側で、静かに、しかし確実に、生まれていた。
そして、その光を、世界の奥底で、ただ一人、静かに、しかし確実に、見守っていたのは――
九尾の大精霊、ラムだった。
銀狐の姿で、碧い眼で、九本の尾を広げ、世界の根を見上げていた、世界の夜明け前に立つ、唯一の観測者。
彼女の銀色の毛並みは、月光を吸い込み、その光を、世界樹の葉が光を蓄えるかのように、静かに、深く、体内に取り込んでいた。
その光は、やがて、リオの胸の紋様を照らし、アレンの魂を呼び覚まし、シュウの誓いを、再び世界樹の葉に刻もうとしていた。
世界の夜明けは、まだ来ない。
だが、その夜明けを告げる、最初の光は、すでに、世界樹の葉の裏側で、静かに、しかし確実に、生まれていた。
ラムは、静かにその揺らぎを受け止めた。
――夜明けはまだ遠い。だが、必ず来る。
その時まで、私は見届けよう。
0
あなたにおすすめの小説

高校生の俺、異世界転移していきなり追放されるが、じつは最強魔法使い。可愛い看板娘がいる宿屋に拾われたのでもう戻りません
下昴しん
ファンタジー
高校生のタクトは部活帰りに突然異世界へ転移してしまう。
横柄な態度の王から、魔法使いはいらんわ、城から出ていけと言われ、いきなり無職になったタクト。
偶然会った宿屋の店長トロに仕事をもらい、看板娘のマロンと一緒に宿と食堂を手伝うことに。
すると突然、客の兵士が暴れだし宿はメチャクチャになる。
兵士に殴り飛ばされるトロとマロン。
この世界の魔法は、生活で利用する程度の威力しかなく、とても弱い。
しかし──タクトの魔法は人並み外れて、無法者も脳筋男もひれ伏すほど強かった。

99歳で亡くなり異世界に転生した老人は7歳の子供に生まれ変わり、召喚魔法でドラゴンや前世の世界の物を召喚して世界を変える
ハーフのクロエ
ファンタジー
夫が病気で長期入院したので夫が途中まで書いていた小説を私なりに書き直して完結まで投稿しますので応援よろしくお願いいたします。
主人公は建築会社を55歳で取り締まり役常務をしていたが惜しげもなく早期退職し田舎で大好きな農業をしていた。99歳で亡くなった老人は前世の記憶を持ったまま7歳の少年マリュウスとして異世界の僻地の男爵家に生まれ変わる。10歳の鑑定の儀で、火、水、風、土、木の5大魔法ではなく、この世界で初めての召喚魔法を授かる。最初に召喚出来たのは弱いスライム、モグラ魔獣でマリウスはガッカリしたが優しい家族に見守られ次第に色んな魔獣や地球の、物などを召喚出来るようになり、僻地の男爵家を発展させ気が付けば大陸一豊かで最強の小さい王国を起こしていた。

異世界へ行って帰って来た
バルサック
ファンタジー
ダンジョンの出現した日本で、じいさんの形見となった指輪で異世界へ行ってしまった。
そして帰って来た。2つの世界を往来できる力で様々な体験をする神須勇だった。

ボクが追放されたら飢餓に陥るけど良いですか?
音爽(ネソウ)
ファンタジー
美味しい果実より食えない石ころが欲しいなんて、人間て変わってますね。
役に立たないから出ていけ?
わかりました、緑の加護はゴッソリ持っていきます!
さようなら!
5月4日、ファンタジー1位!HOTランキング1位獲得!!ありがとうございました!
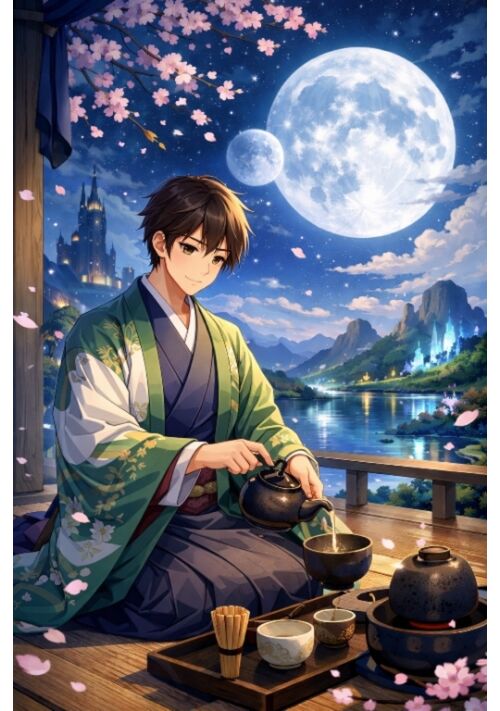
水神飛鳥の異世界茶会記 ~戦闘力ゼロの茶道家が、神業の【陶芸】と至高の【和菓子】で、野蛮な異世界を「癒やし」で侵略するようです~
月神世一
ファンタジー
「剣を下ろし、靴を脱いでください。……茶が入りましたよ」
猫を助けて死んだ茶道家・水神飛鳥(23歳)。
彼が転生したのは、魔法と闘気が支配する弱肉強食のファンタジー世界だった。
チート能力? 攻撃魔法?
いいえ、彼が手にしたのは「茶道具一式」と「陶芸セット」が出せるスキルだけ。
「私がすべき事は、戦うことではありません。一服の茶を出し、心を整えることです」
ゴブリン相手に正座で茶を勧め、
戦場のど真ん中に「結界(茶室)」を展開して空気を変え、
牢屋にぶち込まれれば、そこを「隠れ家カフェ」にリフォームして看守を餌付けする。
そんな彼の振る舞う、異世界には存在しない「極上の甘味(カステラ・羊羹)」と、魔法よりも美しい「茶器」に、武闘派の獣人女王も、強欲な大商人も、次第に心を(胃袋を)掴まれていき……?
「野暮な振る舞いは許しません」
これは、ブレない茶道家が、殺伐とした異世界を「おもてなし」で平和に変えていく、一期一会の物語。

異世界転生したらたくさんスキルもらったけど今まで選ばれなかったものだった~魔王討伐は無理な気がする~
宝者来価
ファンタジー
俺は異世界転生者カドマツ。
転生理由は幼い少女を交通事故からかばったこと。
良いとこなしの日々を送っていたが女神様から異世界に転生すると説明された時にはアニメやゲームのような展開を期待したりもした。
例えばモンスターを倒して国を救いヒロインと結ばれるなど。
けれど与えられた【今まで選ばれなかったスキルが使える】 戦闘はおろか日常の役にも立つ気がしない余りものばかり。
同じ転生者でイケメン王子のレイニーに出迎えられ歓迎される。
彼は【スキル:水】を使う最強で理想的な異世界転生者に思えたのだが―――!?
※小説家になろう様にも掲載しています。

スーパーの店長・結城偉介 〜異世界でスーパーの売れ残りを在庫処分〜
かの
ファンタジー
世界一周旅行を夢見てコツコツ貯金してきたスーパーの店長、結城偉介32歳。
スーパーのバックヤードで、うたた寝をしていた偉介は、何故か異世界に転移してしまう。
偉介が転移したのは、スーパーでバイトするハル君こと、青柳ハル26歳が書いたファンタジー小説の世界の中。
スーパーの過剰商品(売れ残り)を捌きながら、微妙にズレた世界線で、偉介の異世界一周旅行が始まる!
冒険者じゃない! 勇者じゃない! 俺は商人だーーー! だからハル君、お願い! 俺を戦わせないでください!

セーブポイント転生 ~寿命が無い石なので千年修行したらレベル上限突破してしまった~
空色蜻蛉
ファンタジー
枢は目覚めるとクリスタルの中で魂だけの状態になっていた。どうやらダンジョンのセーブポイントに転生してしまったらしい。身動きできない状態に悲嘆に暮れた枢だが、やがて開き直ってレベルアップ作業に明け暮れることにした。百年経ち、二百年経ち……やがて国の礎である「聖なるクリスタル」として崇められるまでになる。
もう元の世界に戻れないと腹をくくって自分の国を見守る枢だが、千年経った時、衝撃のどんでん返しが待ち受けていて……。
【お知らせ】6/22 完結しました!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















