55 / 90
第三章 領主夫人、王都へと出向く
12.それは希望か絶望か
しおりを挟む
「…アオイ、アオイ、起きてください。」
「…んー…」
名前を呼ばれて、深い眠りから呼び戻される。いつの間に眠っていたのか、今、何時くらいだろう。重い瞼を開けて、声のした方、セルジュへと顔を向ける。
「…おはよう、セルジュ…」
「すみません、こんな時間に。」
「…こんな時間?」
言われて周囲を見回せば、カーテンを引いたままの窓の外は既に十分明るい。それに何より、目の前の彼は既に寝間着を脱いでいるのだから、そう早い時間にも思えないのだけれど。
「…昨夜、あまり眠れなかったのではありませんか…?」
「?」
「出来れば、アオイが目覚めるまで、起こしたくはなかったのですが…」
「あー…」
思い出した。昨夜はセルジュ相手に痴態を晒したあげく、どうやら、そのまま泣きつかれて眠ってしまったらしい。
(…子どもか。)
自分で突っ込んで、笑ってしまう。
「ありがとう、セルジュ。でも、うん、大丈夫みたい。」
笑えることにホッとして、セルジュに尋ねた。
「それで?何かあったの?セルジュが態々起こしに来てくれたってことは…?」
「…それが…」
「?」
「王太子殿下より、呼び出しがありました。」
「え?」
呼び出された王太子の執務室、一歩その場に足を踏み入れた瞬間に、場の異様な雰囲気に動揺した。昨日の今日、しかも、夜会開け。本来なら、王都に住む人間の一日が始まるのなんて、それこそ、午後も遅い時間になってからのはずなのに。居並ぶのはいつものメンバー、それから─
「こんな時間に呼び出してすまない、アンブロス卿、巫女。応じてくれて、感謝する。」
「いえ。殿下のお呼びとあらば…」
頭を下げるセルジュの横、彼に倣って頭を下げた。そのままチラリと部屋の奥へと視線を流す。
(…なんで、この男がここに…?)
昨夜、顔を突き合わせてしまったばかりの男、アンバー・フォーリーンがその場に居るだけでも不穏なのに、アンバーの放つ異様な空気が、こちらを余計に落ち着かない気分にさせる。
(なに?怒ってるの…?)
表情が抜け落ちたかのよう男の顔、ただ、目だけは異様なほどにギラついていて、しかも、よく見れば、身に着けている服は昨夜の夜会で目にしたものと同じ─
「…座ってくれ。」
着席を促す王太子の言葉に従い、昨日と同じく、セルジュと二人、並んでソファに腰を下ろす。
「…巫女。」
王太子の呼びかけに視線を向ける。
「君にいくつか尋ねたいことがある。そのために、君をここに呼んだ。」
「私…?」
目的が私、セルジュはその付き添いなのだと示す王太子の言葉にますます嫌な予感しかしない。
「単刀直入に聞くが、先ずは、そうだな、…君は、クリューガー伯爵令嬢の居場所に心当たりはあるか?」
「え…?」
問われた質問の意味が分からずに、一瞬、混乱する。
(クリューガー伯爵令嬢?…それって、あの男の…?)
思わず向けた視線の先、険しい眼差しの男と目が合った。
「…無駄ですよ、殿下。この女がティアの行方を知るはずがない。ティアは、彼女は…!」
「…落ち着け、アンバー。…一応の確認だ。…まだ、お前の推論が正しいと決まったわけではない。」
「ハッ!冗談でしょうっ!?この僕が間違っているとでも!?こんな無駄な時間に付き合わすくらいなら、さっさと僕を解放してください!」
「待て。落ち着け。…お前の推論が正しいのだとしても、巫女の持つ情報は必要だ。違うか?」
「っ!?」
(…なに?)
訳が分からない。アンバー・フォーリーンの激昂も、殿下に諭された後に見せた消沈も、意味が分からずにただ黙って二人のやり取りを眺めれば、殿下の視線が再びこちらを向く。
「…巫女、心して聞いて欲しい。」
「…」
殿下の真剣な眼差しに、沸々とこみ上げてくる恐怖。隣に座るセルジュの手を握った。
「…昨夜、ティアナ・クリューガー嬢が失踪した。」
告げられた言葉、二人のやり取りから薄々感じていたその事実に、声が震える。
「…それが、私に、何の関係が…」
「ああ…。…ティアナ嬢とアンバーは、昨夜…」
セルジュの手が、励ますよう、強く握り返してくる。
「…二人きりで、巫女召喚を行ったそうだ。」
「っ!?」
あり得ない─
(だって、そんな…!)
思考がグルグルする。言葉が出てこない。代わりに、隣から聞こえた声。
「…殿下、巫女召喚は二十四年周期、その決まりを破って召喚が行われたということでしょうか?召喚陣の使用は陛下がお認めになられたのですか?」
「いや、違う。…召喚は、アンバー自らが陣を描いた。…前回の召喚時に見た陣の構成を覚えていたそうだ。」
「それは…」
セルジュの、少し驚いたような声。その声に、それが普通ではないこと、とんでもないことなのだということだけは伝わった。
一拍の間をおいて、セルジュが殿下に尋ねる。
「…それで?その巫女召喚と、クリューガー伯爵令嬢の失踪にどういう関係が?」
「…ここからは、アンバーの言によるものだが…」
前置きして、殿下が重いため息をついた。
「召喚陣の起動自体には成功したそうだ。…陣が発動し、こちらと巫女の世界が繋がった。…ただ、肝心の巫女は喚ばれなかった。」
「っ!」
その言葉に、色んな感情がこみ上げた。その中でも、一番大きなのは安堵。
(良かった…)
自分と同じ思いをする「誰か」が居なくて。
「…その代わり、ではないが…」
続く殿下の言葉に耳を傾ける。
「陣の発動と同時、その場に居合わせたティアナ嬢が忽然と姿を消してしまったらしい…」
「…それって、どういう…?」
「…ここからはアンバーの推論、確定した事実ではない、が…」
「…」
「…ティアナ嬢は巫女の世界に飛ばされてしまった可能性がある。」
「っ!?」
「アオイ…!」
頭を殴られたような衝撃。一瞬、本当に頭が真っ白になった。
(それって、だって、それじゃあ…)
ふらついた体をセルジュに支えられる。言葉を口にしようとして、ただ、それが否定されるのも、肯定されるのも聞きたくなくて躊躇う。
「…セルジュ。」
縋るのは、隣の存在。彼の服の袖を握り締める。
「…殿下。」
隣から聞こえた凪いだ声。
「今の、魔術師長の推論は、巫女召喚の陣は双方向性を持つということ、こちらからアオイの世界へ赴くことが可能だという解釈でよろしいでしょうか?」
「…ああ、そうだ。」
(っ!?嘘!)
そんな、だって─
「っ!帰れないって言ったじゃない!」
一瞬で膨れ上がった熱。怒り、悲しみ、恐怖、あの頃に感じていたもの。
「召喚は一方通行だって!喚ばれた人間は、二度と帰れないんだって!そう言ってたじゃない!」
だから、私は、それを信じて─
「…すまない、巫女。我々も、召喚陣を用いての巫女の帰還については、昨夜、初めてその可能性を認識した。…今まで、決して、巫女を謀っていたわけではない。」
「っ!」
「ただ、今は、その場の状況、アンバーの証言からも、その可能性が一番高いという結論に至っている。…でなければ、ティアナ嬢の失踪は説明のしようがない。」
「…そんな…」
心臓が、五月蠅いくらいに鳴っている。頭がズキズキする。
「…巫女、その前提を踏まえた上で、巫女にいくつか質問したい。」
「…質問?なにを…」
何を言ってるんだろう。この人は。
(…この状況で、私に、質問…?)
嘘をついていたわけではないから、自分たちも知らなかったから、仕方ない。こちらにとっては一大事を、「すまない」の一言で流してしまおうとする男が理解できず、疑問符ばかりが頭を占める。
「…巫女の世界は、その、どういった世界なのだろうか?」
「どうって…」
そんなのもう、こちらに喚ばれた直後に散々─
「ああ、いや、そうだな。聞き方を変えよう。…ティアナ嬢が、真実、巫女の世界に飛ばされていたとして、彼女はどういう境遇に置かれるだろうか?」
「境遇…?」
聞き返す、自分の声が遠い。聞かれているのは─
「っ!殿下!このような無駄な時間、さっさと終わりにして頂きたい!」
「待て、アンバー!」
部屋の奥、突如立ち上がり叫び出した男に視線を向ける。激昂した男の姿が見えてはいるが。
「巫女、頼む!」
(頼む?なにを…?)
王太子の必死な声、だけど、彼が何を求めているのか、頭が理解を拒む。
「…巫女の世界に関して、少しでも情報が欲しい。ティアナ嬢が、彼の地でどのような扱いを受けるか、彼女の身分は保障されるだろうか?身の安全は?」
「…」
この人は、それを聞いてどうするというのだろう。
ここで「保障されない」と答えて、それで?今ここに居る人間に一体何が出来るというのか。
(…でも…)
思い出すのは、昨夜の彼女のまだ幼さの残る姿、それに、彼女を大切に思っているであろうマルステア辺境伯の姿も─
小さく、息をつく。
「…言葉は?」
「言葉?」
「…私がこちらに喚ばれた時、最初から言葉が通じましたよね?召喚陣に翻訳のような魔術が掛かっているとは聞きましたけど、逆は?ティアナさんが向こうの、…日本語を話すことは出来るんですか?」
「それは…」
王太子の視線がアンバー・フォーリーンへと向けられるが、男は顔を歪めるばかり。応えの無いことが答えだと知る。
「…それじゃあ、服は?」
「…服?」
続けた問いに反応したのは、目の前の王太子ではなく、隣のセルジュだった。その反応に、「そう言えば」と思い出す。
「…巫女召喚の詳細って秘匿されてるんだったね。」
「アオイ、服というのは…?」
「…その、召喚魔術って、自分以外は陣を越えられないらしくて…」
「それは、つまり…?」
「うん。…こっちに来た時、私、何も着てなかった。」
「っ!?」
セルジュの息をのむ気配。だけど、私はまだマシ。こちらに来た瞬間、待ち構えていた王太子により羽織らされた服があったし、王太子自身も、こちらを直視することを避けていた。だけど、彼女がもし、あの時の私と同じ状態で、何の助けも望めないとしたら─
「…それも…」
王太子の漏らした声。その小さな音を拾う。
「…アンバーが、ティアナ嬢が異世界へ飛ばされたとしている根拠なのだが…」
「?」
「…召喚陣の側に、服だけが残されていたそうだ。」
「…」
(ああ…)
だったらもう─
ほとんど確定なんじゃないかという言葉は飲み込んだ。そこから、もっと具体的に想像してみる。彼女が、私の元いた世界、日本に飛ばされたとしたら─
「…ティアナさんは、魔術が使えるんですか?」
「いや…」
「…」
だとしたら、日本での彼女は国籍不明、言葉も通じず、身を助ける手段もないということになる。
「…私が元いた国は、管理社会でした。」
「管理社会?」
「はい。…個人の情報、その大元は国が管理しています。一人ひとりに『戸籍』というものが存在し、それが、その人が日本という国の人間であるという保証になります。」
「…では?」
「ティアナさんには戸籍がありませんので、恐らく、別の国から来た不法滞在者という扱いになるんだと思います。」
まさか、彼女が異世界から来たなんて思う人間は居ないだろうから、彼女の容姿からして、そう判断される可能性が高い。ただ、当然ながら、彼女はどの国の国籍も持っていない。
だから、恐らく─
「…彼女が、あちらでまともに生きていくのは難しいかもしれません。」
「っ!?」
「日本では、戸籍がなければ、仕事に就くことさえ難しいんです。」
加えて言葉も常識も通じない世界。例え言葉が通じても、階級制度の無い日本で、彼女の「伯爵令嬢」という立場が保障されるわけもなく、未だ十七、八の若さで一人生きていくのは、きっと難しい。
(…最悪、犯罪に巻き込まれるか、食い物にされるか…)
どう考えても、明るい展望など描けない。ただ一つ、救いがあるとすれば、
「…命を落とす危険だけは、こちらよりよほど少ないと思います。」
「それは…」
「犯罪に巻き込まれる可能性が無いとは言いませんが、多分、殺されるようなことだけは起きないんじゃないかと…」
殺人は犯罪、魔物も居ない世界、命を落とすまでのことは─
「…殿下。」
「…アンバー…」
それまで黙って話を聞いていたアンバー・フォーリーンがフラリと立ち上がった。生気の無い表情、その体がユラリと揺れた気がした。
「…召喚の間への立ち入り許可を。」
「っ!?無理だ!巫女召喚が行えるのは蒼月の夜のみ!今、召喚を行っても、」
「分かっています。陣は起動させません。…ただ、陣の調査許可を頂きたい。」
「それは…」
「…一年後、もう一度、異界への扉を開きます。」
「っ!?」
「…一年…」
「っ!待て、アンバー!」
「…一年で、必ず、ティアを取り戻す…」
言いながら、フラフラと部屋を出ていくアンバー・フォーリーン、その後姿を、何も言えずに見送った。
彼の去った部屋、残された者たちの間に聞こえたため息は、一体、誰のものだったのか。
「…んー…」
名前を呼ばれて、深い眠りから呼び戻される。いつの間に眠っていたのか、今、何時くらいだろう。重い瞼を開けて、声のした方、セルジュへと顔を向ける。
「…おはよう、セルジュ…」
「すみません、こんな時間に。」
「…こんな時間?」
言われて周囲を見回せば、カーテンを引いたままの窓の外は既に十分明るい。それに何より、目の前の彼は既に寝間着を脱いでいるのだから、そう早い時間にも思えないのだけれど。
「…昨夜、あまり眠れなかったのではありませんか…?」
「?」
「出来れば、アオイが目覚めるまで、起こしたくはなかったのですが…」
「あー…」
思い出した。昨夜はセルジュ相手に痴態を晒したあげく、どうやら、そのまま泣きつかれて眠ってしまったらしい。
(…子どもか。)
自分で突っ込んで、笑ってしまう。
「ありがとう、セルジュ。でも、うん、大丈夫みたい。」
笑えることにホッとして、セルジュに尋ねた。
「それで?何かあったの?セルジュが態々起こしに来てくれたってことは…?」
「…それが…」
「?」
「王太子殿下より、呼び出しがありました。」
「え?」
呼び出された王太子の執務室、一歩その場に足を踏み入れた瞬間に、場の異様な雰囲気に動揺した。昨日の今日、しかも、夜会開け。本来なら、王都に住む人間の一日が始まるのなんて、それこそ、午後も遅い時間になってからのはずなのに。居並ぶのはいつものメンバー、それから─
「こんな時間に呼び出してすまない、アンブロス卿、巫女。応じてくれて、感謝する。」
「いえ。殿下のお呼びとあらば…」
頭を下げるセルジュの横、彼に倣って頭を下げた。そのままチラリと部屋の奥へと視線を流す。
(…なんで、この男がここに…?)
昨夜、顔を突き合わせてしまったばかりの男、アンバー・フォーリーンがその場に居るだけでも不穏なのに、アンバーの放つ異様な空気が、こちらを余計に落ち着かない気分にさせる。
(なに?怒ってるの…?)
表情が抜け落ちたかのよう男の顔、ただ、目だけは異様なほどにギラついていて、しかも、よく見れば、身に着けている服は昨夜の夜会で目にしたものと同じ─
「…座ってくれ。」
着席を促す王太子の言葉に従い、昨日と同じく、セルジュと二人、並んでソファに腰を下ろす。
「…巫女。」
王太子の呼びかけに視線を向ける。
「君にいくつか尋ねたいことがある。そのために、君をここに呼んだ。」
「私…?」
目的が私、セルジュはその付き添いなのだと示す王太子の言葉にますます嫌な予感しかしない。
「単刀直入に聞くが、先ずは、そうだな、…君は、クリューガー伯爵令嬢の居場所に心当たりはあるか?」
「え…?」
問われた質問の意味が分からずに、一瞬、混乱する。
(クリューガー伯爵令嬢?…それって、あの男の…?)
思わず向けた視線の先、険しい眼差しの男と目が合った。
「…無駄ですよ、殿下。この女がティアの行方を知るはずがない。ティアは、彼女は…!」
「…落ち着け、アンバー。…一応の確認だ。…まだ、お前の推論が正しいと決まったわけではない。」
「ハッ!冗談でしょうっ!?この僕が間違っているとでも!?こんな無駄な時間に付き合わすくらいなら、さっさと僕を解放してください!」
「待て。落ち着け。…お前の推論が正しいのだとしても、巫女の持つ情報は必要だ。違うか?」
「っ!?」
(…なに?)
訳が分からない。アンバー・フォーリーンの激昂も、殿下に諭された後に見せた消沈も、意味が分からずにただ黙って二人のやり取りを眺めれば、殿下の視線が再びこちらを向く。
「…巫女、心して聞いて欲しい。」
「…」
殿下の真剣な眼差しに、沸々とこみ上げてくる恐怖。隣に座るセルジュの手を握った。
「…昨夜、ティアナ・クリューガー嬢が失踪した。」
告げられた言葉、二人のやり取りから薄々感じていたその事実に、声が震える。
「…それが、私に、何の関係が…」
「ああ…。…ティアナ嬢とアンバーは、昨夜…」
セルジュの手が、励ますよう、強く握り返してくる。
「…二人きりで、巫女召喚を行ったそうだ。」
「っ!?」
あり得ない─
(だって、そんな…!)
思考がグルグルする。言葉が出てこない。代わりに、隣から聞こえた声。
「…殿下、巫女召喚は二十四年周期、その決まりを破って召喚が行われたということでしょうか?召喚陣の使用は陛下がお認めになられたのですか?」
「いや、違う。…召喚は、アンバー自らが陣を描いた。…前回の召喚時に見た陣の構成を覚えていたそうだ。」
「それは…」
セルジュの、少し驚いたような声。その声に、それが普通ではないこと、とんでもないことなのだということだけは伝わった。
一拍の間をおいて、セルジュが殿下に尋ねる。
「…それで?その巫女召喚と、クリューガー伯爵令嬢の失踪にどういう関係が?」
「…ここからは、アンバーの言によるものだが…」
前置きして、殿下が重いため息をついた。
「召喚陣の起動自体には成功したそうだ。…陣が発動し、こちらと巫女の世界が繋がった。…ただ、肝心の巫女は喚ばれなかった。」
「っ!」
その言葉に、色んな感情がこみ上げた。その中でも、一番大きなのは安堵。
(良かった…)
自分と同じ思いをする「誰か」が居なくて。
「…その代わり、ではないが…」
続く殿下の言葉に耳を傾ける。
「陣の発動と同時、その場に居合わせたティアナ嬢が忽然と姿を消してしまったらしい…」
「…それって、どういう…?」
「…ここからはアンバーの推論、確定した事実ではない、が…」
「…」
「…ティアナ嬢は巫女の世界に飛ばされてしまった可能性がある。」
「っ!?」
「アオイ…!」
頭を殴られたような衝撃。一瞬、本当に頭が真っ白になった。
(それって、だって、それじゃあ…)
ふらついた体をセルジュに支えられる。言葉を口にしようとして、ただ、それが否定されるのも、肯定されるのも聞きたくなくて躊躇う。
「…セルジュ。」
縋るのは、隣の存在。彼の服の袖を握り締める。
「…殿下。」
隣から聞こえた凪いだ声。
「今の、魔術師長の推論は、巫女召喚の陣は双方向性を持つということ、こちらからアオイの世界へ赴くことが可能だという解釈でよろしいでしょうか?」
「…ああ、そうだ。」
(っ!?嘘!)
そんな、だって─
「っ!帰れないって言ったじゃない!」
一瞬で膨れ上がった熱。怒り、悲しみ、恐怖、あの頃に感じていたもの。
「召喚は一方通行だって!喚ばれた人間は、二度と帰れないんだって!そう言ってたじゃない!」
だから、私は、それを信じて─
「…すまない、巫女。我々も、召喚陣を用いての巫女の帰還については、昨夜、初めてその可能性を認識した。…今まで、決して、巫女を謀っていたわけではない。」
「っ!」
「ただ、今は、その場の状況、アンバーの証言からも、その可能性が一番高いという結論に至っている。…でなければ、ティアナ嬢の失踪は説明のしようがない。」
「…そんな…」
心臓が、五月蠅いくらいに鳴っている。頭がズキズキする。
「…巫女、その前提を踏まえた上で、巫女にいくつか質問したい。」
「…質問?なにを…」
何を言ってるんだろう。この人は。
(…この状況で、私に、質問…?)
嘘をついていたわけではないから、自分たちも知らなかったから、仕方ない。こちらにとっては一大事を、「すまない」の一言で流してしまおうとする男が理解できず、疑問符ばかりが頭を占める。
「…巫女の世界は、その、どういった世界なのだろうか?」
「どうって…」
そんなのもう、こちらに喚ばれた直後に散々─
「ああ、いや、そうだな。聞き方を変えよう。…ティアナ嬢が、真実、巫女の世界に飛ばされていたとして、彼女はどういう境遇に置かれるだろうか?」
「境遇…?」
聞き返す、自分の声が遠い。聞かれているのは─
「っ!殿下!このような無駄な時間、さっさと終わりにして頂きたい!」
「待て、アンバー!」
部屋の奥、突如立ち上がり叫び出した男に視線を向ける。激昂した男の姿が見えてはいるが。
「巫女、頼む!」
(頼む?なにを…?)
王太子の必死な声、だけど、彼が何を求めているのか、頭が理解を拒む。
「…巫女の世界に関して、少しでも情報が欲しい。ティアナ嬢が、彼の地でどのような扱いを受けるか、彼女の身分は保障されるだろうか?身の安全は?」
「…」
この人は、それを聞いてどうするというのだろう。
ここで「保障されない」と答えて、それで?今ここに居る人間に一体何が出来るというのか。
(…でも…)
思い出すのは、昨夜の彼女のまだ幼さの残る姿、それに、彼女を大切に思っているであろうマルステア辺境伯の姿も─
小さく、息をつく。
「…言葉は?」
「言葉?」
「…私がこちらに喚ばれた時、最初から言葉が通じましたよね?召喚陣に翻訳のような魔術が掛かっているとは聞きましたけど、逆は?ティアナさんが向こうの、…日本語を話すことは出来るんですか?」
「それは…」
王太子の視線がアンバー・フォーリーンへと向けられるが、男は顔を歪めるばかり。応えの無いことが答えだと知る。
「…それじゃあ、服は?」
「…服?」
続けた問いに反応したのは、目の前の王太子ではなく、隣のセルジュだった。その反応に、「そう言えば」と思い出す。
「…巫女召喚の詳細って秘匿されてるんだったね。」
「アオイ、服というのは…?」
「…その、召喚魔術って、自分以外は陣を越えられないらしくて…」
「それは、つまり…?」
「うん。…こっちに来た時、私、何も着てなかった。」
「っ!?」
セルジュの息をのむ気配。だけど、私はまだマシ。こちらに来た瞬間、待ち構えていた王太子により羽織らされた服があったし、王太子自身も、こちらを直視することを避けていた。だけど、彼女がもし、あの時の私と同じ状態で、何の助けも望めないとしたら─
「…それも…」
王太子の漏らした声。その小さな音を拾う。
「…アンバーが、ティアナ嬢が異世界へ飛ばされたとしている根拠なのだが…」
「?」
「…召喚陣の側に、服だけが残されていたそうだ。」
「…」
(ああ…)
だったらもう─
ほとんど確定なんじゃないかという言葉は飲み込んだ。そこから、もっと具体的に想像してみる。彼女が、私の元いた世界、日本に飛ばされたとしたら─
「…ティアナさんは、魔術が使えるんですか?」
「いや…」
「…」
だとしたら、日本での彼女は国籍不明、言葉も通じず、身を助ける手段もないということになる。
「…私が元いた国は、管理社会でした。」
「管理社会?」
「はい。…個人の情報、その大元は国が管理しています。一人ひとりに『戸籍』というものが存在し、それが、その人が日本という国の人間であるという保証になります。」
「…では?」
「ティアナさんには戸籍がありませんので、恐らく、別の国から来た不法滞在者という扱いになるんだと思います。」
まさか、彼女が異世界から来たなんて思う人間は居ないだろうから、彼女の容姿からして、そう判断される可能性が高い。ただ、当然ながら、彼女はどの国の国籍も持っていない。
だから、恐らく─
「…彼女が、あちらでまともに生きていくのは難しいかもしれません。」
「っ!?」
「日本では、戸籍がなければ、仕事に就くことさえ難しいんです。」
加えて言葉も常識も通じない世界。例え言葉が通じても、階級制度の無い日本で、彼女の「伯爵令嬢」という立場が保障されるわけもなく、未だ十七、八の若さで一人生きていくのは、きっと難しい。
(…最悪、犯罪に巻き込まれるか、食い物にされるか…)
どう考えても、明るい展望など描けない。ただ一つ、救いがあるとすれば、
「…命を落とす危険だけは、こちらよりよほど少ないと思います。」
「それは…」
「犯罪に巻き込まれる可能性が無いとは言いませんが、多分、殺されるようなことだけは起きないんじゃないかと…」
殺人は犯罪、魔物も居ない世界、命を落とすまでのことは─
「…殿下。」
「…アンバー…」
それまで黙って話を聞いていたアンバー・フォーリーンがフラリと立ち上がった。生気の無い表情、その体がユラリと揺れた気がした。
「…召喚の間への立ち入り許可を。」
「っ!?無理だ!巫女召喚が行えるのは蒼月の夜のみ!今、召喚を行っても、」
「分かっています。陣は起動させません。…ただ、陣の調査許可を頂きたい。」
「それは…」
「…一年後、もう一度、異界への扉を開きます。」
「っ!?」
「…一年…」
「っ!待て、アンバー!」
「…一年で、必ず、ティアを取り戻す…」
言いながら、フラフラと部屋を出ていくアンバー・フォーリーン、その後姿を、何も言えずに見送った。
彼の去った部屋、残された者たちの間に聞こえたため息は、一体、誰のものだったのか。
102
あなたにおすすめの小説

完結 王族の醜聞がメシウマ過ぎる件
音爽(ネソウ)
恋愛
王太子は言う。
『お前みたいなつまらない女など要らない、だが優秀さはかってやろう。第二妃として存分に働けよ』
『ごめんなさぁい、貴女は私の代わりに公儀をやってねぇ。だってそれしか取り柄がないんだしぃ』
公務のほとんどを丸投げにする宣言をして、正妃になるはずのアンドレイナ・サンドリーニを蹴落とし正妃の座に就いたベネッタ・ルニッチは高笑いした。王太子は彼女を第二妃として迎えると宣言したのである。
もちろん、そんな事は罷りならないと王は反対したのだが、その言葉を退けて彼女は同意をしてしまう。
屈辱的なことを敢えて受け入れたアンドレイナの真意とは……
*表紙絵自作

【完結】虐げられて自己肯定感を失った令嬢は、周囲からの愛を受け取れない
春風由実
恋愛
事情があって伯爵家で長く虐げられてきたオリヴィアは、公爵家に嫁ぐも、同じく虐げられる日々が続くものだと信じていた。
願わくば、公爵家では邪魔にならず、ひっそりと生かして貰えたら。
そんなオリヴィアの小さな願いを、夫となった公爵レオンは容赦なく打ち砕く。
※完結まで毎日1話更新します。最終話は2/15の投稿です。
※「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています。

私が行方不明の皇女です~生死を彷徨って帰国したら信じていた初恋の従者は婚約していました~
marumi
恋愛
「あら アルヴェイン公爵がドゥーカス令嬢をエスコートされていますわ」
「ご婚約されたと噂を聞きましたが、まさか本当だとは!」
私は五年前までこの国の皇女エリシアだった。
暗殺事件に巻き込まれ、幼なじみで初恋の相手だった従者――アルヴェイン公子と共に命からがら隣国、エルダールへ亡命した。
彼の「必ず迎えに来る」その言葉を信じて、隣国の地で彼を待ち続けた……。
それなのに……。
やっとの思いで帰国した帝国の華やかなパーティー会場で、一際目立っているのは、彼と、社交界の華と言われる令嬢だった――。
※校正にAIを使用していますが、自身で考案したオリジナル小説です。
※イメージが伝わればと思い、表紙画像をAI生成してみました。
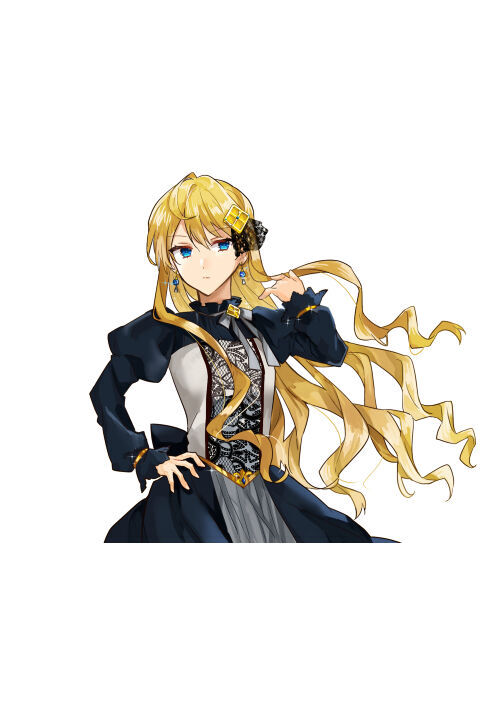
私はどうしようもない凡才なので、天才の妹に婚約者の王太子を譲ることにしました
克全
恋愛
「アルファポリス」「カクヨム」「小説家になろう」に同時投稿しています。
フレイザー公爵家の長女フローラは、自ら婚約者のウィリアム王太子に婚約解消を申し入れた。幼馴染でもあるウィリアム王太子は自分の事を嫌い、妹のエレノアの方が婚約者に相応しいと社交界で言いふらしていたからだ。寝食を忘れ、血の滲むほどの努力を重ねても、天才の妹に何一つ敵わないフローラは絶望していたのだ。一日でも早く他国に逃げ出したかったのだ。

姉に代わって立派に息子を育てます! 前日譚
mio
恋愛
ウェルカ・ティー・バーセリクは侯爵家の二女であるが、母亡き後に侯爵家に嫁いできた義母、転がり込んできた義妹に姉と共に邪魔者扱いされていた。
王家へと嫁ぐ姉について王都に移住したウェルカは侯爵家から離れて、実母の実家へと身を寄せることになった。姉が嫁ぐ中、学園に通いながらウェルカは自分の才能を伸ばしていく。
数年後、多少の問題を抱えつつ姉は懐妊。しかし、出産と同時にその命は尽きてしまう。そして残された息子をウェルカは姉に代わって育てる決意をした。そのためにはなんとしても王宮での地位を確立しなければ!
自分でも考えていたよりだいぶ話数が伸びてしまったため、こちらを姉が子を産むまでの前日譚として本編は別に作っていきたいと思います。申し訳ございません。

愛されなかった公爵令嬢のやり直し
ましゅぺちーの
恋愛
オルレリアン王国の公爵令嬢セシリアは、誰からも愛されていなかった。
母は幼い頃に亡くなり、父である公爵には無視され、王宮の使用人達には憐れみの眼差しを向けられる。
婚約者であった王太子と結婚するが夫となった王太子には冷遇されていた。
そんなある日、セシリアは王太子が寵愛する愛妾を害したと疑われてしまう。
どうせ処刑されるならと、セシリアは王宮のバルコニーから身を投げる。
死ぬ寸前のセシリアは思う。
「一度でいいから誰かに愛されたかった。」と。
目が覚めた時、セシリアは12歳の頃に時間が巻き戻っていた。
セシリアは決意する。
「自分の幸せは自分でつかみ取る!」
幸せになるために奔走するセシリア。
だがそれと同時に父である公爵の、婚約者である王太子の、王太子の愛妾であった男爵令嬢の、驚くべき真実が次々と明らかになっていく。
小説家になろう様にも投稿しています。
タイトル変更しました!大幅改稿のため、一部非公開にしております。

白い結婚の行方
宵森みなと
恋愛
「この結婚は、形式だけ。三年経ったら、離縁して養子縁組みをして欲しい。」
そう告げられたのは、まだ十二歳だった。
名門マイラス侯爵家の跡取りと、書面上だけの「夫婦」になるという取り決め。
愛もなく、未来も誓わず、ただ家と家の都合で交わされた契約だが、彼女にも目的はあった。
この白い結婚の意味を誰より彼女は、知っていた。自らの運命をどう選択するのか、彼女自身に委ねられていた。
冷静で、理知的で、どこか人を寄せつけない彼女。
誰もが「大人びている」と評した少女の胸の奥には、小さな祈りが宿っていた。
結婚に興味などなかったはずの青年も、少女との出会いと別れ、後悔を経て、再び運命を掴もうと足掻く。
これは、名ばかりの「夫婦」から始まった二人の物語。
偽りの契りが、やがて確かな絆へと変わるまで。
交差する記憶、巻き戻る時間、二度目の選択――。
真実の愛とは何かを、問いかける静かなる運命の物語。
──三年後、彼女の選択は、彼らは本当に“夫婦”になれるのだろうか?

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















