56 / 90
第三章 領主夫人、王都へと出向く
13.帰る場所
しおりを挟む
「…殿下、いくつか、確認させて頂きたいことがあるのですが…」
沈黙の支配する部屋、最初に口を開いたのはセルジュだった。
「…聞こう。」
王太子の返事に、セルジュが「では」と言葉を紡ぐ。
「一年後、フォーリーン魔術師長の巫女召喚をお許しになるおつもりですか?」
「…ティアナ嬢の救出、異界よりの召喚が可能だと判断されれば、その可能性は高い。」
「では、魔術師長に召喚陣の調査、使用を許可されると?」
「…最終的には陛下の判断を仰ぐことになるが、恐らくは。…ことは、伯爵令嬢の命に関わる。」
王太子の言葉に、セルジュと繋いだ手に力がこもる。思わず、口を挟んだ。
「巫女召喚って、そんなに何度も出来ることなんですか?二十四年毎にっていう、あれは何だったんですか?」
「それは…」
一瞬だけ言い淀んだ王太子だったが、直ぐに言葉を続ける。
「召喚陣は神代の遺物、王家の記録にも、その正確な始まりは残されていない。ただ、『国の始まりより存在した』とだけ記され、その最初の記録から、既に巫女召喚は二十四年周期と定められている。」
「理由は、無いんですか?」
「…明記はされていない。失伝してしまったか、或いは、元より、根拠など存在しないのか。」
「…」
「ただ、一つだけ、今までその理由として考えられてきたことがある。…その理由が、アンバーの暴走を招いたとも言えるが。」
苦い顔。どうやら彼も、今回のアンバー・フォーリーンの行動を良くは思っていないらしい。
「…通常、巫女召喚には百人を超える魔術師が必要だとされている。それだけの数の魔術師が限界まで魔力を行使し、漸く陣が起動するかしないかだが、例え、召喚に成功しても、関わった魔術師の多くは、その魔力を失ってしまう。」
「え…」
「巫女召喚とはそれほどの秘術であり、その代償の大きさから、二十四年周期とされたと考えられてきた。…だからこそ、単独での召喚に成功したアンバーは、その定めを逸脱してしまったのだろうが。」
悔やむかのような王太子の言葉、だったら、と思う。
(…だったら、もっとちゃんと、あの男を鎖で繋いでおけばいいのに。)
筆頭魔術師だか何だか知らないけれど、私の目から見ても、あの男はかなりの自由を許されている。時に、王太子相手に辛辣な意見を吐くこともあったし、それなりの「立場」を与えられていたはずの私に対しても、一切の敬意を払うことがなかった。それを咎めもしなかったのだから─
「…或いは…」
「?」
セルジュの呟き、独り言のようにも聞こえた声に、隣を向く。
「或いは、やはり、二十四年という周期には何らかの意味があり、その周期を外れた召喚ゆえに、今回の事故が起こった、とも考えられますが…」
言って、暫し考え込む様子を見せるセルジュ。だけど、それも、直ぐに首を振って、
「…何にしろ、魔術師長の調査の結果を待ってから、…でなければ、正確な答えは得られないでしょう…。…陣の調査でどこまで分かるかは、不明ですが。」
「まぁ、そうだな…」
歯切れの悪い王太子の言葉が空虚に響く。召喚陣がどういうものかは分からないまでも、そこに二十四年周期の根拠があるのなら、とっくに誰かが気づいていそうなもの。望み薄の状況は分かっていて、だけど、ティアナが飛ばされた原因を知る術は他にない。
「…殿下。」
セルジュが再び口を開いた。
「いま一つ、お尋ねしたいことがあります。」
「なんだ…?」
王太子の言葉に、セルジュの視線がこちらを向く。
「…クリューガー伯爵令嬢が飛ばされた先は、本当に、アオイの元居た世界なのでしょうか?」
「えっ!?」
「…どういう意味だ?」
王太子の疑問より先、驚きに声を上げてしまった。
セルジュの視線が真っすぐに王太子へと向けられる。
「…巫女召喚に関する情報を持ちえぬが故の戯言とお聞き流し下さってもいいのですが、多少、気になることが。…召喚の際、陣が繋ぐ世界は、必ずアオイの居た世界、一意に定まるのでしょうか?」
「…」
セルジュの問いに、王太子が口を噤んだ。
(え?待って、待って、どういうこと…?)
「…セルジュ、あの、それって、今までの巫女が、私とは違う世界の人間かもしれないって、そういうこと?」
「…召喚陣の構成次第ではありますが、可能性はあります。」
「っ!?」
驚いて、王太子へと視線を向ける。今まで、考えたこともなかったこと。ここと自分の居た世界以外に、全く別の世界が存在するなんて。
向けた視線、それを避けるように、王太子がため息をついた。
「…いや、それはない。召喚陣が繋ぐのは、巫女の居た世界、ただ一つだけだ。」
「…そう、なのですか…?」
あまり納得のいっていなさそうなセルジの返事。何かを考え込む仕草を見せる彼の様子に、王太子が言葉を重ねた。
「…召喚陣の具体的な構成については明かせないが、陣によって繋がる世界が指定されていることは間違いない。というよりも、繋ぐことが出来る世界が、『蒼月の裏にある世界』、巫女の居た世界しかないということだ。」
「…なるほど。」
納得したかのような返事に、それでもまだ何かを考え込んでいるセルジュ。その姿に不安を覚え、王太子へと視線を向けた。それを受け止めた王太子が─
「…加えて、だ。」
何かを諦めるように、ため息をついた。
「…王家には、代々の巫女に関する記録が残っている。」
「…え?」
今度こそ、信じられなくて、王太子の顔をまじまじと見つめてしまう。
「…嘘、だって、前に聞いた時、他の巫女に関する情報は無いって…」
「…すまない。」
いい加減、聞き飽きた言葉。その顔に浮かぶのは罪悪感なのか何なのか、僅かに逸らされた視線、王太子が口を開く。
「…召喚巫女に関する記録は全て王家の秘伝。…例え、巫女相手であろうと、その中身を明かすことは許されていない。」
「…」
「…明かすことが出来ない以上、存在そのものを『無い』と答えるしかなかった。…当時の君は、その、かなり、不安定だったため、私がそう判断した。」
「…」
あと、いくつ─
あといくつ、こうして騙されていること、彼が「言わなかった」ことがあるんだろうか。辛うじてあったはずの王太子への信頼というものが音を立てて崩れていく。ただ、今はそれを、「どうでもいい」と思える強さがあるから─
(…大丈夫。)
握ったままだったセルジュの右手、そこに、もう一つの温もりが重ねられた。
「では…」
揺るぎない声が隣から響く。
「その王家の記録、禁書には、巫女様方の記録が残されている。その内容から、陣の繋ぐ世界は同一世界だと、そう判明しているわけですね?」
「ああ、そうだ…」
王太子の肯定、それに漸く納得がいったらしいセルジュが頷いた。
そのまま、礼と退出を告げるセルジュに、疲れたような王太子の声が返る。
「…もし、巫女の世界に関して、また何か確認すべきことがあれば、こちらから連絡する。…今後も、巫女の協力を仰ぎたい。」
「…可能な範囲であれば。」
「ああ、それで構わない…」
それ以上、何も言われることはなく、二人で王太子の執務室を後にした。
王宮に乗り付けてきたアンブロス家の馬車、それに乗り込んでもまだ、ずっと何かを考え込んでいるセルジュ。その横顔を眺めながら、先ほどまでの短時間で起きた出来事を思い返す。眩暈がするような話の数々、信じていた色々なものが根本から崩れて、本当ならもっと、足元が不安になるような恐怖を覚えてもいいはず。そうならないのは─
「…アオイは…」
「?」
隣同士、漸くこちらを向いたセルジュ、ただ、その眼差しがどこか不安げで─
「…アオイは、どうしたいですか?」
「え?」
(…どうしたい?)
「…仮に、フォーリーン魔術師長の推論が正しく、召喚陣が双方向性を持つ場合、アオイの世界への帰還が可能だとすれば、アオイは…」
(ああ…)
そうか─
セルジュが、この人がこんな顔をする時は、全部─
「…帰らないよ。」
「…ですが…」
「言ったじゃない、昨日の夜。」
「…」
「帰れるとしても帰らない。…ずっと、セルジュの側にいる。」
「アオイ…」
伸ばされた手、セルジュの腕に囲われて、その温もりに捕らわれる。
「…だから、一緒に帰ろう?…アンブロス、みんなのところに…」
「…はい。」
沈黙の支配する部屋、最初に口を開いたのはセルジュだった。
「…聞こう。」
王太子の返事に、セルジュが「では」と言葉を紡ぐ。
「一年後、フォーリーン魔術師長の巫女召喚をお許しになるおつもりですか?」
「…ティアナ嬢の救出、異界よりの召喚が可能だと判断されれば、その可能性は高い。」
「では、魔術師長に召喚陣の調査、使用を許可されると?」
「…最終的には陛下の判断を仰ぐことになるが、恐らくは。…ことは、伯爵令嬢の命に関わる。」
王太子の言葉に、セルジュと繋いだ手に力がこもる。思わず、口を挟んだ。
「巫女召喚って、そんなに何度も出来ることなんですか?二十四年毎にっていう、あれは何だったんですか?」
「それは…」
一瞬だけ言い淀んだ王太子だったが、直ぐに言葉を続ける。
「召喚陣は神代の遺物、王家の記録にも、その正確な始まりは残されていない。ただ、『国の始まりより存在した』とだけ記され、その最初の記録から、既に巫女召喚は二十四年周期と定められている。」
「理由は、無いんですか?」
「…明記はされていない。失伝してしまったか、或いは、元より、根拠など存在しないのか。」
「…」
「ただ、一つだけ、今までその理由として考えられてきたことがある。…その理由が、アンバーの暴走を招いたとも言えるが。」
苦い顔。どうやら彼も、今回のアンバー・フォーリーンの行動を良くは思っていないらしい。
「…通常、巫女召喚には百人を超える魔術師が必要だとされている。それだけの数の魔術師が限界まで魔力を行使し、漸く陣が起動するかしないかだが、例え、召喚に成功しても、関わった魔術師の多くは、その魔力を失ってしまう。」
「え…」
「巫女召喚とはそれほどの秘術であり、その代償の大きさから、二十四年周期とされたと考えられてきた。…だからこそ、単独での召喚に成功したアンバーは、その定めを逸脱してしまったのだろうが。」
悔やむかのような王太子の言葉、だったら、と思う。
(…だったら、もっとちゃんと、あの男を鎖で繋いでおけばいいのに。)
筆頭魔術師だか何だか知らないけれど、私の目から見ても、あの男はかなりの自由を許されている。時に、王太子相手に辛辣な意見を吐くこともあったし、それなりの「立場」を与えられていたはずの私に対しても、一切の敬意を払うことがなかった。それを咎めもしなかったのだから─
「…或いは…」
「?」
セルジュの呟き、独り言のようにも聞こえた声に、隣を向く。
「或いは、やはり、二十四年という周期には何らかの意味があり、その周期を外れた召喚ゆえに、今回の事故が起こった、とも考えられますが…」
言って、暫し考え込む様子を見せるセルジュ。だけど、それも、直ぐに首を振って、
「…何にしろ、魔術師長の調査の結果を待ってから、…でなければ、正確な答えは得られないでしょう…。…陣の調査でどこまで分かるかは、不明ですが。」
「まぁ、そうだな…」
歯切れの悪い王太子の言葉が空虚に響く。召喚陣がどういうものかは分からないまでも、そこに二十四年周期の根拠があるのなら、とっくに誰かが気づいていそうなもの。望み薄の状況は分かっていて、だけど、ティアナが飛ばされた原因を知る術は他にない。
「…殿下。」
セルジュが再び口を開いた。
「いま一つ、お尋ねしたいことがあります。」
「なんだ…?」
王太子の言葉に、セルジュの視線がこちらを向く。
「…クリューガー伯爵令嬢が飛ばされた先は、本当に、アオイの元居た世界なのでしょうか?」
「えっ!?」
「…どういう意味だ?」
王太子の疑問より先、驚きに声を上げてしまった。
セルジュの視線が真っすぐに王太子へと向けられる。
「…巫女召喚に関する情報を持ちえぬが故の戯言とお聞き流し下さってもいいのですが、多少、気になることが。…召喚の際、陣が繋ぐ世界は、必ずアオイの居た世界、一意に定まるのでしょうか?」
「…」
セルジュの問いに、王太子が口を噤んだ。
(え?待って、待って、どういうこと…?)
「…セルジュ、あの、それって、今までの巫女が、私とは違う世界の人間かもしれないって、そういうこと?」
「…召喚陣の構成次第ではありますが、可能性はあります。」
「っ!?」
驚いて、王太子へと視線を向ける。今まで、考えたこともなかったこと。ここと自分の居た世界以外に、全く別の世界が存在するなんて。
向けた視線、それを避けるように、王太子がため息をついた。
「…いや、それはない。召喚陣が繋ぐのは、巫女の居た世界、ただ一つだけだ。」
「…そう、なのですか…?」
あまり納得のいっていなさそうなセルジの返事。何かを考え込む仕草を見せる彼の様子に、王太子が言葉を重ねた。
「…召喚陣の具体的な構成については明かせないが、陣によって繋がる世界が指定されていることは間違いない。というよりも、繋ぐことが出来る世界が、『蒼月の裏にある世界』、巫女の居た世界しかないということだ。」
「…なるほど。」
納得したかのような返事に、それでもまだ何かを考え込んでいるセルジュ。その姿に不安を覚え、王太子へと視線を向けた。それを受け止めた王太子が─
「…加えて、だ。」
何かを諦めるように、ため息をついた。
「…王家には、代々の巫女に関する記録が残っている。」
「…え?」
今度こそ、信じられなくて、王太子の顔をまじまじと見つめてしまう。
「…嘘、だって、前に聞いた時、他の巫女に関する情報は無いって…」
「…すまない。」
いい加減、聞き飽きた言葉。その顔に浮かぶのは罪悪感なのか何なのか、僅かに逸らされた視線、王太子が口を開く。
「…召喚巫女に関する記録は全て王家の秘伝。…例え、巫女相手であろうと、その中身を明かすことは許されていない。」
「…」
「…明かすことが出来ない以上、存在そのものを『無い』と答えるしかなかった。…当時の君は、その、かなり、不安定だったため、私がそう判断した。」
「…」
あと、いくつ─
あといくつ、こうして騙されていること、彼が「言わなかった」ことがあるんだろうか。辛うじてあったはずの王太子への信頼というものが音を立てて崩れていく。ただ、今はそれを、「どうでもいい」と思える強さがあるから─
(…大丈夫。)
握ったままだったセルジュの右手、そこに、もう一つの温もりが重ねられた。
「では…」
揺るぎない声が隣から響く。
「その王家の記録、禁書には、巫女様方の記録が残されている。その内容から、陣の繋ぐ世界は同一世界だと、そう判明しているわけですね?」
「ああ、そうだ…」
王太子の肯定、それに漸く納得がいったらしいセルジュが頷いた。
そのまま、礼と退出を告げるセルジュに、疲れたような王太子の声が返る。
「…もし、巫女の世界に関して、また何か確認すべきことがあれば、こちらから連絡する。…今後も、巫女の協力を仰ぎたい。」
「…可能な範囲であれば。」
「ああ、それで構わない…」
それ以上、何も言われることはなく、二人で王太子の執務室を後にした。
王宮に乗り付けてきたアンブロス家の馬車、それに乗り込んでもまだ、ずっと何かを考え込んでいるセルジュ。その横顔を眺めながら、先ほどまでの短時間で起きた出来事を思い返す。眩暈がするような話の数々、信じていた色々なものが根本から崩れて、本当ならもっと、足元が不安になるような恐怖を覚えてもいいはず。そうならないのは─
「…アオイは…」
「?」
隣同士、漸くこちらを向いたセルジュ、ただ、その眼差しがどこか不安げで─
「…アオイは、どうしたいですか?」
「え?」
(…どうしたい?)
「…仮に、フォーリーン魔術師長の推論が正しく、召喚陣が双方向性を持つ場合、アオイの世界への帰還が可能だとすれば、アオイは…」
(ああ…)
そうか─
セルジュが、この人がこんな顔をする時は、全部─
「…帰らないよ。」
「…ですが…」
「言ったじゃない、昨日の夜。」
「…」
「帰れるとしても帰らない。…ずっと、セルジュの側にいる。」
「アオイ…」
伸ばされた手、セルジュの腕に囲われて、その温もりに捕らわれる。
「…だから、一緒に帰ろう?…アンブロス、みんなのところに…」
「…はい。」
111
あなたにおすすめの小説

完結 王族の醜聞がメシウマ過ぎる件
音爽(ネソウ)
恋愛
王太子は言う。
『お前みたいなつまらない女など要らない、だが優秀さはかってやろう。第二妃として存分に働けよ』
『ごめんなさぁい、貴女は私の代わりに公儀をやってねぇ。だってそれしか取り柄がないんだしぃ』
公務のほとんどを丸投げにする宣言をして、正妃になるはずのアンドレイナ・サンドリーニを蹴落とし正妃の座に就いたベネッタ・ルニッチは高笑いした。王太子は彼女を第二妃として迎えると宣言したのである。
もちろん、そんな事は罷りならないと王は反対したのだが、その言葉を退けて彼女は同意をしてしまう。
屈辱的なことを敢えて受け入れたアンドレイナの真意とは……
*表紙絵自作

【完結】虐げられて自己肯定感を失った令嬢は、周囲からの愛を受け取れない
春風由実
恋愛
事情があって伯爵家で長く虐げられてきたオリヴィアは、公爵家に嫁ぐも、同じく虐げられる日々が続くものだと信じていた。
願わくば、公爵家では邪魔にならず、ひっそりと生かして貰えたら。
そんなオリヴィアの小さな願いを、夫となった公爵レオンは容赦なく打ち砕く。
※完結まで毎日1話更新します。最終話は2/15の投稿です。
※「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています。

姉に代わって立派に息子を育てます! 前日譚
mio
恋愛
ウェルカ・ティー・バーセリクは侯爵家の二女であるが、母亡き後に侯爵家に嫁いできた義母、転がり込んできた義妹に姉と共に邪魔者扱いされていた。
王家へと嫁ぐ姉について王都に移住したウェルカは侯爵家から離れて、実母の実家へと身を寄せることになった。姉が嫁ぐ中、学園に通いながらウェルカは自分の才能を伸ばしていく。
数年後、多少の問題を抱えつつ姉は懐妊。しかし、出産と同時にその命は尽きてしまう。そして残された息子をウェルカは姉に代わって育てる決意をした。そのためにはなんとしても王宮での地位を確立しなければ!
自分でも考えていたよりだいぶ話数が伸びてしまったため、こちらを姉が子を産むまでの前日譚として本編は別に作っていきたいと思います。申し訳ございません。

【完結】地味な私と公爵様
ベル
恋愛
ラエル公爵。この学園でこの名を知らない人はいないでしょう。
端正な顔立ちに甘く低い声、時折見せる少年のような笑顔。誰もがその美しさに魅了され、女性なら誰もがラエル様との結婚を夢見てしまう。
そんな方が、平凡...いや、かなり地味で目立たない伯爵令嬢である私の婚約者だなんて一体誰が信じるでしょうか。
...正直私も信じていません。
ラエル様が、私を溺愛しているなんて。
きっと、きっと、夢に違いありません。
お読みいただきありがとうございます。短編のつもりで書き始めましたが、意外と話が増えて長編に変更し、無事完結しました(*´-`)

【完結】【番外編追加】お迎えに来てくれた当日にいなくなったお姉様の代わりに嫁ぎます!
まりぃべる
恋愛
私、アリーシャ。
お姉様は、隣国の大国に輿入れ予定でした。
それは、二年前から決まり、準備を着々としてきた。
和平の象徴として、その意味を理解されていたと思っていたのに。
『私、レナードと生活するわ。あとはお願いね!』
そんな置き手紙だけを残して、姉は消えた。
そんな…!
☆★
書き終わってますので、随時更新していきます。全35話です。
国の名前など、有名な名前(単語)だったと後から気付いたのですが、素敵な響きですのでそのまま使います。現実世界とは全く関係ありません。いつも思いつきで名前を決めてしまいますので…。
読んでいただけたら嬉しいです。

わかったわ、私が代役になればいいのね?[完]
風龍佳乃
恋愛
ブェールズ侯爵家に生まれたリディー。
しかしリディーは
「双子が産まれると家門が分裂する」
そんな言い伝えがありブェールズ夫婦は
妹のリディーをすぐにシュエル伯爵家の
養女として送り出したのだった。
リディーは13歳の時
姉のリディアーナが病に倒れたと
聞かされ初めて自分の生い立ちを知る。
そしてリディアーナは皇太子殿下の
婚約者候補だと知らされて葛藤する。
リディーは皇太子殿下からの依頼を
受けて姉に成り代わり
身代わりとしてリディアーナを演じる
事を選んだリディーに試練が待っていた。
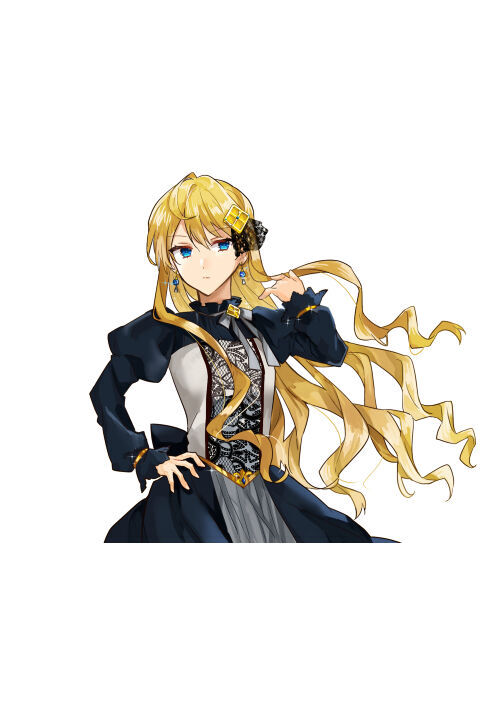
私はどうしようもない凡才なので、天才の妹に婚約者の王太子を譲ることにしました
克全
恋愛
「アルファポリス」「カクヨム」「小説家になろう」に同時投稿しています。
フレイザー公爵家の長女フローラは、自ら婚約者のウィリアム王太子に婚約解消を申し入れた。幼馴染でもあるウィリアム王太子は自分の事を嫌い、妹のエレノアの方が婚約者に相応しいと社交界で言いふらしていたからだ。寝食を忘れ、血の滲むほどの努力を重ねても、天才の妹に何一つ敵わないフローラは絶望していたのだ。一日でも早く他国に逃げ出したかったのだ。

愛されなかった公爵令嬢のやり直し
ましゅぺちーの
恋愛
オルレリアン王国の公爵令嬢セシリアは、誰からも愛されていなかった。
母は幼い頃に亡くなり、父である公爵には無視され、王宮の使用人達には憐れみの眼差しを向けられる。
婚約者であった王太子と結婚するが夫となった王太子には冷遇されていた。
そんなある日、セシリアは王太子が寵愛する愛妾を害したと疑われてしまう。
どうせ処刑されるならと、セシリアは王宮のバルコニーから身を投げる。
死ぬ寸前のセシリアは思う。
「一度でいいから誰かに愛されたかった。」と。
目が覚めた時、セシリアは12歳の頃に時間が巻き戻っていた。
セシリアは決意する。
「自分の幸せは自分でつかみ取る!」
幸せになるために奔走するセシリア。
だがそれと同時に父である公爵の、婚約者である王太子の、王太子の愛妾であった男爵令嬢の、驚くべき真実が次々と明らかになっていく。
小説家になろう様にも投稿しています。
タイトル変更しました!大幅改稿のため、一部非公開にしております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















