74 / 90
最終章 領主夫人、再び王都へ
4.二年でさえ
しおりを挟む
「…これは、無いんじゃない…?」
「…どうあっても、という意志を感じますね…」
降臨祭出席のためにアンブロス領を出てから三日、王都の城門にたどり着いたところでの突然の足止め。現れたのは王太子殿下直属だという使者で、このまま王宮へ招きたいという彼の言葉に、いよいよ頭痛がしてきた。
(…さっきまでは、アンブロス領のみんなの心配でいっぱいだったのに。)
レナータは泣いていないか、魔物以外の危険に晒されていないか。マティアスやオットー達は無茶はしていないか、目を離した隙にまた子ども達がやんちゃをしていたらどうしよう。
杞憂だと思う一方で、側に居られない不安が膨らみきっていた中、まさか、面倒事が自分の方にやって来るなんて。
「…お断り、…は難しいんですよね?」
「…どうか…」
彼もそれがお仕事なんだろうけれど、ひたすらに頭を下げる使者に、段々、拒否するのも難しくなってくる。
「…分かりました。」
「アオイ…」
「殿下に会って、直接、お断りする。…もう、それしかないんじゃないかなって。」
「…」
黙したセルジュも、最終的には頷いてくれた。苦い顔のまま、夫婦そろって、王宮へと向かう。
「…よく、来てくれた。」
「…本日はお招きに預かり、」
「いや、礼を言うのはこちらの方だ。…どうか、くつろいでくれ。」
型どおりの挨拶をぶった切って、着席を進める王太子の言葉に従う。セルジュと並んでソファに腰を下ろしながらも、意識はずっと部屋の奥、ただ一人の男に向けられていた。
(…なに、アレ…)
部屋の隅、魔力の見えない私でも禍々しいものを感じてしまうほどの何かをまとった男、二年ぶりに目にするアンバー・フォーリーンの姿。二年前、最後に会った時の男の様相も異様なものだったが、今では、全くの別人にさえ見える。服から覗く細い手足、顔の肉は落ち、目の下には酷い隈。どこを見ているのか分からない、けれど、そこだけが生気を失っていない瞳をギラギラと輝かせて─
「…巫女、…いや、アンブロス夫人、単刀直入に願おう。」
「…」
「クリューガー伯爵令嬢帰還に力を貸してもらいたい。」
「…それは、既にお断りしているはずですが。」
「…夫人の意志は聞いている。だが、そこを曲げて、どうか、頼む…」
「…」
言って、頭を下げた王太子に、彼の背後でサキアが僅かに表情を変えた。一国の王太子が頭を下げるほどの価値、それが彼女にあるということなんだろうけれど─
「っ…!?」
「…アンブロス夫人?」
「…いえ…」
(…うっわぁ…)
─最悪だ
人一人が行方不明になっている。その安否を気に掛けるのは普通の感覚で、救助可能ならば救助する。それが当然だと、以前の自分なら、そう胸を張って言えた。それが、
(…人を、身分とか、価値の有無で見るようになるなんて…)
少なくとも、私は、今、王太子の人格ではなく、その身分で彼の行為を判断してしまった。同じく、クリューガー伯爵令嬢のことも。
(…染まっちゃってるなぁ…)
身分なんてそんなもの、関係ないっていう世界で生きていたはずなのに。
(…彼女を、ちゃんと、一人の女性として見るなら…)
こちらの世界ではぎりぎり成人。それでも、自活できる力は持たない。マルステア辺境伯の姪で、アンバー・フォーリーンの婚約者。
そして、きっと、家族に愛されていた女の子─
「…私も…」
「…夫人?」
「…私も、クリューガー伯爵令嬢の身は案じていますし、無事であればと祈っています。」
「っ!では?」
「ただ、承諾できない理由があります。…私だって、何の理由もなく、殿下の要請をお断りしているわけではないんです…」
「…理由?…理由があるのか?」
身を乗り出す勢いの王太子に、願いをぶつける。これで断られれば仕方ない。その時は、こちらも要求を飲めないだけのこと。
「…王家の、禁書というのを見せてください。」
「…なに?」
「歴代巫女に関する資料があるんですよね?」
「それは…」
「見せてください。…でなければ、殿下の願いを聞くことは出来ません。」
「…」
厳しい顔、思い悩んだ様子の王太子だったが、数舜の葛藤の後、再び口を開いた。
「閲覧を許せば、令嬢帰還への助力を確約してもらえるのだろうか?」
「いえ。禁書はあくまで判断材料、…どうしても、気になることがあるんです。」
「それを、今ここで明かすことは?」
「…それはちょっと。」
言いながら、視線を部屋の奥へと向ける。
「…私も、確信があるわけではありませんので。」
嘘をついた。
本当は、ほとんど確信してしまっている。ただ、根拠なんて何もない「私だけの感覚」を理解してもらえるとは思えなかった。
「…分かった。」
「…」
「禁書の閲覧を許可しよう。」
「…ありがとうございます。」
「いや。…夫人の助力を請う手段がそれだけならばやむを得ない。…出来れば、良い返事を期待している。」
「…」
最後の、王太子の言葉には頷けなかった。私がしようとしていることは、彼の望みとは正反対だったから。
「…どうあっても、という意志を感じますね…」
降臨祭出席のためにアンブロス領を出てから三日、王都の城門にたどり着いたところでの突然の足止め。現れたのは王太子殿下直属だという使者で、このまま王宮へ招きたいという彼の言葉に、いよいよ頭痛がしてきた。
(…さっきまでは、アンブロス領のみんなの心配でいっぱいだったのに。)
レナータは泣いていないか、魔物以外の危険に晒されていないか。マティアスやオットー達は無茶はしていないか、目を離した隙にまた子ども達がやんちゃをしていたらどうしよう。
杞憂だと思う一方で、側に居られない不安が膨らみきっていた中、まさか、面倒事が自分の方にやって来るなんて。
「…お断り、…は難しいんですよね?」
「…どうか…」
彼もそれがお仕事なんだろうけれど、ひたすらに頭を下げる使者に、段々、拒否するのも難しくなってくる。
「…分かりました。」
「アオイ…」
「殿下に会って、直接、お断りする。…もう、それしかないんじゃないかなって。」
「…」
黙したセルジュも、最終的には頷いてくれた。苦い顔のまま、夫婦そろって、王宮へと向かう。
「…よく、来てくれた。」
「…本日はお招きに預かり、」
「いや、礼を言うのはこちらの方だ。…どうか、くつろいでくれ。」
型どおりの挨拶をぶった切って、着席を進める王太子の言葉に従う。セルジュと並んでソファに腰を下ろしながらも、意識はずっと部屋の奥、ただ一人の男に向けられていた。
(…なに、アレ…)
部屋の隅、魔力の見えない私でも禍々しいものを感じてしまうほどの何かをまとった男、二年ぶりに目にするアンバー・フォーリーンの姿。二年前、最後に会った時の男の様相も異様なものだったが、今では、全くの別人にさえ見える。服から覗く細い手足、顔の肉は落ち、目の下には酷い隈。どこを見ているのか分からない、けれど、そこだけが生気を失っていない瞳をギラギラと輝かせて─
「…巫女、…いや、アンブロス夫人、単刀直入に願おう。」
「…」
「クリューガー伯爵令嬢帰還に力を貸してもらいたい。」
「…それは、既にお断りしているはずですが。」
「…夫人の意志は聞いている。だが、そこを曲げて、どうか、頼む…」
「…」
言って、頭を下げた王太子に、彼の背後でサキアが僅かに表情を変えた。一国の王太子が頭を下げるほどの価値、それが彼女にあるということなんだろうけれど─
「っ…!?」
「…アンブロス夫人?」
「…いえ…」
(…うっわぁ…)
─最悪だ
人一人が行方不明になっている。その安否を気に掛けるのは普通の感覚で、救助可能ならば救助する。それが当然だと、以前の自分なら、そう胸を張って言えた。それが、
(…人を、身分とか、価値の有無で見るようになるなんて…)
少なくとも、私は、今、王太子の人格ではなく、その身分で彼の行為を判断してしまった。同じく、クリューガー伯爵令嬢のことも。
(…染まっちゃってるなぁ…)
身分なんてそんなもの、関係ないっていう世界で生きていたはずなのに。
(…彼女を、ちゃんと、一人の女性として見るなら…)
こちらの世界ではぎりぎり成人。それでも、自活できる力は持たない。マルステア辺境伯の姪で、アンバー・フォーリーンの婚約者。
そして、きっと、家族に愛されていた女の子─
「…私も…」
「…夫人?」
「…私も、クリューガー伯爵令嬢の身は案じていますし、無事であればと祈っています。」
「っ!では?」
「ただ、承諾できない理由があります。…私だって、何の理由もなく、殿下の要請をお断りしているわけではないんです…」
「…理由?…理由があるのか?」
身を乗り出す勢いの王太子に、願いをぶつける。これで断られれば仕方ない。その時は、こちらも要求を飲めないだけのこと。
「…王家の、禁書というのを見せてください。」
「…なに?」
「歴代巫女に関する資料があるんですよね?」
「それは…」
「見せてください。…でなければ、殿下の願いを聞くことは出来ません。」
「…」
厳しい顔、思い悩んだ様子の王太子だったが、数舜の葛藤の後、再び口を開いた。
「閲覧を許せば、令嬢帰還への助力を確約してもらえるのだろうか?」
「いえ。禁書はあくまで判断材料、…どうしても、気になることがあるんです。」
「それを、今ここで明かすことは?」
「…それはちょっと。」
言いながら、視線を部屋の奥へと向ける。
「…私も、確信があるわけではありませんので。」
嘘をついた。
本当は、ほとんど確信してしまっている。ただ、根拠なんて何もない「私だけの感覚」を理解してもらえるとは思えなかった。
「…分かった。」
「…」
「禁書の閲覧を許可しよう。」
「…ありがとうございます。」
「いや。…夫人の助力を請う手段がそれだけならばやむを得ない。…出来れば、良い返事を期待している。」
「…」
最後の、王太子の言葉には頷けなかった。私がしようとしていることは、彼の望みとは正反対だったから。
110
あなたにおすすめの小説

完結 王族の醜聞がメシウマ過ぎる件
音爽(ネソウ)
恋愛
王太子は言う。
『お前みたいなつまらない女など要らない、だが優秀さはかってやろう。第二妃として存分に働けよ』
『ごめんなさぁい、貴女は私の代わりに公儀をやってねぇ。だってそれしか取り柄がないんだしぃ』
公務のほとんどを丸投げにする宣言をして、正妃になるはずのアンドレイナ・サンドリーニを蹴落とし正妃の座に就いたベネッタ・ルニッチは高笑いした。王太子は彼女を第二妃として迎えると宣言したのである。
もちろん、そんな事は罷りならないと王は反対したのだが、その言葉を退けて彼女は同意をしてしまう。
屈辱的なことを敢えて受け入れたアンドレイナの真意とは……
*表紙絵自作

【完結】虐げられて自己肯定感を失った令嬢は、周囲からの愛を受け取れない
春風由実
恋愛
事情があって伯爵家で長く虐げられてきたオリヴィアは、公爵家に嫁ぐも、同じく虐げられる日々が続くものだと信じていた。
願わくば、公爵家では邪魔にならず、ひっそりと生かして貰えたら。
そんなオリヴィアの小さな願いを、夫となった公爵レオンは容赦なく打ち砕く。
※完結まで毎日1話更新します。最終話は2/15の投稿です。
※「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています。

姉に代わって立派に息子を育てます! 前日譚
mio
恋愛
ウェルカ・ティー・バーセリクは侯爵家の二女であるが、母亡き後に侯爵家に嫁いできた義母、転がり込んできた義妹に姉と共に邪魔者扱いされていた。
王家へと嫁ぐ姉について王都に移住したウェルカは侯爵家から離れて、実母の実家へと身を寄せることになった。姉が嫁ぐ中、学園に通いながらウェルカは自分の才能を伸ばしていく。
数年後、多少の問題を抱えつつ姉は懐妊。しかし、出産と同時にその命は尽きてしまう。そして残された息子をウェルカは姉に代わって育てる決意をした。そのためにはなんとしても王宮での地位を確立しなければ!
自分でも考えていたよりだいぶ話数が伸びてしまったため、こちらを姉が子を産むまでの前日譚として本編は別に作っていきたいと思います。申し訳ございません。

【完結】地味な私と公爵様
ベル
恋愛
ラエル公爵。この学園でこの名を知らない人はいないでしょう。
端正な顔立ちに甘く低い声、時折見せる少年のような笑顔。誰もがその美しさに魅了され、女性なら誰もがラエル様との結婚を夢見てしまう。
そんな方が、平凡...いや、かなり地味で目立たない伯爵令嬢である私の婚約者だなんて一体誰が信じるでしょうか。
...正直私も信じていません。
ラエル様が、私を溺愛しているなんて。
きっと、きっと、夢に違いありません。
お読みいただきありがとうございます。短編のつもりで書き始めましたが、意外と話が増えて長編に変更し、無事完結しました(*´-`)

【完結】【番外編追加】お迎えに来てくれた当日にいなくなったお姉様の代わりに嫁ぎます!
まりぃべる
恋愛
私、アリーシャ。
お姉様は、隣国の大国に輿入れ予定でした。
それは、二年前から決まり、準備を着々としてきた。
和平の象徴として、その意味を理解されていたと思っていたのに。
『私、レナードと生活するわ。あとはお願いね!』
そんな置き手紙だけを残して、姉は消えた。
そんな…!
☆★
書き終わってますので、随時更新していきます。全35話です。
国の名前など、有名な名前(単語)だったと後から気付いたのですが、素敵な響きですのでそのまま使います。現実世界とは全く関係ありません。いつも思いつきで名前を決めてしまいますので…。
読んでいただけたら嬉しいです。

わかったわ、私が代役になればいいのね?[完]
風龍佳乃
恋愛
ブェールズ侯爵家に生まれたリディー。
しかしリディーは
「双子が産まれると家門が分裂する」
そんな言い伝えがありブェールズ夫婦は
妹のリディーをすぐにシュエル伯爵家の
養女として送り出したのだった。
リディーは13歳の時
姉のリディアーナが病に倒れたと
聞かされ初めて自分の生い立ちを知る。
そしてリディアーナは皇太子殿下の
婚約者候補だと知らされて葛藤する。
リディーは皇太子殿下からの依頼を
受けて姉に成り代わり
身代わりとしてリディアーナを演じる
事を選んだリディーに試練が待っていた。
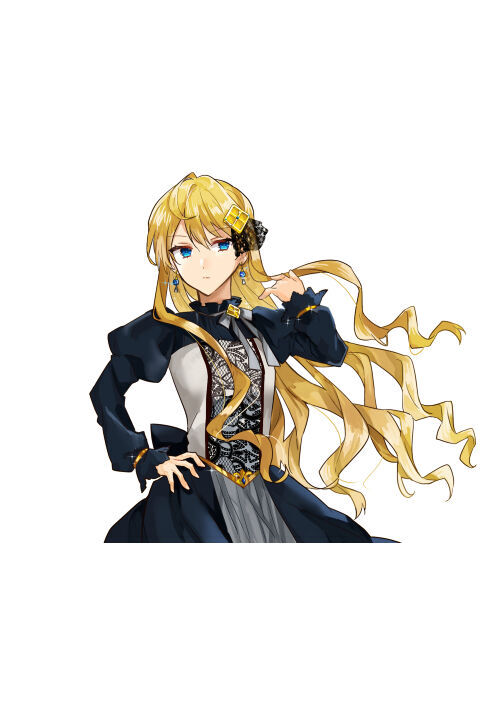
私はどうしようもない凡才なので、天才の妹に婚約者の王太子を譲ることにしました
克全
恋愛
「アルファポリス」「カクヨム」「小説家になろう」に同時投稿しています。
フレイザー公爵家の長女フローラは、自ら婚約者のウィリアム王太子に婚約解消を申し入れた。幼馴染でもあるウィリアム王太子は自分の事を嫌い、妹のエレノアの方が婚約者に相応しいと社交界で言いふらしていたからだ。寝食を忘れ、血の滲むほどの努力を重ねても、天才の妹に何一つ敵わないフローラは絶望していたのだ。一日でも早く他国に逃げ出したかったのだ。

愛されなかった公爵令嬢のやり直し
ましゅぺちーの
恋愛
オルレリアン王国の公爵令嬢セシリアは、誰からも愛されていなかった。
母は幼い頃に亡くなり、父である公爵には無視され、王宮の使用人達には憐れみの眼差しを向けられる。
婚約者であった王太子と結婚するが夫となった王太子には冷遇されていた。
そんなある日、セシリアは王太子が寵愛する愛妾を害したと疑われてしまう。
どうせ処刑されるならと、セシリアは王宮のバルコニーから身を投げる。
死ぬ寸前のセシリアは思う。
「一度でいいから誰かに愛されたかった。」と。
目が覚めた時、セシリアは12歳の頃に時間が巻き戻っていた。
セシリアは決意する。
「自分の幸せは自分でつかみ取る!」
幸せになるために奔走するセシリア。
だがそれと同時に父である公爵の、婚約者である王太子の、王太子の愛妾であった男爵令嬢の、驚くべき真実が次々と明らかになっていく。
小説家になろう様にも投稿しています。
タイトル変更しました!大幅改稿のため、一部非公開にしております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















