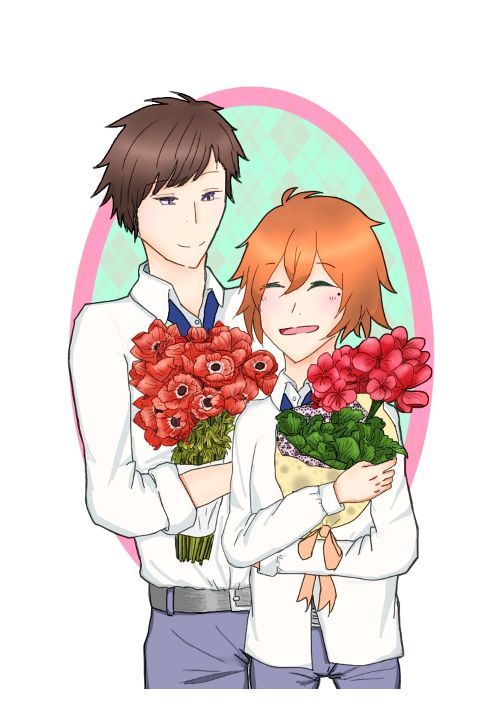88 / 90
最終章 領主夫人、再び王都へ
18.理不尽
しおりを挟む
「嫌っ!!絶対に嫌っ!そんなの無理に決まってるでしょうっ!?」
「…アンブロス夫人、頼む、落ち着いてくれ。一度、私の話を、」
「なんでそんな話聞かなくちゃいけないのよっ!?」
ああ、嫌だ嫌だ嫌だ─
「話なんて聞かない!あなた達の言い分なんて関係ないっ!」
「夫人、これは、あなたにしか頼めない、」
「知らないってばっ!」
立ち上がり、逃げ出す。扉へと駆け寄ってドアノブを引くが、その扉が開くことはない。
「っ!?」
ああ、また─
「…アンブロス夫人。」
「っ!?」
背後、聞こえた声に反射的に振り向いた。そこに立つ男を見上げる。
「私からも頼む。…殿下の話を、」
「来ないでっ!!」
いつの間に、この距離まで近づかれていたのか。手の届きそうな距離にある男の巨体から逃れるため、部屋の隅へと走る。
「…アンブロス夫人、どうか…」
「来ないでってばっ!ガイラスッ!それ以上、近づかないでっ!」
「…」
顔に苦渋をにじませる男、かつて、同じような状況で、彼には何度も拘束されたことがある。当時も恐怖を覚えたが、今はそれ以上に嫌悪が大きい。
「…来ないでっ…!」
上がった息を整えながら、自分の馬鹿さ加減を呪った。
(…最悪、最低、本っ当、バカすぎる…)
彼らを信用して、こんな状況に追い込まれて。
彼らへの怒りと、自分自身への怒りから、パニックに陥っていた思考が少しだけまともに動き出す。
(兎に角、今は、この状況から逃げ出すこと…)
話の内容から、命を取られることはないはずだから。
「…話は、聞く。…だから、離れて。…私に、触れないで。」
「…」
「…戻れ、ガイラス。」
ガイラスを呼び戻す王太子の声に、ガイラスが一歩を引いた。そのまま、定位置、王太子の背後へと回る彼の姿を確認してから、王太子へと向き直る。
「…アンブロス夫人、どうか、こちらへ掛けてくれないか?その場所では、」
「いい。ここで聞く。…さっさと話して。」
「…そうか。なら…」
部屋の隅、どれだけ距離をとっても、彼らがその気になれば直ぐに捕まってしまうだろう。分かっていても、彼らの近くに戻るなんて冗談じゃない。立ったまま、王太子が言葉を続けるのを待てば、深いため息が聞こえて─
「…アンバー・フォーリーンの暴走は、この国に致命的な損害を与えた。」
「…」
「彼の行った巫女召喚によって、召喚陣が損傷を受けている。」
「そん、しょう…?」
「ああ。…召喚陣の基盤である召喚の間の床に亀裂がいくつか…、現状では、修復は不可能だと判断された。」
淡々と告げられた言葉を飲み込んで、咀嚼して、漸く理解する。
「…それって、じゃあ…」
「ああ。…この国は巫女召喚を行う手段を失った。少なくとも、この国の技術が神代に追いつく、向こう数百年先までは…」
「…」
その言葉に、どう反応していいものか迷う。これから先、自分の居なくなった未来において、自分と同じ思いをする人間が居なくなったことは単純に良かったと思う。ただ、アンブロスの将来はまだ、巫女の存在を失っても万全だとは言い難い。
(…ううん、アンブロスはまだいい。何とかなる、…これから、何とかしてみせる。)
だけど、それが、この国全体に関してとなると─
「…この国には、巫女が二度と現れない可能性すらある。…だとすれば、我々が望むもの、期待するものが、あなたにも分かるだろう?」
「…知らない。」
「…僅かな望みであろうと、可能性があるならば、我々はそれに賭けるしかない。」
「知らないってば!」
「…結界の巫女と同等の魔力を持つ子の誕生。」
「っ!」
拒否しているのに。
告げられた内容の醜悪さに吐き気がする。人を、子どもを、都合の良い「モノ」のように扱おうとする傲慢さ─
「…私を含むこの場に居る三人は、国内でも上位の魔力持ちだ。その…、夫人と年も近く、知らぬ間柄ではない。…あなたが望むならば他の者を選ぶことも可能だが、出来るならば、」
「しないってばっ!」
「…」
「選ばないし!セルジュ以外の人の子どもなんて産まない!」
愛する人以外の誰かの子どもを産む。そこに至るまでの過程を全て無視して、結果だけを求めようとする彼らがおぞましくて仕方なかった。
「大体っ!」
視線を、部屋の奥、泰然と構え、薄っすら笑みさえ浮かべている王太子妃へと向ける。
「大体っ!こんなバカみたいな話!妃殿下やアイシャさんは認めてるのっ!?自分の夫が私と、…子どもを持つなんて、認められるのっ!?」
否定の言葉が欲しくて叫ぶが、視線の先の女性は優雅に微笑んだまま。
「あら?勿論、私は承知済みですわ。…アイシャ様におかれましても、…そうですね、感情はどうあれ、お立場的にご理解はされているのではないでしょうか?」
「っ!嘘っ!そんなの嘘っ!」
「嘘ではございません。」
言い切った王太子妃の顔から笑みが消える。怖いくらいに真剣な眼差しを向けられる。
「…私は王太子妃、将来、この国の王となられる殿下の唯一の妃です。」
「…」
「…殿下が王太子として望まれるなら、この国のために必要と判断されたことであれば、私に否やはありません。」
「っ!でも、だけどっ!そんなの嫌でしょうっ!?あなただって、本当は!」
「巫女様。私は、幼き頃より殿下の隣に立つと決めておりましたの。」
王太子妃が笑う。
「私は私の役目、王太子妃という立場を理解しております。『嫌』などという感情でその役目を放り出すつもりはございません。」
「っ!?」
(なに、なんで…)
理解出来ない。彼女の笑みが薄気味悪くて仕方ない。私が王太子を望む未来もあったと仄めかした時の彼女の反応、彼女が怒りを見せたのは、つい昨日のことだというのに。
「…そんな、…だって、妃殿下は、殿下を好き、…愛してるんでしょう?」
「ええ。勿論ですわ。」
「…」
「だからこそ、私は殿下の定めに最後まで従います。私は、死ぬその時まで、殿下の妃ですから。」
そう言い切る彼女には余裕すら感じられて、彼女が、この場での味方にはなり得ないことを知る。
「…でも、だけど…」
視線を王太子の居る方へと彷徨わせた。
「私の子どもが魔力を受け継ぐとは限らないじゃない…。実際、レナータ、私の子は魔力を受け継いでいないし…」
「…そう、だな。」
「禁書にだって、巫女の魔力を受け継ぐ子どもが産まれたっていう記録はなかった。絶望的だって…」
「ああ、それも承知している。それでも…」
「…」
「その、僅かな可能性に賭けるしかないほどに我々は追い詰められている…」
「…そんなの、勝手すぎる。」
王太子の言いたいことを理解したくない。この国の現状なんて知りたくなくて、首を振る。
「…私はもう巫女じゃない。…好きにして良いって、自由に生きていいって許されてるはずじゃないの?」
「…それは…」
「それを今更、こんなバカみたいなことを押し付けられるなんて。…王族の言葉ってそんなに軽いの?そんなに簡単に覆されちゃうものなの?」
「…」
黙り込んだ王太子が、その顔に苦痛を見せた。分かっている。彼だって、こんなことを望んでいる訳ではない。だけど、この男は、「国のため」という理由であれば、理不尽さえも強要出来る人間だということも知っている。
「…元々…」
下を向き、苦痛を吐き出すように言葉を紡ぐ王太子。
「…召喚された巫女は、私の妃として迎えることになっていた。」
「え…?」
小さく聞こえた呟きは王太子妃のもの。どうやら、これは、彼女も知らない話らしい。王太子妃を振り返ることなく、王太子が言葉を続ける。
「…歴代の巫女が子を産まないのは、この国の待遇、巫女に対する扱いに創世の巫女がお怒りになっているせいだという意見が教会から上がっていた。…過去、唯一、子を残した巫女は、当時の王弟に嫁いだ一人だけだったからな…」
「…」
「…先代巫女は、王の宮に入れはしたが、妃として遇されることはなかった。…結果は…」
禁書にある通り。彼女もまた、「魔力ある子」を産むことなく亡くなっている。
「…巫女を迎えるに当たり、身分的にも、年齢的にも、釣り合いが取れるのは王太子である私であろうということになっていた。…正妃として、巫女を娶るべきだと…」
「…そんな…!」
王太子の告白に、王太子妃の口から悲鳴が上がる。
「…すまない、シルヴィア。…君に明かすつもりはなかったが。」
「っ!?なぜっ!?なぜですかっ!?なぜ、私に隠し事などっ!」
「…私は、…私が妃にと望むのは、初めからずっと君一人だからだ。」
「っ!」
「召喚される巫女がどのような人物であろうと、私は妃に迎えるつもりはなかった。だからこそ…」
言って、疲れたようにため息をついた王太子。
「…だからこそ、アンバー・フォーリーンを取り立て、魔術師長として最大限の権利を与えていた。…彼さえ居れば、巫女召喚を確実に成功させることが出来る。…次の巫女召喚も、間違いなく成功するはずだった。」
「…それって…」
思わず、口にしてしまう。
「最低じゃない…、自分は嫌だから、他の人に押し付ける。そのために、また巫女召喚をするつもりだったなんて…」
「…そう、だな。」
頷いて、顔を上げた王太子と視線が合う。遠めに分かる、彼らしくない、卑屈な笑み。
「…だが、その担保があるからこそ、私はシルヴィアを妃に迎えることが出来た。…そして…」
「…」
「巫女、あなたに許された自由も、同じ担保があったからだと言えば、分かるか?」
「っ!?」
「…アンバー・フォーリーンが消えた今、あなたに許された自由はもはや形だけのもの。」
「じょう、っだんでしょうっ!」
信じたくなくて叫ぶけれど、自分の置かれた状況というのが、嫌でも分かってしまう。
逃げられない─
「…アンブロス夫人。」
王太子が立ち上がる。
「…どうか、あなたに、再び、この国を救って頂きたい。」
「っ!?」
深く、深く、頭を下げる王太子。彼に倣うように、背後で頭を下げる男達。
「…いや。」
「…この国を救えるのは、」
「嫌だってばっ!」
嫌だ嫌だ嫌だ─
離れたままの距離、彼らが近づいてくることはない。だけど、増していく、息苦しさ、圧迫される。押しつぶされそうになるのは、過去の記憶のせい。
あの頃、毎日のように感じていた重圧。「この国を救えるのはあなただけ」「誰もがあなたの降臨を待ちわびていた」「どうか、この国の巫女となり、守護の結界を」
嫌だった。巫女になんてなりたくなかった。
だけど、「私が巫女にならなければ国が滅びる?」「本当に国中の人が私が巫女になることを望んでるの?」「…もしも、拒否し続けたら?」
世界中に独りきり。誰も、味方なんていないと思っていた。怖くて、辛くて、張り続ける意地も限界で─
─受け入れたら、楽になる
「自分さえ我慢すれば上手くいく」「もう、辛い思いをすることもない」「…苦しいのも、きっと今だけ」
騙して、言い聞かせて、飲み込んで。
最終的に下した判断は、私をひどく惨めな気持ちにさせた。
そして、今も─
顔を上げた王太子と視線が合う。感情を押し殺したかのような無表情、その姿に、脳裏をよぎるものがあった。
(…ううん、ううん、違う…)
足りない空気を吸い込むため、深呼吸をする。少しだけ、気持ちが落ちついた。
(……今は、違う、…あの頃とは違う。)
私は、一人じゃない。
(私には…、セルジュが居る。)
彼ならきっと、こんなバカげた話は一蹴してくれるはず。きっと、味方になってくれる。「国のため」なんて理由で、私に理不尽を強いたりはしない。
そう、信じることが出来る。セルジュのことだけは、絶対に─
それに、
(もしかしたら、アンブロスの皆も…)
味方になってくれるかもしれない。国を敵に回すことになっても。
(…大丈夫、大丈夫。)
私は一人じゃない。
だから、今度は諦めない─
「…アンブロス夫人、頼む、落ち着いてくれ。一度、私の話を、」
「なんでそんな話聞かなくちゃいけないのよっ!?」
ああ、嫌だ嫌だ嫌だ─
「話なんて聞かない!あなた達の言い分なんて関係ないっ!」
「夫人、これは、あなたにしか頼めない、」
「知らないってばっ!」
立ち上がり、逃げ出す。扉へと駆け寄ってドアノブを引くが、その扉が開くことはない。
「っ!?」
ああ、また─
「…アンブロス夫人。」
「っ!?」
背後、聞こえた声に反射的に振り向いた。そこに立つ男を見上げる。
「私からも頼む。…殿下の話を、」
「来ないでっ!!」
いつの間に、この距離まで近づかれていたのか。手の届きそうな距離にある男の巨体から逃れるため、部屋の隅へと走る。
「…アンブロス夫人、どうか…」
「来ないでってばっ!ガイラスッ!それ以上、近づかないでっ!」
「…」
顔に苦渋をにじませる男、かつて、同じような状況で、彼には何度も拘束されたことがある。当時も恐怖を覚えたが、今はそれ以上に嫌悪が大きい。
「…来ないでっ…!」
上がった息を整えながら、自分の馬鹿さ加減を呪った。
(…最悪、最低、本っ当、バカすぎる…)
彼らを信用して、こんな状況に追い込まれて。
彼らへの怒りと、自分自身への怒りから、パニックに陥っていた思考が少しだけまともに動き出す。
(兎に角、今は、この状況から逃げ出すこと…)
話の内容から、命を取られることはないはずだから。
「…話は、聞く。…だから、離れて。…私に、触れないで。」
「…」
「…戻れ、ガイラス。」
ガイラスを呼び戻す王太子の声に、ガイラスが一歩を引いた。そのまま、定位置、王太子の背後へと回る彼の姿を確認してから、王太子へと向き直る。
「…アンブロス夫人、どうか、こちらへ掛けてくれないか?その場所では、」
「いい。ここで聞く。…さっさと話して。」
「…そうか。なら…」
部屋の隅、どれだけ距離をとっても、彼らがその気になれば直ぐに捕まってしまうだろう。分かっていても、彼らの近くに戻るなんて冗談じゃない。立ったまま、王太子が言葉を続けるのを待てば、深いため息が聞こえて─
「…アンバー・フォーリーンの暴走は、この国に致命的な損害を与えた。」
「…」
「彼の行った巫女召喚によって、召喚陣が損傷を受けている。」
「そん、しょう…?」
「ああ。…召喚陣の基盤である召喚の間の床に亀裂がいくつか…、現状では、修復は不可能だと判断された。」
淡々と告げられた言葉を飲み込んで、咀嚼して、漸く理解する。
「…それって、じゃあ…」
「ああ。…この国は巫女召喚を行う手段を失った。少なくとも、この国の技術が神代に追いつく、向こう数百年先までは…」
「…」
その言葉に、どう反応していいものか迷う。これから先、自分の居なくなった未来において、自分と同じ思いをする人間が居なくなったことは単純に良かったと思う。ただ、アンブロスの将来はまだ、巫女の存在を失っても万全だとは言い難い。
(…ううん、アンブロスはまだいい。何とかなる、…これから、何とかしてみせる。)
だけど、それが、この国全体に関してとなると─
「…この国には、巫女が二度と現れない可能性すらある。…だとすれば、我々が望むもの、期待するものが、あなたにも分かるだろう?」
「…知らない。」
「…僅かな望みであろうと、可能性があるならば、我々はそれに賭けるしかない。」
「知らないってば!」
「…結界の巫女と同等の魔力を持つ子の誕生。」
「っ!」
拒否しているのに。
告げられた内容の醜悪さに吐き気がする。人を、子どもを、都合の良い「モノ」のように扱おうとする傲慢さ─
「…私を含むこの場に居る三人は、国内でも上位の魔力持ちだ。その…、夫人と年も近く、知らぬ間柄ではない。…あなたが望むならば他の者を選ぶことも可能だが、出来るならば、」
「しないってばっ!」
「…」
「選ばないし!セルジュ以外の人の子どもなんて産まない!」
愛する人以外の誰かの子どもを産む。そこに至るまでの過程を全て無視して、結果だけを求めようとする彼らがおぞましくて仕方なかった。
「大体っ!」
視線を、部屋の奥、泰然と構え、薄っすら笑みさえ浮かべている王太子妃へと向ける。
「大体っ!こんなバカみたいな話!妃殿下やアイシャさんは認めてるのっ!?自分の夫が私と、…子どもを持つなんて、認められるのっ!?」
否定の言葉が欲しくて叫ぶが、視線の先の女性は優雅に微笑んだまま。
「あら?勿論、私は承知済みですわ。…アイシャ様におかれましても、…そうですね、感情はどうあれ、お立場的にご理解はされているのではないでしょうか?」
「っ!嘘っ!そんなの嘘っ!」
「嘘ではございません。」
言い切った王太子妃の顔から笑みが消える。怖いくらいに真剣な眼差しを向けられる。
「…私は王太子妃、将来、この国の王となられる殿下の唯一の妃です。」
「…」
「…殿下が王太子として望まれるなら、この国のために必要と判断されたことであれば、私に否やはありません。」
「っ!でも、だけどっ!そんなの嫌でしょうっ!?あなただって、本当は!」
「巫女様。私は、幼き頃より殿下の隣に立つと決めておりましたの。」
王太子妃が笑う。
「私は私の役目、王太子妃という立場を理解しております。『嫌』などという感情でその役目を放り出すつもりはございません。」
「っ!?」
(なに、なんで…)
理解出来ない。彼女の笑みが薄気味悪くて仕方ない。私が王太子を望む未来もあったと仄めかした時の彼女の反応、彼女が怒りを見せたのは、つい昨日のことだというのに。
「…そんな、…だって、妃殿下は、殿下を好き、…愛してるんでしょう?」
「ええ。勿論ですわ。」
「…」
「だからこそ、私は殿下の定めに最後まで従います。私は、死ぬその時まで、殿下の妃ですから。」
そう言い切る彼女には余裕すら感じられて、彼女が、この場での味方にはなり得ないことを知る。
「…でも、だけど…」
視線を王太子の居る方へと彷徨わせた。
「私の子どもが魔力を受け継ぐとは限らないじゃない…。実際、レナータ、私の子は魔力を受け継いでいないし…」
「…そう、だな。」
「禁書にだって、巫女の魔力を受け継ぐ子どもが産まれたっていう記録はなかった。絶望的だって…」
「ああ、それも承知している。それでも…」
「…」
「その、僅かな可能性に賭けるしかないほどに我々は追い詰められている…」
「…そんなの、勝手すぎる。」
王太子の言いたいことを理解したくない。この国の現状なんて知りたくなくて、首を振る。
「…私はもう巫女じゃない。…好きにして良いって、自由に生きていいって許されてるはずじゃないの?」
「…それは…」
「それを今更、こんなバカみたいなことを押し付けられるなんて。…王族の言葉ってそんなに軽いの?そんなに簡単に覆されちゃうものなの?」
「…」
黙り込んだ王太子が、その顔に苦痛を見せた。分かっている。彼だって、こんなことを望んでいる訳ではない。だけど、この男は、「国のため」という理由であれば、理不尽さえも強要出来る人間だということも知っている。
「…元々…」
下を向き、苦痛を吐き出すように言葉を紡ぐ王太子。
「…召喚された巫女は、私の妃として迎えることになっていた。」
「え…?」
小さく聞こえた呟きは王太子妃のもの。どうやら、これは、彼女も知らない話らしい。王太子妃を振り返ることなく、王太子が言葉を続ける。
「…歴代の巫女が子を産まないのは、この国の待遇、巫女に対する扱いに創世の巫女がお怒りになっているせいだという意見が教会から上がっていた。…過去、唯一、子を残した巫女は、当時の王弟に嫁いだ一人だけだったからな…」
「…」
「…先代巫女は、王の宮に入れはしたが、妃として遇されることはなかった。…結果は…」
禁書にある通り。彼女もまた、「魔力ある子」を産むことなく亡くなっている。
「…巫女を迎えるに当たり、身分的にも、年齢的にも、釣り合いが取れるのは王太子である私であろうということになっていた。…正妃として、巫女を娶るべきだと…」
「…そんな…!」
王太子の告白に、王太子妃の口から悲鳴が上がる。
「…すまない、シルヴィア。…君に明かすつもりはなかったが。」
「っ!?なぜっ!?なぜですかっ!?なぜ、私に隠し事などっ!」
「…私は、…私が妃にと望むのは、初めからずっと君一人だからだ。」
「っ!」
「召喚される巫女がどのような人物であろうと、私は妃に迎えるつもりはなかった。だからこそ…」
言って、疲れたようにため息をついた王太子。
「…だからこそ、アンバー・フォーリーンを取り立て、魔術師長として最大限の権利を与えていた。…彼さえ居れば、巫女召喚を確実に成功させることが出来る。…次の巫女召喚も、間違いなく成功するはずだった。」
「…それって…」
思わず、口にしてしまう。
「最低じゃない…、自分は嫌だから、他の人に押し付ける。そのために、また巫女召喚をするつもりだったなんて…」
「…そう、だな。」
頷いて、顔を上げた王太子と視線が合う。遠めに分かる、彼らしくない、卑屈な笑み。
「…だが、その担保があるからこそ、私はシルヴィアを妃に迎えることが出来た。…そして…」
「…」
「巫女、あなたに許された自由も、同じ担保があったからだと言えば、分かるか?」
「っ!?」
「…アンバー・フォーリーンが消えた今、あなたに許された自由はもはや形だけのもの。」
「じょう、っだんでしょうっ!」
信じたくなくて叫ぶけれど、自分の置かれた状況というのが、嫌でも分かってしまう。
逃げられない─
「…アンブロス夫人。」
王太子が立ち上がる。
「…どうか、あなたに、再び、この国を救って頂きたい。」
「っ!?」
深く、深く、頭を下げる王太子。彼に倣うように、背後で頭を下げる男達。
「…いや。」
「…この国を救えるのは、」
「嫌だってばっ!」
嫌だ嫌だ嫌だ─
離れたままの距離、彼らが近づいてくることはない。だけど、増していく、息苦しさ、圧迫される。押しつぶされそうになるのは、過去の記憶のせい。
あの頃、毎日のように感じていた重圧。「この国を救えるのはあなただけ」「誰もがあなたの降臨を待ちわびていた」「どうか、この国の巫女となり、守護の結界を」
嫌だった。巫女になんてなりたくなかった。
だけど、「私が巫女にならなければ国が滅びる?」「本当に国中の人が私が巫女になることを望んでるの?」「…もしも、拒否し続けたら?」
世界中に独りきり。誰も、味方なんていないと思っていた。怖くて、辛くて、張り続ける意地も限界で─
─受け入れたら、楽になる
「自分さえ我慢すれば上手くいく」「もう、辛い思いをすることもない」「…苦しいのも、きっと今だけ」
騙して、言い聞かせて、飲み込んで。
最終的に下した判断は、私をひどく惨めな気持ちにさせた。
そして、今も─
顔を上げた王太子と視線が合う。感情を押し殺したかのような無表情、その姿に、脳裏をよぎるものがあった。
(…ううん、ううん、違う…)
足りない空気を吸い込むため、深呼吸をする。少しだけ、気持ちが落ちついた。
(……今は、違う、…あの頃とは違う。)
私は、一人じゃない。
(私には…、セルジュが居る。)
彼ならきっと、こんなバカげた話は一蹴してくれるはず。きっと、味方になってくれる。「国のため」なんて理由で、私に理不尽を強いたりはしない。
そう、信じることが出来る。セルジュのことだけは、絶対に─
それに、
(もしかしたら、アンブロスの皆も…)
味方になってくれるかもしれない。国を敵に回すことになっても。
(…大丈夫、大丈夫。)
私は一人じゃない。
だから、今度は諦めない─
応援ありがとうございます!
12
お気に入りに追加
2,090
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる