2 / 4
2
しおりを挟む
夜会場から逃げ出した私は、自分がどの門をくぐり、どの通りを曲がり、どの角を折れたのか――そのほとんどを覚えていなかった。
気がつけば、ただ無我夢中で、足だけが勝手に前へ前へと動いていた。頭の中は真っ白で、考える余裕などなかった。ただ、背後から追いかけてくるかもしれない眩しい光や、人々の好奇と嘲笑が入り混じった視線から、必死に逃げたかった。
ドレスの裾が石畳に擦れる音さえ、やけに大きく響く。振り返れば、まだ誰かがそこにいるような気がして、何度も無意味に肩越しを見た。もちろん、そこには誰もいなかったけれど、それでも足を止めることはできなかった。
どれくらい歩いたのか。
息が上がり、胸が苦しくなり、ようやく立ち止まったとき、私は街の中心から外れた裏道に立っていた。昼間なら、行商人や近所の人々が行き交うはずの場所だろう。けれど、今はまるで世界から切り離されたかのように、人の気配がまったくなかった。
辺りは静まり返り、聞こえるのは自分の荒い呼吸と、どこか遠くでかすかに響く噴水の水音だけだった。その音が、やけに現実味を帯びて耳に残る。
足元の石畳は、夜の冷気をたっぷりと吸い込んでいて、薄い靴越しでもはっきりと冷たさが伝わってきた。まるで、今の私の心そのもののようだ、と、ぼんやり思う。
ふと顔を上げると、空は驚くほど高く、雲一つない夜闇の中に、無数の星が瞬いていた。
ついさっきまで浴びていた、まぶしい照明や耳を打つ音楽、計算された笑顔や社交辞令。それらが、最初から存在しなかったかのように、遠い別世界の出来事に感じられる。
「……もう、帰らなきゃ」
誰に聞かせるでもなく、小さく、ほとんど息のような声でつぶやいた。
それは決意というより、自分に言い聞かせるための言葉だった。震える声が、今の心細さを何より雄弁に物語っていた。
そのときだった。
足元の石畳に、不自然な黒い影が落ちていることに気づいた。
月明かりの角度のせいか、影は歪んだ形をしていて、最初は誰かが置き忘れた荷物か、壊れた木箱のようにも見えた。こんな裏道なら、そういうものが転がっていても不思議ではない。
けれど、もう一歩近づき、目を凝らした瞬間――私は思わず息をのんだ。
「え……?」
それは、人だった。
黒い鎧を身に着けた男性が、壁にもたれかかるようにして地面に崩れ落ちている。顔は影に覆われ、はっきりとは見えない。それでも、胸元がかすかに上下しているのがわかり、思わず安堵とも恐怖ともつかない感情が胸をよぎった。
生きている。
けれど、その呼吸は、あまりにも浅く、弱々しかった。
「だ、大丈夫ですか……?」
恐る恐る声をかけてみたが、返事はなかった。
代わりに、静寂だけが重く、圧迫するように周囲を満たす。
私は一瞬、その場に立ち尽くした。
今の私は、夜会で全てを失ったばかりだ。心も体も、すっかり疲れ切っている。誰かを助ける余裕なんて、本当はどこにもないはずだった。
関わらない方がいい。
そう頭では何度も繰り返した。こんな夜道で、正体もわからない男に近づくなんて、危険に決まっている。
それなのに――足が、勝手に動いた。
「血……」
暗がりでもはっきりわかるほど、彼の服は赤く染まっていた。その色を見た瞬間、胸の奥がひやりと冷え、指先がかすかに震えた。
考えるより先に、私はポケットからハンカチを取り出していた。夜会用に持っていた、真っ白な布だ。こんな形で使うことになるなんて、想像もしなかった。
「ちょっと、動かないでくださいね。今、止血しますから」
自分でもわかるほど、声が震えていた。
相手が誰なのか、どんな立場の人なのか――そんなことは、頭からすっかり抜け落ちていた。ただ、このまま放っておくことだけは、どうしてもできなかった。
傷は深そうだったが、無茶な動きをしていなければ、きっと助かる。
そう信じて、私はできる限り丁寧に布を当て、そっと圧迫する。血が滲むたびに、心臓が跳ねる。それでも、手を止めることはなかった。
祈るような気持ちで、何度も呼吸を確かめた。
「……君」
かすれた、低い声が耳に届いた。
「あ、気がつきましたか? よかった……。今は、無理にしゃべらなくていいですから」
男性は、ゆっくりと目を開け、私をじっと見つめた。その視線は鋭く、どこか張り詰めている。それなのに、不思議と恐怖は感じなかった。
「なぜ……逃げない」
掠れた声が、静かに問いを投げかける。
「え?」
「こんな場所で、倒れている男に近づくのは……危険だ」
私は一瞬考え、それから、正直な気持ちをそのまま口にした。
「そうかもしれません。でも、放っておいたら、もっと危ないです」
彼はしばらく黙り込み、星空を仰ぐように視線を逸らした。そして、短く息をつく。
「……変わった娘だ」
それが、彼の最初の評価だった。
応急処置を終えると、私はそっと立ち上がった。これ以上、今の私にできることはない。
「ちゃんとした治療を、早く受けてください。これは、本当に応急処置だけですから」
「名は……?」
そう聞かれ、私は静かに首を振った。
「名乗るほどの者じゃありません。あなたも、無理に教えなくていいです」
そう言って背を向けた。これ以上、関わるつもりはなかった。
あの夜の出来事は、私の中では、ただの夢のような、曖昧な記憶になるはずだった。
けれど、数日後。
私の元に、王城からの呼び出しが届いた。
「……私が、ですか?」
使いの兵士に思わず聞き返すと、彼は静かにうなずいた。
「正式な招待です。断ることはできません」
理由はわからなかった。
それでも、逃げることは許されず、私は王城へ向かった。
広い広間。
整列した騎士たち。
その中央に、見覚えのある背中があった。
黒い鎧。
まっすぐで、揺るぎない立ち姿。
――あの夜、裏道に倒れていた男性だった。
「来てくれて、感謝する」
振り返った彼は、あのときとは比べものにならないほど堂々としていた。
「紹介しよう。こちらは、王直属騎士団長。王の右腕と呼ばれる方だ」
周囲がざわめく。
「……え?」
頭が、まったく追いつかなかった。
「そして――数日前、命を救ってくれた恩人だ」
私は慌てて首を振る。
「そ、そんな……本当に、たまたま通りかかっただけです」
騎士団長は、わずかに口元をゆるめた。
「君は、逃げることもできた。だが、そうしなかった。それは、判断力と勇気の証だ」
言葉を失う私に、彼は続ける。
「夜会での出来事も、すでに聞いている」
胸が、ぎゅっと縮んだ。
「君は、理不尽に切り捨てられた。だが、それは君が弱いからではない」
彼は、まっすぐに私を見据えた。
「君は、弱くない。ただ、踏みにじられていただけだ」
その言葉が、胸の奥に、静かに、しかし確かに沈んでいく。
「私は、君に庇護を与えたい。王城で学び、力を取り戻すといい。無理にとは言わない」
私は、しばらく黙っていた。
自分がそんな提案を受ける価値があるとは、どうしても思えなかった。
「……私、何もできません」
絞り出すように言うと、彼は静かに首を横に振った。
「できることがない者など、いない。君はすでに、それを示している」
胸の奥で、何かが、ほんのわずかに動いた。
長い間、私は「役に立たない」と言われ続け、それを疑いもせず信じてきた。
けれど――。
「少し、考えさせてください」
「ああ。待とう」
その声は、静かで、揺るぎなかった。
その日を境に、私の中に巣食っていた自己否定は、少しずつ、しかし確実に、音を立てて崩れ始めていた。
気がつけば、ただ無我夢中で、足だけが勝手に前へ前へと動いていた。頭の中は真っ白で、考える余裕などなかった。ただ、背後から追いかけてくるかもしれない眩しい光や、人々の好奇と嘲笑が入り混じった視線から、必死に逃げたかった。
ドレスの裾が石畳に擦れる音さえ、やけに大きく響く。振り返れば、まだ誰かがそこにいるような気がして、何度も無意味に肩越しを見た。もちろん、そこには誰もいなかったけれど、それでも足を止めることはできなかった。
どれくらい歩いたのか。
息が上がり、胸が苦しくなり、ようやく立ち止まったとき、私は街の中心から外れた裏道に立っていた。昼間なら、行商人や近所の人々が行き交うはずの場所だろう。けれど、今はまるで世界から切り離されたかのように、人の気配がまったくなかった。
辺りは静まり返り、聞こえるのは自分の荒い呼吸と、どこか遠くでかすかに響く噴水の水音だけだった。その音が、やけに現実味を帯びて耳に残る。
足元の石畳は、夜の冷気をたっぷりと吸い込んでいて、薄い靴越しでもはっきりと冷たさが伝わってきた。まるで、今の私の心そのもののようだ、と、ぼんやり思う。
ふと顔を上げると、空は驚くほど高く、雲一つない夜闇の中に、無数の星が瞬いていた。
ついさっきまで浴びていた、まぶしい照明や耳を打つ音楽、計算された笑顔や社交辞令。それらが、最初から存在しなかったかのように、遠い別世界の出来事に感じられる。
「……もう、帰らなきゃ」
誰に聞かせるでもなく、小さく、ほとんど息のような声でつぶやいた。
それは決意というより、自分に言い聞かせるための言葉だった。震える声が、今の心細さを何より雄弁に物語っていた。
そのときだった。
足元の石畳に、不自然な黒い影が落ちていることに気づいた。
月明かりの角度のせいか、影は歪んだ形をしていて、最初は誰かが置き忘れた荷物か、壊れた木箱のようにも見えた。こんな裏道なら、そういうものが転がっていても不思議ではない。
けれど、もう一歩近づき、目を凝らした瞬間――私は思わず息をのんだ。
「え……?」
それは、人だった。
黒い鎧を身に着けた男性が、壁にもたれかかるようにして地面に崩れ落ちている。顔は影に覆われ、はっきりとは見えない。それでも、胸元がかすかに上下しているのがわかり、思わず安堵とも恐怖ともつかない感情が胸をよぎった。
生きている。
けれど、その呼吸は、あまりにも浅く、弱々しかった。
「だ、大丈夫ですか……?」
恐る恐る声をかけてみたが、返事はなかった。
代わりに、静寂だけが重く、圧迫するように周囲を満たす。
私は一瞬、その場に立ち尽くした。
今の私は、夜会で全てを失ったばかりだ。心も体も、すっかり疲れ切っている。誰かを助ける余裕なんて、本当はどこにもないはずだった。
関わらない方がいい。
そう頭では何度も繰り返した。こんな夜道で、正体もわからない男に近づくなんて、危険に決まっている。
それなのに――足が、勝手に動いた。
「血……」
暗がりでもはっきりわかるほど、彼の服は赤く染まっていた。その色を見た瞬間、胸の奥がひやりと冷え、指先がかすかに震えた。
考えるより先に、私はポケットからハンカチを取り出していた。夜会用に持っていた、真っ白な布だ。こんな形で使うことになるなんて、想像もしなかった。
「ちょっと、動かないでくださいね。今、止血しますから」
自分でもわかるほど、声が震えていた。
相手が誰なのか、どんな立場の人なのか――そんなことは、頭からすっかり抜け落ちていた。ただ、このまま放っておくことだけは、どうしてもできなかった。
傷は深そうだったが、無茶な動きをしていなければ、きっと助かる。
そう信じて、私はできる限り丁寧に布を当て、そっと圧迫する。血が滲むたびに、心臓が跳ねる。それでも、手を止めることはなかった。
祈るような気持ちで、何度も呼吸を確かめた。
「……君」
かすれた、低い声が耳に届いた。
「あ、気がつきましたか? よかった……。今は、無理にしゃべらなくていいですから」
男性は、ゆっくりと目を開け、私をじっと見つめた。その視線は鋭く、どこか張り詰めている。それなのに、不思議と恐怖は感じなかった。
「なぜ……逃げない」
掠れた声が、静かに問いを投げかける。
「え?」
「こんな場所で、倒れている男に近づくのは……危険だ」
私は一瞬考え、それから、正直な気持ちをそのまま口にした。
「そうかもしれません。でも、放っておいたら、もっと危ないです」
彼はしばらく黙り込み、星空を仰ぐように視線を逸らした。そして、短く息をつく。
「……変わった娘だ」
それが、彼の最初の評価だった。
応急処置を終えると、私はそっと立ち上がった。これ以上、今の私にできることはない。
「ちゃんとした治療を、早く受けてください。これは、本当に応急処置だけですから」
「名は……?」
そう聞かれ、私は静かに首を振った。
「名乗るほどの者じゃありません。あなたも、無理に教えなくていいです」
そう言って背を向けた。これ以上、関わるつもりはなかった。
あの夜の出来事は、私の中では、ただの夢のような、曖昧な記憶になるはずだった。
けれど、数日後。
私の元に、王城からの呼び出しが届いた。
「……私が、ですか?」
使いの兵士に思わず聞き返すと、彼は静かにうなずいた。
「正式な招待です。断ることはできません」
理由はわからなかった。
それでも、逃げることは許されず、私は王城へ向かった。
広い広間。
整列した騎士たち。
その中央に、見覚えのある背中があった。
黒い鎧。
まっすぐで、揺るぎない立ち姿。
――あの夜、裏道に倒れていた男性だった。
「来てくれて、感謝する」
振り返った彼は、あのときとは比べものにならないほど堂々としていた。
「紹介しよう。こちらは、王直属騎士団長。王の右腕と呼ばれる方だ」
周囲がざわめく。
「……え?」
頭が、まったく追いつかなかった。
「そして――数日前、命を救ってくれた恩人だ」
私は慌てて首を振る。
「そ、そんな……本当に、たまたま通りかかっただけです」
騎士団長は、わずかに口元をゆるめた。
「君は、逃げることもできた。だが、そうしなかった。それは、判断力と勇気の証だ」
言葉を失う私に、彼は続ける。
「夜会での出来事も、すでに聞いている」
胸が、ぎゅっと縮んだ。
「君は、理不尽に切り捨てられた。だが、それは君が弱いからではない」
彼は、まっすぐに私を見据えた。
「君は、弱くない。ただ、踏みにじられていただけだ」
その言葉が、胸の奥に、静かに、しかし確かに沈んでいく。
「私は、君に庇護を与えたい。王城で学び、力を取り戻すといい。無理にとは言わない」
私は、しばらく黙っていた。
自分がそんな提案を受ける価値があるとは、どうしても思えなかった。
「……私、何もできません」
絞り出すように言うと、彼は静かに首を横に振った。
「できることがない者など、いない。君はすでに、それを示している」
胸の奥で、何かが、ほんのわずかに動いた。
長い間、私は「役に立たない」と言われ続け、それを疑いもせず信じてきた。
けれど――。
「少し、考えさせてください」
「ああ。待とう」
その声は、静かで、揺るぎなかった。
その日を境に、私の中に巣食っていた自己否定は、少しずつ、しかし確実に、音を立てて崩れ始めていた。
137
あなたにおすすめの小説

崖からポイ捨てされた不運令嬢ですが、銀髪イケメン竜王に『最愛の伴侶』としてスカウトされました!
阿里
恋愛
不作も天災も、全部わたしのせい!?
「不運な女」と虐げられ、生贄として崖から捨てられたわたし、ミラ。
でも、落ちた先で待っていたのは、まぶしいほど綺麗な銀髪の竜王・アルベルト様でした!
「君がいたから、この国は守られていたんだよ」
えっ、わたしって実はすごい聖女だったの!?
竜宮城で贅沢三昧&溺愛生活スタート!
そんな中、わたしを捨てて大ピンチになった元婚約者が「ミラ、戻ってきて!」と泣きついてきて……。

「華がない」と婚約破棄されたけど、冷徹宰相の恋人として帰ってきたら……
阿里
恋愛
「貴族の妻にはもっと華やかさが必要なんだ」
そんな言葉で、あっさり私を捨てたラウル。
涙でくしゃくしゃの毎日……だけど、そんな私に声をかけてくれたのは、誰もが恐れる冷徹宰相ゼノ様だった。
気がつけば、彼の側近として活躍し、やがては恋人に――!
数年後、舞踏会で土下座してきたラウルに、私は静かに言う。
「あなたが捨てたのは、私じゃなくて未来だったのね」

婚約破棄された夜、最強魔導師に「番」だと告げられました
阿里
恋愛
学院の祝宴で告げられた、無慈悲な婚約破棄。
魔力が弱い私には、価値がないという現実。
泣きながら逃げた先で、私は古代の遺跡に迷い込む。
そこで目覚めた彼は、私を見て言った。
「やっと見つけた。私の番よ」
彼の前でだけ、私の魔力は輝く。
奪われた尊厳、歪められた運命。
すべてを取り戻した先にあるのは……

地味令嬢と嘲笑された私ですが、第二王子に見初められて王妃候補になったので、元婚約者はどうぞお幸せに
阿里
恋愛
「君とは釣り合わない」――そう言って、騎士団長の婚約者はわたしを捨てた。
選んだのは、美しくて派手な侯爵令嬢。社交界でも人気者の彼女に、わたしは敵うはずがない……はずだった。
けれどその直後、わたしが道で偶然助られた男性は、なんと第二王子!?
「君は特別だよ。誰よりもね」
優しく微笑む王子に、わたしの人生は一変する。

婚約破棄されましたが、今さら後悔されても困ります
阿里
恋愛
復讐なんて興味ありません。でも、因果応報って本当にあるんですね。あなたのおかげで、私の幸せが始まりました。
・・・
政略結婚の駒として扱われ、冷酷非道な婚約者クラウスに一方的に婚約破棄を突きつけられた令嬢エマ・セルディ。
名誉も財産も地に堕とされ、愛も希望も奪われたはずの彼女だったが、その胸には消せない復讐と誇りが燃えていた。
そんな折、誠実で正義感あふれる高位貴族ディーン・グラスフィットと運命的に出会い、新たな愛と絆を育む。
ディーンの支えを受け、エマはクラウスの汚職の証拠を暴き、公の場で彼を徹底的に追い詰める──。

私を捨てた婚約者へ――あなたのおかげで幸せです
阿里
恋愛
「役立たずは消えろ」
理不尽な理由で婚約を破棄された伯爵令嬢アンナ。
涙の底で彼女を救ったのは、かつて密かに想いを寄せてくれた完璧すぎる男性――
名門貴族、セシル・グラスフィット。
美しさ、強さ、優しさ、すべてを兼ね備えた彼に愛され、
アンナはようやく本当の幸せを手に入れる。
そんな中、落ちぶれた元婚約者が復縁を迫ってくるけれど――
心優しき令嬢が報われ、誰よりも愛される、ざまぁ&スカッと恋愛ファンタジー
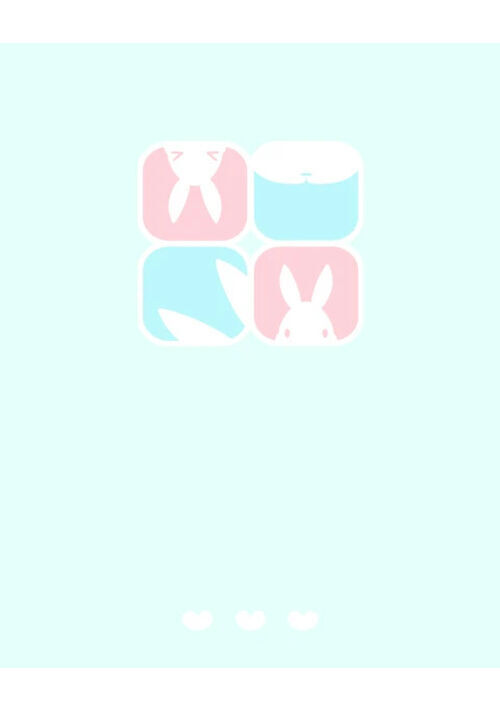
【完結】王太子に婚約破棄され、父親に修道院行きを命じられた公爵令嬢、もふもふ聖獣に溺愛される〜王太子が謝罪したいと思ったときには手遅れでした
まほりろ
恋愛
【完結済み】
公爵令嬢のアリーゼ・バイスは一学年の終わりの進級パーティーで、六年間婚約していた王太子から婚約破棄される。
壇上に立つ王太子の腕の中には桃色の髪と瞳の|庇護《ひご》欲をそそる愛らしい少女、男爵令嬢のレニ・ミュルべがいた。
アリーゼは男爵令嬢をいじめた|冤罪《えんざい》を着せられ、男爵令嬢の取り巻きの令息たちにののしられ、卵やジュースを投げつけられ、屈辱を味わいながらパーティー会場をあとにした。
家に帰ったアリーゼは父親から、貴族社会に向いてないと言われ修道院行きを命じられる。
修道院には人懐っこい仔猫がいて……アリーゼは仔猫の愛らしさにメロメロになる。
しかし仔猫の正体は聖獣で……。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
・ざまぁ有り(死ネタ有り)・ざまぁ回には「ざまぁ」と明記します。
・婚約破棄、アホ王子、モフモフ、猫耳、聖獣、溺愛。
2021/11/27HOTランキング3位、28日HOTランキング2位に入りました! 読んで下さった皆様、ありがとうございます!
誤字報告ありがとうございます! 大変助かっております!!
アルファポリスに先行投稿しています。他サイトにもアップしています。

婚約破棄の帰り道
春月もも
恋愛
婚約破棄を宣言されたその日、彼女はただ静かに頷いた。
拍手の中を背筋を伸ばして歩き、令嬢としての役目をひとつ終える。
やがて醜聞にまみれ、「傷物」「行き遅れ」と囁かれながらも、
薔薇と風だけを相手に庭でお茶を飲む日々。
気品だけを残して、心はゆっくりと枯れていく。
――そんな彼女の前に現れたのは、
かつて身分違いで諦めた幼馴染、隣国の若き王だった。
「迎えに来た」
静かな破滅の先に訪れる、軍を率いた一途な求婚。
これは、声を荒げずにすべてを覆す、上品な逆転劇。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















