あなたにおすすめの小説

嘘つくつもりはなかったんです!お願いだから忘れて欲しいのにもう遅い。王子様は異世界転生娘を溺愛しているみたいだけどちょっと勘弁して欲しい。
季邑 えり
恋愛
異世界転生した記憶をもつリアリム伯爵令嬢は、自他ともに認めるイザベラ公爵令嬢の腰ぎんちゃく。
今日もイザベラ嬢をよいしょするつもりが、うっかりして「王子様は理想的な結婚相手だ」と言ってしまった。それを偶然に聞いた王子は、早速リアリムを婚約者候補に入れてしまう。
王子様狙いのイザベラ嬢に睨まれたらたまらない。何とかして婚約者になることから逃れたいリアリムと、そんなリアリムにロックオンして何とかして婚約者にしたい王子。
婚約者候補から逃れるために、偽りの恋人役を知り合いの騎士にお願いすることにしたのだけど…なんとこの騎士も一筋縄ではいかなかった!
おとぼけ転生娘と、麗しい王子様の恋愛ラブコメディー…のはず。
イラストはベアしゅう様に描いていただきました。

契約妻に「愛さない」と言い放った冷酷騎士、一分後に彼女の健気さが性癖に刺さって理性が崩壊した件
水月
恋愛
冷酷騎士様の「愛さない」は一分も持たなかった件の旦那様視点短編となります。
「君を愛するつもりはない」
結婚初夜、帝国最強の冷酷騎士ヴォルフラム・ツヴァルト公爵はそう言い放った。
出来損ないと蔑まれ、姉の代わりの生贄として政略結婚に差し出されたリーリア・ミラベルにとって、それはむしろ救いだった。
愛を期待されないのなら、失望させることもない。
契約妻として静かに役目を果たそうとしたリーリアは、緩んだ軍服のボタンを自らの銀髪と微弱な強化魔法で直す。
ただ「役に立ちたい」という一心だった。
――その瞬間。
冷酷騎士の情緒が崩壊した。
「君は、自分の価値を分かっていない」
開始一分で愛さない宣言は撤回。
無自覚に自己評価が低い妻に、激重独占欲を発症した最強騎士が爆誕する。

第一王女は制度で王になる ―揺らがぬ王国の継承譚―
しおしお
恋愛
第一王女として生まれたその日から、彼女は“未来の王”だった。
王位継承は男女を問わない――。
明文化された制度は揺らがず、王国は安定を保っていた。だが、制度があるだけでは足りない。市場の動揺、干ばつ、国境の示威、旧勢力の揺さぶり。王国は何度も試される。
そのたびに選び、学び、積み重ねていく王女。
分配の判断、持続の視点、怒りを制する理性。
守られる存在から、守る存在へ。
これは“ざまぁ”の物語ではない。
だが、女王は結果で黙らせる。
「制度は人が守らねばなりません」
揺らがぬ王国を築いた父母のもとで育ち、やがて自ら王冠を戴く少女。
血ではなく覚悟で継承する、静かで力強い女王誕生譚。
生まれる前から王だった少女が、選び続けて本当の王になるまでの十六年。

わたくしが社交界を騒がす『毒女』です~旦那様、この結婚は離婚約だったはずですが?
澤谷弥(さわたに わたる)
恋愛
※完結しました。
離婚約――それは離婚を約束した結婚のこと。
王太子アルバートの婚約披露パーティーで目にあまる行動をした、社交界でも噂の毒女クラリスは、辺境伯ユージーンと結婚するようにと国王から命じられる。
アルバートの側にいたかったクラリスであるが、国王からの命令である以上、この結婚は断れない。
断れないのはユージーンも同じだったようで、二人は二年後の離婚を前提として結婚を受け入れた――はずなのだが。
毒女令嬢クラリスと女に縁のない辺境伯ユージーンの、離婚前提の結婚による空回り恋愛物語。
※以前、短編で書いたものを長編にしたものです。
※蛇が出てきますので、苦手な方はお気をつけください。

二度捨てられた白魔女王女は、もうのんびりワンコと暮らすことにしました ~え? ワンコが王子とか聞いてません~
吉高 花
恋愛
魔力があった、ただそれだけの理由で王女なのに捨て子として育ったマルガレーテは、隣国との政略結婚のためだけにある日突然王女として引っぱりだされ、そして追放同然に邪悪な国と恐れられるルトリアへと送られた。
そしてルトリアでの魔力判定により、初めて自分が白の魔力を持つ者と知る。しかし白の魔力を持つ者は、ルトリアではもれなく短命となる運命だった。
これでは妃なんぞには出来ぬとまたもや辺鄙な離宮に追放されてしまったマルガレーテ。
しかし彼女はその地で偶然に病床の王妃を救い、そして流れ着いたワンコにも慕われて、生まれて初めて自分が幸せでいられる居場所を得る。
もうこのまま幸せにここでのんびり余生を送りたい。そう思っていたマルガレーテは、しかし愛するワンコが実は自分の婚約者である王子だったと知ったとき、彼を救うために、命を賭けて自分の「レイテの魔女」としての希有な能力を使うことを決めたのだった。
不幸な生い立ちと境遇だった王女が追放先でひたすら周りに愛され、可愛がられ、大切な人たちを救ったり救われたりしながら幸せになるお話。
このお話は「独身主義の魔女ですが、ワンコな公爵様がなぜか離してくれません」のスピンオフとなりますが、この話だけでも読めるようになっています。

ストーカー婚約者でしたが、転生者だったので経歴を身綺麗にしておく
犬野きらり
恋愛
リディア・ガルドニ(14)、本日誕生日で転生者として気付きました。私がつい先程までやっていた行動…それは、自分の婚約者に対して重い愛ではなく、ストーカー行為。
「絶対駄目ーー」
と前世の私が気づかせてくれ、そもそも何故こんな男にこだわっていたのかと目が覚めました。
何の物語かも乙女ゲームの中の人になったのかもわかりませんが、私の黒歴史は証拠隠滅、慰謝料ガッポリ、新たな出会い新たな人生に進みます。
募集 婿入り希望者
対象外は、嫡男、後継者、王族
目指せハッピーエンド(?)!!
全23話で完結です。
この作品を気に留めて下さりありがとうございます。感謝を込めて、その後(直後)2話追加しました。25話になりました。

地味令嬢は結婚を諦め、薬師として生きることにしました。口の悪い女性陣のお世話をしていたら、イケメン婚約者ができたのですがどういうことですか?
石河 翠
恋愛
美形家族の中で唯一、地味顔で存在感のないアイリーン。婚約者を探そうとしても、失敗ばかり。お見合いをしたところで、しょせん相手の狙いはイケメンで有名な兄弟を紹介してもらうことだと思い知った彼女は、結婚を諦め薬師として生きることを決める。
働き始めた彼女は、職場の同僚からアプローチを受けていた。イケメンのお世辞を本気にしてはいけないと思いつつ、彼に惹かれていく。しかし彼がとある貴族令嬢に想いを寄せ、あまつさえ求婚していたことを知り……。
初恋から逃げ出そうとする自信のないヒロインと、大好きな彼女の側にいるためなら王子の地位など喜んで捨ててしまう一途なヒーローの恋物語。ハッピーエンドです。
この作品は、小説家になろう及びエブリスタにも投稿しております。
扉絵はあっきコタロウさまに描いていただきました。
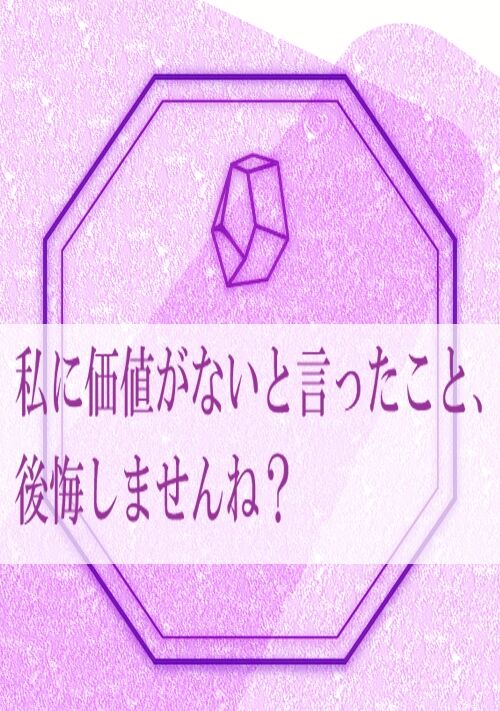
私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね?
みこと。
恋愛
鉛色の髪と目を持つクローディアは"鉱石姫"と呼ばれ、婚約者ランバートからおざなりに扱われていた。
「俺には"宝石姫"であるタバサのほうが相応しい」そう言ってランバートは、新年祭のパートナーに、クローディアではなくタバサを伴う。
(あんなヤツ、こっちから婚約破棄してやりたいのに!)
現代日本にはなかった身分差のせいで、伯爵令嬢クローディアは、侯爵家のランバートに逆らえない。
そう、クローディアは転生者だった。現代知識で鉱石を扱い、カイロはじめ防寒具をドレス下に仕込む彼女は、冷えに苦しむ他国の王女リアナを助けるが──。
なんとリアナ王女の正体は、王子リアンで?
この出会いが、クローディアに新しい道を拓く!
※小説家になろう様でも「私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね? 〜不実な婚約者を見限って。冷え性令嬢は、熱愛を希望します」というタイトルで掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















