50 / 59
翼の標
ep3
しおりを挟む
アリシアはナハトの後を追いかけながら歩いていたのだが、ふと、だいぶ日が高くなってきたのを見てお腹がキュルキュルと情けない音を立てた。
「…あ」
朝から何も食べていない。そのことに気が付いたが、それを抑える前に腹が鳴ってしまい、ナハトの頭の上に乗っている飛燕が振り返った。
だが、何を思ったのか、思いついたような顔で相棒を見た。
「ナハト、そう言えばご飯の時間だね」
ナハトが頷いた。
「そうだな…」
そして、アリシアの方を振り返り、口元を小さく綻ばせる。
「ほら」
アリシアは彼が鞄から取り出して放り投げたリンゴを一つ受け取っていた。
「腹ペコさん、一つ食べておけ」
「…あっ…」
顔を真っ赤にしたアリシアの腹がさらに大きな音で鳴ったのを聞いてナハトはフードを目深にかぶり直しながら楽し気に声を弾ませた。
「薬なんて仕込むわけないだろうが」
「…そうではなく、いつから…気が付いて?」
「俺たちの後をついてきた辺りから、かな。あんたの足音はずっと聞こえていたし、草木のガサガサいう音とか、足を忍ばせているつもりかもしれないが、バレバレだ」
「う…」
アリシアがゆっくりと姿を現すと、ナハトは倒木に腰を下ろしてリンゴをシャクリと一口齧る。
「あんたもラクラを探しているんだろう?」
「…なんで、それを?」
「まあ、俺のいる会社は色々と情報網があるだけだ。一枚岩じゃないが、それでも利用価値のある、…な」
アリシアも遠慮がちにナハトと少し距離を取って倒木に腰掛けた。そして、エプロンでリンゴを磨いてからシャクリと一口齧る。
「あ、美味しい…」
「アーネア商会のリンゴは最高に旨いからな。初めてするキスの味、だそうだ?」
アリシアが思わずむせかえったが、ナハトはどこ吹く風でリンゴを齧っている。
「おちょくらないでください。――でも、なぜ疑問形なのです?」
「口と口でしたことなんてないからな。そこまで気持ちが傾かないというか…前世の記憶なんて”眠った”あとはほとんど覚えていないし、キスの味も覚えていない」
彼女は首筋に手をやって顔を真っ赤にしながら頬を膨らませた。
「で、でも! でも、私の首筋に…!」
「それはマーキングみたいなものだ。とはいえ、シリウスが騒ぐから加護は与えられないんだが」
「騒ぐって…」
「まあ、いろいろあるんだよ。聖龍同士だってな? …とにかく、それは俺からのお守りみたいなものだ。変わった経歴だからどういうやつなのかと思ってみたら、よく淘汰されずに生き残ってきたと思えるくらい天然で、変わったやつだったし?」
「…それは怒ればいいのか、笑えばいいのかわからないのですが…?」
「とりあえず笑っておけば可愛いと思うな」
飛燕がそう言うと、ナハトが飛燕の首根っこをつかまえて呆れ顔をした。
「意外だな。お前が好んで焼き鳥になりたいというとは…」
「や、やだなぁ、ナハト。僕はいつだって君の味方だよ?」
「余計なことは言うな」
リンゴを食べ終えた後に芯を魔法で焼却して灰にし、ペコッと軽くデコピンをしたナハトと、デコピンを食らってクラクラしているように見える飛燕を見比べながら、アリシアはちょっと吹き出した。
「仲がいいんですね?」
「相棒だからね。それに、僕がナハトを選んだんだから仲良くないわけないでしょ? ただ、ナハトはこう見えて人見知りだからとっつきにくいけどね」
アリシアも何とか食べきってリンゴの芯を地面に魔法で埋めると、立ち上がった。
「人見知りには見えませんけどね」
「見えないでしょ? アリシアさんが無害そうなオーラを放っているからナハトも気楽にしているだけで、普段は絶対に感情も見せないし、むしろ冷徹って感じなんだよ。本当は優しいのにね」
ナハトは不機嫌そうに相棒をつまみ上げた。
「優しくなんかない。単に、欲しいものを欲し、欲しくないものには感情を使う義務もないってだけだ」
「また、そんなことを言って~」
飛燕はそう言ったが、ナハトはそれを露骨に無視して立ち上がり、歩き出した。
慌ててアリシアも彼を追いかけ、何とか横に並んだ。
「ラクラはどこにいるんです?」
「体の部分がすっぽりと覆われるような、そういう空間がラクラはとても好きなんだそうだ。岩陰の傍とか、鍾乳洞の奥の、行き止まりの吹き抜けスペースみたいな場所…とか」
「探知魔法は?」
「この森では使用できない。そもそも、ラクラはシャイなんだ。だから、長い年月をかけてラクラは身を隠すために探知魔法を阻害する体質を身に着けた。――とはいえ、見た目はバレバレなんだがな」
ナハトは歩幅を緩めて歩いていたが、ふと、足を止めた。
「…雲行きが怪しくなってきたな」
「え? でも、結構晴れていますよ?」
アリシアが不思議そうな顔をするのも無理はなく、少し上空に雲が浮かんでいるものの、雨が降る気配はみじんも感じられなかった。
「俺たち聖龍は魔力変化に敏感だ。一時間後に曇ってくる。夕食の食材と、休憩を取るための場所を探した方がよさそうだな」
「曇るだけで雨が降るとは…」
アリシアは困惑した顔をしていたが、彼と一緒に歩いているうちに本当に空が曇り始めた。
飛燕が見つけた洞窟に入った後、数分後には本降りの雨が降り始めていた。
それを見ながらアリシアは不安げな顔をした。
「ルピルが待っているのにこれでは…」
「星獣は簡単に死なない。あまり根詰めるとこっちが危ないだけだ」
ナハトがそう言いながら洞窟に来る途中でかき集めてきた薪代わりの枯れ枝などを窪みに入れ、そこに魔法で火をつけた。
すると焚火が完成し仄かにあたたかくなった。
飛燕がのんきに告げる。
「アリシアさんも焚火に当たらないの? 風邪をひいちゃうよ?」
「え、あ、ありがとうございます」
それでも浮かない表情ではあったが、アリシアはトボトボと焚火の傍にやってきて、腰を下ろした。
「そういえば、一緒にギュスターヴ様もいたのですが…置いてきちゃいました」
「アレのことは気にしなくていい。それより、腹ごしらえだな」
「アレって…」
アリシアが不安そうな顔をすると、ナハトは小さく首を横に振る。
「ギュスターヴは心配いらないし、ルピルはそもそも青の眷属だ。雨の日なんかは割と調子も良くなる。ラクラは雨の中でも動き続けられるが、俺たちはそうじゃない。キチンと食べて、しっかりと休んだら出発する。――いいな?」
「は、はい…って、なんで仕切っているんですか!」
アリシアがむぅっと頬を膨らませると、ナハトは鞄から干し肉とクラッカーを取り出した。
「野営は慣れているんでね」
「…ううっ」
干し肉を剣に変えた飛燕でスライスし、クラッカーに乗せてアリシアに差し出した。
「準備がいいんですね…」
「ラクラが簡単に見つかってたまるか。前は丸三日間かかった。だが、時間をかけるだけの価値はあるからな。ラクラの花や木は本当に妙薬だ」
彼はフードを目深にかぶり直し、焚火を挟んでアリシアの真向かいに腰を下ろした。
「あなたもどこか体調が…?」
「どうしても必要な人がいる。一年に一回、必ず」
アリシアはそれ以上聞く勇気がなく、モグモグと干し肉を乗せたクラッカーを食べ、それ以降は無言で過ごした。
だが、しばらくしてアリシアは小さく欠伸を漏らす。
「眠いなら寝てもいいぞ。見張りをしておくから」
「…交代制にしましょうよ」
「俺と飛燕で何とかなるから気にしなくていい。それに、明日もかなり歩く。いいから眠っておけ」
「……私が眠っている間に、変なこと…しないで、くださ、い…ね」
アリシアは眠そうに大きく欠伸をすると、ぶるっと小さく身震いした。ナハトが呆れたように肩をすくめ、アリシアの隣に腰を下ろす。
「嫌だろうがぴったりとくっついていた方が寒くないぞ」
「…は、い…」
微かに返事をしたものの、アリシアが寝息を立て始めてしまい、ナハトは彼女の肩を抱くようにして肩を貸し、凭れさせてやった。
穏やかに眠るアリシアの横顔を眺めながらナハトは口元に苦笑いを浮かべた。
「…ここまで素直に信じられると心苦しいものがあるな、飛燕」
飛燕は小首を傾げた。
「いいじゃない? いつも疑っているより、素直に信じられた方が」
「それは俺に対する嫌味か?」
そう言いながらフード付きのコートを脱いで仮面の下にある亜麻色の短い髪の毛を撫でつけた。そして、その上着を彼女にかけてやる。
「風邪をひくよ。それに、素顔を見られる危険性が高まるけど、いいの?」
「いつかバレるなら、早い方がいい。もし、明日打ち明けられなくても、ラクラが見つかった後に嫌でも見せることになるんだ。――これで否定されるなら、それはそれでいいさ」
皮肉気なナハトの声を聞きながら、飛燕は小さく呟いた。
「…そんな悲しいことを言わないでよ、ナハト」
飛燕はナハトの肩に降りると、スリッと体をこすりつけた。
嫌そうな顔でナハトは押しのけようとしたが、アリシアの体が傾きそうになったので飛燕の悪ふざけにも近いような甘えの仕草を黙ってされるがままにしていた。
「…あ」
朝から何も食べていない。そのことに気が付いたが、それを抑える前に腹が鳴ってしまい、ナハトの頭の上に乗っている飛燕が振り返った。
だが、何を思ったのか、思いついたような顔で相棒を見た。
「ナハト、そう言えばご飯の時間だね」
ナハトが頷いた。
「そうだな…」
そして、アリシアの方を振り返り、口元を小さく綻ばせる。
「ほら」
アリシアは彼が鞄から取り出して放り投げたリンゴを一つ受け取っていた。
「腹ペコさん、一つ食べておけ」
「…あっ…」
顔を真っ赤にしたアリシアの腹がさらに大きな音で鳴ったのを聞いてナハトはフードを目深にかぶり直しながら楽し気に声を弾ませた。
「薬なんて仕込むわけないだろうが」
「…そうではなく、いつから…気が付いて?」
「俺たちの後をついてきた辺りから、かな。あんたの足音はずっと聞こえていたし、草木のガサガサいう音とか、足を忍ばせているつもりかもしれないが、バレバレだ」
「う…」
アリシアがゆっくりと姿を現すと、ナハトは倒木に腰を下ろしてリンゴをシャクリと一口齧る。
「あんたもラクラを探しているんだろう?」
「…なんで、それを?」
「まあ、俺のいる会社は色々と情報網があるだけだ。一枚岩じゃないが、それでも利用価値のある、…な」
アリシアも遠慮がちにナハトと少し距離を取って倒木に腰掛けた。そして、エプロンでリンゴを磨いてからシャクリと一口齧る。
「あ、美味しい…」
「アーネア商会のリンゴは最高に旨いからな。初めてするキスの味、だそうだ?」
アリシアが思わずむせかえったが、ナハトはどこ吹く風でリンゴを齧っている。
「おちょくらないでください。――でも、なぜ疑問形なのです?」
「口と口でしたことなんてないからな。そこまで気持ちが傾かないというか…前世の記憶なんて”眠った”あとはほとんど覚えていないし、キスの味も覚えていない」
彼女は首筋に手をやって顔を真っ赤にしながら頬を膨らませた。
「で、でも! でも、私の首筋に…!」
「それはマーキングみたいなものだ。とはいえ、シリウスが騒ぐから加護は与えられないんだが」
「騒ぐって…」
「まあ、いろいろあるんだよ。聖龍同士だってな? …とにかく、それは俺からのお守りみたいなものだ。変わった経歴だからどういうやつなのかと思ってみたら、よく淘汰されずに生き残ってきたと思えるくらい天然で、変わったやつだったし?」
「…それは怒ればいいのか、笑えばいいのかわからないのですが…?」
「とりあえず笑っておけば可愛いと思うな」
飛燕がそう言うと、ナハトが飛燕の首根っこをつかまえて呆れ顔をした。
「意外だな。お前が好んで焼き鳥になりたいというとは…」
「や、やだなぁ、ナハト。僕はいつだって君の味方だよ?」
「余計なことは言うな」
リンゴを食べ終えた後に芯を魔法で焼却して灰にし、ペコッと軽くデコピンをしたナハトと、デコピンを食らってクラクラしているように見える飛燕を見比べながら、アリシアはちょっと吹き出した。
「仲がいいんですね?」
「相棒だからね。それに、僕がナハトを選んだんだから仲良くないわけないでしょ? ただ、ナハトはこう見えて人見知りだからとっつきにくいけどね」
アリシアも何とか食べきってリンゴの芯を地面に魔法で埋めると、立ち上がった。
「人見知りには見えませんけどね」
「見えないでしょ? アリシアさんが無害そうなオーラを放っているからナハトも気楽にしているだけで、普段は絶対に感情も見せないし、むしろ冷徹って感じなんだよ。本当は優しいのにね」
ナハトは不機嫌そうに相棒をつまみ上げた。
「優しくなんかない。単に、欲しいものを欲し、欲しくないものには感情を使う義務もないってだけだ」
「また、そんなことを言って~」
飛燕はそう言ったが、ナハトはそれを露骨に無視して立ち上がり、歩き出した。
慌ててアリシアも彼を追いかけ、何とか横に並んだ。
「ラクラはどこにいるんです?」
「体の部分がすっぽりと覆われるような、そういう空間がラクラはとても好きなんだそうだ。岩陰の傍とか、鍾乳洞の奥の、行き止まりの吹き抜けスペースみたいな場所…とか」
「探知魔法は?」
「この森では使用できない。そもそも、ラクラはシャイなんだ。だから、長い年月をかけてラクラは身を隠すために探知魔法を阻害する体質を身に着けた。――とはいえ、見た目はバレバレなんだがな」
ナハトは歩幅を緩めて歩いていたが、ふと、足を止めた。
「…雲行きが怪しくなってきたな」
「え? でも、結構晴れていますよ?」
アリシアが不思議そうな顔をするのも無理はなく、少し上空に雲が浮かんでいるものの、雨が降る気配はみじんも感じられなかった。
「俺たち聖龍は魔力変化に敏感だ。一時間後に曇ってくる。夕食の食材と、休憩を取るための場所を探した方がよさそうだな」
「曇るだけで雨が降るとは…」
アリシアは困惑した顔をしていたが、彼と一緒に歩いているうちに本当に空が曇り始めた。
飛燕が見つけた洞窟に入った後、数分後には本降りの雨が降り始めていた。
それを見ながらアリシアは不安げな顔をした。
「ルピルが待っているのにこれでは…」
「星獣は簡単に死なない。あまり根詰めるとこっちが危ないだけだ」
ナハトがそう言いながら洞窟に来る途中でかき集めてきた薪代わりの枯れ枝などを窪みに入れ、そこに魔法で火をつけた。
すると焚火が完成し仄かにあたたかくなった。
飛燕がのんきに告げる。
「アリシアさんも焚火に当たらないの? 風邪をひいちゃうよ?」
「え、あ、ありがとうございます」
それでも浮かない表情ではあったが、アリシアはトボトボと焚火の傍にやってきて、腰を下ろした。
「そういえば、一緒にギュスターヴ様もいたのですが…置いてきちゃいました」
「アレのことは気にしなくていい。それより、腹ごしらえだな」
「アレって…」
アリシアが不安そうな顔をすると、ナハトは小さく首を横に振る。
「ギュスターヴは心配いらないし、ルピルはそもそも青の眷属だ。雨の日なんかは割と調子も良くなる。ラクラは雨の中でも動き続けられるが、俺たちはそうじゃない。キチンと食べて、しっかりと休んだら出発する。――いいな?」
「は、はい…って、なんで仕切っているんですか!」
アリシアがむぅっと頬を膨らませると、ナハトは鞄から干し肉とクラッカーを取り出した。
「野営は慣れているんでね」
「…ううっ」
干し肉を剣に変えた飛燕でスライスし、クラッカーに乗せてアリシアに差し出した。
「準備がいいんですね…」
「ラクラが簡単に見つかってたまるか。前は丸三日間かかった。だが、時間をかけるだけの価値はあるからな。ラクラの花や木は本当に妙薬だ」
彼はフードを目深にかぶり直し、焚火を挟んでアリシアの真向かいに腰を下ろした。
「あなたもどこか体調が…?」
「どうしても必要な人がいる。一年に一回、必ず」
アリシアはそれ以上聞く勇気がなく、モグモグと干し肉を乗せたクラッカーを食べ、それ以降は無言で過ごした。
だが、しばらくしてアリシアは小さく欠伸を漏らす。
「眠いなら寝てもいいぞ。見張りをしておくから」
「…交代制にしましょうよ」
「俺と飛燕で何とかなるから気にしなくていい。それに、明日もかなり歩く。いいから眠っておけ」
「……私が眠っている間に、変なこと…しないで、くださ、い…ね」
アリシアは眠そうに大きく欠伸をすると、ぶるっと小さく身震いした。ナハトが呆れたように肩をすくめ、アリシアの隣に腰を下ろす。
「嫌だろうがぴったりとくっついていた方が寒くないぞ」
「…は、い…」
微かに返事をしたものの、アリシアが寝息を立て始めてしまい、ナハトは彼女の肩を抱くようにして肩を貸し、凭れさせてやった。
穏やかに眠るアリシアの横顔を眺めながらナハトは口元に苦笑いを浮かべた。
「…ここまで素直に信じられると心苦しいものがあるな、飛燕」
飛燕は小首を傾げた。
「いいじゃない? いつも疑っているより、素直に信じられた方が」
「それは俺に対する嫌味か?」
そう言いながらフード付きのコートを脱いで仮面の下にある亜麻色の短い髪の毛を撫でつけた。そして、その上着を彼女にかけてやる。
「風邪をひくよ。それに、素顔を見られる危険性が高まるけど、いいの?」
「いつかバレるなら、早い方がいい。もし、明日打ち明けられなくても、ラクラが見つかった後に嫌でも見せることになるんだ。――これで否定されるなら、それはそれでいいさ」
皮肉気なナハトの声を聞きながら、飛燕は小さく呟いた。
「…そんな悲しいことを言わないでよ、ナハト」
飛燕はナハトの肩に降りると、スリッと体をこすりつけた。
嫌そうな顔でナハトは押しのけようとしたが、アリシアの体が傾きそうになったので飛燕の悪ふざけにも近いような甘えの仕草を黙ってされるがままにしていた。
0
あなたにおすすめの小説
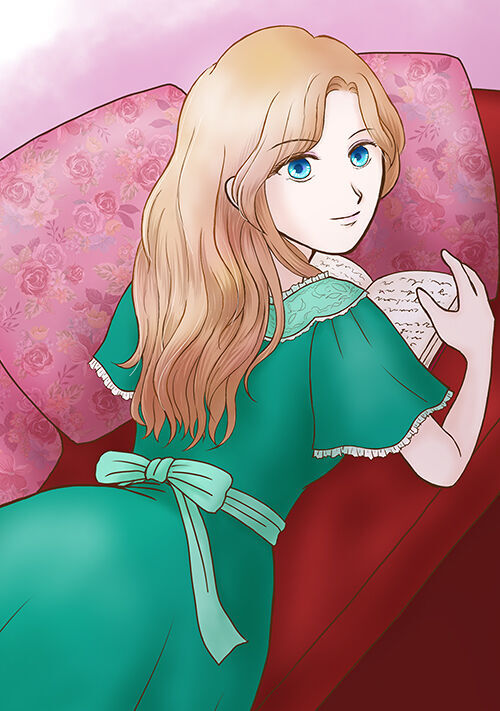
ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―
冬野月子
恋愛
侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。
のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。
けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。
※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

伯爵令嬢の25通の手紙 ~この手紙たちが、わたしを支えてくれますように~
朝日みらい
恋愛
煌びやかな晩餐会。クラリッサは上品に振る舞おうと努めるが、周囲の貴族は彼女の地味な外見を笑う。
婚約者ルネがワインを掲げて笑う。「俺は華のある令嬢が好きなんだ。すまないが、君では退屈だ。」
静寂と嘲笑の中、クラリッサは微笑みを崩さずに頭を下げる。
夜、涙をこらえて母宛てに手紙を書く。
「恥をかいたけれど、泣かないことを誇りに思いたいです。」
彼女の最初の手紙が、物語の始まりになるように――。

寵愛の花嫁は毒を愛でる~いじわる義母の陰謀を華麗にスルーして、最愛の公爵様と幸せになります~
紅葉山参
恋愛
アエナは貧しい子爵家から、国の英雄と名高いルーカス公爵の元へと嫁いだ。彼との政略結婚は、彼の底なしの優しさと、情熱的な寵愛によって、アエナにとってかけがえのない幸福となった。しかし、その幸福を妬み、毎日のように粘着質ないじめを繰り返す者が一人、それは夫の継母であるユーカ夫人である。
「たかが子爵の娘が、公爵家の奥様面など」 ユーカ様はそう言って、私に次から次へと理不尽な嫌がらせを仕掛けてくる。大切な食器を隠したり、ルーカス様に嘘の告げ口をしたり、社交界で恥をかかせようとしたり。
だが、私は決して挫けない。愛する公爵様との穏やかな日々を守るため、そして何より、彼が大切な家族と信じているユーカ様を悲しませないためにも、私はこの毒を静かに受け流すことに決めたのだ。
誰も気づかないほど巧妙に、いじめを優雅にスルーするアエナ。公爵であるあなたに心配をかけまいと、彼女は今日も微笑みを絶やさない。しかし、毒は徐々に、確実に、その濃度を増していく。ついに義母は、アエナの命に関わるような、取り返しのつかない大罪に手を染めてしまう。
愛と策略、そして運命の結末。この溺愛系ヒロインが、華麗なるスルー術で、最愛の公爵様との未来を掴み取る、痛快でロマンティックな物語の幕開けです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

置き去りにされた転生シンママはご落胤を秘かに育てるも、モトサヤはご容赦のほどを
青の雀
恋愛
シンママから玉の輿婚へ
学生時代から付き合っていた王太子のレオンハルト・バルセロナ殿下に、ある日突然、旅先で置き去りにされてしまう。
お忍び旅行で来ていたので、誰も二人の居場所を知らなく、両親のどちらかが亡くなった時にしか発動しないはずの「血の呪縛」魔法を使われた。
お腹には、殿下との子供を宿しているというのに、政略結婚をするため、バレンシア・セレナーデ公爵令嬢が邪魔になったという理由だけで、あっけなく捨てられてしまったのだ。
レオンハルトは当初、バレンシアを置き去りにする意図はなく、すぐに戻ってくるつもりでいた。
でも、王都に戻ったレオンハルトは、そのまま結婚式を挙げさせられることになる。
お相手は隣国の王女アレキサンドラ。
アレキサンドラとレオンハルトは、形式の上だけの夫婦となるが、レオンハルトには心の妻であるバレンシアがいるので、指1本アレキサンドラに触れることはない。
バレンシアガ置き去りにされて、2年が経った頃、白い結婚に不満をあらわにしたアレキサンドラは、ついに、バレンシアとその王子の存在に気付き、ご落胤である王子を手に入れようと画策するが、どれも失敗に終わってしまう。
バレンシアは、前世、京都の餅菓子屋の一人娘として、シンママをしながら子供を育てた経験があり、今世もパティシエとしての腕を生かし、パンに製菓を売り歩く行商になり、王子を育てていく。
せっかくなので、家庭でできる餅菓子レシピを載せることにしました

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています
藤谷 要
恋愛
サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。
結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。
聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。
侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。
※全11話 2万字程度の話です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















