3 / 5
第3編「嵐の前の微熱」
しおりを挟む3‑1 元婚約者の焦り
王都に遅い春雨が降り注いだ翌朝、青騎士団の演武場では金属音が染み込んだ湿気の中を鋭く裂いていた。長柄槍の鍔迫(つばぜ)り合い、弩(いしゆみ)の試射、そして剣戟の交差──若き騎士たちの汗と泥に混じり、ディラン=アルバーグ副団長は苛立った様子で木剣を振るっている。
「副団長、今日はずいぶん荒れておられる」
部下が恐る恐る声をかけるが、ディランは返答の代わりに剣先で砂を跳ね上げ、次の鍛錬相手を命じた。
──あの女が、侯爵夫人として称賛された?
耳にした噂が頭から離れない。王宮の夜会でルシアが示した気品と機転、王子をも唸らせた着こなし、貴婦人たちの掌返し。挙句〈藤の一撃〉などと雅号めいた呼び名まで付けられたと聞く。
(“没落寸前の令嬢”は、俺を踏み台にして一段上がったか……)
胸を灼(や)くのは嫉妬だった。侯爵家の権威と、世間の掌返しが見せつけた自分の失策。計算高いはずのディランが唯一読み違えたのは、婚約破棄した女がここまで輝く未来を掴んでしまうという一点。
「副団長、午后(ごご)から王宮外郭警備の当番です!」
伝令の声に思考を引き戻される。名ばかりの警備など退屈そのものだが、今日は好都合だった。ちょうど侯爵夫人──いや“ルシア”が王宮図書館の特別閲覧許可証を受け取る日だという情報を得ている。
◆ ◆ ◆
正午過ぎ、王宮図書館前。白磁の外壁に蔦(つた)を絡ませた重厚な建物の前に、藤色のパラソルを掲げた女性が現れた。ルシア=ヴァンフィールド侯爵夫人。簡素な銀刺繍の外套(がいとう)を羽織るだけの静かな装いなのに、周囲の侍従たちが一斉に頭を下げる。
ディランは衛兵詰所の陰から様子を窺(うかが)った。まるで“別人”のように凛然と歩く姿。かつて彼の後ろを二歩下がって付いて来た少女の面影はもはや希薄で、隣に侍女を伴(ともな)い、先頭に立つ指揮者のようだ。
(……今すぐ話をつけねば、完全に手の届かない場所へ行く)
衛兵の槍を借りて詰所を出るとき、部下が慌てて追いすがる。
「副団長! 規定外の動きは──」
「警邏(けいら)だ。文句があるか」
一蹴して大理石の階段を上る。図書館の重い扉の前で、ルシアは侍女と言葉を交わしていた。そこへ半ば強引に歩み寄ると、芳香と同時に、ほのかな薬草の匂いが鼻を掠めた。侯爵邸の温室の香だろうか。
「久しいな、ルシア」
呼び捨てにした瞬間、侍女の肩が震えた。ルシアはゆっくり振り向き、視線を合わせる。その瞳に怯(おび)えも動揺もなく、澄んだ水面のような静けさ。
「公務中の副団長殿が、私的な挨拶とは感心しませんわね」
「……話がある」
「でしたら、書面で。侯爵家宛にどうぞ」
扇子を開き、さりげなく横をすり抜けようとする。その肩先を掴もうと出した手を、ディランは土壇場で引っ込めた。ここは王宮、衛兵の目もある。
「俺は……お前のことを誤解していたようだ」
「誤解?」
「お前がこんなにも聡明で、自立した女だと知らなかった。それを踏まえた上で……婚約破棄を撤回したい」
階段の上、春の光が二人の影を伸ばす。ルシアは軽く瞬きをしたが、それは驚きではなく、まるで可哀想なものを見るような微笑だった。
「誤解ではなく、見下していただけですわ。私を“家柄の損失”と断じたのはあなた。侯爵家が私を迎えた今、価値が変わったと?」
「違う! 俺は……」
「あなたの“俺”は聞き飽きました」
パラソルの先端で石畳をコツン、と叩く。微かな音なのに、ディランの胸には槍より鋭く突き刺さった。
「侯爵家の夫人として忠告します。王宮の階段で元婚約者を引き留める行為は、公務の逸脱です。お止(や)めにならないと、あなたの名誉に関わりますよ」
ディランは歯噛みした。人払いもなく、公の場で返り討ちに遭った形だ。この場を収めるには退くしかない。
「……まだ終わっていない」
絞り出すと、ルシアは首を傾げた。
「ええ、あなたの汚職調査も、まだ終わっていませんわね」
低い囁き。意味を悟った瞬間、背筋を氷柱が滑り落ちた。ディランは顔色を失い、声が出ない。ルシアはもう一度だけ礼を取ると、今度こそ図書館の扉をくぐった。
◆ ◆ ◆
王宮の外に出る頃、ディランの掌は汗で濡れていた。汚職調査──ノア=ヴァンフィールドが水面下で動いていると耳にした噂。まさかルシアも一枚噛んでいるのか。
(まずい……アルバーグ男爵家の金融部門が繋(つな)ぎと知られれば、俺の立場は……いや、王太子騎士団すら揺らぐ)
焦燥が喉を締め付ける。頭を冷やそうと庭の噴水へ向かった瞬間、後ろから声が飛んだ。
「副団長! 王宮検察局が“会計局の不正支出”について事情聴取を要請しています」
青騎士団の若手が汗だくで決裁文書を掲げている。ディランの鼓動が破裂しそうだった。
──ルシアとノアが本気で動いた。もし帳簿が裁判所へ渡れば、婚約破棄など比べ物にならない致命傷が待っている。
「……わかった。すぐ向かう」
返答したものの、足取りは鉛のように重かった。焦りが霧のように視界を曇らせる。白い藤の花弁が風に舞い、その一片が肩鎧(かたよろい)に貼りついた。払っても払っても、ひらひらと視界に入る淡紫。まるで、あの夜会で見た侯爵夫人のドレス色が、彼の未来をからかうように追い立ててくる。
ルシアが背を向けた瞬間から、ディランの“安全な王宮ライフ”は急速に崩れ始めた。焦りは恐怖へ、恐怖は苛立ちへ。
──しかし彼はまだ知らない。これが、ヴァンフィールド侯爵夫妻が仕掛ける“ざまぁ劇”の、ほんの序章にすぎないことを。
第3編「嵐の前の微熱」
3‑2 侯爵令嬢狙撃事件
王宮東庭園――正式名を〈千花回廊〉という。春蘭と晩咲きの椿が競い合い、藤棚は薄紫のヴェールを垂らす。午后の陽差しがまだ柔らかい時刻、王太子主催の弓術祝賀会が始まった。各領の貴族子弟が腕を披露し、後見人の貴婦人たちは白木の観覧席で優雅に扇を揺らす。
ルシア=ヴァンフィールド侯爵夫人は、淡水色に藤の刺繍を散らしたドレスでその列に座り、手もとには簡素な茶器。隣に腰かけるノアは公務のため黒銀の正装。
「弓術会など久しぶりね」
「王太子が“武門の伝統を再興する”と意気込んだ催しだ。旧派貴族も無視できまい」
気圧(けお)し合いの裏で、ノアが視線だけで警戒範囲を示す。ルシアは頷き、扇子を胸元に立てた。昨夜遅くまで汚職資料を読み込んだせいで少し眠いが、今日の式典は〈帳簿の証人〉の一部が揃う重要な場でもある。
やがて弓台(ゆんだい)に並ぶ騎士候補生たちが号令で弦を引いた。的まで四十間、矢羽根が一斉に唸りを上げる。
――その瞬間。
キィン、と金属を擦る甲高い音がした。
「!」
矢束の一本が金柑(きんかん)色の軌跡を描き、仲間の矢列から離脱。観覧席をかすめ、藤棚の蔭(かげ)へ突っ込む――はずだった。
「伏せろ!」
ノアの怒号。だが彼は叫ぶより早く、ルシアの肩を抱きかかえ、椅子ごと背後へ転がした。空気を裂く風圧が頬を打ち、次の瞬間、硬い衝撃音。矢尻が観覧席背面の石柱に突き刺さり、礫(つぶて)のような破片が飛び散った。
ルシアは息を呑む間もなく床に押し倒され、冷えた芝の匂いを嗅いだ。腕の中ではノアの外套布がふわりと覆い、彼の鼓動が掌へ伝わる。
「怪我は?」
「大丈夫……あなたは?」
「かすり傷だ」
ノアの袖口が裂け、細い切り傷に紅が滲んでいた。それでも彼は顔色ひとつ変えず立ち上がり、観覧席を見回す。貴婦人たちは悲鳴を上げ、衛兵が駆け込む。弓台の騎士団は混乱し、誤射を叫ぶ声と命令が交錯した。
(これが偶然? いいえ……)
ルシアは石柱に刺さった矢を凝視した。通常の競技用より重い鉄矢尻、羽根に刻まれた見慣れぬ銀纹。狙いは明らかに“席の最前列、つまり侯爵夫人”だ。
「ノア、あれを」
「見ている。──衛兵長、射手を拘束しろ!」
ノアが命じると、青鎧の副官が弓台へ突進し、的前で呆然と立つ候補生を組み伏せた。だが拘束される青年の顔に悪意の色はなく、狼狽(ろうばい)しきっている。
「仕組まれた偽装だ」
ノアは矢を引き抜き、羽根を細目で検分する。「弦痕(げんこん)がない。……飛来途中で別の弦で射出し直された矢だ」
「つまり途中で軌道を変えられた?」
「強弩(ごうど)か機巧弓が植え込みに隠れているはず」
衛兵たちが園丁用倉庫や藤棚の蔭を捜索し、間もなく小型弩の残骸と油紙包みの矢束、そして黒布の匂袋が見つかった。
ルシアは黒布に刺繍された意匠を一目見て眉を吊り上げる。――それはイリーナ公女の母方一族、〈ルクス侯家〉の家紋と酷似していた。
(やはり、イリーナ……!)
貴族の誰かが悲鳴混じりに「暗殺未遂!」と叫び、庭は蜂の巣をつついた騒ぎとなった。王太子の侍従が駆け寄り、ルシアとノアを別室へ案内しようとする。が、ノアは首を振る。
「犯人を逃せば第二、第三の矢が来る。私が追う」
「私も行くわ」
「君は安全を──」
「共犯者でしょう? 証拠の取り扱いは私も責任を負う」
押し問答する暇もなく、ノアは短く息を噛み切った。
「……では、背後に張りついて。絶対に離れるな」
了解のしるしにルシアは頷き、ドレスの裾をたくし上げる。一礼して侍女を下がらせると、二人は藤棚の裏道へ駆けた。
◆ ◆ ◆
追跡は十分足らずで終わった。温室裏の配送門で黒装束の男が馬を用意していたが、ノアの抜刀術――鞘(さや)ごと打つ烈風の一撃に膝を折った。仮面を剥ぎ取ると、男の右耳にはルクス侯家の私兵が付ける銀環(ぎんかん)。
「黒幕はイリーナで、間違いないようね」
ルシアが目隠し用の布で男の手首を縛り、ノアは押収した矢束を確認する。
「王家の勅印偽造にも当たる。……これで法廷は動く」
ルシアは胸の奥に冷たい炎を感じた。矢は自分だけでなく、王太子主催の政務行事そのものを狙ったテロだ。貴族社会の安全神話に亀裂を入れ、旧派閥に揺さぶりを掛ける乱暴な方法。
ノアが立ち上がり、ルシアを見下ろす。
「怖くないか」
「少しは。でも……あなたが矢を弾いたとき、なぜか安心したわ」
頬が熱くなりかけたが、すぐに笑みに変えた。「共犯者だからね」
「共犯者、か」ノアは一度だけ視線を外し、ふと柔らかな声で囁く。「助けたのは……義務だけでは説明できない」
ルシアの心拍が跳ねた。返す言葉を探す間もなく、遠方から号砲が鳴り、王宮騎士隊の増援が到着する。
「行こう。公爵夫人として証言を」
ルシアは頷き、ノアと並んで庭園へ引き返した。
春光が葉に砕け、石畳に散った藤色の花弁はさざめくように二人の足元を彩る。狙撃事件は中断した祝賀会を一瞬で凍りつかせたが、その陰で――“仮面の夫婦”は確かに一歩近づいていた。
危険と隣り合わせの絆。その微熱は、嵐を呼ぶ序章としてますます強く脈打っていく。
3‑3 とまどう二人の本音
王宮での事情聴取は日が暮れるまで続いた。
襲撃犯がルクス侯家所属の私兵だった事実、弓術祝賀会に紛れ込んだ経緯、犯行に使われた機巧弩の性能──一つひとつを証言し、証拠品へ署名し終えた頃には、夜気が石壁へ重く沈み込んでいた。
ヴァンフィールド侯爵邸へ戻る馬車の中、ルシアとノアは向かい合ったまま長い沈黙を抱え込んでいた。
油灯の揺らぎがカーテン越しに影を作り、車輪のリズムがゆるやかに胸を揺さぶる。
「……傷、痛まない?」
先に口を開いたのはルシアだった。ノアの腕には浅い切創をかばう白布が巻かれ、薄紅が滲んでいる。
「もう塞がったさ。君こそ震えている」
「あれは……冷えで少し」
本当は違う。
石柱へ突き立つ黒矢。かすめた死の気配。
そして、抱き寄せられた瞬間に走った熱。
馬車が門を潜ると、待ち構えていたセドリックが扉を開けた。執事長はふたりの顔を見比べ、控えめに言う。
「晩餐は温め直しますか?」
「軽いスープでいい。……食堂ではなく、藤花の間へ」
ノアの指示に、セドリックは一礼して去る。
照明の落ちた回廊を歩き、共用の応接へ入ると、暖炉には新しい薪が組まれていた。火がはぜ、薬草の香がほんのり漂う。
「さっきから黙っている」
ノアがコートを脱ぎつつ振り返る。
「何か言いたいことがあるなら、遠慮なく」
「……護ってくれた理由を聞かせて」
問いは思ったより大きく空気を震わせた。
「義務? 共犯者としての利? それとも……」
言葉がそこでほどけ、ルシアは扇子を握り締めた。
契約を結んだ夜、自分は“盾”“取引”と口にした。
なのに矢が飛んできたとき、彼を『夫』として求める心が確かに胸を突いた。
ノアは暖炉の光を背に、静かに息を吐く。
「理由……分からない」
「分からない?」
「私は論理で動く人間だと思っていたよ。領地改革も、王宮工作も、妻選びすら――だが今日、理由を組み立てる暇はなかった。身体が勝手に動いた」
燃える薪がぱちり、と小さく爆ぜる。
ルシアは視線を落とし、ドレスの裾を指で摘む。
「あなたは私の盾。私はあなたの剣。そのはずだったのに」
「変わったのなら、言葉を更新しよう」
ノアは歩み寄り、袖の包帯を外した。
薄い傷痕を見せ、「ここを守ったのは剣でも盾でもなく――ただの男の衝動だ」と囁く。
喉が、からりと鳴った。
「……私はどう応えればいい?」
「答えを急がなくていい。ただ、確かめたい」
ノアは手袋を外し、ルシアの扇子をそっと閉じた。
指先と指先が触れる。
肌の温度が伝わり、血流の音が耳奥で高鳴る。
「義務なら、これ以上近づくなと言える。情なら、拒めなくなる。君は?」
問い返され、ルシアは肺いっぱいに夜気を吸った。
揺れる炎の匂い。薬草と、彼の淡い香。
「まだ……怖いわ」
「何が?」
「この温度が、契約の外側に落ちてしまうのが」
正直な言葉だった。
ノアは薄く笑い、手を離しかけ――けれど、ふと思い直したようにその手でルシアの髪先を掬い上げた。
「なら一歩だけ。耳許に触れる、一センチの距離は維持する」
さらりと銀糸を撫で、すぐ戻す。
「契約は破らない。だが条文には『触れてはならぬ』とは書かれていない」
その狡猾さに、ルシアは吹き出しそうになった。
「ずるいわ」
「君が教えたんだ。“交渉は弱みを隠した者が勝つ”と」
火影が揺れ、二人の影が寄り添う。
食前のスープが運ばれ、卓上に湯気が立つ。
だがさほど空腹を感じないほど、胸の内は熱で満ちていた。
スプーンを握る手が震え、ノアが笑って取り替える。
向かい合いながら、同じ皿を片側ずつ掬う。
銀の器に映る二つの顔が近づいたり、離れたり。
ふと、ルシアがまた口を開く。
「私を守って怖くなかった?」
「怖かったさ。初めて剣ではなく腕で受けた。だが――」
ノアは匙を置き、真っ直ぐ見つめる。
「怖さより君を失う恐れの方が強かった」
句点のように落ちる静寂。
咄嗟に視線を逸らせず、ルシアは頬を染めた。
心が傾ぐ音を聞いた気がする。契約の檻の鉄格子が、わずかに軋んだ。
「……裁判が終わるまで、この距離でいましょう」
やっと絞り出した台詞は、震えを隠せない。
「終われば?」
「その時は……また交渉を」
ノアは短く笑い、グラスの水を掲げた。
「では、未来の交渉に――暫定的な祝杯を」
グラスの澄んだ音が、藤花の間に柔らかく響いた。
夜は更けゆく。
仮面の夫婦が自覚した本音は、まだ名もない“微熱”のまま。
だがそれは確かに、義務でも利害でもない場所で燃え始めていた。
3‑4 策略の影
王宮襲撃未遂の夜から三日。
ヴァンフィールド侯爵邸の地下書庫には、蝋燭(ろうそく)の明かりだけが揺れていた。壁一面の棚に埋まった羊皮紙の背表紙が、灯の粒を飲み込んでは返す。昼の公務に追われたノアとルシアがようやく腰を下ろせるのは、深夜も更けたこの時刻だった。
「襲撃犯の供述は“無名の雇い主”で押し通されている。だが奴の耳環と資金経路がイリーナ公女へ続くことは確定的だ」
ノアが指で書類の束を叩く。王宮検察局が押収した財務記録の写しや、密偵が集めたルクス侯家の私兵配置図が重ねられている。
「問題は、公女を直接糾弾できる“決定打”がまだ足りないことね」
ルシアは羽ペンを回し、証拠リストの余白にメモを取った。
「暗殺未遂と汚職……ふたつの事件を一本の糸で結ばないと、旧派の議員は“偶然”と強弁するわ」
「そこで君の“離縁条項”が生きる」ノアが笑う。「正式に侯爵夫人が離縁を宣言すれば、一時的に“法的独身”になれる。そうなればルシア・レイオット個人として公女に民事告訴を起こせる。王家の外で、私闘ではなく〈被害者の矜持〉として」
「私闘よりも民事。ええ、女同士の水面下の足の引っ張り合いに見えない分、陪席の貴族が冷静に証拠を評価できる……」
ルシアは肩にかかる髪をかき上げた。
「ただし世間は“侯爵に捨てられた妻が泥仕合”と嗤(わら)うでしょうね。私の名誉は傷つくわ」
「名誉なら取り戻せる。証言台の上でね」
ノアは黒檀(こくたん)の小箱を開き、一枚の銀細工を取り出した。淡紫の宝珠を抱く小さな翼のブローチ。
「君が離縁を宣言する瞬間、これを差し出す。正式求婚の証だ」
「……一度離縁して、即日プロポーズ? 前代未聞じゃない?」
「印象は派手でいい。公女が仕掛けた暗闘を“華麗に踏み台にした復縁劇”と王都中が囃(はや)し立てる。最終的に失うのはイリーナの評判だけだ」
ルシアはブローチを覆うビロードに指を沈めた。
「……リスクの計算は完璧。でも」
「怖いか?」
「少し。私は私で、今まで守ってきた“冷静な令嬢”の仮面を脱ぎ捨てる覚悟が要るもの」
ノアは柔らかく目を細める。
「仮面は時に凶刃を受け止める盾になる。だが砕ければ、傷つくのは肌だ。……だから私が隣に立つ」
灯心がぱち、と音を立てた。ルシアは胸に小さな笑みを咲かせる。
「――共犯者、ね」
「共犯者以上、恋人未満だとしても」
その真意を尋ねる前に、書庫の扉がノックされた。
セドリックが深夜用の簡易筆記具を携えて入室し、一礼する。
「侯爵閣下、夫人。宮廷司法庁より“臨時公聴会”の通達です。議会三日後、場所は銀鷲(ぎんわし)ホール。出席者は王族監査官、枢密顧問五名、第一王子殿下を筆頭とする陪審十二名」
「……早いわね」ルシアが息を呑む。
ノアは顎に手を当てた。
「旧派が“泥仕合”を誘い、時機を逸さぬうちに数字の辻褄(つじつま)を消す腹かもしれない。ならばこちらも早めるしかない」
セドリックが視線だけで問いを投げる。ノアは頷き、地下書庫の鍵束を渡した。
「ルシア嬢の父上――レイオット公爵から取り寄せた鉱山台帳は?」
「部下が精査中です。粉飾の痕跡が消えていないとの報告」
「装飾バラ付き領収証を抜き出して公聴会に提出。裏帳簿と照合すれば、私兵の人件費や武器調達費が“鉱山の設備修繕費”として再循環していた証明になる」
「わかりました」
執事長が去ると、ノアは燭台を戻し、書類の山をルシアへ押しやった。
「本番は三日後。今夜からは“夫婦共用の応接室”ではなく、“作戦司令室”だ」
ルシアは笑って胸を張る。
「了解。では第一段――“離縁宣言”の文案を作るわ。少し刺激的にね。どうせ茶会の噂を煽るなら徹底的に」
「好きに暴れていい。後始末は私が引き受ける」
机上の二つのインク壺が月光を映す。
ルシアは深呼吸し、白紙に向かった。
――――――――――――――――――――――――――――――
私、ルシア・レイオットは、ヴァンフィールド侯爵閣下との婚姻契約に基づき、一年満了以前の解除条項を行使する。
解除理由:侯爵家及び私自身の身の安全を脅かす外部勢力の介入に伴い、円満離縁をもって当該勢力との縁を絶つため
――――――――――――――――――――――――――――――
筆先が走るたび、胸の奥が奇妙な高揚で熱くなる。これはただの策略。けれど紙面に綴る言葉は、なぜか自分の未来を切り拓く誓いのようにも感じられた。
ノアは向かいで帳簿に朱を入れながら、ときおり視線を上げた。
ルシアの横顔を照らす灯りが彼の瞳に映る。
(この距離……指先一センチ)
まだ触れない。それが二人のルール。
けれど鋼鉄のようだった契約は、既に紙より薄く、そして肌より近い。
夜更け――銀時計が二時を告げた頃、ルシアは最後の一筆を書き終え、そっと羽ペンを置いた。
「……完成。侯爵閣下、ご確認を」
ノアは紙を受け取り、黙読し、深く息を吐く。
「完璧だ。……別れの宣言とは思えないほど、私への信頼が滲んでいる」
「裏切者には読めない隠し味よ」ルシアが微笑む。「私たちでしか解けない暗号みたいなもの。――共犯者の証」
二人の視線が重なり合い、暖炉の火がぱっと跳ねる。
嵐の前――温室で芽吹いた微熱は、今や戦場へ持ち込まれる刃へと姿を変えた。
あと三日。
公女イリーナと旧派閥、元婚約者ディランを呑み込む公開裁判が、静かな夜に向けて胎動していた。
ルシアは胸元で拳を握り、そっと呟く。
「必ず……勝つわ。そして“契約”を、自分の意志で塗り替える」
ノアは静かな微笑を浮かべ、応えず頷いた。
炎に映る影は、寄り添うでもなく離れるでもなく、まっすぐ前を向いて並んでいた――。
0
あなたにおすすめの小説

追放された悪役令嬢、辺境で植物魔法に目覚める。銀狼領主の溺愛と精霊の加護で幸せスローライフ!〜真の聖女は私でした〜
黒崎隼人
恋愛
「王国の害悪」として婚約破棄され、魔物が棲む最果ての地『魔狼の森』へ追放された悪役令嬢リリア。
しかし、彼女には前世の記憶と、ゲーム知識、そして植物を癒やし育てる不思議な力があった!
不毛の地をハーブ園に変え、精霊と友達になり、スローライフを満喫しようとするリリア。
そんな彼女を待っていたのは、冷徹と噂される銀狼の獣人領主・カイルとの出会いだった。
「お前は、俺の宝だ」
寡黙なカイルの不器用な優しさと、とろけるような溺愛に包まれて、リリアは本当の幸せを見つけていく。
一方、リリアを追放した王子と偽聖女には、破滅の足音が迫っていて……?
植物魔法で辺境を開拓し、獣人領主に愛される、大逆転ハッピーエンドストーリー!
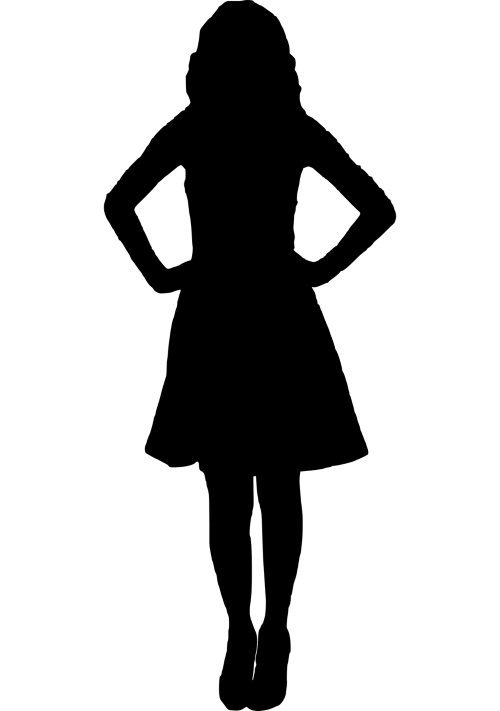
気がついたら婚約者アリの後輩魔導師(王子)と結婚していたんですが。
三谷朱花
恋愛
「おめでとう!」
朝、職場である王城に着くと、リサ・ムースは、魔導士仲間になぜか祝われた。
「何が?」
リサは祝われた理由に心当たりがなかった。
どうやら、リサは結婚したらしい。
……婚約者がいたはずの、ディランと。

都会から田舎に追放された令嬢ですが、辺境伯様と畑を耕しながらのんびり新婚スローライフしています
さら
恋愛
王都一の名門で育ちながら、婚約破棄と共に「無能」と烙印を押され、辺境へと追放された令嬢クラリッサ。
行き着いた先で出会ったのは、過去の戦場で心を閉ざし、孤独に領地を守る辺境伯ライナルトだった。
荒れ果てた畑、限られた食糧、迫り来る悪徳商会の策略――。
王都では役に立たなかった薬草や農作の知識が、この地では大きな力となる。
村人たちと共に畑を耕し、薬草園を育て、やがてクラリッサは「無能令嬢」から「皆に必要とされる奥方」へ。
剣で村を守るライナルトと、知恵と優しさで人を支えるクラリッサ。
二人が並び立った時、どんな脅威も跳ね除けられる――。
「あなたとなら、どんな嵐も越えていける」
追放から始まる辺境スローライフは、やがて夫婦の愛と未来を育む物語へ。
のんびり畑を耕しながら、気がつけば“無双”の幸せ新婚生活!?

婚約破棄された侯爵令嬢、帝国最強騎士に拾われて溺愛される
夜桜
恋愛
婚約者である元老院議員ディアベルに裏切られ、夜会で婚約破棄を宣言された侯爵令嬢ルイン。
さらにバルコニーから突き落とされ、命を落としかけた彼女を救ったのは、帝国自由騎士であるジョイアだった。
目を覚ましたルインは、落下のショックで記憶を失っていた。
優しく寄り添い守ってくれるジョイアのもとで、失われた過去と本当の自分を探し始める。
一方、ルインが生きていると知ったディアベルと愛人セリエは、再び彼女を排除しようと暗躍する。
しかし、ルインの中に眠っていた錬金術師としての才能が覚醒し、ジョイアや父の助けを得て、裏切った元婚約者に立ち向かう力を取り戻していく。

天然だと思ったギルド仲間が、実は策士で独占欲強めでした
星乃和花
恋愛
⭐︎完結済ー本編8話+後日談7話⭐︎
ギルドで働くおっとり回復役リィナは、
自分と似た雰囲気の“天然仲間”カイと出会い、ほっとする。
……が、彼は実は 天然を演じる策士だった!?
「転ばないで」
「可愛いって言うのは僕の役目」
「固定回復役だから。僕の」
優しいのに過保護。
仲間のはずなのに距離が近い。
しかも噂はいつの間にか——「軍師(彼)が恋してる説」に。
鈍感で頑張り屋なリィナと、
策を捨てるほど恋に負けていくカイの、
コメディ強めの甘々ギルド恋愛、開幕!
「遅いままでいい――置いていかないから。」

婚約破棄ブームに乗ってみた結果、婚約者様が本性を現しました
ラム猫
恋愛
『最新のトレンドは、婚約破棄!
フィアンセに婚約破棄を提示して、相手の反応で本心を知ってみましょう。これにより、仲が深まったと答えたカップルは大勢います!
※結果がどうなろうと、我々は責任を負いません』
……という特設ページを親友から見せられたエレアノールは、なかなか距離の縮まらない婚約者が自分のことをどう思っているのかを知るためにも、この流行に乗ってみることにした。
彼が他の女性と仲良くしているところを目撃した今、彼と婚約破棄して身を引くのが正しいのかもしれないと、そう思いながら。
しかし実際に婚約破棄を提示してみると、彼は豹変して……!?
※『小説家になろう』様、『カクヨム』様にも投稿しています

婚約破棄された悪役令嬢ですが、なぜか変人侯爵に溺愛されてます
春夜夢
恋愛
婚約破棄された伯爵令嬢・レイナは、王子とその「自称ヒロイン」の公開断罪を、冷静に受け入れた――いや、むしろ内心大喜びだった。
自由を手に入れたレイナが次に出会ったのは、変人と名高い天才侯爵様。なぜか彼から猛烈な溺愛求婚が始まって……!?
「君がいい。契約結婚でも構わないから、今すぐ結婚してくれ」
「……私、今しがた婚約破棄されたばかりなのですが」
婚約破棄から始まる、予測不能な溺愛ラブコメディ。
策士な令嬢と、ちょっとズレた変人侯爵様の恋の行方は――?

望まぬ結婚をさせられた私のもとに、死んだはずの護衛騎士が帰ってきました~不遇令嬢が世界一幸せな花嫁になるまで
越智屋ノマ
恋愛
「君を愛することはない」で始まった不遇な結婚――。
国王の命令でクラーヴァル公爵家へと嫁いだ伯爵令嬢ヴィオラ。しかし夫のルシウスに愛されることはなく、毎日つらい仕打ちを受けていた。
孤独に耐えるヴィオラにとって唯一の救いは、護衛騎士エデン・アーヴィスと過ごした日々の思い出だった。エデンは強くて誠実で、いつもヴィオラを守ってくれた……でも、彼はもういない。この国を襲った『災禍の竜』と相打ちになって、3年前に戦死してしまったのだから。
ある日、参加した夜会の席でヴィオラは窮地に立たされる。その夜会は夫の愛人が主催するもので、夫と結託してヴィオラを陥れようとしていたのだ。誰に救いを求めることもできず、絶体絶命の彼女を救ったのは――?
(……私の体が、勝手に動いている!?)
「地獄で悔いろ、下郎が。このエデン・アーヴィスの目の黒いうちは、ヴィオラ様に指一本触れさせはしない!」
死んだはずのエデンの魂が、ヴィオラの体に乗り移っていた!?
――これは、望まぬ結婚をさせられた伯爵令嬢ヴィオラと、死んだはずの護衛騎士エデンのふしぎな恋の物語。理不尽な夫になんて、もう絶対に負けません!!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















