6 / 10
風邪っぴきの君へ
しおりを挟む
「なっ、何だって!?」
金曜日の昼下がり。
ローズメリーで紅茶片手にタブレットを覗き込んでいた亜嵐は、今にもひっくり返りそうな勢いで立ち上がった。
「どうしたの!? 亜嵐さん」
何事かと目を見張る客たちに頭を下げながら翠が駆けつけると、亜嵐は震える指で画面を示した。
翠が覗き込んだそこには、メールアプリが開いており――。
『お疲れさまです。風邪をひいたので、明日のアルバイトはお休みさせてください。――藤宮湊』
「あらあら、大変!」
「そうですとも! 風邪をひいているのに、一人きりだなんて……あぁ、きっと心細いに違いない。私はどうすれば!?」
頭を抱えて狼狽する男を見遣り、翠は「やれやれ……」と眉根を寄せた。
***
「いいこと、亜嵐さん。無理をさせないのが一番なの。だから、藤宮くんが『大丈夫です』って言ったら、おとなしく引き下がるのよ?」
「湊はいつだって奥ゆかしい。――しかし大丈夫。私ならきっと、彼の望むことを読み取れるはずです!」
差し入れのバスケットを大事そうに抱え、やたら使命感に燃える亜嵐に、翠は「はぁ……」とため息を吐いた。
「それがダメだって言ってるの。……やっぱり私が行こうかしら?」
家事一般がからっきしなくせに、自分が行くと言い張るものだから、翠は渋々バスケットを渡したのだが。
(そりゃあ亜嵐さんが顔を見せるのが、一番の薬にはなるでしょうけれど)
湊に関してのみ妙に押しが強いのが、他は完璧なこの男の困ったところだ。
そして湊はいつだって、亜嵐には特別に甘い。
亜嵐がわざわざ自宅にやってきたとなれば、何かと世話を焼こうとするだろう。
「藤宮くんの手を煩わせないこと。ご飯も飲み物も入っているから、亜嵐さんは台所に入っちゃダメよ? それからご飯をあーんで食べさせようとしたり、着替えを手伝おうとしたりもね?」
「……前々から感じていましたが、あなたは私を何だと思っているんです?」
胡乱な目を向けつつ、バスケットを抱えて離さない亜嵐に、翠は再度大きなため息を吐いた。
「じゃあ――行ってらっしゃい。藤宮くんにお大事にって伝えてね」
「はい! 行ってきます!」
気合の入った背中が小さくなるまで見送って、翠はそっと扉を閉じた。
***
亜嵐にとって、湊は特別な存在だ。
自分の話に熱中するときのキラキラした瞳も、ホットケーキを焼いてくれるときの優しい笑顔も、資料整理をしているときの真剣な横顔も、全てが好ましい。
(出会った頃は、どこか似ていると思ったが……とんだ思い違いだった)
人とのかかわりに擦り切れて厭世的になった自分とは違い、湊は悲しみや寂しさと共にありながら、真っ直ぐに相手を見つめて向き合っている。
裏にあるものを疑うのではなく、自分の目で見て感じたものを素直に信じる。
(私は彼のようにできなかった……)
亜嵐の目に映る湊は、いつだって輝いている。
この気持ちは純粋な崇敬だ。
小さな独占欲は否定しないが、そんなものより湊自身を尊重したいと、亜嵐は常々思っている。
ふと、色鮮やかなショーウィンドーが目に飛び込んで来た。
「花屋……そうだ、見舞いには花がつきものだな」
彼のように明るくて、素敵な花を選ぼう。
亜嵐は迷うことなく、自動ドアの前に立った。
***
「いらっしゃいませー!」
「見舞い用の花を作ってほしい」
一陣の風のように現れた美青年に、女性店員はわずかばかり頬を染めた。
「ご希望の雰囲気や色はありますか?」
「見るだけで元気が出るようなものをお願いしたいのだが」
「それなら、オレンジをメインにしたビタミンカラーはいかがでしょう」
ラナンキュラスに手を伸ばした店員に、亜嵐は「いや」と言った。
「その花は私たちに合わない。別の……そうだな」
亜嵐は、生花が所狭しと並んだ冷蔵ショーケースをぐるりと見回した。
――と、その視線がぴたりと止まる。
視線の先にあるのは、色とりどりのガーベラが投げ込まれた青いバケツ。
一つ頷くと、亜嵐は店員を振り返った。
「赤と黄のガーベラを合わせて六本。それ以外の花はお任せする。優しい人を励ますものに仕上げてほしい」
「……はい。かしこまりました」
その花選びと本数に、店員の心はほっこりと温かくなった。
しばらくして出来上がったアレンジメントは、二色のガーベラをメインに、カーネーションや小ぶりな胡蝶蘭が華を添える豪奢なものになった。
亜嵐は一つ一つの花を丁寧に確認すると、店員に「素敵なものをありがとう」と言って、店を後にした。
(気に入ってもらえてよかった。あれだけの想いが込められた花がもらえる相手の人、ちょっと羨ましいかも……なんてね)
作業台を片付けながら、店員は目を細めてふふっと笑った。
***
湊の自宅最寄り駅に到着した亜嵐は、スマートフォンを取り出した。
アルバイト用に一応履歴書をもらっているので、住所は知っている。
地図アプリに入力しておいたので、あとはナビの通りに歩けばいい。
そのはずだった。
「……おかしいな」
ナビが到着を告げたポイントは、ぽつんと空いた更地だった。
どこかで道を一本間違えたかとナビを再起動しても、頑なに『到着』を表示するばかり。
「これは……困った」
近くには来ているはずだから、湊に連絡をすれば――そう考えて、亜嵐はふるふると首を振った。
体調が悪い湊に迎えを頼むなど、できるはずがない。
亜嵐は空き地に背を向けると、近くの家の表札を一軒ずつ確認し始めた。
「――あった! ここだ」
ひとつ辻を違えた場所に、目指す家はあった。
木製の桟を模した塀が敷地をぐるりと取り囲み、植栽はほとんどない。
駐車スペースはがらんどうで、冷たいコンクリートがむき出しになっていた。
母親を早くに亡くし、残されたのは思春期の息子と、仕事柄家を空ける父。
最低限片付けられてはいるが、生活の匂いが少ないのも当然と言えた。
ポストと一体になった門の前で荷物を下ろすと、亜嵐は手で髪をさっと整え、上着を払った。
そしてぐっと息を呑むと、震える手でインターフォンを押した。
「…………」
一分ほど待ってみたが、反応はない。
もう一度押すと、今度は慌てたような声が機械を通して響いた。
『はっ、はい……! どちら様ですか?』
「私だ、湊」
『えっ……えぇっ、亜嵐さん!?』
ドタドタという音を最後に通話が途切れ、代わりにカチリという音が手元で鳴った。
門の鍵が開いたようだ。
門扉から玄関ドアまでのアプローチを、可能な限り速足で進む。
――と。
ドタンッ!
人が転んだような大きな音が響き、続いてガチャッ! とドアが開く音がした。
ハッとして見ると、カーディガンを羽織った湊が、ぴょこりと外を窺っていた。
その手は痛そうに、癖毛の跳ねた頭を擦っている。
「湊! 大丈夫――」
「来ないでっ!」
鋭い言葉と共に玄関ドアはバン! と閉じられ、カチャリと鍵が掛けられた。
亜嵐は駆け寄って、ドアをドンドンと叩いた。
「湊、どうして!?」
「何で来たんですか!」
「何でって……体調が悪い君を、放ってなどおけるものか!」
ドアに縋りつくものの、鍵が開く気配はない。
不安と焦りで、亜嵐は激しく動揺した。
「翠さんが作った差し入れを持って来たんだ。元気が出るように花も選んだ。開けてくれ、湊!」
「ダメです! 全部そこに置いて、すぐ帰ってください!」
「湊、そんな……君が私を拒むなんて……」
その呟きは弱々しく、ドアに当てた手も震えている。
すると無機質な扉を隔てて、啜り泣くような声が亜嵐の耳に届いた。
「亜嵐さんが、来てくれたのは……うっ、うれしいけどっ! でも、会ったら……っ」
途切れ途切れの声に、亜嵐の胸は締め付けられる。
「病気と知って、いてもたってもいられなくなった。私は君に会いたい、顔が見たいんだ。君も同じ気持ちなら、どうかここを開けてほしい」
真摯に懇願するも、扉の向こうの湊が動く気配はない。
そして涙ながらの声は「ダメです」と重ねた。
「だって……会って風邪をうつしたくないんです。俺のせいで亜嵐さんに苦しい思いをさせるなんて、絶対に嫌なんです。だから……会えません。お願いです、帰ってください……」
ずびっと鼻を啜り、ついで軽く咳き込む息音。
それを聞いた亜嵐は足元に視線を落とし、拳をギュッと握った。
「……わかった。君の言うとおりにしよう。だが本当に辛くなったら、いつでも連絡してくれ。真夜中だって構わない……いいね? 必ずだ」
「はい。ありがとうございます、亜嵐さん。ごめんなさい……」
「謝る必要はない、押し掛けたのは私なのだから。……ではこれで失礼する。翠さんの料理は必ず食べるように、きっと元気になる」
バスケットと花を玄関前に並べると、亜嵐は足を引きずるようにその場を後にした。
完全に気配がなくなってから、湊は鍵を開け、そっと扉を押した。
そこに置かれていたのは、赤いチェックの布が掛けられた大きなバスケットと、鮮やかなガーベラが目を惹く大きなフラワーアレンジメント。
「うわぁ、すっごく綺麗だ。……あれ?」
カーネーションの隙間に小さなカードがあるのに気付き、湊はそれを手に取った。
二つ折りのカードを広げると――。
『君のいない週末は寂しい。待っているから、早く元気になってほしい』
美しい文字で綴られた、切なる言葉。
「あ……亜嵐さん……」
ぶわっと涙が溢れる。
(本当は会いたかった――傍にいてほしかった……!)
自分から断ったけれど、扉一枚の距離に亜嵐がいたことがうれしくて、同時にその距離が恨めしくなった。
「ふぇっ……」
上着の袖で涙を拭いながら差し入れを持ちあげようとして――。
「……あ」
門扉の陰から玄関を覗き込む男と目が合う。
途端、男は両手を大袈裟に振った。
「これ以上近寄ったりしない! だからせめて君が家に入るまでは、見届けさせてくれ!」
「……っ! あ、亜嵐さん……」
その場に座り込み、べそべそと泣き出した湊に、亜嵐はどうしようもない庇護欲を掻き立てられた。
けれど彼の気持ちを最優先にするために、走り出したい衝動をどうにか堪える。
「亜嵐さん。俺のためにこんなにしてくれて……俺、すごく……」
「君相手だから、私はこうしたいんだ。それより早く家に入りなさい、風邪が酷くなってしまう」
「はい……うぇっ……」
しかしなかなか動けない湊に、亜嵐はちょっとだけ声を低くした。
「風邪は他人にうつすと治るらしいな。何なら私が、君の風邪を引き受けてもいいのだが――」
「だっ、ダメです!」
湊は慌てて荷物を抱え、扉の向こうに姿を消した。
それを見て、亜嵐は安堵の笑みを浮かべた。
しばらくすると、生活感のない家の窓に、ぽつんと明かりが灯った。
その明るさの下で、花を眺めながら湊は差し入れを食べているはずだ。
それだけで、亜嵐の心に安堵が広がる。
「――また来週、必ず会おう。湊」
名残惜しい気持ちを抑え、亜嵐は明かりに背を向け歩き出した。
アスファルトを踏む革靴の音は、静かな住宅街に溶け込んでいった。
秘密はいつもティーカップの向こう側 BONUS TRACK
風邪っぴきの君へ / 完
◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側
本編もアルファポリスで連載中です☕
ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」
シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」
シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」
シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪
金曜日の昼下がり。
ローズメリーで紅茶片手にタブレットを覗き込んでいた亜嵐は、今にもひっくり返りそうな勢いで立ち上がった。
「どうしたの!? 亜嵐さん」
何事かと目を見張る客たちに頭を下げながら翠が駆けつけると、亜嵐は震える指で画面を示した。
翠が覗き込んだそこには、メールアプリが開いており――。
『お疲れさまです。風邪をひいたので、明日のアルバイトはお休みさせてください。――藤宮湊』
「あらあら、大変!」
「そうですとも! 風邪をひいているのに、一人きりだなんて……あぁ、きっと心細いに違いない。私はどうすれば!?」
頭を抱えて狼狽する男を見遣り、翠は「やれやれ……」と眉根を寄せた。
***
「いいこと、亜嵐さん。無理をさせないのが一番なの。だから、藤宮くんが『大丈夫です』って言ったら、おとなしく引き下がるのよ?」
「湊はいつだって奥ゆかしい。――しかし大丈夫。私ならきっと、彼の望むことを読み取れるはずです!」
差し入れのバスケットを大事そうに抱え、やたら使命感に燃える亜嵐に、翠は「はぁ……」とため息を吐いた。
「それがダメだって言ってるの。……やっぱり私が行こうかしら?」
家事一般がからっきしなくせに、自分が行くと言い張るものだから、翠は渋々バスケットを渡したのだが。
(そりゃあ亜嵐さんが顔を見せるのが、一番の薬にはなるでしょうけれど)
湊に関してのみ妙に押しが強いのが、他は完璧なこの男の困ったところだ。
そして湊はいつだって、亜嵐には特別に甘い。
亜嵐がわざわざ自宅にやってきたとなれば、何かと世話を焼こうとするだろう。
「藤宮くんの手を煩わせないこと。ご飯も飲み物も入っているから、亜嵐さんは台所に入っちゃダメよ? それからご飯をあーんで食べさせようとしたり、着替えを手伝おうとしたりもね?」
「……前々から感じていましたが、あなたは私を何だと思っているんです?」
胡乱な目を向けつつ、バスケットを抱えて離さない亜嵐に、翠は再度大きなため息を吐いた。
「じゃあ――行ってらっしゃい。藤宮くんにお大事にって伝えてね」
「はい! 行ってきます!」
気合の入った背中が小さくなるまで見送って、翠はそっと扉を閉じた。
***
亜嵐にとって、湊は特別な存在だ。
自分の話に熱中するときのキラキラした瞳も、ホットケーキを焼いてくれるときの優しい笑顔も、資料整理をしているときの真剣な横顔も、全てが好ましい。
(出会った頃は、どこか似ていると思ったが……とんだ思い違いだった)
人とのかかわりに擦り切れて厭世的になった自分とは違い、湊は悲しみや寂しさと共にありながら、真っ直ぐに相手を見つめて向き合っている。
裏にあるものを疑うのではなく、自分の目で見て感じたものを素直に信じる。
(私は彼のようにできなかった……)
亜嵐の目に映る湊は、いつだって輝いている。
この気持ちは純粋な崇敬だ。
小さな独占欲は否定しないが、そんなものより湊自身を尊重したいと、亜嵐は常々思っている。
ふと、色鮮やかなショーウィンドーが目に飛び込んで来た。
「花屋……そうだ、見舞いには花がつきものだな」
彼のように明るくて、素敵な花を選ぼう。
亜嵐は迷うことなく、自動ドアの前に立った。
***
「いらっしゃいませー!」
「見舞い用の花を作ってほしい」
一陣の風のように現れた美青年に、女性店員はわずかばかり頬を染めた。
「ご希望の雰囲気や色はありますか?」
「見るだけで元気が出るようなものをお願いしたいのだが」
「それなら、オレンジをメインにしたビタミンカラーはいかがでしょう」
ラナンキュラスに手を伸ばした店員に、亜嵐は「いや」と言った。
「その花は私たちに合わない。別の……そうだな」
亜嵐は、生花が所狭しと並んだ冷蔵ショーケースをぐるりと見回した。
――と、その視線がぴたりと止まる。
視線の先にあるのは、色とりどりのガーベラが投げ込まれた青いバケツ。
一つ頷くと、亜嵐は店員を振り返った。
「赤と黄のガーベラを合わせて六本。それ以外の花はお任せする。優しい人を励ますものに仕上げてほしい」
「……はい。かしこまりました」
その花選びと本数に、店員の心はほっこりと温かくなった。
しばらくして出来上がったアレンジメントは、二色のガーベラをメインに、カーネーションや小ぶりな胡蝶蘭が華を添える豪奢なものになった。
亜嵐は一つ一つの花を丁寧に確認すると、店員に「素敵なものをありがとう」と言って、店を後にした。
(気に入ってもらえてよかった。あれだけの想いが込められた花がもらえる相手の人、ちょっと羨ましいかも……なんてね)
作業台を片付けながら、店員は目を細めてふふっと笑った。
***
湊の自宅最寄り駅に到着した亜嵐は、スマートフォンを取り出した。
アルバイト用に一応履歴書をもらっているので、住所は知っている。
地図アプリに入力しておいたので、あとはナビの通りに歩けばいい。
そのはずだった。
「……おかしいな」
ナビが到着を告げたポイントは、ぽつんと空いた更地だった。
どこかで道を一本間違えたかとナビを再起動しても、頑なに『到着』を表示するばかり。
「これは……困った」
近くには来ているはずだから、湊に連絡をすれば――そう考えて、亜嵐はふるふると首を振った。
体調が悪い湊に迎えを頼むなど、できるはずがない。
亜嵐は空き地に背を向けると、近くの家の表札を一軒ずつ確認し始めた。
「――あった! ここだ」
ひとつ辻を違えた場所に、目指す家はあった。
木製の桟を模した塀が敷地をぐるりと取り囲み、植栽はほとんどない。
駐車スペースはがらんどうで、冷たいコンクリートがむき出しになっていた。
母親を早くに亡くし、残されたのは思春期の息子と、仕事柄家を空ける父。
最低限片付けられてはいるが、生活の匂いが少ないのも当然と言えた。
ポストと一体になった門の前で荷物を下ろすと、亜嵐は手で髪をさっと整え、上着を払った。
そしてぐっと息を呑むと、震える手でインターフォンを押した。
「…………」
一分ほど待ってみたが、反応はない。
もう一度押すと、今度は慌てたような声が機械を通して響いた。
『はっ、はい……! どちら様ですか?』
「私だ、湊」
『えっ……えぇっ、亜嵐さん!?』
ドタドタという音を最後に通話が途切れ、代わりにカチリという音が手元で鳴った。
門の鍵が開いたようだ。
門扉から玄関ドアまでのアプローチを、可能な限り速足で進む。
――と。
ドタンッ!
人が転んだような大きな音が響き、続いてガチャッ! とドアが開く音がした。
ハッとして見ると、カーディガンを羽織った湊が、ぴょこりと外を窺っていた。
その手は痛そうに、癖毛の跳ねた頭を擦っている。
「湊! 大丈夫――」
「来ないでっ!」
鋭い言葉と共に玄関ドアはバン! と閉じられ、カチャリと鍵が掛けられた。
亜嵐は駆け寄って、ドアをドンドンと叩いた。
「湊、どうして!?」
「何で来たんですか!」
「何でって……体調が悪い君を、放ってなどおけるものか!」
ドアに縋りつくものの、鍵が開く気配はない。
不安と焦りで、亜嵐は激しく動揺した。
「翠さんが作った差し入れを持って来たんだ。元気が出るように花も選んだ。開けてくれ、湊!」
「ダメです! 全部そこに置いて、すぐ帰ってください!」
「湊、そんな……君が私を拒むなんて……」
その呟きは弱々しく、ドアに当てた手も震えている。
すると無機質な扉を隔てて、啜り泣くような声が亜嵐の耳に届いた。
「亜嵐さんが、来てくれたのは……うっ、うれしいけどっ! でも、会ったら……っ」
途切れ途切れの声に、亜嵐の胸は締め付けられる。
「病気と知って、いてもたってもいられなくなった。私は君に会いたい、顔が見たいんだ。君も同じ気持ちなら、どうかここを開けてほしい」
真摯に懇願するも、扉の向こうの湊が動く気配はない。
そして涙ながらの声は「ダメです」と重ねた。
「だって……会って風邪をうつしたくないんです。俺のせいで亜嵐さんに苦しい思いをさせるなんて、絶対に嫌なんです。だから……会えません。お願いです、帰ってください……」
ずびっと鼻を啜り、ついで軽く咳き込む息音。
それを聞いた亜嵐は足元に視線を落とし、拳をギュッと握った。
「……わかった。君の言うとおりにしよう。だが本当に辛くなったら、いつでも連絡してくれ。真夜中だって構わない……いいね? 必ずだ」
「はい。ありがとうございます、亜嵐さん。ごめんなさい……」
「謝る必要はない、押し掛けたのは私なのだから。……ではこれで失礼する。翠さんの料理は必ず食べるように、きっと元気になる」
バスケットと花を玄関前に並べると、亜嵐は足を引きずるようにその場を後にした。
完全に気配がなくなってから、湊は鍵を開け、そっと扉を押した。
そこに置かれていたのは、赤いチェックの布が掛けられた大きなバスケットと、鮮やかなガーベラが目を惹く大きなフラワーアレンジメント。
「うわぁ、すっごく綺麗だ。……あれ?」
カーネーションの隙間に小さなカードがあるのに気付き、湊はそれを手に取った。
二つ折りのカードを広げると――。
『君のいない週末は寂しい。待っているから、早く元気になってほしい』
美しい文字で綴られた、切なる言葉。
「あ……亜嵐さん……」
ぶわっと涙が溢れる。
(本当は会いたかった――傍にいてほしかった……!)
自分から断ったけれど、扉一枚の距離に亜嵐がいたことがうれしくて、同時にその距離が恨めしくなった。
「ふぇっ……」
上着の袖で涙を拭いながら差し入れを持ちあげようとして――。
「……あ」
門扉の陰から玄関を覗き込む男と目が合う。
途端、男は両手を大袈裟に振った。
「これ以上近寄ったりしない! だからせめて君が家に入るまでは、見届けさせてくれ!」
「……っ! あ、亜嵐さん……」
その場に座り込み、べそべそと泣き出した湊に、亜嵐はどうしようもない庇護欲を掻き立てられた。
けれど彼の気持ちを最優先にするために、走り出したい衝動をどうにか堪える。
「亜嵐さん。俺のためにこんなにしてくれて……俺、すごく……」
「君相手だから、私はこうしたいんだ。それより早く家に入りなさい、風邪が酷くなってしまう」
「はい……うぇっ……」
しかしなかなか動けない湊に、亜嵐はちょっとだけ声を低くした。
「風邪は他人にうつすと治るらしいな。何なら私が、君の風邪を引き受けてもいいのだが――」
「だっ、ダメです!」
湊は慌てて荷物を抱え、扉の向こうに姿を消した。
それを見て、亜嵐は安堵の笑みを浮かべた。
しばらくすると、生活感のない家の窓に、ぽつんと明かりが灯った。
その明るさの下で、花を眺めながら湊は差し入れを食べているはずだ。
それだけで、亜嵐の心に安堵が広がる。
「――また来週、必ず会おう。湊」
名残惜しい気持ちを抑え、亜嵐は明かりに背を向け歩き出した。
アスファルトを踏む革靴の音は、静かな住宅街に溶け込んでいった。
秘密はいつもティーカップの向こう側 BONUS TRACK
風邪っぴきの君へ / 完
◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側
本編もアルファポリスで連載中です☕
ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」
シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」
シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」
シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪
2
あなたにおすすめの小説

秘密はいつもティーカップの向こう側 ~追憶の英国式スコーン~
天月りん
キャラ文芸
食べることは、生きること。
紅茶がつなぐのは、人の想いと、まだ癒えぬ記憶。
大学生・湊と英国紳士・亜嵐が紡ぐ、心を温めるハートフル・ストーリー。
――つまり料理とは、単なる習慣ではなく、歴史の語り部でもあるのだよ――
その言葉に心を揺らした大学生・藤宮湊は、食文化研究家にしてフードライターの西園寺亜嵐と出会う。
ひょんな縁から彼と同じテーブルで紅茶を飲むうちに、湊は『食と心』に秘められた物語へと惹かれていく。
舞台は、ティーハウス<ローズメリー>
紅茶の香りが、人々の過去と未来を優しく包み込み、二人の絆を静かに育んでいく――。
◆・◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪

秘密はいつもティーカップの向こう側 ~サマープディングと癒しのレシピ~
天月りん
キャラ文芸
食べることは、生きること。
紅茶とともに、人の心に寄り添う『食』の物語、再び。
「栄養学なんて、大嫌い!」
大学の図書館で出会った、看護学部の女学生・白石美緒。
彼女が抱える苦手意識の裏には、彼女の『過去』が絡んでいた。
大学生・藤宮湊と、フードライター・西園寺亜嵐が、食の知恵と温かさで心のすれ違いを解きほぐしていく――。
ティーハウス<ローズメリー>を舞台に贈る、『秘密はいつもティーカップの向こう側』シリーズ第2弾。
紅茶と食が導く、優しくてちょっぴり切ないハートフル・キャラ文芸。
◆・◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪
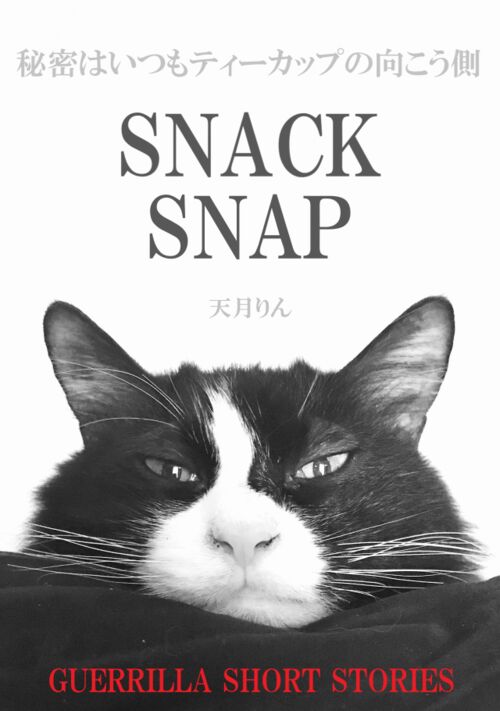
秘密はいつもティーカップの向こう側 ―SNACK SNAP―
天月りん
キャラ文芸
食べることは、生きること。
ティーハウス<ローズメリー>に集う面々に起きる、ほんの些細な出来事。
楽しかったり、ちょっぴり悲しかったり。
悔しかったり、ちょっぴり喜んだり。
彼らの日常をそっと覗き込んで、写し撮った一枚のスナップ――。
『秘密はいつもティーカップの向こう側』SNACK SNAPシリーズ。
気まぐれ更新。
ティーカップの紅茶に、ちょっとミルクを入れるようなSHORT STORYです☕
◆・◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側(本編) ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪

烏の王と宵の花嫁
水川サキ
キャラ文芸
吸血鬼の末裔として生まれた華族の娘、月夜は家族から虐げられ孤独に生きていた。
唯一の慰めは、年に一度届く〈からす〉からの手紙。
その送り主は太陽の化身と称される上級華族、縁樹だった。
ある日、姉の縁談相手を誤って傷つけた月夜は、父に遊郭へ売られそうになり屋敷を脱出するが、陽の下で倒れてしまう。
死を覚悟した瞬間〈からす〉の正体である縁樹が現れ、互いの思惑から契約結婚を結ぶことになる。
※初出2024年7月

妻が通う邸の中に
月山 歩
恋愛
最近妻の様子がおかしい。昼間一人で出掛けているようだ。二人に子供はできなかったけれども、妻と愛し合っていると思っている。僕は妻を誰にも奪われたくない。だから僕は、妻の向かう先を調べることににした。


『後宮祓いの巫女は、鬼将軍に嫁ぐことになりました』
由香
キャラ文芸
後宮で怪異を祓う下級巫女・紗月は、ある日突然、「鬼」と噂される将軍・玄耀の妻になれと命じられる。
それは愛のない政略結婚――
人ならざる力を持つ将軍を、巫女の力で制御するための契約だった。
後宮の思惑に翻弄されながらも、二人は「契約」ではなく「選んだ縁」として、共に生きる道を選ぶ――。

〖完結〗終着駅のパッセージ
苺迷音
恋愛
分厚い眼鏡と、ひっつめた髪を毛糸帽で覆う女性・カレン。
彼女はとある想いを胸に北へ向かう蒸気機関車に乗っていた。
王都から離れてゆく車窓を眺めながら、カレンは振り返る。
夫と婚姻してから三年という長い時間。
その間に夫が帰宅したのは数えるほどだった。
※ご覧いただけましたらとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















