5 / 8
愉悦の果てに
しおりを挟む
蝋燭の明かりが揺らめく寝室に、あえかな嬌声と淫靡な水音が響く。
簡素な寝台の上では一糸まとわぬ姿のアマーリエに、半裸のリナルドが覆いかぶさっていた。
「あっ! あ、あ」
雨のように落ちてくる接吻と、絶え間なく施される巧みな愛撫――リナルドはどこまでも優しく、アマーリアは全身を桜色に染めながら震えていた。
恥ずかしくてしかたないのに、快感を追わずにいられない。
嫁ぐ日のために房事について教えられてはいたが、初めて知る行為は想像をはるかに超えていた。
リナルドの指や唇は信じられないようなところに触れ、優しく探り、未知の扉を次々と開いていった。何かされるたびに、両脚の間にある秘められた場所が疼いて、とろりと蜜を零す。
アマーリアは怯えながらも愉悦に酔いしれた。
「だめぇ……そんな」
自分の声とは思えないような鼻にかかった喘ぎ声。
しかしいくら訴えても、リナルドは甘い攻撃をやめてはくれない。
「望んだのは……あなたです、アマーリア様」
ただ囁かれるだけでも妖しい刺激を感じてしまうのに、ふいに右胸の頂に口づけられた。唇で肉粒を挟まれ、舌先で突かれて、閉じた目蓋の裏で白い光が弾けた。
「やうっ!」
「かわいらしい方だ、本当に」
性戯に不慣れで生硬な身体を気遣ってくれているのだろう。
リナルドは決して急がず、丁寧にアマーリアを追い上げる。
(わたくしはずっと……こうしてほしかったのだわ)
リナルドと肌を合わせたのは、ある目的を果たすためだ。
それなのに快楽の渦に巻き込まれ、そのまま押し流されそうになる。何年も一緒に過ごすうちに、アマーリアは献身的な従者に心惹かれるようになっていたのだから。
いつからリナルドの姿を目で追うようになったのだろう?
旅の途中、森で襲ってきた獣を切り捨ててくれた時?
それともまったくの初心者であるアマーリアに、根気よく剣術を教えてくれた時だろうか?
いや、もしかしたら初めて会った日に、もう恋に落ちていたのかもしれない。
リナルドは常に一番重い荷物を持ち、誰より先に起きて、床につくのは最後だ。口数は多くないが、心が折れそうになった時は必ず隣で励ましてくれた。
けれども彼への想いが深まるにつれ、アマーリアの胸にはある疑惑が芽生え、その暗い影は日ごとに大きくなっていった。こうして抱かれている今でさえも。
「リナルド、待って……お願いだから」
さんざん喘がされ、掠れ始めた声で、アマーリアは懸命に訴えた。
「わたくしに……あなたのすべてを見せて……どうか今宵の思い出に」
「かしこまりました」
リナルドには睦言のように聞こえたかもしれないが、狙いは別にあった。
アマーリアは彼の身体に刻まれているかもしれない標を探そうとしていたのだ。
本当はそんなことをしたくなかった。きっと何も見つからない、リナルドに裏の顔などあるはずがない――何度もそう思い込もうとしてきたけれど。
ほどなく蝋燭の明かりが、軍神のように鍛え上げられた肉体と、その中心で息づく欲望を照らし出した。
「お許しください、アマーリア様。俺は……あなたをお慕いしておりました。従者の身でありながら、もう何年間も」
「うれしいわ、リナルド」
両脚を割り開かれ、熱杭に穿たれて、アマーリアは泣きながら呟く。
その言葉に嘘はなかったが、もはや幸福な未来を夢見ることはできなかった。
耳の奥で、母から聞かされた子守歌が鳴り響いていたのだ。
――二つの頭を持つ獅子が、近づかないよう守ってる
リナルドの下腹部、ちょうど臍の右下あたりに双頭の獅子の刺青が彫られていることを、アマーリアははっきり確認してしまったのだから。
簡素な寝台の上では一糸まとわぬ姿のアマーリエに、半裸のリナルドが覆いかぶさっていた。
「あっ! あ、あ」
雨のように落ちてくる接吻と、絶え間なく施される巧みな愛撫――リナルドはどこまでも優しく、アマーリアは全身を桜色に染めながら震えていた。
恥ずかしくてしかたないのに、快感を追わずにいられない。
嫁ぐ日のために房事について教えられてはいたが、初めて知る行為は想像をはるかに超えていた。
リナルドの指や唇は信じられないようなところに触れ、優しく探り、未知の扉を次々と開いていった。何かされるたびに、両脚の間にある秘められた場所が疼いて、とろりと蜜を零す。
アマーリアは怯えながらも愉悦に酔いしれた。
「だめぇ……そんな」
自分の声とは思えないような鼻にかかった喘ぎ声。
しかしいくら訴えても、リナルドは甘い攻撃をやめてはくれない。
「望んだのは……あなたです、アマーリア様」
ただ囁かれるだけでも妖しい刺激を感じてしまうのに、ふいに右胸の頂に口づけられた。唇で肉粒を挟まれ、舌先で突かれて、閉じた目蓋の裏で白い光が弾けた。
「やうっ!」
「かわいらしい方だ、本当に」
性戯に不慣れで生硬な身体を気遣ってくれているのだろう。
リナルドは決して急がず、丁寧にアマーリアを追い上げる。
(わたくしはずっと……こうしてほしかったのだわ)
リナルドと肌を合わせたのは、ある目的を果たすためだ。
それなのに快楽の渦に巻き込まれ、そのまま押し流されそうになる。何年も一緒に過ごすうちに、アマーリアは献身的な従者に心惹かれるようになっていたのだから。
いつからリナルドの姿を目で追うようになったのだろう?
旅の途中、森で襲ってきた獣を切り捨ててくれた時?
それともまったくの初心者であるアマーリアに、根気よく剣術を教えてくれた時だろうか?
いや、もしかしたら初めて会った日に、もう恋に落ちていたのかもしれない。
リナルドは常に一番重い荷物を持ち、誰より先に起きて、床につくのは最後だ。口数は多くないが、心が折れそうになった時は必ず隣で励ましてくれた。
けれども彼への想いが深まるにつれ、アマーリアの胸にはある疑惑が芽生え、その暗い影は日ごとに大きくなっていった。こうして抱かれている今でさえも。
「リナルド、待って……お願いだから」
さんざん喘がされ、掠れ始めた声で、アマーリアは懸命に訴えた。
「わたくしに……あなたのすべてを見せて……どうか今宵の思い出に」
「かしこまりました」
リナルドには睦言のように聞こえたかもしれないが、狙いは別にあった。
アマーリアは彼の身体に刻まれているかもしれない標を探そうとしていたのだ。
本当はそんなことをしたくなかった。きっと何も見つからない、リナルドに裏の顔などあるはずがない――何度もそう思い込もうとしてきたけれど。
ほどなく蝋燭の明かりが、軍神のように鍛え上げられた肉体と、その中心で息づく欲望を照らし出した。
「お許しください、アマーリア様。俺は……あなたをお慕いしておりました。従者の身でありながら、もう何年間も」
「うれしいわ、リナルド」
両脚を割り開かれ、熱杭に穿たれて、アマーリアは泣きながら呟く。
その言葉に嘘はなかったが、もはや幸福な未来を夢見ることはできなかった。
耳の奥で、母から聞かされた子守歌が鳴り響いていたのだ。
――二つの頭を持つ獅子が、近づかないよう守ってる
リナルドの下腹部、ちょうど臍の右下あたりに双頭の獅子の刺青が彫られていることを、アマーリアははっきり確認してしまったのだから。
0
あなたにおすすめの小説

『嫌われ令嬢ですが、最終的に溺愛される予定です』
由香
恋愛
貴族令嬢エマは、自分が周囲から嫌われていると信じて疑わなかった。
婚約者である侯爵令息レオンからも距離を取られ、冷たい視線を向けられている――そう思っていたのに。
ある日、思いがけず聞いてしまった彼の本音。
「君を嫌ったことなど、一度もない」
それは誤解とすれ違いが重なっただけの、両片思いだった。
勘違いから始まる、甘くて優しい溺愛恋物語。

英雄魔術師様とのシークレットベビーが天才で隠し通すのが大変です
氷雨そら
恋愛
――この魔石の意味がわからないほど子どもじゃない。
英雄魔術師カナンが遠征する直前、フィアーナと交わした一夜で授かった愛娘シェリア。フィアーナは、シェリアがカナンの娘であることを隠し、守るために王都を離れ遠い北の地で魔石を鑑定しながら暮らしていた。けれど、シェリアが三歳を迎えた日、彼女を取り囲む全ての属性の魔石が光る。彼女は父と同じ、全属性の魔力持ちだったのだ。これは、シークレットベビーを育てながら、健気に逞しく生きてきたヒロインが、天才魔術師様と天才愛娘に翻弄されながらも溺愛される幸せいっぱいハートフルストーリー。小説家になろうにも投稿しています。

【完結】無口な旦那様は妻が可愛くて仕方ない
ベル
恋愛
旦那様とは政略結婚。
公爵家の次期当主であった旦那様と、領地の経営が悪化し、没落寸前の伯爵令嬢だった私。
旦那様と結婚したおかげで私の家は安定し、今では昔よりも裕福な暮らしができるようになりました。
そんな私は旦那様に感謝しています。
無口で何を考えているか分かりにくい方ですが、とてもお優しい方なのです。
そんな二人の日常を書いてみました。
お読みいただき本当にありがとうございますm(_ _)m
無事完結しました!

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

バッドエンド予定の悪役令嬢が溺愛ルートを選んでみたら、お兄様に愛されすぎて脇役から主役になりました
美咲アリス
恋愛
目が覚めたら公爵令嬢だった!?貴族に生まれ変わったのはいいけれど、美形兄に殺されるバッドエンドの悪役令嬢なんて絶対困る!!死にたくないなら冷酷非道な兄のヴィクトルと仲良くしなきゃいけないのにヴィクトルは氷のように冷たい男で⋯⋯。「どうしたらいいの?」果たして私の運命は?
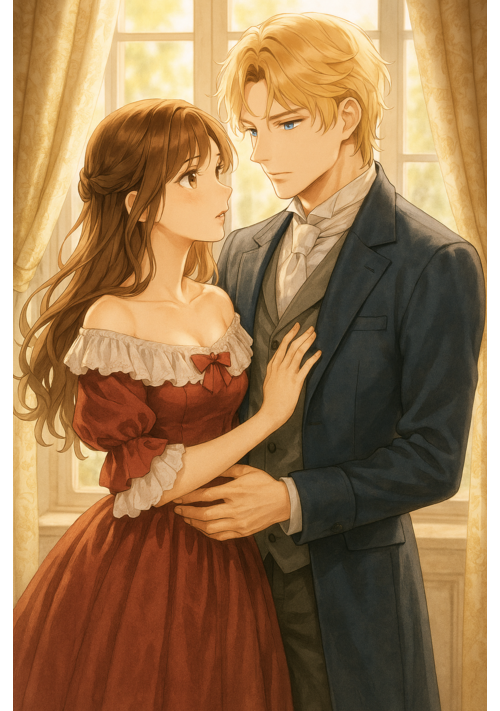
《完結》追放令嬢は氷の将軍に嫁ぐ ―25年の呪いを掘り当てた私―
月輝晃
恋愛
25年前、王国の空を覆った“黒い光”。
その日を境に、豊かな鉱脈は枯れ、
人々は「25年ごとに国が凍る」という不吉な伝承を語り継ぐようになった。
そして、今――再びその年が巡ってきた。
王太子の陰謀により、「呪われた鉱石を研究した罪」で断罪された公爵令嬢リゼル。
彼女は追放され、氷原にある北の砦へと送られる。
そこで出会ったのは、感情を失った“氷の将軍”セドリック。
無愛想な将軍、凍てつく土地、崩れゆく国。
けれど、リゼルの手で再び輝きを取り戻した一つの鉱石が、
25年続いた絶望の輪を、少しずつ断ち切っていく。
それは――愛と希望をも掘り当てる、運命の物語。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

狼隊長さんは、私のやわはだのトリコになりました。
汐瀬うに
恋愛
目が覚めたら、そこは獣人たちの国だった。
元看護師の百合は、この世界では珍しい“ヒト”として、狐の婆さんが仕切る風呂屋で働くことになる。
与えられた仕事は、獣人のお客を湯に通し、その体を洗ってもてなすこと。
本来ならこの先にあるはずの行為まで求められてもおかしくないのに、百合の素肌で背中を撫でられた獣人たちは、皆ふわふわの毛皮を揺らして眠りに落ちてしまうのだった。
人間の肌は、獣人にとって子犬の毛並みのようなもの――そう気づいた時には、百合は「眠りを売る“やわはだ嬢”」として静かな人気者になっていた。
そんな百合の元へある日、一つの依頼が舞い込む。
「眠れない狼隊長を、あんたの手で眠らせてやってほしい」
戦場の静けさに怯え、目を閉じれば仲間の最期がよみがえる狼隊長ライガ。
誰よりも強くあろうとする男の震えに触れた百合は、自分もまた失った人を忘れられずにいることを思い出す。
やわらかな人肌と、眠れない心。
静けさを怖がるふたりが、湯気の向こうで少しずつ寄り添っていく、獣人×ヒトの異世界恋愛譚。
[こちらは以前あげていた「やわはだの、お風呂やさん」の改稿ver.になります]
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















