14 / 87
第1章 ◆ はじまりと出会いと
14. ライゼンとクリス
しおりを挟む
私はグランツ学園魔導具研究科五年生のライゼン。
魔導具研究科最高顧問のクレスト様は、私の魔導具の師だ。
助手として学園に連れてこられたが、師が「いい機会だから魔導具研究科に入るといい」と言ったので生徒になってしまった。
正直、人と関わるのは苦手だ。というか嫌いかもしれない。
関わらないといけないのは十分わかっているが、それでも嫌なものは嫌なのだ。
だから、極力人と関わるのを避けている。
「ライゼンさんっ」
聞き覚えのある声に呼ばれた。
振り返って見れば、いつか学園で会った少女がいた。
初めて会った時と同じ、教育科の制服を着ている。
名は、確かクリスと言ったか。
私にしては珍しく、自分から関わった人間だ。
初めて出会った日、少女が無邪気に校舎を見ていたものだから、気になってしばらく様子を見ていた。
すると、周りを歩く人々が立ち止まっている少女を疎ましそうに見ていくので、これではいけないと思い、声をかけた。
そのまま手を繋いで案内してしまったのは自分でも驚いている。
少女があまりにも純粋だったから、思わず助けたいと思ってしまったのだ。
その少女、クリスを改めて見れば、息が上がっている。
走ってきたのか?
「ラ、ライゼンさん、っも、この馬車、乗るん、っです、か!?」
「まずは息を整えろ」
あまりにも息苦しそうだから、いったん落ち着いてもらう。
クリスは両腕を広げたり閉じたり、深呼吸を何度かして息を整える。
その仕草は子どもらしく、動く度に頭のアホ毛がぴょこぴょこ揺れている。
ん?出会ったときは感じなかったが、こんなに背が小さかっただろうか?
もっと大きい印象だったのだが。
そう思いながら見つめていると、気まずそうにクリスが目を合わせてきた。
「えと、声かけたらいけなかったですか?」
困った顔で見上げてくるクリス。
「いや。ただ、小さいなと思っていただけだ」
「がーん」
しまった、言葉が足りなかったかもしれない。
クリスはとてもショックを受けたという顔をしていた。
その後は肩を落として、しょぼん…と効果音まで聞こえてきそうな落ち込みっぷり。
へにょりとアホ毛も落ち込んでいるように見えるのは気のせいだろうか。
小さい子どもを相手にするのは得意ではないのだが仕方がない。
「そんな顔をするな。悪口で言ったわけではない」
ぎこちなく、頭をぽんぽんとなでてやる。
クリスは驚いたように顔を上げたが、すぐに目を輝かせて笑った。
ころころ変わる表情に、彼女の素直さが見て取れる。
「馬車に乗るのかという質問だったな。肯定だ」
「こ、こうてい…?」
首をかしげるクリス。
ああ、そうか。肯定という言葉を知らないのか。
いや、こんな子どもが使っていたら驚く。普通使わない。
「肯定とは…」
「ちょっと待って!」
慌てて言葉をさえぎってくると、考える仕草をするクリス。
誰かに教えてもらったことがあるのか、意味を思い出そうとしているようだ。
「えーと、えーと、うー…、お兄ちゃんが言ってたよね…あっ!」
ぴょこんっとアホ毛が揺れる。
何なんだ、このアホ毛。
感情と連動しているのか?
「そのとおりって意味ですよね!?」
両手で握り拳をしながら自信満々に言ったクリス。
内心苦笑しながら肯定を表す。
クリスは正解したのがうれしかったのか、また笑顔になった。
「えへへっ。じゃあ、ライゼンさんと同じ馬車で帰れるんだ。うれしいな」
今度は口に両手を当てながら笑う。
聞こえないように呟いているようだが、丸聞こえだ。
女というものは面倒で嫌いだが、クリスのような子どもの純粋さは嫌いではない。
今まで見てきた人間は醜い感情ばかりで、一緒にいるだけで吐き気がしていた。
だが、この少女の素直さは不思議と心が癒される気分だ。
「…クリスは、どこまで帰るんだ?」
「ここから三つ目の停留所の村です」
クリスは行き先に続いている道を指差しながら言った。
私のお遣いの行き先と同じだ。
クリスはユグ村の子どもだったのか。
ユグ村はオルデンと東の街イスントの間にある大きな森の中にある村だ。
村と言っても小さくはなく、役所や自警団がある。
周りは「深霧の森」に囲まれていて、通過する時は必ず一度この村で停留しなければならない。
それは、この村が森を護る仕事を森の精霊から受けており、森を抜けるには、村から「加護」魔法を受けなければならないからだ。
「深霧の森」は、厄介なことに入るのは自由だが、抜けるのは不可能だ。
「加護」を持たない者は、森で彷徨い続けて果てるか、「あちら」へ連れて行かれる。
森の精霊はこちらが何もしなければ、おとなしい。
だが、森に危害を加えたり、怒らせることをすると「加護」を発動させる。
発動させられたら最後、「こちら」へ戻っては来られなくなる。
この「加護」は森を抜けると解けるようになっていて、森の中での印でもあり保険だが、通る人のためのものではない。森のためのものだということだ。
ちなみに、ユグ村の者は「加護」がなくても森を通過することができる。
それは、村の者を精霊が仲間と認識するのだとか。
だから、馬車で森へ近づいてくると御者がユグ村の御者と交代する。
村に着くまでの間は、ユグ村の者に免じて精霊が森の中を通してくれるというわけだ。
…話が逸れた。
懐の懐中時計を見れば、夕方の五時を過ぎていた。
いつもなら、定刻の少し前に着くはずの馬車はまだ来ていない。定刻はもう過ぎている。
クリスも遅い馬車が気になっているようだ。不安そうに道を見つめている。
立っているのも疲れてきたから、停留所のベンチにクリスと座ることにした。
クリスは大きな荷物に気がついたようで、じっと荷物の方を見つめてくる。
それに気づかないふりをして、無言で馬車を待つ。
「…ライゼンさんは、何科の生徒なんですか?その制服、教育科ではないですよね?」
「……」
答える義務も義理もないから、無言でやり過ごす。
知っても関係のないことだ。
「ご、ごめんなさい。聞いちゃダメでしたか?」
目を向ければ、最初に出会った時と同じ顔で見上げてくるクリス。
怖がっているような、困っているような顔だ。
目を合わせると一瞬怯んだようだったが、それでも一生懸命見つめてくる。
クリスの大きな目は、まるで磨かれた宝玉のようだった。
それをよく見ようと顔を近づけようとしたら、馬車がやってきた。
「ごめんね~。待たせたね~」
年配の男性御者がゆっくり馬を停止させて、馬車に乗り込むための板を降ろす。
馬車には誰も乗っていなかった。
普段なら、御者がもう一人「深霧の森」のために乗っているはずだ。
いないということは、この馬車の御者はユグ村の者だということだろう。
何事もなかったかのようにクリスから離れて、馬車に乗る。
クリスも慌てて馬車に乗り込んだ。
「それじゃあ、出発するよ~」
御者の声に二人で頷けば、馬車はゆっくりと動き出す。
街の石畳をしばらく走り、街を抜ければ「深霧の森」まで平原が広がっている。
平原にも停留所があるが、滅多に人が乗ってくることはない。
それは、ユグ村までクリスと馬車の中で二人きりになることを意味していた。
ガラガラガラガラ…
順調に馬車は街を出て平原を走る。
ここまで一言もクリスと話すことなく、目を合わすこともしなかった。
目を上げると、クリスは隅の方で蹲るように膝を抱いて座っている。
さっきの会話で怒らせたとでも思っているのだろう、アホ毛が落ち込んでいる。
本当にわかりやすい。
「クリス」
呼ばれた少女は恐る恐るこちらを見上げる。
その目を見ると、何かが揺らめいて瞬きをした。
不安に揺れる瞳は先ほど近くで見た時よりも暗くなっている。
「ライゼンさん、怒ってますか?訊いちゃいけないことだったなら、ごめんなさい…」
怒ってはいないのだが、そんな風に言われれば無視した自分が悪い気がしてくる。
いや、ここは自分が悪いのだろう。
いつも師に「言葉が足りない」と言われるから。
小さくため息をついて、クリスの隣へ席を移す。
「いや、怒っていない。悪かった。言う必要がないと思っていたんだ」
「そ、そうだったんですか…?」
驚いた顔で見上げてくるクリスの目は、もう暗くなかった。
停留所で見た時も思ったが、不思議な目だ。
ラズベリーレッド色の目は、まるで水面に映る星空のように光が散りばめられて輝いている。
本当に星があるのではないだろうか?
それに引き込まれるように見つめていると、クリスが目を泳がせた。
「えと、言いたくないのなら言わなくていいです。誰にだって、秘密はあります」
「言いたくないというわけではない。…私は魔導具研究科の五年生だ」
「まどーぐ?」
不思議そうに首を傾げるクリスに、内心笑ってしまった。
本当に感情に素直な奴だ。
そんな風に見つめられたら、釣られて答えたくなってしまうではないか。
「魔導具は魔法が込められた道具だ。身近なもので言えば、そうだな…」
大きな荷物の中から一つの道具を探す。クリスは興味津々に身を乗り出して私の手元を見ていた。
程なくして、荷物の奥から目当てのものを見つけ、少女ーnの手に小さなカンテラを乗せた。
「明かり!」
クリスにとっては珍しいものなのだろうな。
小さなカンテラをうれしそうに観察する姿は、なんとも微笑ましい。
「これはカンテラ。この窪みを押すと明かりがつく。この中の光は、この道具に込められた光魔法で輝いている」
「へえぇ~!」
説明しながらカンテラに明かりをつけて見せると、クリスは一層目を輝かせた。
こんなどこにでもある道具でそこまで喜んでもらえるとは。
思わず綻びそうになった口元を慌てて抑えた。
「ねえ!ライゼンさん!他にもある!?」
「見てみたいか?」
「うんっ!」
こうして、すっかり敬語を遣うのを忘れたクリスとユグ村に着くまで魔導具について話した。
このクリスとの会話はとても楽しく、今の自分には得難い時間だった。
魔導具研究科最高顧問のクレスト様は、私の魔導具の師だ。
助手として学園に連れてこられたが、師が「いい機会だから魔導具研究科に入るといい」と言ったので生徒になってしまった。
正直、人と関わるのは苦手だ。というか嫌いかもしれない。
関わらないといけないのは十分わかっているが、それでも嫌なものは嫌なのだ。
だから、極力人と関わるのを避けている。
「ライゼンさんっ」
聞き覚えのある声に呼ばれた。
振り返って見れば、いつか学園で会った少女がいた。
初めて会った時と同じ、教育科の制服を着ている。
名は、確かクリスと言ったか。
私にしては珍しく、自分から関わった人間だ。
初めて出会った日、少女が無邪気に校舎を見ていたものだから、気になってしばらく様子を見ていた。
すると、周りを歩く人々が立ち止まっている少女を疎ましそうに見ていくので、これではいけないと思い、声をかけた。
そのまま手を繋いで案内してしまったのは自分でも驚いている。
少女があまりにも純粋だったから、思わず助けたいと思ってしまったのだ。
その少女、クリスを改めて見れば、息が上がっている。
走ってきたのか?
「ラ、ライゼンさん、っも、この馬車、乗るん、っです、か!?」
「まずは息を整えろ」
あまりにも息苦しそうだから、いったん落ち着いてもらう。
クリスは両腕を広げたり閉じたり、深呼吸を何度かして息を整える。
その仕草は子どもらしく、動く度に頭のアホ毛がぴょこぴょこ揺れている。
ん?出会ったときは感じなかったが、こんなに背が小さかっただろうか?
もっと大きい印象だったのだが。
そう思いながら見つめていると、気まずそうにクリスが目を合わせてきた。
「えと、声かけたらいけなかったですか?」
困った顔で見上げてくるクリス。
「いや。ただ、小さいなと思っていただけだ」
「がーん」
しまった、言葉が足りなかったかもしれない。
クリスはとてもショックを受けたという顔をしていた。
その後は肩を落として、しょぼん…と効果音まで聞こえてきそうな落ち込みっぷり。
へにょりとアホ毛も落ち込んでいるように見えるのは気のせいだろうか。
小さい子どもを相手にするのは得意ではないのだが仕方がない。
「そんな顔をするな。悪口で言ったわけではない」
ぎこちなく、頭をぽんぽんとなでてやる。
クリスは驚いたように顔を上げたが、すぐに目を輝かせて笑った。
ころころ変わる表情に、彼女の素直さが見て取れる。
「馬車に乗るのかという質問だったな。肯定だ」
「こ、こうてい…?」
首をかしげるクリス。
ああ、そうか。肯定という言葉を知らないのか。
いや、こんな子どもが使っていたら驚く。普通使わない。
「肯定とは…」
「ちょっと待って!」
慌てて言葉をさえぎってくると、考える仕草をするクリス。
誰かに教えてもらったことがあるのか、意味を思い出そうとしているようだ。
「えーと、えーと、うー…、お兄ちゃんが言ってたよね…あっ!」
ぴょこんっとアホ毛が揺れる。
何なんだ、このアホ毛。
感情と連動しているのか?
「そのとおりって意味ですよね!?」
両手で握り拳をしながら自信満々に言ったクリス。
内心苦笑しながら肯定を表す。
クリスは正解したのがうれしかったのか、また笑顔になった。
「えへへっ。じゃあ、ライゼンさんと同じ馬車で帰れるんだ。うれしいな」
今度は口に両手を当てながら笑う。
聞こえないように呟いているようだが、丸聞こえだ。
女というものは面倒で嫌いだが、クリスのような子どもの純粋さは嫌いではない。
今まで見てきた人間は醜い感情ばかりで、一緒にいるだけで吐き気がしていた。
だが、この少女の素直さは不思議と心が癒される気分だ。
「…クリスは、どこまで帰るんだ?」
「ここから三つ目の停留所の村です」
クリスは行き先に続いている道を指差しながら言った。
私のお遣いの行き先と同じだ。
クリスはユグ村の子どもだったのか。
ユグ村はオルデンと東の街イスントの間にある大きな森の中にある村だ。
村と言っても小さくはなく、役所や自警団がある。
周りは「深霧の森」に囲まれていて、通過する時は必ず一度この村で停留しなければならない。
それは、この村が森を護る仕事を森の精霊から受けており、森を抜けるには、村から「加護」魔法を受けなければならないからだ。
「深霧の森」は、厄介なことに入るのは自由だが、抜けるのは不可能だ。
「加護」を持たない者は、森で彷徨い続けて果てるか、「あちら」へ連れて行かれる。
森の精霊はこちらが何もしなければ、おとなしい。
だが、森に危害を加えたり、怒らせることをすると「加護」を発動させる。
発動させられたら最後、「こちら」へ戻っては来られなくなる。
この「加護」は森を抜けると解けるようになっていて、森の中での印でもあり保険だが、通る人のためのものではない。森のためのものだということだ。
ちなみに、ユグ村の者は「加護」がなくても森を通過することができる。
それは、村の者を精霊が仲間と認識するのだとか。
だから、馬車で森へ近づいてくると御者がユグ村の御者と交代する。
村に着くまでの間は、ユグ村の者に免じて精霊が森の中を通してくれるというわけだ。
…話が逸れた。
懐の懐中時計を見れば、夕方の五時を過ぎていた。
いつもなら、定刻の少し前に着くはずの馬車はまだ来ていない。定刻はもう過ぎている。
クリスも遅い馬車が気になっているようだ。不安そうに道を見つめている。
立っているのも疲れてきたから、停留所のベンチにクリスと座ることにした。
クリスは大きな荷物に気がついたようで、じっと荷物の方を見つめてくる。
それに気づかないふりをして、無言で馬車を待つ。
「…ライゼンさんは、何科の生徒なんですか?その制服、教育科ではないですよね?」
「……」
答える義務も義理もないから、無言でやり過ごす。
知っても関係のないことだ。
「ご、ごめんなさい。聞いちゃダメでしたか?」
目を向ければ、最初に出会った時と同じ顔で見上げてくるクリス。
怖がっているような、困っているような顔だ。
目を合わせると一瞬怯んだようだったが、それでも一生懸命見つめてくる。
クリスの大きな目は、まるで磨かれた宝玉のようだった。
それをよく見ようと顔を近づけようとしたら、馬車がやってきた。
「ごめんね~。待たせたね~」
年配の男性御者がゆっくり馬を停止させて、馬車に乗り込むための板を降ろす。
馬車には誰も乗っていなかった。
普段なら、御者がもう一人「深霧の森」のために乗っているはずだ。
いないということは、この馬車の御者はユグ村の者だということだろう。
何事もなかったかのようにクリスから離れて、馬車に乗る。
クリスも慌てて馬車に乗り込んだ。
「それじゃあ、出発するよ~」
御者の声に二人で頷けば、馬車はゆっくりと動き出す。
街の石畳をしばらく走り、街を抜ければ「深霧の森」まで平原が広がっている。
平原にも停留所があるが、滅多に人が乗ってくることはない。
それは、ユグ村までクリスと馬車の中で二人きりになることを意味していた。
ガラガラガラガラ…
順調に馬車は街を出て平原を走る。
ここまで一言もクリスと話すことなく、目を合わすこともしなかった。
目を上げると、クリスは隅の方で蹲るように膝を抱いて座っている。
さっきの会話で怒らせたとでも思っているのだろう、アホ毛が落ち込んでいる。
本当にわかりやすい。
「クリス」
呼ばれた少女は恐る恐るこちらを見上げる。
その目を見ると、何かが揺らめいて瞬きをした。
不安に揺れる瞳は先ほど近くで見た時よりも暗くなっている。
「ライゼンさん、怒ってますか?訊いちゃいけないことだったなら、ごめんなさい…」
怒ってはいないのだが、そんな風に言われれば無視した自分が悪い気がしてくる。
いや、ここは自分が悪いのだろう。
いつも師に「言葉が足りない」と言われるから。
小さくため息をついて、クリスの隣へ席を移す。
「いや、怒っていない。悪かった。言う必要がないと思っていたんだ」
「そ、そうだったんですか…?」
驚いた顔で見上げてくるクリスの目は、もう暗くなかった。
停留所で見た時も思ったが、不思議な目だ。
ラズベリーレッド色の目は、まるで水面に映る星空のように光が散りばめられて輝いている。
本当に星があるのではないだろうか?
それに引き込まれるように見つめていると、クリスが目を泳がせた。
「えと、言いたくないのなら言わなくていいです。誰にだって、秘密はあります」
「言いたくないというわけではない。…私は魔導具研究科の五年生だ」
「まどーぐ?」
不思議そうに首を傾げるクリスに、内心笑ってしまった。
本当に感情に素直な奴だ。
そんな風に見つめられたら、釣られて答えたくなってしまうではないか。
「魔導具は魔法が込められた道具だ。身近なもので言えば、そうだな…」
大きな荷物の中から一つの道具を探す。クリスは興味津々に身を乗り出して私の手元を見ていた。
程なくして、荷物の奥から目当てのものを見つけ、少女ーnの手に小さなカンテラを乗せた。
「明かり!」
クリスにとっては珍しいものなのだろうな。
小さなカンテラをうれしそうに観察する姿は、なんとも微笑ましい。
「これはカンテラ。この窪みを押すと明かりがつく。この中の光は、この道具に込められた光魔法で輝いている」
「へえぇ~!」
説明しながらカンテラに明かりをつけて見せると、クリスは一層目を輝かせた。
こんなどこにでもある道具でそこまで喜んでもらえるとは。
思わず綻びそうになった口元を慌てて抑えた。
「ねえ!ライゼンさん!他にもある!?」
「見てみたいか?」
「うんっ!」
こうして、すっかり敬語を遣うのを忘れたクリスとユグ村に着くまで魔導具について話した。
このクリスとの会話はとても楽しく、今の自分には得難い時間だった。
0
あなたにおすすめの小説

あなたの片想いを聞いてしまった夜
柴田はつみ
恋愛
「『好きな人がいる』——その一言で、私の世界は音を失った。」
公爵令嬢リリアーヌの初恋は、隣家の若き公爵アレクシスだった。
政務や領地行事で顔を合わせるたび、言葉少なな彼の沈黙さえ、彼女には優しさに聞こえた。——毎日会える。それだけで十分幸せだと信じていた。
しかしある日、回廊の陰で聞いてしまう。
「好きな人がいる。……片想いなんだ」
名前は出ない。だから、リリアーヌの胸は残酷に結論を作る。自分ではないのだ、と。

魔物に嫌われる「レベル0」の魔物使い。命懸けで仔犬を助けたら―実は神域クラスしかテイムできない規格外でした
たつき
ファンタジー
魔物使いでありながらスライム一匹従えられないカイルは、3年間尽くしたギルドを「無能」として追放される。 同世代のエリートたちに「魔物避けの道具」として危険な遺跡に連れ出され、最後は森の主(ヌシ)を前に囮として見捨てられた。
死を覚悟したカイルが崩落した壁の先で見つけたのは、今にも息絶えそうな一匹の白い仔犬。 「自分と同じように、理不尽に見捨てられたこの子だけは助けたい」 自分の命を顧みず、カイルが全魔力を込めて「テイム」を試みた瞬間、眠っていた真の才能が目覚める。
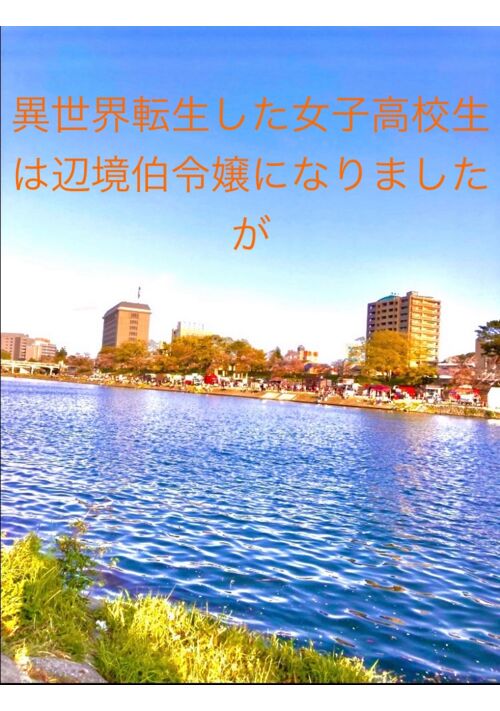
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

自業自得じゃないですか?~前世の記憶持ち少女、キレる~
浅海 景
恋愛
前世の記憶があるジーナ。特に目立つこともなく平民として普通の生活を送るものの、本がない生活に不満を抱く。本を買うため前世知識を利用したことから、とある貴族の目に留まり貴族学園に通うことに。
本に釣られて入学したものの王子や侯爵令息に興味を持たれ、婚約者の座を狙う令嬢たちを敵に回す。本以外に興味のないジーナは、平穏な読書タイムを確保するために距離を取るが、とある事件をきっかけに最も大切なものを奪われることになり、キレたジーナは報復することを決めた。
※2024.8.5 番外編を2話追加しました!

精霊に愛される(呪いにもにた愛)少女~全属性の加護を貰う~
如月花恋
ファンタジー
今この世界にはたくさんの精霊がいる
その精霊達から生まれた瞬間に加護を貰う
稀に2つ以上の属性の2体の精霊から加護を貰うことがある
まぁ大体は親の属性を受け継ぐのだが…
だが…全属性の加護を貰うなど不可能とされてきた…
そんな時に生まれたシャルロッテ
全属性の加護を持つ少女
いったいこれからどうなるのか…

「魔物の討伐で拾われた少年――アイト・グレイモント」
(イェイソン・マヌエル・ジーン)
ファンタジー
魔物の討伐中に見つかった黄金の瞳の少年、アイト・グレイモント。
王宮で育てられながらも、本当の冒険を求める彼は7歳で旅に出る。
風の魔法を操り、師匠と幼なじみの少女リリアと共に世界を巡る中、古代の遺跡で隠された力に触れ——。

【魔女ローゼマリー伝説】~5歳で存在を忘れられた元王女の私だけど、自称美少女天才魔女として世界を救うために冒険したいと思います!~
ハムえっぐ
ファンタジー
かつて魔族が降臨し、7人の英雄によって平和がもたらされた大陸。その一国、ベルガー王国で物語は始まる。
王国の第一王女ローゼマリーは、5歳の誕生日の夜、幸せな時間のさなかに王宮を襲撃され、目の前で両親である国王夫妻を「漆黒の剣を持つ謎の黒髪の女」に殺害される。母が最後の力で放った転移魔法と「魔女ディルを頼れ」という遺言によりローゼマリーは辛くも死地を脱した。
15歳になったローゼは師ディルと別れ、両親の仇である黒髪の女を探し出すため、そして悪政により荒廃しつつある祖国の現状を確かめるため旅立つ。
国境の街ビオレールで冒険者として活動を始めたローゼは、運命的な出会いを果たす。因縁の仇と同じ黒髪と漆黒の剣を持つ少年傭兵リョウ。自由奔放で可愛いが、何か秘密を抱えていそうなエルフの美少女ベレニス。クセの強い仲間たちと共にローゼの新たな人生が動き出す。
これは王女の身分を失った最強天才魔女ローゼが、復讐の誓いを胸に仲間たちとの絆を育みながら、王国の闇や自らの運命に立ち向かう物語。友情、復讐、恋愛、魔法、剣戟、謀略が織りなす、ダークファンタジー英雄譚が、今、幕を開ける。

三十年後に届いた白い手紙
RyuChoukan
ファンタジー
三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。
彼は最後まで、何も語らなかった。
その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。
戴冠舞踏会の夜。
公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。
それは復讐でも、告発でもない。
三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、
「渡されなかった約束」のための手紙だった。
沈黙のまま命を捨てた男と、
三十年、ただ待ち続けた女。
そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。
これは、
遅れて届いた手紙が、
人生と運命を静かに書き換えていく物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















