18 / 87
第1章 ◆ はじまりと出会いと
18. まだ言えない決意
しおりを挟む
俺はグランツ学園教育科光組八番、カイト。
この組の中では最年長だ。学園に来てから、ずっと光組に在籍している。
その理由は、一部の人しか知られていない。知っているのは、担任の先生やリリー、あと学園長ぐらいだな。
今年も進級しないつもりだったが、最近友達になったクリスと一緒に過ごしているうちに進級も悪くないと思えてきた。
単位はとうの昔に取ってるし、クリスやリリーと進級するのも悪くないかもしれねーな。
今では、リリーやクリスとは一番近くにいて、喧嘩もしたりお互いに認め合ったりする、良き友人となった。
そんな風に穏やかに学園生活を送っていたある日、突然それはやってくる。
クリスの前に、あいつが現れた。
ぬるま湯につかった日々が崩れる音がした。
なんで俺は、こんなにのんきに過ごしていたんだろうな。
クリスの目に映ったあいつは、どんなふうに見えたのかわからない。
ただ、クリスの様子から恐怖だけは感じ取れた。
オルデンから、はるか西にある大きな湖の傍。
その湖の岸から少し離れた水上で寝転がっている影がある。
そいつは、俺の仇敵。白い髪の黒目の少年。
俺がいた村を全滅させた張本人。
「…ずいぶん探したぞ。ゼロ」
「やあ、カイト」
俺が来るのをわかっていたんだろう。
呟いたように言った言葉に、ゼロは返事をした。
「ああ、やっと僕が見えるようになった?昔の勘を取り戻したのかな?」
「うるせぇ。おまえ、なんでグランツ学園にいたんだ。何かするつもりか?」
寝転んだままのゼロを睨みつける。
ゼロは、そんな視線など気にもしないで、ただ笑う。
「君こそ、まだあの学園にいたんだね?君も飽きないねぇ」
ゼロは、ゆっくり起き上がると水上を歩いてこっちに近づいてくる。
本当は近づきたくはないが、こいつには訊きたいことがある。
「おまえ、クリスに会って何を企んでるんだ」
「ん?クリス…?」
わざとらしく顎に手を当て、首を傾げるゼロ。
「ああ。あの図書室で会った君のお友達?やだなぁ、会ったのは偶然だよ」
くすくすとおもしろいものを見つけたように笑うゼロをさらに睨みつける。
笑っているが、その目は冷たく沈んでいて、どこか恐怖さえ感じる目だ。
「それにしても、あの子には驚いたよ。だって、僕の姿が見えてたんだから。あの子、何者?」
「……知らねーよ」
「ふーん…」
ゼロは探るような目をして見つめてくる。
クリスのことは本当に何も知らない。
クラスメイトで、年の離れた有名人な兄がいて、それをとても誇りに思ってるということぐらいしか。
魔法が下手だけど素直で頑張り屋の、ただの小さな女の子だ。
「でも、君がそんな風に言うってことは、カイトの特別になりえる子なのかな?」
その言葉に一瞬戸惑った。
「特別」と言うには少し違うと思うが、ゼロの言うとおり、クリスは「それ」に該当するかもしれない。
「それ」は、俺が魔法を完全に使えるようになる最も大きな条件だから。
無意識に考えないようにしていたことをあっさりと見抜かれて、なんだか腹が立つ。
クリスは大事な友人だ。これからも、ずっと。
だから、クリスが望まない限り、俺はクリスの良き友人でいるつもりだ。
沈黙を貫いていると、ゼロはつまらなそうな顔をしてため息をつく。
「そっかぁ。やっぱりあの子は特別なんだね。魔力も不思議な性質だったし…」
「! おい!クリスの魔力を奪ったのか!?」
それが本当なら、クリスにはちゃんと魔力があるということになる。しかも、一定量の。
ゼロは、その魔力の性質で他人の魔力を知ることができる。性質はもちろん、魔力量や得意な魔法までも。
ゼロはにやりと笑って、水面からふわりと高く浮かんでみせる。
「教えてあげなーい♪」
「ゼロ!」
笑いながら空中を飛ぶゼロは、俺から一定の距離を取ると、背を向けた。
それに違和感を感じながら、もう一度ゼロを呼ぶ。
「…君は、今でも僕のことをその名で呼んでくれるんだね」
その一瞬の静寂に、身震いをした。
「だから君のことは大嫌いなんだ」
「っ!?」
急に俺の中の魔力が引っ張られる。
そう思ったら、目の前に大きな竜巻が起きた。
竜巻は、湖の水をまきあげながら、ゼロと俺の間でどんどん膨れ上がる。
「くっ!!」
「ふふ、カイト。相変わらず君の魔力は極上だね。本当、もったいないよ」
竜巻がどんどん大きくなればなるほど、体から魔力が抜けていく。
この竜巻は、俺の魔力で発動している。いや、発動させられていると言った方が正しい。
竜巻の向こうのゼロを見れば、愉快に笑いながら空中に指でなぞるようにして魔法文字を並べている。
この魔法は、ゼロが発動させている。俺の魔力を使って。
それがゼロの魔力の性質、マジックイーター。
自分の魔力で魔法を発動できない代わりに、近くの人間の魔力を勝手に吸い上げて、その魔力で魔法を使う。
戦闘となれば、相手が強ければ強いほど自分も強い魔法が使えるってわけだ。
相手は魔力を吸い取られるから、すぐに倒さないとゼロによって魔力をすべて使われてしまう。
しかも、ゼロは吸い上げた魔力の性質を無視して使える。
ゼロの魔力の性質がそうさせているんだ。
くっそ、そんなの反則だろ。
体が吹き飛ばされないように、自分に重力魔法をかけておく。
ゼロは何の影響もないかのように、くるくると竜巻の周りを鳥のように飛んでいる。
絶対、楽しんでやがる。
「ゼロ、君はどうして『それ』に固執するの?魔力の性質なんて無視したらいいじゃないか」
「僕みたいにね」と笑うゼロはさらに魔法を重ねがけしてくる。
どんどん威力を増してくる竜巻に、目を開けていられない。
このままじゃ、逃げられる。
「俺は、自分のために魔法を使いたくねーだけだ」
俺は今までそうやって生きてきたから。
いや、そういう風にしか使ったことがなかったんだ。
「そう言うってことは、本当は使えるんだ?」
「使えねーよ!」
その俺の答えに、ゼロは心底わからないような声音で問いかけてくる。
「なんでそんなことになってるの?君はどちらかと言えば、こっち側だろ?好きに使えばいいじゃないか」
「使えねーものは使えねーんだよ!」
おまえと一緒にするな!
実際魔法が制限されているのは本当のこと。
俺の魔力の性質もあるが、それ以外にもう一つ制限をつけてある。
それにはある条件があって、それを果たさなければ完全に魔法を使うことはできない。
今の俺は、そのせいで生活魔法しか使えない。
この秘密だけは決して守らなければならないもの。
それは、目の前のゼロに知られてはいけない。絶対に。
「そんな君なんて、つまらないな。クリスの方がもっとおもしろそうだ」
静かに呟かれたその言葉は、竜巻で聞き取ることができなかった。
竜巻がさらに大きくなり、俺の魔力も底を尽きようとしていた。
飛ばされないように、自分にかけていた重力魔法ももう効力が切れる。
「じゃあ、一つだけ教えてあげる。クリスは僕に似てるよ。君とは相性がいいかもしれないね?」
「…っ!?どういうことだ!!」
それはクリスの魔力のことか?
ゼロに似てるってことは、自分の魔力は使えない類の性質なのか?
問いただそうと睨みつけるも、ゼロはただ愉快に笑うだけだった。
「あはははっ、教えないよ~。簡単にわかっちゃったらおもしろくないじゃないか」
ゼロがそう言った瞬間、竜巻が爆発するように膨れ上がった。
その威力に耐えられず、俺の体は大きく吹き飛ばされてしまった。
幸い、周りは樹が生い茂っていたから、落下の大きな衝撃はなんとか避けられたみたいだった。
気がついた時には、竜巻もゼロも消えていた。
「くそ…派手に使いやがって…」
辺りは、竜巻の魔法でぐちゃぐちゃになっていた。
湖には木の葉や枝が浮き、水底までかき回されたのか、水も濁っている。
ボサボサの髪とドロドロの服をなんとか整えて、立ち上がる。
骨は折れてないな。怪我も、大したことない。
思ったほど痛みはないから、大丈夫だろ、たぶん。
ゼロがいた方向に目をやれば、太陽がだいぶ傾いていた。
慌ててポケットの時計を見れば、ゼロと会ってから二時間ほど経っていた。
げ。そんなに気を失ってたのか?
ポケットに時計を戻すと、遠くから人の声と甲冑の音が聞こえてきた。
あれだけ大きな竜巻が発生すれば、周辺の町や村の騎士団が来てもおかしくはない。
自然現象と呼ぶにはだいぶおかしい、急激に発達した竜巻だったし、それが爆発すれば、魔法戦闘が起きていると容易にわかる。
ここは、騎士団とかち合わない方が無難だ。
そういうわけで、早々に逃げることにした。
あの場から逃げて、グランツ学園に着いた時には、もうすでに真夜中だった。
門をくぐると、転移魔法で先生が数人現れた。
相変わらず、グランツ学園のセキュリティはすげーな。
ゼロには簡単に侵入されてたけど。
あいつは特殊だから仕方ねーか。
しゃべる元気もないから、軽く無視して横を通り過ぎれば、腕を掴まれた。
疲れたように目を上げれば、腕を掴んだのは魔法実技担当のギルだった。
「カイトさん、ボロボロじゃないか!一体何があったんだい?」
それはとても心配をしている目だった。
他の先生もよく見れば心配そうにしていて、光組八番を担当している先生達だった。
俺のことを知っている人間だ。
「大丈夫だ。ちょっと竜巻に巻き込まれただけだし」
「ええっ!!?」
ギルは青ざめながら、俺の体をくまなく調べた。
すり傷や切り傷、青痣などがあったが、大したことない怪我にギルはほっとした。
かと思えば、キッと俺を睨みつける。
「カイトさん、無茶をしないで!あなたは今、大きな魔法を使えないんだよ!?怪我をしてもあなたを守る…―――っ!」
それから先の言葉は出なかった。いや、俺が言わせなかった。
軽く睨みつけると、ギルは口を噤む。
すると、担任のリストが困った顔で俺に頭を下げる。
「カイト君、ギル先生の気持ちもわかってやってくれ。とても心配してたんだぞ」
「……」
それはわかってる。
わかってるけど、過剰に心配されるのはどうにも慣れない。
「…悪かった。頭を上げろよ」
ほっとした先生達に、俺は背を向ける。寮に帰るのだ。
黙って先生達は俺を見送ったが、リストに声をかけられた。
「カイト君、クリスさんとリリーさんもとても心配してたぞ。明日、授業に出るなら一言何か言ってやれよ」
「わかったよ」
ただ一言、そう返した。
次の日の朝、リリーは怒った顔で、クリスは心配そうな顔で待っていた。
席に座れば、組の奴らが「おはよう」と普通に挨拶をする。
組の奴らは俺の用事が終わったと思っているんだろう。まあ、リストにそう言っておけと頼んだからな。
で、この二人は例外なわけで。
「カイト、どこに行ってたの?怪我とかしてないでしょうね?」
ジト目で見つめてくるリリーは怒っているように見えるが、心配してくれている。
なんでリリーにはわかるんだよ。敵わねーな。
俺のことを知っているリリーは、なんとなく俺がどうしていなくなったのかわかったんだろう。
妙に勘のいいところは、さすが、エルフなだけある。
「え?カイト君、怪我するような用事だったの?」
クリスはとても心配している顔で、見つめてくる。
その目は、どこか不安と疑問が混じったようなものだった。
クリスはきっと、ゼロのことが気になってるんだろうな…。
俺が出て行ったのも、あいつのせいだと思っているのかも。
ゼロのことは詳しく言えないが、クリスが安心するなら、嘘の一つや二つ吐いてやろうじゃねーか。
俺は何事もなかったかのように頬杖をして、クリスに向き合う。
「全然?むしろ、いいことがあったぜ?」
「えっ、なになに?」
クリスはパッと顔を明るくして、詰め寄ってくる。
リリーは意外そうな顔をして俺を見つめている。
「ちょっと調べものしてきたんだよ。ま、結果は上々だな」
「そうだったんだ」
怪我とか用事の内容とか諸々を省略してクリスに伝える。
クリスは何の疑問も持たず、ほっとしたように笑った。
嘘だけどな。
ゼロには逃げられたし、魔力も底をついて回復中。軽い怪我もしてる。
はっきり言って惨敗だ。
だが、一つだけいいこともあった。
ゼロとのやり取りで、迷っていた俺の中に、ある決意が生まれた。
無意識に逃げてたけど、あいつに「特別」と言われたとき、認めざるを得なくなった。
認めてしまえば、難てことはない。
クリスのように素直になればいいことだ。
もし、クリスにゼロのような奴が近づくなら、俺が護ってやる。
「クリス」
「なあに?」
今はまだ、はっきりとクリスには言えない。
だけど。
これから言う言葉は本当のこと。
俺が、決めたことだ。
「クリス。おまえにはちゃんと魔力があって、それはおまえにしか理解できねーし、使えない」
「? うん」
何をいまさらと言う顔でクリスは頷く。
「でも、俺は違う。クリス、もしおまえが魔法で困ったら、俺に言えよ。おまえの力になってやる」
「うんっ!もちろんだよ!カイト君も困ったことがあったら言ってね!私も力になるよ!」
両手で力拳を作って、即答したクリス。
その純粋な、素直な返事に胸が温かくなる。
クリスは、俺が言ったことをそんなに重く受け止めていないだろう。
俺がおまえに力を貸す、それはすごいことなんだぞ?
そう思いながら、隣でうれしそうにするクリスに釣られるように微笑んだ。
リリーは、そんな俺達を心底うれしそうに見つめていた。
いつか、クリスが魔法で困った時、その時は迷わずクリスに自分のことを話そうと思う。
この組の中では最年長だ。学園に来てから、ずっと光組に在籍している。
その理由は、一部の人しか知られていない。知っているのは、担任の先生やリリー、あと学園長ぐらいだな。
今年も進級しないつもりだったが、最近友達になったクリスと一緒に過ごしているうちに進級も悪くないと思えてきた。
単位はとうの昔に取ってるし、クリスやリリーと進級するのも悪くないかもしれねーな。
今では、リリーやクリスとは一番近くにいて、喧嘩もしたりお互いに認め合ったりする、良き友人となった。
そんな風に穏やかに学園生活を送っていたある日、突然それはやってくる。
クリスの前に、あいつが現れた。
ぬるま湯につかった日々が崩れる音がした。
なんで俺は、こんなにのんきに過ごしていたんだろうな。
クリスの目に映ったあいつは、どんなふうに見えたのかわからない。
ただ、クリスの様子から恐怖だけは感じ取れた。
オルデンから、はるか西にある大きな湖の傍。
その湖の岸から少し離れた水上で寝転がっている影がある。
そいつは、俺の仇敵。白い髪の黒目の少年。
俺がいた村を全滅させた張本人。
「…ずいぶん探したぞ。ゼロ」
「やあ、カイト」
俺が来るのをわかっていたんだろう。
呟いたように言った言葉に、ゼロは返事をした。
「ああ、やっと僕が見えるようになった?昔の勘を取り戻したのかな?」
「うるせぇ。おまえ、なんでグランツ学園にいたんだ。何かするつもりか?」
寝転んだままのゼロを睨みつける。
ゼロは、そんな視線など気にもしないで、ただ笑う。
「君こそ、まだあの学園にいたんだね?君も飽きないねぇ」
ゼロは、ゆっくり起き上がると水上を歩いてこっちに近づいてくる。
本当は近づきたくはないが、こいつには訊きたいことがある。
「おまえ、クリスに会って何を企んでるんだ」
「ん?クリス…?」
わざとらしく顎に手を当て、首を傾げるゼロ。
「ああ。あの図書室で会った君のお友達?やだなぁ、会ったのは偶然だよ」
くすくすとおもしろいものを見つけたように笑うゼロをさらに睨みつける。
笑っているが、その目は冷たく沈んでいて、どこか恐怖さえ感じる目だ。
「それにしても、あの子には驚いたよ。だって、僕の姿が見えてたんだから。あの子、何者?」
「……知らねーよ」
「ふーん…」
ゼロは探るような目をして見つめてくる。
クリスのことは本当に何も知らない。
クラスメイトで、年の離れた有名人な兄がいて、それをとても誇りに思ってるということぐらいしか。
魔法が下手だけど素直で頑張り屋の、ただの小さな女の子だ。
「でも、君がそんな風に言うってことは、カイトの特別になりえる子なのかな?」
その言葉に一瞬戸惑った。
「特別」と言うには少し違うと思うが、ゼロの言うとおり、クリスは「それ」に該当するかもしれない。
「それ」は、俺が魔法を完全に使えるようになる最も大きな条件だから。
無意識に考えないようにしていたことをあっさりと見抜かれて、なんだか腹が立つ。
クリスは大事な友人だ。これからも、ずっと。
だから、クリスが望まない限り、俺はクリスの良き友人でいるつもりだ。
沈黙を貫いていると、ゼロはつまらなそうな顔をしてため息をつく。
「そっかぁ。やっぱりあの子は特別なんだね。魔力も不思議な性質だったし…」
「! おい!クリスの魔力を奪ったのか!?」
それが本当なら、クリスにはちゃんと魔力があるということになる。しかも、一定量の。
ゼロは、その魔力の性質で他人の魔力を知ることができる。性質はもちろん、魔力量や得意な魔法までも。
ゼロはにやりと笑って、水面からふわりと高く浮かんでみせる。
「教えてあげなーい♪」
「ゼロ!」
笑いながら空中を飛ぶゼロは、俺から一定の距離を取ると、背を向けた。
それに違和感を感じながら、もう一度ゼロを呼ぶ。
「…君は、今でも僕のことをその名で呼んでくれるんだね」
その一瞬の静寂に、身震いをした。
「だから君のことは大嫌いなんだ」
「っ!?」
急に俺の中の魔力が引っ張られる。
そう思ったら、目の前に大きな竜巻が起きた。
竜巻は、湖の水をまきあげながら、ゼロと俺の間でどんどん膨れ上がる。
「くっ!!」
「ふふ、カイト。相変わらず君の魔力は極上だね。本当、もったいないよ」
竜巻がどんどん大きくなればなるほど、体から魔力が抜けていく。
この竜巻は、俺の魔力で発動している。いや、発動させられていると言った方が正しい。
竜巻の向こうのゼロを見れば、愉快に笑いながら空中に指でなぞるようにして魔法文字を並べている。
この魔法は、ゼロが発動させている。俺の魔力を使って。
それがゼロの魔力の性質、マジックイーター。
自分の魔力で魔法を発動できない代わりに、近くの人間の魔力を勝手に吸い上げて、その魔力で魔法を使う。
戦闘となれば、相手が強ければ強いほど自分も強い魔法が使えるってわけだ。
相手は魔力を吸い取られるから、すぐに倒さないとゼロによって魔力をすべて使われてしまう。
しかも、ゼロは吸い上げた魔力の性質を無視して使える。
ゼロの魔力の性質がそうさせているんだ。
くっそ、そんなの反則だろ。
体が吹き飛ばされないように、自分に重力魔法をかけておく。
ゼロは何の影響もないかのように、くるくると竜巻の周りを鳥のように飛んでいる。
絶対、楽しんでやがる。
「ゼロ、君はどうして『それ』に固執するの?魔力の性質なんて無視したらいいじゃないか」
「僕みたいにね」と笑うゼロはさらに魔法を重ねがけしてくる。
どんどん威力を増してくる竜巻に、目を開けていられない。
このままじゃ、逃げられる。
「俺は、自分のために魔法を使いたくねーだけだ」
俺は今までそうやって生きてきたから。
いや、そういう風にしか使ったことがなかったんだ。
「そう言うってことは、本当は使えるんだ?」
「使えねーよ!」
その俺の答えに、ゼロは心底わからないような声音で問いかけてくる。
「なんでそんなことになってるの?君はどちらかと言えば、こっち側だろ?好きに使えばいいじゃないか」
「使えねーものは使えねーんだよ!」
おまえと一緒にするな!
実際魔法が制限されているのは本当のこと。
俺の魔力の性質もあるが、それ以外にもう一つ制限をつけてある。
それにはある条件があって、それを果たさなければ完全に魔法を使うことはできない。
今の俺は、そのせいで生活魔法しか使えない。
この秘密だけは決して守らなければならないもの。
それは、目の前のゼロに知られてはいけない。絶対に。
「そんな君なんて、つまらないな。クリスの方がもっとおもしろそうだ」
静かに呟かれたその言葉は、竜巻で聞き取ることができなかった。
竜巻がさらに大きくなり、俺の魔力も底を尽きようとしていた。
飛ばされないように、自分にかけていた重力魔法ももう効力が切れる。
「じゃあ、一つだけ教えてあげる。クリスは僕に似てるよ。君とは相性がいいかもしれないね?」
「…っ!?どういうことだ!!」
それはクリスの魔力のことか?
ゼロに似てるってことは、自分の魔力は使えない類の性質なのか?
問いただそうと睨みつけるも、ゼロはただ愉快に笑うだけだった。
「あはははっ、教えないよ~。簡単にわかっちゃったらおもしろくないじゃないか」
ゼロがそう言った瞬間、竜巻が爆発するように膨れ上がった。
その威力に耐えられず、俺の体は大きく吹き飛ばされてしまった。
幸い、周りは樹が生い茂っていたから、落下の大きな衝撃はなんとか避けられたみたいだった。
気がついた時には、竜巻もゼロも消えていた。
「くそ…派手に使いやがって…」
辺りは、竜巻の魔法でぐちゃぐちゃになっていた。
湖には木の葉や枝が浮き、水底までかき回されたのか、水も濁っている。
ボサボサの髪とドロドロの服をなんとか整えて、立ち上がる。
骨は折れてないな。怪我も、大したことない。
思ったほど痛みはないから、大丈夫だろ、たぶん。
ゼロがいた方向に目をやれば、太陽がだいぶ傾いていた。
慌ててポケットの時計を見れば、ゼロと会ってから二時間ほど経っていた。
げ。そんなに気を失ってたのか?
ポケットに時計を戻すと、遠くから人の声と甲冑の音が聞こえてきた。
あれだけ大きな竜巻が発生すれば、周辺の町や村の騎士団が来てもおかしくはない。
自然現象と呼ぶにはだいぶおかしい、急激に発達した竜巻だったし、それが爆発すれば、魔法戦闘が起きていると容易にわかる。
ここは、騎士団とかち合わない方が無難だ。
そういうわけで、早々に逃げることにした。
あの場から逃げて、グランツ学園に着いた時には、もうすでに真夜中だった。
門をくぐると、転移魔法で先生が数人現れた。
相変わらず、グランツ学園のセキュリティはすげーな。
ゼロには簡単に侵入されてたけど。
あいつは特殊だから仕方ねーか。
しゃべる元気もないから、軽く無視して横を通り過ぎれば、腕を掴まれた。
疲れたように目を上げれば、腕を掴んだのは魔法実技担当のギルだった。
「カイトさん、ボロボロじゃないか!一体何があったんだい?」
それはとても心配をしている目だった。
他の先生もよく見れば心配そうにしていて、光組八番を担当している先生達だった。
俺のことを知っている人間だ。
「大丈夫だ。ちょっと竜巻に巻き込まれただけだし」
「ええっ!!?」
ギルは青ざめながら、俺の体をくまなく調べた。
すり傷や切り傷、青痣などがあったが、大したことない怪我にギルはほっとした。
かと思えば、キッと俺を睨みつける。
「カイトさん、無茶をしないで!あなたは今、大きな魔法を使えないんだよ!?怪我をしてもあなたを守る…―――っ!」
それから先の言葉は出なかった。いや、俺が言わせなかった。
軽く睨みつけると、ギルは口を噤む。
すると、担任のリストが困った顔で俺に頭を下げる。
「カイト君、ギル先生の気持ちもわかってやってくれ。とても心配してたんだぞ」
「……」
それはわかってる。
わかってるけど、過剰に心配されるのはどうにも慣れない。
「…悪かった。頭を上げろよ」
ほっとした先生達に、俺は背を向ける。寮に帰るのだ。
黙って先生達は俺を見送ったが、リストに声をかけられた。
「カイト君、クリスさんとリリーさんもとても心配してたぞ。明日、授業に出るなら一言何か言ってやれよ」
「わかったよ」
ただ一言、そう返した。
次の日の朝、リリーは怒った顔で、クリスは心配そうな顔で待っていた。
席に座れば、組の奴らが「おはよう」と普通に挨拶をする。
組の奴らは俺の用事が終わったと思っているんだろう。まあ、リストにそう言っておけと頼んだからな。
で、この二人は例外なわけで。
「カイト、どこに行ってたの?怪我とかしてないでしょうね?」
ジト目で見つめてくるリリーは怒っているように見えるが、心配してくれている。
なんでリリーにはわかるんだよ。敵わねーな。
俺のことを知っているリリーは、なんとなく俺がどうしていなくなったのかわかったんだろう。
妙に勘のいいところは、さすが、エルフなだけある。
「え?カイト君、怪我するような用事だったの?」
クリスはとても心配している顔で、見つめてくる。
その目は、どこか不安と疑問が混じったようなものだった。
クリスはきっと、ゼロのことが気になってるんだろうな…。
俺が出て行ったのも、あいつのせいだと思っているのかも。
ゼロのことは詳しく言えないが、クリスが安心するなら、嘘の一つや二つ吐いてやろうじゃねーか。
俺は何事もなかったかのように頬杖をして、クリスに向き合う。
「全然?むしろ、いいことがあったぜ?」
「えっ、なになに?」
クリスはパッと顔を明るくして、詰め寄ってくる。
リリーは意外そうな顔をして俺を見つめている。
「ちょっと調べものしてきたんだよ。ま、結果は上々だな」
「そうだったんだ」
怪我とか用事の内容とか諸々を省略してクリスに伝える。
クリスは何の疑問も持たず、ほっとしたように笑った。
嘘だけどな。
ゼロには逃げられたし、魔力も底をついて回復中。軽い怪我もしてる。
はっきり言って惨敗だ。
だが、一つだけいいこともあった。
ゼロとのやり取りで、迷っていた俺の中に、ある決意が生まれた。
無意識に逃げてたけど、あいつに「特別」と言われたとき、認めざるを得なくなった。
認めてしまえば、難てことはない。
クリスのように素直になればいいことだ。
もし、クリスにゼロのような奴が近づくなら、俺が護ってやる。
「クリス」
「なあに?」
今はまだ、はっきりとクリスには言えない。
だけど。
これから言う言葉は本当のこと。
俺が、決めたことだ。
「クリス。おまえにはちゃんと魔力があって、それはおまえにしか理解できねーし、使えない」
「? うん」
何をいまさらと言う顔でクリスは頷く。
「でも、俺は違う。クリス、もしおまえが魔法で困ったら、俺に言えよ。おまえの力になってやる」
「うんっ!もちろんだよ!カイト君も困ったことがあったら言ってね!私も力になるよ!」
両手で力拳を作って、即答したクリス。
その純粋な、素直な返事に胸が温かくなる。
クリスは、俺が言ったことをそんなに重く受け止めていないだろう。
俺がおまえに力を貸す、それはすごいことなんだぞ?
そう思いながら、隣でうれしそうにするクリスに釣られるように微笑んだ。
リリーは、そんな俺達を心底うれしそうに見つめていた。
いつか、クリスが魔法で困った時、その時は迷わずクリスに自分のことを話そうと思う。
0
あなたにおすすめの小説

あなたの片想いを聞いてしまった夜
柴田はつみ
恋愛
「『好きな人がいる』——その一言で、私の世界は音を失った。」
公爵令嬢リリアーヌの初恋は、隣家の若き公爵アレクシスだった。
政務や領地行事で顔を合わせるたび、言葉少なな彼の沈黙さえ、彼女には優しさに聞こえた。——毎日会える。それだけで十分幸せだと信じていた。
しかしある日、回廊の陰で聞いてしまう。
「好きな人がいる。……片想いなんだ」
名前は出ない。だから、リリアーヌの胸は残酷に結論を作る。自分ではないのだ、と。

魔物に嫌われる「レベル0」の魔物使い。命懸けで仔犬を助けたら―実は神域クラスしかテイムできない規格外でした
たつき
ファンタジー
魔物使いでありながらスライム一匹従えられないカイルは、3年間尽くしたギルドを「無能」として追放される。 同世代のエリートたちに「魔物避けの道具」として危険な遺跡に連れ出され、最後は森の主(ヌシ)を前に囮として見捨てられた。
死を覚悟したカイルが崩落した壁の先で見つけたのは、今にも息絶えそうな一匹の白い仔犬。 「自分と同じように、理不尽に見捨てられたこの子だけは助けたい」 自分の命を顧みず、カイルが全魔力を込めて「テイム」を試みた瞬間、眠っていた真の才能が目覚める。
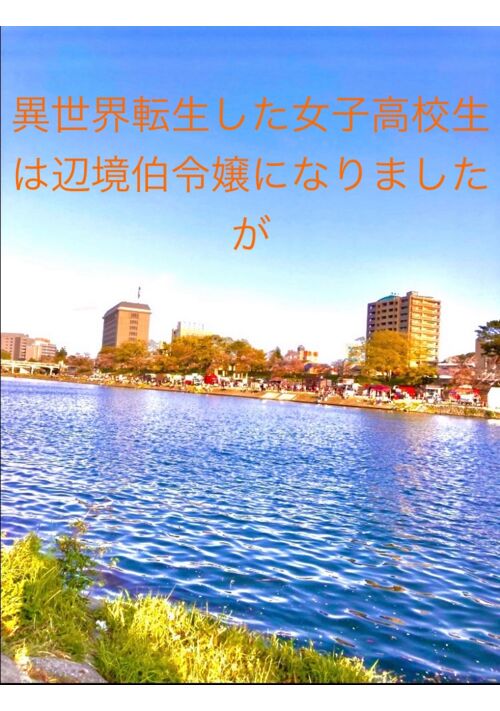
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

自業自得じゃないですか?~前世の記憶持ち少女、キレる~
浅海 景
恋愛
前世の記憶があるジーナ。特に目立つこともなく平民として普通の生活を送るものの、本がない生活に不満を抱く。本を買うため前世知識を利用したことから、とある貴族の目に留まり貴族学園に通うことに。
本に釣られて入学したものの王子や侯爵令息に興味を持たれ、婚約者の座を狙う令嬢たちを敵に回す。本以外に興味のないジーナは、平穏な読書タイムを確保するために距離を取るが、とある事件をきっかけに最も大切なものを奪われることになり、キレたジーナは報復することを決めた。
※2024.8.5 番外編を2話追加しました!

精霊に愛される(呪いにもにた愛)少女~全属性の加護を貰う~
如月花恋
ファンタジー
今この世界にはたくさんの精霊がいる
その精霊達から生まれた瞬間に加護を貰う
稀に2つ以上の属性の2体の精霊から加護を貰うことがある
まぁ大体は親の属性を受け継ぐのだが…
だが…全属性の加護を貰うなど不可能とされてきた…
そんな時に生まれたシャルロッテ
全属性の加護を持つ少女
いったいこれからどうなるのか…

「魔物の討伐で拾われた少年――アイト・グレイモント」
(イェイソン・マヌエル・ジーン)
ファンタジー
魔物の討伐中に見つかった黄金の瞳の少年、アイト・グレイモント。
王宮で育てられながらも、本当の冒険を求める彼は7歳で旅に出る。
風の魔法を操り、師匠と幼なじみの少女リリアと共に世界を巡る中、古代の遺跡で隠された力に触れ——。

【魔女ローゼマリー伝説】~5歳で存在を忘れられた元王女の私だけど、自称美少女天才魔女として世界を救うために冒険したいと思います!~
ハムえっぐ
ファンタジー
かつて魔族が降臨し、7人の英雄によって平和がもたらされた大陸。その一国、ベルガー王国で物語は始まる。
王国の第一王女ローゼマリーは、5歳の誕生日の夜、幸せな時間のさなかに王宮を襲撃され、目の前で両親である国王夫妻を「漆黒の剣を持つ謎の黒髪の女」に殺害される。母が最後の力で放った転移魔法と「魔女ディルを頼れ」という遺言によりローゼマリーは辛くも死地を脱した。
15歳になったローゼは師ディルと別れ、両親の仇である黒髪の女を探し出すため、そして悪政により荒廃しつつある祖国の現状を確かめるため旅立つ。
国境の街ビオレールで冒険者として活動を始めたローゼは、運命的な出会いを果たす。因縁の仇と同じ黒髪と漆黒の剣を持つ少年傭兵リョウ。自由奔放で可愛いが、何か秘密を抱えていそうなエルフの美少女ベレニス。クセの強い仲間たちと共にローゼの新たな人生が動き出す。
これは王女の身分を失った最強天才魔女ローゼが、復讐の誓いを胸に仲間たちとの絆を育みながら、王国の闇や自らの運命に立ち向かう物語。友情、復讐、恋愛、魔法、剣戟、謀略が織りなす、ダークファンタジー英雄譚が、今、幕を開ける。

三十年後に届いた白い手紙
RyuChoukan
ファンタジー
三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。
彼は最後まで、何も語らなかった。
その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。
戴冠舞踏会の夜。
公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。
それは復讐でも、告発でもない。
三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、
「渡されなかった約束」のための手紙だった。
沈黙のまま命を捨てた男と、
三十年、ただ待ち続けた女。
そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。
これは、
遅れて届いた手紙が、
人生と運命を静かに書き換えていく物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















