62 / 80
第11章 小説なんて書かない方がいい
11-6 専属執事にしてもらうから大丈夫
しおりを挟む
月曜日はもちろん、松岡くんが仕事で来る。
「本日もよろしくお願いいたします」
「はい、よろしくお願いします」
通常通りアフタヌーンティをして、左手だけでもキーを叩いていたら松岡くんに怒られそうなので、こたつでごろごろ。
掃除や片付けが終わり、今日も夕食の買い出しに連れ出してくれた。
新婚さん気分を満喫して帰ってくると、待っているのは……例の郵便。
「……入ってる?」
「……あるな」
日曜月曜と二日分のそれは、先週のより大きくなっている。
「なんで大きくなってるんだろ」
「開けなくてもいいんだぞ」
松岡くんは鋏を握った私を止めてくれたけれど、気になる、から。
適当にひいた紙の上に中身を出す。
――ゴト。
「ひぃっ」
妙に重い音とともに出てきたそれに悲鳴が漏れる。
「今日は足かよ……」
大きいはずだ、封筒には黒猫の後ろ足が一本ずつ入っていたのだから。
「セバスチャン、セバスチャン……」
あっという間に松岡くんは下にひいた紙ごとくるんで、私の目に入らないようにした。
「セバスチャン、セバスチャンが」
縋るように松岡くんの腕を掴む。
見上げた彼は泣き出しそうに顔を歪めていた。
「紅夏、落ち着け。
あれはセバスチャンじゃない」
「でも、でも」
あたまではわかっているのだ、あれはセバスチャンじゃないって。
だって家を出る前、セバスチャンはミカンを転がして遊んでいたのだから。
「あれはセバスチャンじゃない。
セバスチャンはあそこにいる」
松岡くんが指さす方向を見る。
そこではセバスチャンがのんきに毛繕いをしていた。
「……うん」
一応納得して、手を離す。
でもあたまの中はぐるぐる回るばかりでちっとも落ち着かない。
「ちょっと待ってろ」
私を安心させるようにか、あたまをぽんぽんして松岡くんは台所へ消えていった。
少しして、カップを手に戻ってくる。
「落ち着くから」
「……うん」
渡されたカップを受け取った手は細かく震えていた。
こぼさないように気をつけながら、淹れてくれた紅茶を飲む。
「あれはセバスチャンじゃない。
セバスチャンはここにいる。
……わかるな?」
セバスチャンはいま、私の視線の先にいる。
あの足はセバスチャンのじゃない。
じゃああの足はどこの猫の?
やっぱり、セバスチャンのじゃ。
ううん、セバスチャンはここにいる。
だから違う。
だけど――。
「……にか。
紅夏!」
「……え?」
松岡くんから肩を揺すられ、我に返った。
私いま、なにを考えていたんだろう……?
「いまはなにも考えるな。
いいな?」
「う、うん」
強く言い聞かせるように言われ、仕方なく頷いた。
松岡くんはテレビをつけてリモコンを私に握らせ、台所へ行ってしまった。
「にゃー」
入れ替わるようにセバスチャンがやってきて、私の身体の隙間にずぼっとあたまを突っ込んでくる。
「セバスチャン」
膝の上にのせてあたまを撫でると、気持ちよさそうにのどを鳴らす。
なぜかそれだけで、わけもわからず涙が溢れてくる。
「なん、で」
悲しくなんてないのに、涙は止まらない。
鼻をずびずびいわせながら、ティッシュを何枚も消費した。
「紅夏」
「松岡、くん。
おかしいよね、なんで私、泣いてるんだろ」
「安心したからだろ」
止まらない涙を、松岡くんがまじめな顔をして拭ってくれる。
「まだ時間じゃないけど、一回帰ってくる」
「なん、で」
いまは傍にいてほしい。
時間までしかいられないがわかっていても。
なのに。
「横井さんにあれ届けて、家に帰ってくる。
んで、着替え取って戻ってくるから」
戻ってくるってどういう意味なんだろう。
「今日はここに泊まる。
こんな紅夏、ひとりにしておけない」
松岡くんの言っていることが理解できない。
「でも業務規定違反、だよね」
「そうだな」
「バレたら会社、クビになっちゃう」
「そのときは紅夏専属の執事にしてもらうからいい」
笑った彼が、ぷにっと私の頬を摘まむ。
「……痛い」
「ん、ちょっと笑ったな」
私の頬から手を離し、なぜか松岡くんは私のあたまをがしがし撫でた。
「ちょっとの間ひとりにするけど、大丈夫な?
すぐに戻ってくるから」
「……うん」
「じゃあ、行ってくる」
松岡くんがレジ袋に入れたそれを持ち、ようやく私のあたまは今日、届いたものを理解した。
……あんなに心配させるほど、取り乱すなんてダメだな、私。
でもあれはそれだけ、インパクトがあったのだ。
前足はまだ小さいから、キーホルダーかなにかに見えないこともなかった。
でも後ろ足は、しかも根元から切り取られていて、……妙にリアルだったのだ。
いや、本物なのだけど。
「金曜日と土曜日が前足……。
日曜日と月曜日が後ろ足……」
じゃあ、火曜日は?
水曜日はなにが届く?
考えると怖くて怖くてたまらない。
「セバスチャン、セバスチャン」
床を這うようにセバスチャンを探す。
セバスチャンはもうすぐごはんがもらえる時間だからか、お皿の前で待っていた。
「セバスチャンは絶対、殺させたりしないから」
無理矢理、セバスチャンを抱きしめる。
身体の震えはいつまでたっても止まらなかった。
「本日もよろしくお願いいたします」
「はい、よろしくお願いします」
通常通りアフタヌーンティをして、左手だけでもキーを叩いていたら松岡くんに怒られそうなので、こたつでごろごろ。
掃除や片付けが終わり、今日も夕食の買い出しに連れ出してくれた。
新婚さん気分を満喫して帰ってくると、待っているのは……例の郵便。
「……入ってる?」
「……あるな」
日曜月曜と二日分のそれは、先週のより大きくなっている。
「なんで大きくなってるんだろ」
「開けなくてもいいんだぞ」
松岡くんは鋏を握った私を止めてくれたけれど、気になる、から。
適当にひいた紙の上に中身を出す。
――ゴト。
「ひぃっ」
妙に重い音とともに出てきたそれに悲鳴が漏れる。
「今日は足かよ……」
大きいはずだ、封筒には黒猫の後ろ足が一本ずつ入っていたのだから。
「セバスチャン、セバスチャン……」
あっという間に松岡くんは下にひいた紙ごとくるんで、私の目に入らないようにした。
「セバスチャン、セバスチャンが」
縋るように松岡くんの腕を掴む。
見上げた彼は泣き出しそうに顔を歪めていた。
「紅夏、落ち着け。
あれはセバスチャンじゃない」
「でも、でも」
あたまではわかっているのだ、あれはセバスチャンじゃないって。
だって家を出る前、セバスチャンはミカンを転がして遊んでいたのだから。
「あれはセバスチャンじゃない。
セバスチャンはあそこにいる」
松岡くんが指さす方向を見る。
そこではセバスチャンがのんきに毛繕いをしていた。
「……うん」
一応納得して、手を離す。
でもあたまの中はぐるぐる回るばかりでちっとも落ち着かない。
「ちょっと待ってろ」
私を安心させるようにか、あたまをぽんぽんして松岡くんは台所へ消えていった。
少しして、カップを手に戻ってくる。
「落ち着くから」
「……うん」
渡されたカップを受け取った手は細かく震えていた。
こぼさないように気をつけながら、淹れてくれた紅茶を飲む。
「あれはセバスチャンじゃない。
セバスチャンはここにいる。
……わかるな?」
セバスチャンはいま、私の視線の先にいる。
あの足はセバスチャンのじゃない。
じゃああの足はどこの猫の?
やっぱり、セバスチャンのじゃ。
ううん、セバスチャンはここにいる。
だから違う。
だけど――。
「……にか。
紅夏!」
「……え?」
松岡くんから肩を揺すられ、我に返った。
私いま、なにを考えていたんだろう……?
「いまはなにも考えるな。
いいな?」
「う、うん」
強く言い聞かせるように言われ、仕方なく頷いた。
松岡くんはテレビをつけてリモコンを私に握らせ、台所へ行ってしまった。
「にゃー」
入れ替わるようにセバスチャンがやってきて、私の身体の隙間にずぼっとあたまを突っ込んでくる。
「セバスチャン」
膝の上にのせてあたまを撫でると、気持ちよさそうにのどを鳴らす。
なぜかそれだけで、わけもわからず涙が溢れてくる。
「なん、で」
悲しくなんてないのに、涙は止まらない。
鼻をずびずびいわせながら、ティッシュを何枚も消費した。
「紅夏」
「松岡、くん。
おかしいよね、なんで私、泣いてるんだろ」
「安心したからだろ」
止まらない涙を、松岡くんがまじめな顔をして拭ってくれる。
「まだ時間じゃないけど、一回帰ってくる」
「なん、で」
いまは傍にいてほしい。
時間までしかいられないがわかっていても。
なのに。
「横井さんにあれ届けて、家に帰ってくる。
んで、着替え取って戻ってくるから」
戻ってくるってどういう意味なんだろう。
「今日はここに泊まる。
こんな紅夏、ひとりにしておけない」
松岡くんの言っていることが理解できない。
「でも業務規定違反、だよね」
「そうだな」
「バレたら会社、クビになっちゃう」
「そのときは紅夏専属の執事にしてもらうからいい」
笑った彼が、ぷにっと私の頬を摘まむ。
「……痛い」
「ん、ちょっと笑ったな」
私の頬から手を離し、なぜか松岡くんは私のあたまをがしがし撫でた。
「ちょっとの間ひとりにするけど、大丈夫な?
すぐに戻ってくるから」
「……うん」
「じゃあ、行ってくる」
松岡くんがレジ袋に入れたそれを持ち、ようやく私のあたまは今日、届いたものを理解した。
……あんなに心配させるほど、取り乱すなんてダメだな、私。
でもあれはそれだけ、インパクトがあったのだ。
前足はまだ小さいから、キーホルダーかなにかに見えないこともなかった。
でも後ろ足は、しかも根元から切り取られていて、……妙にリアルだったのだ。
いや、本物なのだけど。
「金曜日と土曜日が前足……。
日曜日と月曜日が後ろ足……」
じゃあ、火曜日は?
水曜日はなにが届く?
考えると怖くて怖くてたまらない。
「セバスチャン、セバスチャン」
床を這うようにセバスチャンを探す。
セバスチャンはもうすぐごはんがもらえる時間だからか、お皿の前で待っていた。
「セバスチャンは絶対、殺させたりしないから」
無理矢理、セバスチャンを抱きしめる。
身体の震えはいつまでたっても止まらなかった。
0
あなたにおすすめの小説
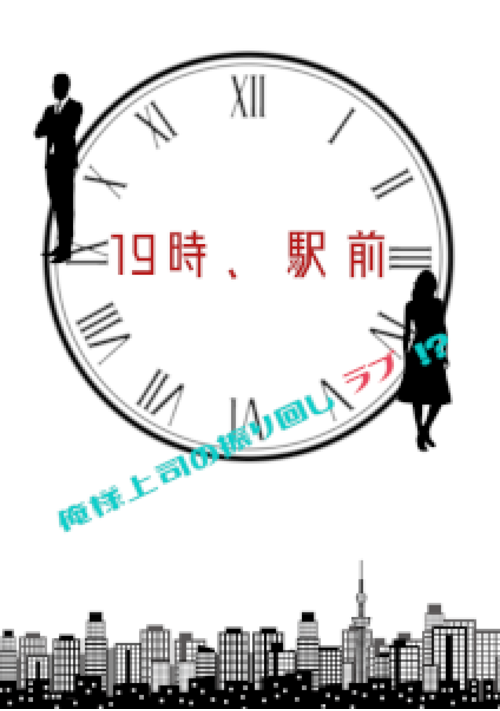
19時、駅前~俺様上司の振り回しラブ!?~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
【19時、駅前。片桐】
その日、机の上に貼られていた付箋に戸惑った。
片桐っていうのは隣の課の俺様課長、片桐課長のことでいいんだと思う。
でも私と片桐課長には、同じ営業部にいるってこと以外、なにも接点がない。
なのに、この呼び出しは一体、なんですか……?
笹岡花重
24歳、食品卸会社営業部勤務。
真面目で頑張り屋さん。
嫌と言えない性格。
あとは平凡な女子。
×
片桐樹馬
29歳、食品卸会社勤務。
3課課長兼部長代理
高身長・高学歴・高収入と昔の三高を満たす男。
もちろん、仕事できる。
ただし、俺様。
俺様片桐課長に振り回され、私はどうなっちゃうの……!?


夜の声
神崎
恋愛
r15にしてありますが、濡れ場のシーンはわずかにあります。
読まなくても物語はわかるので、あるところはタイトルの数字を#で囲んでます。
小さな喫茶店でアルバイトをしている高校生の「桜」は、ある日、喫茶店の店主「葵」より、彼の友人である「柊」を紹介される。
柊の声は彼女が聴いている夜の声によく似ていた。
そこから彼女は柊に急速に惹かれていく。しかし彼は彼女に決して語らない事があった。

【完結】伯爵令嬢の25通の手紙 ~この手紙たちが、わたしを支えてくれますように~
朝日みらい
恋愛
煌びやかな晩餐会。クラリッサは上品に振る舞おうと努めるが、周囲の貴族は彼女の地味な外見を笑う。
婚約者ルネがワインを掲げて笑う。「俺は華のある令嬢が好きなんだ。すまないが、君では退屈だ。」
静寂と嘲笑の中、クラリッサは微笑みを崩さずに頭を下げる。
夜、涙をこらえて母宛てに手紙を書く。
「恥をかいたけれど、泣かないことを誇りに思いたいです。」
彼女の最初の手紙が、物語の始まりになるように――。

一億円の花嫁
藤谷 郁
恋愛
奈々子は家族の中の落ちこぼれ。
父親がすすめる縁談を断り切れず、望まぬ結婚をすることになった。
もうすぐ自由が無くなる。せめて最後に、思いきり贅沢な時間を過ごそう。
「きっと、素晴らしい旅になる」
ずっと憧れていた高級ホテルに到着し、わくわくする奈々子だが……
幸か不幸か!?
思いもよらぬ、運命の出会いが待っていた。
※エブリスタさまにも掲載

契約書は婚姻届
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
「契約続行はお嬢さんと私の結婚が、条件です」
突然、降って湧いた結婚の話。
しかも、父親の工場と引き替えに。
「この条件がのめない場合は当初の予定通り、契約は打ち切りということで」
突きつけられる契約書という名の婚姻届。
父親の工場を救えるのは自分ひとり。
「わかりました。
あなたと結婚します」
はじまった契約結婚生活があまー……いはずがない!?
若園朋香、26歳
ごくごく普通の、町工場の社長の娘
×
押部尚一郎、36歳
日本屈指の医療グループ、オシベの御曹司
さらに
自分もグループ会社のひとつの社長
さらに
ドイツ人ハーフの金髪碧眼銀縁眼鏡
そして
極度の溺愛体質??
******
表紙は瀬木尚史@相沢蒼依さん(Twitter@tonaoto4)から。

ソウシソウアイ?
野草こたつ/ロクヨミノ
恋愛
政略結婚をすることになったオデット。
その相手は初恋の人であり、同時にオデットの姉アンネリースに想いを寄せる騎士団の上司、ランヴァルド・アーノルト伯爵。
拒否に拒否を重ねたが強制的に結婚が決まり、
諦めにも似た気持ちで嫁いだオデットだが……。

私に告白してきたはずの先輩が、私の友人とキスをしてました。黙って退散して食事をしていたら、ハイスペックなイケメン彼氏ができちゃったのですが。
石河 翠
恋愛
飲み会の最中に席を立った主人公。化粧室に向かった彼女は、自分に告白してきた先輩と自分の友人がキスをしている現場を目撃する。
自分への告白は、何だったのか。あまりの出来事に衝撃を受けた彼女は、そのまま行きつけの喫茶店に退散する。
そこでやけ食いをする予定が、美味しいものに満足してご機嫌に。ちょっとしてネタとして先ほどのできごとを話したところ、ずっと片想いをしていた相手に押し倒されて……。
好きなひとは高嶺の花だからと諦めつつそばにいたい主人公と、アピールし過ぎているせいで冗談だと思われている愛が重たいヒーローの恋物語。
この作品は、小説家になろう及びエブリスタでも投稿しております。
扉絵は、写真ACよりチョコラテさまの作品をお借りしております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















