2 / 48
第一章 暗闇は深く
第1話 逃げ場のない叱責
しおりを挟む
壁掛け時計の針が、いつもより重く回る。
普段ならちらほらと雑談が聞こえる室内は、様子をうかがうように静まり返っていた。
それが更に居心地の悪さを助長させ、私は呼吸を浅くする。
目の前に座った直属の上司である村上さんは、慣れた手つきで書類をバサリと机に投げ出した。
「これ、なんとかならなかったの?」
指差された書類には、部下である夏目さんの小さなミスが赤字で囲まれていた。
夏目さんは私よりも三年後輩の社員。
入社三年目の彼女は、いわゆる今どきの女の子で、チケット管理や手順書の更新といった地味な作業に、どうしても熱量が感じられなかった。
ただ、愛嬌は人一倍あって、エンジニアや取引先からの受けはいい。
仕様の確認や軽い問い合わせ対応もそつなくこなすため、評価自体は悪くないのだ。
その分、現場を仕切る立場の村上さんからは、あまり良く思われていないようだった。
そして、そのしわ寄せは教育係の私に回ってくる。
コツコツと机を指先で叩きながらわざとらしいため息をつく村上さんに私は「すみません」と小さく呟いた。
私、木崎茉莉は、この会社に勤めて6年目のITアシスタントだ。
当たり障りのないオフィスカジュアルに髪をひとつにまとめ、視力のあまり良くない目には大きめの黒縁メガネをかけている。
正直地味な私は、自分に自信があるとは決して言えない性格をしていた。
「あなたの教育が悪いからこうなるのよ。来月からは新入社員が増えるっていうのに、ちゃんと指導してるの?」
この会社でITアシスタントと呼ばれているのは、私と村上さん、夏目さんの三人だけ。
一方で、開発や保守を担うエンジニアは十人在籍していて、私たちは三人でその全員を支えなければならないのだから、村上さんがピリピリするのには納得している。
「はい……申し訳ありません」
もう一度頭を下げると、村上さんは息をついて続けた。
「本当に分かってるの?あなたたち若い人は、ほんと責任感がないわね。私の時代には考えられなかった」
その内容は、夏目さんのことから聞きなれたいつもの説教へと変わっていった。
始まると止まらなくなる村上さんの話は、頭が痛くなるほど聞いていた。
実際に改善点がどうとかの話ではなく、とにかく嫌味が止まらないような話の内容。
それもオフィスに響き渡るような大きな声で言われるものだから、私は肩身が狭い思いで「すみません」と小声で相槌を続けた。
どれだけその内容が納得のいかないものでも、村上さんに反発するほど私に自我はない。
実際、私は人を叱るのが得意ではないし、言われても仕方ないとすら思っていた。
学生時代の友人に「茉莉は控えめすぎるよ」と言われたことをぼんやりと思い出したけれど、それを変えられるほどの自信は未だ身につけられていない。
そうしている間にも、時計の針はずしりずしりと重たい音を立てながら進んでいた。
「こういうことが続くと、周りからも信頼を失うって言ってるの。分かっている?」
「はい……」
窓の外では小雨が降り続いている。
3月になったというのに、少しも暖かくならない気候は私の心にもどんよりと影を落としていた。
_/_/_/_/_/_/
やっとのことで解放された私は、逃げるようにオフィスを出た。
「やっと終わったみたい、毎日毎日辞めてほしいよね」
「木崎さんももう少し上手くやったらいいのにね」
扉を出るまでのあいだ、ひそひそと囁かれる小声に、私は俯いて視線を逸らすしかできなかった。
要領が悪いと囁かれていることは私の耳にも入っている。
けれど実際には、三人で分担して回さなければならない業務を、私はほとんど一人で抱え込んでいた。
厄介な御局様として知られる村上さんは、判断や責任をこちらに投げたまま、結果だけを見て声を荒らげる。
一方で後輩の夏目さんは、定時になればさっさと席を立ち、面倒な対応やトラブル処理は、当然のように私のところへ回してくる。
それでも評価されるのは、声を上げる人間か、要領よく立ち回る人間だけ。
静かに破綻を埋めている私は、ただ「仕事が遅い人」として扱われていた。
損な性格をしている。
それは、私自身も自覚している、紛れもない事実だった。
_/_/_/_/_/_/
昼下がりの給湯室では、いつものように夏目さんが笑顔を振りまいていた。
もうすぐやってくる春を連想させるラベンダーカラーのブラウスに、小ぶりのアクセサリー。
派手ではないが、男性社員の視線を集めるには十分の魅力的な姿。
憂鬱な気持ちを無理やり引き上げ、彼女に声をかける。
「夏目さん、ちょっといい?」
「はいっ!どうかしました?」
彼女はいつものように後輩らしい人懐っこい笑顔を向けた。
けれど緩やかに細められた視線は、給湯室の外にふわりと流れる。
そんな小さな仕草から勝手に本心を読み取って何も言えなくなる自分に、また情けなくなった。
「アカウント発行依頼の書類、もう少し丁寧に確認してほしいの。それと……」
言いづらい指摘を前に、言葉を詰まらせる。
どう伝えたら、彼女にちゃんと届くのだろう。
彼女が入社してから三年間ずっと、私は夏目さんを見てきた。
直接伝えたこともあったし、食事をしながら柔らかく話したこともある。
それでも何も変わらなくて、帰り道で涙が止まらなくなった日もあった。
結局、彼女にとっては気にするほどのことではないのだろう。
そう思うようになってからは、どれだけ村上さんに口酸っぱく言われても、私が我慢すれば仕事は回ると、自分に言い聞かせていた。
それでも今日は……。
これだけ大きく騒がれた以上、形だけでも伝えなければならない。
私は深く息を吸い、覚悟を決めてから、もう一度彼女を見つめた。
「前にも少し言ったけど、村上さんが、夏目さんのこと気にしてるみたいだから、社内の雰囲気も考えて行動してくれると助かる」
結局口から出たのはそんなふんわりとした言葉だった。
大事なところで踏み込めないのは、私の悪い癖だ。
上昇意欲もなく、強い意思もない私は、周りにとって都合のいい存在なのだと思う。
「はーい、気をつけますね。でも……」
夏目さんは少し考える素振りを見せてから、続けた。
「私、そんなに悪いことしてるつもりはなくて。
木崎さんも、村上さんのこと、そこまで気にしなくていいんじゃないですか?
村上さんって結構、厄介だって言われてますし……目つけられてて大変そうですね」
困ったように首を傾げるその仕草に、私は一瞬言葉を失った。
私が村上さんに目をつけられているのは事実だ。
けれど、その理由に彼女自身が深く関わっていることには、まるで興味がない。
「わかった。でも、お願いね」
その衝撃をも飲み込むことしかできない自分が嫌になる。
胸の奥に小さな虚しさを抱えたまま、私は話を切り上げた。
_/_/_/_/_/_/
第一話、読んでいただきありがとうございます_(⑉• •⑉_)
気に入っていただけたら、お気に入りやエールをいただけますと励みになります!
次回もぜひよろしくお願いいたします。
普段ならちらほらと雑談が聞こえる室内は、様子をうかがうように静まり返っていた。
それが更に居心地の悪さを助長させ、私は呼吸を浅くする。
目の前に座った直属の上司である村上さんは、慣れた手つきで書類をバサリと机に投げ出した。
「これ、なんとかならなかったの?」
指差された書類には、部下である夏目さんの小さなミスが赤字で囲まれていた。
夏目さんは私よりも三年後輩の社員。
入社三年目の彼女は、いわゆる今どきの女の子で、チケット管理や手順書の更新といった地味な作業に、どうしても熱量が感じられなかった。
ただ、愛嬌は人一倍あって、エンジニアや取引先からの受けはいい。
仕様の確認や軽い問い合わせ対応もそつなくこなすため、評価自体は悪くないのだ。
その分、現場を仕切る立場の村上さんからは、あまり良く思われていないようだった。
そして、そのしわ寄せは教育係の私に回ってくる。
コツコツと机を指先で叩きながらわざとらしいため息をつく村上さんに私は「すみません」と小さく呟いた。
私、木崎茉莉は、この会社に勤めて6年目のITアシスタントだ。
当たり障りのないオフィスカジュアルに髪をひとつにまとめ、視力のあまり良くない目には大きめの黒縁メガネをかけている。
正直地味な私は、自分に自信があるとは決して言えない性格をしていた。
「あなたの教育が悪いからこうなるのよ。来月からは新入社員が増えるっていうのに、ちゃんと指導してるの?」
この会社でITアシスタントと呼ばれているのは、私と村上さん、夏目さんの三人だけ。
一方で、開発や保守を担うエンジニアは十人在籍していて、私たちは三人でその全員を支えなければならないのだから、村上さんがピリピリするのには納得している。
「はい……申し訳ありません」
もう一度頭を下げると、村上さんは息をついて続けた。
「本当に分かってるの?あなたたち若い人は、ほんと責任感がないわね。私の時代には考えられなかった」
その内容は、夏目さんのことから聞きなれたいつもの説教へと変わっていった。
始まると止まらなくなる村上さんの話は、頭が痛くなるほど聞いていた。
実際に改善点がどうとかの話ではなく、とにかく嫌味が止まらないような話の内容。
それもオフィスに響き渡るような大きな声で言われるものだから、私は肩身が狭い思いで「すみません」と小声で相槌を続けた。
どれだけその内容が納得のいかないものでも、村上さんに反発するほど私に自我はない。
実際、私は人を叱るのが得意ではないし、言われても仕方ないとすら思っていた。
学生時代の友人に「茉莉は控えめすぎるよ」と言われたことをぼんやりと思い出したけれど、それを変えられるほどの自信は未だ身につけられていない。
そうしている間にも、時計の針はずしりずしりと重たい音を立てながら進んでいた。
「こういうことが続くと、周りからも信頼を失うって言ってるの。分かっている?」
「はい……」
窓の外では小雨が降り続いている。
3月になったというのに、少しも暖かくならない気候は私の心にもどんよりと影を落としていた。
_/_/_/_/_/_/
やっとのことで解放された私は、逃げるようにオフィスを出た。
「やっと終わったみたい、毎日毎日辞めてほしいよね」
「木崎さんももう少し上手くやったらいいのにね」
扉を出るまでのあいだ、ひそひそと囁かれる小声に、私は俯いて視線を逸らすしかできなかった。
要領が悪いと囁かれていることは私の耳にも入っている。
けれど実際には、三人で分担して回さなければならない業務を、私はほとんど一人で抱え込んでいた。
厄介な御局様として知られる村上さんは、判断や責任をこちらに投げたまま、結果だけを見て声を荒らげる。
一方で後輩の夏目さんは、定時になればさっさと席を立ち、面倒な対応やトラブル処理は、当然のように私のところへ回してくる。
それでも評価されるのは、声を上げる人間か、要領よく立ち回る人間だけ。
静かに破綻を埋めている私は、ただ「仕事が遅い人」として扱われていた。
損な性格をしている。
それは、私自身も自覚している、紛れもない事実だった。
_/_/_/_/_/_/
昼下がりの給湯室では、いつものように夏目さんが笑顔を振りまいていた。
もうすぐやってくる春を連想させるラベンダーカラーのブラウスに、小ぶりのアクセサリー。
派手ではないが、男性社員の視線を集めるには十分の魅力的な姿。
憂鬱な気持ちを無理やり引き上げ、彼女に声をかける。
「夏目さん、ちょっといい?」
「はいっ!どうかしました?」
彼女はいつものように後輩らしい人懐っこい笑顔を向けた。
けれど緩やかに細められた視線は、給湯室の外にふわりと流れる。
そんな小さな仕草から勝手に本心を読み取って何も言えなくなる自分に、また情けなくなった。
「アカウント発行依頼の書類、もう少し丁寧に確認してほしいの。それと……」
言いづらい指摘を前に、言葉を詰まらせる。
どう伝えたら、彼女にちゃんと届くのだろう。
彼女が入社してから三年間ずっと、私は夏目さんを見てきた。
直接伝えたこともあったし、食事をしながら柔らかく話したこともある。
それでも何も変わらなくて、帰り道で涙が止まらなくなった日もあった。
結局、彼女にとっては気にするほどのことではないのだろう。
そう思うようになってからは、どれだけ村上さんに口酸っぱく言われても、私が我慢すれば仕事は回ると、自分に言い聞かせていた。
それでも今日は……。
これだけ大きく騒がれた以上、形だけでも伝えなければならない。
私は深く息を吸い、覚悟を決めてから、もう一度彼女を見つめた。
「前にも少し言ったけど、村上さんが、夏目さんのこと気にしてるみたいだから、社内の雰囲気も考えて行動してくれると助かる」
結局口から出たのはそんなふんわりとした言葉だった。
大事なところで踏み込めないのは、私の悪い癖だ。
上昇意欲もなく、強い意思もない私は、周りにとって都合のいい存在なのだと思う。
「はーい、気をつけますね。でも……」
夏目さんは少し考える素振りを見せてから、続けた。
「私、そんなに悪いことしてるつもりはなくて。
木崎さんも、村上さんのこと、そこまで気にしなくていいんじゃないですか?
村上さんって結構、厄介だって言われてますし……目つけられてて大変そうですね」
困ったように首を傾げるその仕草に、私は一瞬言葉を失った。
私が村上さんに目をつけられているのは事実だ。
けれど、その理由に彼女自身が深く関わっていることには、まるで興味がない。
「わかった。でも、お願いね」
その衝撃をも飲み込むことしかできない自分が嫌になる。
胸の奥に小さな虚しさを抱えたまま、私は話を切り上げた。
_/_/_/_/_/_/
第一話、読んでいただきありがとうございます_(⑉• •⑉_)
気に入っていただけたら、お気に入りやエールをいただけますと励みになります!
次回もぜひよろしくお願いいたします。
13
あなたにおすすめの小説

わたしの愉快な旦那さん
川上桃園
恋愛
あまりの辛さにブラックすぎるバイトをやめた。最後塩まかれたけど気にしない。
あ、そういえばこの店入ったことなかったな、入ってみよう。
「何かお探しですか」
その店はなんでも取り扱うという。噂によると彼氏も紹介してくれるらしい。でもそんなのいらない。彼氏だったらすぐに離れてしまうかもしれないのだから。
店員のお兄さんを前にてんぱった私は。
「旦那さんが欲しいです……」
と、斜め上の回答をしてしまった。でもお兄さんは優しい。
「どんな旦那さんをお望みですか」
「え、えっと……愉快な、旦那さん?」
そしてお兄さんは自分を指差した。
「僕が、お客様のお探しの『愉快な旦那さん』ですよ」
そこから始まる恋のお話です。大学生女子と社会人男子(御曹司)。ほのぼのとした日常恋愛もの
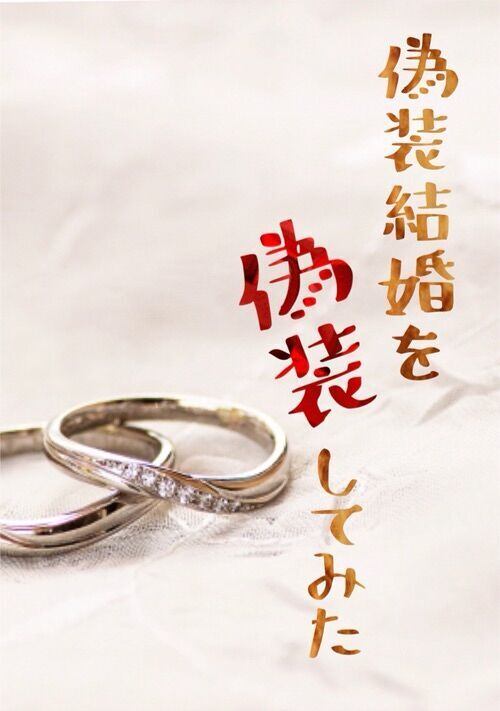
偽装結婚を偽装してみた
小海音かなた
恋愛
「家借りるときさぁ、保証人が必要だと困るとき来そうで不安なんだよね」
酒の席で元後輩にそんなことをグチったら、旦那ができました――。
降って湧いたような結婚話を承諾したら、そこにはすれ違いの日々が待っていた?!
想いを寄せている相手の気持ちに確信が持てず、“偽装”を“偽装している”夫婦のモダモダ遠回り生活。
苦くてしょっぱくて甘酸っぱい、オトナ思春期ラブストーリー第2弾。
※毎日19時、20時、21時に一話ずつ公開していきます。

地味系秘書と氷の副社長は今日も仲良くバトルしてます!
楓乃めーぷる
恋愛
見た目はどこにでもいそうな地味系女子の小鳥風音(おどりかざね)が、ようやく就職した会社で何故か社長秘書に大抜擢されてしまう。
秘書検定も持っていない自分がどうしてそんなことに……。
呼び出された社長室では、明るいイケメンチャラ男な御曹司の社長と、ニコリともしない銀縁眼鏡の副社長が風音を待ち構えていた――
地味系女子が色々巻き込まれながら、イケメンと美形とぶつかって仲良くなっていく王道ラブコメなお話になっていく予定です。
ちょっとだけ三角関係もあるかも?
・表紙はかんたん表紙メーカーで作成しています。
・毎日11時に投稿予定です。
・勢いで書いてます。誤字脱字等チェックしてますが、不備があるかもしれません。
・公開済のお話も加筆訂正する場合があります。

【完結】溺愛予告~御曹司の告白躱します~
蓮美ちま
恋愛
モテる彼氏はいらない。
嫉妬に身を焦がす恋愛はこりごり。
だから、仲の良い同期のままでいたい。
そう思っているのに。
今までと違う甘い視線で見つめられて、
“女”扱いしてるって私に気付かせようとしてる気がする。
全部ぜんぶ、勘違いだったらいいのに。
「勘違いじゃないから」
告白したい御曹司と
告白されたくない小ボケ女子
ラブバトル開始

会社のイケメン先輩がなぜか夜な夜な私のアパートにやって来る件について(※付き合っていません)
久留茶
恋愛
地味で陰キャでぽっちゃり体型の小森菜乃(24)は、会社の飲み会で女子一番人気のイケメン社員・五十嵐大和(26)を、ひょんなことから自分のアパートに泊めることに。
しかし五十嵐は表の顔とは別に、腹黒でひと癖もふた癖もある男だった。
「お前は俺の恋愛対象外。ヤル気も全く起きない安全地帯」
――酷い言葉に、菜乃は呆然。二度と関わるまいと決める。
なのに、それを境に彼は夜な夜な菜乃のもとへ現れるようになり……?
溺愛×性格に難ありの執着男子 × 冴えない自分から変身する健気ヒロイン。
王道と刺激が詰まったオフィスラブコメディ!
*全28話完結
*辛口で過激な発言あり。苦手な方はご注意ください。
*他誌にも掲載中です。

私の婚活事情〜副社長の策に嵌まるまで〜
みかん桜
恋愛
身長172センチ。
高身長であること以外ごく普通のアラサーOL、佐伯花音。
婚活アプリに登録し、積極的に動いているのに中々上手く行かない。
「名前からしてもっと可愛らしい人かと……」ってどういうこと?
そんな男、こっちから願い下げ!
——でもだからって、イケメンで仕事もできる副社長……こんなハイスペ男子も求めてないっ!
って思ってたんだけどな。気が付いた時には既に副社長の手の内にいた。

冷徹社長は幼馴染の私にだけ甘い
森本イチカ
恋愛
妹じゃなくて、女として見て欲しい。
14歳年下の凛子は幼馴染の優にずっと片想いしていた。
やっと社会人になり、社長である優と少しでも近づけたと思っていた矢先、優がお見合いをしている事を知る凛子。
女としてみて欲しくて迫るが拒まれてーー
★短編ですが長編に変更可能です。

花咲くように 微笑んで 【書籍化】
葉月 まい
恋愛
初恋の先輩、春樹の結婚式に
出席した菜乃花は
ひょんなことから颯真と知り合う
胸に抱えた挫折と失恋
仕事への葛藤
互いの悩みを打ち明け
心を通わせていくが
二人の関係は平行線のまま
ある日菜乃花は別のドクターと出かけることになり、そこで思わぬ事態となる…
✼•• ┈┈┈ 登場人物 ┈┈┈••✼
鈴原 菜乃花(24歳)…図書館司書
宮瀬 颯真(28歳)…救急科専攻医
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















