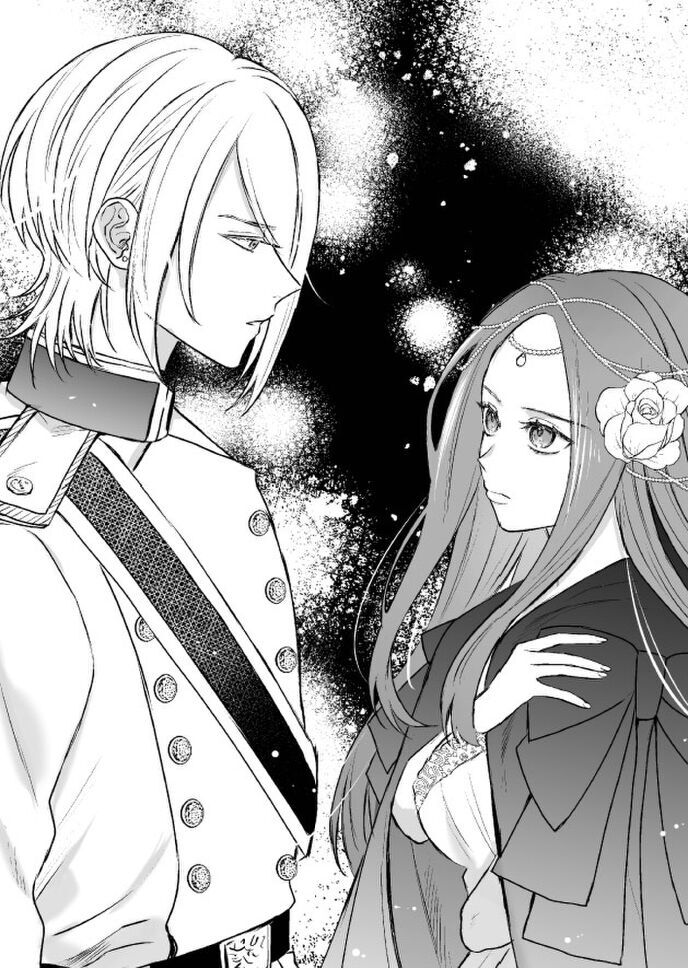5 / 19
1巻
1-3
しおりを挟む
幸い、この中には妃達と皇帝のみ。イザベラはふっと笑ってから、堂々とした仕草と口調で反撃した。
(仮でも夫と妃達だけよ。堂々としていれば大丈夫よね。ナイアードの者として他国の姫君に舐められるような事があってはいけないの)
「そうなの、祖国では女性だからと締め付けられるだけの窮屈な格好は主流じゃないの。皆、作らずともありのままで美しいのよ」
「なっ!? それは私達が作り上げた身体だと?」
メリダが引き攣った顔でそう言うと、立ち上がったイザベラの美しさに圧倒されたように声を失った。
「……そうね、そういう意味ではないけれど。そちらこそ、はしたないというのはこう言うことかしら?」
濡れて重くなったドレスを床に落として、下着姿だというのに堂々とした所作で見惚れるローレンスの肩に手を置いて頬に口付け「では、お先に」とその場を後にしようとして、追撃する。
「あら、下着まで濡れたわね」
ランジェリーを拾えとでもいうようにサラの目の前に落として、床のドレスをチラリと見るとイザベラはメリダの方を向いて「この部屋には侍女が居ないのよ」と困ったように言った。
この部屋では妃達が皇帝のお世話をする。その為侍女達は妃達の部屋の隣の各部屋で待機していたのだ。
ローレンスはハッと我に返り、イザベラにジャケットをかける。
「では、私が部屋まで連れよう。お前達、此処を片付けておくように」
それだけを言い残してイザベラを横抱きにして部屋を出てしまった。
妃達は、まるで自分がイザベラの侍女にでもなったような気さえもして、ローレンスが完璧に彼女の肩を持った事が悔しくて顔を怒りで歪めた。
「……ありがとうございます。下ろして下さい」
真ん中の部屋を囲うように円に作られた廊下を出れば、入り口の反対側の扉からすぐの場所に皇后の部屋があり、その奥には使用人の部屋がある。
使用人達の出入りは外からの扉となっていて、妃達の部屋を通る必要は無い。妃達の部屋側からしか鍵がかからないようになっており、部屋と部屋の間は小さめだが温室のような、室内にも関わらず美しい中庭があった。
そして、二人がいるのは廊下の皇后の部屋の前である。
ローレンスはそっとイザベラを下ろすと、何か言いたげに眉を顰めた。
「……」
「陛下、お戻りになりませんと妃達が心配致します」
「皇后は、いつもあのような悪意の中にいるのか?」
イザベラは腹立たしい気持ちをグッと抑えるように、ローレンスを見ずに返事をする。
「まるで、ご自分の行いは悪意に入っていないように仰るのね」
顔を上げたイザベラの鋭い光を放つ瞳と目が合うと、不謹慎にもローレンスは薄暗く見えていた景色が鮮やかに映るような感覚がした。
ゾワゾワと何かが身体を走るような感覚さえしたし、イザベラのエメラルドグリーンの瞳は今まで見たどの宝石よりも鮮やかで美しく感じた。
(いや、私はいったい何を……国政の為、大臣達に言われ妃達を娶るのは致し方無かったとはいえ、私にはメリダしかいないはずだろう……血迷ったか)
雑念を追い払い、ローレンスはイザベラに向き直る。
「……どういう意味だ?」
「私の品格維持費や、その他諸々はナイアードからきちんと有り余る程に援助されている筈ですが、使用人の人数が一番少ないのは皇后宮です。何をするにも『なぜか』予算がないと皇帝陛下がお断りになるので、私の生活は必要最低限以上は私財で賄っていますのよ?」
ローレンスは驚愕した。
ナイアードから援助された皇后宮へ宛てる費用は毎月きちんと皇后に使われるように指示していたし、余れば皇后の手に渡るように言っていたのだ。
それに……
「私の指示ではない。記帳された帳簿も毎度きちんと確認している」
今度は、イザベラが驚愕する番であった。
ローレンスが嘘を言っているようには見えない。
「では、お金だけが消えていると?」
ナイアードが援助を断った訳ではないのは確実であった。
兄からの手紙にはライネル帝国ではなく、ナイアードがイザベラの生活資金を援助する理由が確かに書いてあったからだ。
イザベラの現状を手紙と噂によって知ったナイアードの王、もといイザベラの父は極度のブラコンであるイザベラの兄と共にライネルへ抗議する事を考えたが、無闇に行動をしてはイザベラの立場を悪くしてしまう可能性もあるのではないかと考え、『ナイアードはイザベラを手放したつもりはない』という意思表示のつもりでイザベラの品格維持費と生活費の全額援助を申し出たという話であった。
イザベラが残してきた幾つかの事業が妹達に引き継がれ、いまだに利益を上げている事に加えて、そもそもナイアードはこの程度で傾きはしないとまで書いてあった。
(それに、いつでも帰って来いとも……)
「調査しよう。……本当に申し訳なかった」
「特に不自由はしておりませんが、これでは祖国からの気持ちを踏み躙る事になりますので。許可を頂けるなら私が調査致します」
「いや……こちらで責任を持って調査しよう」
「……」
「不服か?」
「ええ、どのように陛下を信頼すればいいのかと」
「……っ、では皇后にも調査の指導権を与える」
「感謝致します。では……、……?」
中々その場を動こうとしないローレンスを疑問に思い首を傾げると、バツが悪そうに視線を彷徨わせる。
「いや、お茶には誘ってくれぬのかと……」
「……? そのような仲ではないでしょう。メリダ妃が待っている筈です。お戻り下さい陛下」
「だが……」
「このような格好ですし、今日は下がらせて頂きますが、明日また参りますのでお話はまた明日」
「皇后……っ!」
ローレンスは閉められた扉を捨て犬のように見つめてから、髪をくしゃりと崩し踵を返す。
若き皇帝にとって、始まりは信頼できる者などいないと思っていた王宮だった。
しばらく王座にいる内に確かな基盤を作れていると思っていたが、改めて身の回りの者達の腹の中を見極める必要がありそうだ。
不慣れな政治を教わった老いぼれ達は、心から信頼していたわけではなかったが、国を想う気持ちは本物だと信じていた。
初めて目にした、妃達から皇后への悪意と、思っていたものとは違う皇后イザベラの対応。
まるで自分だけが何かを見落としている気さえした。
(さっきのメリダは……イザベラよりも彼女の方が……)
皇帝が去った部屋で、苛立ちを隠せないと言うようにメリダがグラスを払い落とす。びくりと肩を揺らす妃達と、スッと目を背ける妃、メリダはそれぞれの反応を確認してから深呼吸して、彼女達を見渡した。
「サラ、片付けておいてくれる?」
我関せずを決めこんでいるテリーヌ以外の妃達にメリダが問いかける。
「私に付いてくる者は? 貴女達が受けている恩恵は計り知れないはずよ」
事実、他の妃達は、なるべく安全に金銭的、権力面での恩恵を受けつつ皇后の座を狙う為に、メリダの味方でいる必要があった。
メリダはローレンスの初恋の女性であり、彼が精神的に絶対的な信頼を寄せる心の支えといってもいい存在だと自負している。
それを上手く利用し、ローレンスの心を癒すのではなく、不安定で人間不信な彼のままでいさせて自分だけが彼の味方だと思い込ませ、まだ未熟だった頃から彼を思うがままにしてきた。
側から見れば、彼女は彼の寵愛を一心に受ける影の皇后であり、イザベラはただ面倒な公務や外交をこなすだけの愛されない便利な皇后であった。
「わ、私……メリダ様に皇后の座をお渡ししたい、です……」
サラがそう言うのは家のためだ。メリダが皇后になる事は身分的にありえない話だが、メリダに対し執着と依存を見せ、それを恋だと疑わないローレンスに対して、目を覚まさせることは出来ないと諦めていた。
であれば下手に逆らって家ごと潰されるよりも、メリダの腰巾着となってせめて家門の名誉を守り、側妃のまま大人しく生きる方がマシだった。
キャロライドとフィージアも、「あなたに付くわ」と返事をしたが、彼女達に関してはとにかく強大なナイアードの姫であるイザベラを排除する力が必要だったからだ。
(メリダは手強いし、皇后と共倒れしてくれればいいわ)
(一時休戦ね。メリダは元より皇帝の恋人、今はまだ勝ち目がないもの)
そうして、彼女達は一時結託して皇后を失脚させるべく組んだのだが、メリダは全く彼女達を尊重するつもりなど無かった。
(王妃となり、この国を思うままに動かす。その為に危険な賭けでローレンスを操ってきたのだから。惚れてくれたのが幸いだったわ。ローレンス、あなたを馬鹿に育てるのは大変だったのよ……早く私を引っ張り上げて! その為にはあの目障りな女とこのクズ達を消さないとね)
各々の思惑が渦巻く中、皇帝が戻って来る。
「遅くなった」
物思いに耽った表情で戻ったローレンスに、メリダが巻き付くように引っ付いた。
「陛下……っ、待っていましたのよ?」
そんなメリダに続いて皆が「陛下、お待ちしておりました」と挨拶をする。まるでメリダを慕うかのように……
先程初めて目にした噂とは真逆の光景に違和感を覚えていたローレンスだったが、このメリダを持ち上げるような皆の態度に更なる違和感を覚える。
今まで妃達や妃達の使用人たちから聞いていたイザベラの噂、横暴で傲慢な行いをして他の妃を従える悪女は、先程からメリダのことに思えて仕方ない。
「……皇后は、本当にお前達を虐げているのか?」
「えっ……?」
「私にはお前達皆が結託し、皇后を陥れたようにも見えた。メリダ、お前は私に嘘をつかないだろう?」
皇帝の威厳の隙間から垣間見える、小鳥の雛が母親を見るような視線。
彼女は密かに口元だけをニヤリと歪ませて、ローレンスの頬に手を伸ばし、優しく撫でた。
「若い妃を娶る事に賛成したのは私でしょう? 嘘をつくはずがありませんわ。今日は皆、皇后の姿を久々に見て気が立っていたのでしょう」
「……そうか」
「ええ、そうよ」
内心では納得がいかないローレンスが手に取るように分かるメリダは、ほっとして安心したように息を吐いた他の妃達をひと睨みし、ローレンスを座らせて自分はその膝に乗った。
彼の許可無く彼に触れられる者はメリダしかおらず、まるで格の違いを見せつけるように他の妃達に世話をさせ、自分はローレンスの膝で皇后にでもなったかのように皆に指示ばかりしていた。
ローレンスが完璧にメリダに惚れていると自負している彼女の行動は段々と大胆になって行き、ローレンスを信じさせ甘やかそうとしたこの日も例外なく始終横柄な態度が滲んでいる。
結果、ローレンスの違和感は消えない。
そしてメリダは、長年そうだったように、メリダ自身を無条件に信じているはずのローレンスの僅かな悩みと違和感を敏感に感じ取った。
(あの皇后……ローレンスに何したの? ローレンス、貴女は盲目的に私を愛し、私だけを信頼し、馬鹿でいなければならないのよ、私のために)
ローレンスを抱きしめる肩越しに見せた彼女のにんまりとした笑顔に、他の妃達は恐怖を覚える。
唯一それが見えていないローレンスは、ただ一人思考に沈む。
今までイザベラとの接触を控えてきたが、唐突にイザベラとの接触が増えて会話を交わしてみて、イザベラがよく目に入るようになった。
今回の中央宮でのメリダの言動と妃達の雰囲気を感じたローレンスは、確信こそ無いが、メリダが自分に嘘をついているような気がしていた。
メリダの変わらぬ体温の中、メリダの願う気持ちとは裏腹に、感じている違和感を確かめようと決心する。
(メリダの助言もあり、老ぼれ達の希望通りの側妃達を娶ったが……政情は整ったとはいえ、前々から不自然だと思っていた。物わかりのいい女性だと感心していたが、私を心から愛しているのなら自分だけを愛して欲しいと考えるはずではないのか……まさか、何かあるのか……?)
それぞれの思考の中、きっとこの閉ざされた皇宮でしがらみなく自由に振る舞える者は彼女しかいないだろうと二人はふと思い浮かべる。
(やはり、皇后と話さなくては)
(やっぱり皇后を潰しとかないと)
日が落ち、他の妃達も自室へと戻ったようだと報告を受けて、イザベラも寝衣の簡素なドレスに着替えてミアに淹れてもらったナイアードから仕入れたお茶でゆったりとしていた。
(これ、キリアンも好きだったわね)
「偶然に上手く下がれたけれど、このまま何も起きずにいて欲しいわね」
「そうですね。私も細心の注意を払いますので、本日はゆっくりお休み下さい」
暫くすると、リーナが少し気まずそうにイザベラに客人の知らせをした。
「イザベラ様……皇帝陛下がお見えです」
イザベラは額に片手を置いて深くため息をつくと、その身を整える事もなく、無粋な夫に対応した。
「陛下……このような夜分にどうされましたか?」
「その、皇后……少し話をしたいんだが、入れてはくれないか?」
(何かしら? 初日だから一応皇后の所へ来たということかしら)
「私は陛下と閨を共にする仲ではありませんが……他の妃ではなくあえて私をお望みでしょうか?」
イザベラは今、黒のレースとシルクを上品に使ったキャミソールの簡素なドレスに同じ素材のガウンを羽織っている。白い肌と真っ直ぐにさらりと下されたエメラルドグリーンの髪は幻想的だ。
ローレンスはそんな彼女に少し緊張した様子で言葉を詰まらせた後に絞り出すように言う。
「邪な理由は無い、皇后と少し話をすればちゃんと自室へと戻ると約束する」
それだけを言うのが精一杯で、なぜか切羽詰まったようにも見える皇帝の姿に、ただ首を縦に振ってミアに視線をやると、すぐにお茶の準備が始まった。
(仮にも夫だし、無碍にはできないわね。来た理由があるはず)
「……いいのか?」
「では、これは誰の分のお茶を用意しているのですか? おかけになって」
呆れたように少し笑ったイザベラに安心した表情をしたローレンスは、ぽつり、ぽつりと話し始めた。
「私は、皇后への噂を疑う事なく信じていた。その噂を口にするものが一人ではなかったからだ。だが、よく考えてみれば何故かそなたはいつも一人で、王宮の者達と対峙し多勢でそなたを敵視している」
「不自然ですが、いつものことです」
「……陥れるならば、一人きりのそなたより皆がそなたを陥れる方が簡単だというのに、私はそなたが傲慢に振る舞っていると信じ目を向けた事もなかった……」
「それは、謝罪と受け取っても宜しいのですか?」
「……正直に言うとまだ誰を信じていいのか分からないのだ。そなたも、メリダも、あの老ぼれ共も……」
「見たものを信じればよいのです。貴方は目を閉じているも同然。例えば……辛い過去や辛い境遇があっても、私達はそれを言い訳にできる立場にありません。今、私もそうであるように」
ローレンスは驚いた。メリダとイザベラとではローレンスに対してかける言葉が百八十度違ったからだ。
『ローレンス、貴方は辛い事ばかりだったわ。時には目を塞ぎ、耳を塞ぎ、身を守る事も大切よ? 貴方はこの国にとって大切な存在だから。私にとってもね」
『私だけを信じてローレンス、私たちはずっと二人で生きてきたわ」
メリダの言葉が頭の中に浮かぶ。
果たしてどちらが正しいのか、今ここで答えを出すには目の前の皇后を知らなすぎた。ただ、長い間視界を塞いでいた何らかの暗示から解放されたような感覚がある。
「陛下、もっと沢山の人を見て意見を聞き、広い視野で貴方なりの意見を持って人々を導いて下さい。貴方が窮屈だと感じるのならば、それは自らが何かに囚われているのです。自分を信じて」
「そなたではなく?」
「信じられる程に、私の事をご存知ないでしょう」
ふっと笑ったイザベラは、ふとローレンスを見て思う。
戦場ではとても強い人だったと、冷酷な人だと聞いていた。
だけど、目の前の彼はどうだ?
深く傷つき、愛した人をただひたすら盲目的に信じるただの青年であり、なんやかんやと他の妃達に対してもそれなりに丁寧に接していた。
思えば、使用人達にも、国民にも優しい彼は、不器用で居心地が悪そうにしながらも、結局は人に優しくしてしまう彼を見てきた。
今までの所業を許す気はないが、それらを見ていたのに傲慢で意地の悪い男だと色眼鏡で見て来た自分にも非はある。
(優しすぎるのね。戦場では立っていても敵は殺しに向かってくるから、生きる為にやるべき事が決まっているけれど、国政となると違う。皆が彼を慕う顔で優しく擦り寄って来る。好意を疑えない人なのかも)
イザベラは、短く息を吐き眉を顰めて俯いているローレンスに諦めたように言葉をかける。
「今日は寝て行かれては? 私にはあの大きなソファがありますので」
そう投げかけて先にソファで寝ころんでしまった。
「え、ちょっと待っ……皇后!」
「お休みなさいませ」
そう言ってしばらくすると静かに熟睡しているイザベラをベッドに運び、誤解を招かぬようクッションでローレンスとイザベラの間に防波堤を作ってから、彼も眠った。
意外にもローレンスは久々に深い眠りにつくことが出来、翌朝イザベラの疑うような目線に必死で弁解することになる。
実際のところ、イザベラは抱き上げられたときに起きており、日頃の恨みの意趣返しだと悪戯っぽく笑っていたのは、侍女二人だけが知る。
翌朝、皇帝の部屋が開放されると、微妙な距離感ではあるがローレンスの隣に座る皇后を見て、他の妃達は顔を真っ青にした。
「おはようございます、陛下」
皆が頭を下げると、妃の代表としてメリダが挨拶を述べる。
その表情は穏やかに見えるが内心は憤っていた。
(この女、どうやってローレンスに取り入った?)
妃達は、咄嗟に脳内でメリダから皇后側に乗り換えるべきか? と頭を悩ませたが、何かの気まぐれかもしれないととりあえずはメリダ派の姿勢を崩さずに様子を見る者が全員であった。
「あぁ、おはようメリダ。それと我が妃達よ。だが挨拶が違う、皇帝の側妃として正しいマナーで挨拶をしろ」
メリダの瞳の奥に怒りが宿るのを全員が感じる。
(仮でも夫と妃達だけよ。堂々としていれば大丈夫よね。ナイアードの者として他国の姫君に舐められるような事があってはいけないの)
「そうなの、祖国では女性だからと締め付けられるだけの窮屈な格好は主流じゃないの。皆、作らずともありのままで美しいのよ」
「なっ!? それは私達が作り上げた身体だと?」
メリダが引き攣った顔でそう言うと、立ち上がったイザベラの美しさに圧倒されたように声を失った。
「……そうね、そういう意味ではないけれど。そちらこそ、はしたないというのはこう言うことかしら?」
濡れて重くなったドレスを床に落として、下着姿だというのに堂々とした所作で見惚れるローレンスの肩に手を置いて頬に口付け「では、お先に」とその場を後にしようとして、追撃する。
「あら、下着まで濡れたわね」
ランジェリーを拾えとでもいうようにサラの目の前に落として、床のドレスをチラリと見るとイザベラはメリダの方を向いて「この部屋には侍女が居ないのよ」と困ったように言った。
この部屋では妃達が皇帝のお世話をする。その為侍女達は妃達の部屋の隣の各部屋で待機していたのだ。
ローレンスはハッと我に返り、イザベラにジャケットをかける。
「では、私が部屋まで連れよう。お前達、此処を片付けておくように」
それだけを言い残してイザベラを横抱きにして部屋を出てしまった。
妃達は、まるで自分がイザベラの侍女にでもなったような気さえもして、ローレンスが完璧に彼女の肩を持った事が悔しくて顔を怒りで歪めた。
「……ありがとうございます。下ろして下さい」
真ん中の部屋を囲うように円に作られた廊下を出れば、入り口の反対側の扉からすぐの場所に皇后の部屋があり、その奥には使用人の部屋がある。
使用人達の出入りは外からの扉となっていて、妃達の部屋を通る必要は無い。妃達の部屋側からしか鍵がかからないようになっており、部屋と部屋の間は小さめだが温室のような、室内にも関わらず美しい中庭があった。
そして、二人がいるのは廊下の皇后の部屋の前である。
ローレンスはそっとイザベラを下ろすと、何か言いたげに眉を顰めた。
「……」
「陛下、お戻りになりませんと妃達が心配致します」
「皇后は、いつもあのような悪意の中にいるのか?」
イザベラは腹立たしい気持ちをグッと抑えるように、ローレンスを見ずに返事をする。
「まるで、ご自分の行いは悪意に入っていないように仰るのね」
顔を上げたイザベラの鋭い光を放つ瞳と目が合うと、不謹慎にもローレンスは薄暗く見えていた景色が鮮やかに映るような感覚がした。
ゾワゾワと何かが身体を走るような感覚さえしたし、イザベラのエメラルドグリーンの瞳は今まで見たどの宝石よりも鮮やかで美しく感じた。
(いや、私はいったい何を……国政の為、大臣達に言われ妃達を娶るのは致し方無かったとはいえ、私にはメリダしかいないはずだろう……血迷ったか)
雑念を追い払い、ローレンスはイザベラに向き直る。
「……どういう意味だ?」
「私の品格維持費や、その他諸々はナイアードからきちんと有り余る程に援助されている筈ですが、使用人の人数が一番少ないのは皇后宮です。何をするにも『なぜか』予算がないと皇帝陛下がお断りになるので、私の生活は必要最低限以上は私財で賄っていますのよ?」
ローレンスは驚愕した。
ナイアードから援助された皇后宮へ宛てる費用は毎月きちんと皇后に使われるように指示していたし、余れば皇后の手に渡るように言っていたのだ。
それに……
「私の指示ではない。記帳された帳簿も毎度きちんと確認している」
今度は、イザベラが驚愕する番であった。
ローレンスが嘘を言っているようには見えない。
「では、お金だけが消えていると?」
ナイアードが援助を断った訳ではないのは確実であった。
兄からの手紙にはライネル帝国ではなく、ナイアードがイザベラの生活資金を援助する理由が確かに書いてあったからだ。
イザベラの現状を手紙と噂によって知ったナイアードの王、もといイザベラの父は極度のブラコンであるイザベラの兄と共にライネルへ抗議する事を考えたが、無闇に行動をしてはイザベラの立場を悪くしてしまう可能性もあるのではないかと考え、『ナイアードはイザベラを手放したつもりはない』という意思表示のつもりでイザベラの品格維持費と生活費の全額援助を申し出たという話であった。
イザベラが残してきた幾つかの事業が妹達に引き継がれ、いまだに利益を上げている事に加えて、そもそもナイアードはこの程度で傾きはしないとまで書いてあった。
(それに、いつでも帰って来いとも……)
「調査しよう。……本当に申し訳なかった」
「特に不自由はしておりませんが、これでは祖国からの気持ちを踏み躙る事になりますので。許可を頂けるなら私が調査致します」
「いや……こちらで責任を持って調査しよう」
「……」
「不服か?」
「ええ、どのように陛下を信頼すればいいのかと」
「……っ、では皇后にも調査の指導権を与える」
「感謝致します。では……、……?」
中々その場を動こうとしないローレンスを疑問に思い首を傾げると、バツが悪そうに視線を彷徨わせる。
「いや、お茶には誘ってくれぬのかと……」
「……? そのような仲ではないでしょう。メリダ妃が待っている筈です。お戻り下さい陛下」
「だが……」
「このような格好ですし、今日は下がらせて頂きますが、明日また参りますのでお話はまた明日」
「皇后……っ!」
ローレンスは閉められた扉を捨て犬のように見つめてから、髪をくしゃりと崩し踵を返す。
若き皇帝にとって、始まりは信頼できる者などいないと思っていた王宮だった。
しばらく王座にいる内に確かな基盤を作れていると思っていたが、改めて身の回りの者達の腹の中を見極める必要がありそうだ。
不慣れな政治を教わった老いぼれ達は、心から信頼していたわけではなかったが、国を想う気持ちは本物だと信じていた。
初めて目にした、妃達から皇后への悪意と、思っていたものとは違う皇后イザベラの対応。
まるで自分だけが何かを見落としている気さえした。
(さっきのメリダは……イザベラよりも彼女の方が……)
皇帝が去った部屋で、苛立ちを隠せないと言うようにメリダがグラスを払い落とす。びくりと肩を揺らす妃達と、スッと目を背ける妃、メリダはそれぞれの反応を確認してから深呼吸して、彼女達を見渡した。
「サラ、片付けておいてくれる?」
我関せずを決めこんでいるテリーヌ以外の妃達にメリダが問いかける。
「私に付いてくる者は? 貴女達が受けている恩恵は計り知れないはずよ」
事実、他の妃達は、なるべく安全に金銭的、権力面での恩恵を受けつつ皇后の座を狙う為に、メリダの味方でいる必要があった。
メリダはローレンスの初恋の女性であり、彼が精神的に絶対的な信頼を寄せる心の支えといってもいい存在だと自負している。
それを上手く利用し、ローレンスの心を癒すのではなく、不安定で人間不信な彼のままでいさせて自分だけが彼の味方だと思い込ませ、まだ未熟だった頃から彼を思うがままにしてきた。
側から見れば、彼女は彼の寵愛を一心に受ける影の皇后であり、イザベラはただ面倒な公務や外交をこなすだけの愛されない便利な皇后であった。
「わ、私……メリダ様に皇后の座をお渡ししたい、です……」
サラがそう言うのは家のためだ。メリダが皇后になる事は身分的にありえない話だが、メリダに対し執着と依存を見せ、それを恋だと疑わないローレンスに対して、目を覚まさせることは出来ないと諦めていた。
であれば下手に逆らって家ごと潰されるよりも、メリダの腰巾着となってせめて家門の名誉を守り、側妃のまま大人しく生きる方がマシだった。
キャロライドとフィージアも、「あなたに付くわ」と返事をしたが、彼女達に関してはとにかく強大なナイアードの姫であるイザベラを排除する力が必要だったからだ。
(メリダは手強いし、皇后と共倒れしてくれればいいわ)
(一時休戦ね。メリダは元より皇帝の恋人、今はまだ勝ち目がないもの)
そうして、彼女達は一時結託して皇后を失脚させるべく組んだのだが、メリダは全く彼女達を尊重するつもりなど無かった。
(王妃となり、この国を思うままに動かす。その為に危険な賭けでローレンスを操ってきたのだから。惚れてくれたのが幸いだったわ。ローレンス、あなたを馬鹿に育てるのは大変だったのよ……早く私を引っ張り上げて! その為にはあの目障りな女とこのクズ達を消さないとね)
各々の思惑が渦巻く中、皇帝が戻って来る。
「遅くなった」
物思いに耽った表情で戻ったローレンスに、メリダが巻き付くように引っ付いた。
「陛下……っ、待っていましたのよ?」
そんなメリダに続いて皆が「陛下、お待ちしておりました」と挨拶をする。まるでメリダを慕うかのように……
先程初めて目にした噂とは真逆の光景に違和感を覚えていたローレンスだったが、このメリダを持ち上げるような皆の態度に更なる違和感を覚える。
今まで妃達や妃達の使用人たちから聞いていたイザベラの噂、横暴で傲慢な行いをして他の妃を従える悪女は、先程からメリダのことに思えて仕方ない。
「……皇后は、本当にお前達を虐げているのか?」
「えっ……?」
「私にはお前達皆が結託し、皇后を陥れたようにも見えた。メリダ、お前は私に嘘をつかないだろう?」
皇帝の威厳の隙間から垣間見える、小鳥の雛が母親を見るような視線。
彼女は密かに口元だけをニヤリと歪ませて、ローレンスの頬に手を伸ばし、優しく撫でた。
「若い妃を娶る事に賛成したのは私でしょう? 嘘をつくはずがありませんわ。今日は皆、皇后の姿を久々に見て気が立っていたのでしょう」
「……そうか」
「ええ、そうよ」
内心では納得がいかないローレンスが手に取るように分かるメリダは、ほっとして安心したように息を吐いた他の妃達をひと睨みし、ローレンスを座らせて自分はその膝に乗った。
彼の許可無く彼に触れられる者はメリダしかおらず、まるで格の違いを見せつけるように他の妃達に世話をさせ、自分はローレンスの膝で皇后にでもなったかのように皆に指示ばかりしていた。
ローレンスが完璧にメリダに惚れていると自負している彼女の行動は段々と大胆になって行き、ローレンスを信じさせ甘やかそうとしたこの日も例外なく始終横柄な態度が滲んでいる。
結果、ローレンスの違和感は消えない。
そしてメリダは、長年そうだったように、メリダ自身を無条件に信じているはずのローレンスの僅かな悩みと違和感を敏感に感じ取った。
(あの皇后……ローレンスに何したの? ローレンス、貴女は盲目的に私を愛し、私だけを信頼し、馬鹿でいなければならないのよ、私のために)
ローレンスを抱きしめる肩越しに見せた彼女のにんまりとした笑顔に、他の妃達は恐怖を覚える。
唯一それが見えていないローレンスは、ただ一人思考に沈む。
今までイザベラとの接触を控えてきたが、唐突にイザベラとの接触が増えて会話を交わしてみて、イザベラがよく目に入るようになった。
今回の中央宮でのメリダの言動と妃達の雰囲気を感じたローレンスは、確信こそ無いが、メリダが自分に嘘をついているような気がしていた。
メリダの変わらぬ体温の中、メリダの願う気持ちとは裏腹に、感じている違和感を確かめようと決心する。
(メリダの助言もあり、老ぼれ達の希望通りの側妃達を娶ったが……政情は整ったとはいえ、前々から不自然だと思っていた。物わかりのいい女性だと感心していたが、私を心から愛しているのなら自分だけを愛して欲しいと考えるはずではないのか……まさか、何かあるのか……?)
それぞれの思考の中、きっとこの閉ざされた皇宮でしがらみなく自由に振る舞える者は彼女しかいないだろうと二人はふと思い浮かべる。
(やはり、皇后と話さなくては)
(やっぱり皇后を潰しとかないと)
日が落ち、他の妃達も自室へと戻ったようだと報告を受けて、イザベラも寝衣の簡素なドレスに着替えてミアに淹れてもらったナイアードから仕入れたお茶でゆったりとしていた。
(これ、キリアンも好きだったわね)
「偶然に上手く下がれたけれど、このまま何も起きずにいて欲しいわね」
「そうですね。私も細心の注意を払いますので、本日はゆっくりお休み下さい」
暫くすると、リーナが少し気まずそうにイザベラに客人の知らせをした。
「イザベラ様……皇帝陛下がお見えです」
イザベラは額に片手を置いて深くため息をつくと、その身を整える事もなく、無粋な夫に対応した。
「陛下……このような夜分にどうされましたか?」
「その、皇后……少し話をしたいんだが、入れてはくれないか?」
(何かしら? 初日だから一応皇后の所へ来たということかしら)
「私は陛下と閨を共にする仲ではありませんが……他の妃ではなくあえて私をお望みでしょうか?」
イザベラは今、黒のレースとシルクを上品に使ったキャミソールの簡素なドレスに同じ素材のガウンを羽織っている。白い肌と真っ直ぐにさらりと下されたエメラルドグリーンの髪は幻想的だ。
ローレンスはそんな彼女に少し緊張した様子で言葉を詰まらせた後に絞り出すように言う。
「邪な理由は無い、皇后と少し話をすればちゃんと自室へと戻ると約束する」
それだけを言うのが精一杯で、なぜか切羽詰まったようにも見える皇帝の姿に、ただ首を縦に振ってミアに視線をやると、すぐにお茶の準備が始まった。
(仮にも夫だし、無碍にはできないわね。来た理由があるはず)
「……いいのか?」
「では、これは誰の分のお茶を用意しているのですか? おかけになって」
呆れたように少し笑ったイザベラに安心した表情をしたローレンスは、ぽつり、ぽつりと話し始めた。
「私は、皇后への噂を疑う事なく信じていた。その噂を口にするものが一人ではなかったからだ。だが、よく考えてみれば何故かそなたはいつも一人で、王宮の者達と対峙し多勢でそなたを敵視している」
「不自然ですが、いつものことです」
「……陥れるならば、一人きりのそなたより皆がそなたを陥れる方が簡単だというのに、私はそなたが傲慢に振る舞っていると信じ目を向けた事もなかった……」
「それは、謝罪と受け取っても宜しいのですか?」
「……正直に言うとまだ誰を信じていいのか分からないのだ。そなたも、メリダも、あの老ぼれ共も……」
「見たものを信じればよいのです。貴方は目を閉じているも同然。例えば……辛い過去や辛い境遇があっても、私達はそれを言い訳にできる立場にありません。今、私もそうであるように」
ローレンスは驚いた。メリダとイザベラとではローレンスに対してかける言葉が百八十度違ったからだ。
『ローレンス、貴方は辛い事ばかりだったわ。時には目を塞ぎ、耳を塞ぎ、身を守る事も大切よ? 貴方はこの国にとって大切な存在だから。私にとってもね」
『私だけを信じてローレンス、私たちはずっと二人で生きてきたわ」
メリダの言葉が頭の中に浮かぶ。
果たしてどちらが正しいのか、今ここで答えを出すには目の前の皇后を知らなすぎた。ただ、長い間視界を塞いでいた何らかの暗示から解放されたような感覚がある。
「陛下、もっと沢山の人を見て意見を聞き、広い視野で貴方なりの意見を持って人々を導いて下さい。貴方が窮屈だと感じるのならば、それは自らが何かに囚われているのです。自分を信じて」
「そなたではなく?」
「信じられる程に、私の事をご存知ないでしょう」
ふっと笑ったイザベラは、ふとローレンスを見て思う。
戦場ではとても強い人だったと、冷酷な人だと聞いていた。
だけど、目の前の彼はどうだ?
深く傷つき、愛した人をただひたすら盲目的に信じるただの青年であり、なんやかんやと他の妃達に対してもそれなりに丁寧に接していた。
思えば、使用人達にも、国民にも優しい彼は、不器用で居心地が悪そうにしながらも、結局は人に優しくしてしまう彼を見てきた。
今までの所業を許す気はないが、それらを見ていたのに傲慢で意地の悪い男だと色眼鏡で見て来た自分にも非はある。
(優しすぎるのね。戦場では立っていても敵は殺しに向かってくるから、生きる為にやるべき事が決まっているけれど、国政となると違う。皆が彼を慕う顔で優しく擦り寄って来る。好意を疑えない人なのかも)
イザベラは、短く息を吐き眉を顰めて俯いているローレンスに諦めたように言葉をかける。
「今日は寝て行かれては? 私にはあの大きなソファがありますので」
そう投げかけて先にソファで寝ころんでしまった。
「え、ちょっと待っ……皇后!」
「お休みなさいませ」
そう言ってしばらくすると静かに熟睡しているイザベラをベッドに運び、誤解を招かぬようクッションでローレンスとイザベラの間に防波堤を作ってから、彼も眠った。
意外にもローレンスは久々に深い眠りにつくことが出来、翌朝イザベラの疑うような目線に必死で弁解することになる。
実際のところ、イザベラは抱き上げられたときに起きており、日頃の恨みの意趣返しだと悪戯っぽく笑っていたのは、侍女二人だけが知る。
翌朝、皇帝の部屋が開放されると、微妙な距離感ではあるがローレンスの隣に座る皇后を見て、他の妃達は顔を真っ青にした。
「おはようございます、陛下」
皆が頭を下げると、妃の代表としてメリダが挨拶を述べる。
その表情は穏やかに見えるが内心は憤っていた。
(この女、どうやってローレンスに取り入った?)
妃達は、咄嗟に脳内でメリダから皇后側に乗り換えるべきか? と頭を悩ませたが、何かの気まぐれかもしれないととりあえずはメリダ派の姿勢を崩さずに様子を見る者が全員であった。
「あぁ、おはようメリダ。それと我が妃達よ。だが挨拶が違う、皇帝の側妃として正しいマナーで挨拶をしろ」
メリダの瞳の奥に怒りが宿るのを全員が感じる。
134
あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

夫が妹を第二夫人に迎えたので、英雄の妻の座を捨てます。
Nao*
恋愛
夫が英雄の称号を授かり、私は英雄の妻となった。
そして英雄は、何でも一つ願いを叶える事が出来る。
そんな夫が願ったのは、私の妹を第二夫人に迎えると言う信じられないものだった。
これまで夫の為に祈りを捧げて来たと言うのに、私は彼に手酷く裏切られたのだ──。
(1万字以上と少し長いので、短編集とは別にしてあります。)

婚約者を想うのをやめました
かぐや
恋愛
女性を侍らしてばかりの婚約者に私は宣言した。
「もうあなたを愛するのをやめますので、どうぞご自由に」
最初は婚約者も頷くが、彼女が自分の側にいることがなくなってから初めて色々なことに気づき始める。
*書籍化しました。応援してくださった読者様、ありがとうございます。

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?
冬馬亮
恋愛
公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。
オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。
だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。
その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・
「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」
「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

【完結】20年後の真実
ゴールデンフィッシュメダル
恋愛
公爵令息のマリウスがが婚約者タチアナに婚約破棄を言い渡した。
マリウスは子爵令嬢のゾフィーとの恋に溺れ、婚約者を蔑ろにしていた。
それから20年。
マリウスはゾフィーと結婚し、タチアナは伯爵夫人となっていた。
そして、娘の恋愛を機にマリウスは婚約破棄騒動の真実を知る。
おじさんが昔を思い出しながらもだもだするだけのお話です。
全4話書き上げ済み。

側妃は捨てられましたので
なか
恋愛
「この国に側妃など要らないのではないか?」
現王、ランドルフが呟いた言葉。
周囲の人間は内心に怒りを抱きつつ、聞き耳を立てる。
ランドルフは、彼のために人生を捧げて王妃となったクリスティーナ妃を側妃に変え。
別の女性を正妃として迎え入れた。
裏切りに近い行為は彼女の心を確かに傷付け、癒えてもいない内に廃妃にすると宣言したのだ。
あまりの横暴、人道を無視した非道な行い。
だが、彼を止める事は誰にも出来ず。
廃妃となった事実を知らされたクリスティーナは、涙で瞳を潤ませながら「分かりました」とだけ答えた。
王妃として教育を受けて、側妃にされ
廃妃となった彼女。
その半生をランドルフのために捧げ、彼のために献身した事実さえも軽んじられる。
実の両親さえ……彼女を慰めてくれずに『捨てられた女性に価値はない』と非難した。
それらの行為に……彼女の心が吹っ切れた。
屋敷を飛び出し、一人で生きていく事を選択した。
ただコソコソと身を隠すつもりはない。
私を軽んじて。
捨てた彼らに自身の価値を示すため。
捨てられたのは、どちらか……。
後悔するのはどちらかを示すために。

断腸の思いで王家に差し出した孫娘が婚約破棄されて帰ってきた
兎屋亀吉
恋愛
ある日王家主催のパーティに行くといって出かけた孫娘のエリカが泣きながら帰ってきた。買ったばかりのドレスは真っ赤なワインで汚され、左頬は腫れていた。話を聞くと王子に婚約を破棄され、取り巻きたちに酷いことをされたという。許せん。戦じゃ。この命燃え尽きようとも、必ずや王家を滅ぼしてみせようぞ。

婚約破棄された令嬢が記憶を消され、それを望んだ王子は後悔することになりました
kieiku
恋愛
「では、記憶消去の魔法を執行します」
王子に婚約破棄された公爵令嬢は、王子妃教育の知識を消し去るため、10歳以降の記憶を奪われることになった。そして記憶を失い、退行した令嬢の言葉が王子を後悔に突き落とす。
過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている
と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
番外編を閲覧することが出来ません。
過去1ヶ月以内にレジーナの小説・漫画を1話以上レンタルしている
と、レジーナのすべての番外編を読むことができます。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。