42 / 1,289
第3話
(12)
しおりを挟む
「――総和会が、お前に目をつけた。仕事を依頼してきたときに、嫌な予感はしたんだ。自由に使える医者を抱え込めるなんて、そうないからな。しかも、完全に長嶺組の身内というわけじゃない。話があると言って、にこにこと愛想よくうちの事務所に来たと思ったら、総和会で先生を預からせてくれないかと言ってきたんだ」
三田村の話では、総和会と所属している組の間では、物品や人材を融通し合うと言っていた。しかし、賢吾の言い方は、融通というより徴収だ。召し上げるという千尋の表現は正しかったのかもしれない。
「無碍に断ることができないから、俺たちの見ている前で、加入書に署名させることになったんだ。総和会の言い分としては、一般人を脅して仕事をさせているんなら、規約違反として、総和会で先生の身柄を保護するってな。お前が自分の意思で署名するなら、引き下がるかと思ったが――」
和彦は思い切り逆上して拒否した挙げ句、逃げ出した。
うろたえる和彦の唇を、賢吾は指で何度も撫でてくる。
「少しばかり事態がややこしくなった。どう責任を取ってくれるんだ。先生」
恫喝するような口調とは裏腹に、賢吾は笑っていた。
ようやく唇から指が離され、和彦は口を開くことができる。
「……自分の理屈ばかり言うな。もしかすると総和会のほうが、長嶺組より居心地がいいと、ぼくが感じるかもしれないだろ」
「ヤクザが言うことだから信用できない、か?」
和彦は、今言ったようなことを本気で思っているわけではない。これは、駆け引きだ。総和会などというわけのわからない組織に目をつけられて怖いから守ってくれと、面と向かって賢吾に言えるはずがない。なんといってもこの男も、筋金入りのヤクザなのだ。
だが少なくとも和彦は、賢吾を知っている。肌や筋肉の感触、体を這い回る唇や舌の感触を。おぞましいのに艶かしい刺青も。
気を悪くしたふうもなく賢吾は頷いた。
「――これから行くところを見てから、答えを出せばいい。長嶺組と総和会、どちらがより、自分を満たしてくれるかな」
賢吾の提案に、ぎこちなく和彦も頷いた。
大通りから外れて数分ほど走った車が停まったのは、レンガ積み外壁の六階建てビルの前だった。
車から降りた和彦は、一階の雑貨屋を見てから、視線を上げていく。それぞれのフロアに入っている会社の看板が出ているが、一番上の階の看板だけは空白だった。
和彦が傍らに立つ賢吾を見ると、ニヤリと笑いかけられた。
「中に入るぞ」
促されるまま、もう一台の車に乗っていた組員たちに先導される形でビルに入り、エレベーターに乗り込む。組の人間以外の目がないということもあり、当然のように賢吾に肩を抱かれる。
不思議なもので、昨日は気が障った行為が、今は素直に受け入れられた。それどころか――。
知らず知らずのうちに頬の辺りが熱くなり、和彦は手荒く擦る。
エレベーターを六階で下りると、さほど広くないエレベーターホールは電気がついていないせいもあり少し薄暗かったが、廊下に出ると、外からの陽射しをたっぷり取り入れているため明るかった。ビルの前を歩道と車道が通っているが、遮音は万全のようだ。
廊下の先にホールがあり、そのホールに面して六つのドアがあった。かつて入っていたテナントの名残りか、ドアにはプレートが貼ってあった形跡がある。
「前まではこのフロアに、小さな会社が二つ、三つ入っていたらしい。会社として考えると、部屋の一つ一つは手狭だが、このフロア全体をクリニックにすると、広さはちょうどいい。診察室に手術室、安静室に事務室――。このホールは待合室でいいな。この廊下の奥にもう一部屋あるが、そこを寝泊りできる部屋にするのもいい」
和彦はホールの中心に立ち、ゆっくりと周囲を見回す。いままで賢吾とともに物件を見てきたが、こんないい場所を和彦にいままで秘密にしていたのだ。多分、和彦が一目で気に入ると確信があったのだろう。実際、その通りだった。
「美容外科の看板を出す以上、いい加減なクリニックにはできないからな。ここは、目くらましのための舞台のようなものだ。若くてハンサムな先生が切り盛りして、せいぜいいい評判を立ててくれ。ヤクザと繋がっているなんて、一切匂わせないぐらいのな」
「……こちらが努力しても、一目見て怪しい人間が頻繁に出入りしていたら、すぐに感づかれるんじゃないか」
「このビルには非常階段が二つある。他の階は、その非常階段に通じるドアが塞がれていて使えない。だが、この六階からは――」
「呆れた。用意周到すぎるな」
「ヤクザだからな」
賢吾なりの冗談なのだろうかと、思わず和彦はまじまじと見つめてしまう。そこに、このホールにやってくる足音が聞こえてきた。三田村だ。ビルの隣の駐車場に車を停めてから、上がってきたのだ。
三田村がやってくるのを待っていたように、急に賢吾がドアの一つに歩み寄り、ポケットから取り出した鍵で開ける。手招きされるまま和彦が歩み寄ると、肩を抱かれて部屋に足を踏み入れた。
正面に大きな窓があり、しかも景色が開けている。六階ということもあり、当然目の前には、林立する建物の一群があると思っていた和彦は意表を突かれた。
「窓の外を見ていろ」
賢吾に背を押され、言われるまま窓に近づいた和彦は、ビルの裏に川が流れていることを知った。水の流れは緩やかで、子供が遊びやすそうな川原が広がっている。すでに春の柔らかさを失った強い陽射しが反射して、水がキラキラと輝いていた。
「――初めて見たな」
隣に立った賢吾がふいに洩らした言葉に、つい景色に見入っていた和彦は我に返る。ちらりと隣を見ると、賢吾は口元に笑みを浮かべて、やはり和彦を見ていた。
「何が……」
「先生が嬉しそうに笑っている顔。仏頂面と、イクときのイイ顔しか見たことがなかったからな」
恥ずかしいことを言うなと怒鳴ろうとした和彦だが、突然、賢吾が動き、体を大きな窓に押さえつけられた。威圧的に迫ってくる賢吾の姿に、言おうとした言葉は空しく口中で消える。
三田村の話では、総和会と所属している組の間では、物品や人材を融通し合うと言っていた。しかし、賢吾の言い方は、融通というより徴収だ。召し上げるという千尋の表現は正しかったのかもしれない。
「無碍に断ることができないから、俺たちの見ている前で、加入書に署名させることになったんだ。総和会の言い分としては、一般人を脅して仕事をさせているんなら、規約違反として、総和会で先生の身柄を保護するってな。お前が自分の意思で署名するなら、引き下がるかと思ったが――」
和彦は思い切り逆上して拒否した挙げ句、逃げ出した。
うろたえる和彦の唇を、賢吾は指で何度も撫でてくる。
「少しばかり事態がややこしくなった。どう責任を取ってくれるんだ。先生」
恫喝するような口調とは裏腹に、賢吾は笑っていた。
ようやく唇から指が離され、和彦は口を開くことができる。
「……自分の理屈ばかり言うな。もしかすると総和会のほうが、長嶺組より居心地がいいと、ぼくが感じるかもしれないだろ」
「ヤクザが言うことだから信用できない、か?」
和彦は、今言ったようなことを本気で思っているわけではない。これは、駆け引きだ。総和会などというわけのわからない組織に目をつけられて怖いから守ってくれと、面と向かって賢吾に言えるはずがない。なんといってもこの男も、筋金入りのヤクザなのだ。
だが少なくとも和彦は、賢吾を知っている。肌や筋肉の感触、体を這い回る唇や舌の感触を。おぞましいのに艶かしい刺青も。
気を悪くしたふうもなく賢吾は頷いた。
「――これから行くところを見てから、答えを出せばいい。長嶺組と総和会、どちらがより、自分を満たしてくれるかな」
賢吾の提案に、ぎこちなく和彦も頷いた。
大通りから外れて数分ほど走った車が停まったのは、レンガ積み外壁の六階建てビルの前だった。
車から降りた和彦は、一階の雑貨屋を見てから、視線を上げていく。それぞれのフロアに入っている会社の看板が出ているが、一番上の階の看板だけは空白だった。
和彦が傍らに立つ賢吾を見ると、ニヤリと笑いかけられた。
「中に入るぞ」
促されるまま、もう一台の車に乗っていた組員たちに先導される形でビルに入り、エレベーターに乗り込む。組の人間以外の目がないということもあり、当然のように賢吾に肩を抱かれる。
不思議なもので、昨日は気が障った行為が、今は素直に受け入れられた。それどころか――。
知らず知らずのうちに頬の辺りが熱くなり、和彦は手荒く擦る。
エレベーターを六階で下りると、さほど広くないエレベーターホールは電気がついていないせいもあり少し薄暗かったが、廊下に出ると、外からの陽射しをたっぷり取り入れているため明るかった。ビルの前を歩道と車道が通っているが、遮音は万全のようだ。
廊下の先にホールがあり、そのホールに面して六つのドアがあった。かつて入っていたテナントの名残りか、ドアにはプレートが貼ってあった形跡がある。
「前まではこのフロアに、小さな会社が二つ、三つ入っていたらしい。会社として考えると、部屋の一つ一つは手狭だが、このフロア全体をクリニックにすると、広さはちょうどいい。診察室に手術室、安静室に事務室――。このホールは待合室でいいな。この廊下の奥にもう一部屋あるが、そこを寝泊りできる部屋にするのもいい」
和彦はホールの中心に立ち、ゆっくりと周囲を見回す。いままで賢吾とともに物件を見てきたが、こんないい場所を和彦にいままで秘密にしていたのだ。多分、和彦が一目で気に入ると確信があったのだろう。実際、その通りだった。
「美容外科の看板を出す以上、いい加減なクリニックにはできないからな。ここは、目くらましのための舞台のようなものだ。若くてハンサムな先生が切り盛りして、せいぜいいい評判を立ててくれ。ヤクザと繋がっているなんて、一切匂わせないぐらいのな」
「……こちらが努力しても、一目見て怪しい人間が頻繁に出入りしていたら、すぐに感づかれるんじゃないか」
「このビルには非常階段が二つある。他の階は、その非常階段に通じるドアが塞がれていて使えない。だが、この六階からは――」
「呆れた。用意周到すぎるな」
「ヤクザだからな」
賢吾なりの冗談なのだろうかと、思わず和彦はまじまじと見つめてしまう。そこに、このホールにやってくる足音が聞こえてきた。三田村だ。ビルの隣の駐車場に車を停めてから、上がってきたのだ。
三田村がやってくるのを待っていたように、急に賢吾がドアの一つに歩み寄り、ポケットから取り出した鍵で開ける。手招きされるまま和彦が歩み寄ると、肩を抱かれて部屋に足を踏み入れた。
正面に大きな窓があり、しかも景色が開けている。六階ということもあり、当然目の前には、林立する建物の一群があると思っていた和彦は意表を突かれた。
「窓の外を見ていろ」
賢吾に背を押され、言われるまま窓に近づいた和彦は、ビルの裏に川が流れていることを知った。水の流れは緩やかで、子供が遊びやすそうな川原が広がっている。すでに春の柔らかさを失った強い陽射しが反射して、水がキラキラと輝いていた。
「――初めて見たな」
隣に立った賢吾がふいに洩らした言葉に、つい景色に見入っていた和彦は我に返る。ちらりと隣を見ると、賢吾は口元に笑みを浮かべて、やはり和彦を見ていた。
「何が……」
「先生が嬉しそうに笑っている顔。仏頂面と、イクときのイイ顔しか見たことがなかったからな」
恥ずかしいことを言うなと怒鳴ろうとした和彦だが、突然、賢吾が動き、体を大きな窓に押さえつけられた。威圧的に迫ってくる賢吾の姿に、言おうとした言葉は空しく口中で消える。
130
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
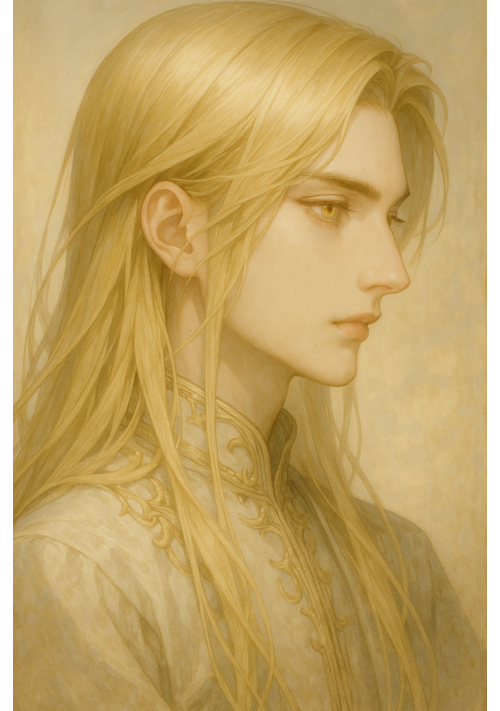
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。


好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















