140 / 1,289
第8話
(12)
しおりを挟む
自分のことのように顔をしかめる中嶋は、とてもではないが、野心的なヤクザには見えない。ただ、この世界に足を踏み入れてわかったが、ヤクザであることを匂わせないヤクザのほうが、実は性質が悪い。
その一人が中嶋なのだが、少なくとも秦の件で見せる表情は、本心だろう。それだけ、あの男――秦を本気で心配しているのだ。頭の切れる中嶋が、明らかに厄介事を背負っている秦をまだ自分の部屋に匿い、世話を焼く理由としては、それしか思いつかない。
「あれだけの内出血だ。さぞかし派手な痣になってるだろうな」
「ええ。男ぶりが台無しだと嘆いてましたよ」
「そんなことが言える余裕があるなら、大丈夫そうだ」
和彦がこう言うと、途端に中嶋は表情を曇らせた。
「一応体を起こせるようにはなりましたが、息をするのもつらそうです。胸が痛いと言って」
「まあ、肋骨が折れているんだからな……」
ここで二人の間に、不自然な沈黙が流れる。肝心な部分をはぐらかして会話することに、どうしても無理が生じてしまうのだ。
組の事情にも立ち入らないし、ヤクザ個人やそれに近い人間の事情にも立ち入らない姿勢を貫きたい和彦だが、つい二日前に賢吾に言われた言葉が脳裏を過る。
いくら和彦が知らないと背を向けたところで、組の事情はどんどんその背にのしかかっていく。和彦が関わった人間の事情もまた、そうやって背にのしかかるのだ。これはもう、和彦の意思だけではどうにもならない。
汗で濡れた髪を手持ち無沙汰に拭きながら、とうとう和彦は切り出した。
「――……君は、何か感じているんだろう。彼が何かしらトラブルに巻き込まれていると。あの怪我は、酔っ払いに絡まれたとか、そういう生易しいものじゃない。痛めつけるという意図を持ったうえでの、リンチの跡だ」
「ええ、まあ。一応、暴力沙汰には慣れているので……」
困ったような中嶋を見ていると、別に責め立てているわけではないのに、居心地が悪くなってくる。中嶋としては、和彦に何を言われても甘んじて受け入れるつもりなのかもしれない。
「秦さんからは、何か説明してもらったのか?」
「……それとなく、仄めかすようなことは。ただ、本名を教えてくれないように、秦さんはどこからどこまでが本当で、ウソなのか、境目がわからないような話し方をするんです。もしかすると、すべてがウソなのかもしれない。もちろん、その反対もありうる」
何を教えてもらったのか、危うく和彦は無防備に尋ねそうになったが、このとき中嶋がようやく見せた、いかにも筋者らしい鋭い笑みに息を呑む。
「俺は、ヤクザですよ。単なるお人好しじゃない。確かに秦さんに恩はあるし、世話にもなってます。だけど、純粋に善意だけで助けたわけじゃないんです。……秦さんからは、金の匂いがする。しかも、真っ当な手段で得る金じゃない。秦さんを襲った連中も、その辺りに関係していそうなんです」
「だから……?」
「秦さんは、俺の手札になるかもしれない。危険な手札ですけどね。だからこそ切り札にもなりうる」
「……総和会で成り上がるために、か」
冷めた口調で和彦が言うと、中嶋は軽く肩をすくめる。
「正直俺は、自分が元にいた組に戻る気はないんです。戻ったところで、俺より使えない人間が大きな顔して居座っている。だけど総和会は生え抜きの人間揃いで、学ぶべきことが多い。だからこそ、総和会での自分の居場所を確保しないといけないんです」
普通の青年の顔をしていても、中嶋は内にたっぷりの野心を秘めたヤクザだ。そんなことはとっくにわかっていたことだ。ただ和彦は、ヤクザの言動を頭から疑ってかかるようにしていたせいか、中嶋の演技を見抜いていた。
「悪党ぶらなくても、君はヤクザのくせに優しい、なんて恥ずかしいことは言わないよ」
目を丸くした中嶋が、まじまじと和彦を見つめてくる。どんな表情を浮かべていいかわからない、といった様子は、とうていヤクザには見えない。
「君が野心家なのも、そのためには他人を利用することも厭わないのもわかる。だけど、彼に対しては、その気持ちがいくらか控えめになるんだろ。恩のあるなしじゃなく……自分たちは似た者同士だと思っているんじゃないか」
参ったな、と洩らした中嶋が苦笑を浮かべる。
「先生は、怖いですね」
「失敬な」
「――でも、甘い」
今度は和彦が目を丸くする番だった。中嶋は目の前で涼しげに笑う。したたかなヤクザの素顔が覗いて見えるようだ。
「今みたいな話を聞いたら、俺の頼みを断れないでしょう?」
「頼みって……」
「もう一度、秦さんを診察してください。一応、先生に言われた通りの手当ては続けていますが、不安なんです。もしこれで異変がないなら、もう無茶は言いません。だからあと一回だけ、お願いします」
テーブルに額を擦りつけるようにして中嶋が頭を下げる。その姿を見ながら和彦は、自分の迂闊さに歯噛みしたくなった。もう面倒事は嫌だと断りたいのに、中嶋が言った通り、断れない。打算だけではない中嶋と秦の奇妙な関係を知ると、和彦は非情に徹しきれないのだ。
聞こえよがしにため息をつき、ぼそりと答えた。
「――……これが最後だからな」
和彦の返事に、中嶋が顔を上げる。このとき一瞬見せたのは、心底安堵したような表情だった。こんな顔をされると、ますます断れない。
ただ、流されるばかりではいけないと、和彦はある条件を出した。
「ぼくは、長嶺組に不信感を抱かれるようなことはしたくない。極力悟られないよう動くが、もしバレて、何をしているのか聞かれたら、正直に答える。君のことも、秦さんのことも」
中嶋は厳しい表情で考え込んでから、頷いた。
「でも――」
「わかっている。ぼくだって、あれこれ追及されるのは嫌だ」
これで話は決まった。
一人で動けるのは夜しかないと和彦が告げると、一方の中嶋は、夜は総和会に詰めているということで、更衣室に移動してから合鍵を渡される。その合鍵を受け取ることに、和彦はためらいを覚えずにはいられなかった。また、秦と二人きりになってしまうのだ。
しかしいまさら嫌だとは言えず、結局、合鍵を受け取った。
その一人が中嶋なのだが、少なくとも秦の件で見せる表情は、本心だろう。それだけ、あの男――秦を本気で心配しているのだ。頭の切れる中嶋が、明らかに厄介事を背負っている秦をまだ自分の部屋に匿い、世話を焼く理由としては、それしか思いつかない。
「あれだけの内出血だ。さぞかし派手な痣になってるだろうな」
「ええ。男ぶりが台無しだと嘆いてましたよ」
「そんなことが言える余裕があるなら、大丈夫そうだ」
和彦がこう言うと、途端に中嶋は表情を曇らせた。
「一応体を起こせるようにはなりましたが、息をするのもつらそうです。胸が痛いと言って」
「まあ、肋骨が折れているんだからな……」
ここで二人の間に、不自然な沈黙が流れる。肝心な部分をはぐらかして会話することに、どうしても無理が生じてしまうのだ。
組の事情にも立ち入らないし、ヤクザ個人やそれに近い人間の事情にも立ち入らない姿勢を貫きたい和彦だが、つい二日前に賢吾に言われた言葉が脳裏を過る。
いくら和彦が知らないと背を向けたところで、組の事情はどんどんその背にのしかかっていく。和彦が関わった人間の事情もまた、そうやって背にのしかかるのだ。これはもう、和彦の意思だけではどうにもならない。
汗で濡れた髪を手持ち無沙汰に拭きながら、とうとう和彦は切り出した。
「――……君は、何か感じているんだろう。彼が何かしらトラブルに巻き込まれていると。あの怪我は、酔っ払いに絡まれたとか、そういう生易しいものじゃない。痛めつけるという意図を持ったうえでの、リンチの跡だ」
「ええ、まあ。一応、暴力沙汰には慣れているので……」
困ったような中嶋を見ていると、別に責め立てているわけではないのに、居心地が悪くなってくる。中嶋としては、和彦に何を言われても甘んじて受け入れるつもりなのかもしれない。
「秦さんからは、何か説明してもらったのか?」
「……それとなく、仄めかすようなことは。ただ、本名を教えてくれないように、秦さんはどこからどこまでが本当で、ウソなのか、境目がわからないような話し方をするんです。もしかすると、すべてがウソなのかもしれない。もちろん、その反対もありうる」
何を教えてもらったのか、危うく和彦は無防備に尋ねそうになったが、このとき中嶋がようやく見せた、いかにも筋者らしい鋭い笑みに息を呑む。
「俺は、ヤクザですよ。単なるお人好しじゃない。確かに秦さんに恩はあるし、世話にもなってます。だけど、純粋に善意だけで助けたわけじゃないんです。……秦さんからは、金の匂いがする。しかも、真っ当な手段で得る金じゃない。秦さんを襲った連中も、その辺りに関係していそうなんです」
「だから……?」
「秦さんは、俺の手札になるかもしれない。危険な手札ですけどね。だからこそ切り札にもなりうる」
「……総和会で成り上がるために、か」
冷めた口調で和彦が言うと、中嶋は軽く肩をすくめる。
「正直俺は、自分が元にいた組に戻る気はないんです。戻ったところで、俺より使えない人間が大きな顔して居座っている。だけど総和会は生え抜きの人間揃いで、学ぶべきことが多い。だからこそ、総和会での自分の居場所を確保しないといけないんです」
普通の青年の顔をしていても、中嶋は内にたっぷりの野心を秘めたヤクザだ。そんなことはとっくにわかっていたことだ。ただ和彦は、ヤクザの言動を頭から疑ってかかるようにしていたせいか、中嶋の演技を見抜いていた。
「悪党ぶらなくても、君はヤクザのくせに優しい、なんて恥ずかしいことは言わないよ」
目を丸くした中嶋が、まじまじと和彦を見つめてくる。どんな表情を浮かべていいかわからない、といった様子は、とうていヤクザには見えない。
「君が野心家なのも、そのためには他人を利用することも厭わないのもわかる。だけど、彼に対しては、その気持ちがいくらか控えめになるんだろ。恩のあるなしじゃなく……自分たちは似た者同士だと思っているんじゃないか」
参ったな、と洩らした中嶋が苦笑を浮かべる。
「先生は、怖いですね」
「失敬な」
「――でも、甘い」
今度は和彦が目を丸くする番だった。中嶋は目の前で涼しげに笑う。したたかなヤクザの素顔が覗いて見えるようだ。
「今みたいな話を聞いたら、俺の頼みを断れないでしょう?」
「頼みって……」
「もう一度、秦さんを診察してください。一応、先生に言われた通りの手当ては続けていますが、不安なんです。もしこれで異変がないなら、もう無茶は言いません。だからあと一回だけ、お願いします」
テーブルに額を擦りつけるようにして中嶋が頭を下げる。その姿を見ながら和彦は、自分の迂闊さに歯噛みしたくなった。もう面倒事は嫌だと断りたいのに、中嶋が言った通り、断れない。打算だけではない中嶋と秦の奇妙な関係を知ると、和彦は非情に徹しきれないのだ。
聞こえよがしにため息をつき、ぼそりと答えた。
「――……これが最後だからな」
和彦の返事に、中嶋が顔を上げる。このとき一瞬見せたのは、心底安堵したような表情だった。こんな顔をされると、ますます断れない。
ただ、流されるばかりではいけないと、和彦はある条件を出した。
「ぼくは、長嶺組に不信感を抱かれるようなことはしたくない。極力悟られないよう動くが、もしバレて、何をしているのか聞かれたら、正直に答える。君のことも、秦さんのことも」
中嶋は厳しい表情で考え込んでから、頷いた。
「でも――」
「わかっている。ぼくだって、あれこれ追及されるのは嫌だ」
これで話は決まった。
一人で動けるのは夜しかないと和彦が告げると、一方の中嶋は、夜は総和会に詰めているということで、更衣室に移動してから合鍵を渡される。その合鍵を受け取ることに、和彦はためらいを覚えずにはいられなかった。また、秦と二人きりになってしまうのだ。
しかしいまさら嫌だとは言えず、結局、合鍵を受け取った。
97
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
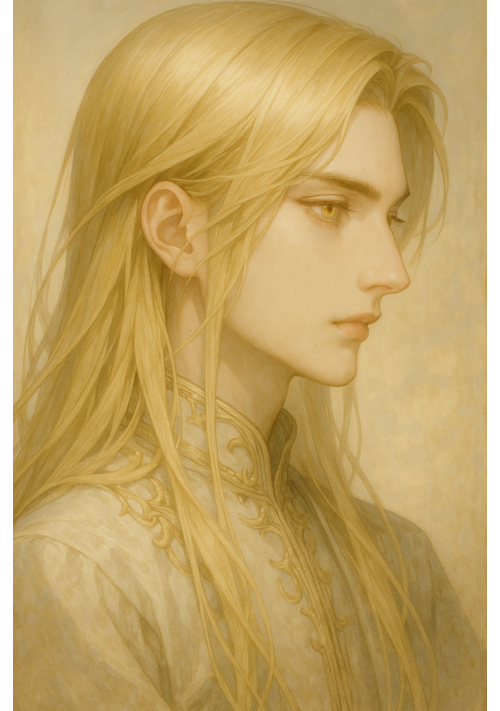
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。


好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















