392 / 1,289
第19話
(5)
しおりを挟む
「わたしが円満に、先生を連れ帰りますよ。先生が今現在、どんな環境で、どんな人間に囲まれて生活しているか、一切うかがわせずに」
「そうだ。いざというとき、ぼくを守ってくれるだけでいいなら、長嶺組の組員に護衛してもらえばいいんだ。だけど、ぼくが長嶺組の身内になっていると知られるわけにはいかない」
それでなくても、澤村には千尋と、英俊には三田村と一緒にいるところを見られている。その点、秦は表向きは青年実業家という肩書きを持ち、仮に素性を調べられたところで、裏での組やその関係者との繋がりの多さが、かえって長嶺組の存在を隠してくれる。
この計画で大丈夫だろうかと、頭の中でめまぐるしく自問を繰り返す和彦に、秦は芝居がかったように明るい声をかけてきた。
「そうだ、先生、中嶋も連れて行っていいですか? あいつこそ、見た目は普通の勤め人に見えて都合がいい」
何を企んでいるのかと、和彦が胡乱な目つきとなると、秦はヌケヌケとこう言った。
「先生の用心棒をしつつ、デート気分を味わおうかと思いまして」
「……正体不明の怪しい男には似合わない、爽やかな言葉だな」
「わたしだって、手探り状態なんですよ、中嶋との関係は。即物的な繋がりを求めている反面、それだけじゃいけないとも思っている。だからこそ、先生のしたたかでしなやかな存在感に、刺激を受けるんです。いい緩衝材であり、接着剤ですよ、先生は」
中嶋の首の付け根についていた赤い痕を思い出し、なぜか和彦のほうが気恥ずかしい気分になってくる。秦と中嶋の関係に、緩衝材や接着剤という言葉はともかく、和彦は搦め捕られ、惹かれている。純粋に、性的な興味を覚えているといってもいい。こういう経験は初めてで、手探り状態なのは和彦も同じだ。
「せっかくなので、わたしと中嶋で、先生へのプレゼントを用意しますよ」
秦の申し出に、和彦は苦笑しつつ首を横に振る。
「正直、誕生日を祝われるのは慣れてないから、いつもと同じように接してもらったほうがありがたい。……昔から、おめでとうと言われても、どういう顔をすればいいのかわからないんだ」
わずかに目を細めた秦は、寿司を口に運んだあと、ぽつりと洩らした。
「いかにも育ちのいい先生にも、いろいろと事情があるんですね」
「ぼく以上にいろいろと事情を背負っている男に言われると、重みがあるな」
秦は、小さく笑い声を洩らしただけで、何も言わなかった。
このとき和彦がふと気になったのは、秦が背負っている事情のいくつかを、中嶋に話しているのだろうかということだ。
寿司屋を出ると、コートの襟を直す秦に向けて和彦は、頭を下げる。
「忙しいだろうが、今日頼んだ件、よろしく頼む」
澤村と会う日時は、仕事帰りに気安く友人と会うという演出のために、二月四日の夕方を考えている。その日は火曜日だが、それ自体に意味はなく、仕事が休みで時間がある土日に、じっくりと腰を据えて話し合う状況を避けたかったのだ。
「先生から頼み事ごとをされて喜んでいるんですから、頭なんて下げないでください」
和彦は頭を上げると、そっと微笑みながら今度は礼を言う。
「今晩は、ありがとう。美味しかった」
「先生には、わたしの店選びを信用してもらっているようなので、気合いが入ります」
一瞬、そんなことを秦に話したことがあっただろうかと考えたが、次の瞬間には、ああ、と声を洩らす。和彦が中嶋に話した内容が、秦に伝わったのだ。
「中嶋が先生の部屋にお邪魔して、もてなしてもらったそうなので、今晩の食事はそのお礼です」
「……もてなしてもらったのは、むしろぼくのほうだと思うが……。しかし、中嶋くんの保護者みたいな口ぶりだ」
和彦が指摘すると、秦が微苦笑を浮かべる。その表情を見て漠然と、秦と中嶋は、本人たちなりのやり方で歩み寄り、確実に距離を縮めているのだと感じた。
頼みごとを引き受けてくれ、食事まで奢ってもらったうえに、最後にいいものを見られたかもしれない。抱えた厄介事が片付いたわけではないのだが、二人の仲の進展具合を感じて、和彦の気持ちは少しだけ柔らかくなっていた。
秦と並んで歩き出す。護衛の組員は先に店を出て、すでに車で待機している。
寿司を食べつつたっぷり話はしたので、いまさらもう、車までの短い距離を歩きながら話すことはない。
そもそも今日は少し話しすぎたと、和彦は顔を背けて小さく咳き込む。なんとなく、喉が痛かった。気遣いのできる男が、すかさず声をかけてくる。
「おや、風邪ですか?」
「いや、外の空気が乾燥しているから……」
「気をつけてください。誕生日だけでなく、バレンタインまで控えた大事な体ですから」
意味深な冗談と受け止めて、和彦が横目でじろりと見たとき、秦はコートのポケットから携帯電話を取り出していた。メールが届いたようだ。
秦が携帯電話の画面を見つめる。数秒の間を置いて、端麗な横顔を怜悧な表情が彩った。素性の怪しい食えない男の本性が、この表情から垣間見えそうだ。
すぐに携帯電話を閉じた秦が、何事もなかったように和彦を見て、表情を和らげた。
「仕事のメールです」
「……忙しそうだな」
「長嶺組の後ろ盾のおかげで、儲け話に事欠かなくなりました」
皮肉とも思えない秦の口ぶりに、和彦は慎重に問いかける。
「長嶺組からのメールなのか……?」
「――先生の旦那さんからです」
あまりにさらりと言われ、危うく聞き流しそうになった和彦だが、ハッと我に返って秦にきつい眼差しを向ける。悪びれることなく、秦は満足げな様子で携帯電話を振った。
「冗談です」
「命知らずだな……。ぼくはともかく、長嶺組組長のことをそんなふうに言えるなんて」
「わたしは一言も、長嶺組長のことだと言ってませんよ」
和彦は、秦の脇腹に拳を入れた。ただし、機嫌を損ねられても困るので、あくまで軽く。
「そうだ。いざというとき、ぼくを守ってくれるだけでいいなら、長嶺組の組員に護衛してもらえばいいんだ。だけど、ぼくが長嶺組の身内になっていると知られるわけにはいかない」
それでなくても、澤村には千尋と、英俊には三田村と一緒にいるところを見られている。その点、秦は表向きは青年実業家という肩書きを持ち、仮に素性を調べられたところで、裏での組やその関係者との繋がりの多さが、かえって長嶺組の存在を隠してくれる。
この計画で大丈夫だろうかと、頭の中でめまぐるしく自問を繰り返す和彦に、秦は芝居がかったように明るい声をかけてきた。
「そうだ、先生、中嶋も連れて行っていいですか? あいつこそ、見た目は普通の勤め人に見えて都合がいい」
何を企んでいるのかと、和彦が胡乱な目つきとなると、秦はヌケヌケとこう言った。
「先生の用心棒をしつつ、デート気分を味わおうかと思いまして」
「……正体不明の怪しい男には似合わない、爽やかな言葉だな」
「わたしだって、手探り状態なんですよ、中嶋との関係は。即物的な繋がりを求めている反面、それだけじゃいけないとも思っている。だからこそ、先生のしたたかでしなやかな存在感に、刺激を受けるんです。いい緩衝材であり、接着剤ですよ、先生は」
中嶋の首の付け根についていた赤い痕を思い出し、なぜか和彦のほうが気恥ずかしい気分になってくる。秦と中嶋の関係に、緩衝材や接着剤という言葉はともかく、和彦は搦め捕られ、惹かれている。純粋に、性的な興味を覚えているといってもいい。こういう経験は初めてで、手探り状態なのは和彦も同じだ。
「せっかくなので、わたしと中嶋で、先生へのプレゼントを用意しますよ」
秦の申し出に、和彦は苦笑しつつ首を横に振る。
「正直、誕生日を祝われるのは慣れてないから、いつもと同じように接してもらったほうがありがたい。……昔から、おめでとうと言われても、どういう顔をすればいいのかわからないんだ」
わずかに目を細めた秦は、寿司を口に運んだあと、ぽつりと洩らした。
「いかにも育ちのいい先生にも、いろいろと事情があるんですね」
「ぼく以上にいろいろと事情を背負っている男に言われると、重みがあるな」
秦は、小さく笑い声を洩らしただけで、何も言わなかった。
このとき和彦がふと気になったのは、秦が背負っている事情のいくつかを、中嶋に話しているのだろうかということだ。
寿司屋を出ると、コートの襟を直す秦に向けて和彦は、頭を下げる。
「忙しいだろうが、今日頼んだ件、よろしく頼む」
澤村と会う日時は、仕事帰りに気安く友人と会うという演出のために、二月四日の夕方を考えている。その日は火曜日だが、それ自体に意味はなく、仕事が休みで時間がある土日に、じっくりと腰を据えて話し合う状況を避けたかったのだ。
「先生から頼み事ごとをされて喜んでいるんですから、頭なんて下げないでください」
和彦は頭を上げると、そっと微笑みながら今度は礼を言う。
「今晩は、ありがとう。美味しかった」
「先生には、わたしの店選びを信用してもらっているようなので、気合いが入ります」
一瞬、そんなことを秦に話したことがあっただろうかと考えたが、次の瞬間には、ああ、と声を洩らす。和彦が中嶋に話した内容が、秦に伝わったのだ。
「中嶋が先生の部屋にお邪魔して、もてなしてもらったそうなので、今晩の食事はそのお礼です」
「……もてなしてもらったのは、むしろぼくのほうだと思うが……。しかし、中嶋くんの保護者みたいな口ぶりだ」
和彦が指摘すると、秦が微苦笑を浮かべる。その表情を見て漠然と、秦と中嶋は、本人たちなりのやり方で歩み寄り、確実に距離を縮めているのだと感じた。
頼みごとを引き受けてくれ、食事まで奢ってもらったうえに、最後にいいものを見られたかもしれない。抱えた厄介事が片付いたわけではないのだが、二人の仲の進展具合を感じて、和彦の気持ちは少しだけ柔らかくなっていた。
秦と並んで歩き出す。護衛の組員は先に店を出て、すでに車で待機している。
寿司を食べつつたっぷり話はしたので、いまさらもう、車までの短い距離を歩きながら話すことはない。
そもそも今日は少し話しすぎたと、和彦は顔を背けて小さく咳き込む。なんとなく、喉が痛かった。気遣いのできる男が、すかさず声をかけてくる。
「おや、風邪ですか?」
「いや、外の空気が乾燥しているから……」
「気をつけてください。誕生日だけでなく、バレンタインまで控えた大事な体ですから」
意味深な冗談と受け止めて、和彦が横目でじろりと見たとき、秦はコートのポケットから携帯電話を取り出していた。メールが届いたようだ。
秦が携帯電話の画面を見つめる。数秒の間を置いて、端麗な横顔を怜悧な表情が彩った。素性の怪しい食えない男の本性が、この表情から垣間見えそうだ。
すぐに携帯電話を閉じた秦が、何事もなかったように和彦を見て、表情を和らげた。
「仕事のメールです」
「……忙しそうだな」
「長嶺組の後ろ盾のおかげで、儲け話に事欠かなくなりました」
皮肉とも思えない秦の口ぶりに、和彦は慎重に問いかける。
「長嶺組からのメールなのか……?」
「――先生の旦那さんからです」
あまりにさらりと言われ、危うく聞き流しそうになった和彦だが、ハッと我に返って秦にきつい眼差しを向ける。悪びれることなく、秦は満足げな様子で携帯電話を振った。
「冗談です」
「命知らずだな……。ぼくはともかく、長嶺組組長のことをそんなふうに言えるなんて」
「わたしは一言も、長嶺組長のことだと言ってませんよ」
和彦は、秦の脇腹に拳を入れた。ただし、機嫌を損ねられても困るので、あくまで軽く。
79
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
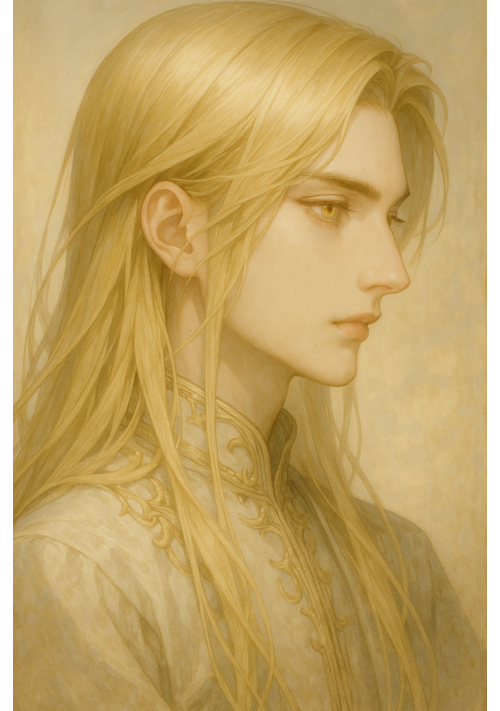
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。


好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















