447 / 1,289
第21話
(9)
しおりを挟む
さっそく和彦がスプーンを手にすると、さりげなく中嶋が言った。
「いろいろと理屈を並べてますが、単純に、俺は先生を好きなんです。もちろん、秦さんも先生を好きですよ」
和彦は、ナンを千切っている中嶋をまじまじと見つめてから、ぼそりと応じる。
「ぼくも、君は好きだ」
「光栄ですね、先生にそう言ってもらえて」
ここで二人は、食えない笑みを交わし合う。ヤクザのオンナとヤクザがカレーを前にして、こうして互いの腹を探り合っているとは、誰も思いはしないだろう。普通に過ごしている限り、和彦も中嶋も、表の世界によく馴染む外見をしているのだ。
野菜カレーをまず口にして、その味に和彦は満足する。中嶋からエビカレーを少し分けてもらい、代わりに和彦は、チキンカレーを食べてもらう。
ラム肉のタンドール焼きを味わっていた和彦は、店内に一人で入ってきた男に目を留めた。食事を始めてから数組の客の出入りを見たが、一見して違和感を覚える。なんとなくだが、食事に訪れたようには見えなかったのだ。
和彦の直感は当たったらしく、スタッフに何か言った男はさっと店内を見回してから、まっすぐこちらにやってくる。セーターの上からダウンジャケットを羽織った、ラフな格好をした若者だ。年齢は千尋と同じぐらいに見えるが、持っている空気がおそろしく鋭い。
「――お食事中、すみません」
若者はテーブルの傍らに立つと、一礼して低く抑えた声を発した。それを受けて、ここまで寛いだ様子を見せていた中嶋が表情を一変させる。口元には笑みを湛えながらも、冴えた目で若者を一瞥した。
「上手く進んだのか?」
中嶋の問いかけに若者は頷く。
「明日の朝、中嶋さんに立ち合って確認してほしいんですが」
「わかった。今日はもういい。他の連中はまだ一緒に?」
「車に待たせています」
二人のやり取りを聞きつつも、和彦は素知らぬ顔をして食事を続ける。賢吾とも食事をしていると、よくあることなのだ。立ち入ってはいけない話が多すぎるので、こうして聞こえていないふりをするのが一番無難だし、相手を警戒させないで済む。
中嶋は自分の財布を取り出すと、数枚の万札を若者に渡した。
「だったらこれで、飲み食いさせてやってくれ。ご苦労さん」
ダウンジャケットのポケットに金を仕舞った若者は、中嶋だけでなく、和彦にまで丁寧に頭を下げてすぐに店を出ていった。
「南郷さんが連れてきたんですよ」
和彦が口を開くより先に、中嶋が質問を先回りして説明を始める。
「総和会は、十一の組から成り立っているでかい組織ですが、実質的に動かしているのは、それぞれの組から推薦されて幹部になった人間と、さらにその幹部が引っ張ってきた人間です。ただし、どの組も平等に、自分の組の人間を総和会に送り込めるわけじゃありません。組の力というのが、如実に出るんです。今、総和会の中で一番組織力を持っているのは――」
「……長嶺組、か」
「より正確に言うなら、長嶺守光という勢力です。会長の力が強ければ強いほど、会長側についている人間の発言力も勢力も増す。自分の子飼いを増やせるということです」
「なら、さっきの若い子が?」
「ええ。南郷さんが昵懇にしている小さな組から連れてきた見習いです。あいつだけじゃない。遊撃隊が使える若い連中を揃えて、鍛えている最中なんですよ。俺は、あいつの他に数人を預かって、面倒を見ています」
「堂に入ってたな、さっきのやり取りは」
率直な和彦の感想に、中嶋は照れたような表情を見せた。こういう顔も、自分の前だから見せてくれるのかと思ったら貴重だ。だがそれも一瞬で、中嶋は軽く周囲を見回してから、声を潜めた。
「遊撃隊に入ってから感じたんですが、なんとなく、南郷さんは総和会の中での足場を固めているような気がするんですよね」
サフランライスの次に、ナンを味わっていた和彦は首を傾げる。
「隊を任されているぐらいなら、足場なんてとっくに固めているんじゃないのか」
「第二遊撃隊は、長嶺会長が南郷さんに居場所を与えるために作った隊だと言われています。長嶺会長が引退をしたら、あとはどうなるかわからないんですよ。だからこそ、ある程度の組織力を今のうちに養っているような――と、あくまで俺の想像ですけどね」
「総和会内での出世を望む君が、南郷さんの第二遊撃隊に入ったぐらいだ。それなりの目算はあってのことだと、ぼくなんかは思うんだが……」
ニヤリと笑った中嶋は、エビにかぶりついた。なんだか楽しそうだなと思いつつ、和彦はグラスの水を一気に飲み干す。カレーの香辛料より、総和会の内情の話のほうがよほど刺激的だ。ただしその刺激は、非常に厄介なものだ。
「いろいろと理屈を並べてますが、単純に、俺は先生を好きなんです。もちろん、秦さんも先生を好きですよ」
和彦は、ナンを千切っている中嶋をまじまじと見つめてから、ぼそりと応じる。
「ぼくも、君は好きだ」
「光栄ですね、先生にそう言ってもらえて」
ここで二人は、食えない笑みを交わし合う。ヤクザのオンナとヤクザがカレーを前にして、こうして互いの腹を探り合っているとは、誰も思いはしないだろう。普通に過ごしている限り、和彦も中嶋も、表の世界によく馴染む外見をしているのだ。
野菜カレーをまず口にして、その味に和彦は満足する。中嶋からエビカレーを少し分けてもらい、代わりに和彦は、チキンカレーを食べてもらう。
ラム肉のタンドール焼きを味わっていた和彦は、店内に一人で入ってきた男に目を留めた。食事を始めてから数組の客の出入りを見たが、一見して違和感を覚える。なんとなくだが、食事に訪れたようには見えなかったのだ。
和彦の直感は当たったらしく、スタッフに何か言った男はさっと店内を見回してから、まっすぐこちらにやってくる。セーターの上からダウンジャケットを羽織った、ラフな格好をした若者だ。年齢は千尋と同じぐらいに見えるが、持っている空気がおそろしく鋭い。
「――お食事中、すみません」
若者はテーブルの傍らに立つと、一礼して低く抑えた声を発した。それを受けて、ここまで寛いだ様子を見せていた中嶋が表情を一変させる。口元には笑みを湛えながらも、冴えた目で若者を一瞥した。
「上手く進んだのか?」
中嶋の問いかけに若者は頷く。
「明日の朝、中嶋さんに立ち合って確認してほしいんですが」
「わかった。今日はもういい。他の連中はまだ一緒に?」
「車に待たせています」
二人のやり取りを聞きつつも、和彦は素知らぬ顔をして食事を続ける。賢吾とも食事をしていると、よくあることなのだ。立ち入ってはいけない話が多すぎるので、こうして聞こえていないふりをするのが一番無難だし、相手を警戒させないで済む。
中嶋は自分の財布を取り出すと、数枚の万札を若者に渡した。
「だったらこれで、飲み食いさせてやってくれ。ご苦労さん」
ダウンジャケットのポケットに金を仕舞った若者は、中嶋だけでなく、和彦にまで丁寧に頭を下げてすぐに店を出ていった。
「南郷さんが連れてきたんですよ」
和彦が口を開くより先に、中嶋が質問を先回りして説明を始める。
「総和会は、十一の組から成り立っているでかい組織ですが、実質的に動かしているのは、それぞれの組から推薦されて幹部になった人間と、さらにその幹部が引っ張ってきた人間です。ただし、どの組も平等に、自分の組の人間を総和会に送り込めるわけじゃありません。組の力というのが、如実に出るんです。今、総和会の中で一番組織力を持っているのは――」
「……長嶺組、か」
「より正確に言うなら、長嶺守光という勢力です。会長の力が強ければ強いほど、会長側についている人間の発言力も勢力も増す。自分の子飼いを増やせるということです」
「なら、さっきの若い子が?」
「ええ。南郷さんが昵懇にしている小さな組から連れてきた見習いです。あいつだけじゃない。遊撃隊が使える若い連中を揃えて、鍛えている最中なんですよ。俺は、あいつの他に数人を預かって、面倒を見ています」
「堂に入ってたな、さっきのやり取りは」
率直な和彦の感想に、中嶋は照れたような表情を見せた。こういう顔も、自分の前だから見せてくれるのかと思ったら貴重だ。だがそれも一瞬で、中嶋は軽く周囲を見回してから、声を潜めた。
「遊撃隊に入ってから感じたんですが、なんとなく、南郷さんは総和会の中での足場を固めているような気がするんですよね」
サフランライスの次に、ナンを味わっていた和彦は首を傾げる。
「隊を任されているぐらいなら、足場なんてとっくに固めているんじゃないのか」
「第二遊撃隊は、長嶺会長が南郷さんに居場所を与えるために作った隊だと言われています。長嶺会長が引退をしたら、あとはどうなるかわからないんですよ。だからこそ、ある程度の組織力を今のうちに養っているような――と、あくまで俺の想像ですけどね」
「総和会内での出世を望む君が、南郷さんの第二遊撃隊に入ったぐらいだ。それなりの目算はあってのことだと、ぼくなんかは思うんだが……」
ニヤリと笑った中嶋は、エビにかぶりついた。なんだか楽しそうだなと思いつつ、和彦はグラスの水を一気に飲み干す。カレーの香辛料より、総和会の内情の話のほうがよほど刺激的だ。ただしその刺激は、非常に厄介なものだ。
89
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。


好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
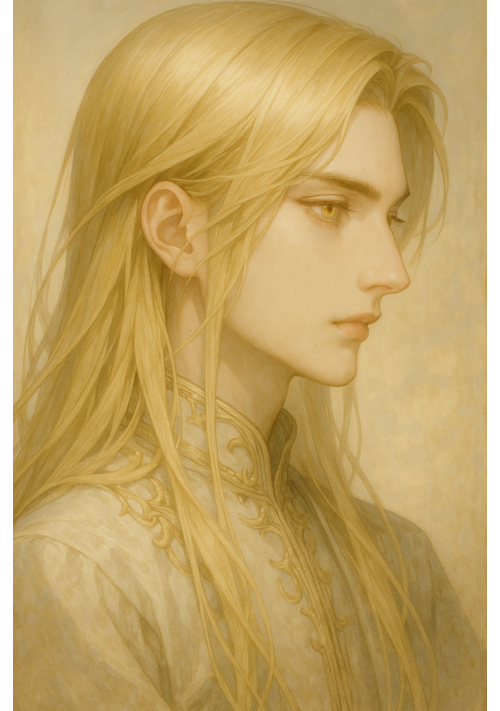
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ


奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















