474 / 1,289
第22話
(11)
しおりを挟む
肩にかかった守光の手に、力が加わる。抱き寄せられた和彦は、抗うこともできず守光におずおずともたれかかった。
守光のもう片方の手があごにかかり、持ち上げられる。初めてこんなに近くから、守光の顔を見ることになる。
端整な容貌の老紳士が、総和会という巨大な組織の頂点に君臨するには、相応の理由がある。見た目がいかに穏やかであろうが、守光の内面がそうであるとは限らない。
守光は、じわじわと本性を露わにしていき、和彦を呑み込んでいく。
「あんたは、自分が逆らえない力に敏感だ。そして、その力に対して巧く身を委ねられる。わしに対してもそうであると、考えていいかね?」
目隠しの布一枚分の理屈が、剥ぎ取られる瞬間だった。もう必要ないと守光は確信しているのだ。そして和彦は――。
守光の目を見つめたまま、ゆっくりと唇を塞がれた。
昨夜知ったばかりの唇の感触に、他の男たちには感じない緊張を強いられる。口づけの感覚を分かち合うというより、自分の身を差し出す感覚に近い。一方的に貪られるのだ。
唇を吸われてから、歯列をこじ開けるようにして舌が口腔に入り込む。その間も和彦は、守光の目を見つめ続けていた。賢吾は目に大蛇を潜ませているが、守光の場合は何も捉えられない。冷たい檻が存在していて、その奥に怪物が棲んでいるのだろうかと想像してしまう。守光の怖さは、正体の掴めなさにあるのだ。
「んっ……」
口腔の粘膜をじっくりと舐め回されたとき、和彦はゾクゾクするような疼きが背筋を駆け抜ける。
顔を見つめ合いながら唇を重ねて、ようやく和彦は実感していた。守光もまた、長嶺の男なのだと。堪らなく怖い存在である守光に、心と体のどこかで強烈に惹かれるものがあるのだ。もしかすると、そう思い込むことで、この世界での自分の身を守ろうとしているのかもしれないが――。
促されるまま舌を差し出し、守光に吸われる。そうしているうちに緩やかに舌を絡めながら、守光の唾液を受け入れる。守光は目を細めて一度唇を離し、この行為の意味を囁いてきた。
「――あんたは今から、長嶺守光の〈オンナ〉だ。いいな?」
まるで暗示にかけられたように和彦は頷く。頭の中が真っ白に染まり何も考えられなかったのだが、たとえ迷ったにしても、用意された答えは一つしかない。それぐらいは理解していた。
「怖がることはない。賢吾と千尋にとっても、あんたは大事で可愛いオンナだ。わしも、それに倣おう」
再び唇が重なり、和彦はようやく目を閉じると、守光との濃厚な口づけに酔った。
ベッドに横になった和彦は、照明に透かすように掲げた片手を、じっと見つめる。なんだか不思議な感覚だった。
自分の体のはずなのに、意識の一部が切り替わったように、こう感じるのだ。――長嶺守光に所有されている体だ、と。
和彦のことを〈オンナ〉と呼ぶ男は、すでに二人いる。当然、賢吾と千尋のことだ。慣れとは恐ろしいもので、屈辱的な呼称を和彦は受け入れ、自分自身、口にすることに抵抗も薄れつつある。だが、五日前に、守光のオンナとしての立場を受け入れてから、和彦は精神的に少し不安定になっていた。
裏の世界で生きる怖さは、この一年で実感しているはずだった。だが、総和会会長と深い関係を持つというのは、長嶺組との関わりでささやかに作り上げた足場をぐらつかせ、底なし沼に足を踏み出したような危うさを和彦に与えてくる。何かの拍子に、とてつもない闇に一気に引きずり込まれてしまいそうだ。
淡白な体の関係だけを求められているわけではないと、守光と接し、会話を交わしていれば察することはできる。賢吾が策謀を張り巡らせる外で、守光はさらに大きな仕掛けを用意しているように感じるのだ。
利用される価値は自分にないと思う一方で、総和会から丁重に扱われているという事実が、和彦を不安にさせる。
守光との旅行から戻ってきて以来、気分が塞ぎ込み、誰とも会いたくない状態が続いている。しかし、クリニックでの仕事がある以上、部屋に閉じこもるわけにもいかず、出勤はしている。ただ、長嶺組の人間との接触は、送迎の車内だけに留めていた。賢吾とも、電話ですら話していない。
勘のいい男は、和彦の素っ気ないメールの内容だけで、ある程度の状況は把握してくれたようだ。今のところ本宅への呼び出しも、部屋を訪ねてくることもない。
守光は、旅行中のことを賢吾に話したのだろうかと、ふと考える。
賢吾は、千尋とつき合っていた和彦を罠に掛ける形で裏の世界に引きずり込み、自分のオンナにした。千尋はそんな賢吾に対して、本宅に戻る条件として、和彦をオンナにすることを認めさせた。血が繋がっているとは言え、長嶺の男たちの関係はヌルくはない。
守光のもう片方の手があごにかかり、持ち上げられる。初めてこんなに近くから、守光の顔を見ることになる。
端整な容貌の老紳士が、総和会という巨大な組織の頂点に君臨するには、相応の理由がある。見た目がいかに穏やかであろうが、守光の内面がそうであるとは限らない。
守光は、じわじわと本性を露わにしていき、和彦を呑み込んでいく。
「あんたは、自分が逆らえない力に敏感だ。そして、その力に対して巧く身を委ねられる。わしに対してもそうであると、考えていいかね?」
目隠しの布一枚分の理屈が、剥ぎ取られる瞬間だった。もう必要ないと守光は確信しているのだ。そして和彦は――。
守光の目を見つめたまま、ゆっくりと唇を塞がれた。
昨夜知ったばかりの唇の感触に、他の男たちには感じない緊張を強いられる。口づけの感覚を分かち合うというより、自分の身を差し出す感覚に近い。一方的に貪られるのだ。
唇を吸われてから、歯列をこじ開けるようにして舌が口腔に入り込む。その間も和彦は、守光の目を見つめ続けていた。賢吾は目に大蛇を潜ませているが、守光の場合は何も捉えられない。冷たい檻が存在していて、その奥に怪物が棲んでいるのだろうかと想像してしまう。守光の怖さは、正体の掴めなさにあるのだ。
「んっ……」
口腔の粘膜をじっくりと舐め回されたとき、和彦はゾクゾクするような疼きが背筋を駆け抜ける。
顔を見つめ合いながら唇を重ねて、ようやく和彦は実感していた。守光もまた、長嶺の男なのだと。堪らなく怖い存在である守光に、心と体のどこかで強烈に惹かれるものがあるのだ。もしかすると、そう思い込むことで、この世界での自分の身を守ろうとしているのかもしれないが――。
促されるまま舌を差し出し、守光に吸われる。そうしているうちに緩やかに舌を絡めながら、守光の唾液を受け入れる。守光は目を細めて一度唇を離し、この行為の意味を囁いてきた。
「――あんたは今から、長嶺守光の〈オンナ〉だ。いいな?」
まるで暗示にかけられたように和彦は頷く。頭の中が真っ白に染まり何も考えられなかったのだが、たとえ迷ったにしても、用意された答えは一つしかない。それぐらいは理解していた。
「怖がることはない。賢吾と千尋にとっても、あんたは大事で可愛いオンナだ。わしも、それに倣おう」
再び唇が重なり、和彦はようやく目を閉じると、守光との濃厚な口づけに酔った。
ベッドに横になった和彦は、照明に透かすように掲げた片手を、じっと見つめる。なんだか不思議な感覚だった。
自分の体のはずなのに、意識の一部が切り替わったように、こう感じるのだ。――長嶺守光に所有されている体だ、と。
和彦のことを〈オンナ〉と呼ぶ男は、すでに二人いる。当然、賢吾と千尋のことだ。慣れとは恐ろしいもので、屈辱的な呼称を和彦は受け入れ、自分自身、口にすることに抵抗も薄れつつある。だが、五日前に、守光のオンナとしての立場を受け入れてから、和彦は精神的に少し不安定になっていた。
裏の世界で生きる怖さは、この一年で実感しているはずだった。だが、総和会会長と深い関係を持つというのは、長嶺組との関わりでささやかに作り上げた足場をぐらつかせ、底なし沼に足を踏み出したような危うさを和彦に与えてくる。何かの拍子に、とてつもない闇に一気に引きずり込まれてしまいそうだ。
淡白な体の関係だけを求められているわけではないと、守光と接し、会話を交わしていれば察することはできる。賢吾が策謀を張り巡らせる外で、守光はさらに大きな仕掛けを用意しているように感じるのだ。
利用される価値は自分にないと思う一方で、総和会から丁重に扱われているという事実が、和彦を不安にさせる。
守光との旅行から戻ってきて以来、気分が塞ぎ込み、誰とも会いたくない状態が続いている。しかし、クリニックでの仕事がある以上、部屋に閉じこもるわけにもいかず、出勤はしている。ただ、長嶺組の人間との接触は、送迎の車内だけに留めていた。賢吾とも、電話ですら話していない。
勘のいい男は、和彦の素っ気ないメールの内容だけで、ある程度の状況は把握してくれたようだ。今のところ本宅への呼び出しも、部屋を訪ねてくることもない。
守光は、旅行中のことを賢吾に話したのだろうかと、ふと考える。
賢吾は、千尋とつき合っていた和彦を罠に掛ける形で裏の世界に引きずり込み、自分のオンナにした。千尋はそんな賢吾に対して、本宅に戻る条件として、和彦をオンナにすることを認めさせた。血が繋がっているとは言え、長嶺の男たちの関係はヌルくはない。
72
あなたにおすすめの小説


執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。
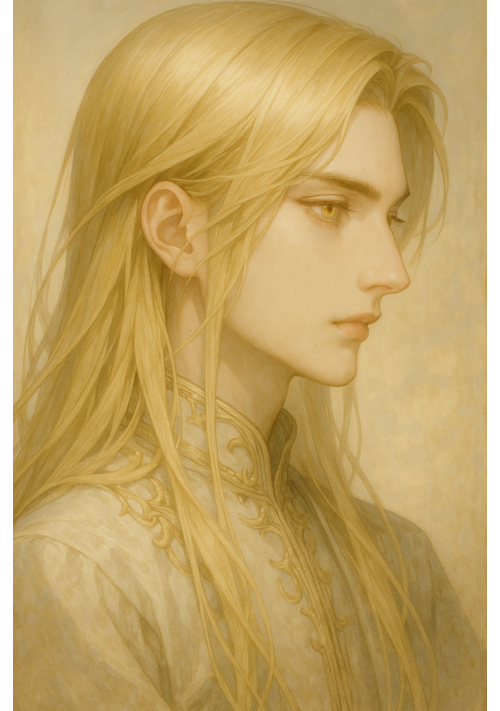
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。


好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















