475 / 1,289
第22話
(12)
しおりを挟む
かつて守光は、総和会会長の立場では、長嶺組の〈身内〉の処遇について命令はできないと言った。今ならこれが、言葉のうえだけの建前でしかないと理解できる。命令はしなくとも、和彦が選択するよう仕向ければいいだけの話なのだ。そして和彦は、選んだ。
男たちの思惑に搦め取られていくうちに、果たして自分はどこに行き着くのか。
考えたところでわかるはずもなく、それがまた和彦の気分を沈み込ませる。何か、しっかりとした支えに掴まっていなければ、今度こそ気持ちを立て直せない危惧すら抱いてしまう。
一度は横になりながらも眠れる心境ではなく、結局和彦は寝室を出る。コーヒーでも入れようかとキッチンに行きはしたものの、カップを出そうとしたところで動きを止める。
一瞬にして芽生えた衝動を必死に抑えようとしたが、できなかった。手早く服を着替えると、財布と部屋の鍵を掴んで玄関を出た。
部屋に引き返したほうがいいと、頭の片隅で弱々しく理性の声がする。しかしそんな声で足を止められるはずもなく、和彦はエレベーターに乗り込む。
マンションを出たときには、これが最初で最後だからと、自分自身に言い訳をしていた。
周囲をうかがいながら小走りで向かったのは、近くのコンビニだった。正確には、コンビニの外に設置された公衆電話に用がある。家から電話をかけると、盗聴器を通して会話を聞かれる恐れがあった。
つまり、組の人間に聞かれたくない電話をかけたいのだ。
慎重に辺りを見回してから受話器を取り上げる。電話番号は、携帯電話に登録したり、メモを手元に残しておくわけにもいかず、頭に叩き込んであった。
番号を押し、呼び出し音を五回聞いたところで受話器を置こうと、心の中で決める。これで、もう縁は切れたのだと諦められると、和彦は思った。
しかし決意とは裏腹に、〈彼〉との縁はそう脆いものではなかったようだ。
三回目の呼び出し音が鳴る前に、あっさりと彼が――里見が電話に出た。
『もしもし?』
電話越しに里見の声を聞いた瞬間、和彦の胸は切なく締め付けられる。自分が高校生だった頃の感覚に引き戻されるが、その一方で、自分の今の生活が脳裏を過ぎる。先日里見と会ってから、さほど日は経っていないというのに、和彦の置かれた状況はますます複雑に、物騒になった。
なんといっても、総和会会長のオンナになったのだ。
和彦が咄嗟に声を出せないでいると、それで里見は察するものがあったのか、いくらか声を潜めて尋ねてきた。
『もしかして、和彦くんか?』
「……こんな時間にごめん、里見さん」
返ってきたのは、安堵したような息遣いだった。
『気にしなくていい。こうして電話をくれたんだ。それだけで嬉しいよ』
里見の穏やかな声につい笑みをこぼしかけた和彦だが、ふとある光景が蘇り、顔が強張った。精神的に塞ぎ込んでいた原因は、何も守光のことだけではない。守光からの旅行の誘いに乗ったとき、和彦の気持ちはすでに不安定だったのだ。
『もう二度と、君の声を聞けないんじゃないかと、気が気じゃなかったんだ。それが、こんなに早く連絡をくれるなんて、嬉しいよ』
「本当は、連絡を取るつもりはなかったんだ。……里見さんに迷惑をかけるのが怖かったから。でも、だとしたら、あなたはもっと心配するんじゃないかとも思った」
『その通り。わたしは今の君について、何も知らないからね。ずっと心配していた』
ここで一度、沈黙が訪れる。和彦は急に寒さが気になり、冷たくなった指先を首筋に押し当てる。せめて手袋ぐらいしてくるべきだったかもしれない。
『――……公衆電話からかけているみたいだけど、寒くないか?』
「寒いけど、外から電話をかける必要があったんだ。携帯も……使えない」
『それは、わたしのことを用心しているのか、それとも君が置かれている環境のせいで、そこまでしないといけないのか。どっちだい?』
「両方だよ。ぼくは、佐伯家と繋がりのある里見さんを警戒している。それに、今ぼくの周囲にいる人間は用心深いんだ」
並んで歩いていた里見と英俊の姿が、脳裏をちらつく。ただ、そんな場面を見たと里見に言うわけにもいかない。
『それは……君を手放したくないからこその、用心深さかい?』
「そうだよ。ここでは大事にされている。それに、必要とされている」
『佐伯家での君を知っているわたしからしたら、胸が痛むね。その言葉は。率直に言って君は、佐伯家に必要とされている人間じゃなかった』
口調は穏やかながら、里見の言葉は切りつけてくるように鋭い。だが、事実だ。
「……あの家は、兄さんだけがいればよかったんだ。実際兄さんは有能だし、父さんと考え方もよく似ている。佐伯家を継ぐに相応しい人だよ」
男たちの思惑に搦め取られていくうちに、果たして自分はどこに行き着くのか。
考えたところでわかるはずもなく、それがまた和彦の気分を沈み込ませる。何か、しっかりとした支えに掴まっていなければ、今度こそ気持ちを立て直せない危惧すら抱いてしまう。
一度は横になりながらも眠れる心境ではなく、結局和彦は寝室を出る。コーヒーでも入れようかとキッチンに行きはしたものの、カップを出そうとしたところで動きを止める。
一瞬にして芽生えた衝動を必死に抑えようとしたが、できなかった。手早く服を着替えると、財布と部屋の鍵を掴んで玄関を出た。
部屋に引き返したほうがいいと、頭の片隅で弱々しく理性の声がする。しかしそんな声で足を止められるはずもなく、和彦はエレベーターに乗り込む。
マンションを出たときには、これが最初で最後だからと、自分自身に言い訳をしていた。
周囲をうかがいながら小走りで向かったのは、近くのコンビニだった。正確には、コンビニの外に設置された公衆電話に用がある。家から電話をかけると、盗聴器を通して会話を聞かれる恐れがあった。
つまり、組の人間に聞かれたくない電話をかけたいのだ。
慎重に辺りを見回してから受話器を取り上げる。電話番号は、携帯電話に登録したり、メモを手元に残しておくわけにもいかず、頭に叩き込んであった。
番号を押し、呼び出し音を五回聞いたところで受話器を置こうと、心の中で決める。これで、もう縁は切れたのだと諦められると、和彦は思った。
しかし決意とは裏腹に、〈彼〉との縁はそう脆いものではなかったようだ。
三回目の呼び出し音が鳴る前に、あっさりと彼が――里見が電話に出た。
『もしもし?』
電話越しに里見の声を聞いた瞬間、和彦の胸は切なく締め付けられる。自分が高校生だった頃の感覚に引き戻されるが、その一方で、自分の今の生活が脳裏を過ぎる。先日里見と会ってから、さほど日は経っていないというのに、和彦の置かれた状況はますます複雑に、物騒になった。
なんといっても、総和会会長のオンナになったのだ。
和彦が咄嗟に声を出せないでいると、それで里見は察するものがあったのか、いくらか声を潜めて尋ねてきた。
『もしかして、和彦くんか?』
「……こんな時間にごめん、里見さん」
返ってきたのは、安堵したような息遣いだった。
『気にしなくていい。こうして電話をくれたんだ。それだけで嬉しいよ』
里見の穏やかな声につい笑みをこぼしかけた和彦だが、ふとある光景が蘇り、顔が強張った。精神的に塞ぎ込んでいた原因は、何も守光のことだけではない。守光からの旅行の誘いに乗ったとき、和彦の気持ちはすでに不安定だったのだ。
『もう二度と、君の声を聞けないんじゃないかと、気が気じゃなかったんだ。それが、こんなに早く連絡をくれるなんて、嬉しいよ』
「本当は、連絡を取るつもりはなかったんだ。……里見さんに迷惑をかけるのが怖かったから。でも、だとしたら、あなたはもっと心配するんじゃないかとも思った」
『その通り。わたしは今の君について、何も知らないからね。ずっと心配していた』
ここで一度、沈黙が訪れる。和彦は急に寒さが気になり、冷たくなった指先を首筋に押し当てる。せめて手袋ぐらいしてくるべきだったかもしれない。
『――……公衆電話からかけているみたいだけど、寒くないか?』
「寒いけど、外から電話をかける必要があったんだ。携帯も……使えない」
『それは、わたしのことを用心しているのか、それとも君が置かれている環境のせいで、そこまでしないといけないのか。どっちだい?』
「両方だよ。ぼくは、佐伯家と繋がりのある里見さんを警戒している。それに、今ぼくの周囲にいる人間は用心深いんだ」
並んで歩いていた里見と英俊の姿が、脳裏をちらつく。ただ、そんな場面を見たと里見に言うわけにもいかない。
『それは……君を手放したくないからこその、用心深さかい?』
「そうだよ。ここでは大事にされている。それに、必要とされている」
『佐伯家での君を知っているわたしからしたら、胸が痛むね。その言葉は。率直に言って君は、佐伯家に必要とされている人間じゃなかった』
口調は穏やかながら、里見の言葉は切りつけてくるように鋭い。だが、事実だ。
「……あの家は、兄さんだけがいればよかったんだ。実際兄さんは有能だし、父さんと考え方もよく似ている。佐伯家を継ぐに相応しい人だよ」
71
あなたにおすすめの小説


かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。
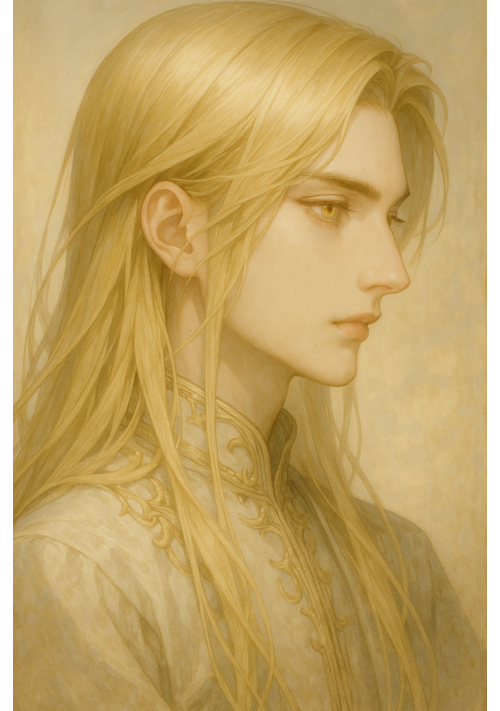
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

魔王の息子を育てることになった俺の話
お鮫
BL
俺が18歳の時森で少年を拾った。その子が将来魔王になることを知りながら俺は今日も息子としてこの子を育てる。そう決意してはや数年。
「今なんつった?よっぽど死にたいんだね。そんなに俺と離れたい?」
現在俺はかわいい息子に殺害予告を受けている。あれ、魔王は?旅に出なくていいの?とりあえず放してくれません?
魔王になる予定の男と育て親のヤンデレBL
BLは初めて書きます。見ずらい点多々あるかと思いますが、もしありましたら指摘くださるとありがたいです。
BL大賞エントリー中です。

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

好きなあいつの嫉妬がすごい
カムカム
BL
新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。
ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。
教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。
「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」
ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















