1,070 / 1,289
第42話
(7)
しおりを挟む
「わかりました」
「あと、着替えもさせてやってほしい。多分、自分ではやらないはずだから。警察を呼ぶとか威勢のいいこと言ってたけど、今は大声は出せないし、床に転がってたスマホは充電されてなかったから大丈夫だ」
細かい指示を出しながらエレベーターに乗り込み、一階へと降りる。
ふっと緊張が解けた途端、空腹を感じた。それもそのはずで、昼食をとっていなかった。きっと賢吾の予定では、買い物のあとに御堂と食事をさせるつもりだったのだろう。
味付けの濃いものが食べたいなと、あれこれメニューに思いを巡らせているうちに、エレベーターの扉が開く。降りた和彦の視界にまっさきに飛び込んできたのは、穏やかな眼差しをこちらに向ける三田村だった。
「三田村っ」
「せっかくの休みだったのに、すまなかった、先生」
三田村から発せられた謝罪の言葉に、和彦は戸惑う。すると三田村が、背後に立つ組員に軽く目配せをする。組員はこちらに頭を下げたあと、小走りでマンションを出て行った。
その後ろ姿を見送って、三田村が表情を一層和らげる。
「不思議そうな顔をしている」
「……突然目の前に現れたあんたから、すまなかったって言われたら、びっくりもするだろう」
「城東会の人間として言ったんだ。今日は土曜日だ。先生はゆっくり過ごしていたところだったんだろう?」
「それは――」
気にしていないと、ぼそぼそと答えた和彦だが、すぐにあることが気になって、三田村に詰め寄る。
「ぼくがさっき診た患者、組長の身内だと言われたんだ。組長っていうのは、城東会の、でいいんだよな?」
「そう。俺が補佐を務めている若頭のことだ」
エレベーターの前で立ち話を続けるわけにもいかず、三田村に促されるまま和彦もマンションを出る。駐車場には、城東会の組員たちだけが残っていた。
「あれっ?」
「今から俺が、先生の護衛を引き継いだ。長嶺組長に言われてのことだから、心配しなくていい」
土曜日の午後を潰してしまったことへの、賢吾なりの気遣いなのだろう。そう受け止めた和彦だが、素直には喜べない。神妙な顔で隣をうかがい見ると、三田村はまた穏やかな眼差しを向けてくる。
「俺も今日、仕事が休みだったんだが、正直時間を持て余していた。先生には悪いが、ちょうどよかった」
「そんなこと言って――……」
「先日のことも気になっていた」
『先日のこと』とは、クリニックに突然、里見が現れたことだ。三田村が駆けつけなければ自分はどうなって――いや、どうしていたか考えると、いまだに鼓動が速くなる。
あのあと和彦は、三田村によって本宅へと送り届けられた。結局、何事もなかったわけだが、素直に安堵するわけにはいかない。表と裏の世界の境界線が曖昧になったことで、自分の今の生活は容易く掻き乱されてしまうと身をもって実感したからだ。
「……里見さんにああいうことをやめさせるよう、父さんには言っておいた。組を刺激するようなまねをするなら、年末に実家に帰ることは考えさせてもらうと言っておいたから、多分、大丈夫」
「先生は?」
助手席のドアをわざわざ開けてくれながら、三田村に問われる。いつも通りのハスキーな声だが、和彦には胸が詰まるほど優しく聞こえた。
「先生は、大丈夫か?」
三田村の顔を見つめ、和彦はできるだけ自然な笑みで返す。
「ぼくは大丈夫だ。なるようにしかならないと思ったら、腹も決まった。とはいっても、気持ちが揺れるときもあるんだけど。仕事でバタバタしているほうが、ありがたいかもな。あれこれ考えなくていい」
ここでわざとらしく大きなため息をつき、顔をしかめて見せる。案の定、三田村が心配そうに顔を覗き込んできた。
「疲れたのか?」
「それより大変なことだ。……実は今、ものすごくお腹が空いているんだ」
軽く目を見開いた三田村が、冗談めかして応じた。
「それは一大事だ」
「だろ? だから――」
和彦が食べたいものをリクエストすると、三田村は車に乗り込んだあと、急いで携帯電話でどこかにかけ始める。深刻な口調で切り出した内容に、助手席で聞いていた和彦は必死に噴き出したくなるのを堪える。
まじめで優しい男は、和彦のリクエストに応えるため、他の組員にお勧めの店を聞いていたのだ。
三田村が連れてきてくれたラーメン店は、どうやら人気店らしい。和彦が水の入ったコップに口をつけながら、壁に貼られたメニューを眺めているわずかな間に、テーブル席はほぼ埋まっていた。
ただ、いいタイミングで飛び込んだらしく、注文したものはさほど待つことなく運ばれてきた。
テーブルに並んだラーメンとチャーハンに、和彦は目を輝かせる。
「炭水化物と炭水化物だ……」
「あと、着替えもさせてやってほしい。多分、自分ではやらないはずだから。警察を呼ぶとか威勢のいいこと言ってたけど、今は大声は出せないし、床に転がってたスマホは充電されてなかったから大丈夫だ」
細かい指示を出しながらエレベーターに乗り込み、一階へと降りる。
ふっと緊張が解けた途端、空腹を感じた。それもそのはずで、昼食をとっていなかった。きっと賢吾の予定では、買い物のあとに御堂と食事をさせるつもりだったのだろう。
味付けの濃いものが食べたいなと、あれこれメニューに思いを巡らせているうちに、エレベーターの扉が開く。降りた和彦の視界にまっさきに飛び込んできたのは、穏やかな眼差しをこちらに向ける三田村だった。
「三田村っ」
「せっかくの休みだったのに、すまなかった、先生」
三田村から発せられた謝罪の言葉に、和彦は戸惑う。すると三田村が、背後に立つ組員に軽く目配せをする。組員はこちらに頭を下げたあと、小走りでマンションを出て行った。
その後ろ姿を見送って、三田村が表情を一層和らげる。
「不思議そうな顔をしている」
「……突然目の前に現れたあんたから、すまなかったって言われたら、びっくりもするだろう」
「城東会の人間として言ったんだ。今日は土曜日だ。先生はゆっくり過ごしていたところだったんだろう?」
「それは――」
気にしていないと、ぼそぼそと答えた和彦だが、すぐにあることが気になって、三田村に詰め寄る。
「ぼくがさっき診た患者、組長の身内だと言われたんだ。組長っていうのは、城東会の、でいいんだよな?」
「そう。俺が補佐を務めている若頭のことだ」
エレベーターの前で立ち話を続けるわけにもいかず、三田村に促されるまま和彦もマンションを出る。駐車場には、城東会の組員たちだけが残っていた。
「あれっ?」
「今から俺が、先生の護衛を引き継いだ。長嶺組長に言われてのことだから、心配しなくていい」
土曜日の午後を潰してしまったことへの、賢吾なりの気遣いなのだろう。そう受け止めた和彦だが、素直には喜べない。神妙な顔で隣をうかがい見ると、三田村はまた穏やかな眼差しを向けてくる。
「俺も今日、仕事が休みだったんだが、正直時間を持て余していた。先生には悪いが、ちょうどよかった」
「そんなこと言って――……」
「先日のことも気になっていた」
『先日のこと』とは、クリニックに突然、里見が現れたことだ。三田村が駆けつけなければ自分はどうなって――いや、どうしていたか考えると、いまだに鼓動が速くなる。
あのあと和彦は、三田村によって本宅へと送り届けられた。結局、何事もなかったわけだが、素直に安堵するわけにはいかない。表と裏の世界の境界線が曖昧になったことで、自分の今の生活は容易く掻き乱されてしまうと身をもって実感したからだ。
「……里見さんにああいうことをやめさせるよう、父さんには言っておいた。組を刺激するようなまねをするなら、年末に実家に帰ることは考えさせてもらうと言っておいたから、多分、大丈夫」
「先生は?」
助手席のドアをわざわざ開けてくれながら、三田村に問われる。いつも通りのハスキーな声だが、和彦には胸が詰まるほど優しく聞こえた。
「先生は、大丈夫か?」
三田村の顔を見つめ、和彦はできるだけ自然な笑みで返す。
「ぼくは大丈夫だ。なるようにしかならないと思ったら、腹も決まった。とはいっても、気持ちが揺れるときもあるんだけど。仕事でバタバタしているほうが、ありがたいかもな。あれこれ考えなくていい」
ここでわざとらしく大きなため息をつき、顔をしかめて見せる。案の定、三田村が心配そうに顔を覗き込んできた。
「疲れたのか?」
「それより大変なことだ。……実は今、ものすごくお腹が空いているんだ」
軽く目を見開いた三田村が、冗談めかして応じた。
「それは一大事だ」
「だろ? だから――」
和彦が食べたいものをリクエストすると、三田村は車に乗り込んだあと、急いで携帯電話でどこかにかけ始める。深刻な口調で切り出した内容に、助手席で聞いていた和彦は必死に噴き出したくなるのを堪える。
まじめで優しい男は、和彦のリクエストに応えるため、他の組員にお勧めの店を聞いていたのだ。
三田村が連れてきてくれたラーメン店は、どうやら人気店らしい。和彦が水の入ったコップに口をつけながら、壁に貼られたメニューを眺めているわずかな間に、テーブル席はほぼ埋まっていた。
ただ、いいタイミングで飛び込んだらしく、注文したものはさほど待つことなく運ばれてきた。
テーブルに並んだラーメンとチャーハンに、和彦は目を輝かせる。
「炭水化物と炭水化物だ……」
66
あなたにおすすめの小説

執着
紅林
BL
聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

結婚初夜に相手が舌打ちして寝室出て行こうとした
紫
BL
十数年間続いた王国と帝国の戦争の終結と和平の形として、元敵国の皇帝と結婚することになったカイル。
実家にはもう帰ってくるなと言われるし、結婚相手は心底嫌そうに舌打ちしてくるし、マジ最悪ってところから始まる話。
オメガバースでオメガの立場が低い世界
こんなあらすじとタイトルですが、主人公が可哀そうって感じは全然ないです
強くたくましくメンタルがオリハルコンな主人公です
主人公は耐える我慢する許す許容するということがあんまり出来ない人間です
倫理観もちょっと薄いです
というか、他人の事を自分と同じ人間だと思ってない部分があります
※この主人公は受けです

秘花~王太子の秘密と宿命の皇女~
めぐみ
BL
☆俺はお前を何度も抱き、俺なしではいられぬ淫らな身体にする。宿命という名の数奇な運命に翻弄される王子達☆
―俺はそなたを玩具だと思ったことはなかった。ただ、そなたの身体は俺のものだ。俺はそなたを何度でも抱き、俺なしではいられないような淫らな身体にする。抱き潰すくらいに抱けば、そなたもあの宦官のことなど思い出しもしなくなる。―
モンゴル大帝国の皇帝を祖父に持ちモンゴル帝国直系の皇女を生母として生まれた彼は、生まれながらの高麗の王太子だった。
だが、そんな王太子の運命を激変させる出来事が起こった。
そう、あの「秘密」が表に出るまでは。

奇跡に祝福を
善奈美
BL
家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。
※不定期更新になります。

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい
日向汐
BL
過保護なかわいい系美形の後輩。
たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡
そんなお話。
【攻め】
雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)
大学1年。法学部。
淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。
甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。
【受け】
睦月伊織(むつき・いおり)
大学2年。工学部。
黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。

君に望むは僕の弔辞
爺誤
BL
僕は生まれつき身体が弱かった。父の期待に応えられなかった僕は屋敷のなかで打ち捨てられて、早く死んでしまいたいばかりだった。姉の成人で賑わう屋敷のなか、鍵のかけられた部屋で悲しみに押しつぶされかけた僕は、迷い込んだ客人に外に出してもらった。そこで自分の可能性を知り、希望を抱いた……。
全9話
匂わせBL(エ◻︎なし)。死ネタ注意
表紙はあいえだ様!!
小説家になろうにも投稿
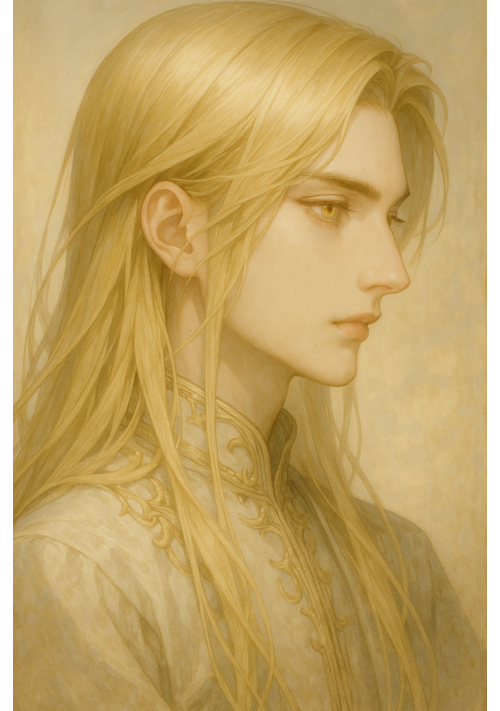
帝は傾国の元帥を寵愛する
tii
BL
セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。
舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。
誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。
だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。
それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。
互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。
誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。
やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。
華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。
冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。
【第13回BL大賞にエントリー中】
投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















