5 / 6
05:新たなる面倒事の始まり
しおりを挟む
あの前代未聞の卒業記念パーティーから、数日が過ぎた。
ベルンシュタイン公爵邸は、表向きはいつもと変わらぬ静寂に包まれている。だがその内部では、ある種の嵐が吹き荒れていた。いや、正確には、嵐が過ぎ去った後の、奇妙な凪の状態にあった。
「レティシア。お前は、本当に……本当に、わしの自慢の娘だ!」
卒業パーティーの日の夜。レティシアは、父であるベルンシュタイン公爵に書斎へと呼び出された。お叱りの言葉を受けるかと思いきや、開口一番そう言われながら力強く抱きしめられた。
武門の誉れ高い公爵は、娘が王宮騎士団を素手で半壊させたという報告を聞き、怒るどころか感涙にむせぶ。
「父様、苦しゅうございます……」
「おお、すまんすまん。しかし、見事だ! あのひ弱な若造どもに、我がベルンシュタイン家の血の何たるかを思い知らせてやったようだな! 特に、あのゲオルグの奴の報告書にあった『舞うような体捌きからの完璧な掌底』という一文! 目に浮かぶようだ!」
興奮冷めやらぬ父とは対照的に、母である公爵夫人は違う意味でむせび泣いた。常識ある令嬢は騎士団を相手に立ち回りなどしない、という至極真っ当な理由で。レティシアはその後きっかり一時間、母から淑女の品格と振る舞いについて涙ながらのお説教を受けることになった。
「わたくしが、どれだけ貴女を完璧な淑女に育てようと努力してきたか……! それなのに、貴女という子は! パーティ会場で騎士団をなぎ倒す令嬢が、世界のどこにおりますか!」
「申し訳ございません、母様。ですが、ドレスは汚さぬよう、細心の注意を払いましたのよ」
「そういう問題ではございません!」
しかし、その叱責の声も後半になるにつれて色合いが変わっていく。
「……それで、相手に怪我はなかったのでしょうね?」
「ええ、手加減はいたしましたわ」
「そう、それなら……まあ、少しは……」
と、母の口ぶりは歯切れが悪くなっていく。
結局のところ、母もまた娘の無事を喜んでいた。加えて武を誇るベルンシュタインの公爵夫人として、理不尽に立ち向かった娘の気骨を、内心では誇らしく思っているのだった。
さて。
両親からの賞賛とお小言、さらに追加で誉め言葉を受けたレティシア本人は、自室の天蓋付きベッドの上で、大の字になっていた。
「ああ、疲れましたわ……」
四肢を投げ出し、天井の豪華な装飾をぼんやりと眺める。肉体的な疲労は、とうにない。あるのは精神的な疲労感だ。面倒事に巻き込まれ、それを排除するために、さらに面倒なことをしでかしてしまった。その自己嫌悪にも似た徒労感が、ずしりと彼女を包み込んでいた。
「もう、王宮関係の面倒事はこりごりですわ」
窓の外では、小鳥がさえずっている。あのパーティーでの出来事が、まるで遠い夢の中の出来事のように感じられた。婚約は破棄され、自由の身になった。これからは、誰に気兼ねすることなく、庭の木に登り、裏山を探検し、うららかな日差しの下で昼寝ができる。そう、平穏な日常が、ようやく戻ってきたのだ。
レティシアは、そう信じて疑わなかった。
―・―・―・―・―・―・―・―
同じ頃、王宮では、まったく別の種類の嵐が吹き荒れていた。
玉座の間。国王ランドール三世は、ゲオルグ騎士団長から提出された詳細な報告書を読み、玉座を揺らさんばかりに大笑いしていた。
「ぶはははは! 面白い! 実に面白いではないか、ゲオルグ!」
「はあ……。陛下、これは笑い事では……」
ゲオルグは、苦虫を噛み潰したような顔をして答える。自分の部下たちが、たったひとりの少女に赤子の手をひねるようにあしらわれたのだ。騎士団長としての面目は丸潰れである。
「何を言うか! これは、我が国の未来にとって、望外の吉報だぞ!」
国王は報告書を掲げるようにして、その中の一文を指差した。
「『対象は、一切の刃物を使用せず、人体の急所を的確に打撃、あるいは関節を制することで、全対象を殺傷することなく、完璧に無力化した』。これだ! この一文に、すべてが詰まっておる!」
国王は、玉座から立ち上がると、興奮した様子で部屋を歩き回る。
「力があるだけの蛮族ではない。力を完璧に制御し、目的を遂行するための最適な手段を選択できる知性。そして何より、ドレスを汚さぬという、その美学! 実に素晴らしい! 素晴らしいじゃじゃ馬ではないか!」
べた褒めであった。常識的な貴族令嬢という存在からは何段階もかけ離れているレティシアに対して、国王は言葉の限りの賞賛を送る。もっとも、それを聞いたとしても素直に喜べるかどうかは疑問ではあるが。
「あの愚息アルフォンスには、もったいなさすぎる器だ。王太子妃などという、窮屈な鳥かごに収まっていていい人材ではない。あの力、あの胆力……活かさぬ手はないだろう」
「陛下……? まさか……」
国王は、ニヤリと、悪戯を思いついた子供のような笑みを浮かべた。
ゲオルグの脳裏に、嫌な予感がよぎる。国王がこういう顔をした時はいつもろくなことにならない。
「よし、決めたぞ! ゲオルグ、すぐに勅命の準備をせよ!」
―・―・―・―・―・―・―・―
平穏な日々が戻ってきたと信じていたレティシア。そんな彼女の元に王宮からの使者が訪れたのは、王が報告を受けて大爆笑をしてから三日後のことだった。
侍女が恭しく銀の盆に乗せて運んできたのは、国王の印である獅子の紋章が刻まれた、豪奢な封蝋で封をされた一通の親書。
「……王宮から? わたくし宛に?」
レティシアは、眉をひそめた。もう関わることはないと思っていた。
アルフォンス殿下からの謝罪の手紙だろうか。
いや、あのプライドの高い殿下が、そんなことをするはずがない。
では、一体なんだろう。
胸騒ぎを覚えながらも、彼女はペーパーナイフで丁寧に封を切る。中から現れた上質な羊皮紙には、力強く、流麗な筆跡でこう記されていた。
『レティシア・フォン・ベルンシュタイン嬢へ
先の卒業記念パーティにおける、貴殿の勇壮なる武勇伝、誠に天晴れであった。その類稀なる武勇と、冷静沈着なる判断力は、王太子妃という器に収まるには、あまりにも大きすぎる。
よって、ここに勅命を下す。
貴殿を、国王直属護衛官、特別遊撃部隊『ロイヤル・フィスト(王の拳)』の初代隊長に任命する。
これは、我が国の暗部を払い、王家の敵を秘密裏に排除するための、影の部隊である。貴殿のその規格外の力は、国の光を守るための、最も鋭き刃となるであろう。
これは決定事項であり、拒否権はない。
三日後、王宮に出仕し、直接余から任務の説明を受けるように。
追伸:執務室は、見晴らしの良い東塔の最上階を用意させた。木登りにはちょうどよかろう。
国王 ランドール三世』
レティシアは親書を読み終えると、そのままの姿勢で固まった。時間が止まったかのように微動だにしない。不敬と分かっていながらも、なんだこれは、と思わずにいられない。
「………………」
しばし、沈黙。
やがて、彼女の口から、か細い、この世の終わりのような声が漏れた。
「……いちばん、面倒なことになりましたわね」
婚約破棄によって手に入れたはずの自由。木登り、猪追い、お昼寝。彼女のささやかな、しかし何物にも代えがたい平穏な日常は、幻のように消え去った。
その代わりに与えられたのは、国王直属の秘密部隊の隊長という、想像を絶するほど面倒くさそうな役職。国の暗部を払う? 王家の敵を排除? そんな、物語の中のような大役を、なぜ自分が? そう思わずにはいられない。
しかも、追伸の一文。
『木登りにはちょうどよかろう』
国王は、すべてお見通しなのだ。自分の本性も、望みも、すべてを知った上で、掌の上で転がしている。これでは、逃げ場がない。
レティシアは、ふらふらと窓辺に歩み寄った。窓の外には、どこまでも広がる青空と、ベルンシュタイン公爵家が誇る広大な庭園が見える。いつもなら、あの木に登ろうか、あの茂みを探検しようか、と心が躍るはずの光景が、今は灰色に見えた。
「はぁ……」
今日一番、いや、人生で一番深いため息が、彼女の唇から漏れた。
面倒事を避けるために、淑女を演じてきた。
理不尽な面倒事を排除するために、一度だけ本性を現した。
その結果、国家規模の、最大級の面倒事を押し付けられることになった。
人生とは、なんと皮肉なものだろう。
「………………」
しかし、彼女はレティシア・フォン・ベルンシュタイン。武門の血を受け継ぐ、不屈のじゃじゃ馬令嬢である。いつまでも、めそめそしてはいられない。
レティシアは窓枠に手をつくと、ぎゅっと拳を握りしめた。その瞳に、再び闘志の光が宿る。
「……こうなったら、やけくそですわ」
どうせやらなければならないのなら、最短距離で、最も効率的に、さっさと終わらせてしまえばいい。国の暗部だろうが王家の敵だろうが、すべてまとめて、この拳で叩き伏せ、無理やりにでも平穏な時間を作り出してみせる。
「まずは、あの悪趣味な国王陛下に、一発お見舞いするところから始めなければなりませんわね」
不敵な笑みを浮かべた彼女の顔は、もはや猫を被った淑女のものではなかった。それは、新たなる戦場へと赴く、最強の戦士の顔だった。
―・―・―・―・―・―・―・―
こうして、お転婆令嬢・レティシアの、まったく平穏ではない新たなる戦いが幕を開けた。
彼女は平穏な日常を取り戻すことができるのか。
心置きなく木登りができる日は、果たしていつになるのだろうか。
それは、まだ誰にも分からない。
-つづく?-
ベルンシュタイン公爵邸は、表向きはいつもと変わらぬ静寂に包まれている。だがその内部では、ある種の嵐が吹き荒れていた。いや、正確には、嵐が過ぎ去った後の、奇妙な凪の状態にあった。
「レティシア。お前は、本当に……本当に、わしの自慢の娘だ!」
卒業パーティーの日の夜。レティシアは、父であるベルンシュタイン公爵に書斎へと呼び出された。お叱りの言葉を受けるかと思いきや、開口一番そう言われながら力強く抱きしめられた。
武門の誉れ高い公爵は、娘が王宮騎士団を素手で半壊させたという報告を聞き、怒るどころか感涙にむせぶ。
「父様、苦しゅうございます……」
「おお、すまんすまん。しかし、見事だ! あのひ弱な若造どもに、我がベルンシュタイン家の血の何たるかを思い知らせてやったようだな! 特に、あのゲオルグの奴の報告書にあった『舞うような体捌きからの完璧な掌底』という一文! 目に浮かぶようだ!」
興奮冷めやらぬ父とは対照的に、母である公爵夫人は違う意味でむせび泣いた。常識ある令嬢は騎士団を相手に立ち回りなどしない、という至極真っ当な理由で。レティシアはその後きっかり一時間、母から淑女の品格と振る舞いについて涙ながらのお説教を受けることになった。
「わたくしが、どれだけ貴女を完璧な淑女に育てようと努力してきたか……! それなのに、貴女という子は! パーティ会場で騎士団をなぎ倒す令嬢が、世界のどこにおりますか!」
「申し訳ございません、母様。ですが、ドレスは汚さぬよう、細心の注意を払いましたのよ」
「そういう問題ではございません!」
しかし、その叱責の声も後半になるにつれて色合いが変わっていく。
「……それで、相手に怪我はなかったのでしょうね?」
「ええ、手加減はいたしましたわ」
「そう、それなら……まあ、少しは……」
と、母の口ぶりは歯切れが悪くなっていく。
結局のところ、母もまた娘の無事を喜んでいた。加えて武を誇るベルンシュタインの公爵夫人として、理不尽に立ち向かった娘の気骨を、内心では誇らしく思っているのだった。
さて。
両親からの賞賛とお小言、さらに追加で誉め言葉を受けたレティシア本人は、自室の天蓋付きベッドの上で、大の字になっていた。
「ああ、疲れましたわ……」
四肢を投げ出し、天井の豪華な装飾をぼんやりと眺める。肉体的な疲労は、とうにない。あるのは精神的な疲労感だ。面倒事に巻き込まれ、それを排除するために、さらに面倒なことをしでかしてしまった。その自己嫌悪にも似た徒労感が、ずしりと彼女を包み込んでいた。
「もう、王宮関係の面倒事はこりごりですわ」
窓の外では、小鳥がさえずっている。あのパーティーでの出来事が、まるで遠い夢の中の出来事のように感じられた。婚約は破棄され、自由の身になった。これからは、誰に気兼ねすることなく、庭の木に登り、裏山を探検し、うららかな日差しの下で昼寝ができる。そう、平穏な日常が、ようやく戻ってきたのだ。
レティシアは、そう信じて疑わなかった。
―・―・―・―・―・―・―・―
同じ頃、王宮では、まったく別の種類の嵐が吹き荒れていた。
玉座の間。国王ランドール三世は、ゲオルグ騎士団長から提出された詳細な報告書を読み、玉座を揺らさんばかりに大笑いしていた。
「ぶはははは! 面白い! 実に面白いではないか、ゲオルグ!」
「はあ……。陛下、これは笑い事では……」
ゲオルグは、苦虫を噛み潰したような顔をして答える。自分の部下たちが、たったひとりの少女に赤子の手をひねるようにあしらわれたのだ。騎士団長としての面目は丸潰れである。
「何を言うか! これは、我が国の未来にとって、望外の吉報だぞ!」
国王は報告書を掲げるようにして、その中の一文を指差した。
「『対象は、一切の刃物を使用せず、人体の急所を的確に打撃、あるいは関節を制することで、全対象を殺傷することなく、完璧に無力化した』。これだ! この一文に、すべてが詰まっておる!」
国王は、玉座から立ち上がると、興奮した様子で部屋を歩き回る。
「力があるだけの蛮族ではない。力を完璧に制御し、目的を遂行するための最適な手段を選択できる知性。そして何より、ドレスを汚さぬという、その美学! 実に素晴らしい! 素晴らしいじゃじゃ馬ではないか!」
べた褒めであった。常識的な貴族令嬢という存在からは何段階もかけ離れているレティシアに対して、国王は言葉の限りの賞賛を送る。もっとも、それを聞いたとしても素直に喜べるかどうかは疑問ではあるが。
「あの愚息アルフォンスには、もったいなさすぎる器だ。王太子妃などという、窮屈な鳥かごに収まっていていい人材ではない。あの力、あの胆力……活かさぬ手はないだろう」
「陛下……? まさか……」
国王は、ニヤリと、悪戯を思いついた子供のような笑みを浮かべた。
ゲオルグの脳裏に、嫌な予感がよぎる。国王がこういう顔をした時はいつもろくなことにならない。
「よし、決めたぞ! ゲオルグ、すぐに勅命の準備をせよ!」
―・―・―・―・―・―・―・―
平穏な日々が戻ってきたと信じていたレティシア。そんな彼女の元に王宮からの使者が訪れたのは、王が報告を受けて大爆笑をしてから三日後のことだった。
侍女が恭しく銀の盆に乗せて運んできたのは、国王の印である獅子の紋章が刻まれた、豪奢な封蝋で封をされた一通の親書。
「……王宮から? わたくし宛に?」
レティシアは、眉をひそめた。もう関わることはないと思っていた。
アルフォンス殿下からの謝罪の手紙だろうか。
いや、あのプライドの高い殿下が、そんなことをするはずがない。
では、一体なんだろう。
胸騒ぎを覚えながらも、彼女はペーパーナイフで丁寧に封を切る。中から現れた上質な羊皮紙には、力強く、流麗な筆跡でこう記されていた。
『レティシア・フォン・ベルンシュタイン嬢へ
先の卒業記念パーティにおける、貴殿の勇壮なる武勇伝、誠に天晴れであった。その類稀なる武勇と、冷静沈着なる判断力は、王太子妃という器に収まるには、あまりにも大きすぎる。
よって、ここに勅命を下す。
貴殿を、国王直属護衛官、特別遊撃部隊『ロイヤル・フィスト(王の拳)』の初代隊長に任命する。
これは、我が国の暗部を払い、王家の敵を秘密裏に排除するための、影の部隊である。貴殿のその規格外の力は、国の光を守るための、最も鋭き刃となるであろう。
これは決定事項であり、拒否権はない。
三日後、王宮に出仕し、直接余から任務の説明を受けるように。
追伸:執務室は、見晴らしの良い東塔の最上階を用意させた。木登りにはちょうどよかろう。
国王 ランドール三世』
レティシアは親書を読み終えると、そのままの姿勢で固まった。時間が止まったかのように微動だにしない。不敬と分かっていながらも、なんだこれは、と思わずにいられない。
「………………」
しばし、沈黙。
やがて、彼女の口から、か細い、この世の終わりのような声が漏れた。
「……いちばん、面倒なことになりましたわね」
婚約破棄によって手に入れたはずの自由。木登り、猪追い、お昼寝。彼女のささやかな、しかし何物にも代えがたい平穏な日常は、幻のように消え去った。
その代わりに与えられたのは、国王直属の秘密部隊の隊長という、想像を絶するほど面倒くさそうな役職。国の暗部を払う? 王家の敵を排除? そんな、物語の中のような大役を、なぜ自分が? そう思わずにはいられない。
しかも、追伸の一文。
『木登りにはちょうどよかろう』
国王は、すべてお見通しなのだ。自分の本性も、望みも、すべてを知った上で、掌の上で転がしている。これでは、逃げ場がない。
レティシアは、ふらふらと窓辺に歩み寄った。窓の外には、どこまでも広がる青空と、ベルンシュタイン公爵家が誇る広大な庭園が見える。いつもなら、あの木に登ろうか、あの茂みを探検しようか、と心が躍るはずの光景が、今は灰色に見えた。
「はぁ……」
今日一番、いや、人生で一番深いため息が、彼女の唇から漏れた。
面倒事を避けるために、淑女を演じてきた。
理不尽な面倒事を排除するために、一度だけ本性を現した。
その結果、国家規模の、最大級の面倒事を押し付けられることになった。
人生とは、なんと皮肉なものだろう。
「………………」
しかし、彼女はレティシア・フォン・ベルンシュタイン。武門の血を受け継ぐ、不屈のじゃじゃ馬令嬢である。いつまでも、めそめそしてはいられない。
レティシアは窓枠に手をつくと、ぎゅっと拳を握りしめた。その瞳に、再び闘志の光が宿る。
「……こうなったら、やけくそですわ」
どうせやらなければならないのなら、最短距離で、最も効率的に、さっさと終わらせてしまえばいい。国の暗部だろうが王家の敵だろうが、すべてまとめて、この拳で叩き伏せ、無理やりにでも平穏な時間を作り出してみせる。
「まずは、あの悪趣味な国王陛下に、一発お見舞いするところから始めなければなりませんわね」
不敵な笑みを浮かべた彼女の顔は、もはや猫を被った淑女のものではなかった。それは、新たなる戦場へと赴く、最強の戦士の顔だった。
―・―・―・―・―・―・―・―
こうして、お転婆令嬢・レティシアの、まったく平穏ではない新たなる戦いが幕を開けた。
彼女は平穏な日常を取り戻すことができるのか。
心置きなく木登りができる日は、果たしていつになるのだろうか。
それは、まだ誰にも分からない。
-つづく?-
13
あなたにおすすめの小説

【完結】悪役令嬢のスローライフ
きゅちゃん
ファンタジー
帝国最高学府ロイヤル・アカデミーで「金糸の蛇」と恐れられ、王太子の婚約者の座を狙う冷酷な悪役令嬢として名を馳せたエレノア・グランツェント。しかしある日、前世の記憶が蘇り、自分が乙女ゲームの悪役令嬢であること、そしてこのままでは破滅エンドが待っていることを知る。
婚約破棄からの国外追放、あるいは死罪——。最悪の結末を回避するため、エレノアは誰もが予想しなかった選択をする。権力争いと虚飾に満ちた帝都の社交界から身を引き、辺境にある自家の領地「銀風の谷」で静かに暮らすことを決意したのだ。
「こんな生き方もあったのね」
かつての冷徹な悪役令嬢は、豊かな自然に囲まれた領地で少しずつ変わり始める。養蜂場の立ち上げ、村の子供たちへの読み聞かせ、季節の収穫祭——。忙しくも心穏やかな日々の中で、エレノアは初めて本当の自分と向き合い、人々との絆を育んでいく。
しかし、彼女の新しい生活は長くは続かないかもしれない。帝都からの思わぬ来客、過去の因縁、そして領地を狙う勢力の影。エレノアの平穏なスローライフは、時に小さな波乱に見舞われる。
前世と今世、二つの人生経験を持つエレノアは、悪役令嬢としての知略と新たに芽生えた優しさを武器に、自分だけの幸せを見つけることができるのか——。
これは、自分の運命を自分の手で書き換えようとする、ある悪役令嬢の新しい物語。
各話完結型で贈る、悪役令嬢のスローライフストーリー。帝都の喧騒を離れ、辺境の領地で見つけた本当の幸せとは——

転生『悪役』公爵令嬢はやり直し人生で楽隠居を目指す
RINFAM
ファンタジー
なんの罰ゲームだ、これ!!!!
あああああ!!!
本当ならあと数年で年金ライフが送れたはずなのに!!
そのために国民年金の他に利率のいい個人年金も掛け、さらに少ない給料の中からちまちまと老後の生活費を貯めてきたと言うのに!!!!
一銭も貰えないまま人生終わるだなんて、あんまりです神様仏様あああ!!
かくなる上はこのやり直し転生人生で、前世以上に楽して暮らせる隠居生活を手に入れなければ。
年金受給前に死んでしまった『心は常に18歳』な享年62歳の初老女『成瀬裕子』はある日突然死しファンタジー世界で公爵令嬢に転生!!しかし、数年後に待っていた年金生活を夢見ていた彼女は、やり直し人生で再び若いままでの楽隠居生活を目指すことに。
4コマ漫画版もあります。

【完結】政略婚約された令嬢ですが、記録と魔法で頑張って、現世と違って人生好転させます
なみゆき
ファンタジー
典子、アラフィフ独身女性。 結婚も恋愛も経験せず、気づけば父の介護と職場の理不尽に追われる日々。 兄姉からは、都合よく扱われ、父からは暴言を浴びせられ、職場では責任を押しつけられる。 人生のほとんどを“搾取される側”として生きてきた。
過労で倒れた彼女が目を覚ますと、そこは異世界。 7歳の伯爵令嬢セレナとして転生していた。 前世の記憶を持つ彼女は、今度こそ“誰かの犠牲”ではなく、“誰かの支え”として生きることを決意する。
魔法と貴族社会が息づくこの世界で、セレナは前世の知識を活かし、友人達と交流を深める。
そこに割り込む怪しい聖女ー語彙力もなく、ワンパターンの行動なのに攻略対象ぽい人たちは次々と籠絡されていく。
これはシナリオなのかバグなのか?
その原因を突き止めるため、全ての証拠を記録し始めた。
【☆応援やブクマありがとうございます☆大変励みになりますm(_ _)m】
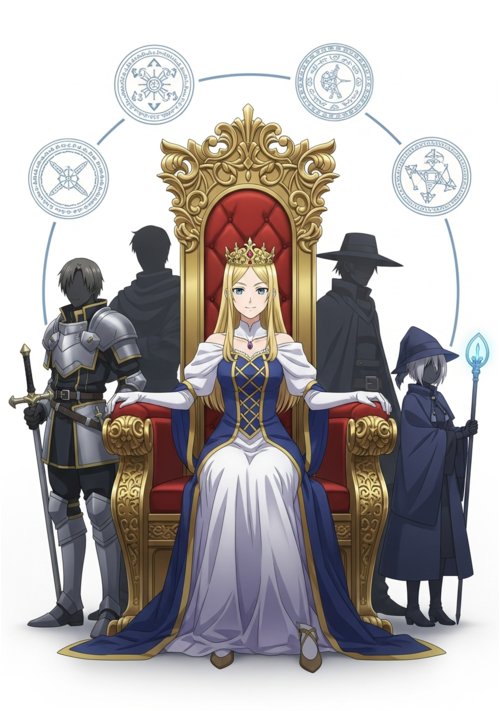
「君は悪役令嬢だ」と離婚されたけど、追放先で伝説の力をゲット!最強の女王になって国を建てたら、後悔した元夫が求婚してきました
黒崎隼人
ファンタジー
「君は悪役令嬢だ」――冷酷な皇太子だった夫から一方的に離婚を告げられ、すべての地位と財産を奪われたアリシア。悪役の汚名を着せられ、魔物がはびこる辺境の地へ追放された彼女が見つけたのは、古代文明の遺跡と自らが「失われた王家の末裔」であるという衝撃の真実だった。
古代魔法の力に覚醒し、心優しき領民たちと共に荒れ地を切り拓くアリシア。
一方、彼女を陥れた偽りの聖女の陰謀に気づき始めた元夫は、後悔と焦燥に駆られていく。
追放された令嬢が運命に抗い、最強の女王へと成り上がる。
愛と裏切り、そして再生の痛快逆転ファンタジー、ここに開幕!
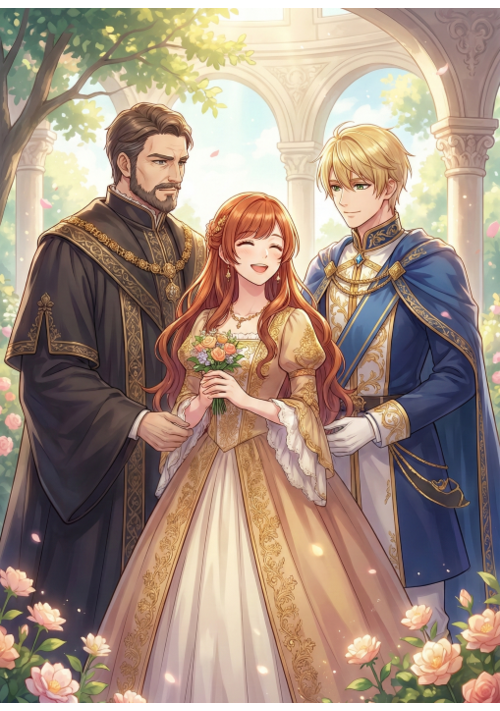
処刑された悪役令嬢、二周目は「ぼっち」を卒業して最強チームを作ります!
みかぼう。
恋愛
地方を救おうとして『反逆者』に仕立て上げられ、断頭台で散ったエリアナ・ヴァルドレイン。
彼女の失敗は、有能すぎるがゆえに「独りで背負いすぎたこと」だった。
ループから始まった二周目。
彼女はこれまで周囲との間に引いていた「線」を、踏み越えることを決意した。
「お父様、私に『線を引け』と教えた貴方に、処刑台から見た真実をお話しします」
「殿下、私が貴方の『目』となります。王国に張り巡らされた謀略の糸を、共に断ち切りましょう」
淑女の仮面を脱ぎ捨て、父と王太子を「共闘者」へと変貌させる政争の道。
未来知識という『目』を使い、一歩ずつ確実に、破滅への先手を取っていく。
これは、独りで戦い、独りで死んだ令嬢が、信頼と連帯によって王国の未来を塗り替える――緻密かつ大胆なリベンジ政争劇。
「私を神輿にするのなら、覚悟してくださいませ。……その行き先は、貴方の破滅ですわ」
(※カクヨムにも掲載中です。)

悪役令嬢の役割を演じきり、婚約破棄で自由を手に入れた私。一途な騎士の愛に支えられ、領地経営に専念していたら、元婚約者たちが後悔し始めたようで
黒崎隼人
ファンタジー
「悪役令嬢」の断罪劇は、彼女の微笑みと共に始まった――。
王太子に婚約破棄を突きつけられた侯爵令嬢エルザ・ヴァイス。乙女ゲームのシナリオ通り、絶望し泣き叫ぶはずだった彼女が口にしたのは、「その茶番、全てお見通しですわ」という、全てを見透かすような言葉だった。
強制された役割から自ら降りたエルザは、王都の悪意を背負いながら、疲弊した領地へと帰還する。そこで彼女を待っていたのは、世間の冷たい目と、幼い頃に救った孤児――騎士レオン・ベルナールの変わらぬ忠誠心だった。
「あなたが悪役などであるはずがない」。彼の言葉に導かれ、エルザは己の才能と知性を武器に、領地の改革に乗り出す。一方、シナリオから外れた王都では、王太子ルキウスやヒロインのリアナが、抱える違和感と罪悪感に苦しんでいた。
しかし、エルザを陥れようとする新たな陰謀が動き出す。果たしてエルザは、自らの人生を切り開き、本当の幸せを掴むことができるのか? そして、ゲームの呪縛から解き放たれた者たちの運命は――。
これは、悪役令嬢という仮面を脱ぎ捨て、真実の愛と自己実現を手にする、美しくも力強い逆転の物語。あなたもきっと、彼女の選択に心を揺さぶられるでしょう。

毒を盛られて生死を彷徨い前世の記憶を取り戻しました。小説の悪役令嬢などやってられません。
克全
ファンタジー
公爵令嬢エマは、アバコーン王国の王太子チャーリーの婚約者だった。だがステュワート教団の孤児院で性技を仕込まれたイザベラに籠絡されていた。王太子達に無実の罪をなすりつけられエマは、修道院に送られた。王太子達は執拗で、本来なら侯爵一族とは認められない妾腹の叔父を操り、父親と母嫌を殺させ公爵家を乗っ取ってしまった。母の父親であるブラウン侯爵が最後まで護ろうとしてくれるも、王国とステュワート教団が協力し、イザベラが直接新種の空気感染する毒薬まで使った事で、毒殺されそうになった。だがこれをきっかけに、異世界で暴漢に腹を刺された女性、美咲の魂が憑依同居する事になった。その女性の話しでは、自分の住んでいる世界の話が、異世界では小説になって多くの人が知っているという。エマと美咲は協力して王国と教団に復讐する事にした。

婚約破棄された令嬢ですが、帳簿があれば辺境でも無双できます ~追い出した公爵家は、私がいないと破産するらしい~
Lihito
ファンタジー
公爵令嬢アイリスは、身に覚えのない罪で婚約破棄され、辺境へ追放された。
だが彼女には秘密がある。
前世は経理OL。そして今世では、物や土地の「価値」が数字で見える能力を持っていた。
公爵家の帳簿を一手に管理していたのは、実は彼女。
追い出した側は、それを知らない。
「三ヶ月で破産すると思うけど……まあ、私には関係ないわね」
荒れ果てた辺境領。誰も気づかなかった資源。無口な護衛騎士。
アイリスは数字を武器に、この土地を立て直すことを決意する。
——追い出したこと、後悔させてあげる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















